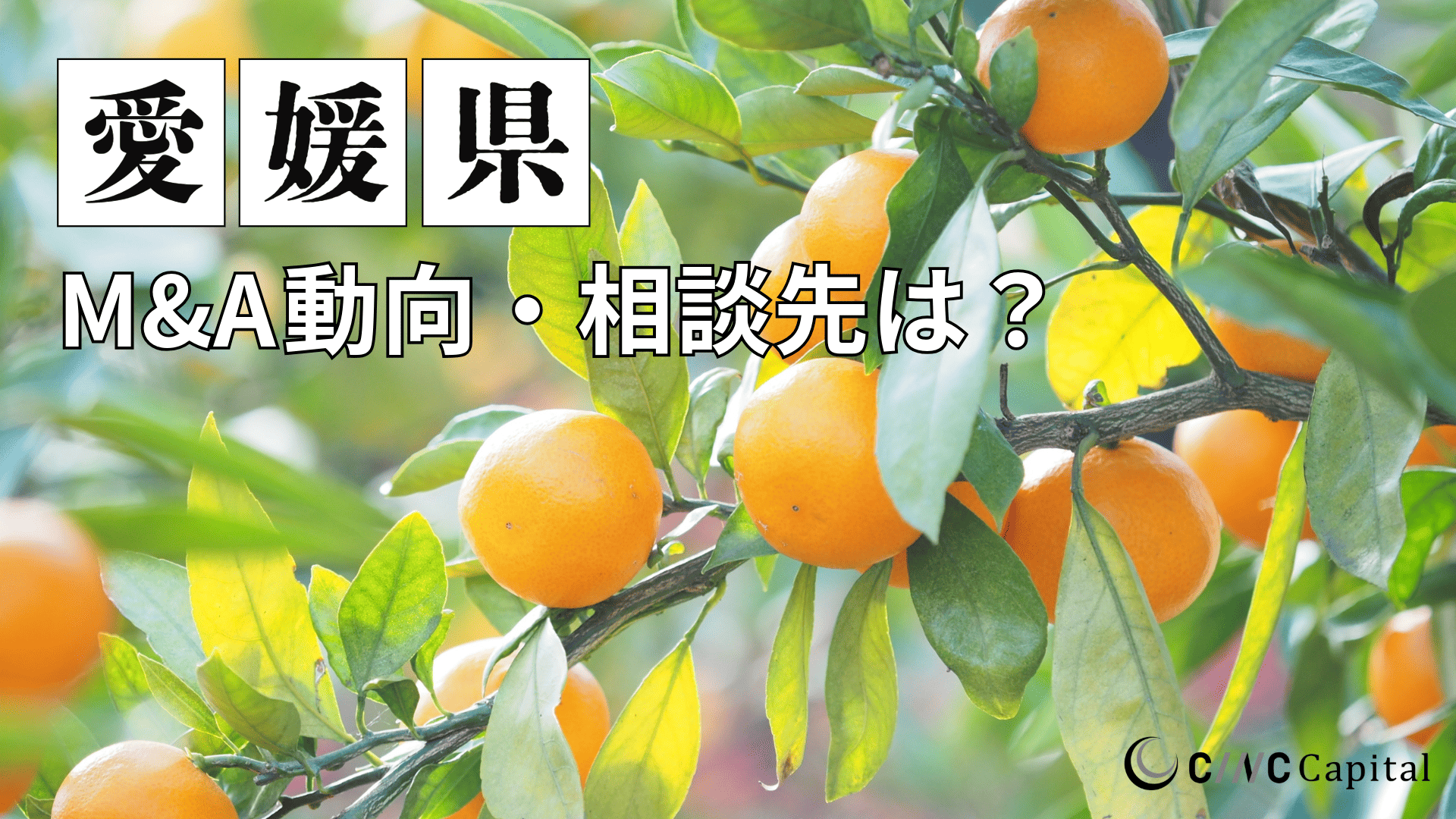CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

エリア
- 最終更新日2025.06.26
長崎県のM&A動向は?事例や信頼できる相談先/M&Aを進めるときの注意点を解説
長崎県では、少子高齢化や後継者不足を背景に、M&A(企業の合併・買収)が注目を集めています。M&Aとは、企業同士が経営統合したり、事業を売買したりすることで、事業継続や成長を目指す手法の一つです。特に長崎では、地元企業の存続や地域経済の活性化を目的としたM&Aの動きが活発化しています。
本記事では、長崎県におけるM&Aの最新動向や具体的な事例、信頼できる相談先、進める際の注意点について解説します。
目次
長崎県のM&Aの最新動向【2025年】
長崎県では、少子高齢化や後継者不足が深刻化するなか、M&Aを活用した事業承継や企業再編が進行しています。まずは、長崎県のM&A市場の主要な動向について解説します。
後継者不足によりM&Aが活発化している
長崎県では、後継者難を理由に事業承継が難しくなっている企業が増加しており、M&Aを選択するケースが増えています。株式会社帝国データバンクの調査によると、2024年の九州・沖縄地方企業の後継者不在率は52.9%でした。長崎県の後継者不在率は59.0%と九州平均を上回っており、多くの企業経営者が事業の存続を模索している状況です。
理由の一つといえるのが長崎県の人口が減少していることです。2015年の人口は約138万4,000人でしたが徐々に減少し、2024年1月時点で126万4,000人となっています。
さらに、若年層の人口が減り、高齢化率が高まっているのも、後継者不在問題に拍車をかけています。2022年時点での長崎県の高齢化率(県の総人口に対する65歳以上の人口の割合)は33.9%です。内閣府の予測では、2045年には40.6%に達すると見られています。
後継者不在の企業が事業を存続させるための手段として、M&Aを積極的に活用する流れが強まっています。
【出典】株式会社帝国データバンク「九州・沖縄地区「後継者不在率」動向調査(2024 年)」
【出典】長崎県県民生活環境部統計課「令和5年長崎県異動人口調査結果」
県外企業による買収案件が増加
長崎県内のM&A案件の多くは、県外企業による買収が占めています。その理由として、長崎県の地場企業が買収に踏み切るよりも、全国規模で事業拡大を狙う企業が長崎の企業を買収するケースが多いためと考えられます。この動きは今後も続く可能性が高く、長崎県の企業にとっては、M&Aを通じて全国規模の企業と提携するチャンスが広がっています。
長崎県でM&Aの相談どこにする?
M&Aを成功させるには、適切な相談先を選ぶことが重要です。長崎県にはM&Aの支援を行う機関やサービスがいくつかあります。M&Aの目的や規模、業種に応じて、最適な相談先を選びましょう。
M&A仲介会社に相談する
M&A仲介会社は、企業の買収・売却を専門的にサポートする機関です。長崎県の企業も全国規模のM&A仲介会社を活用することで、より広いネットワークの中から最適な相手を見つけやすくなります。特に東京を拠点とする大手仲介会社は、長崎県内のM&A案件も積極的に取り扱っており、県外企業とのマッチングも期待できます。
仲介会社を利用すると、相手企業の選定や交渉、契約のサポートを一貫して受けられるため、M&Aの手続きをスムーズに進めることが可能です。ただし、仲介手数料が発生する点には注意が必要です。
金融機関や公的機関を利用する
長崎県内の地元金融機関や公的機関も、M&Aの相談先として有力です。例えば、十八親和銀行やたちばな信用金庫などは、地域密着型のサービスを提供しており、長崎県内の企業間でのM&Aをサポートするケースが増えています。また、金融機関はM&Aに伴う資金調達の支援も行っており、資金面での相談もしやすいのが特徴です。
さらに、長崎県の商工会議所や自治体関連のM&A支援機関では、地域の中小企業向けに事業承継やM&Aの相談を受け付けています。特に後継者問題を抱える企業向けの支援が充実しているため、長崎県内で事業承継を検討している企業にとって有益な選択肢となるでしょう。
M&Aマッチングサイトで探す
近年、M&Aマッチングサイトを利用して売却・買収先を探す企業も増えています。東京を中心に全国で展開されているマッチングプラットフォームを活用すれば、長崎県にいながら全国規模でM&Aの相手を探すことが可能です。
M&Aマッチングサイトは、インターネットを通じて売り手・買い手が直接交渉できる仕組みを提供しており、手軽にM&Aを進められる点がメリットです。
また、仲介会社を通すよりもコストを抑えられる場合が多いため、比較的規模の小さい企業にも向いています。ただし、専門的なサポートが不足しやすいため、M&Aの知識がない場合は注意が必要です。
長崎県で信頼できるM&Aの相談先一覧
M&Aや事業承継を検討する際、信頼できる相談先を選ぶことが重要です。ここでは、長崎県内で利用可能な公的機関やサービスをご紹介します。
長崎県事業承継・引継ぎ支援センター
長崎県事業承継・引継ぎ支援センターは、中小企業の事業承継や引継ぎを支援する公的な相談窓口です。親族内承継や従業員承継、第三者への引継ぎなど、幅広い相談に対応しています。また、事業承継診断や計画策定支援、M&Aマッチング支援なども行っており、専門家によるサポートを受けることが可能です。
長崎商工会議所
長崎商工会議所では、地域の中小企業向けに事業承継やM&Aに関する相談を受け付けています。経営相談や専門家の紹介など、多岐にわたるサポートを提供しており、地元企業の強い味方となっています。
【参考】長崎商工会議所
CINC Capital
CINC Capitalは、最先端のテクノロジーと業界特化型のプロフェッショナルによるサポートを融合し、企業のM&Aを強力に支援するM&A仲介会社です。長崎県のM&A案件にも対応しています。生成AIや自然言語処理を活用し、従来は取得が難しかった未上場企業のM&A実績データを独自に収集・成型。各業界に精通し、数十件以上の成約実績を持つプロアドバイザーが、業界特性や最新動向を踏まえたM&A戦略を提案しています。
【参考】CINC Capital
長崎県のM&A事例
最後に、長崎県のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
ハウステンボス株式会社・ハウステンボス観光株式会社・株式会社ウォーターマークホテル長崎の合併
2023年7月、長崎県佐世保市のテーマパーク運営会社であるハウステンボス株式会社は、同じくグループ会社であるハウステンボス観光株式会社および株式会社ウォーターマークホテル長崎を吸収合併しました。ハウステンボス社が存続会社となり、観光事業とホテル事業を一体化する再編となります。
本合併により、テーマパーク事業と周辺観光サービス、宿泊事業を含めたオペレーションの効率化とグループシナジーの最大化を目指します。観光需要の回復基調が続く中で、ブランド力の強化とサービスの一体提供により顧客満足度の向上が期待されます。
同業他社も統合による運営効率の改善を進める中、本件は観光施設を中心とした統合モデルの好例といえるでしょう。
【出典】ハウステンボス株式会社「合併公告及び合併につき株券等提出公告」
株式会社フードプラス・ホールディングスによる株式会社庄屋フーズ&ライフのM&A
2023年6月、フードプラス・ホールディングスは、給食事業を展開する株式会社庄屋フーズ&ライフの全株式を、給食業界大手のハーベスト株式会社へ譲渡しました。
これにより、庄屋フーズ&ライフはハーベスト社のグループ傘下となり、学校や介護医療、企業向けの給食サービスを引き続き提供していきます。
本件は、地域に根差した給食事業者が大手グループの一員となることで、経営基盤の安定化とサービス品質の向上を図る動きといえます。
給食業界では人手不足や物価高への対応が課題となる中、スケールメリットの活用による業務効率化や商品力の強化が期待されます。今後も業界再編が進む中で、M&Aを通じた成長戦略がより一層注目されるでしょう。
【出典】株式会社フードプラス・ホールディングス「株式会社庄屋フーズ&ライフの株式譲渡に関するお知らせ」
株式会社雲仙湯元ホテルによる株式会社メモリードのM&A
長崎県・雲仙温泉にある創業300年以上の老舗旅館「雲仙湯元ホテル」は、後継者不在の課題に直面し、2018年に地元企業である株式会社メモリードへの事業承継を実現しました。
本件は、長崎県事業引継ぎ支援センターを介した第三者承継であり、全従業員の雇用継続や取引先との関係維持、歴史ある屋号の存続など、地域への配慮を重視したM&Aでした。
譲受企業のメモリードは、冠婚葬祭業を中心にリゾートホテルなども展開する県内有力企業であり、経営ノウハウや集客力を活かして再生を図っています。今回の事例は、地方の老舗企業が「地域資源」としての価値を維持しながら、持続可能な形で承継された好例といえます。
宿泊業界では、高齢化・人手不足・設備老朽化といった課題が山積する中で、M&Aによる第三者承継が今後さらに進むと見られます。伝統と経営資源の両立を図る、地域密着型の承継スキームに注目が集まっています。
【出典】事業承継・引継ぎ支援センター「〈事例3〉雲仙湯元ホテル|第三者承継の事例紹介」
長崎県でM&Aを進めるときの注意点
長崎県でM&Aを検討する売り手企業にとって、地域特有の市場環境や業界動向を踏まえた戦略が不可欠です。ここでは、長崎県でM&Aを進める際に押さえておくべきポイントを解説します。
地域特性を活かした戦略立案
長崎県の県内総生産では製造業が1位となっていますが、なかでも造船産業や航空機産業、半導体産業などが盛んです。世界的な脱炭素化の動きを捉えた省エネルギーな船舶開発も進んでいます。また、多くの観光資源を持つ長崎では、観光業が主な産業となっているのも特徴です。2023年の延べ宿泊客数は7,324,524人で、前年の6,320,373人から15.9%増加しています。
M&Aにおいても、これらの産業特性を踏まえた戦略が重要になります。例えば、製造業においては技術や設備の承継、観光業ではブランド力や立地を活かした付加価値向上など、長崎ならではの優位性を活かすM&Aが求められることに注意しましょう。
【出典】長崎県 文化観光国際部 観光振興課「長崎県観光統計 令和5年(1月~12月)」
PMI(買収後の統合計画)の重視
M&Aの成否は、買収後の経営統合(PMI:Post-Merger Integration)にかかっています。特に地方企業の場合、企業文化の違いや従業員の不安が統合の障壁になる場合があります。事前に経営方針を明確にし、従業員のケアや業務移行を円滑に行うことが成功の鍵です。
適切な専門家に相談する
M&Aの成功には、実績のある専門家のサポートが不可欠です。長崎県内の経済団体や金融機関、M&Aアドバイザリー会社と連携し、適切なスケジューリングや戦略立案を進めましょう。豊富なM&Aデータと専門的な知識を兼ね備えたアドバイザーを活用することで、より有利な条件でのM&Aを実現できます。
M&Aを検討する際に知っておきたい基礎知識
M&Aを検討する際には、基本的な知識を押さえておくことが重要です。ここでは、M&Aに関するよくある疑問について、一問一答形式で解説します。
M&Aと事業譲渡の違いはなんですか?
事業譲渡は特定の事業を売買する手法です。一方、M&Aには株式譲渡や合併などの手法も含まれます。株式譲渡や合併では会社全体の経営権ごと移転することが多いですが、事業譲渡は会社の一部門や特定の資産・負債のみを売買する点が異なります。
M&Aの手法について、詳細は以下の関連記事で解説しています。こちらも併せてお読みください。
【参考】M&Aとは?意味や目的、手法ごとのメリットデメリットをわかりやすく解説
M&Aのメリットとデメリットはなんですか?
M&Aのメリットには、売り手にとっては資金の確保や事業承継の解決策となる点、買い手にとっては事業の拡大やシナジー効果が期待できる点が挙げられます。一方で、デメリットとしては、企業文化の統合の難しさやM&Aにかかるコスト・時間などがあります。
M&Aのメリットとデメリットについて、詳しくは以下の関連記事で解説しています。こちらも併せてお読みください。
【参考】M&Aのメリットとデメリットは?買い手と売り手の立場別にわかりやすく解説
M&Aの相場はどのくらいですか?
M&Aの相場は企業の規模や売上高、業種、市場環境などによって異なります。価格は「企業価値評価」に基づいて決定されるのが一般的です。インカムアプローチ・マーケットアプローチ・コストアプローチなどの方法を複数組み合わせて計算されます。
M&Aへ向けて自社の企業価値を知りたい方は、以下のページから「企業価値算定シミュレーション」をご利用ください。
【参考】企業価値算定シミュレーション
M&Aでおすすめの相談先はどこですか?
M&Aを進める際には、実績のある専門家に相談することが重要です。主な相談先としては、M&A仲介会社、フィナンシャルアドバイザー、弁護士、税理士などが挙げられます。特に、M&A仲介会社は買い手・売り手のマッチングや交渉サポートを行うため、専門家の支援を受けながらスムーズな取引が期待できるでしょう。
M&Aの相談先について、詳しくは以下の関連記事で解説しています。こちらも併せてお読みください。
【参考】M&Aはどこに相談する?相談先の選び方やメリットデメリットを解説
まとめ|長崎県のM&Aのポイント
長崎県では、地域特有の産業構造や後継者不足の課題を背景に、事業承継型M&Aが活発に行われています。特に、水産業・観光業・製造業などの分野では、地元企業同士の統合や、県外企業とのM&Aによる成長戦略が注目されています。
M&Aを成功させるためには、手法の違いやメリット・デメリットを理解し、自社の企業価値を正しく把握することが重要です。また、適切な相談先を選ぶことで、スムーズな取引が実現しやすくなります。M&Aを検討する際は、専門家のサポートを活用しながら、最適な選択を行いましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。