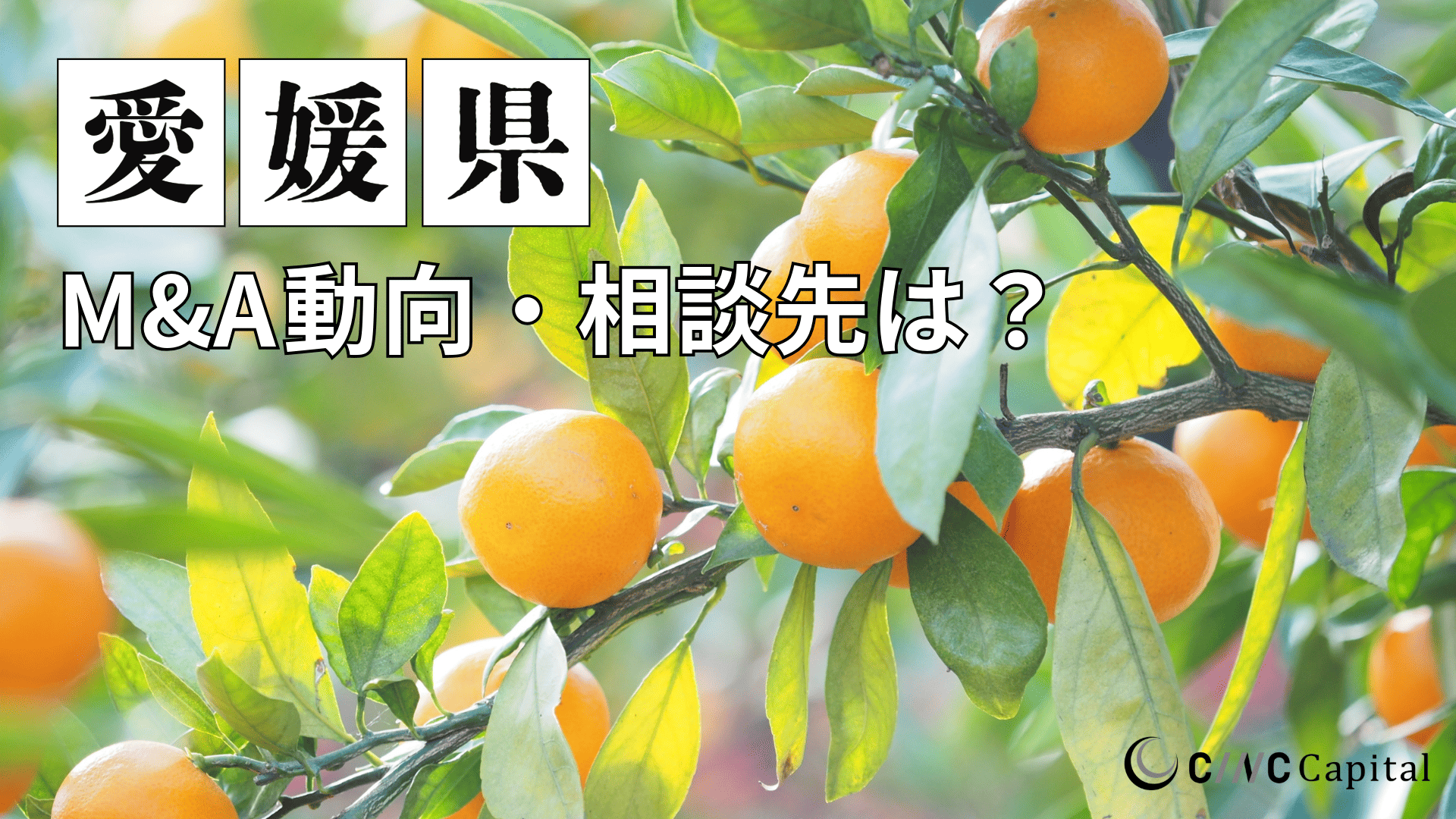CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

エリア
- 最終更新日2025.06.26
神奈川県のM&A動向は?事例や信頼できる相談先/M&Aを進める時の注意点を解説
神奈川県県内の中小企業経営者にとって、M&A(合併・買収)は事業承継や成長戦略における有効な選択肢です。M&Aとは、企業の経営権や事業を他社に譲渡・取得する手法を指します。後継者不足や競争激化の環境下において、企業価値を最大化し、事業を未来につなげるための意思決定ともいえるでしょう。
今回は、神奈川県県内におけるM&Aの最新動向をはじめ、基礎知識から相談先選びまで、経営判断に役立つ実践的な情報をご紹介します。
目次
神奈川県のM&Aの最新動向【2025年】
神奈川県県は事業所数が多く企業の集積度が高いため、M&Aや事業承継の取引件数も比較的多い地域です。ここでは、同エリアにおけるM&Aの最新動向をご紹介します。
後継者不足が追い風となりM&A市場が急成長
「帝国データバンク」の調査によると、神奈川県県内企業の後継者不在率は2024年時点で60.5%となっています。全国平均の52.1%を8.4ポイント上回っており、後継者不在率は依然として高い水準にあります。
また、県内で休廃業や解散を選んだ企業経営者の平均年齢は70歳を超えており、事業承継問題は待ったなしの状況です。こうした高齢経営者の企業も、事業価値を失う前にM&Aによる承継を選択するケースが見られます。
【出典】帝国データバンク「神奈川県県「後継者不在率」動向調査(2024年)」
【出典】帝国データバンク「神奈川県県「休廃業・解散」動向調査(2024年)」
製造業を中心とした技術獲得型M&Aの増加
近年、神奈川県県を含む日本の製造業は国際競争で苦戦する状況にあります。この課題に対応するため、競争力強化や事業規模拡大を目指したM&Aに取り組む企業も少なくありません。特に技術やノウハウ、市場シェア獲得による競争基盤強化を目的とした戦略的M&Aが注目を集めています。
神奈川県県には大企業が多く集積しているため、取引額が数百億円を超える大型M&A案件も見られますが、中小企業の事業承継を目的とした比較的小規模な案件も少なくありません。また、東京都に隣接する立地から、サービス業や小売業の企業も多数点在しており、営業エリア・市場シェア拡大を図るM&Aも活発です。
神奈川県でM&Aの相談どこにする?
神奈川県県のM&A市場は活発な取引が行われており、とりわけ製造業を中心に多くの案件が成立しています。ここでは、神奈川県県におけるM&Aの相談窓口を3つご紹介します。
M&A仲介会社に相談する
神奈川県県でM&Aを検討するなら、M&A仲介会社に相談するのがおすすめです。M&A仲介会社は企業売買を包括的にサポートする専門家で、売り手・買い手の双方と契約を結び、交渉調整から企業価値評価、必要書類作成まであらゆる業務に対応します。
M&A仲介会社の強みは、豊富な案件情報と専門知識にあります。常に売却検討企業を調査し、業界や規模に応じた多様な選択肢から最適なパートナーを見つけ出す専門家といえます。初めてM&Aに取り組む企業には、具体的なアドバイスと手厚いサポートを受けられるのが大きな利点です。
金融機関や公的機関を利用する
地方銀行や信用金庫などの金融機関は、地域企業の事業承継・経営支援に積極的に取り組み、M&A案件に関する豊富な情報を持っています。近年は多くの金融機関がM&A支援に特化した専門部署を設置し、企業のM&A活動を強力にバックアップしています。
最大の利点は、現時点で取引関係がある場合に相談しやすく、地域企業情報を多く把握している点です。また、資金調達の専門知識を活かしたアドバイスや事業承継における株式移転サポートなど、総合的な支援を受けられるのも大きいでしょう。
M&Aマッチングサイトで探す
近年では、インターネット上でM&A案件を探せるマッチングサイトを活用する企業も見られます。M&Aマッチングサイトの特徴は、時間や場所を問わずオンラインで企業売却案件を探せることです。一部のM&A仲介会社では「M&Aプラットフォーム」を運営し、AIを活用した高精度なマッチングシステムを提供しているケースもあります。
神奈川県で信頼できるM&Aの相談先一覧
神奈川県県でM&Aを検討する際には、専門知識と経験、十分な実績を持つ相談先を選びましょう。ここでは、神奈川県県で信頼できるM&Aの相談先をご紹介します。
神奈川県県事業承継・引継ぎ支援センター
神奈川県県事業承継・引継ぎ支援センターは、中小企業や小規模事業者の事業承継を支援する公的機関です。後継者不在に悩む小規模事業者と起業を希望する方をマッチングする「神奈川県県後継者バンク」を運営しており、地域に密着した支援を提供しています。
神奈川県県よろず支援拠点
神奈川県県よろず支援拠点は、公益財団法人神奈川県産業振興センターを母体とする公的支援機関です。専門のコーディネーターが中小企業向けに経営アドバイスや指導を行っており、M&Aや事業承継に関する相談も受け付けています。
【参考】神奈川県県よろず支援拠点
CINC Capital
CINC Capitalは、最新のビッグデータ技術を駆使したM&A仲介会社です。横浜市を中心とした神奈川県県全域でのサービス提供に加え、東京都や埼玉県、千葉県のM&A案件にも対応しています。
同社の強みは、買い手企業のM&A実績データを独自に収集・分析するマーケティングテクノロジーと、業界経験10年以上を誇るベテランアドバイザーによる実践的なサポートにあります。製造業や小売業、サービス業など、幅広い業種のM&Aに対応できる柔軟性もCINC Capitalの特長です。
【参考】CINC Capital
神奈川県のM&A事例
最後に、神奈川県のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
株式会社ロピア・ホールディングスによる株式会社スーパーバリューのM&A
スーパーマーケット事業を展開する株式会社スーパーバリューは、2022年より株式会社ロピア・ホールディングス(ロピアHD)と資本業務提携を進めており、2022年8月には第三者割当増資を通じてロピアHDの子会社となりました。
両社は店舗運営のノウハウ共有やモデル店の共同開発を進めており、2023年4月には営業面の強化を目的とした覚書を締結。ロピアHDからの取締役派遣も含め、店舗改革を本格化させています。急成長中のロピアの知見を活かした改革が、スーパーバリューの競争力強化に寄与することが期待される取り組みです。
【出典】株式会社スーパーバリュー「株式会社ロピア・ホールディングスとの資本業務提携契約書に関する覚書の締結に関するお知らせ」
加賀電子株式会社とと富士通セミコンダクター株式会社による富士通エレクトロニクス株式会社のM&A
加賀電子株式会社は、2019年1月を目途に富士通セミコンダクター株式会社から富士通エレクトロニクス株式会社(FEI)の株式70%を取得し、子会社化する契約を締結しました。
残る30%についても2021年内の譲渡が予定されており、段階的に完全子会社化を進める方針です。エレクトロニクス商社を取り巻く競争環境が激化する中、両社の事業統合により、電子部品・半導体分野でのシェア拡大、EMS事業の非連続な成長、経営効率の向上を目指しています。
加賀電子は今回のM&Aを中期経営計画における成長戦略の一環と位置付け、グローバル競争力の強化に取り組んでいます。
【出典】富士通セミコンダクタ―株式会社、加賀電子株式会社「加賀電子 富士通エレクトロニクス株式取得を決定富士通セミコンダクターより 70%株式取得」
株式会社JPホールディングスによる株式会社アメニティライフのM&A
JPホールディングスは、連結子会社である株式会社日本保育サービスと株式会社アメニティライフを2022年4月1日付で合併しました。
日本保育サービスは全国297施設を展開する大手で、アメニティライフは横浜市で5園を運営しており、今回の合併により経営資源の効率化と保育サービスの質的向上を図る方針です。保育業界では施設運営の集約や効率化が進んでおり、本件もその一環といえます。
今後は、統合によるスケールメリットを活かし、選ばれる園づくりと競争力の強化が期待されます。
【出典】株式会社JPホールディングス「連結子会社間の合併に関するお知らせ」
神奈川県でM&Aを進めるときの注意点
神奈川県県でM&Aを成功させるには、いくつかの大切なポイントを押さえる必要があります。ここでは、M&Aを進める際に知っておきたい注意点を売り手企業目線で解説します。
地域特性を考慮した企業価値評価を行う
神奈川県県には京浜工業地帯を中心とした製造業の集積地があり、工場や設備などの不動産評価が重要になります。特に横浜・川崎エリアでは、都市開発による土地価格の変動が大きく、不動産鑑定評価を適切に行うことが企業価値評価の重要なポイントとなります。
無形資産の価値評価を行う
M&Aにおける企業価値評価では、無形資産の評価も重視されます。例えば、神奈川県県で多く見られる製造業の場合、工場や設備などの有形資産だけでなく、技術やノウハウといった「見えない資産」の評価が意味を持ちます。特許権や製造プロセスのノウハウ、研究開発能力といった無形資産は収益に直結するため、専門家による適切な評価が不可欠です。
適切な専門家に相談する
神奈川県県内の企業同士でのM&Aと県外企業とのM&Aでは、注意しておきたいポイントが異なります。地域商習慣の違いやビジネスカルチャーの差異にも注意が必要です。特に取引先との関係性や従業員の処遇に関しては、地域性を考慮した対応が求められます。
M&Aを成功させるためには専門家に依頼してサポートを受け、適切な交渉・調整を行うことが重要です。成功実績の多さ、業界への専門性、担当者との相性、マッチング力の高さなどを総合的に判断し、自社に最適なパートナーを見つけましょう。
M&Aを検討する際に知っておきたい基礎知識
これからM&Aを検討する経営者は、以下の基礎知識をしっかりと抑えておきましょう。
M&Aと事業譲渡の違いはなんですか?
M&Aは会社そのものを取得する方法です。株式や持分を購入することで、資産・負債・契約関係をすべて引き継ぎます。手続きは比較的シンプルで登記変更のみで済む場合もあります。
事業譲渡は特定の事業や資産のみを譲渡する方法です。対象を選択できますが、資産ごとの所有権移転手続きや契約関係の個別承継が必要となります。そのため、手続きがM&Aよりも複雑になることが一般的です。
M&Aの手法について、詳しくは以下の関連記事で解説しています。こちらも併せてお読みください。
【関連記事】M&Aとは?意味や目的、手法ごとのメリットデメリットをわかりやすく解説
M&Aのメリットとデメリットはなんですか?
売り手側メリットは、後継者問題の解決、事業継続、従業員雇用の維持、経営資源の価値化などです。一方、企業文化の変化や従業員処遇への不安が生じるデメリットがあります。
買い手側のメリットは、新規事業への迅速参入、人材・技術の即時獲得、シナジー効果の創出などです。ただし、企業文化の統合課題、適正価値評価の難しさ、予期せぬ問題発生リスクなどが挙げられるため、買い手もまた慎重な対応が求められます。
M&Aのメリットとデメリットについて、詳しくは以下の関連記事で解説しています。こちらも併せてお読みください。
【関連記事】M&Aのメリットとデメリットは?買い手と売り手の立場別にわかりやすく解説
M&Aの相場はどのくらいですか?
M&Aの相場は業種・規模・収益性・成長性により異なりますが、主な算出方法には以下があります。
-
マルチプル法
-
DCF法
-
時価純資産法
算出結果はあくまでも参考値に過ぎず、高収益・成長企業や独自技術保有企業においては、相場以上の価格で取引されるケースがあります。
M&Aへ向けて自社の企業価値を知りたい方は、以下のページから「企業価値算定シミュレーション」をご利用ください。
【参考】企業価値算定シミュレーション
M&Aでおすすめの相談先はどこですか?
M&Aの相談先は、専門知識を持つM&A仲介会社、地域ネットワークに強い地方銀行・信用金庫、無料相談可能な事業承継・引継ぎ支援センターなどの公的機関、そして税務・法務面をサポートする税理士・弁護士などがあります。自社の状況や求めるサポート内容に合わせて最適な相談先を選びましょう。
M&Aの相談先について、詳しくは以下の関連記事で解説しています。こちらも併せてお読みください。
【関連記事】M&Aはどこに相談する?相談先の選び方やメリットデメリットを解説
まとめ|神奈川県のM&Aのポイント
M&Aの複雑なプロセスを成功に導くには、豊富な実績と地域特性を理解した専門家のサポートが必須です。特に神奈川県のように多様な企業が集まる地域では、地域特性や市場動向を熟知した専門家のアドバイスが必須といえます。まずはM&A仲介会社などの専門家に相談し、自社を守るための第一歩を踏み出しましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。