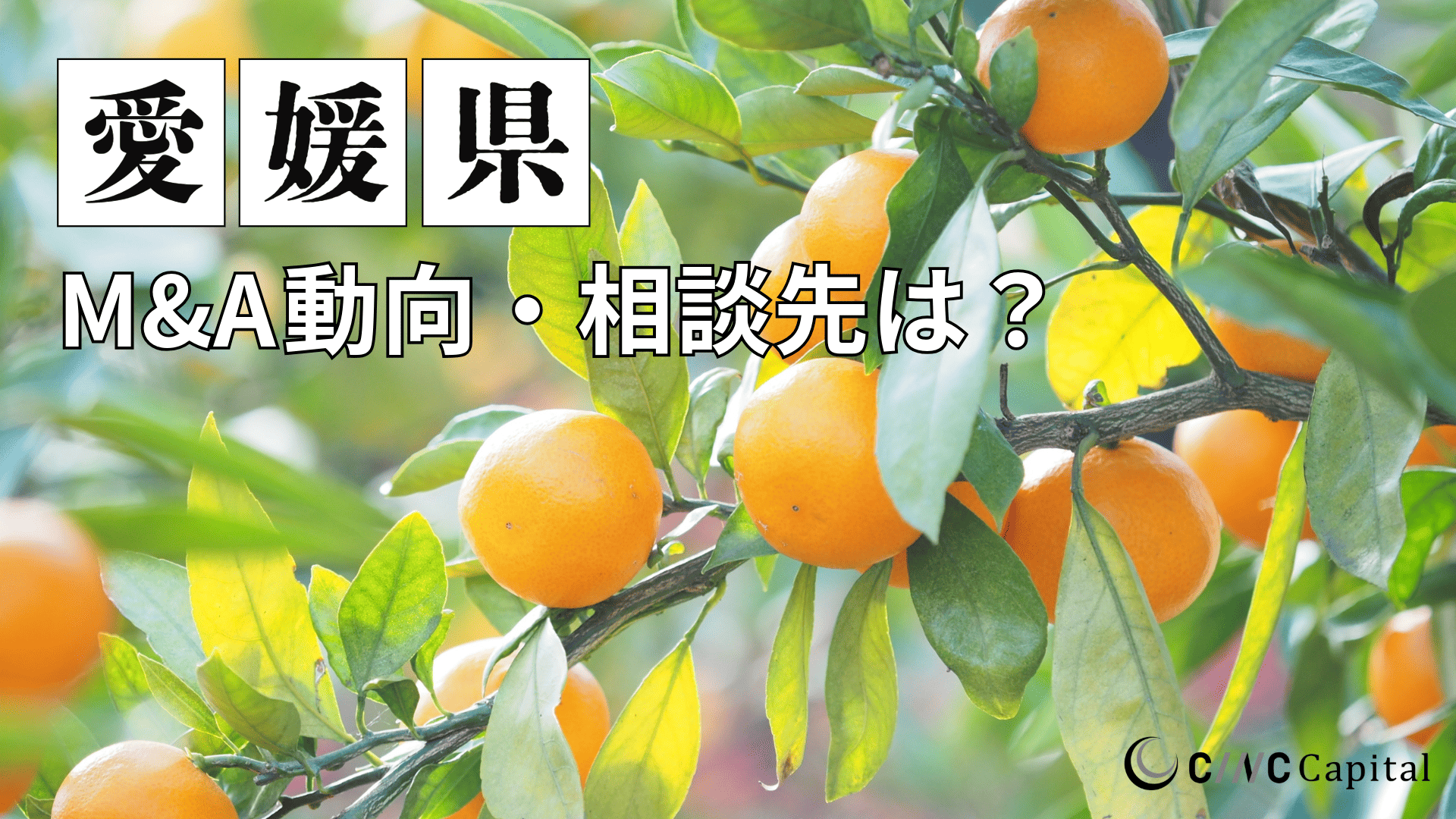CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
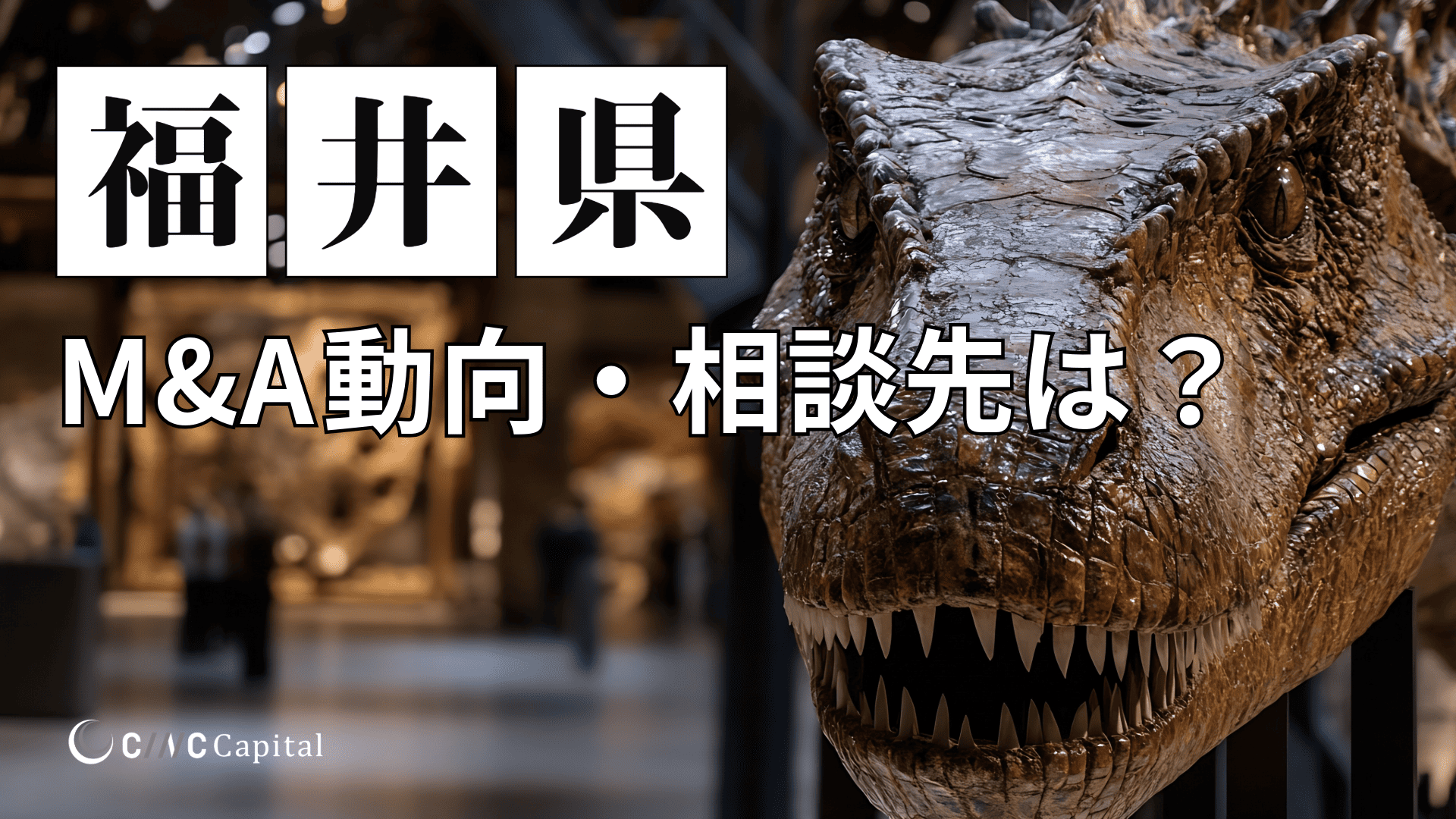
エリア
- 最終更新日2025.06.26
福井県のM&A動向は?事例や信頼できる相談先/M&Aを進めるときの注意点を解説
近年、福井県でも中小企業を中心にM&A(企業の合併・買収)への関心が寄せられています。M&Aとは、企業同士が経営資源を統合することで、事業拡大や後継者問題の解決などを図る手法です。少子高齢化が進む中、事業承継の手段としてM&Aを選ぶ福井県内の企業も見られます。
本記事では、福井県におけるM&Aの最新動向や実際の事例、信頼できる相談先、注意点について詳しく解説します。M&Aに興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
目次
福井県のM&Aの最新動向【2025年】
近年、福井県では中小企業の経営者の高齢化や後継者不足を背景に、M&Aによる事業承継の動きが見られるようになっています。ここでは、2025年時点で注目される福井県のM&A・事業承継の動向について解説します。
後継者不在率は全国平均を上回る水準で推移
福井県における中小企業の後継者不在率は、2024年時点で53.5%と全国平均(52.1%)をやや上回る結果となっています。全国的に見れば、事業承継支援の強化や意識の変化により後継者不在率は年々改善しています。一方で福井県では、依然として半数以上の企業が後継者を確保できていない状況です。
この背景には、県内における若年層の都市部流出や、地場産業の将来性に対する不安などが影響していると考えられます。そのため、近年では第三者への事業承継、すなわちM&Aによる引き継ぎの需要が高まりつつあります。地元金融機関や支援機関によるマッチング支援も少しずつ整備され、M&Aに前向きな企業も出てきています。
【出典】帝国データバンク「全国『後継者不在率』動向調査(2024年)」
休廃業・解散件数が過去最多を更新し、M&Aの重要性が浮き彫りに
2024年に福井県で発生した休廃業・解散件数は442件で、前年比13.6%増となり、過去最多を記録しました。これは2023年の389件(前年比6.3%増)に続く2年連続の増加であり、地域経済に大きな影響を及ぼしています。
要因としては、コロナ禍後の支援終了による経営環境の悪化、物価高や人手不足の影響、さらには後継者不在による「あきらめ廃業」の増加が挙げられます。特に小規模事業者ほど影響を受けやすく、経営資源を外部に引き継ぐ選択肢としてのM&Aの重要性が高まっているといえるでしょう。
こうした背景の中で、企業が早期に事業承継やM&Aの可能性を検討することが、地域経済の持続性においても不可欠になりつつあります。福井県内のM&A支援体制の整備と企業側の意識改革が今後の鍵を握るでしょう。
【出典】帝国データバンク「全国企業『休廃業・解散』動向調査(2024年)」
福井県でM&Aの相談どこにする?
東京や大阪のような大都市圏と比べると選択肢が限られているように感じられるかもしれませんが、福井県にもM&Aを支援してくれる頼れる相談先は存在します。自社の規模や業種、譲渡後の方向性などを踏まえて、最適な相談先を選びましょう。
M&A仲介会社に相談する
福井県内でM&Aを進めたいと考えたとき、まず候補に挙がるのがM&A仲介会社です。東京を拠点とする大手仲介会社も福井県の中小企業を対象とした案件を扱っており、地域に関係なく相談可能な体制を整えています。
また、北陸エリア全体で支援実績のある仲介会社も存在し、福井県内の事業承継ニーズにも対応しています。専門的な知識とノウハウを持つ仲介会社であれば、買い手候補のリストアップから成約まで一貫して支援しているケースが多いようです。
金融機関や公的機関を利用する
福井県では、地方銀行や信用金庫など地元密着型の金融機関でもM&A相談を受け付けています。福井銀行や福邦銀行など、地域経済に精通した金融機関は、地場企業とのネットワークを活かして適切な買い手・売り手を紹介してくれることがあります。また、福井商工会議所や県の支援センターなどの公的機関でも中小企業向けの事業承継支援を行っており、初めてM&Aを検討する経営者にとって心強い存在です。
M&Aマッチングサイトで探す
最近では、福井県のような地方でもM&Aマッチングサイトを活用して相手企業を探す経営者が増えています。東京や大阪の買い手が地方企業に関心を持つケースも多く、福井県の魅力ある事業に全国からアクセスがあることもメリットです。
特に、事業規模が小さい企業や後継者不足に悩む個人経営の方などには、手軽に情報を発信できる手段として有効です。自分で相手を探しながら、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、柔軟なM&Aを進められます。
福井県で信頼できるM&Aの相談先一覧
福井県では、人口減少や高齢化に伴う後継者不足により、中小企業の廃業が相次いでいるのが社会的課題となっています。こうした課題に対応するため、国や自治体、公的支援機関によるM&A・事業承継の支援が積極的に行われています。福井県内でM&Aに関する相談が可能な、信頼性の高い相談先をチェックしてみましょう。
福井県事業承継・引継ぎ支援センター
福井商工会議所内に設置された公的支援機関で、国からの委託事業として運営されています。事業承継に悩む中小企業経営者に対し、後継者候補とのマッチングや専門家による個別支援を提供しています。「後継者人材バンク」などを活用することで、創業希望者とのスムーズなマッチングも可能です。
福井県事業承継ネットワーク(公益財団法人ふくい産業支援センター)
公益財団法人ふくい産業支援センターが立ち上げた、福井県や県内の公的機関、金融機関、士業団体と連携して事業承継支援体制を構築しているネットワークです。地域の実情に即したきめ細やかな支援を実施しており、事業承継に関する総合的な相談窓口として機能しています。
【参考】福井県事業承継ネットワーク(公益財団法人ふくい産業支援センター)
CINC Capital
CINC Capital(シンクキャピタル)は、全国の中堅・中小企業を対象にM&A仲介支援を行う専門会社です。独自のネットワークを活かし、幅広い業界でのマッチングを実現しています。福井県のM&A案件にも対応しており、地域に根ざした課題にも柔軟に対応可能です。案件数が少ない地域においても、広域でのマッチングにより選択肢を広げたい企業におすすめです。
【参考】CINC Capital
福井県のM&A事例
最後に、福井県のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
前田工繊による釧路ハイミールのM&A
2018年10月、土木資材大手の前田工繊株式会社は、水産加工を手がける釧路ハイミール(北海道釧路市)の全株式を取得し、子会社化しました。
釧路ハイミールは、養殖魚や家畜用飼料となるフィッシュミール製造の先駆企業であり、魚油の製造など健康食品原料の分野でも実績があります。
前田工繊はこれまで農業系スタートアップへの投資などを通じて食・ヘルスケア分野への事業拡大を模索しており、今回の買収もその一環と位置付けられています。同社が保有する原材料調達力や加工ノウハウは、ヘルスケア事業の基盤構築において大きな強みとなると期待されています。
今後は他子会社との統合なども視野に、グループ全体での再編を進める方針です。水産業を起点とした健康領域への進出は、食品・ヘルスケア業界でのM&Aトレンドの一つとして注目されます。
【出典】日本経済新聞「前田工繊 釧路の水産加工会社買収 ヘルスケア事業構築の一環」
三谷商事株式会社による栄冠商事株式会社のM&A
2017年12月、三谷商事株式会社の孫会社にあたるクラウン防災株式会社は、福井県坂井市の栄冠商事株式会社の全事業を譲り受けました。
栄冠商事は1953年創業の老舗企業で、消火器や火災報知器といった消防機器の販売・施工・保守を中心に、自治体向けの消防車や救助資機材の提供も手がけていました。
譲受の背景には、クリーンガス福井を中心としたグループ全体の商材拡充とサービスの多角化を通じた相乗効果の期待がありました。
クラウン防災はこの事業取得により、ガス機器販売と防災分野の融合による地域密着型のトータルソリューション企業としての体制を強化。防災ニーズの高まりを受けて、地方の中小事業者の機能を取り込む動きは今後も継続するとみられます。
【出典】三谷商事株式会社「栄冠商事株式会社の事業を譲り受けることに関するお知らせ」
ルックスオティカによる福井めがね工業のM&A
2018年3月、イタリアの眼鏡大手ルックスオティカグループは、福井県鯖江市の眼鏡フレーム製造企業・福井めがね工業の株式67%を取得し、子会社化しました。
福井めがねは1969年創業で、チタン製フレームの加工技術に強みを持ち、国内外のブランドにOEM供給を行ってきました。特に高品質なβチタン素材を用いた軽量設計などが評価され、ルックス社との取引が徐々に拡大していた背景があります。
今回の買収により、両社の職人技術と生産ノウハウの融合が進み、製品力や生産性の向上が期待されます。福井の地場産業である眼鏡製造とグローバルブランドとの連携は、地域技術の国際競争力強化を図るM&Aの好例といえます。従業員の雇用や他社との取引も維持され、安定した経営基盤のもと成長戦略が進められています。
【出典】日本経済新聞「福井めがね工業、伊大手が買収 フレーム加工技術評価」
福井県でM&Aを進めるときの注意点
福井県で会社や事業の売却を検討している経営者にとって、M&Aは事業の未来を託す重要な手段です。ここでは、売り手側の視点から、福井県でM&Aを行う際に押さえておきたい注意点をご紹介します。
地域性を踏まえて買い手を選ぶ
福井県では地域に根ざした企業が多く、人とのつながりや信頼関係が重視される傾向があります。そのため、買い手企業が地域の文化や商習慣に配慮できるかどうかは重要なポイントです。M&A後に企業文化の違いが原因で従業員の離職や取引先との関係悪化が起こるケースもあるため、地域への理解がある相手かどうかを見極める必要があります。
事業の魅力を整理してから売却活動を始める
買い手にとって魅力的に映るよう、自社の強みや成長性、安定した収益構造などをわかりやすくまとめておくことが大切です。必要に応じて事業計画書や業績資料を整え、数値に基づいた説明ができるようにしましょう。簿外債務や経営課題がある場合でも、正直に開示し、改善の取り組みを提示することで信頼につながります。
適切な専門家に相談する
福井県では地域と深く関わる企業が多い一方で、M&Aの情報が外部に出にくいという特徴もあります。そのため、買い手とのマッチングが難航するケースも少なくありません。
また、後継者不在の背景など、複雑な事情が絡むことも多いため、M&Aの実績がある専門家に相談することが大切です。福井県の事業承継に対応している公的機関のほか、広域で案件を取り扱うM&A専門会社を活用することで、より円滑な交渉や成約を目指せます。
M&Aを検討する際に知っておきたい基礎知識
M&Aを初めて検討する方にとっては、専門用語や手続きの流れがわかりにくいと感じることも多いかもしれません。ここでは、M&Aに関する基本的な疑問について、簡潔に解説します。
M&Aと事業譲渡の違いはなんですか?
M&Aは「合併と買収(Mergers and Acquisitions)」の総称で、手法の一つに事業譲渡があります。事業譲渡は特定の事業部門のみを売却する方法です。
株式譲渡が会社の所有権そのものを移転するのに対し、事業譲渡は特定の資産・負債・契約などを個別に移転させる点が異なります。譲渡対象の範囲や法的手続き、税務上の扱いなども異なる点に留意しましょう。
M&Aの手法について、詳しくは以下の関連記事で解説しています。こちらも併せてお読みください。
【関連記事】M&Aとは?意味や目的、手法ごとのメリットデメリットをわかりやすく解説
M&Aのメリットとデメリットはなんですか?
売り手にとっては後継者問題の解決や資金回収ができる一方、従業員や取引先との関係に影響が出る可能性もあります。買い手側にも同様に利点とリスクがあるため、事前に把握しておくことが大切です。
M&Aのメリットとデメリットについて、詳しくは以下の関連記事で解説しています。こちらも併せてお読みください。
【関連記事】M&Aのメリットとデメリットは?買い手と売り手の立場別にわかりやすく解説
M&Aの相場はどのくらいですか?
M&Aの相場は業種や規模、収益性などによって異なります。一般的に中小企業のM&Aでは、「時価純資産+営業権法」や「マルチプル法」によって企業価値が評価されます。例えば「時価純資産+営業権法」の場合、「時価純資産+営業利益×2~5年」といった形で算定するのが特徴です。
M&Aへ向けて自社の企業価値を知りたい方は、以下のページから「企業価値算定シミュレーション」をご利用ください。
【参考】企業価値算定シミュレーション
M&Aでおすすめの相談先はどこですか?
M&Aを相談する際は、実績のあるM&A仲介会社や専門家への相談が安心です。公的機関や金融機関も選択肢に入りますが、交渉力やマッチング力を重視するなら、民間の専門会社が適しています。
M&Aの相談先について、詳しくは以下の関連記事で解説しています。こちらも併せてお読みください。
【関連記事】M&Aはどこに相談する?相談先の選び方やメリットデメリットを解説
まとめ|福井県のM&Aのポイント
福井県では後継者不在や地域経済の変化に対応するため、M&Aが企業の存続と成長を支える有力な選択肢となっています。地域密着型の取引が多いことから、信頼関係の構築や取引先への配慮が特に重要です。さらに、スムーズなM&Aを実現するためには、専門的な知識や経験を持つパートナーに相談することが欠かせません。
CINC Capitalでは、地域の特性に配慮したM&A支援を行っており、福井県内の中小企業の課題に寄り添った提案が可能です。M&Aをご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。