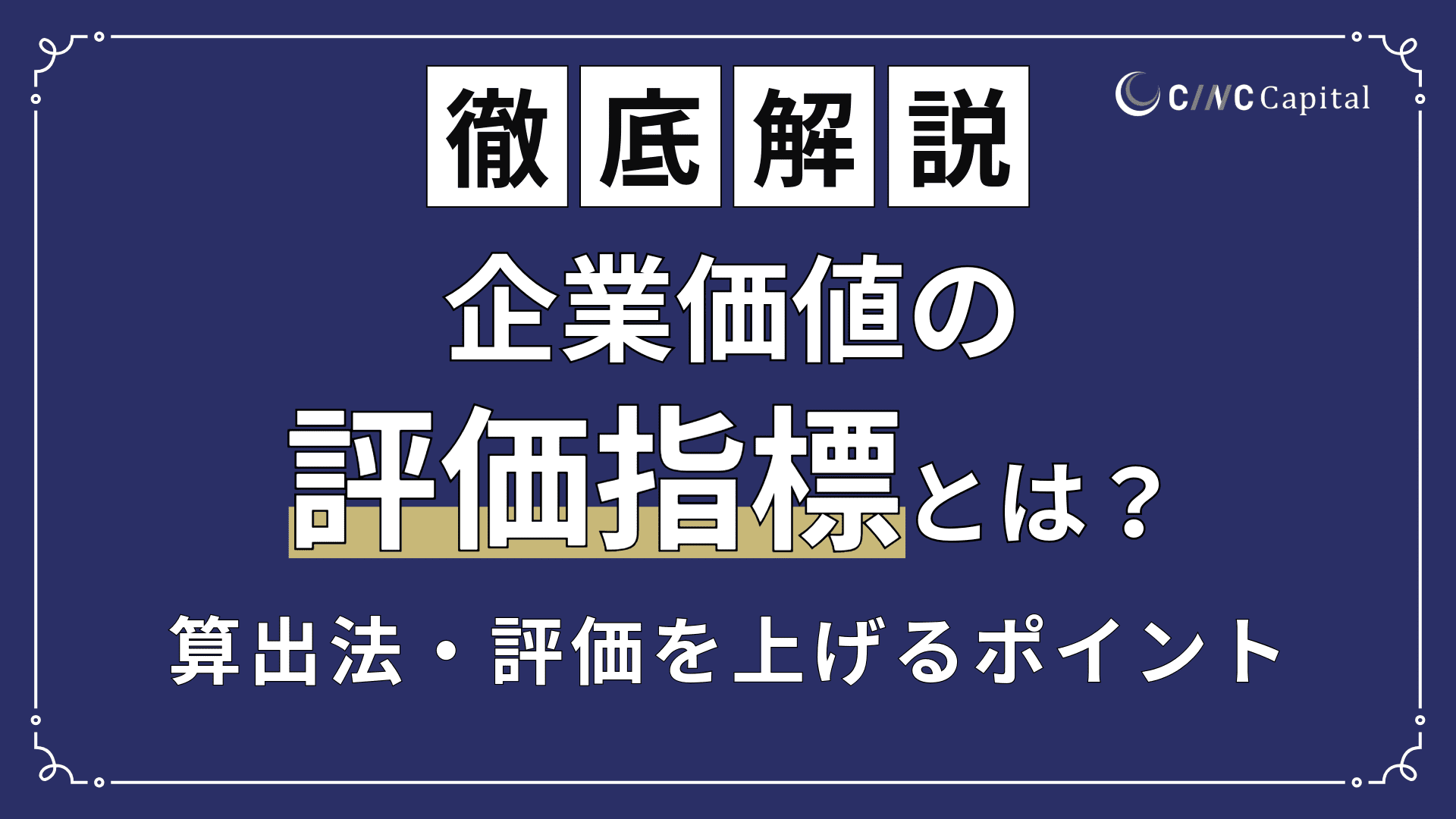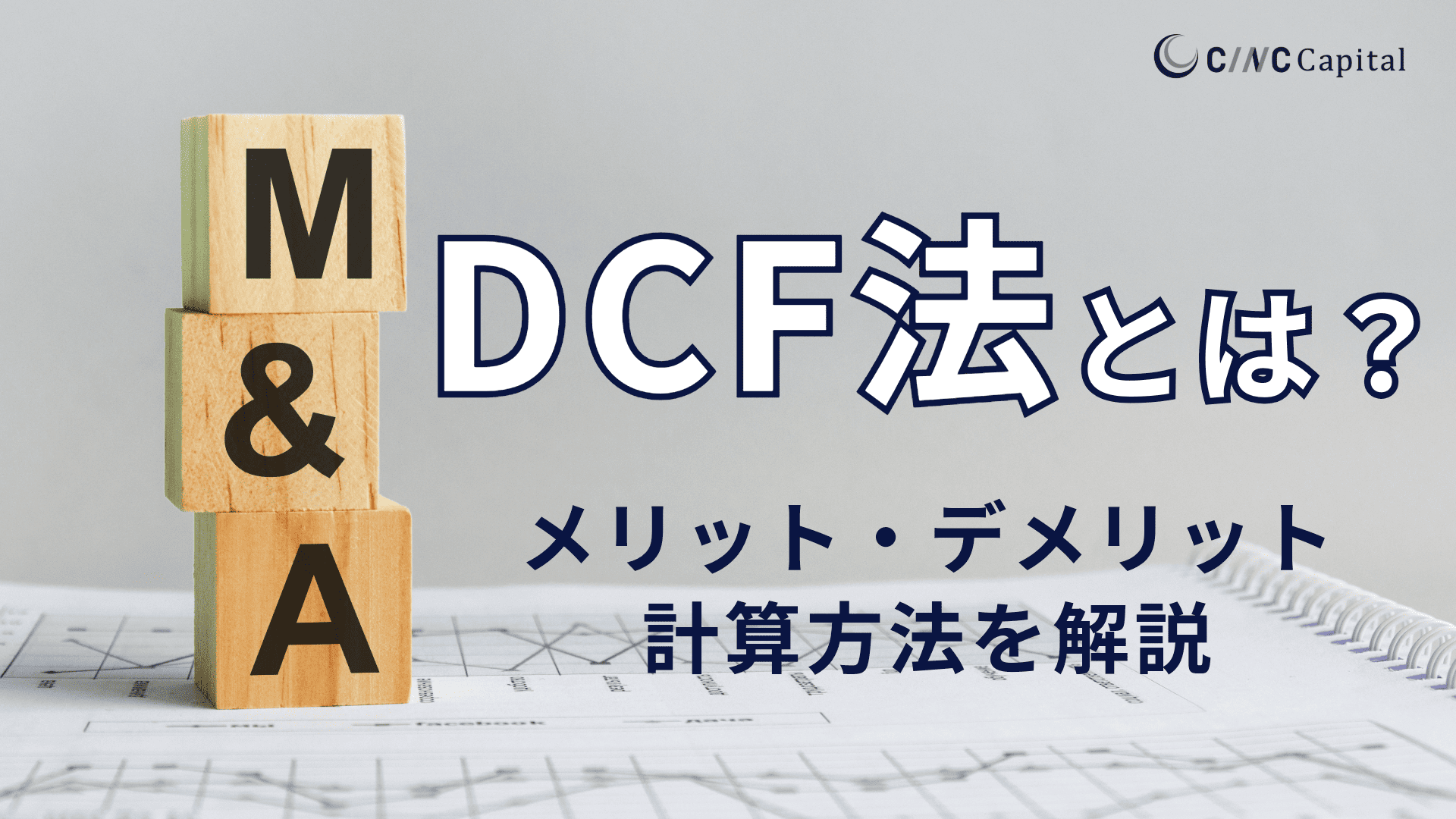CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
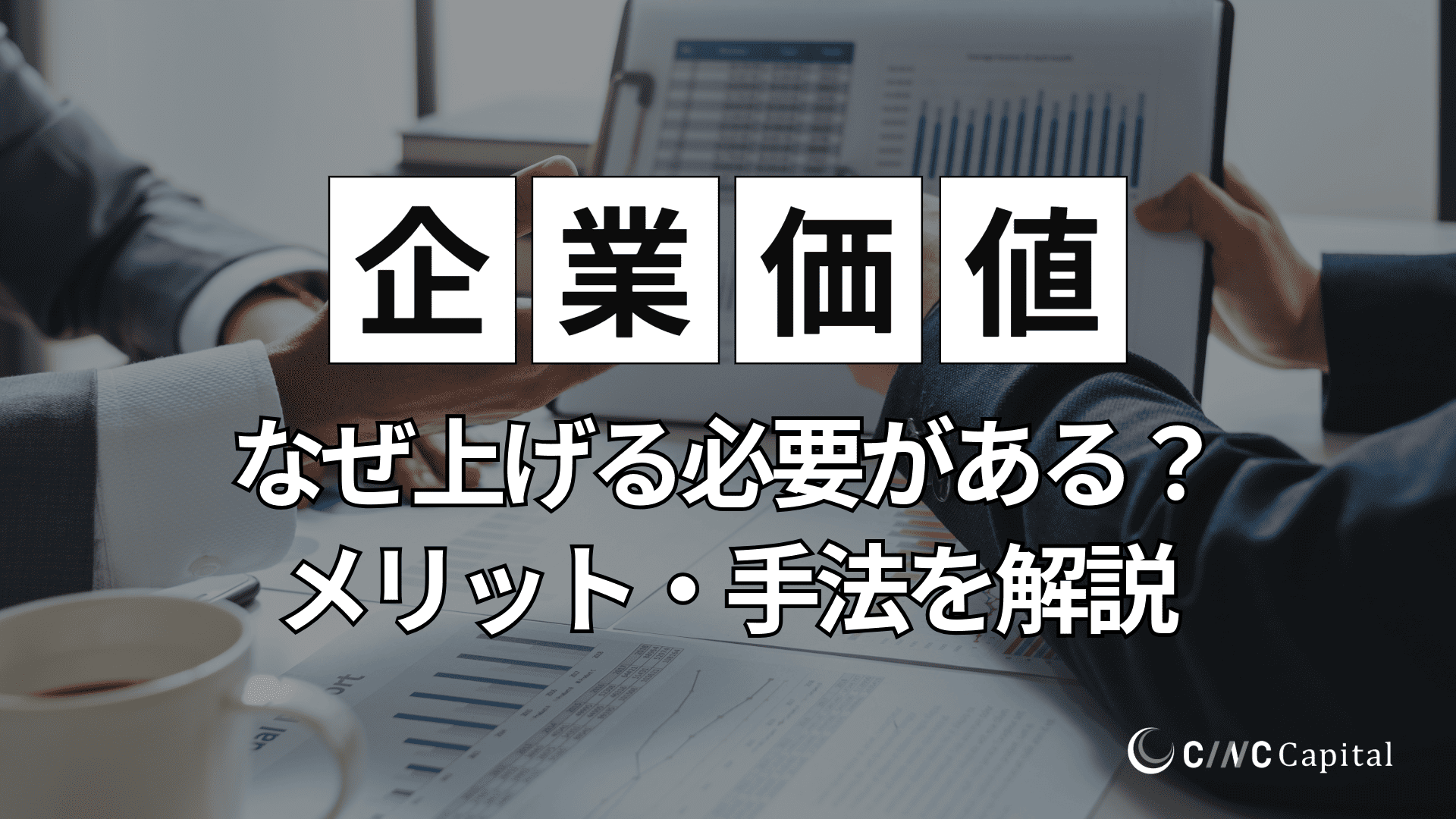
評価 / 企業価値評価(バリュエーション)
- 最終更新日2025.09.26
企業価値向上はなぜ必要?メリットや手法、企業ができる取り組みを解説
M&Aや資金調達の場面で「企業価値を上げろ」と言われても、何から手を付けるべきか悩む方は多いのではないでしょうか。実際、「企業価値とは何か」「どうやって高めるのか」が曖昧なまま、施策が場当たり的になってしまう企業も少なくありません。
本記事では、企業価値の定義から評価方法、価値を高めるための実践的な手法までを体系的に解説します。
目次
企業価値とは?
企業価値(Enterprise Value)とは、財務理論上、企業が将来にわたって生み出す事業キャッシュフローの現在価値(事業価値)と非事業用資産の合計として定義されます。つまり、企業が保有する資産や将来生み出す利益、ブランド力や人材力などを含めた、企業全体の経済的な価値を示す概念です。
株主価値とは異なり、負債も含めた企業全体の価値を示すため、M&Aや事業価値評価において重要な指標となります。本章では、企業価値の基本的な定義と企業価値を向上させるメリットについて解説します。
▶ 売却やM&Aの予定がなくても、企業価値を知っておくことは経営のヒントになります。自社の企業価値を無料でチェックしてみませんか?
企業価値向上はなぜ必要?
企業価値の向上は、企業の競争力を高め、持続的な成長を実現するために不可欠です。なぜなら、企業価値が高い企業は、M&Aや資金調達、採用活動などあらゆる場面で有利な立場を築けるからです。
たとえば、企業価値が高まると、買収・売却の際に好条件で交渉できる可能性が高まります。また、資金調達の場面では、銀行や投資家からの信頼が向上し、より良い条件で融資や出資を受けられます。さらに、社会的信用が向上することで、顧客や取引先からの評価も高まり、安定した事業運営につながります。
このように、企業価値を高めることは、経営の選択肢を広げ、企業の未来を強固にするために必要です。
企業価値を向上させるメリット
企業価値を向上させることで、経営の安定性が増し、さらなる成長の好循環を生み出せます。その理由は、企業価値の高い企業は、さまざまな面で有利な評価を受け、外部からの支援や信頼を得られるからです。
具体的には、投資家や金融機関からの資金調達がスムーズになり、設備投資や人材確保の余地が広がります。また、企業ブランドの評価が高まることで、優秀な人材の採用や顧客ロイヤルティの向上にもつながります。
市場や顧客、地域社会など多方面からの信頼が集まり、結果として事業拡大の基盤を築くことが可能になるでしょう。
企業価値を向上させる主な手法
企業価値を高めるためには、単に売上を伸ばすだけでは不十分です。財務、ブランド、経営統合、組織体制といった複数の観点から、戦略的に改善を重ねることが求められます。本章では、企業価値の向上に直結する代表的な4つの手法について紹介します。
財務戦略
財務戦略の強化は、企業価値を高める最も基本的かつ重要な手法です。その理由は、利益率や資本効率が向上すれば、投資家からの評価や資金調達環境が改善されるからです。
たとえば、ROEやROICの数値を意識し、無駄なコストを削減することで収益性が高まります。加えて、余剰資本を見直して自己資本比率や配当政策を最適化すれば、資本コストの低減にもつながります。
こうした取り組みは、企業の財務体質を健全化し、継続的な利益創出の土台を強化することが可能です。財務戦略を見直すことで、企業の稼ぐ力と資本活用力が向上し、市場からの評価も高まるでしょう。
ブランディング
ブランディングの強化は、企業価値を高めるための有効な手段のひとつです。なぜなら、ブランド力が高い企業は顧客から選ばれやすく、価格競争に巻き込まれにくくなるからです。
たとえば、自社の価値観や独自性を明確に伝え、顧客の信頼や愛着を獲得すれば、ロイヤルカスタマーの獲得につながります。また、優れたブランドは企業イメージを高め、人材採用や取引先との信頼構築にも好影響を与えることができるでしょう。
近年はSNSやWebメディアを活用したデジタルブランディングによって、低コストで高い効果を得られる機会も増えています。ブランディングは、目に見えない資産である企業の「信頼」を高めることで、企業価値を継続的に押し上げます。
M&A
M&Aの活用は、企業価値を大きく引き上げるための戦略的な選択肢です。なぜなら、他社の経営資源を取り込むことで、自社だけでは実現できない成長を短期間で可能にするからです。
たとえば、競合他社や技術力のあるベンチャー企業を買収すれば、既存事業とのシナジーを生み、売上や利益を一気に拡大できます。さらに、海外進出や新規事業への展開においても、現地企業との統合によってスムーズな市場参入が可能になるでしょう。
ただし、M&Aを成功させるには、買収価格や統合後のマネジメントにも慎重な計画と実行が求められます。
組織改革
組織改革は、企業内部の力を最大化し、企業価値を高めるための重要な施策です。その理由は、社員の生産性やエンゲージメントが向上すれば、事業全体のパフォーマンスが改善されるからです。
たとえば、意思決定のスピードを上げるために組織構造をフラット化したり、部門間の連携を強化してシナジーを生み出したりします。また、人材育成や評価制度の見直しによって、社員が自ら成長しようとする環境を整えることも重要です。
働きやすい職場づくりが進めば、優秀な人材が集まりやすくなり、離職率も下がります。このように、社内からの改革によって組織の柔軟性と活力が高まり、企業全体の価値向上につながるでしょう。
企業価値の評価方法
企業価値を正しく把握するためには、客観的な評価手法を活用する必要があります。なぜなら、価値を高める施策の効果を判断するには、定量的な評価軸が不可欠だからです。評価手法には、「インカムアプローチ」、「コストアプローチ」、「マーケットアプローチ」があります。
本章では、企業価値を数値として算定するために活用される3つの代表的な評価アプローチについて解説します。
インカムアプローチ
インカムアプローチは、将来の利益やキャッシュフローを現在価値に割り引いて企業価値を算出する方法です。この手法が選ばれる理由は、企業が将来的に生み出す価値を反映できるため、事業の成長性や収益性を評価しやすいからです。
代表的な手法であるDCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)では、将来の事業計画に基づき5〜10年程度のフリーキャッシュフローを予測し、各年のキャッシュフローを資本コスト(WACC:加重平均資本コスト)で割り引いて現在価値化します。
予測期間以降については、継続価値(ターミナルバリュー)を計算し、これらを合計して企業価値を算出します。上場企業や大企業のM&Aでは、このDCF法が主要な評価手法として採用されることが多く、経営戦略の変化や将来の成長性を数値に反映できる点が大きな特徴です。
コストアプローチ
コストアプローチは、企業の純資産額をもとに企業価値を評価する方法です。この手法が用いられるのは、企業の保有資産の実態を重視し、収益性ではなく資産の価値に着目するケースが多いためです。
特に日本の中小企業のM&Aでは、「時価純資産+営業権法」が広く採用されています。この方法では、まず貸借対照表上の資産・負債を時価に修正して時価純資産を算出し、そこに営業権(のれん価値)を加えて企業価値を評価します。営業権は一般的に過去の利益実績をもとに計算され、これにより収益性も加味した評価が可能になります。
この手法は、財務諸表が整っていない中小企業や、不動産など実物資産を多く保有する企業の評価に特に適しており、日本のM&A実務では非常に一般的な評価方法です。
マーケットアプローチ
マーケットアプローチは、類似企業や市場の取引事例と比較して企業価値を評価する方法です。この手法が選ばれる理由は、市場の相場感や投資家の評価を反映した現実的な金額で算出できるからです。
特に実務で重要なのが「マルチプル法」で、上場企業の評価では株価収益率(PER)や株価純資産倍率(PBR)などが用いられます。一方、中小企業のM&Aや非上場企業の評価では、EBITDAマルチプル(企業価値÷EBITDA)が広く採用されています。
EBITDAとは利払前・税引前・減価償却前利益のことで、企業の収益力を示す指標として重視されています。業種によって適正なマルチプル倍率は異なりますが、一般的には3〜8倍程度の範囲で評価されることが多いです。
ただし、企業価値と売上高の間に直接的な相関関係があるという誤解は避けるべきで、利益の質や安定性、成長性などが企業価値の決定要因となります。
企業価値向上のために企業ができる取り組みや施策
企業価値を高めるには、戦略だけでなく現場で実行できる具体的な施策が重要です。なぜなら、実務レベルの積み重ねが企業の収益性や信頼性に直結するからです。この章では、企業が現場で実行できる主要な取り組み・施策を解説します。
財務戦略の最適化を実施する
財務戦略を最適化することで、企業は利益の質と資本の効率を高め、企業価値を安定的に押し上げることが可能です。その理由は、ROEやROICの改善、コスト削減、資本政策の見直しがすべて、企業の収益性と信頼性に直結するからです。
特にM&Aを視野に入れている企業にとって、財務戦略の最適化は極めて重要です。買収側企業の立場では、無駄な資産や非効率な事業を整理し、バランスシートを健全化することで買収資金の調達力が向上します。一方、売却側企業の立場では、収益の安定性を高め、キャッシュフローの質を改善することで、より高い評価を受けることが可能になります。
また、EBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益)を向上させる取り組みは、企業価値評価で重視されるマルチプル法において直接的に企業価値の向上につながります。
このため、コア事業への集中と非コア事業の整理、固定費の適正化、運転資本の効率化などは、M&Aを見据えた企業価値向上の重要な施策となります。
ブランディングとマーケティング戦略を強化する
ブランディングとマーケティングの強化は、企業価値を高める無形資産の形成につながります。なぜなら、顧客の信頼と愛着を獲得できれば、持続的な収益を生む基盤が構築できるからです。
たとえば、自社の理念や独自性を明確に発信し、消費者に対して一貫したブランドイメージを届けることで、ブランド価値が向上します。また、顧客満足度の向上施策や会員制度などを通じてロイヤルティを強化すれば、リピート率の増加にもつながるでしょう。
さらに、SNSやWeb広告を活用したデジタルマーケティングは、少ないコストで広範囲に訴求できる有効な手段です。
人材戦略と社員エンゲージメントを向上させる
人材戦略の見直しとエンゲージメントの向上は、組織の生産性と創造力を高め、企業価値の源泉となります。その理由は、社員一人ひとりの能力と意欲が、企業の競争力に直結するからです。
たとえば、働きがいのある環境を整えることで、社員の満足度やモチベーションが向上し、離職率が下がります。加えて、キャリアパスの整備やスキルアップ支援によって人材の成長を促進すれば、長期的な企業力の強化にもつながるのです。
さらに、多様性を尊重するダイバーシティ&インクルージョンの推進は、新しい価値創造の土壌となり、社会からの評価向上にも貢献します。人的資本に投資する企業は、内側からの活力を得て、持続的な企業価値の向上を実現できるでしょう。
イノベーションと新規事業の創出を行う
イノベーションと新規事業の創出は、企業の将来価値を押し上げる重要な推進力になります。なぜなら、新しい価値を継続的に生み出すことで、企業の収益基盤を多様化できるからです。
たとえば、自社の強みを活かした研究開発(R&D)投資を行えば、独自技術や製品を通じて市場での優位性を確立できます。また、社外との連携を活かすオープンイノベーションは、スピーディーな事業開発や柔軟なアイデア創出を可能にします。
さらに、スタートアップ企業との協業や買収を通じて、自社にないノウハウや技術を迅速に取り込むことも有効です。
ESG・サステナビリティ経営を推進する
ESGとは、「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(ガバナンス)」の頭文字を取った言葉で、企業が中長期的に価値を創出していくために重要とされる非財務領域の3つの視点を指します。
ESGやサステナビリティ経営の推進は、企業の社会的信頼と長期的価値の向上に欠かせません。その理由は、環境・社会・ガバナンスへの責任ある対応が、今や投資家や消費者からの重要な評価軸となっているためです。
たとえば、脱炭素への取り組み、再生可能エネルギーの導入、リサイクル資源の活用促進など、環境負荷の軽減施策は、気候変動リスクの低減とブランド向上を両立します。また、地域社会や従業員への貢献、CSR活動の展開は、企業の社会的役割への理解と共感を得ることにつながります。
さらに、ガバナンス面ではコンプライアンスの徹底や情報開示の透明性を高めることで、企業への信頼が強固になります。ESGを経営の中心に据えることで、企業は社会からの支持を得ながら、持続的な成長と価値向上を実現できるでしょう。
まとめ|企業価値の向上の取り組みを継続し、持続的な成長を
企業価値は、財務指標や資産だけでなく、ブランド力や人材、将来性など多面的な要素で成り立っています。価値を向上させるには、財務戦略の見直しやブランディングの強化、M&Aの活用、組織改革などを戦略的に実施する必要があります。
さらに、実行段階では、収益性や資本効率の改善、顧客との関係構築、社員エンゲージメントの向上、イノベーション推進、ESG経営への対応が重要です。企業価値の向上の取り組みを継続すれば、信頼性や市場評価が高まり、企業の持続的成長につながるでしょう。