CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
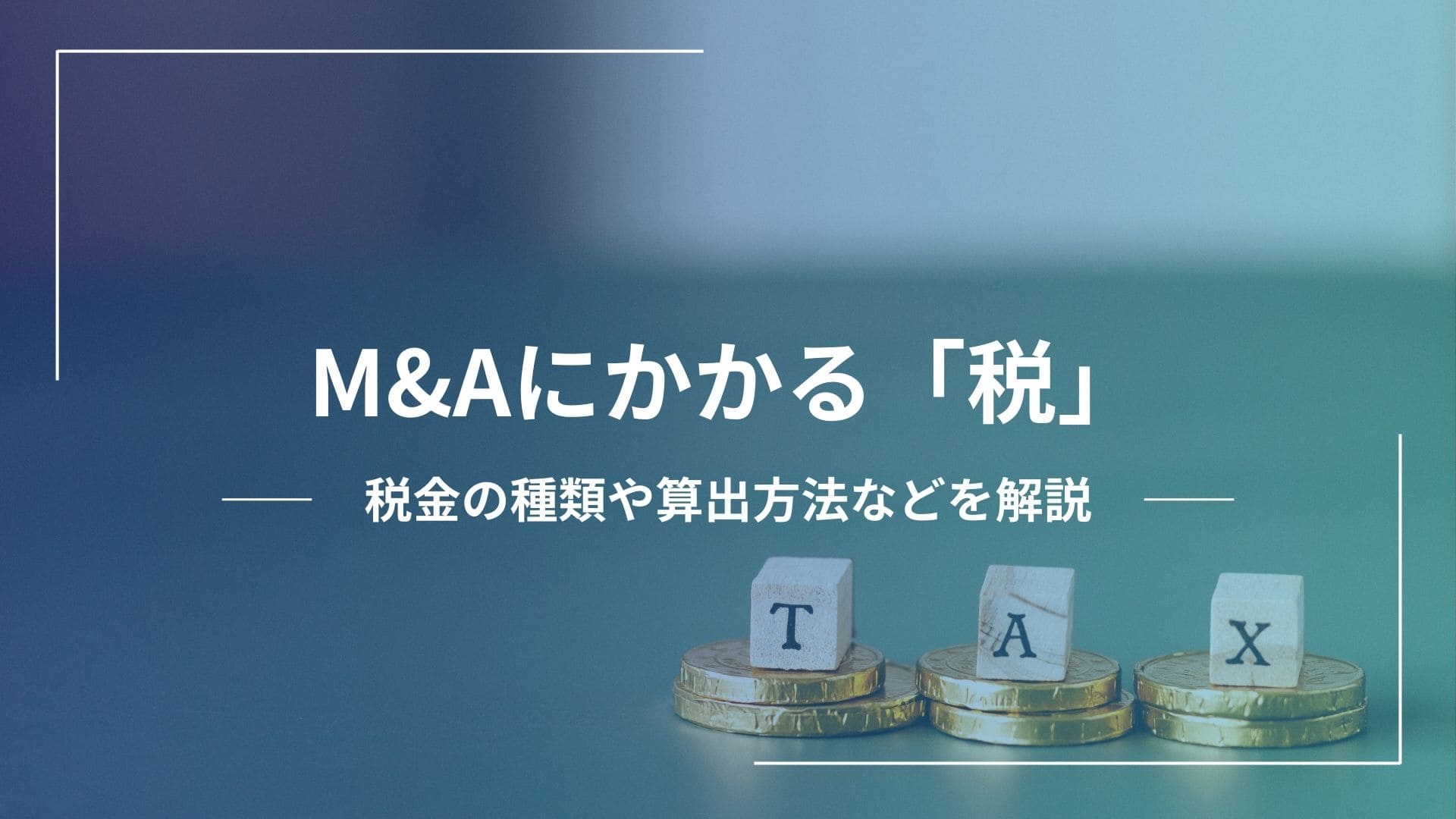
税務
- 最終更新日2025.06.26
M&Aにかかる税とは?税金の種類と算出方法、必要となる税務
M&Aで株式や事業を売却すると、さまざまな税金が発生します。場合によっては複雑な計算や手続きが必要となり、税務で多くの手間がかかります。
また、適切なM&Aスキームの選択によって節税につながる可能性があるため、自社に適した方法を選ぶことが大切です。
M&Aを支援するサービスの利用も視野に入れると良いでしょう。この記事では、M&Aにかかる税の基礎知識を解説します
目次
M&Aにかかる税は?
M&Aにかかる税は、「個人・法人のどちらに該当するか」「どのような手法でM&Aを行うか」によって違いがあります。初めに、M&Aにかかる税の基礎知識を解説します。
個人と法人で異なる
個人がM&Aで売却する場合は「所得税」や「住民税」などが発生し、法人がM&Aで売却する場合は「法人税」「地方法人税」「法人住民税」「事業税」「特別法人事業税」などが発生します。それぞれの税について、詳しくは後の見出しで解説します。
株式譲渡や事業譲渡などの手法によっても異なる
M&Aでは、株式を取引する「株式譲渡」、事業を取引する「事業譲渡」の手法があります。株式譲渡は個人・法人の売り手が、個人・法人の買い手と取引します。一方、事業譲渡は法人の売り手が、法人の買い手と取引するのが違いです。株式譲渡では、譲渡益への所得税(個人の場合)または法人税(法人の場合)が課されます。一方、事業譲渡では課税資産への消費税、譲渡益への法人税が課されます。
M&Aにかかる税の主な種類
ここでは、M&Aにかかる税の主な種類を解説します。個人と法人それぞれの例をご紹介するため、該当する税を確認してみましょう。
個人の場合
所得税
所得税は、個人が株式譲渡で株式を売却した際に、譲渡所得に対して課されます。税率は15%です。以下で解説する「復興特別所得税(0.315%)」や「個人住民税(5%)」と合わせて、分離課税で一律20.315%の税率となります。
復興特別所得税
復興特別所得税とは、自然災害などからの復興の財源を確保するための税金のことです。所得税を納める個人に納税の義務があり、M&Aの譲渡所得も対象となります。個人が株式譲渡で株式を売却した際の譲渡所得に対して課され、税率は0.315%です。
個人住民税
個人住民税とは、居住する市区町村で行政サービスを受けるために納める税金のことです。市区町村内に住所がある個人に納税義務が生じ、税率は5%となっています。個人が株式譲渡で株式を売却した際の譲渡所得に対しても住民税が課されます。
法人の場合
法人税
法人の売り手がM&Aで株式譲渡や事業譲渡をする場合は、法人税を納める必要があります。実効税率(=実質的に負担することになる税率)は、株式譲渡と事業譲渡のいずれも約30~34%となっています。納税する金額は、譲渡益と本業で得た利益に法人税率を掛けて算出します。
地方法人税
地方法人税とは、法人の所得に対して生じる税金の中でも、地域間の税収の格差をなくすために地方自治体の財源とする国税のことです。税率は10.3%となっています。法人税と同様に、譲渡益と本業で得た利益に地方法人税率を掛けて算出します。株式譲渡や事業譲渡で発生します。
法人住民税
法人住民税とは、法人が所在する都道府県や市町村に納める地方税で、株式譲渡や事業譲渡で発生する税金の一つです。資本金の金額や従業員数に応じて課される「均等割」、法人税額に応じて課される「法人税割」からなっています。そのため、税率は会社や自治体ごとに異なります。
法人事業税
法人事業税とは、法人が行政サービスを受けるために納める地方税のことです。株式譲渡や事業譲渡で発生し、法人が所在する都道府県に対して納めます。業種に応じて「付加価値割」「資本割」「所得割」「収入割」の複数の税割で納税する必要があり、それぞれ税率が異なります。
特別法人事業税
特別法人事業税とは、前述した法人事業税から分離され、地方法人課税の税収の格差をなくすために納めるものです。税率は法人の種類によって異なり、「基準法人所得割額」または「基準法人収入割額」に税率を掛けて算出します。株式譲渡や事業譲渡で納める必要があります。
M&Aにかかる税の算出方法
続いて、M&Aで売り手側にかかる税の計算方法をご紹介します。手法ごとに以下の計算式で税を算出します。
株式譲渡にかかる税
売り手側の株式譲渡にかかる税を計算する場合は、「譲渡益×税率」の計算式が用いられます。まず譲渡価額から必要経費を差し引いて譲渡益を算出し、それぞれの税率を掛けることで税金の金額を算出できます。なお、必要経費には株式の取得費用やサービスの手数料などが含まれます。
事業譲渡にかかる税
売り手側の事業譲渡にかかる消費税は、商標や営業権などの課税資産に対して課されます。実際に消費税を負担するのは買い手側ですが、消費税分を上乗せして売り手側に支払い、売り手側が納付するのが一般的です。その際は、「課税資産×消費税率(10%)」の計算式が用いられます。
事業譲渡にかかる法人税は、譲渡益に対して課されます。譲渡によって得た対価が、譲渡する資産と負債の差額よりも多くなった場合に税金が発生するのがポイントです。計算する際は「譲渡益×法人税率」の計算式が用いられます。
その他の関連税金(不動産取得税、登録免許税など)
ここまで売り手側の税金について解説しましたが、事業譲渡では買い手側に税金が発生する場合があります。例えば、譲渡対象に不動産が含まれるケースでは、買い手側に「不動産取得税」や「登録免許税」などが課されます。いずれも土地または建物の固定資産税評価額に税率を掛けて算出します。
M&Aで必要となる税務
M&Aで必要となる税務は、手法や適用条件によって異なります。税金の金額を踏まえて自社に適した手法を選択するためには、M&Aの税務知識が必要となります。場合によっては専門のサービスによるサポートを検討すると良いでしょう。
株式譲渡の税務
株式譲渡の場合、売り手側が買い手側へ株式の引き渡しを行い、売り手側へ対価を支払います。その際、M&Aの株式譲渡では一般的に多額の対価が生じるケースが多いことから、正確に税金の計算を行うことが重要です。株式を引き渡した日の翌年に確定申告によって税金を納付する必要があります。
事業譲渡の税務
事業譲渡の場合、売り手側の企業が買い手側の企業へ事業を引き渡し、売り手側はその後に退職金や配当によって対価を受け取ります。譲渡する資産・負債の対象が多いほど手続きの負担が大きくなります。また、事業譲渡を実行すると売り手側の企業は多額の譲渡益に対して課税されるため、節税対策が求められます。
合併、株式交換・移転、会社分割の税務
M&Aでは会社の組織再編が行われる場合があります。具体的には、複数の会社を合併するケース、別の会社へ株式を取得させて株式交換や株式移転をするケース、事業を他の会社へ承継させ会社分割をするケースなどが挙げられます。
これらの組織再編を行う場合は、組織再編税制が適用され税金の負担を軽減できる可能性がある一方、適切に納税するための専門知識が不可欠です。
まとめ|M&Aにおける税の仕組みを理解した上で活用しよう
ここまで、M&Aで押さえておきたい税の仕組みを解説しました。M&Aで売り手となる企業は、「法人税」「地方法人税」「法人住民税」「事業税」「特別法人事業税」などを納める必要があります。その際、会社の規模や所在地などの条件によって税率が変わる場合があり、税務では複雑な計算や手続きが生じます。
M&Aを利用する際は専門家によるサポートを受けるのも一つの手です。M&Aにおける税の仕組みを理解し、自社の条件に合わせて節税につながる方法を検討しましょう。

















