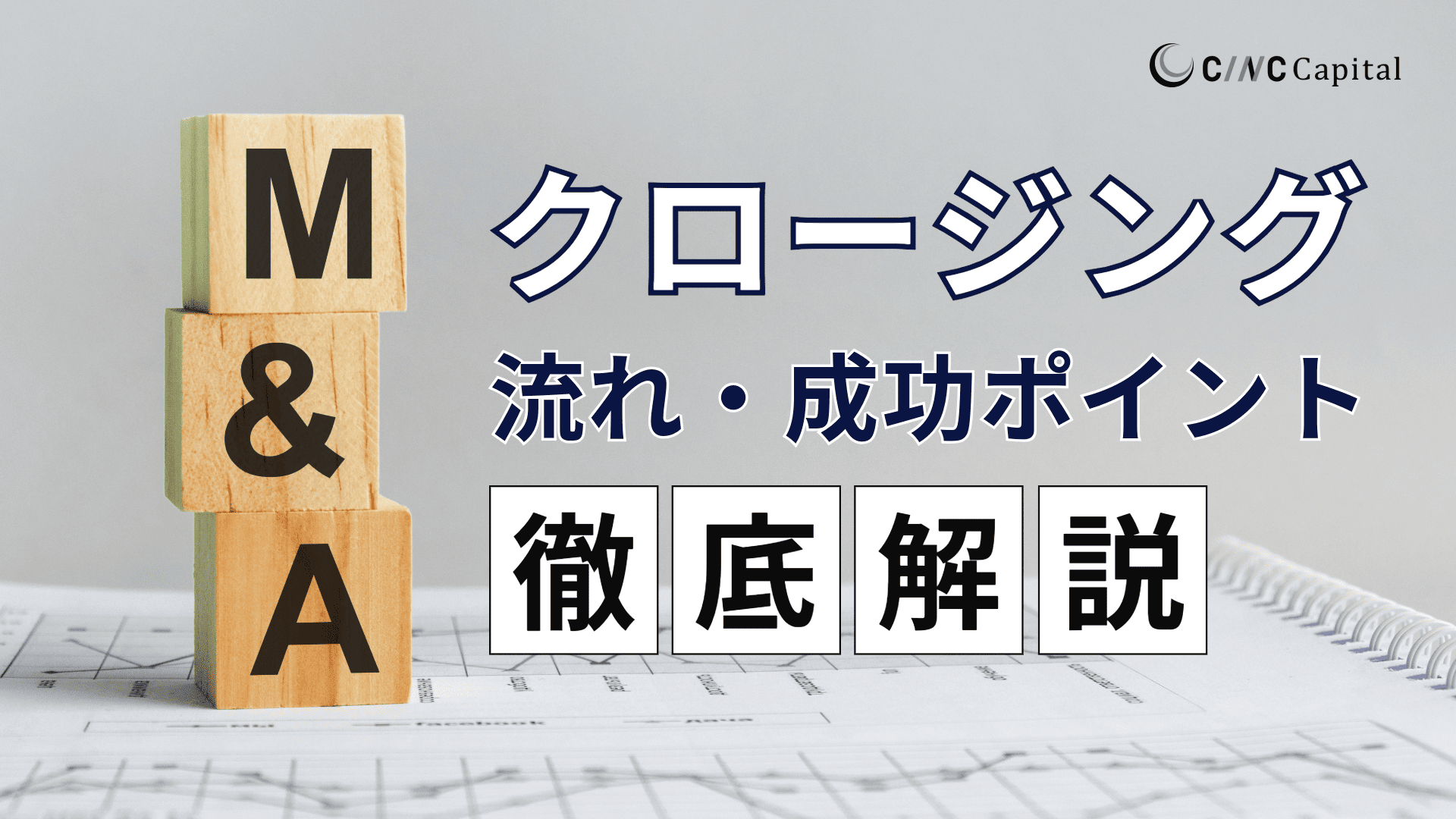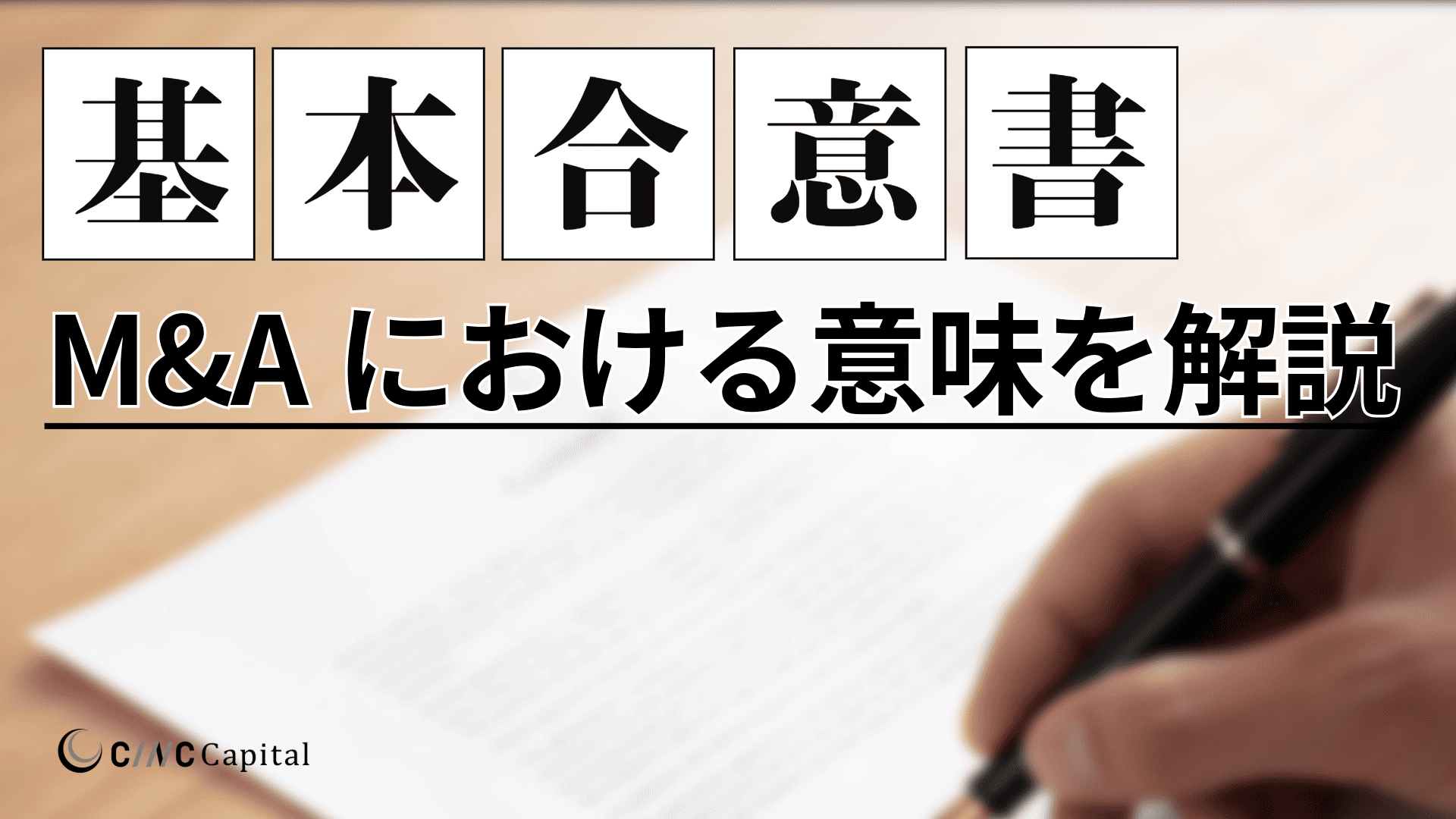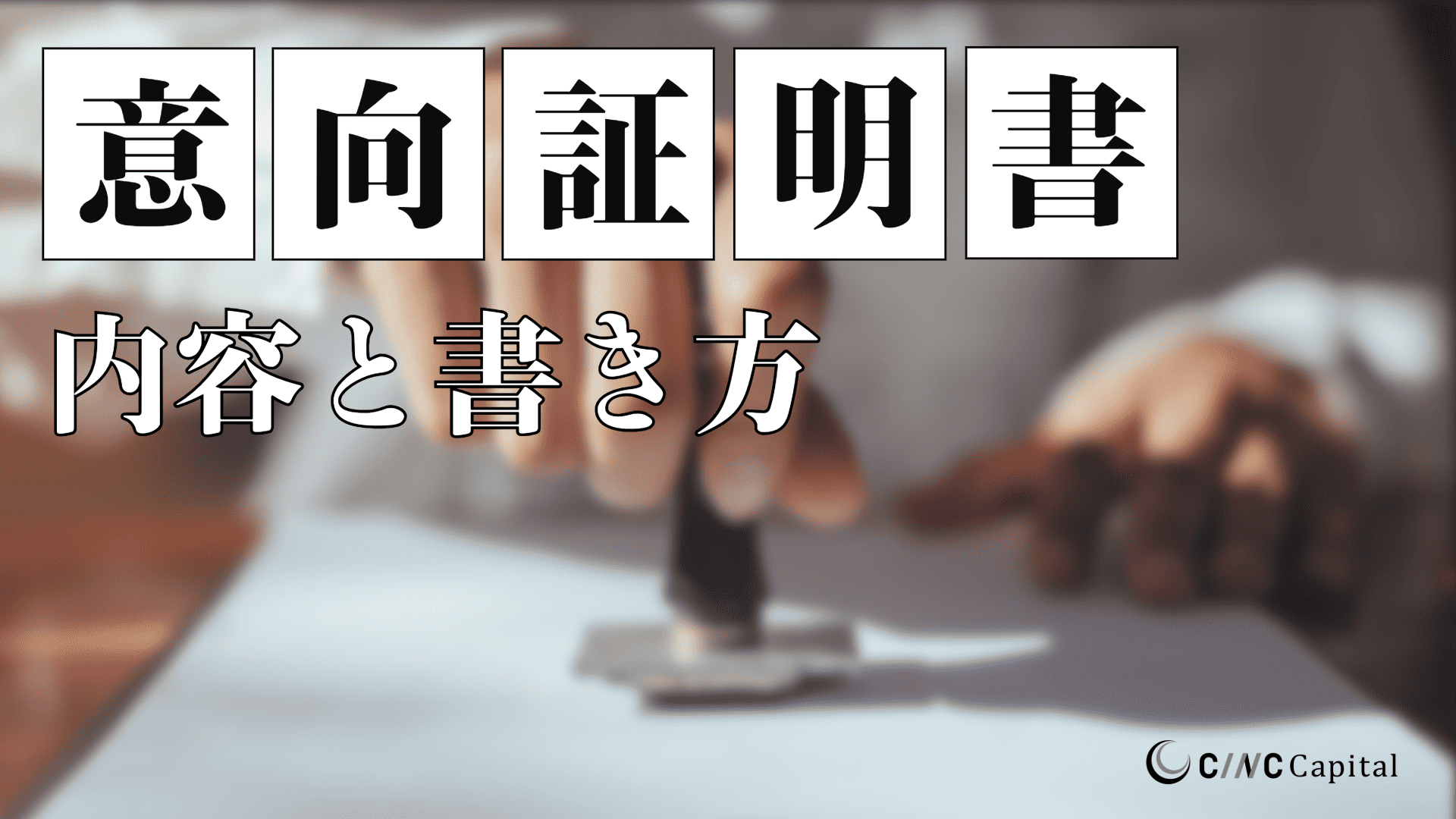CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

手続き・契約
- 最終更新日2025.06.26
M&Aで必要な契約書の種類や注意点を徹底解説!
M&A(Mergers and Acquisitions)を実施する際には、さまざまな法的観点やリスクをカバーするために複数の契約書が必要になります。単に合意内容を紙に落とし込むだけでなく、各契約書にはそれぞれ特有の役割や重要な条項が存在します。
例えば、秘密保持契約(NDA)は交渉の早い段階で締結されることが多く、機密情報の取り扱いに関するルールを明確化する必要があります。また、最終契約書(SPAや事業譲渡契約書など)では合意内容が法的拘束力をもって定められるため、条件面や責任範囲をきちんと把握しておかなければなりません。
本記事では、M&Aで取り交わされる契約書の種類やその内容、さらにトラブルを防ぐための重要事項や作成時の注意点について掘り下げて解説します。実際の交渉や手続きを円滑に進めるうえで不可欠な知識を身につけ、より安心してM&Aを進められるようにしましょう。
目次
M&A契約書が必要となる理由
M&Aでは多くの情報や資産がやり取りされるため、法的拘束力を持つ契約書が欠かせません。口頭での合意や非公式な書類では、情報不足や認識のズレによるリスクが高まるため、書面によって詳細を明確化する必要があります。契約書があることで、当事者間の責任範囲やリスク分担が明確になり、後から起こり得る紛争を最小限に抑えられるのです。
特にM&Aでは企業の内部情報や知的財産が扱われるため、事前に秘密保持に関する規定を過不足なく盛り込むことが不可欠です。株式譲渡や事業譲渡などの取引手法に応じて、契約書の内容も変わってきます。そうした複数の書類を正しく使い分けることで、取引のスムーズな進行が期待できます。
また、売り手と買い手の目的や条件、そしてリスクへの考え方もそれぞれ異なるケースが多いため、契約書の作成過程では綿密な協議が行われます。協議の内容を反映した契約書を作成しておけば、交渉結果を後々まで正確に残しておけるだけでなく、法的にも強く保護される点が大きなメリットです。
M&A契約書の種類と内容
M&Aにおいて取り交わされる主な契約書には、取引前の情報保護を担保するものから、最終合意内容を明文化するものまでさまざまな種類があります。ここでは、主な契約書を整理します。
秘密保持契約(NDA)
秘密保持契約は、取引相手へ開示する企業情報やノウハウを外部に漏らさないことを約束するための書面です。交渉が始まる段階で締結されることが一般的であり、デューデリジェンスや価格交渉の際に安心して情報をやり取りするための基本ルールを示します。
具体的には、開示する情報の範囲や禁止行為、違反時の損害賠償に関する取り決めを含むケースが多いです。特に機密情報の扱いによっては、企業価値に大きな影響が生じる可能性もあるため、きちんと精査し適切な締結を行うことが求められます。
機密情報の定義があいまいなままだと、開示する側も受け取る側もリスクを負うことになるため、契約書中では可能な限り明確な記載をすることが重要です。これによって、後の段階で生じる誤解やトラブルを防止できます。
アドバイザリー契約書
M&Aアドバイザーに業務を依頼する際に取り交わすのがアドバイザリー契約書です。ここでは報酬体系や成果報酬の条件、業務範囲、契約期間などが明示されます。専任契約(独占契約)の場合は、他のアドバイザーを同時に利用しない規定を盛り込むケースもあります。
アドバイザリー契約によって、アドバイザーが提供するサービスの範囲と責任が明確化され、双方とも交渉プロセスを円滑に進められます。さらに成功報酬などのフィー構造が合意されることで、アドバイザーのモチベーションや役割が明確となり、質の高いサポートが期待できます。
業務範囲の確認は非常に大切で、デューデリジェンスや企業評価、さらには交渉アレンジといった各ステップをどこまでサポートしてもらうか、事前にしっかりすり合わせる必要があります。納得いく契約形態を選ぶことで不足や重複を防ぎ、スムーズなM&Aプロセスに貢献します。
意向表明書(LOI)
意向表明書は、買い手または売り手がM&Aに関する初期段階での意思や主な条件を示すための書面です。法的拘束力が限定的であることから、双方が合意に至る前のたたき台として利用されます。
この段階では価格帯や大まかなスケジュール、前提条件などが提示されることが多く、契約の最終カタチを見極めやすくする効果があります。ただし、あくまで意向ベースの内容であるため、後の交渉において条件が変動する可能性も念頭に置く必要があります。
また、あまりに詳細を盛り込みすぎると、基本合意書との境界があいまいになり、後のステップで混乱を引き起こす場合があります。意向表明書としての位置づけと役割をしっかり認識し、適度なレベルの情報をまとめるようにしましょう。
基本合意書(MOU)
意向表明書に続き、当事者間で主要条件に合意した段階で取り交わされるのが基本合意書です。ここでは価格の基準や譲渡・譲受の条件、スケジュールなどについて、比較的具体的な合意内容を記載します。
基本合意書には、法的拘束力がある条項とそうでない条項が混在しているケースが多いため、文言の使い方や各条項の解釈が重要です。多くの場合、排他交渉権や違約金の定めなど、ある程度拘束力のある内容を含むことも少なくありません。
この段階で合意内容が固まってくると、買収監査(デューデリジェンス)や更なるネゴシエーションが進められ、最終契約書へと段階が移行します。明確な基本合意書が存在すれば、次のステップをスムーズに進められる大きな手がかりとなります。
最終契約書
最終契約書は、M&Aにおける実質的な契約の締結を意味し、法的拘束力を持つ合意を正式に確定する書類です。この契約書には取引価格や譲渡の条件、責任分担などが具体的かつ詳細に明示されています。必ず弁護士などの専門家と連携して、内容を精査するようにしましょう。
通常、最終契約書には表明保証や違約金、秘密保持義務、競業避止義務など、後々のトラブルを防止するための条項が網羅的に含まれます。さらに、クロージング後の調整事項や、想定外の事象が発生した場合の対応策など、実務上の考慮点も含まれるケースが一般的です。
締結後に契約内容が修正されるのは容易ではないため、作成段階で丁寧に協議を行い、双方が合意した内容を漏れなく形にすることが肝要です。次に、最終契約書の中でも主要な株式譲渡契約書、事業譲渡契約書について紹介します。
株式譲渡契約書(SPA)
株式譲渡契約書(Share Purchase Agreement)は、株式の売買条件や譲渡価格、支払い方法、譲渡時期などを詳細に定める契約書です。株主構成の変更によって会社支配権が移転するため、特に法務・財務リスクの評価が重要となります。
この契約書には、対象会社の表明保証や責任追及に関する規定が盛り込まれることが一般的です。表明保証で虚偽があった場合には、損害賠償や契約解除に発展する可能性があるため、売り手・買い手ともに書面の内容を十分に検討する必要があります。
また、株式譲渡時の代金支払い方法にもいくつかのパターンがあります。現金取引や株式交換、分割払いなどさまざまであり、双方の合意と税務・会計上の考慮が必要です。事前に専門家へ相談することで、最適なスキームを選択しやすくなります。
事業譲渡契約書
事業譲渡契約書では、事業に関する資産や負債、従業員の引き継ぎ範囲を明確化します。株式譲渡とは異なり、譲渡対象となる事業部門や資産・負債を選別して移転する仕組みであるため、細かい取り決めが必要です。
引き継ぎ対象の詳細や債権債務の扱い、従業員の雇用条件など、最終契約書に含めるべきポイントは多岐にわたります。事業ごと移転する場合には、ライセンス契約の移転や取引先との契約関係なども整理しなければなりません。
必要に応じて分割登記や許認可の再取得など、法的な手続きも発生し得るため、締結前にこれらのハードルを洗い出しておくことが大切です。実務面でもスムーズに移行できるよう、複数のステップを見据えた計画的な準備が求められます。
M&A契約書に盛り込むべき重要事項
契約書には、交渉段階からトラブルを防ぐために重要な条項が盛り込まれます。中でも、契約書に掲載すべき重要事項を説明します。
有効期限
契約書の効力がどの時点から開始し、いつまで存続するかを明確に定めるのが有効期限の条項です。交渉が長期化する場合には、期限を設けることで再度の交渉や契約更新の判断がしやすくなります。
また、有効期限が明確でないと、いつまでも拘束力が続いてしまうリスクがあり、特に秘密保持義務や競業禁止義務などの期間設定には注意が必要です。契約書ごとに適切な期限を設けることで、双方のリスクと負担をバランスよく管理できます。
期限を定める際には、法律上の要件や実務上の手続きを考慮することも大切です。特に許認可が必要な業種や長期間にわたるプロジェクト型のM&Aの場合、期限設定に柔軟性を持たせる場合もあります。
表明保証条項
表明保証条項は、売り手と買い手の双方が提示する情報の正確性や適法性を保証するための重要な規定です。企業の財務状況や契約関係、知的財産の帰属など、あらゆる面で正確な情報が開示されていることを前提に、取引の条件が成り立ちます。
万が一、情報が虚偽や不正確であることが判明した場合には、損害賠償や契約解除といった重い責任が生じる可能性があります。特に買い手は、表明保証条項を入念にチェックすることで、潜在的なリスクを把握し、価格交渉やリスク分担に反映させることができます。
ただし、売り手側にとっては表明保証の範囲を広げすぎるとリスクが大きくなるため、できるかぎり負担を限定的にする工夫が必要です。専門家のアドバイスを受けながら精度の高い条項を設定することで、双方が納得できる契約内容を構築できます。
違約金、損害賠償、解除条項
契約違反が発生した場合に備えて、違約金や損害賠償、そして契約解除の条件を明確にしておくことは必須です。特に大規模なM&Aでは、交渉決裂や契約違反による損失が多額に及ぶ可能性があるため、こうした条項の設定は慎重に行われます。
違約金は実質的にペナルティとして機能し、当事者間に適度な緊張感をもたらす役割を果たします。しかし、過度に高い設定をすると契約締結自体が困難になる場合もあるため、現実的な水準を見極めることが重要です。
損害賠償や解除条項についても、何が違約行為にあたるのかや、どの程度の損害をカバーするのかといった点を具体的に定める必要があります。曖昧な規定で合意してしまうと、後に解釈の相違から紛争が起こるリスクが高まるでしょう。
競業避止義務と秘密保持規定
M&A後に売り手や経営陣が新たな事業を始め、買収先のビジネスに直接競合する状況は避けたいと考える買い手が多いです。そこで設定されるのが競業避止義務の条項で、一定期間や地域での競業を制限することで買い手の投資を保護します。
同時に、秘密保持規定も重要性を増します。取引後も企業のノウハウや顧客情報が外部に漏れることは大きなリスクにつながるため、秘密情報の取り扱いを明確に定めることで情報保護を徹底するのです。
これらの条項は一方的に設定すると契約が不利になりがちです。双方のビジネス事情を踏まえ、制限期間や対象範囲を慎重に調整することで、適切なバランスを保つことが望まれます。
クロージング後のフォローアップ対応
クロージング後にも、引き継ぎ作業の進行や契約条件の変更への対応などが必要になる場合があります。そこで、事後処理や追加対応についてのルールを明確に取り決めておくことが、円滑な移行を支えるポイントになります。
具体的には、債権債務の整理や許認可の変更手続き、従業員への対応、さらには担当者間の情報共有といったタスクが挙げられます。こうした事務的な作業がスムーズに完了しないと、予定通りのシナジーが得られないリスクも生じます。
クロージング後のトラブルが起きた場合の調整方法や仲裁プロセスも、事前に取り決めがあると安心です。取引終了後も一定期間は連携体制を保つことで、スムーズな統合やシナジー創出を実現しやすくなります。
M&A契約書作成の流れと注意点
契約書を作成する際、各ステップごとに明確な目的と注意点を押さえることが重要です。ここでは、契約書作成の大まかな流れとともに、主な注意点を3つご紹介します。
契約書作成前の準備
契約書の作成に取りかかる前に、まずはM&Aの目的やスキーム、予算、スケジュールなど基本的な事項を整理しておく必要があります。ここで整理ができていないと、交渉の方向性がぶれたり、不要なリスクを背負ったりする可能性があるからです。
また、交渉相手との理解を深めるために、企業の経営状況や市場ポジションなども事前調査を進めることが重要です。これにより、どのような条件を契約書に盛り込むべきかが明確になります。
さらに、社内外の担当者や専門家を適切なタイミングで巻き込み、役割分担を明確にすることも大切です。そうすることで、必要な書類の準備や法的リスクの早期チェックが可能となり、スムーズに契約作成へ移行できます。
法的拘束力やリスクの明確化
M&A契約書には、法的拘束力を持つ条項と、あくまで協議事項であるにとどまる条項が混在する場合があります。そのため、それぞれの条項がどの程度の拘束力を持つのかを明確にし、双方の認識にずれがないようにすることが重要です。
また、リスクが高いと判断した分野に関しては、詳細な条項や条件を追加し、リスクの所在や責任分担を明確化することが望まれます。例えば、財務リスクや訴訟リスクがある場合には、売り手・買い手どちらの責任とするのかを契約書にきちんと書き込む必要があります。
曖昧な表現のまま合意してしまうと、後から解釈の違いが生まれ、有利・不利をめぐる対立が発生する可能性が大きくなります。契約書は将来の紛争防止策でもあるため、明確化できる点は可能な限り明記する姿勢を持つことが大切です。
専門家との連携(弁護士、税理士等)
M&Aでは大規模な資本移動や組織変更が伴うため、法律・税務・会計など幅広い分野の知識が必要です。そこで、弁護士や税理士、会計士など専門家との連携が不可欠となります。彼らの知見を得ることで、契約書作成の精度と交渉力を高めることが期待できます。
特に最終契約書の内容は、実際の取引成果やリスク分担に大きく影響するため、専門家のチェックがないまま条項を決めてしまうと後で見落としが発覚するおそれがあります。時間やコストはかかりますが、リスクを最小化するためには必須のプロセスと言えます。
また、税制優遇措置の活用や必要な許認可の確認など、専門家にしかわからない要素も多々あります。契約書に記載すべき事項や見直すべきスキームをスピーディーに把握するためにも、早めの段階から専門家を巻き込むことが推奨されます。
まとめ|M&A契約書の役割と重要性
M&Aにおける契約書は、取引の安全とスムーズな進行を保証するために欠かせない要素です。
各段階で取り交わされる秘密保持契約や基本合意書、最終契約書は、それぞれが異なる目的や拘束力を持った重要な書面です。これらを正しく使い分けて内容を明確化することで、後の紛争リスクを最小限に抑えながら円滑に手続きを進められます。
また、契約書には有効期限や表明保証、競業避止義務など、実務仮定で大変重要な要素が多く含まれます。こうした条項をしっかりと整理し、買い手・売り手双方が納得する形で合意を結ぶことが、M&Aの成功には不可欠です。
最終的には、専門家と緊密に協力しながら契約書を作成・チェックし、法人税や関連法令への適合性も十分に考慮する姿勢が重要です。リスクと責任の所在を明確化し、安心して取引を完了させるために、M&A契約書の制作に十分な時間とリソースを投入しましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aに関するご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。