CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
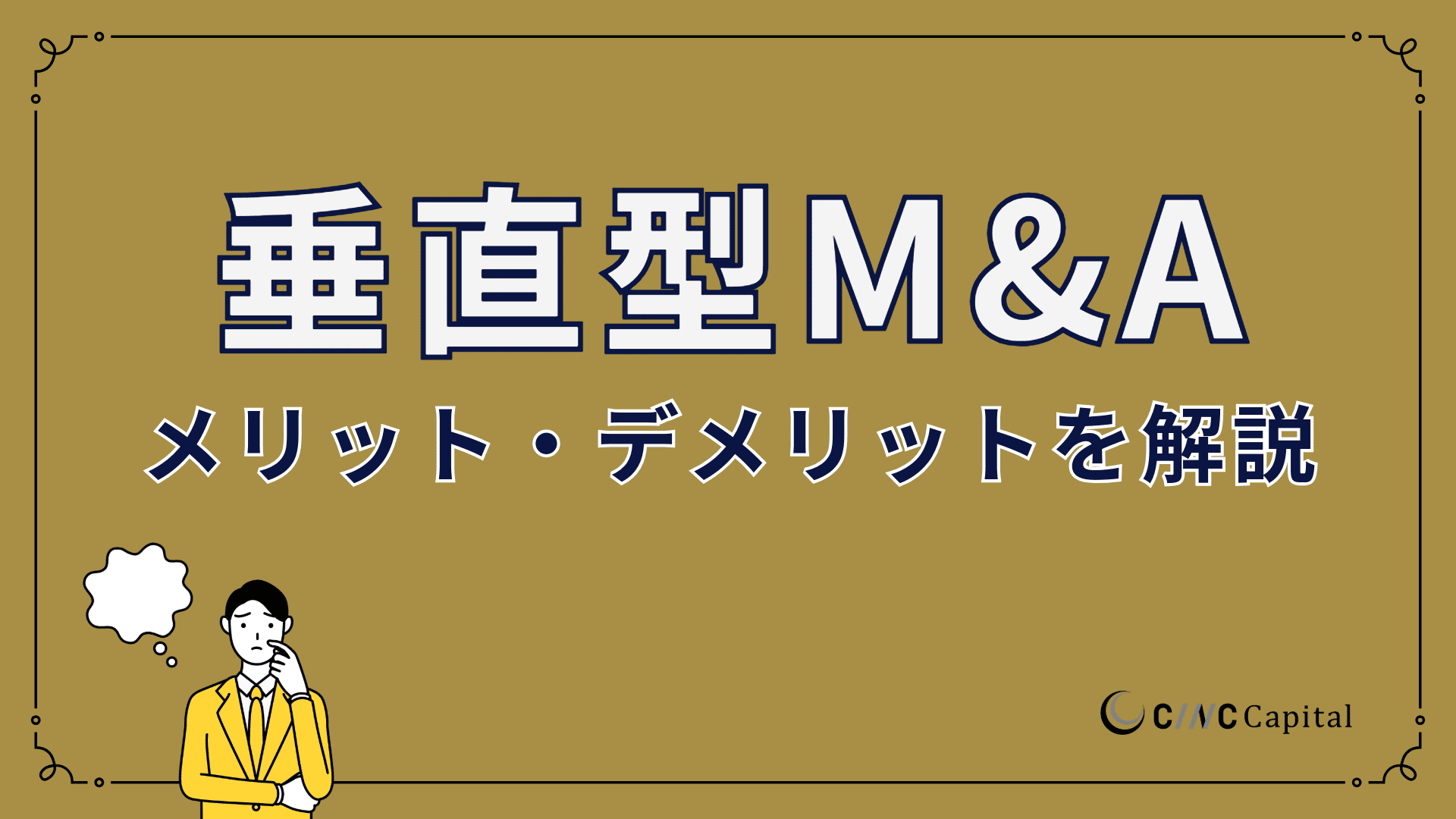
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.07.09
垂直型M&Aとは?水平型M&Aとの違いやメリットデメリットを解説
企業の成長戦略としてM&A(合併・買収)を検討する際、どのような形態が最適か悩むことがあるのではないでしょうか。特に、サプライチェーンの最適化やコスト削減を目的とした垂直型M&Aに興味を持つ経営者も多いはずです。
本記事では、垂直型M&Aの基本概念から、メリット・デメリット、成功事例、実施時のポイントまで詳しく解説します。
目次
垂直型M&Aとは?
垂直型M&Aとは、企業がサプライチェーンの異なる段階にある企業を買収し、統合するM&Aの形態です。主に原材料の供給、製造、流通、販売などの事業プロセスを内製化し、コスト削減や供給の安定化を目的としています。
垂直型M&Aと水平型M&Aとの違い
垂直型M&Aと水平型M&Aの違いは、統合する企業の関係性にあります。垂直型M&Aはサプライチェーンの異なる段階にある企業同士の統合を指し、供給の安定化やコスト削減を主な目的としています。一方、水平型M&Aは同じ業界内の企業同士が統合し、市場シェアの拡大や競争力の強化を目指すものです。どちらのM&Aを選択するかは、企業の戦略や成長目標に応じて慎重に判断する必要があります。
垂直型M&Aのメリット
垂直型M&Aを実施することで、企業は様々なメリットを享受できます。ここでは、垂直型M&Aによって得られる代表的なメリットについて解説します。
サプライチェーンの内製化によりコスト削減ができる
垂直型M&Aによって、企業はサプライチェーンの各工程を自社で管理できるようになります。これにより、外部業者への支払いを抑え、コスト削減を実現できます。
外部のサプライヤーを利用すると、中間マージンや取引コストが発生するため、製造コストが高くなります。しかし、必要な原材料や部品の供給元を自社グループ内に持つことで、これらのコストを削減できます。
コスト削減は、製品価格の引き下げや利益率の向上につながります。結果として、市場での競争力を強化し、企業の成長を後押しする要因となります。
原材料や流通の安定確保により供給リスクを低減できる
垂直型M&Aを実施すると、企業は原材料の調達や流通の管理を自社で行えるようになり、供給の安定化が図れます。これにより、市場の変動や外部業者の事情に左右されるリスクを低減できます。
外部の供給業者に依存している場合、天候不順や経済状況の変化により原材料の供給が滞ることがあります。しかし、自社で供給元を確保していれば、こうしたリスクを軽減できます。
供給リスクの低減は、生産計画の安定化につながります。安定した供給体制を構築することで、企業の信頼性が向上し、事業の持続的な成長が可能となります。
中間マージンを排除して利益率を向上させられる
垂直型M&Aにより、企業は製造から販売までのプロセスを自社で管理できるようになります。これにより、卸売業者や販売代理店などの中間業者を介さずに済み、利益率を向上させることが可能になります。
外部業者を経由すると、仲介手数料や販売マージンが発生し、製品価格が高くなります。しかし、自社で販売網を確保することで、これらの余分なコストを削減できます。
利益率の向上は、企業の収益性を高め、価格競争においても優位に立つことができます。特に、コスト競争の激しい市場では、中間マージンを削減することで価格設定の自由度を高めることができます。
製造から販売までの一貫体制により品質管理を強化できる
垂直型M&Aを活用すると、企業は製造から販売までのプロセスを一貫して管理できるようになります。これにより、品質管理を徹底し、ブランド価値を高めることが可能になります。
外部業者に生産や流通を委託すると、品質基準が一律に保たれないリスクがあります。しかし、自社内で管理することで、厳格な品質基準を設定し、製品のばらつきを防ぐことができます。
品質管理の強化は、顧客満足度の向上やクレームの削減につながります。品質の安定性が確保されることで、長期的なブランド価値の向上が期待できます。
競合他社への依存度を下げて市場での競争力を高められる
垂直型M&Aを行うことで、企業は特定の供給網における競合他社との差別化を図り、市場での競争力を強化できます。
外部のサプライヤーや流通業者に依存している場合、同じサプライヤーを利用する競合他社との差別化が難しくなり、価格や納期での優位性を確保しづらくなります。
しかし、重要な供給元をグループ内に取り込むことで、自社の裁量で価格や供給戦略を柔軟に構築できるようになります。
こうした競争力の強化は、企業の市場での地位確立やブランド優位性の向上に寄与し、持続的な成長につながります。
垂直型M&Aのデメリット
垂直型M&Aは多くのメリットをもたらしますが、一方で経営の難易度が上がったり、取引先との関係悪化を招いたりするといったデメリットもあります。ここでは、垂直型M&Aのデメリットについて解説します。
異なる業種・事業を統合することで経営の複雑さが増す
異業種の統合により、ビジネスモデルや商習慣の違いから経営が複雑化し、統一方針の確立に時間やコストがかかります。
このような課題を解決するには、M&A前に十分な業界調査を行い、統合プロセスをスムーズに進めるための計画を立てることが重要です。
既存の取引先との関係が悪化しビジネス機会を失うリスクがある
垂直型M&Aを実施すると、自社内での業務完結が可能になりますが、これまで取引のあった外部企業との関係が変化することがあります。その結果、取引機会の減少や、パートナーシップの悪化につながる可能性があります。
このようなリスクを回避するには、統合後の取引先との関係を慎重に管理し、必要に応じて新たなビジネスモデルを構築することが求められます。
特定のバリューチェーンに依存することで事業の柔軟性が低下する
垂直型M&Aによって企業はサプライチェーンの内製化を進めますが、その結果として外部との取引が減少し、市場環境の変化に対応しにくくなるリスクがあります。
こうしたリスクを回避するには、特定の供給ルートや流通チャネルに依存しすぎないよう、一定の外部取引を維持し、柔軟な経営戦略を策定することが重要です。
統合によるシナジーが期待どおりに発揮されないおそれがある
M&Aを行う際、多くの企業はコスト削減や業務効率化といったシナジー効果を期待します。しかし、実際には想定した効果が得られないケースも多く、統合の失敗につながることがあります。
このようなリスクを軽減するには、M&A前に統合計画を慎重に策定し、想定される課題を明確にしたうえで、実行可能な戦略を立てることが不可欠です。
新たな業界のノウハウや専門知識が必要になり運営負担が増加する
異業種の企業を統合する場合、その業界特有の知識やノウハウを習得する必要があり、運営負担が増加するリスクがあります。
このような問題を防ぐためには、M&Aの計画段階で必要な人材の確保や研修プログラムの導入を検討し、適切な体制を整えることが重要です。
垂直型M&Aが向いている企業の特徴
垂直型M&Aは、すべての企業にとって有効な戦略とは限りません。しかし、特定の業種やビジネスモデルでは、競争力の向上やコスト削減の面で大きなメリットをもたらします。ここでは、垂直型M&Aが適している企業の特徴について詳しく解説します。
原材料や部品の安定調達が事業の成長に直結する企業
原材料や部品の調達が事業の安定性に直結する企業にとって、垂直型M&Aは有効な戦略です。供給元を自社グループ内に取り込むことで、外部環境の影響を受けにくくなり、安定した事業運営が可能になります。
外部のサプライヤーに依存している場合、市場の変動や物流の混乱によって原材料の調達が滞るリスクがあります。例えば、自動車業界では半導体不足が大きな課題となり、生産が一時的に停止する事態も発生しました。しかし、自動車メーカーが半導体メーカーを買収し、自社グループ内で部品の供給を確保すれば、このようなリスクを軽減できます。
安定した調達体制を確立することで、生産計画をより柔軟に管理できるようになります。特に、長期的な供給の確保が成長戦略の鍵となる企業にとって、垂直型M&Aは競争力を高める手段となります。
自社ブランドの品質管理やコスト管理を強化したい企業
ブランドの品質を維持し、コスト管理を強化したい企業にとって、垂直型M&Aは大きなメリットをもたらします。生産から販売までを一貫して管理できるため、品質の安定性が向上し、コスト削減も可能になります。
外部の製造業者や流通業者を利用する場合、自社の品質基準を完全に適用することが難しくなります。しかし、自社で生産設備を持ち、製造工程を管理すれば、細かな品質管理が可能になります。例えば、高級化粧品ブランドが自社工場を買収することで、成分や製造工程を厳格に管理し、ブランド価値を向上させることができます。
また、コスト管理の面でもメリットがあります。外部業者を利用すると、中間マージンや余分なコストが発生しますが、自社グループ内で一貫した生産体制を築くことで、コストを最適化できます。品質とコストの両面で競争力を向上させるために、垂直型M&Aは有効な選択肢となります。
流通や販売チャネルの確保によって競争優位性を高めたい企業
販売チャネルの確保が競争力に直結する企業にとって、垂直型M&Aは効果的な戦略です。流通や販売ネットワークを自社で保有することで、市場での影響力を強化できます。
流通業者や販売代理店に依存している場合、流通コストの増加や他社製品との競争によって、自社製品の販売が思うように伸びないことがあります。しかし、小売業者や流通業者を買収し、販売ネットワークを自社グループ内に取り込めば、自社製品を優先的に取り扱うことができ、競争優位性を確保できます。例えば、スポーツ用品メーカーが直営店舗を拡大することで、競合ブランドよりも自社製品を優先的に販売できるようになります。
また、流通や販売チャネルを内製化することで、消費者との直接的な接点を持つことができ、マーケティング戦略の強化にもつながります。市場での存在感を高めるために、流通網の確保は重要な要素となります。
垂直型M&Aの成功事例
垂直型M&Aは、企業の成長戦略の一環として多くの業界で活用されています。特に、供給網の安定化やコスト削減、ブランド力の強化を目的とした事例が多く、適切に実施されれば大きな成功を収めることができます。
例えば、トヨタ自動車は部品メーカーや販売会社と資本関係や長期取引関係を築き、製造から販売までをグループ内で機能的に連携させる「緩やかな垂直統合」を形成しています。これにより、品質管理の統一や供給の安定化を図りつつ、柔軟な協力体制を維持しています。
また、Amazonが食品スーパーマーケットのホールフーズを買収した事例では、流通と販売ネットワークを確保し、EC事業との相乗効果を高めました。
垂直型M&Aを実施する際のポイント
垂直型M&Aを成功させるには、戦略的な計画と慎重な実行が不可欠です。単に供給網を統合するだけでは、期待した効果を得られないこともあります。ここでは、垂直型M&Aを実施するうえで考慮したいポイントについて解説します。
統合によるシナジー効果を明確に定義し戦略を策定する
垂直型M&Aを成功させるには、統合によるシナジー効果を明確に定義し、具体的な戦略を策定することが重要です。統合の目的が曖昧なままでは、期待した効果を十分に得ることができません。
例えば、原材料の安定調達を目的とする場合、供給コストの削減や調達リードタイムの短縮といった具体的な目標を設定することが求められます。また、流通ネットワークの強化を目的とするなら、販売チャネルの拡大やブランドの市場浸透率の向上を目標に据えるべきです。
成功の鍵は、事前に統合後のビジョンを明確にし、達成すべき数値目標やKPIを設定することです。統合の進捗を定期的に評価し、必要に応じて戦略を調整することで、M&Aの成果を最大化できます。
買収先の業界特性や経営ノウハウを十分に分析する
垂直型M&Aを成功させるには、買収先の業界特性や経営ノウハウを十分に分析し、統合後のリスクを最小限に抑えることが不可欠です。異なる業界を統合することで、オペレーションのギャップや経営方針の不一致が生じる可能性があるためです。
例えば、製造業の企業が物流業者を買収する場合、物流業界特有のコスト構造や在庫管理の手法を理解する必要があります。また、食品メーカーが農場を買収するケースでは、農作物の生産プロセスや天候リスクなどを考慮することが求められます。
これらのリスクを回避するためには、買収前のデューデリジェンスを徹底し、買収先の経営ノウハウを吸収する体制を整えることが重要です。買収後も、専門人材の確保や教育プログラムの導入を通じて、統合の円滑化を図る必要があります。
既存の取引先やパートナーとの関係変化を考慮する
垂直型M&Aを実施する際は、既存の取引先やパートナーとの関係変化を慎重に考慮することが重要です。統合後のビジネスモデルの変化が、従来の取引先との関係に影響を与える可能性があるためです。
例えば、食品メーカーが流通業者を買収し、自社流通網を確立した場合、従来の卸売業者との取引量が減少することがあります。この変化により、取引先が競合企業と新たな提携を結び、市場での競争が激化する可能性もあります。
こうしたリスクを回避するためには、M&Aの計画段階で取引先との関係変化を想定し、必要に応じて代替戦略を準備することが求められます。例えば、既存の取引先に新たな役割を与え、関係を維持する方法を検討することが効果的です。
まとめ|垂直型M&Aを適切に活用し、持続的な成長の実現を
垂直型M&Aは、サプライチェーン上の重要な機能を統合することで、コスト削減や供給の安定化を図り、競争力を強化する有効な手段です。一方で、経営の複雑化や取引先との関係変化といったリスクも伴うため、慎重な計画と戦略の策定が求められます。
特に、大規模な垂直統合を行う場合には、独占禁止法(反トラスト法)などの法的規制にも注意が必要です。統合によって市場での競争を実質的に制限する恐れがあると判断された場合、規制当局から審査や差し止めを受ける可能性があります。
こうしたリスクを避けるためには、事前に法的なチェックを行い、必要に応じて専門家の助言を得ることが重要です。大切なのは、統合によるシナジー効果を明確に定義し、買収先の業界特性を十分に分析したうえで、適切な実行プロセスを設計することです。また、既存の取引先との関係変化を考慮し、長期的な視点で経営戦略を策定することも欠かせません。
垂直型M&Aを適切に活用すれば、企業は市場での競争力を高め、持続的な成長を実現できます。事前の準備と法的な配慮を徹底し、成功につながる戦略を構築しましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















