CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
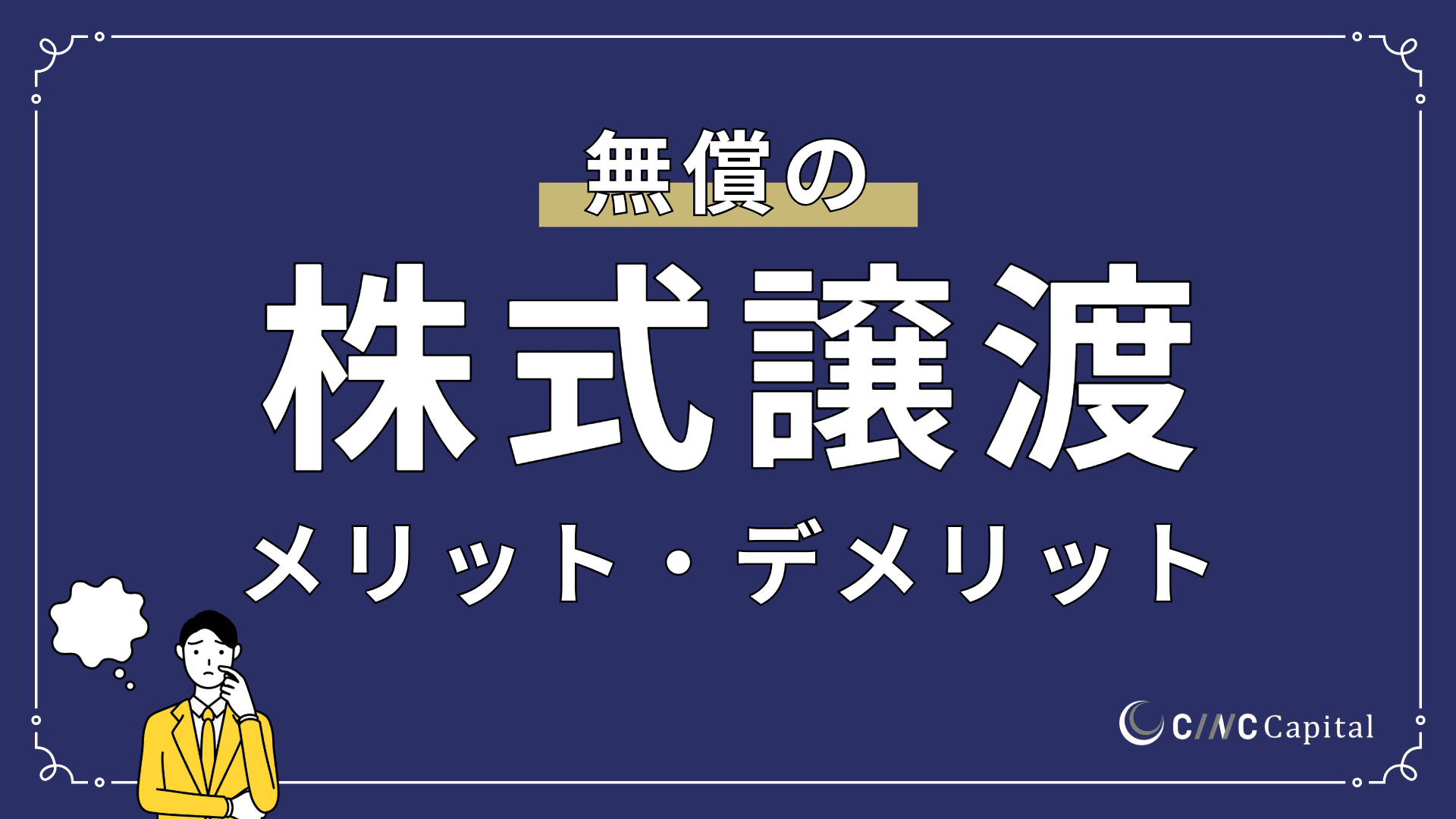
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.06.26
無償の株式譲渡とは?メリットやデメリット、方法、発生する税金について解説
会社の株式を譲渡する際、通常は売却額が発生しますが、特定のケースでは無償で譲渡されることもあります。無償の株式譲渡は、親族間での事業承継や経営権の移転、資本関係の整理などで使われる譲渡方法です。しかし、税金の問題や法的なリスクが伴うことがあり、適切な手続きを踏まなければ思わぬ負担が生じる可能性があります。
本記事では、無償で株式を譲渡するメリットやデメリット、具体的な手続き方法、そして発生する税金について解説します。株式を譲渡する側・受け取る側の双方にとって重要なポイントを押さえ、適切に対応できるようにしましょう。
目次
無償の株式譲渡とは
株式譲渡は有償と無償の2種類に大きく分けられ、取引の目的や関係性によって選択されます。
有償譲渡では、買い手側が譲渡対価を支払うことで株式を取得します。対価は現金で受け取り可能なため、売却資金を確保しやすい点が特徴です。一般的なM&Aや事業売却の手段として広く利用されます。
一方、無償の株式譲渡は、対価の支払いを伴わない譲渡方法であり、主に親族間での事業承継や資本関係の整理などの場面で活用されます。特に中小企業では、後継者へのスムーズな経営権の移転を目的として、無償譲渡が選ばれるケースが多く見られます。
ただし、税務上の取り扱いが異なり、贈与税や法人税などが発生する可能性があるため、事前に適切な対応を検討することが重要です。
例えば個人間の無償譲渡では、時価相当額の贈与とみなされ、株式の評価額に基づいて贈与税が課税されます。一方、法人が関与する場合は、受贈益の計上や寄附金としての処理など、法人税法上の課税関係が生じます。
無償で株式譲渡するメリット
無償で株式を譲渡することには、譲渡側と譲受側の双方にとっていくつかのメリットがあります。ここでは、無償の株式譲渡がもたらす主なメリットについて解説します。
後継者へのスムーズな事業承継が可能になる
無償の株式譲渡は、事業承継を円滑に進める手段の一つです。親族内での事業承継では、後継者が資金を用意する必要がなく、財務的な負担をかけずに経営権を移転できます。さらに、外部への売却と異なり、会社の理念や経営方針を維持したまま継続できるため、取引先や従業員の安心感にもつながります。
譲渡時の資金負担を抑えられる
有償譲渡では、買い手側が譲渡価格を支払う必要がありますが、無償譲渡では譲渡時の直接的な資金負担を抑えられます。譲渡側は株価評価や税務申告などの手続きを行うことで、株式を引き継げます。
ただし、無償譲渡においても贈与税などの税負担が発生する可能性があるため、後継者が税金相当額の資金を用意するケースも存在する点に留意しておきましょう。
取引先や従業員の信用を維持しやすくなる
M&Aによる事業売却では、経営権の移転によって取引先や従業員の不安を招くことがあります。しかし、無償譲渡による親族や信頼できる関係者への引き継ぎであれば、経営の継続性が保たれるため、取引先との契約や従業員の雇用も安定しやすくなります。
相続や贈与の選択肢を広げられる
無償で株式を譲渡することで、相続や贈与と組み合わせた資産承継の選択肢が広がります。例えば、親族への株式譲渡を進める際、贈与税の非課税枠を活用することで税負担を軽減できる可能性があります。また、相続税対策の一環として、早い段階で無償譲渡を行うことで、後継者に株式を移転しながら計画的な資産管理を進めることが可能です。
無償で株式譲渡するデメリット
無償で株式を譲渡することには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、無償譲渡における主なデメリットについて解説します。
税務上の問題が発生する可能性がある
無償で株式を譲渡する場合、税務上の問題が発生する可能性があります。譲渡する株式に市場価値がある場合、税務当局からは譲渡側が株式を贈与したものとみなされ、贈与税や法人税の課税対象となることがあります。特に法人が法人に対して株式を譲渡する際には、時価との差額が寄付金とみなされるケースもあり、思わぬ税負担が生じる可能性があるため、事前の税務対策が必要です。
公平性の観点からトラブルが生じるおそれがある
無償譲渡は、株主間や関係者間の公平性の問題を引き起こす可能性があります。例えば複数の相続人がいる場合、一部の相続人にのみ無償譲渡を行うと、ほかの相続人から不公平感を持たれ、トラブルに発展する可能性があります。また、社内で複数の後継者候補がいる場合にも、特定の人物にだけ無償譲渡すると、従業員や関係者との関係が悪化するリスクがあるため注意が必要です。
経営権の移転に伴うリスクが高まる
事業の経営権が移転すると、譲受側の経営能力や事業運営の適性が不十分な場合、会社の業績が悪化するリスクがあります。特に無償譲渡の場合は、経営権の移転価値を認識せずに譲り受けた場合、事業に対する責任感や価値認識が希薄になると懸念されます。
また、譲受側が株式を取得した後、会社の経営方針を大きく変更することで、従業員や取引先との関係に悪影響を及ぼす可能性もあります。経営権移転前に経営参画期間を設定したり、段階的な株式譲渡を行ったりする対策を検討しましょう。
法人株主の財務へ影響を与える可能性がある
株式を無償で譲渡することで、株式を譲渡する法人の財務状況に悪影響を及ぼす可能性もあります。法人が所有する株式を無償譲渡する場合、譲渡した株式の価値が法人の資産から減少するため、貸借対照表上の純資産が減少することになります。これは、金融機関からの信用低下につながる可能性があり、今後の資金調達に影響を及ぼす要因となることもあるため注意が必要です。
無償譲渡が適切でないケースがある
無償譲渡は、すべてのケースにおいて適切とは限りません。特に、事業の成長を見込める企業の場合、株式の市場価値が高まる可能性があるため、無償で譲渡することが将来的に経済的な損失を生むこともあります。
また、事業の承継を目的とした無償譲渡であっても、譲受側に経営能力が備わっていない場合、事業の存続自体が危うくなる可能性も考えられます。そのため、無償譲渡が本当に最適な選択肢であるのか慎重に判断することが重要です。
無償で株式譲渡をする方法・流れ
無償で株式を譲渡する場合、金銭の授受は不要ですが、税務上や法的な観点から適切な手続きを踏むことが重要です。場合によっては、有償譲渡よりも複雑な対応が必要になることもあります。ここでは、無償譲渡の具体的な流れについて説明します。
譲渡承認請求
株式を譲渡する際は、まず譲渡先に譲渡承認請求を行います。譲渡制限のある株式の場合、会社の承認を得る必要があるため、取締役会設置会社では取締役会へ、非設置会社では株主総会へ承認を求めることになります。譲渡の条件や相手についても、慎重に検討しましょう。
株主総会・取締役会での承認
譲渡承認請求がなされた後、取締役会や株主総会での承認手続きに進みます。承認の可否を決定し、議事録に記録を残すことで、後のトラブルを未然に防ぐことが可能です。なお、会社が譲渡を拒否する場合には、代替買い取り人の指定が求められることもあります。
決議内容の通知
株主総会または取締役会で承認が得られた場合、その決議内容を通知します。この通知は、承認請求から2週間以内に行う必要があります。万が一通知が行われなかった場合でも、一定の期間が経過すると承認されたものとみなされることがあるため、速やかに手続きを進めましょう。
株式譲渡契約(無償)を締結する
承認が完了したら、株式譲渡契約(無償)を締結します。「株式贈与契約書」や「株式譲渡契約書(無償)」には、譲渡する株式の種類や数量、譲渡人・譲受人の情報を明記し、無償である旨も記載しておく必要があります。また、譲渡後のトラブルを防ぐために、株主名簿の変更や株式の二重譲渡に関する条項を設けることも重要です。
株主名簿の書き換え
株式譲渡が完了した後は、株主名簿の書き換えを行います。株主名簿には株主の氏名、住所、持ち株数などが記録されており、これを変更することで譲受人が正式な株主として認められます。中小企業では株主名簿が未整備な場合もありますが、適切に管理することで株主としての権利を明確にすることが可能です。
株式の無償譲渡にかかる税金
無償で株式を譲渡する際、税金の負担は譲渡側と譲受側の関係によって異なります。無償での株式譲渡には、さまざまな税務上の影響があるため、事前に税理士などの専門家に相談して適切な手続きを進めることが重要です。ここでは、それぞれのケースでかかる税金について解説します。
個人から個人へ譲渡する場合
個人間で株式を無償譲渡する場合、譲渡側には所得税などの税金は発生しません。しかし、譲受側には贈与税が課される可能性があります。年間110万円の基礎控除額を超える贈与を受けた場合、超過分に対して贈与税がかかるため、事前に計算を行いましょう。なお、贈与税の計算は複雑なため、税理士など専門家に相談するのがおすすめです。
個人から法人へ譲渡する場合
個人が法人に無償で株式を譲渡した場合、譲受側の法人には法人税が課されます。これは、受け取った株式の時価相当額が「受贈益」として計上され、法人の課税所得に含まれるためです。原則として譲渡側の個人には課税関係は生じませんが、「寄附」と認定されるケースでは、「みなし譲渡所得課税」が生じる可能性があるため注意が必要です。
法人から個人へ譲渡する場合
法人から個人へ株式を無償で譲渡すると、譲受側の個人には所得税が発生します。譲受側が法人の従業員であれば「給与所得」、それ以外であれば「一時所得」として扱われるのが一般的です。一方、譲渡側の法人には、従業員への譲渡が賞与として扱われる場合にその時価相当額は損金として処理できる一方で、法人税・社会保険料等の負担が生じます。
法人から法人へ譲渡する場合
法人間で株式の無償譲渡を行う場合、譲受側の法人は時価相当額の株式受贈を計上し、その分法人税が課税されます。一方、譲渡側の法人は、その譲渡が「寄附金」として扱われ、損金算入限度額を超える部分については損金に算入できないため課税所得が増加します。また、場合によっては株式の簿価と時価の差額に対して譲渡損益が発生することもあります。
無償で株式譲渡を行う際の注意点
無償で株式を譲渡する際には、契約内容や税制上の扱いなど、さまざまなポイントに注意が必要です。ここでは、無償譲渡を行う際に確認しておくべき重要なポイントを解説します。
契約書の内容を必ず確認する
無償での株式譲渡には公的な手続きの義務はありませんが、当事者間で契約を結ぶことが一般的です。契約書がない場合、後から条件の食い違いが発生するリスクがあります。
また、譲渡契約の有効性や正当性を確保するためにも、契約書の内容は慎重に確認しましょう。特に、譲渡の目的や条件、税務上の取り扱いなどを明記することが重要です。適切な契約内容を確保するために、専門家に相談するのも一つの方法です。
必要に応じて株券を発行する
株券発行会社の場合、株式譲渡の対抗要件として株券の交付が必要です。既発行の株券がある場合はそれを譲受人に引き渡し、株券が発行されていない場合は新たに発行を請求することができます。定款の内容を事前に確認し、株主名簿の書換手続きも忘れないようにしましょう。手続きに不安がある場合は、法務の専門家に相談することをお勧めします。
まとめ|無償の株式譲渡を成功させるには専門家への相談がおすすめ
無償での株式譲渡は、金銭の授受がありません。しかし、税務上の取り扱いや契約内容の確認、必要に応じた株券の発行など、慎重に対応すべきポイントが多くあります。特に、税金の発生や手続きの不備によるトラブルを避けるためには、事前に十分な準備を行うことが重要です。
複雑な手続きを円滑に進め、リスクを最小限に抑えるためには、税理士や弁護士などの専門家にご相談ください。専門家のアドバイスを受けながら進めることで、スムーズかつ適正に株式譲渡を完了させられます。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















