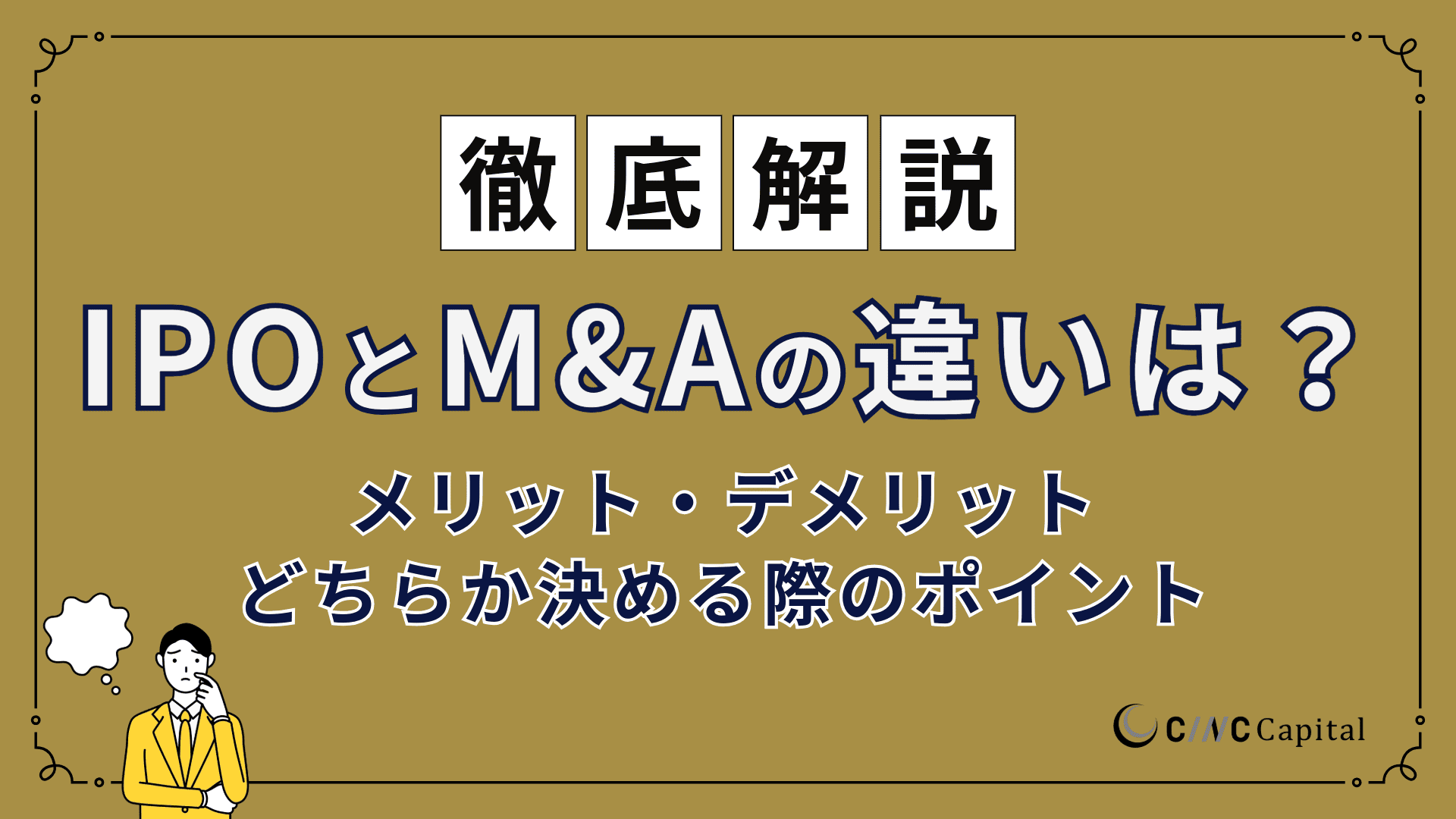CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
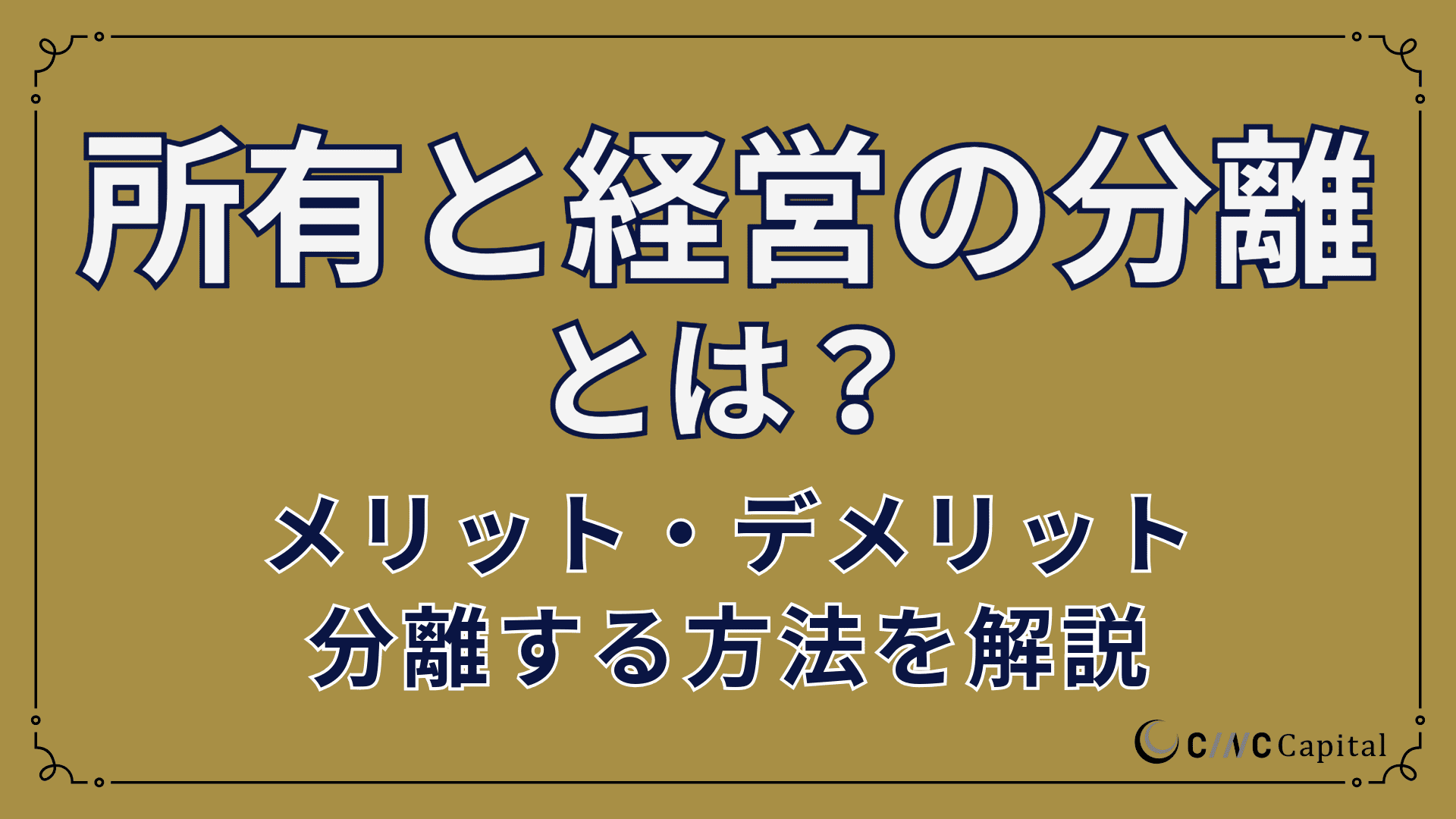
M&A / スキーム
- 公開日2025.09.29
所有と経営の分離とは?メリットやデメリット、分離する方法をわかりやすく解説
会社の成長を考えるなかで、「オーナー経営を続けるべきか、それとも経営を他人に任せるべきか」と悩む経営者は少なくありません。
特に事業承継や上場を検討する段階では、このテーマは避けて通れない問題です。
本記事では、「所有と経営の分離」とは何か、そのメリット・デメリット、そして具体的な実現方法について、わかりやすく解説します。
目次
所有と経営の分離とは?
所有と経営の分離とは、会社の出資者である株主と、実際に会社を運営する経営者の役割を明確に分ける仕組みのことです。
これは株式会社における基本構造のひとつであり、特に上場企業においては一般的な体制です。
中小企業ではオーナーが経営も担うケースが多いものの、所有と経営を分離することで、経営の専門性や客観性を確保しやすくなります。
まずは、所有と経営の分離に関わる理論や法律上の仕組みについて説明します。
バーリミーンズ理論とは
所有と経営の分離における代表的な理論として、バーリ=ミーンズ理論が広く知られています。
これは、1932年にアメリカの経済学者ガーディナー・ミーンズと法律家アドルフ・バーリによって提唱されました。
この理論では、企業の株式が多数の株主に分散した結果、株主が経営に直接関与しなくなり、実際には経営者が企業の実権を握る構造が生まれると指摘されています。
その結果、経営者が自己の利益を優先して行動するリスクが高まり、所有者である株主の利益と乖離する「エージェンシー問題」が発生する可能性があるとされました。
この問題意識は、今日のコーポレートガバナンス論の基礎となっており、経営の監視機能や外部取締役制度の導入など、多くの制度設計に影響を与えています。
会社法での分離の扱い
日本の会社法では、所有と経営の分離が基本原則として制度設計されています。
株主は会社の所有者として議決権を持ち、取締役を選任する権限を有しますが、日常的な経営判断は取締役会が担うことで、出資と経営の役割が明確に分けられています。
特に公開会社においては、社外取締役の設置や監査役会、会計監査人の設置が義務付けられており、経営の監視体制が制度的に強化されています。
これにより、経営者による独断的な判断を防ぎ、株主を含む利害関係者の利益を守る枠組みが整えられているのです。
一方、非公開会社では柔軟性が高く、取締役の任期を最大10年まで延長できるほか、取締役1名での経営も可能とされています。
そのため、オーナー経営を維持したい中小企業などでは、所有と経営の一致を保ちやすい仕組みになっています。
企業の規模や目的に応じて、分離の程度を調整できる点が会社法の大きな特徴です。
所有と経営の分離のメリット
所有と経営を分離することで、会社の運営に多くのプラス効果が生まれます。
ここでは、主に「人材の確保」「資金調達」「ガバナンスの強化」「株主利益の向上」という4つの観点から解説します。
優秀な人材を確保できる
所有と経営を分離することで、経営に特化した外部人材を柔軟に登用しやすくなります。
これは、出資者が経営に直接関与しない体制が整うため、経営判断を専門家に委ねることができるからです。
例えば、資金調達や事業構想には優れているものの、現場の経営経験が不足しているオーナーがいた場合でも、実務に精通したプロ経営者を招くことで企業の運営レベルを大きく引き上げることができます。
さらに、役割が明確に分かれていることで意思決定も効率化され、出資者と経営者それぞれの得意分野を最大限に発揮できる環境が整います。
このような体制は、企業の競争力を強化し、持続的な成長を後押しする土台となるでしょう。
資金調達しやすい
所有と経営を分離することにより、外部からの資金調達がしやすくなります。
株式が分散し、特定のオーナー経営者に依存しないことから、経営のガバナンスや透明性が担保されやすくなり、投資家との信頼関係を構築しやすくなるからです。
特に、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家などの出資者は、ガバナンス体制が整っており、経営の意思決定が個人に依存しない企業を好みます。
経営の透明性や監査体制が整っていることは、企業の信用力や成長性の指標にもなります。
そのため、資金調達の機会が増えるだけでなく、株主の多様化によって企業の意思決定にも幅が生まれ、経営の質が高まる可能性もあります。
結果として、個人の資金力に頼らず、企業全体での持続的な成長を目指す経営が可能です。
コーポレートガバナンスの向上が期待できる
経営者と株主の役割が明確に分かれることで、経営に対する監視と評価の体制が制度的に強化されます。
これは、経営者による独断的な意思決定を抑制し、企業活動が株主の利益と整合するよう促す効果があります。
特に、社外取締役や監査役、監査委員会などの導入が進んでいる企業では、経営の透明性が高まり、不正行為や利益相反といったリスクを未然に防ぐことが可能になります。
さらに、経営者が株主や取締役会に対して説明責任を果たす環境が整うことで、業績や施策に対する評価が適切に行われるようになります。
こうしたガバナンス体制の整備は、取引先や投資家、従業員からの信頼を高め、企業全体のブランド価値や社会的信用力の向上にもつながるでしょう。
株主への利益還元がしやすくなる
所有と経営が分離されている企業では、経営者が株主の利益を最優先に考えた判断を下しやすくなります。
これは、経営者自身が出資者でない場合でも、株主からの評価や期待に応える責任を強く意識する立場にあるためです。
例えば、株価の安定や上昇を重視する姿勢から、利益の一定割合を配当として還元したり、自社株買いを行うことで株主へのリターンを高める動きが見られます。
また、経営の透明性や説明責任を果たす体制が整うことで、株主は企業経営に対する信頼を深め、長期的な資本参加を行いやすくなります。
所有と経営の分離のデメリット
所有と経営を分けることには多くの利点がありますが、一方でいくつかのリスクや課題も伴います。
ここでは、主に「意思決定の遅延」「経営者の意欲低下」「株式譲渡によるリスク」の3点について解説します。
意思決定の際に時間がかかりやすい
所有と経営が分かれていると、重要な判断に時間がかかる傾向があります。
なぜなら、経営者が意思決定を行う前に、株主や取締役会の承認を得る必要があるからです。
新規事業の開始や大規模投資などでは、迅速な判断が求められる場面が多くありますが、所有と経営が一致している企業に比べて調整に時間を要するケースが多くなります。
このような状況は、変化の激しい市場環境では不利に働く可能性があります。
モチベーションが低下するリスクがある
経営者が自社株を持たず、単なる雇われの立場になると、経営への意欲が下がる可能性があります。
理由は、会社の成長による利益が経営者自身に還元されにくくなるためです。
例えば、オーナー経営者であれば株価上昇や配当増加の恩恵を直接受けられますが、所有と経営が分離された環境ではそれらの恩恵が限定的になります。
会社のために全力を尽くす動機が弱まり、業績や組織全体にも悪影響を及ぼすリスクが生じるでしょう。
株式譲渡のリスクが高まる
所有と経営の分離が進み、株式の流動性が高まると、意図しない相手への株式譲渡リスクが高まります。
株式が自由に売買できる状態では、敵対的買収者が株式を買い集めて経営権を奪う恐れがあるからです。
例えば、上場企業では株式の売却によって外部のファンドが経営に介入する事例もあります。
このような事態を防ぐには、防衛策や株主構成の管理が必要になり、結果としてガバナンスの複雑化やコスト増加を招く恐れがあります。
所有と経営を分離する方法
所有と経営を分けるには、制度や組織の仕組みを整える必要があります。
M&Aを活用して第三者に株式譲渡や第三者割当増資を行うことで、新たな株主を迎え入れ、経営体制を刷新する方法も広く活用されています。
中でもよく使われる方法が、「株式公開(IPO)」と「持株会社の設立」です。
本章では、それぞれの方法の特徴や活用のポイントをわかりやすく説明します。
株式公開(IPO)を行う
株式公開は、所有と経営の分離を実現する最も典型的な手段です。
なぜなら、IPOによって不特定多数の投資家が株主となり、経営が市場の評価にさらされる構造が生まれるからです。
例えば、創業者が保有株を売却することで、経営権を手放しつつ資金を調達できるため、経営はプロフェッショナルな役員陣に任せることが可能になります。
こうした体制は、ガバナンス強化や人材登用の自由度向上にもつながります。
持株会社(ホールディングス)を設立する
持株会社を設立する方法も、所有と経営を分離する有効な手段の一つです。
この方法では、親会社としての持株会社が株式を保有し、子会社が事業運営を担う体制を構築します。
例えば、持株会社が経営方針を決定し、実際の執行は事業会社の経営者が行うことで、戦略と現場の役割が分かれます。
これにより、経営の透明性を確保しながら、各事業の自律性を維持することが可能です。
まとめ
所有と経営の分離は、企業の成長や持続的な発展を実現するうえで有効な仕組みです。
優秀な経営人材の登用や資金調達の柔軟性、ガバナンスの強化といった多くのメリットが得られます。
一方で、意思決定の遅延や経営者のモチベーション低下といった課題も存在するため、企業の規模や目的に応じて慎重に導入を検討することが重要です。
企業価値の最大化を図るために、目的に適した手法を選びましょう。