CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
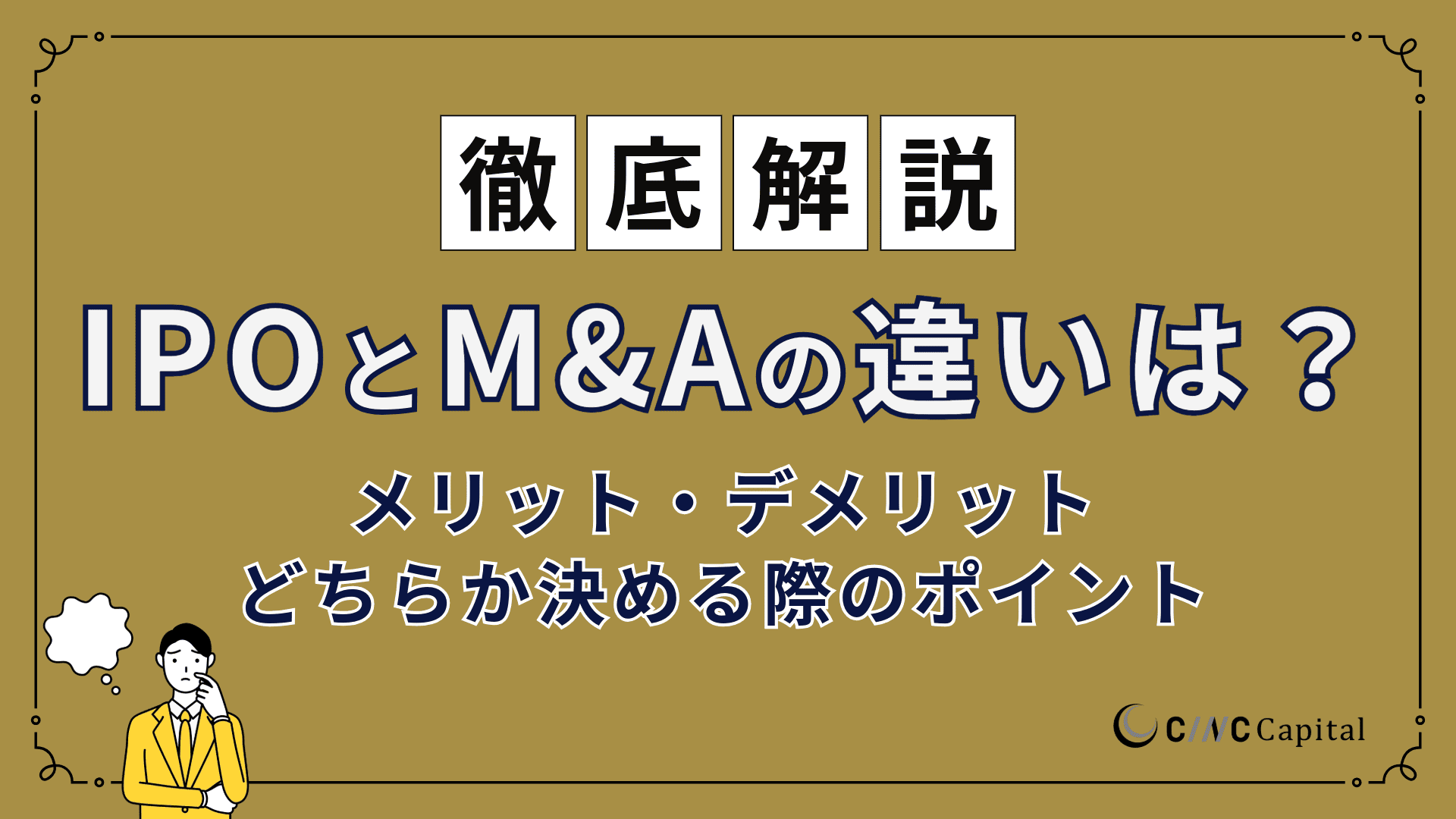
イグジット
- 最終更新日2025.06.26
IPOとM&Aの違いは?割合やメリットデメリット、イグジット戦略を決める際のポイントを解説
IPOとM&A、どちらを選ぶべきか悩んでいませんか?企業の成長や出口戦略を考える中で、この2つの選択肢に迷う経営者は少なくありません。
本記事では、IPOとM&Aの違いから、それぞれのメリット・デメリット、適しているケース、そして選択のための判断基準まで、網羅的に解説します。
目次
IPOとM&Aの違いとは?
企業が成長や事業の転機を迎えたとき、最終的な出口戦略として「IPO」または「M&A」を選択するケースが増えています。どちらも資金調達や企業価値の向上に寄与しますが、目的や手続き、企業にもたらす変化には大きな違いがあります。
本章では、それぞれの定義や目的、特徴を整理しながら、どのような違いがあるのかを解説します。
IPOとは
IPOとは、新規株式公開のことを指し、未上場企業が証券取引所に自社株式を上場させることで、広く一般投資家から資金を調達する仕組みです。この手段を選ぶ企業の多くは、事業の拡大に向けて多額の資金を必要としています。
実際に上場を実現するには通常2〜3年程度の準備期間が必要とされ、内部統制の整備、監査法人による監査、主幹事証券会社の選定、上場申請書類の作成、取引所の審査といった複数のステップを踏む必要があります。
これらを経て上場を達成すれば、企業の信用度や知名度が向上し、資金調達力も強化されるため、長期的な成長を目指す企業にとって有力な選択肢となります。
M&Aとは
M&Aとは、企業の合併や買収を通じて他社の経営資源やノウハウ、シェアを取り込む手法です。この戦略は、事業承継やスピーディーな成長を図るうえで非常に効果的です。
M&Aには、株式譲渡や事業譲渡、合併など複数の形態があり、目的に応じて適切な手法が選ばれます。また、売却側にとっては経営権の移譲と引き換えに、まとまった資金を得ることができるため、創業者や投資家の出口戦略としても活用されています。
M&AはIPOに比べて準備期間が短く、柔軟に進められるという利点があり、近年では中小企業を中心に活用が進んでいるのです。
国内のIPOとM&Aの割合は?
IPOとM&Aのいずれも企業の重要な出口戦略ですが、近年はその選択傾向に明確な差が表れています。日本においては、M&Aの実施件数がIPO件数を大きく上回っています。たとえば、2022年の国内IPO件数は91社であったのに対し、同年のM&A件数は4,304件となっています。
この違いの背景には、M&Aの方が手続きが柔軟で、短期間で成立しやすいことに加え、後継者不在の中小企業にとって有効な承継手段として定着している点が挙げられます。また、IPOは景気や株式市場の影響を受けやすく、審査や準備に時間とコストがかかるため、選択肢としては限定的になりやすいです。
結果として、イグジット手段としては、M&Aの方がより多くの企業にとって現実的で実行しやすい選択肢となっています。
IPOとM&Aのメリットとデメリット
IPOとM&Aはいずれも、企業が資金調達や出口戦略を実行するための有力な選択肢です。しかし、どちらにも一長一短があるため、選択には十分な比較検討が必要となります。
本章では、IPOとM&Aそれぞれのメリットとデメリットを詳しく解説していきます。
IPOとM&Aのメリット
IPOとM&Aには、それぞれ異なるメリットがあります。IPOの最大の利点は、株式市場から大規模な資金を得られる点にあります。これにより、企業は事業拡大に必要な資金を一気に確保し、上場企業としての信頼性も獲得できます。
一方で、M&Aは迅速な実行が可能であり、経営資源の補完やシナジー創出によって事業成長を早期に実現できます。以下の表に、それぞれのメリットをまとめたので参考にしてください。
|
観点 |
IPOのメリット |
M&Aのメリット |
|
資金調達 |
株式市場から多額の資金を調達できる |
売却により創業者利益を得ることが可能 |
|
成長戦略 |
調達資金により研究開発や設備投資を加速できる |
他社の経営資源を取り込むことで短期間で成長を実現 |
|
信用力 |
上場により企業の知名度や社会的信用が高まる |
経営基盤の安定、ブランド力の強化、シナジー効果の獲得が期待できる |
|
その他 |
株式の流動性が高まり、人材採用や株式報酬の活用が可能 |
事業承継や経営者の引退において、後継者不在の問題を解決できる |
IPOとM&Aのデメリット
IPOとM&Aには、それぞれ特有のデメリットも存在します。
IPOでは、上場までに長期間の準備と多額のコストがかかり、上場後は情報開示義務や株主対応といった新たな負担が発生しますさらに、経営の自由度が下がることで、意思決定のスピードが鈍る可能性もあります。
一方、M&Aでは経営権を手放すことになるため、創業者の理念が継承されにくくなる場合があります。以下の表に、それぞれのデメリットをまとめたので参考にしてください。
|
観点 |
IPOのデメリット |
M&Aのデメリット |
|
費用と準備 |
上場準備に数年を要し、多額の費用が発生する |
デューデリジェンスや交渉などにコストがかかる |
|
経営の自由度 |
株主が増えることで経営に対する制約が増す |
経営権を譲渡するケースが多く、創業者が意思決定に関われなくなることがある |
|
義務と負担 |
四半期ごとの開示義務やコンプライアンス対応が求められる |
買収後の組織統合に失敗すると、業績や士気の低下につながる可能性がある |
|
その他 |
市場環境に左右されやすく、株価低迷のリスクが常に伴う |
ブランド変更や雇用条件の変化による社内外への影響リスクがある |
IPOとM&Aはどちらが良い?
IPOとM&Aは、いずれも企業にとって有効な成長戦略やイグジット手段となりますが、最適な選択肢は企業の状況や目的によって異なります。事業規模、資金ニーズ、経営者の意向を総合的に判断し、自社にとって最適な道を選ぶことが重要です。
本章では、「IPOが向いているケース」「M&Aが向いているケース」に分けて解説します。
IPOが向いているケース
企業が独立性を保ちながら長期的な成長を追求したい場合、IPOの選択が適しています。なぜなら、IPOによって多額の資金を市場から調達しつつ、創業者が経営権を維持できるからです。上場後は企業の知名度や社会的信用が大きく高まり、人材確保や事業提携の面でも有利に働きます。
さらに、今後の中長期計画において研究開発や新規投資が必要な場合、IPOによる資金調達は成長の原動力となります。財務基盤やガバナンス体制が整っており、厳格な上場基準をクリアできる企業にとって、IPOは最も効果的な選択肢の一つです。
M&Aが向いているケース
後継者が不在で事業承継が必要な場合や、経営者が一定のタイミングでリタイアを希望する場合には、M&Aの活用が適しています。特に中小企業においては、M&Aによって第三者に経営を引き継ぐことで、従業員や取引先との関係を維持しながら企業を存続させることが可能です。
また、成長の限界を感じている企業が、大手企業の傘下に入ることでシナジーを得て再成長を狙うケースも多く見られます。創業者や投資家が持株を一括で売却し、資金化したいと考える場面でも、M&Aは即時のEXIT手段として有効です。
このように、経営の自由度にこだわらず、スピード感や実行性を重視したい企業にとって、M&Aは最適な選択肢となります。
適切なイグジット戦略を選択するためのポイント
IPOとM&Aは、それぞれに明確なメリットとデメリットがあります。そのため、単純な数値や印象で判断せず、企業ごとの状況や目的に合わせた選択が求められます。本章では、適切なイグジット戦略を見極めるうえで検討すべき5つのポイントを紹介します。
企業の成長ビジョンと経営者の意向を明確にする
イグジット戦略を決める上で最も重要な出発点は、企業の将来像と経営者自身の意向を明確にすることです。なぜなら、IPOとM&Aでは企業のその後の姿が大きく異なるからです。
たとえば、上場後も独立した経営を続けたいならIPOが向いており、経営から身を引きたい場合はM&Aが適しています。どの道を選ぶかによって、社員の働き方や組織文化にも大きな影響が及ぶため、目指すべきビジョンを言語化しておくことが不可欠です。
資金調達の必要性とリスク許容度を考慮する
資金調達の必要性と、どれだけのリスクを取れるかという点も、戦略選定の重要な基準です。IPOは大規模な資金を調達できますが、そのぶん情報開示義務や株価変動リスクも伴います。加えて、準備から上場までには通常2〜3年かかり、長期的な視点での計画が求められます。
一方、M&Aは必要な資金を確実に得られる手段であり、条件が整えば数ヶ月で資金化が可能なケースもあります。その反面、経営権を譲る可能性が高くなる点には注意が必要です。たとえば、新規事業への多額の投資が必要で、かつ経営リスクを許容できる場合には、IPOが効果的です。逆に、一定の対価を得て確実な利益回収を望むなら、M&Aのほうが現実的です。
資金の規模、調達スピード、そして想定されるリスクに対するスタンスを照らし合わせることで、最適な道が見えてきます。
市場環境や業界動向を分析する
IPOやM&Aの成否は、外部環境に大きく左右されるため、市場や業界の動向を読み解くことが不可欠です。なぜなら、好景気や株高のタイミングであればIPOによる高い企業評価が見込める一方、不況時にはM&Aの方が成立しやすくなるからです。
たとえば、2022年は米国の金利上昇や景気後退の影響でIPO件数が減少し、M&Aの活用が加速しました。
また、自社の属する業界に買収ニーズが高まっている場合には、好条件での売却も期待できます。市場全体の流れを把握したうえで、最も成果を出せるタイミングを見極めることが大切です。
事業承継や経営体制の方向性を検討する
後継者問題や経営体制の今後を見据えることも、イグジット戦略において重要な判断材料です。なぜなら、将来的に誰が経営を担うかによって、選ぶべき道が根本的に変わるからです。例えば、社内に後継者が育っていない場合には、第三者への事業承継としてM&Aを選ぶ方が合理的です。
逆に、次世代の経営者がすでに準備されており、株式を分散させつつ事業を引き継がせたい場合は、IPOが効果的に機能します。組織の継続性と後継者の育成状況を踏まえ、最も自然な承継の形を選ぶことが長期的な企業価値の維持につながります。
専門家のアドバイスを活用し適切な判断をする
イグジット戦略の選択には、多くの専門知識と客観的な視点が求められるため、専門家の支援を受けることが有効です。なぜなら、IPOにもM&Aにも複雑な手続きやリスク評価が伴うからです。
たとえば、M&Aであれば企業価値の算定や買い手との交渉、PMIの設計まで専門性が必要となります。IPOも同様に、証券会社や監査法人、IR活動など多方面の調整が発生します。そのため、M&A仲介会社や会計士、弁護士などの専門家と連携することで、判断の精度が高まり、成功確率も大きく上がります。
最善の選択をするために、専門家の知見を積極的に活用しましょう。
まとめ|IPOとM&Aの異なる特徴を理解し最適な選択を
IPOとM&Aは、それぞれ異なる特徴と役割を持つイグジット戦略です。企業の目的や状況に応じて最適な手法は変わるため、成長ビジョンや資金ニーズ、事業承継の方針を明確にし、慎重に選択することが重要です。
適切な判断を下すためには、市場環境の分析や専門家のサポートも積極的に活用しましょう。自社にとって最も価値ある出口を見極めることが、持続的な成長と経営者の満足につながります。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















