CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
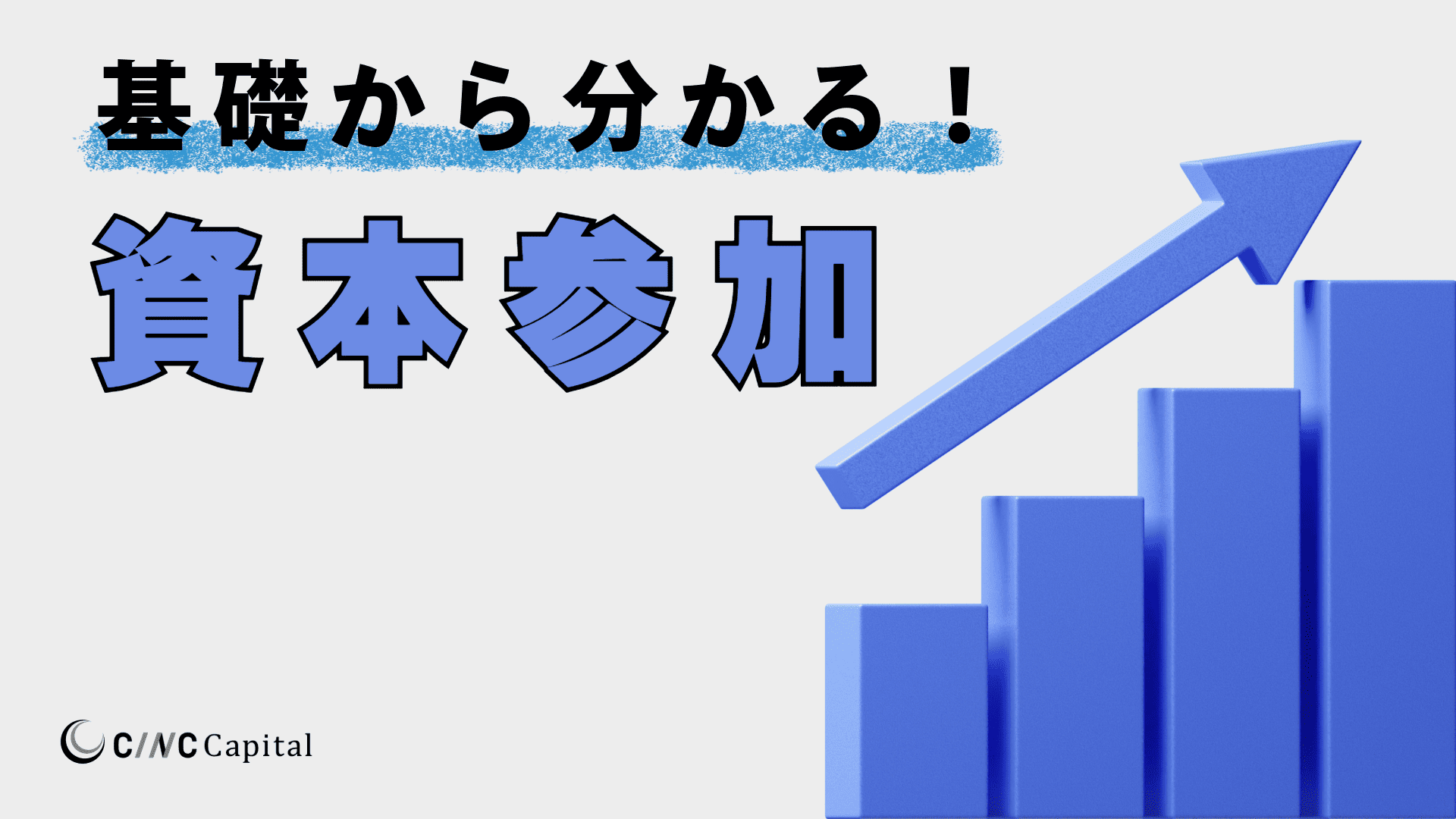
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.06.26
資本参加とは?ほかの出資・提携手法との違い、メリットと注意点
企業間の出資・提携手法の一つである「資本参加」は、M&Aや事業承継を含む幅広い場面で活用されています。
相手企業の株式を取得し株主となることで、議決権や経営権を持ちながら企業間の関係性の強化などを目的としています。
2024年現在、多様な目的でこのスキームが採用されており、株主総会での議決権行使や少数株主権を活用した意思決定の支援など、柔軟な経営が可能です。
一方で、手続きやデューデリジェンスなどの準備が必要であり、対象企業の経営状況を十分に把握しなければ、さまざまなデメリットが生じるリスクもあります。
本記事では、資本参加の基礎知識を解説したうえで、ほかのスキームとの違いやメリット、注意点についてご紹介します。
目次
資本参加とは?
資本参加とは、ほかの企業の株式を取得・保有することで、出資する企業(資本参加者)が出資を受ける企業の経営や意思決定に関与する手法を指します。
資本参加者は株主として議決権や請求権などの権利を得ることができ、相手企業との関係性を戦略的に構築できます。M&Aや事業承継といった場面で活用されることが多く、企業の成長戦略や経営課題の解決に役立ちます。
例えば、業界内での競争力強化や新規事業の開拓を目的に資本参加が行われることが一般的です。資本参加者は資本を提供することから、出資を受ける企業よりも規模が大きいパターンが多く見られます。
資本参加と資本提携との違い
資本参加と資本提携は混同されがちですが、違いがあります。資本参加は、他社の株式を取得して資本関係を構築する手法です。一方で、資本提携は2つの企業がお互いの株式を取得し合うことで企業間で協力関係を構築することを指します。なお、資本参加は資本提携の一形態として捉えることもできます。
資本参加と業務提携との違い
業務提携は、出資を伴わずに複数の企業が特定の目的で協力関係を築く手法です。例えば、「技術提携」「販売提携」「生産提携」などがあり、業務リソースの共有が中心となります。
一方、資本参加では株式取得を通じて相手企業と資本関係を構築します。これにより株主としての権利(議決権行使など)が得られ、場合によっては役員派遣などを通じて経営への関与も可能となります。
なお、実務では資本参加と業務提携を組み合わせて実施されることも多く、両者は必ずしも相反する関係ではありません。
資本参加と株式取得との違い
資本参加は株式取得という手段を用いて行われます。株式取得の目的はさまざまで、経営権の取得を目指す場合もあれば、戦略的提携を目指す場合もあります。資本参加は、株式取得を通じて他社との資本関係を構築することを指します。
資本参加と事業譲渡との違い
事業譲渡は、事業に関する資産・負債・契約関係等を包括的に移転する手法です。一方、資本参加は株式取得を通じて株主としての権利を取得する手法です。
事業譲渡では対象事業に関する権利義務が直接的に移転するのに対し、資本参加では株主としての間接的な関与となります。また、事業譲渡では個別の事業単位での取引が可能ですが、資本参加では企業単位での取引となります。
なお、どちらの手法を選択するかは、取引の目的や状況によって判断する必要があります。
資本参加のメリット
資本参加は、企業間のつながりを強化し、相互に利益を生む可能性がある手法です。出資を受ける側、出資する側の双方に異なるメリットがあります。それぞれの立場から、資本参加の利点を具体的に見ていきましょう。
出資を受ける企業側のメリット
返済義務のない資金調達が可能
資本参加を通じて、出資を受ける企業は借入と異なり返済義務のない資金調達が可能です。これにより、事業拡大や新規事業の資金として活用できます。また、出資者との関係構築により経営ノウハウを獲得したり、ビジネスネットワークを拡大したりできる点もメリットだといえるでしょう。
出資する企業側のメリット
出資先企業との関係性が深まる
資本参加によって、出資する企業は出資先企業との関係性をより深めることができます。株主として議決権行使や株主提案権などの権利を持ち、保有比率に応じて経営に関与することが可能です。また、役員派遣などを通じてより直接的な関係構築を図ることもできます。
新たなビジネスチャンスにつながる
資本参加は、新たなビジネスチャンスを創出するきっかけともなります。例えば、出資先企業の市場や顧客基盤を活用することで、自社事業の拡大が図れるでしょう。
また、相手企業のノウハウや技術を取り入れることで、製品やサービスの品質向上、新市場への参入など、さまざまなシナジー効果が期待できます。特に、異業種や海外市場への進出を目指す企業にとって、資本参加は戦略的な手段となるでしょう。
資本参加における注意点
資本参加には多くのメリットがある一方で、慎重に検討すべきリスクや注意点も存在します。これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じることが成功の鍵です。以下では、資本参加において特に留意すべきポイントを解説します。
資金調達面のリスクがある
資本参加を受ける企業は、将来の資金需要に備えて、追加の資本参加や増資を期待せずに独自の資金調達計画を立てるのが望ましいです。株主の期待に応えられない場合、将来の資金調達に影響が出る可能性があるので、経営の自由度と資金調達のバランスを考慮した株主構成が求められます。
資本参加を受ける際には、一時的な資金調達としてだけでなく、長期的な企業価値向上の観点から検討すると良いでしょう。
期待していたシナジー効果が得られない可能性がある
資本参加の主な目的の一つであるシナジー効果が、期待通りに得られないケースもあります。例えば、相手企業との事業連携がうまくいかなかったり、双方の企業文化の違いが原因で協力関係が機能しなかったりすることがあります。
これにより、目的であった事業拡大や収益向上が実現できない可能性があるため、相手企業の特性や実績、双方の相性に関する事前の調査が必要です。
自社の裁量のみで経営がしにくくなるリスクがある
資本参加を受け入れることで、株主としての権利(議決権行使や株主提案権など)を持つ新たな株主が加わることになります。そのため、株主の意向を考慮した経営判断が必要となり、従来通りの経営の自由度が変化する可能性があります。
あらかじめ株主間契約での取り決めを行ったり、議決権行使に関する合意を得たりしておくと良いでしょう。
まとめ|会社状況を理解し、資本参加を成功させよう
資本参加は、自社と相手企業が強みを活かしながら、互いに成長を目指すために有効な手法です。しかし、成功させるためには、資本参加のメリットだけでなく、リスクや注意点を十分に理解し、事前準備を入念に行うことが求められます。
特に、出資比率や契約条件の確認、相手企業との相性の見極めなどは、事前にしっかり行っておきましょう。
また、資本参加を行う際には、双方の企業が目指す目的を共有し、透明性のあるコミュニケーションを図ることがポイントとなります。デューデリジェンスを通じて事前にリスクを把握し、効果的な資本参加を実現しましょう。
不明点がある場合は、M&A仲介会社など専門知識を持つプロに相談することがおすすめです。自社の状況に応じて適切な選択を叶えられるよう、専門家のアドバイスを受けましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、資本参加のご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















