CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
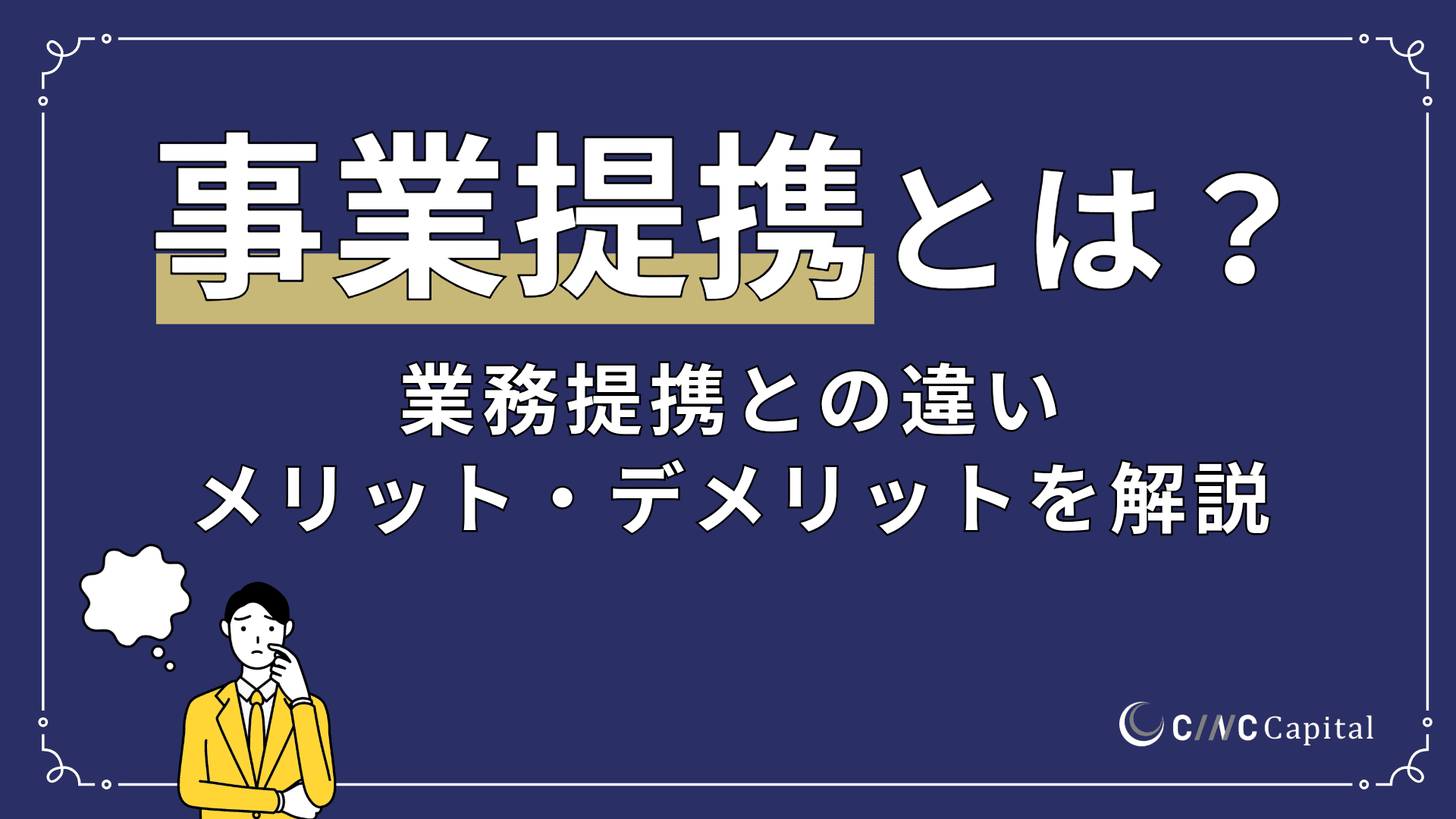
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.06.26
事業提携とは?業務提携との違いやメリット・デメリットを解説
事業提携を検討しているが、どのように進めれば成功するのか分からないと悩んでいませんか?
提携先の選定や契約内容、運用方法を誤ると、期待していた成果が得られないどころか、トラブルに発展することもあります。
本記事では、事業提携の基本概念から種類、メリット・デメリット、成功事例、契約のポイント、進め方までを詳しく解説します。
目次
事業提携とは?
事業提携とは、企業同士が互いの強みを活かし、協力関係を築くことでシナジーを生み出し、事業の成長を加速させる戦略の一つです。ここでは、事業提携の基本概念を確認した上で、業務提携・協業・M&Aとの違いについて詳しく解説します。
業務提携との違い
事業提携と業務提携は、企業間の協力関係を築くという点で共通していますが、協力の範囲と目的が異なります。事業提携は、販売や生産、技術開発など事業全体に関わる広範な協力を前提とします。一方、業務提携は、特定の業務プロセスやサービスの提供に限定されるケースが多いです。
例えば、製品の共同開発は事業提携に該当しますが、特定のシステムの運用を委託する場合は業務提携となります。事業提携は、より包括的な協力関係を構築し、中長期的な戦略を視野に入れるため、業務提携よりも企業間の結びつきが強くなります。
協業との違い
協業とは、企業が相互に協力して事業を進めることを指す広義の概念です。事業提携も協業の一種ですが、提携契約を通じて具体的な役割分担や責任を明確化する点が異なります。例えば、同じ業界の企業が共同でマーケティング活動を行う場合、それは協業と呼ばれます。
しかし、その協力関係が契約によって制度化され、明確な利益分配のルールが存在する場合は事業提携となります。事業提携は、企業間の協力をより戦略的に進めるための仕組みとして、明確なルール設定が求められます。
M&Aとの違い
事業提携とM&Aは、どちらも企業の成長戦略として活用されますが、根本的な違いがあります。M&Aは、企業の経営権を移転し、買収または合併によって一方の企業が他方の企業を支配下に置く戦略です。
一方、事業提携は、企業の独立性を維持したまま協力関係を築くため、柔軟な運用が可能です。M&Aは短期間で市場シェアを拡大できる一方で、企業文化の統合が課題となる場合があります。事業提携は、長期的な視点で競争力を向上させる手法として、経営の自由度を保ちながら市場展開を進めたい企業に適しています。
また、M&Aの手法の一つである「事業譲渡」についても理解しておくことが重要です。事業譲渡とは、会社全体ではなく特定の事業部門や資産のみを他社に譲渡する方法です。
事業提携が協力関係の構築に重点を置くのに対し、事業譲渡は事業そのものの所有権が移転する点が大きく異なります。企業が本業に集中するために非コア事業を手放したり、シナジー効果を求める企業に事業を売却したりする場合に選択されることが多いです。
事業提携から始まり、その後の展開として事業譲渡へと進展するケースもあります。
事業提携の種類
事業提携にはさまざまな形態があり、目的や業界によって適した提携方法が異なります。企業はそれぞれの経営資源を活用しながら、市場拡大や技術開発、コスト削減などの目標を達成するために事業提携を活用します。ここでは、主要な事業提携の種類として「販売提携」「生産提携」「技術提携」「共同開発提携」の4つを解説します。
販売提携
販売提携とは、自社製品やサービスの販売を他社の流通網や販売チャネルを活用して行う提携です。市場拡大や販売促進を目的に、多くの企業が採用しています。例えば、海外市場に進出する際に、現地の販売ネットワークを持つ企業と提携すれば、販路を効率的に確保できます。また、ブランド力のある企業と組むことで、販売促進の相乗効果も期待できます。ただし、販売戦略の不一致やブランドイメージの管理が課題となるため、契約時に販売条件やプロモーション方針を明確に定めることが重要です。
生産提携
生産提携とは、製品や部品の生産を他社に委託したり、共同で生産体制を構築したりする提携です。企業は設備投資を抑えつつ、生産能力を強化できるため、コスト削減や供給力の向上につながります。特に、需要変動の大きい業界では、生産提携により迅速な供給調整が可能になります。
また、製造技術や品質管理のノウハウを共有することで、生産の効率化も期待できます。ただし、品質基準の違いや供給の安定性が課題となるため、契約時に生産プロセスの管理基準や品質保証の仕組みを定めることが求められます。
技術提携
技術提携とは、企業間で技術やノウハウを共有し、新技術の開発や既存技術の高度化を目指す提携です。市場の変化が激しい業界では、技術提携により競争力の向上が期待できます。
例えば、AI技術を持つ企業と製造業の企業が提携することで、スマートファクトリーの実現が可能になります。また、特許技術を持つ企業と製品開発力のある企業が協力すれば、新しい製品の開発が加速し、市場投入のスピードが向上します。一方で、技術流出のリスクが伴うため、機密保持契約の締結や知的財産権の取り扱いを明確にすることが重要です。
共同開発提携
共同開発提携とは、複数の企業が技術や資金、人材を持ち寄り、新製品や新サービスを共同で開発する提携です。単独では実現が難しい技術革新も、異業種企業や競合企業との協力によって実現可能になります。
例えば、自動車メーカーと電池メーカーが協力し、新しい電気自動車用バッテリーを開発するケースが挙げられます。また、研究開発のリスクを分散しつつ、技術の最適化を図ることも可能です。ただし、開発成果の権利帰属やコスト分担に関する合意が必要であり、契約時に明確なルールを定めることが求められます。
事業提携のメリット
事業提携には、企業の成長や競争力の向上に寄与するさまざまなメリットがあります。ここでは、事業提携の具体的なメリットについて、「経営資源の相互活用」「新規市場・顧客層へのアクセス」「研究開発や技術力の強化」「コスト削減と業務効率化」「競争力の向上」の観点から解説します。
経営資源を相互に活用できる
事業提携により、企業は互いの経営資源を有効活用できます。提携先が持つ技術、人材、販売ネットワークを活用することで、自社の弱点を補完し、事業の成長を加速できます。
例えば、技術力のある企業と市場開拓力のある企業が提携すれば、革新的な製品を効果的に市場に投入できます。また、設備や物流インフラを共有することで、投資コストの削減や業務の最適化も可能になります。ただし、経営資源の活用範囲や責任分担を明確にしないと、提携効果が十分に発揮されないため、契約時に役割を明確にすることが重要です。
新規市場や顧客層へのアクセスが容易になる
事業提携は、新たな市場や顧客層へ迅速にアクセスする手段として有効です。特に、海外市場への進出や異業種との連携において、提携先の既存の販売網やブランド力を活用できる点が大きなメリットになります。
例えば、日本のメーカーが海外の流通企業と提携することで、現地の市場にスムーズに参入できます。また、異業種の企業と提携することで、これまでリーチできなかった顧客層にアプローチすることも可能です。ただし、市場環境の違いや販売戦略の相違が問題になる場合があるため、事前に市場調査を徹底し、提携後の戦略を慎重に策定する必要があります。
研究開発や技術力の強化につながる
事業提携により、企業は技術開発を加速させ、競争力のある製品やサービスを生み出せます。単独では実現が難しい高度な技術開発も、提携先と共同で取り組むことで、開発期間を短縮し、コストを抑えながら成果を上げることが可能になります。
例えば、自動車メーカーと電池メーカーが協力し、新しい電気自動車用バッテリーを開発するケースが挙げられます。また、特許やノウハウを相互に活用することで、技術革新を推進できます。ただし、知的財産権の帰属や技術流出のリスクがあるため、機密保持契約の締結や適切な管理体制を整えることが求められます。
コスト削減や業務効率化が可能になる
事業提携は、スケールメリットを活かしてコスト削減や業務効率化を実現できます。例えば、生産提携により製造ラインを共有すれば、設備投資の負担を軽減できます。また、物流提携を行うことで、配送コストを削減し、効率的な供給体制を構築できます。さらに、共同購買によるコスト低減や、管理業務の効率化も期待できます。
ただし、コスト削減を最優先すると品質低下やサービス低下につながる可能性があるため、提携の目的を明確にし、適切なコスト管理を行うことが重要です。
競争力を高め、市場での優位性を確保できる
事業提携により、市場での競争力を強化し、業界内での優位性を確保できます。特に、競争が激しい業界では、企業間の協力によって製品やサービスの差別化を図ることが重要になります。
例えば、異業種との提携により、従来にはない新たな価値を提供する製品を開発できれば、市場での競争力が向上します。また、業界内の主要プレイヤーとの戦略的提携により、市場シェアの拡大やブランド価値の向上が可能になります。ただし、提携に依存しすぎると独自の競争力を失うリスクがあるため、バランスの取れた戦略を構築する必要があります。
事業提携のデメリット
事業提携には多くのメリットがある一方で、いくつかのリスクも伴います。ここでは、事業提携の主なデメリットについて解説し、それぞれのリスクを回避するためのポイントを紹介します。
意思決定に時間がかかることがある
事業提携では、関係する企業が複数存在するため、意思決定に時間がかかるケースが多くなります。特に、戦略的な判断や重要な投資決定を行う際は、各社の承認を得る必要があり、スピード感をもった対応が難しくなります。
例えば、新製品の開発や市場投入に関する決定を行う場合、提携企業の間で合意形成が必要になるため、単独で事業を進めるよりもリードタイムが長くなります。こうした遅れは、市場の変化に迅速に対応できない要因となるため、迅速な判断が求められる場面では、意思決定プロセスを効率化する仕組みを導入することが重要です。
利益配分や責任の所在が不明確になりやすい
事業提携では、複数の企業が共同で利益を生み出すため、適切な配分ルールを設定しないとトラブルの原因になります。特に、投資額や業務負担に対して利益が適切に分配されていないと、不満が生じる可能性があります。
例えば、販売提携において、一方の企業が販路を提供し、もう一方が製品を開発する場合、売上が伸びても利益の取り分が不平等になれば関係が悪化します。また、責任の所在が曖昧になると、トラブル発生時に対応が遅れるリスクもあります。これを防ぐために、契約時に詳細な利益配分ルールや責任範囲を明確に定めることが求められます。
提携先との戦略や価値観の違いによる摩擦が生じる
事業提携では、企業文化や経営戦略の違いが原因で摩擦が生じることがあります。特に、異業種や海外企業との提携では、意思決定のプロセスや事業方針が異なるため、協力関係の維持が難しくなることがあります。
例えば、革新的なアプローチを重視するスタートアップと、リスク回避を優先する大企業が提携した場合、事業展開のスピードやリスク管理の方針にズレが生じ、結果として関係が破綻するケースがあります。こうした摩擦を防ぐためには、提携前にビジョンや戦略のすり合わせを行い、共通の目標を明確にすることが重要です。
機密情報の漏洩リスクが高まる
事業提携では、技術情報や経営戦略などの機密情報を共有することが多く、情報漏洩のリスクが高まります。特に、技術提携や共同開発では、提携先企業に自社のノウハウを提供するため、適切な管理が求められます。
例えば、新技術の開発を共同で行った後に、提携企業が競合と独自に契約を結び、開発成果を流用するようなケースが発生する可能性があります。これを防ぐためには、機密保持契約(NDA)の締結や、情報共有の範囲を限定する対策が必要になります。
提携解消時にトラブルが発生するおそれがある
事業提携は、企業の戦略変更や市場環境の変化により解消されることがありますが、契約の終了時にトラブルが発生するケースがあります。特に、共同で開発した技術の権利や顧客リストの取り扱いをめぐって対立することが多いです。
例えば、提携が解消された後に、一方の企業が共同開発した製品を単独で販売しようとする場合、知的財産の帰属が曖昧だと訴訟に発展する可能性があります。こうした問題を避けるためには、契約締結時に提携解消後の資産・顧客・知的財産の処理について明確なルールを定めておくことが不可欠です。
事業提携の成功事例
事業提携が成功すれば、企業の成長を加速させ、市場における競争力を強化できます。日本企業においても、戦略的な事業提携によって大きな成果を上げた事例があります。
例えば、ユニクロは、東レと提携し、高機能素材を活用した製品開発を進めてきました。この提携により、「ヒートテック」や「エアリズム」などの革新的な商品を生み出し、世界的なブランドへと成長したのです。ユニクロは東レの最先端技術を活用することで、競争力のある商品を市場に投入し、収益を拡大しました。一方で、東レもユニクロとの長期的な契約を通じて安定的な取引を確保し、新素材の開発力を強化したのです。両社が互いの強みを活かしながら、持続的な成長を実現した成功事例といえるでしょう。
【出典】ユニクロ・東レ「『戦略的パートナーシップ』の構築について」
事業提携の契約書のポイント
事業提携を成功させるためには、契約の内容を明確に定め、トラブルを未然に防ぐことが重要です。契約書には、各当事者の役割や責任、利益配分、契約解除条件などを具体的に記載する必要があります。本章では、契約書作成時に特に重要となるポイントを解説します。
各当事者の役割と責任を明確にする
事業提携では、提携する企業がそれぞれどのような役割を担うのかを契約で明確に定めることが重要です。役割分担が曖昧だと、業務の責任範囲が不明確になり、後にトラブルを引き起こす可能性があります。
例えば、販売提携において「どちらがマーケティング戦略を担当するのか」「商品の在庫管理はどちらが行うのか」が不明確な場合、業務の負担が一方に偏ることがあります。こうした問題を防ぐために、契約書には具体的な業務範囲、責任分担、対応すべきリスクなどを詳細に記載することが求められます。これにより、双方が納得できる体制を構築し、円滑な提携運営が可能になります。
利益配分や費用負担のルールを決める
事業提携では、提携によって生じる利益をどのように分配するのか、発生するコストをどのように負担するのかを明確に定める必要があります。適切なルールを設けていないと、売上や利益の配分をめぐって対立が生じ、提携関係が悪化する可能性があります。
例えば、共同開発した製品の売上をどの比率で分けるのか、販売促進のための広告費をどちらがどれだけ負担するのかといった点を契約書で規定することが重要です。適正な利益配分のルールを事前に合意しておくことで、公平な関係を維持し、提携の持続可能性を高められます。
契約の解除条件を明記する
事業提携には、環境の変化や経営方針の変更などによって、提携を解消しなければならない状況が発生することがあります。その際、契約解除の条件を明確にしておかないと、提携解消時にトラブルが生じる可能性があります。
例えば、「契約期間の満了時にどのような条件で更新するのか」「一方的な解約を認める場合、どの程度の事前通知が必要か」「契約解除後の資産や顧客リストの取り扱いをどうするか」などを契約書に記載しておくことが求められます。これにより、提携解消がスムーズに進み、企業間の関係悪化を防ぐことができます。
事業提携の進め方
事業提携を成功させるには、戦略的に計画を立て、慎重にプロセスを進める必要があります。ここでは、事業提携を進めるための具体的なステップについて解説します。
提携の目的と戦略を明確にする
事業提携を成功させるためには、まず提携の目的を明確にし、戦略を具体化することが重要です。目的が曖昧なまま提携を進めると、方針のズレや意思決定の遅れが生じ、最終的に成果が出にくくなります。
例えば、新規市場の開拓を目的とする場合、提携先に求める条件や協力範囲を事前に整理する必要があります。また、技術提携であれば、どのような技術力が必要か、研究開発の方向性をどう設定するかを明確にすることが求められます。こうした戦略の明確化により、適切なパートナー選定や契約交渉がスムーズに進み、事業提携の成功確率が高まります。
適切な提携先を選定し、条件を交渉する
事業提携の成功には、自社の目標に合致する適切な提携先を選ぶことが不可欠です。提携相手の経営状況、技術力、市場での評判などを十分に調査し、互いにメリットを享受できる関係を築くことが重要になります。
例えば、海外市場に進出するための販売提携を検討する場合、現地での販売実績やブランド力のある企業を選定することで、市場参入がスムーズになります。また、提携の目的や条件について詳細な交渉を行い、合意内容を明文化することで、後のトラブルを防ぐことが可能になります。慎重なパートナー選定と適切な条件交渉が、長期的に成功する提携関係の基盤を築きます。
契約を締結し、役割と責任を明確にする
提携が合意に至った後は、正式な契約を締結し、各企業の役割と責任を明確にすることが重要です。契約内容が曖昧な場合、業務の負担が一方に偏るリスクがあり、提携関係が円滑に進まない可能性があります。
例えば、共同開発を行う場合、どちらが開発資金を負担するのか、知的財産の権利はどのように分配するのかを明確に定める必要があります。また、利益配分や契約解除時の対応についても契約書に記載し、後のトラブルを未然に防ぐことが重要です。こうした明確なルール設定により、企業間の信頼関係を維持しながら、安定した提携運営が可能になります。
小規模な試験運用を実施し、実効性を確認する
提携が正式にスタートした後、いきなり大規模な事業展開を行うのではなく、小規模な試験運用を実施し、提携の実効性を確認することが望ましいです。試験運用を行うことで、業務プロセスの問題点や改善点を把握し、適切な対応を講じることが可能になります。
例えば、新製品を共同開発した場合、特定の地域や特定の顧客層でテスト販売を行い、市場の反応を確認することで、本格展開時のリスクを抑えられます。また、業務提携であれば、まず一部の業務をアウトソーシングし、その成果を評価することで、継続的な提携が有益かを判断できます。試験運用を通じて課題を明確化し、必要な調整を行うことで、提携の成功確率を高められます。
定期的に見直しを行い、必要に応じて調整する
事業提携を継続的に成功させるためには、定期的に提携の進捗を評価し、必要に応じて戦略を調整することが不可欠です。市場環境や競争状況は常に変化するため、提携開始時の条件が最適であるとは限りません。
例えば、販売提携の場合、当初の販売戦略が期待した成果を上げていない場合は、価格設定や販売チャネルの見直しを行う必要があります。また、提携相手の経営状況が変化した場合は、新たな条件で契約を見直すことが求められるケースもあります。定期的な見直しを行い、柔軟に戦略を修正することで、事業提携の効果を最大限に引き出し、持続的な成長を実現できます。
事業提携相手の見つけ方
事業提携を成功させるには、自社の目的に合った適切なパートナーを見つけることが重要です。提携先の選定を誤ると、協力関係がうまく機能せず、期待した成果が得られない可能性があります。そのため、信頼できる企業を見極めるための情報収集や候補の絞り込みが不可欠です。ここでは、提携先を見つけるための3つの方法について解説します。
業界ネットワークや商工会、展示会を活用する
事業提携相手を見つける方法の一つとして、業界ネットワークや商工会、展示会を活用することが挙げられます。こうした場では、同業種や関連業界の企業と直接交流でき、提携候補を見つける機会が広がります。
例えば、業界団体が主催するセミナーや交流会に参加すれば、業界内の最新動向を把握しつつ、有望な企業との関係を構築できます。また、展示会では、自社の事業と親和性の高い企業の技術やサービスを直接確認しながら、提携の可能性を探ることが可能です。提携を検討する企業との信頼関係を築くには、定期的なコミュニケーションを行い、相互の事業目標を理解することが重要になります。
既存の取引先や紹介を通じて候補を探す
事業提携の候補を探す際には、既存の取引先や業界関係者からの紹介を活用する方法も有効です。すでに取引のある企業であれば、互いの事業内容や信頼性を把握しているため、提携交渉がスムーズに進みます。
例えば、仕入れ先や販売先と協力し、新たな商品開発や販路拡大を行うケースが挙げられます。また、金融機関やコンサルティング会社、弁護士などの専門家が提携先を紹介することもあり、第三者の推薦を通じて信頼性の高い候補を見つけることが可能です。こうした紹介を活用することで、事前の信用調査の負担を軽減しながら、より適したパートナーを見つけられます。
オンラインのマッチングサービスを利用する
近年では、オンラインのビジネスマッチングサービスを活用して事業提携先を見つける企業が増えています。これらのサービスでは、企業の事業内容や提携の目的を登録し、条件に合う相手を効率的に検索できます。
例えば、BtoB向けのマッチングプラットフォームでは、特定の技術を持つ企業や、販路を拡大したい企業と簡単にコンタクトを取ることができます。また、AIを活用したレコメンド機能により、最適な提携先を自動的に提案してくれるサービスも登場しています。ただし、オンラインのみの情報では企業の実態が見えにくいため、実際に対面での面談や訪問を行い、信頼性を慎重に確認することが求められます。
事業提携で失敗しないためのポイント
事業提携は、適切に進めることで大きな成果を生む一方、戦略や管理が不十分だとトラブルに発展する可能性があります。ここでは、事業提携で失敗しないために意識すべき3つのポイントについて解説します。
提携先の経営状況や価値観を十分に調査する
事業提携では、提携先の経営状況や価値観を十分に調査し、信頼できる相手を選定することが重要です。相手企業の経営基盤が脆弱である場合、提携後に経営破綻するリスクがあり、事業計画が大きく狂う可能性があります。
例えば、財務状況を確認せずに提携を進めた結果、相手企業の資金繰りが悪化し、提携事業が頓挫するケースもあります。また、企業文化や経営方針が自社と大きく異なると、意思決定のスピードや業務遂行の進め方に齟齬が生じ、スムーズな連携が難しくなります。これを防ぐためには、提携前に相手企業の財務状況、事業計画、経営方針を徹底的に調査し、相性を見極めることが求められます。
契約内容を細かく取り決め、リスク管理を徹底する
事業提携では、契約の詳細を詰め、リスク管理を徹底することで、トラブルを未然に防ぐことができるとされています。契約が曖昧だと、利益配分や責任の所在が不明確になり、後々の対立につながるリスクが高まります。
例えば、共同開発を行う際に知的財産の帰属を明確に決めていないと、提携終了後に技術の使用権を巡るトラブルが発生することがあります。また、機密情報の取り扱いや競業避止義務についても、詳細に取り決めることで、情報流出のリスクを低減できます。こうしたリスクを回避するためには、提携の範囲や責任分担を明確にした契約書を作成し、法的なリスクを最小限に抑えることが必要になります。
まとめ|慎重な準備と戦略的な運営で、事業提携を成功へ
事業提携は、企業の成長や競争力の向上に有効な手段であり、販売拡大や技術革新、コスト削減などの多くのメリットをもたらします。一方で、意思決定の遅れや利益配分の不明確さ、戦略の違いによる摩擦といったデメリットも存在します。
成功させるためには、提携の目的を明確にし、適切なパートナーを選定し、契約を慎重に策定することが重要です。また、定期的な見直しを行い、柔軟に戦略を調整することで、長期的な関係を築くことが可能になります。事業提携は適切に管理すれば、企業の持続的な成長を促す強力な手段となるため、慎重な準備と戦略的な運営が求められます。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















