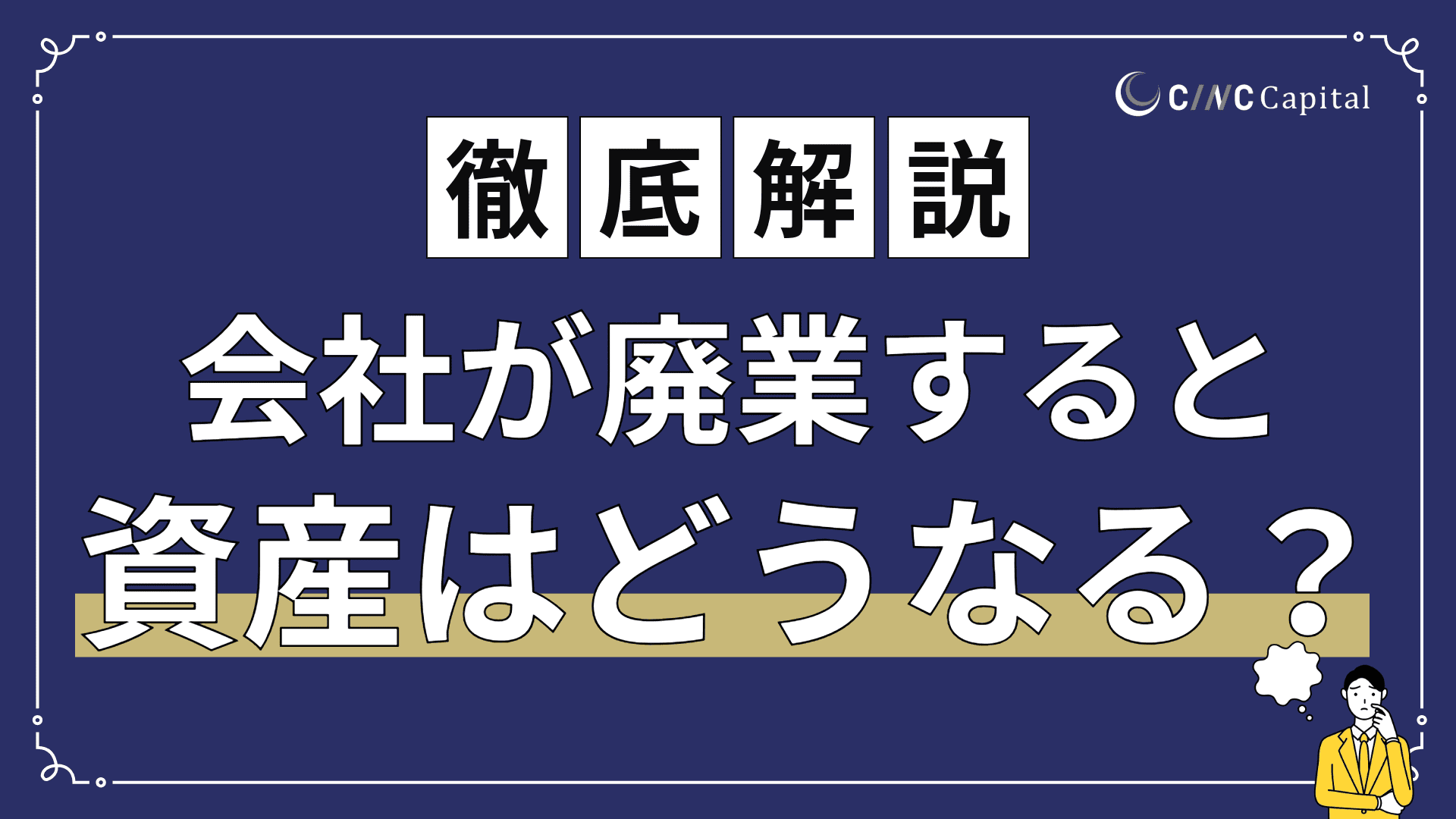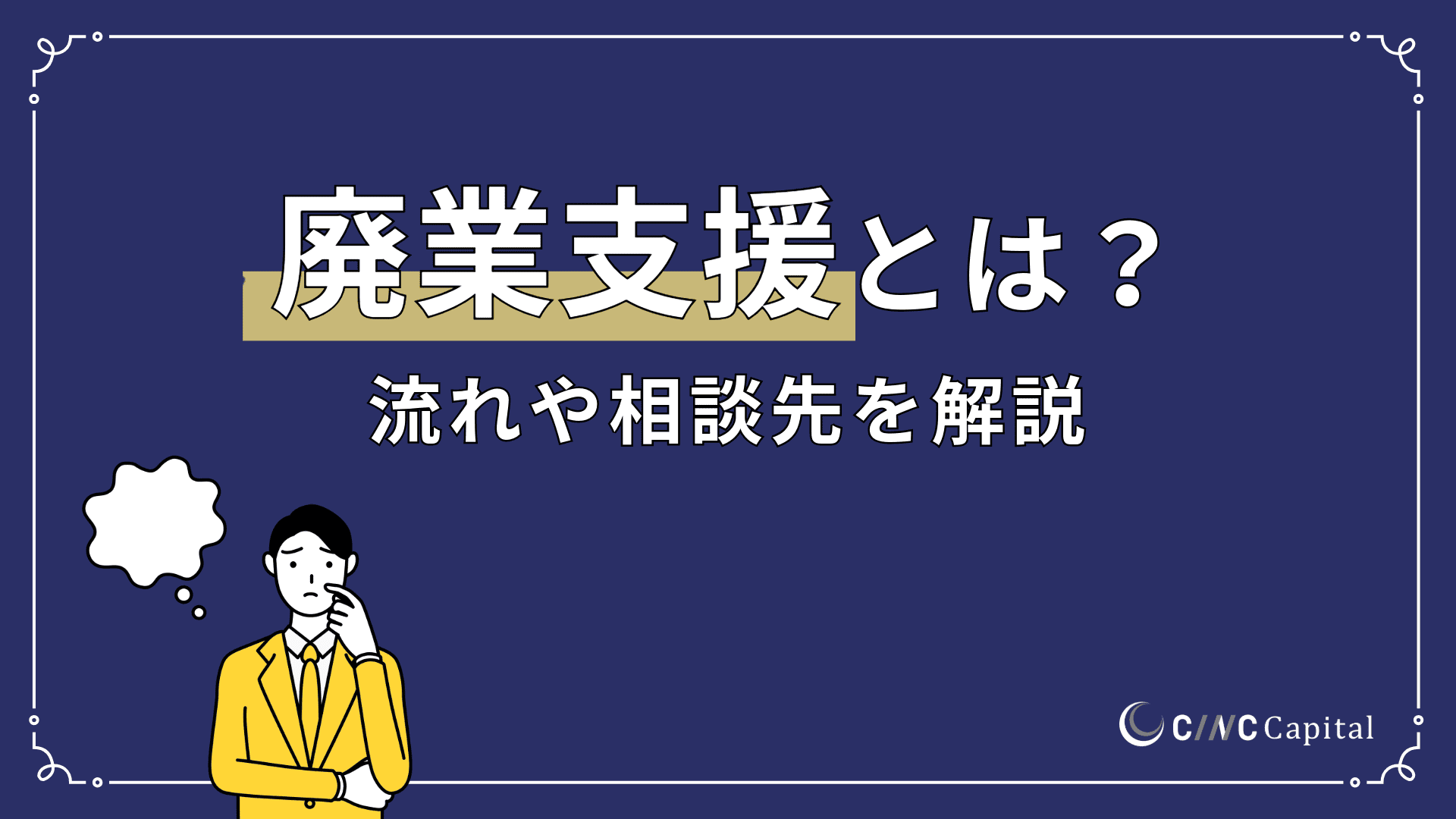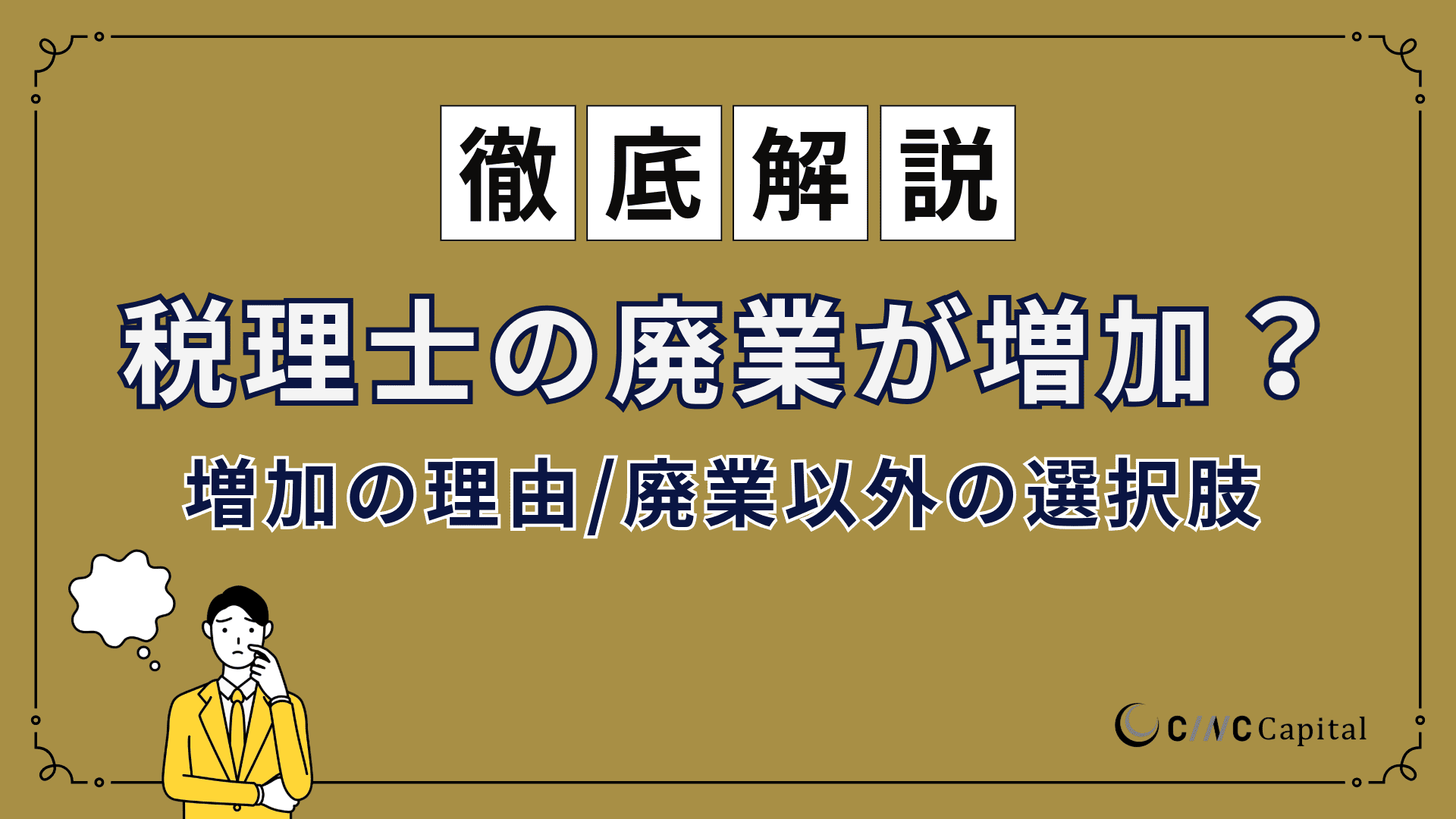CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
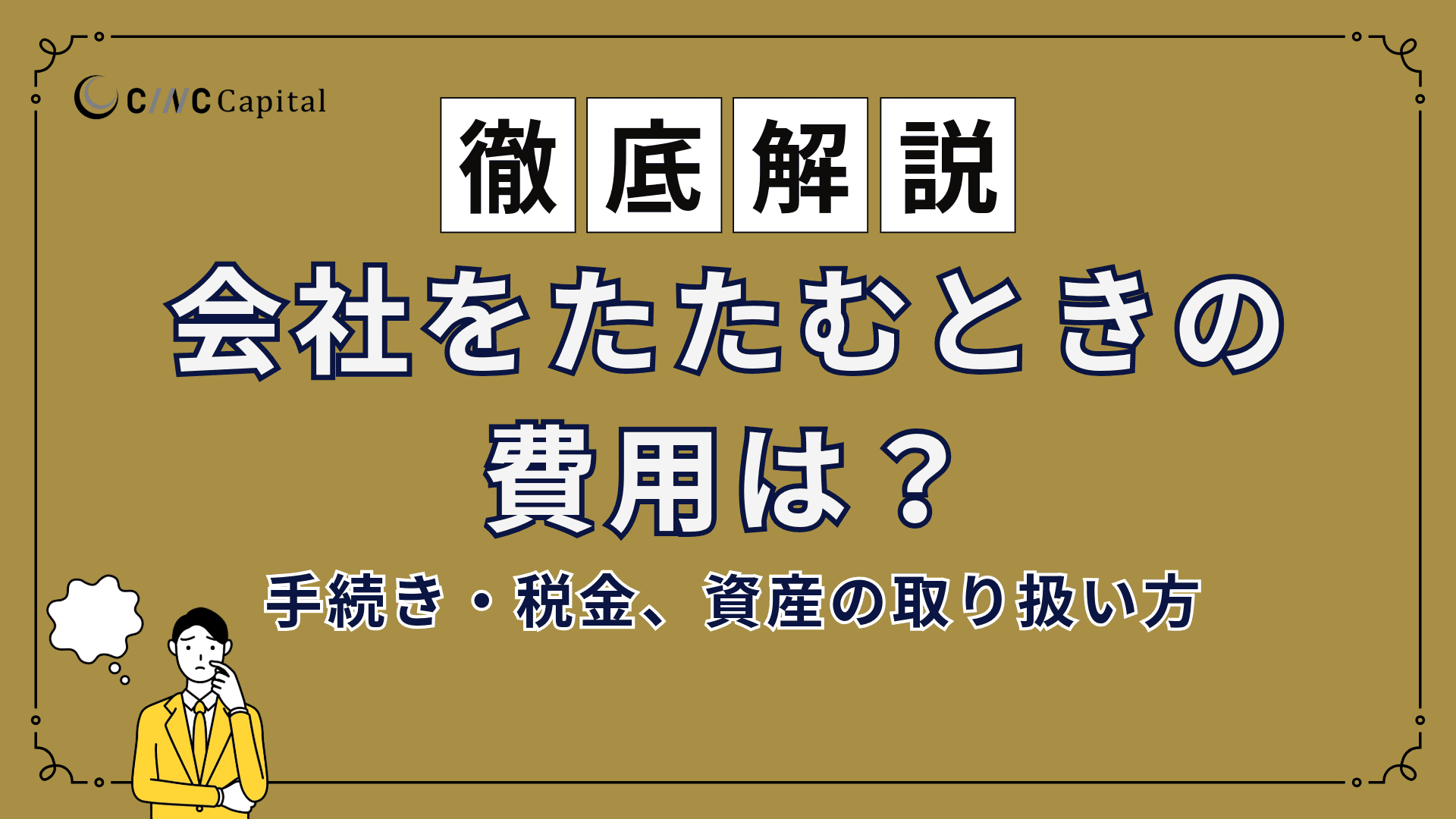
清算・廃業・解散 / 廃業
- 最終更新日2025.06.26
会社をたたむときにかかる費用は?手続きや税金、資産の取り扱いについて解説
会社経営にはさまざまな判断が求められますが、その中でも「会社をたたむ」という決断は大きな節目です。この記事では、会社をたたむ際の手続きや費用、税金、資産の取り扱いなどをわかりやすく解説します。手続きを誤ると余計な費用が発生する可能性もあるため、正しい知識を身につけておきましょう。
目次
会社をたたむ(解散・清算)と倒産の違いは?
「会社をたたむ」と聞くと「倒産」と混同されがちですが、実はまったく異なる意味があります。それぞれの違いを理解しておくことは、適切な選択につながります。
会社をたたむという表現には、「解散」と「清算」の手続きが含まれます。これは会社の意思で自主的に事業を終了し、法人格を消滅させることを意味します。
一方、倒産は、会社が経営破綻して債務を返済できなくなった状態を指します。つまり、「会社をたたむ」は前向きな整理であり、「倒産」は経営不振による強制的な終了です。
解散・清算は、法的手続きに則って進めることで、株主や債権者との関係をきれいに整理し、トラブルを防ぐことが可能です。
しかし、倒産は裁判所の関与のもとで進行し、民事再生や破産といった法的整理が必要になります。この違いを理解することで、今後の方向性をより冷静に判断できます。
会社のたたみ方・手続きの流れ
会社を円滑にたたむためには、法的な流れを正しく理解し、計画的に進めることが重要です。ここでは、解散から清算結了までの具体的な流れを見ていきましょう。
株主総会での解散決議
会社を解散するには、まず株主総会を開催し、特別決議として解散を決定します。これは会社法に基づく正式な手続きで、出席株主の3分の2以上の賛成が必要です。定款によってはさらに厳しい要件がある場合もあります。
例えば、社長一人で経営している会社(いわゆる一人会社)であっても、名義株主が別にいる場合は注意が必要です。解散の決議がないまま手続きを進めると、無効になる可能性もあるため、慎重に対応しましょう。
解散登記と清算人の選任
解散決議後は、法務局に対して解散登記を行う必要があります。あわせて、清算人を選任し、その旨も登記します。清算人は、会社の資産・負債を整理し、清算手続き全般を担う重要な役割です。
通常は代表取締役がそのまま清算人になるケースが多いですが、第三者を選任することも可能です。選任登記を怠ると手続きが無効になる可能性があるため、早めの対応が肝心です。
官報公告と債権者対応
解散登記が完了したら、次に「解散したこと」「債権者が一定期間内に申し出るよう」という公告を官報に掲載します。公告期間は2ヶ月以上が基本で、この間に債権者からの申し出がなければ、次の清算段階へ進めます。
公告と同時に、債権者が明確にわかっている場合は、個別に通知を送付する義務もあります。これを怠ると、債権者とのトラブルに発展するおそれがあるため、正確なリスト作成と通知は必須となります。
資産の処分と債務の精算
公告期間中または終了後に、会社が保有している資産の処分や債務の支払いを進めます。不動産、設備、車両などは売却し、売却益をもとに債務を精算します。この段階で適切な価格で売却できるよう、外部専門家への依頼も検討すると良いでしょう。
また、未収金の回収も同時並行で進める必要があります。資産・負債を正確に把握しておくことで、スムーズな清算が可能になります。
残余財産の分配
債務の精算が完了すると、最終的に残った財産は株主に分配されます。これは出資割合に応じて行われ、会社法上のルールに従う必要があります。ただし、税務上の取り扱いが発生するため、必ず専門家に確認しましょう。
残余財産が残っている場合は嬉しい反面、適切な処理を怠ると税務調査の対象となることもあります。配分後は記録として書類を保管し、対応に備えましょう。
清算結了登記と届出
清算人がすべての処理を終えたら、最後に「清算結了登記」を行い、会社の法人格を正式に消滅させます。これで会社のたたみ方としての法的手続きは完了します。
また、税務署や都道府県税事務所、市区町村への異動届も忘れずに行いましょう。手続きの不備が後から発覚すると、罰則や追加納税のリスクがあるため、最後まで丁寧な対応が求められます。
会社をたたむときにかかる主な費用
会社をたたむ際には、予想以上に多くの費用がかかることがあります。事前に費用の内訳を把握しておくことで、資金計画を立てやすくなります。
登記抹消にかかる費用
会社の清算結了登記には登録免許税が必要です。株式会社であれば3万円が基本となります。これに加えて、司法書士などに依頼する場合は別途報酬が発生します。
手続きを自分で行う場合は費用を抑えることができますが、書類不備や不受理のリスクもあるため、基本的には専門家に依頼するのが良いでしょう。
官報への公告費用
官報への掲載には公告費用がかかります。1回あたりおよそ3〜4万円が相場です。解散時と清算結了時の2回掲載する必要があるため、合計で6〜8万円程度を見込んでおくべきです。
特に官報は国の公的情報媒体としての役割があるため、法的義務として掲載が求められます。怠ると手続きに不備が生じる可能性があるため、確実に行いましょう。
事務所や店舗の原状回復費
賃貸物件を利用している場合、退去時には原状回復費用が発生します。内容は物件の契約条件によりますが、数十万円単位になることもあります。
設備や内装を大幅に改修していた場合は、契約前に工事費用の見積もりを取っておくことが望ましいです。貸主とのトラブルを避けるためにも、早めに相談することが重要です。
在庫や資産の処分費用
不要となった在庫や資産を処分するには、運搬費や廃棄費用がかかります。特に廃棄物処理には法的ルールがあり、産業廃棄物であれば専門業者への依頼が必要です。
さらに、高額な設備や車両などの売却時には、査定や仲介手数料がかかることもあります。費用対効果を見極めながら、無駄な出費を避ける工夫が求められます。
従業員の退職関連費用
従業員がいる場合は、退職金や未払い賃金、有給休暇の精算などが必要です。退職金規定がある場合、そのルールに基づいて支払わなければなりません。
また、社会保険や雇用保険の手続きも必要であり、これらの対応に漏れがあると後からトラブルになる可能性があります。専門家への相談も視野に入れましょう。
税理士や司法書士への報酬
会社の解散・清算には専門的な手続きが多いため、税理士や司法書士に依頼するケースが一般的です。相場として、税理士の報酬は10万円〜30万円、司法書士は5万円〜15万円程度です。
複雑な資産処分や税務申告がある場合は、費用がさらに高額になることもありますが、安心して手続きを進められるメリットがあります。
未払い債務や未処理の取引費用
過去の未払い請求書や取引先との未精算の費用も、会社をたたむ際に処理が必要です。これらは見落とされがちですが、清算の段階でトラブルの火種になることも多いため、事前に洗い出しておくべきです。
また、税務署などの公的機関への未納分があれば、優先的に精算されます。会社の信用を守るためにも、漏れのない対応が求められます。
会社をたたむときに税金は発生する?
会社をたたむ際には、税金の発生についても注意が必要です。事前に税務のポイントを押さえておくことで、予期せぬ負担を防ぐことができます。
会社の解散・清算に伴って発生する主な税金には、法人税、消費税、地方税などがあります。まず、解散時点までの事業年度について法人税の確定申告と納税が必要です。また、清算期間中に利益が出た場合には、清算所得として法人税の課税対象となります。
例えば、資産売却により利益が出た場合、それは通常の事業所得とは異なり「清算所得」として申告が必要です。これは清算結了の日の翌日から2カ月以内に確定申告を行う必要があります。
さらに、在庫の売却や固定資産の譲渡がある場合には消費税も課税対象となる場合があります。従業員への退職金の支払いについては源泉徴収や所得税の対応も必要です。清算時の税務処理は通常の会計処理とは異なるため、税理士と連携して慎重に進めることが求められます。
会社をたたむと残ったお金(資産)はどうなる?
会社をたたんだあとに残る資産は、法的な手続きに従って処理されます。正しい取り扱いを理解し、トラブルや課税リスクを避けましょう。
すべての債務を精算したあとに残る財産は、「残余財産」として株主に分配されます。これは出資比率に応じて配分され、会社の財産である現金、売却済み資産の代金、未収金などが対象となります。
注意すべきは、この残余財産には「みなし配当」として課税される場合があることです。みなし配当とは、会社の資本からの払い戻し以外で株主に帰属する金銭などを指し、通常の配当と同様に課税対象になります。
例えば、資産の売却益が多く、分配額が出資額を超える場合、その差額は課税される可能性があります。法人から個人へ財産が移転する際には、税務署からの確認が入ることもあるため、記録と証拠書類の保管が重要です。
また、会社によっては資産の現物(車両や不動産)を株主が受け取るケースもありますが、その場合も時価評価による課税が発生する可能性があります。専門家と連携し、適正な処理を行うことが重要です。
会社をたたむ以外の選択肢はある?
「会社をたたむ」以外にも、事業を継続しながら手放す方法は存在します。選択肢を知ることで、より柔軟な対応が可能になります。
事業譲渡で他社に引き継ぐ
事業譲渡とは、会社の一部または全部の事業を他社に売却・譲渡する方法です。会社そのものは存続しますが、事業は他者の手に渡ります。
例えば、店舗運営や特定の事業部門のみを譲渡することで、従業員の雇用や顧客との取引を維持しながら経営を整理できます。ただし、資産や契約を個別に移転する必要があるため、法的手続きや合意形成が必要です。
特に債務超過の会社が資産のみを譲渡する場合、債権者を害する「詐害行為」とみなされるリスクがあります。債権者を犠牲にして資産だけを移転させるような取引は民法上の詐害行為取消権の対象となり、後から取り消される可能性があるため、法律専門家への相談が不可欠です。
株式譲渡で経営権を移す
株式譲渡は、会社の株式を他者に売却して経営権を移す方法です。法人格をそのままに、経営者が変わる形になります。会社名や事業内容を継続できるため、従業員や顧客との関係を維持しやすいのが特徴です。
中小企業ではオーナー交代による事業継続の手段として活用されることが多く、M&Aの一種として注目されています。買い手探しや株価の評価など、専門家の支援が不可欠です。
休眠会社として存続させる
一時的に事業を停止し、会社の登記を残したまま「休眠会社」とする方法もあります。将来的に再開する可能性がある場合や、今すぐ清算せずに様子を見たいときに有効です。
ただし、法人住民税など最低限のコストはかかり続けるため、長期間の休眠には注意が必要です。2年間届出がなければ、みなし解散されることもあります。定期的な状況確認が必要です。
親族や従業員、第三者に事業承継をする
事業承継とは、現経営者が親族や従業員、外部の第三者に事業を引き継ぐことです。従業員承継は特に顧客との関係性を維持しやすく、事業価値の継続にもつながります。
承継には時間がかかるため、早めの準備が求められます。資産や契約、取引関係を明確にしておくことで、スムーズな移行が実現できます。
M&Aで他社に統合や売却する
M&A(合併・買収)には、前述の事業譲渡や株式譲渡のほかにも、合併や会社分割などの手法があります。合併は2つ以上の会社が1つになる方法で、会社分割は一部の事業を切り離して別会社にする方法です。
赤字や借入があっても、ノウハウや人材、顧客基盤が評価されることで成立するケースも多く、事業価値を最大化しながら会社の承継が可能です。M&Aは買い手との交渉や契約が複雑なため、専門機関の支援が必須です。事前の価値査定やデューデリジェンス(精査)を行うことで、安心して進められます。
まとめ|専門家に相談し、納得のいく形で会社を閉じましょう
会社をたたむ際は、「倒産」ではなく計画的な「解散・清算」として、法的に整理を行うことができます。経営から手を引く方法は、会社をたたむ以外にも、事業譲渡や株式譲渡、M&Aなどの選択肢があり、状況によっては事業の価値を活かしながら経営を離れることもできます。
経営の終わり方に正解はありませんが、納得のいく形で会社を閉じるためにも、早めに専門家へ相談することが重要です。
CINC Capitalでは、会社のたたみ方からM&A、事業承継まで、経営者様の状況に合わせた最適なご提案を行っています。完全成功報酬の採用により、相談は無料ですのでぜひお気軽にご相談ください。