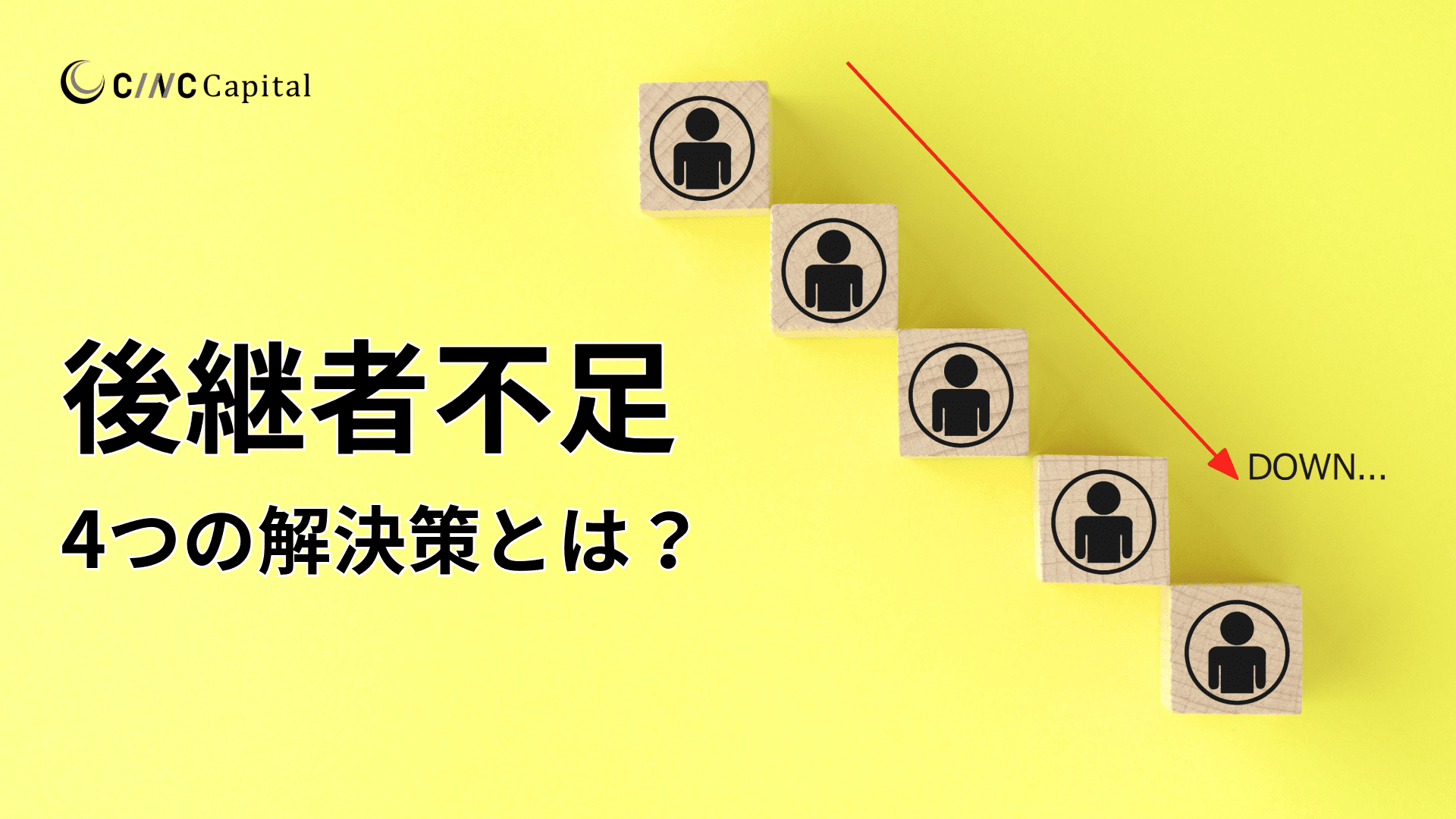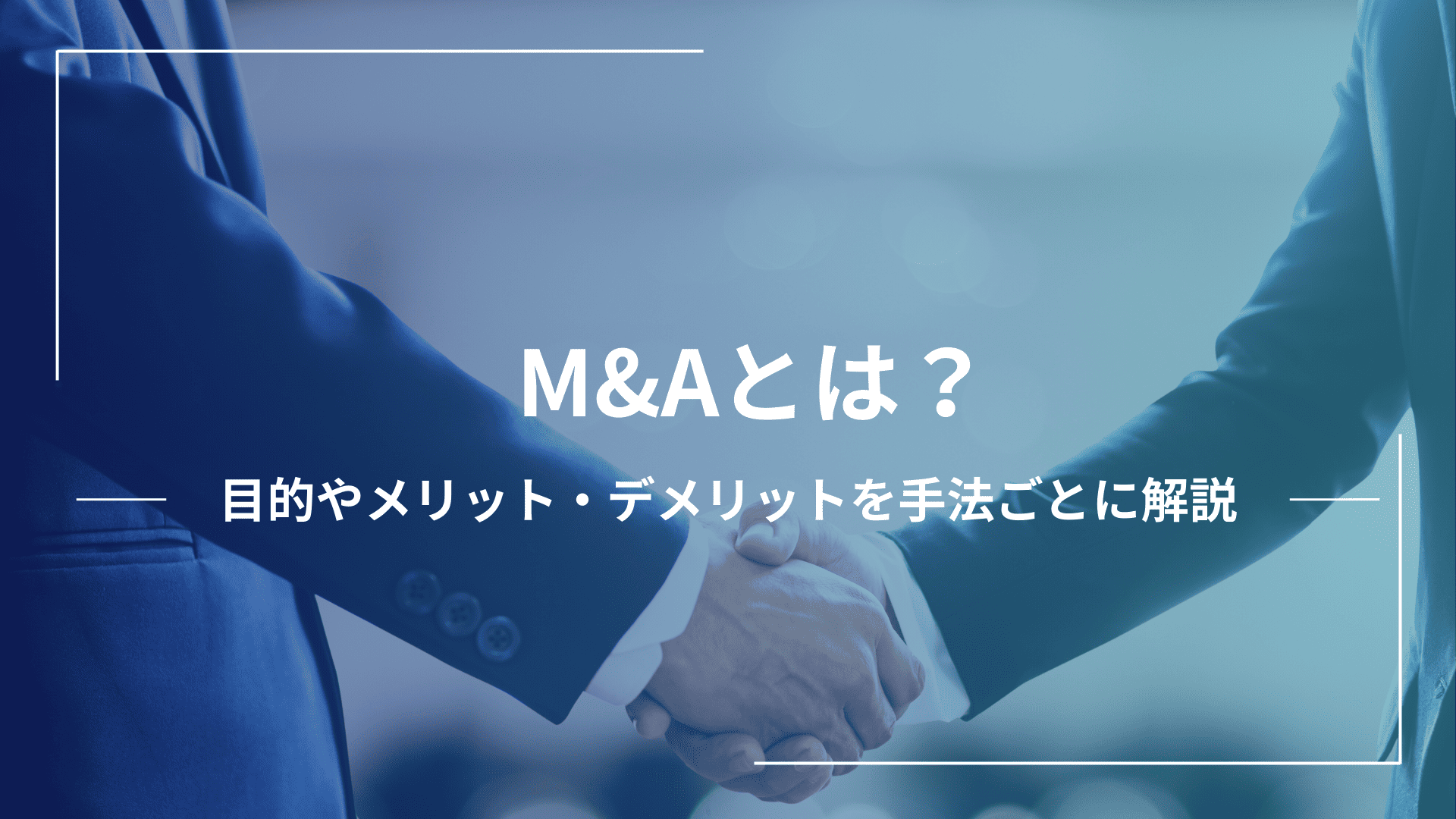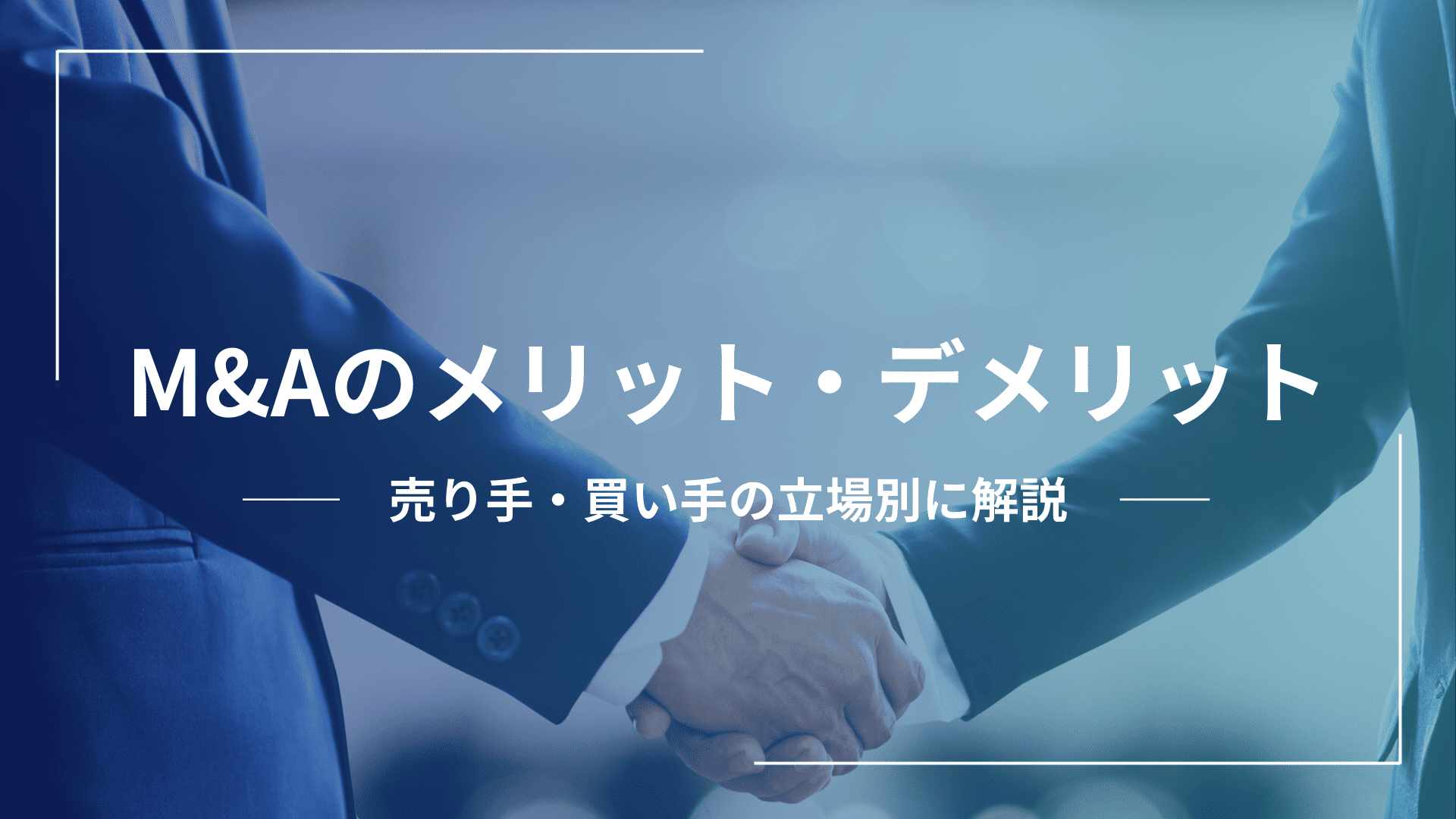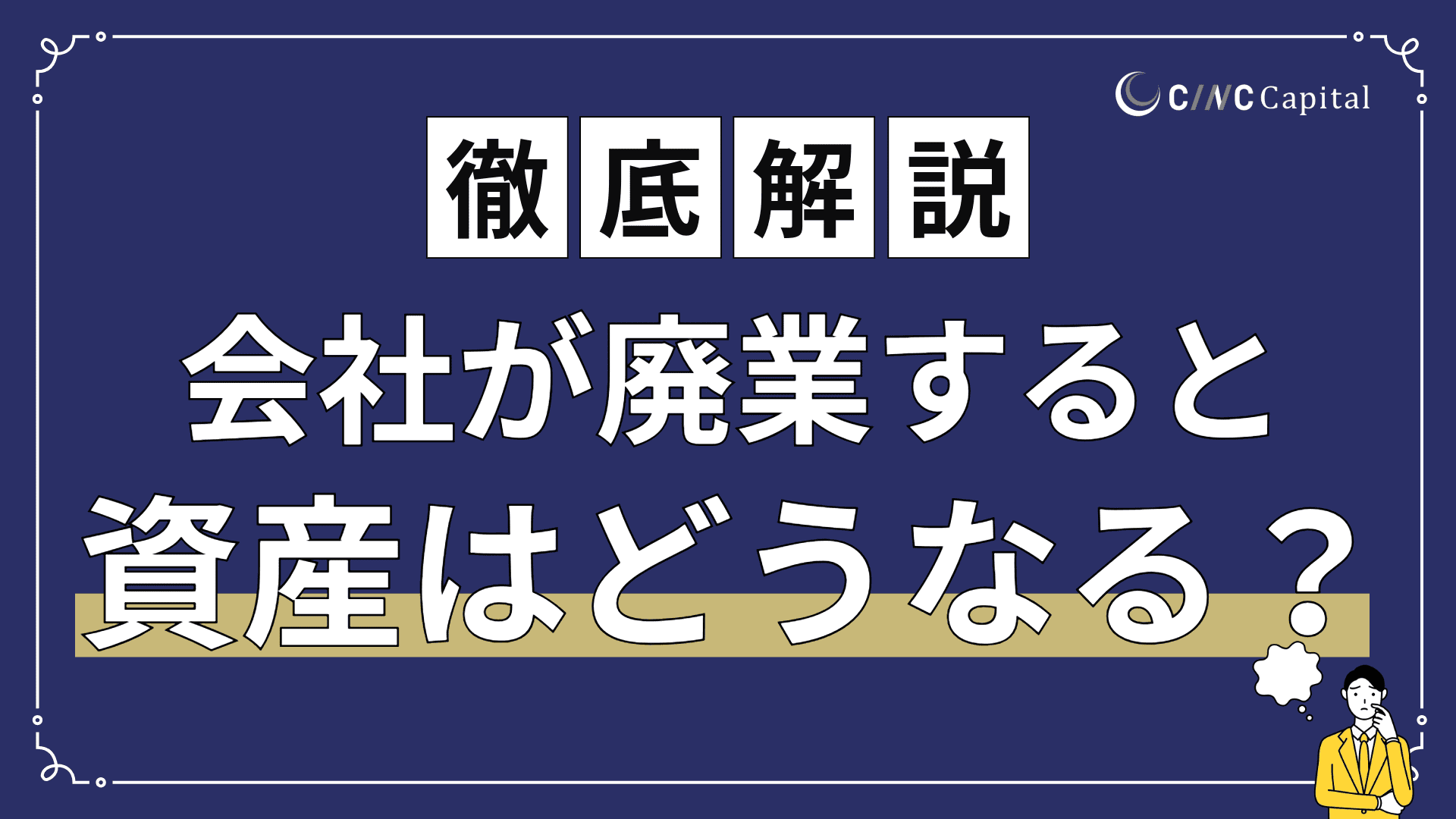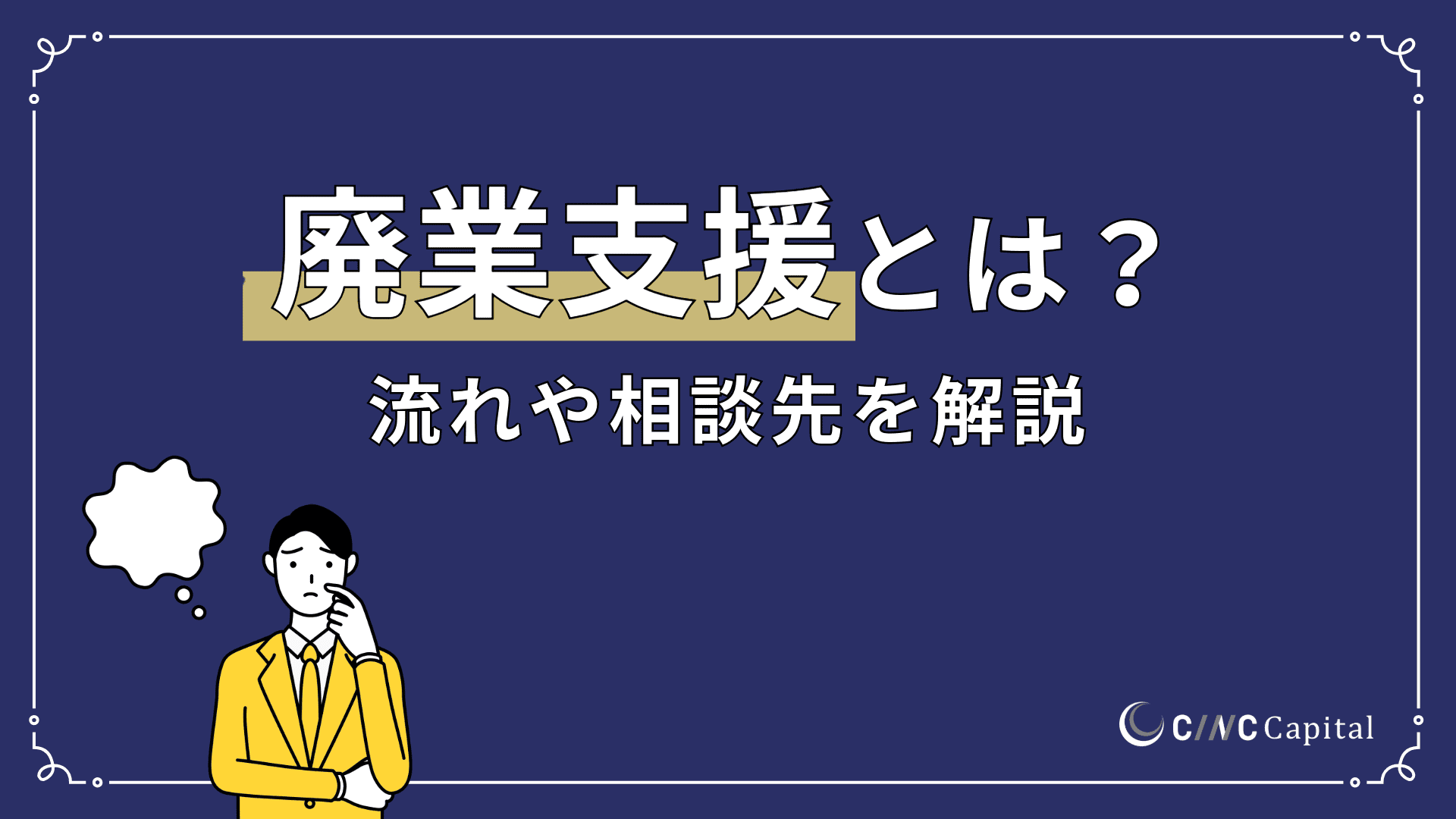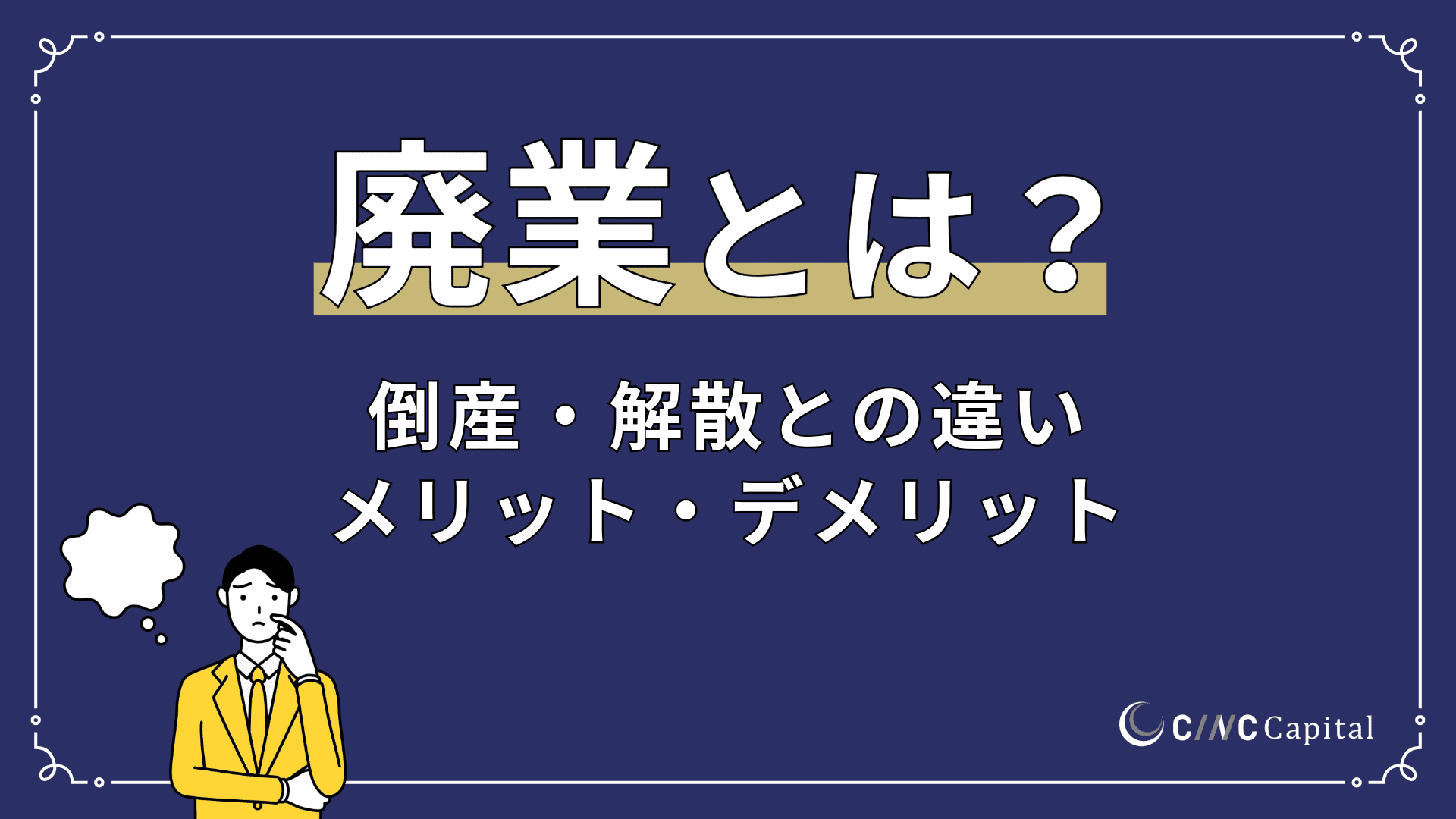CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
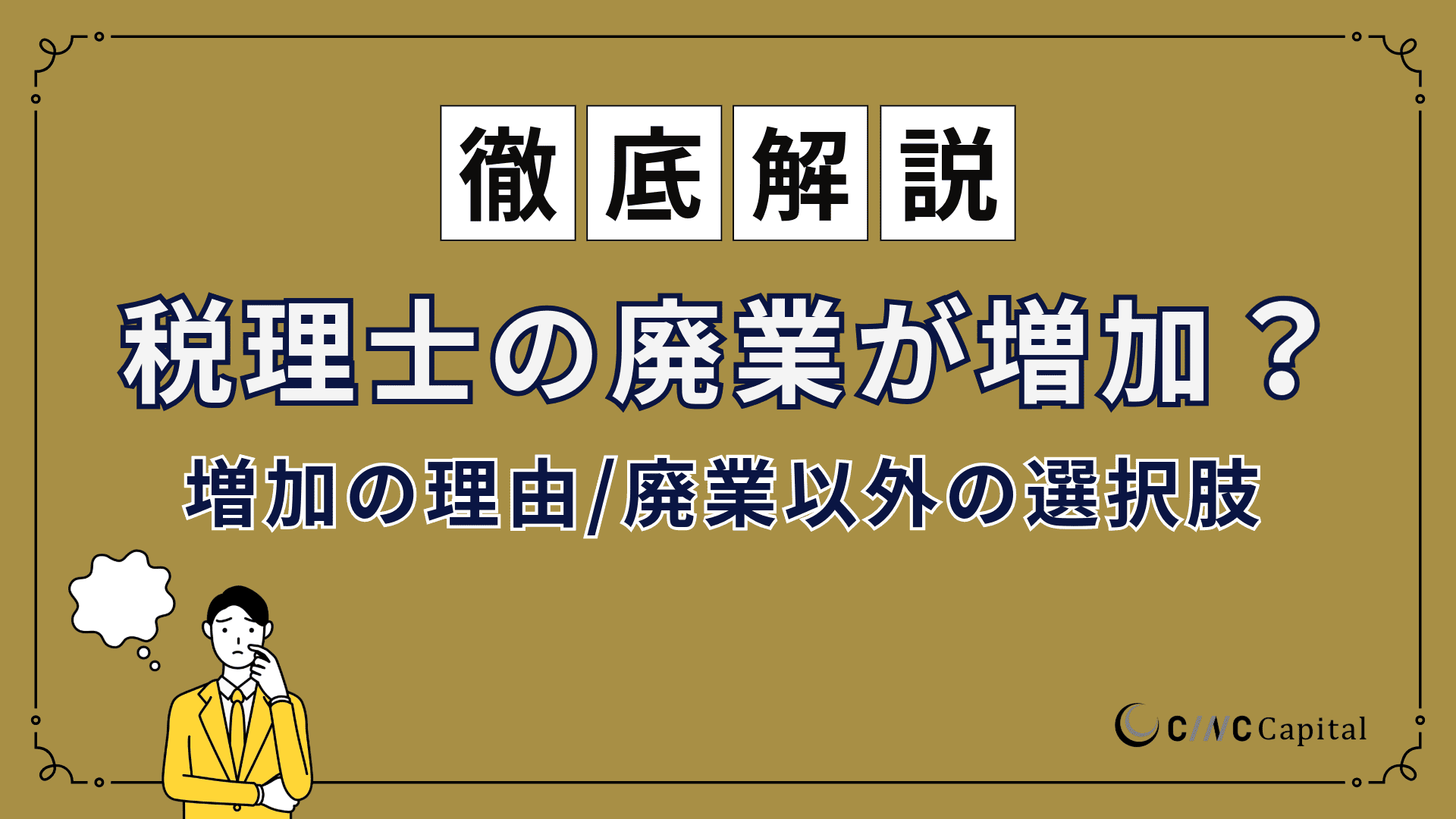
清算・廃業・解散 / 廃業
- 最終更新日2025.10.15
税理士の廃業が増加?理由や廃業率、手続き方法、再登録、廃業以外の選択肢を解説
近年、税理士の廃業が増加していることをご存じでしょうか。高齢化や人材不足、業界の変化などさまざまな要因が背景にあります。税理士としてのキャリアを続けるか、それとも廃業するか、悩ましい選択に直面する方も少なくありません。
本記事では、税理士の廃業が増えている理由や実際の廃業率、廃業時の具体的な手続き、再登録の流れ、そして廃業以外に考えられる選択肢まで、幅広く解説します。将来を考えるうえで知っておきたい情報を、ぜひ参考にしてください。
目次
税理士の廃業率は?
税理士の廃業率は年々上昇傾向にあり、業界全体の課題として注目されています。帝国データバンクの調査によると、2024年の業種別休廃業・解散率のなかでもっとも高かったのが「税理士事務所」で、5.61%という結果でした。この数字は全業種のなかでも突出しており、税理士業界がいかに厳しい局面にあるかを示しています。
この背景には、税理士の高齢化が進んでいることに加え、顧問企業の減少や顧問料の低下など経営環境の悪化が影響していると考えられます。また、インボイス制度の導入など新たな業務対応も求められ、対応しきれず廃業を選ぶケースも少なくありません。
独立開業した税理士にとって将来性がないわけではありませんが、顧問先のニーズや時代の変化に柔軟に対応できるかどうかが、今後の明暗を分ける鍵となっているのです。
【出典】株式会社帝国データバンク「全国企業『休廃業・解散』動向調査(2024年)」
税理士の廃業が増加している理由
税理士事務所の廃業が増えている背景には、単一の要因ではなく複数の要素が複雑に絡み合っています。ここでは、税理士業界における廃業増加の主な要因についてご紹介します。
高齢化による後継者不足の影響
税理士業界では高齢化が深刻化しており、それに伴う後継者不足が廃業の大きな要因となっています。税理士の平均年齢は高く、引退を視野に入れる年齢に達しても、後を継ぐ人材が見つからないという事務所が多数あります。実際に、2024年時点で休業や廃業に至った日本の企業経営者の平均年齢は71.3歳に達しており、年齢的な限界からやむを得ず廃業するケースが増加中です。
さらに、若手税理士のなかには独立開業よりも企業内税理士や他のキャリアを選ぶ人も多く、事務所を引き継ぐ人材の確保が難しい状況です。こうした後継者問題が解決されない限り、税理士事務所の廃業は今後も続くと見られています。
収益性の悪化と顧問先の減少の問題
税理士事務所の経営環境は近年、収益性の面でも厳しさを増しています。クラウド会計ソフトの普及や価格競争の激化により、従来のように安定的に顧問料を得ることが難しくなってきました。特に中小規模の税理士事務所では、既存顧問先の契約終了や新規獲得の難しさから収入が減少し、経営が成り立たなくなるケースも増えています。
また、顧問先の事業者側も経営難や人手不足を理由に税理士との契約を見直す動きが強まり、契約数自体が減少している傾向も見られます。収益構造の見直しや業務の多角化が求められるなか、変化に対応できない事務所は廃業を選ばざるを得ない状況に追い込まれているのです。
インボイス制度や電帳法などによる業務の煩雑化
2023年から順次施行されているインボイス制度や電子帳簿保存法(電帳法)は、税理士にとって業務負担の大きな要因となっています。これらの制度により、顧問先の会計処理や請求書管理の支援がより複雑化し、税理士側には新たな知識習得やシステム対応が求められました。
特に高齢の税理士や小規模事務所にとっては、こうした制度変更への対応が難しく、業務量の増加と人手不足が直撃する結果となっています。結果として、業務の煩雑さに対応できずに廃業を決断する事務所も見られるようになっています。
制度変更がもたらした影響は一律ではありません。体制を整えた事務所にとっては新たなビジネスチャンスとなる一方、変化に対応できない事務所には淘汰の波として押し寄せています。今後もこの業務環境の二極化は続くと考えられ、税理士業界全体の構造転換が求められています。
【廃業をお考えの税理士さまへ】
税理士業の廃業を決断する前に、「事業承継」「M&A」という選択肢を検討する方が増えています。これからの選択を前向きに考えるきっかけとしてM&A・事業承継の完全ガイドをぜひご活用ください。
【個人事業主】税理士の廃業手続きの流れ
個人で税理士事務所を運営している場合、廃業時に届出が必要な書類の種類や提出期限は多岐にわたるため、正確に把握しておくことが重要です。ここでは、個人事業主として税理士を営んでいた方が廃業する際の主な手続きの流れを解説します。
税務署へ個人事業の廃業届出書の提出
はじめに必要となるのが、「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出です。廃業日から1カ月以内に所轄の税務署へ提出しなければなりません。提出期限が土日祝に重なる場合は翌営業日が期限となるため、提出日には注意が必要です。
青色申告の取りやめと消費税の事業廃止届出
青色申告をしていた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要です。こちらは、青色申告を取りやめる年の翌年3月15日までに提出します。また、課税事業者であった場合には「消費税の事業廃止届出書」も速やかに提出が求められます。廃業の理由を記載する欄には「廃業のため」と明記しましょう。
給与支払事務所の廃止届(従業員がいる場合)
従業員や家族への給与支払いを行っていた場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出も必要です。書類は廃止日から1カ月以内に税務署へ提出します。提出が遅れると、源泉所得税の処理などに影響が出る可能性があるため注意しましょう。
都道府県税事務所へ事業税の廃止届出
税務署への手続きに加えて、都道府県税事務所への廃業届も必要です。使用する届出書の様式や提出期限は都道府県によって異なります。例えば東京都では廃業から10日以内、大阪府では「遅滞なく」と決められています。各地のルールに従えるよう、事前に公式サイトなどで確認しておきましょう。
税理士会への退会届と証票返却
最後に、税理士業務に関する手続きとして、所属していた税理士会への退会届の提出が必要です。同時に、税理士証票やバッジ(記章)などの返却も求められます。退会後も会費が発生する可能性があるため、早めの手続きが推奨されます。また、将来的に再登録を検討する場合は、必要な書類や再登録条件についても確認しておくと安心です。
【法人事務所】税理士の廃業手続きの流れ
法人として税理士業務を行っていた場合、廃業時には会社法や税法に基づく各種の手続きが必要です。ここでは、税理士法人の廃業にあたって必要な手続きの流れを解説します。
会社の解散決議と清算人の選任
税理士法人を廃業するには、株主総会を開いて「解散決議」を行う必要があります。解散事由に該当する場合(例:定款の存続期間満了、特別決議による解散など)に限り、解散が可能です。
このとき、会社の残務処理を行う「清算人」も併せて選任します。清算人は通常、代表取締役や取締役のなかから選ばれます。営業活動は解散決議の前に停止し、取引先や従業員への説明・通知も行っておきましょう。
法務局での解散登記と官報公告
解散決議後、2週間以内に管轄の法務局で解散登記を行います。このとき、清算人の就任登記も併せて行いましょう。解散登記が完了すると、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取得できるようになります。
さらに、債権者に対して異議を申し出る機会を与えるため、「官報」にて解散公告を行います。公告期間は最低2カ月必要となるため、できるだけ早い段階で実施するのが望ましいでしょう。
財産の清算と清算結了登記
官報公告期間が終了し、債権回収や債務整理、資産の売却など清算業務が完了したら、残余財産を株主に分配します。これらの処理が終わり、「清算時の決算書類」を作成すると、株主総会の承認を得ることが可能です。承認後は、2週間以内に法務局で「清算結了登記」を行い、これをもって法人格が正式に消滅します。
法人税等の確定申告(解散・清算)
法人であっても、解散時と清算結了時にはそれぞれのタイミングで法人税等の確定申告が必要です。
まず、解散日までの期間についての決算を行い「解散確定申告書」を提出します。次に、清算結了時には「清算確定申告書」を作成し、税務署と都道府県税事務所、市区町村役場へ提出します。併せて、異動届出書や閉鎖事項証明書などの関連書類も提出が必要です。
これらをすべて完了することで、税務上の廃業処理が整います。
税理士会への退会届と証票返却
最後に、税理士としての登録を廃止するため、所属している税理士会に退会届を提出し、税理士証票やバッジを返却します。法人として登録していた場合には、法人単位での手続きも必要となるため、事前に税理士会へ確認して漏れのないように進めましょう。
税理士は廃業後に再登録や再開はできる?
一度廃業した税理士でも、一定の条件を満たせば再び税理士業務に復帰することが可能です。ただし、過去の懲戒処分や廃業の経緯によっては再登録が認められないケースもあるため、注意が必要です。ここでは、税理士廃業後の再登録・再開に関するポイントをご紹介します。
再登録や再開可能な条件
税理士が廃業後に再び登録するには、まず再登録申請を行うことが必要です。再登録は基本的に可能ですが、条件があります。過去に懲戒処分を受けた場合や、廃業の理由が不正行為に関係する場合には、一定期間の業務禁止が課され、その期間中は登録が認められません。
例えば、不正行為により「2年間の業務停止相当」とされた場合、その期間が経過するまでは再登録不可となります。再登録には税理士会の審査も必要で、登録の可否は審査結果によって判断されます。
再登録に必要な書類と費用
再登録には、以下のような書類の提出が求められます。
- 税理士登録申請書
- 登録免許税納付書
- 履歴書や身分証明書などの添付書類
- 過去の登録証票がある場合はその返却または紛失届
再登録の際も新規登録と同様、登録免許税がかかるため、再開には一定の費用が必要です。そのほか、所属税理士会に対する入会金や年会費も再度発生する場合があります。
登録拒否となるケースは?
以下のような場合には、税理士会からの再登録が拒否される可能性があります。
- 廃業前に重大な不正行為があり、調査の結果として懲戒処分相当と認定された場合
- 税理士法に基づく業務禁止期間中である場合
- 登録申請における記載内容に虚偽がある場合
- 犯罪歴や社会的信用に関わる問題があると判断された場合 など
特に、近年は「懲戒逃れ」としての自主廃業が社会問題化しています。政府は元税理士に対しても調査と処分が可能となるよう、税理士法の改正を検討中です。そのため、不正行為による廃業であった場合は、たとえ形式上の廃業であっても再登録は厳しく制限される傾向があります。
税理士事務所を廃業せずに承継する方法とは?
長年培ってきた税理士事務所を、廃業せずに引き継ぎたいと考える方は少なくありません。税理士事務所の承継にはさまざまな方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。ここでは、主な5つの承継方法について解説します。
親族への承継
税理士事務所の承継方法としてもっとも一般的なのが、子どもなどの親族への引き継ぎです。身内であるため、引き継ぎ側の人柄や価値観、事務所の理念への理解が深く、スムーズな承継が期待できます。また、事務所の資産や設備の相続においても比較的手続きが簡単に済むのが利点です。
ただし、当然ながら税理士資格を持っていなければ業務の引き継はできません。将来的に税理士になる可能性がある親族がいる場合でも、承継には時間をかけて計画的に進める必要があります。
所内の従業員税理士への承継
事務所内に税理士資格を持つ職員がいる場合、従業員に事務所を引き継いでもらう方法も有効です。事務所の業務内容や方針に精通しており、既存のクライアントとも信頼関係を築けていることが多いため、比較的自然な形での承継が可能です。
ただし、税理士としての実務能力とは別に、経営者としての資質が求められます。そのため、後継者候補が事業全体を運営できるよう、段階的に経営のノウハウを引き継ぐことが重要です。何よりも、本人が後継者となる意志を持っているかどうかを確認することから始めましょう。
外部の若手税理士とのマッチングによる承継
知り合いの若手税理士など、事務所外から後継者を招くケースもあります。特に、独立志向があるものの経験や顧客基盤が乏しい若手税理士にとっては、既存の事務所を引き継ぐことは大きなチャンスです。
この方法では、新旧の税理士が一定期間ともに業務を行いながら徐々に承継を進める「段階的引き継ぎ」が効果的です。ただし、既存の職員との関係性やコミュニケーションに注意が必要で、所長税理士が両者の間に立って信頼関係を築くことが欠かせません。
税理士法人への統合・加入による承継
近年は、個人事務所を税理士法人に統合・吸収合併する形での承継も増えています。事務所のブランドやスタッフを守りながら、業務体制をより強化することが可能です。
この方法は、個人では対応しきれない業務量や責任分散の面でも有効で、法人側にとっても拠点拡大や人材確保のメリットがあります。ただし、法人の経営方針や理念との整合性を確認し、双方が納得する形で進める必要があります。
M&A仲介会社を活用した第三者承継
後継者が身近に見当たらない場合でも、税理士事務所を第三者に譲渡する「M&A」という選択肢があります。最近では、会計業界に特化したM&A仲介会社が数多く存在しており、信頼できる譲渡先とのマッチングを支援してくれます。
M&Aにより、従業員の雇用や顧問先との関係を維持しながら、事務所を適切な評価での売却を目指すことが可能です。ただし、価格や条件の調整には一定の交渉が必要となる場合があります。また、譲渡先との相性や事務所の理念の共有も重要です。M&A仲介会社を活用することで、こうした交渉や調整の負担を軽減できるでしょう。
一方で、税理士事務所のM&Aには、顧問先の引き継ぎやスタッフの雇用継続、知識・ノウハウの移転といった特有の課題もあります。こういった問題に対応するために、譲渡前から引き継ぎに向けた準備を進めておくことが求められます。仲介会社は課題解決に向けたアドバイスも行ってくれるため、早めに相談することがおすすめです。
また、希望通りのM&Aを実現するためには、事前に事務所の価値を高めておくことも重要です。例えば、顧問料の見直しによる収益の安定化や、業務効率化・デジタル化の推進といった施策が有効になる場合があります。M&A仲介会社の支援を受けながら、売却を視野に入れた準備を進めましょう。
まとめ|事業承継の成功に向けて、専門家に早めの相談を
税理士事務所の未来を考えるうえで、早めに後継者や承継方法を検討することは非常に重要です。承継の方法ごとに異なるメリットや注意点があるため、しっかり見極めましょう。特に後継者がいない場合でも、M&Aという選択肢を活用すれば、顧問先や従業員を守りながら円滑な引き継ぎを実現できます。
廃業を避け、事務所の信頼と実績を次世代につなげるためには、時間をかけて準備し、適切な選択肢を見極めていくことが求められます。自身の希望や状況に合った方法を選び、納得のいく形で次のステージへと進んでいきましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。