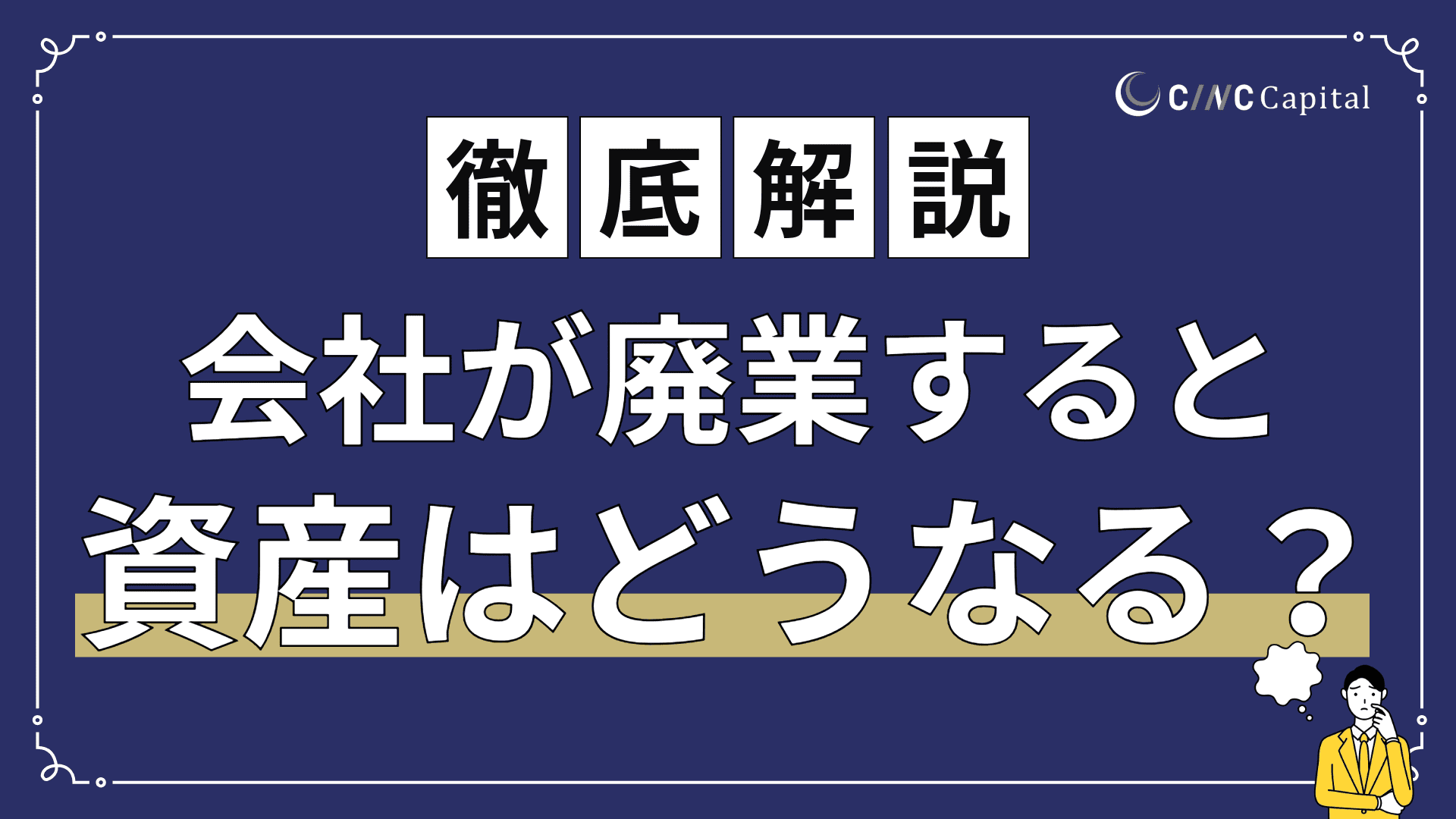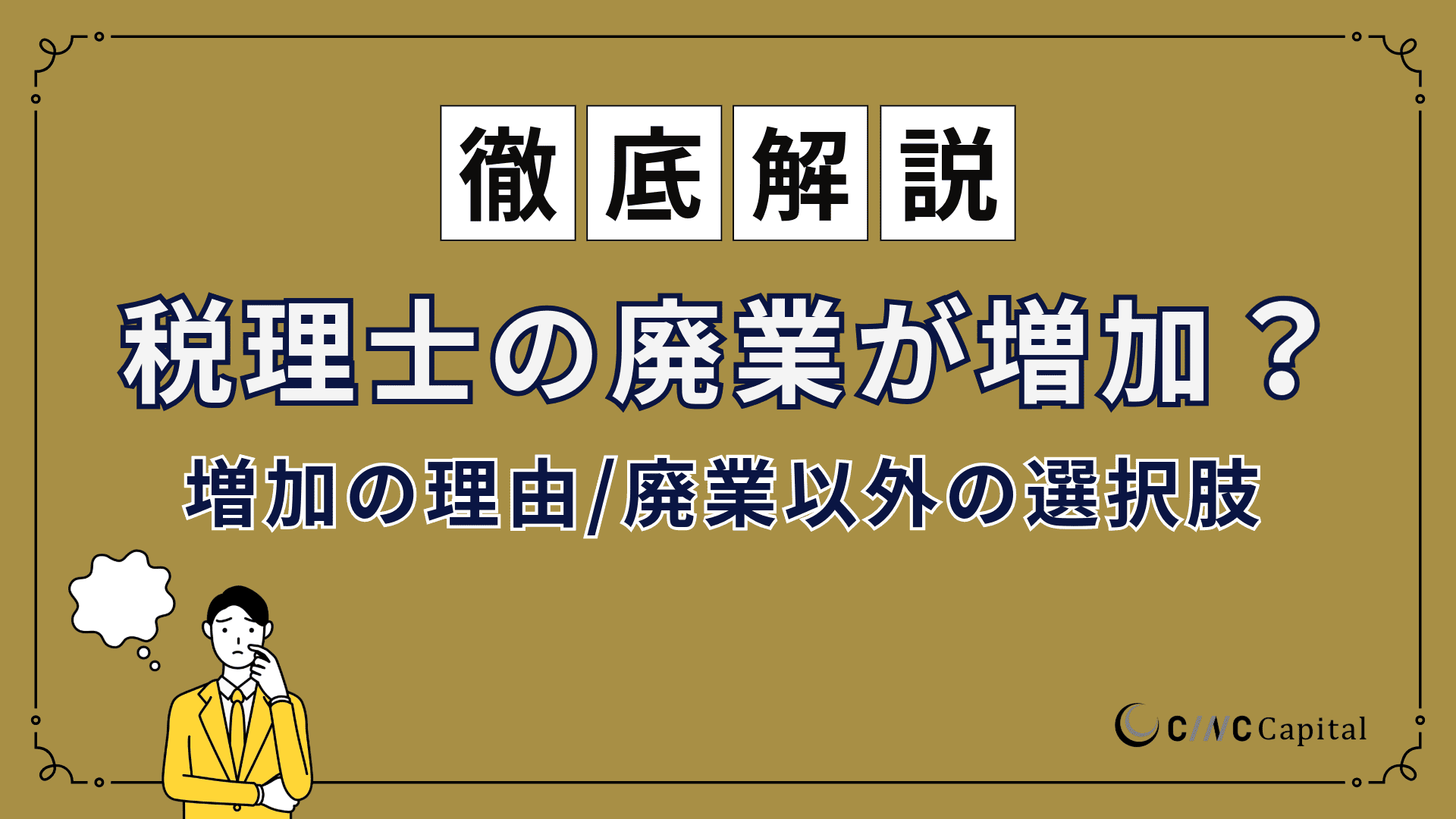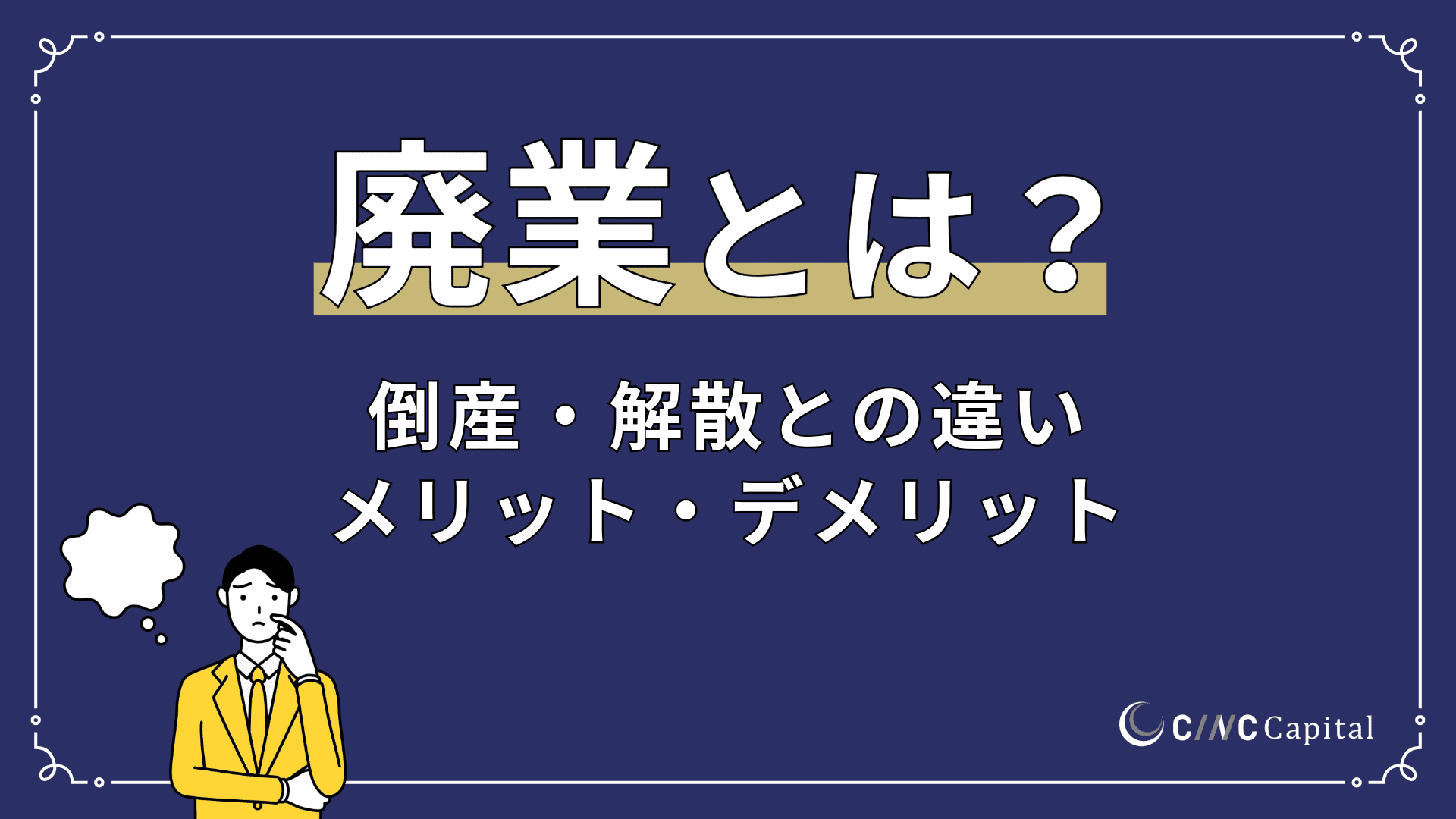CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
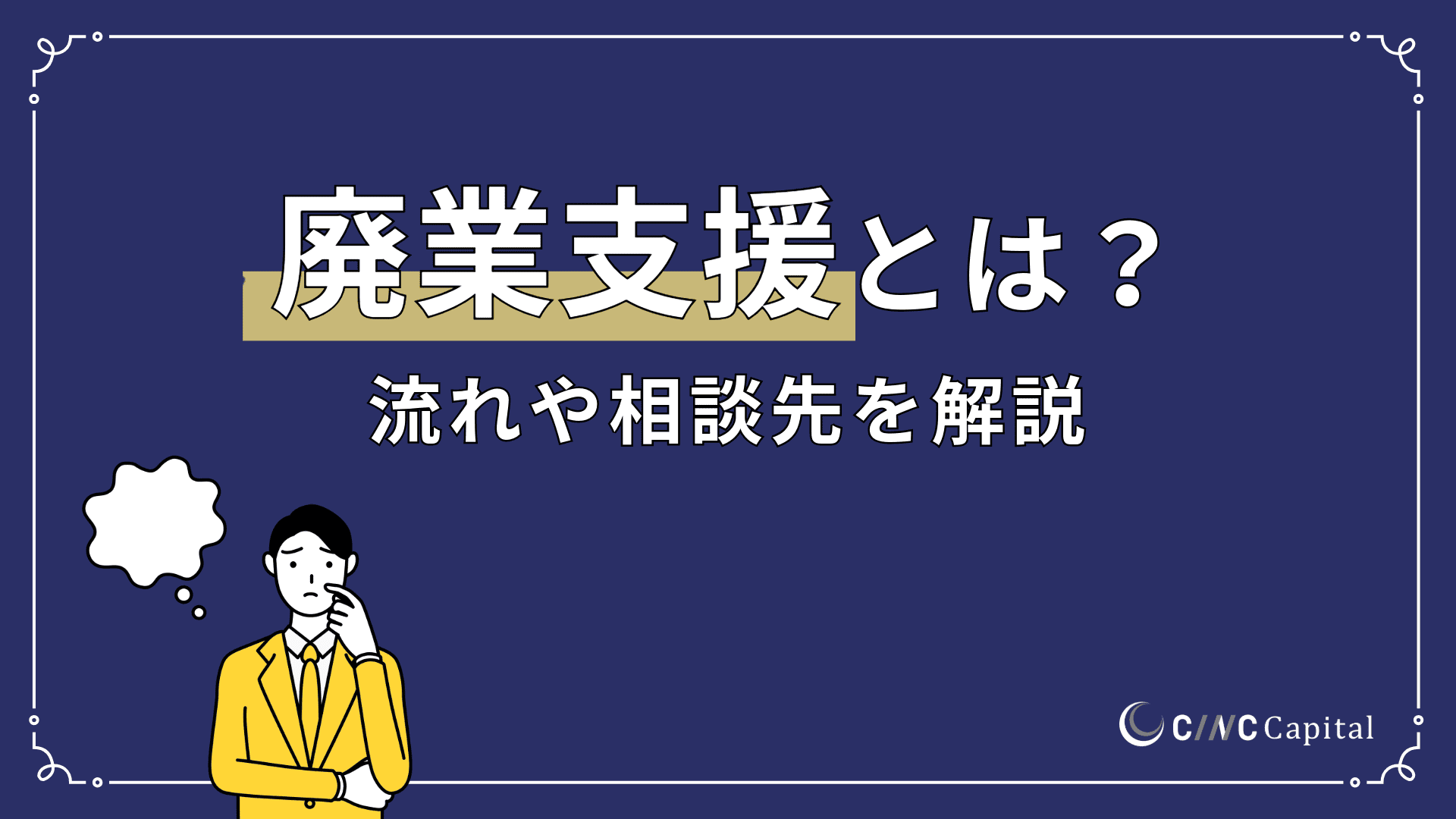
清算・廃業・解散 / 廃業
- 最終更新日2025.06.26
廃業支援とは?手続きの流れや利用できる廃業支援制度、相談先を解説
廃業を検討している企業や個人事業主にとって、どのように手続きを進めるのか、誰に相談し、どのような支援制度を活用すれば良いかは気になるポイントではないでしょうか。
今の事業を終わらせると決めても、従業員や取引先への影響、負債の整理など考慮すべきことは多岐にわたります。必要な手順を踏まずに安易に廃業を進めると、後から思わぬトラブルや追加コストが発生する可能性もあります。スムーズに廃業を進めるためには、専門家や公的機関のサポートを受けることが大切です。
本記事では、廃業へのサポートとしての廃業支援の概要や、法人・個人事業主別の手続きの流れ、費用の目安、そして活用できる支援制度や相談先を解説します。
目次
廃業支援とは?
廃業支援は、事業を円滑に終了するために必要な情報や専門的サポートを提供する取り組みです。公的機関や専門家が連携しながら、経営者の負担を軽減することを目的としています。
企業が自主的に事業を終える場合、ただ業務を停止すれば良いわけではなく、取引先や従業員への告知、行政への届出、債務整理など幅広い対応が求められます。
こうした一連の手続きを漏れなく行うために、廃業支援を活用することが重要です。廃業支援を受けることで、廃業時の費用負担や負債処理など、経営者にかかる精神的・経済的なプレッシャーの軽減も期待できます。
経営の専門家や公的支援をうまく取り入れることで、次のステップに向けた準備も同時に進めやすくなるでしょう。
廃業手続きの流れ
廃業の流れは、法人か個人事業主かによって手続きが異なります。いずれの場合も、計画的に準備を進めることが重要です。ここからは、法人と個人事業主それぞれの廃業の流れを見ていきましょう。
法人
法人の廃業手続きは、まず原則として株主総会(合同会社の場合は社員全員の同意)で解散を決議し、清算人を選任します(株式会社では通常、取締役が清算人となるケースが多いです)。清算人の選任後は、法務局への解散登記を行い、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、日本年金機構などの関係機関に解散届出を提出します。
続いて、資産の現金化、債権の回収、債務の弁済などの清算業務を行い、債権者に対しては官報により解散公告を出し、2か月以上の期間を設けて債権申出を催告します。清算手続きが完了した後、清算事務報告書を作成し、株主総会(または社員総会)の承認を得て、法務局に清算結了登記を申請します。同時に、清算結了届出書を税務署などに提出します。
清算後は、清算事務報告書や帳簿書類などを法令に基づき一定期間(通常7年間)保管し、清算の完了をもって法人の廃業手続きが完了します。これらの手続きには複雑な法的要件を伴うため、司法書士や弁護士などの専門家のサポートを受けることで、手続きの正確性を高めることができます。
個人事業主
個人事業主が廃業する場合、まず税務署へ「個人事業の廃業届出書」を提出する必要があります。 この届出は、事業を廃止した日から1か月以内に提出しなければなりません。
併せて、廃業した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税や消費税(該当する場合)などの最終的な納税額を確定させます。課税事業者の場合には、必要に応じて「消費税の事業廃止届出書」などの提出も行いましょう。
また、従業員がいる場合には、以下の届出が必要です。
- 労働保険(労災保険・雇用保険)の「事業所廃止届」の提出
- 雇用保険加入者に関する「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出
- 社会保険(健康保険・厚生年金)の「適用事業所全喪届」の提出
さらに、取引先や仕入先には廃業を告知し、必要に応じて契約解除の手続きを行うことも重要です。告知は、口頭だけでなく書面で通知しておくとトラブル防止になります。
これらの手続きを怠ると、加算税や延滞金などのペナルティが発生する可能性もあります。各手続きの期限や必要書類を事前に確認し、漏れなく進めましょう。
なお、本章では廃業時の主な手続きの流れについて解説しましたが、廃業を検討する前に、M&Aによる事業譲渡も選択肢として検討するのが望ましいです。事業に価値があれば、廃業ではなく事業譲渡によって経済的なメリットを得られる可能性があります。特に人材や取引先、技術やノウハウなど、目に見えない資産が企業価値となることもあります。
例えば、後継者不在で廃業を検討していた製造企業が、同業他社へのM&Aにより従業員の雇用を守りながら、オーナーも適切な対価を得られたケースがあります。廃業の決断をする前に、まずは会社・事業を残す道を探してみましょう。
廃業時に利用できる支援制度
公的機関が提供している廃業支援制度を活用することで、経営者の経済的・精神的負担を軽減できるケースがあります。特に中小企業や個人事業主向けの制度は多岐にわたるため、条件や手続きをよく確認しましょう。
中小企業庁「小規模企業共済制度」
小規模企業共済制度は、中小企業経営者や個人事業主が積立を行い、廃業時などに退職金のような形で共済金を受け取れる仕組みです。
毎月の掛金は所得控除の対象となるため、節税効果も見込めます。廃業後の生活資金に充てられるほか、新たに事業を始めるための資金にも活用しやすいメリットがあります。積立期間が長いほど受け取れる金額は増えるため、早めに加入して将来のリスクに備えるケースが一般的です。
【参考】独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済とは」
中小企業庁「事業承継・M&A補助金」
事業承継・M&A補助金は、後継者への承継やM&Aによる事業譲渡など、事業の引き継ぎを円滑に行うために活用できる補助金です。事業承継・M&A補助金の中には、事業承継やM&Aを検討する中で既存事業を廃止し、再チャレンジする際に活用できる「廃業・再チャレンジ」枠が設けられています。
本制度を活用すれば、廃業時にかかる費用の一部補助を受けつつ、新しいチャレンジに伴う費用負担の軽減が期待できます。なお、補助金の内容は年によって変更になる可能性があるため、詳細は公式ページをご確認ください。(本年度の実施については2025年4月現在未発表)
廃業についての相談窓口や専門家
公的機関や専門家は、廃業に関する多様な相談を受け付けています。自社の状況に合わせて適切な相談先を選び、計画的に廃業を進めましょう。ここでは、廃業についての相談ができる窓口や専門家について紹介します。
中小企業支援センター
中小企業支援センターは、全国各地に設置されている公的機関で、経営や廃業を含むあらゆる相談に応じています。中小企業庁が管轄しており、経営に関する基本的なアドバイスを無料または低コストで受けられる場合も多いため、費用面の負担を抑えつつ適切な指導を受けることができます。
廃業を検討する際には、手続きや各種手配について相談しやすい窓口として有効に活用できるでしょう。まずは近くの支援センターを調べ、電話やオンラインで予約するところから始めるのがおすすめです。
事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継・引継ぎ支援センターは、中小企業庁が各都道府県に設置している公的機関で、主に事業の後継者探しやM&Aなどをサポートしています。廃業の一つの選択肢として、事業を譲渡して経営者が退くという方式を活用するケースも少なくありません。
こうした状況で、引き継ぎをスムーズに行うためのマッチングやアドバイスを提供してくれるのが事業承継・引継ぎ支援センターです。無料で相談を受け付けている場合が多いので、まずは現状や課題を相談してみることから始めましょう。
よろず支援拠点
よろず支援拠点は中小企業庁の施策として展開されている相談拠点で、経営全般から廃業まで幅広い相談に対応しています。廃業を決断するにあたって、事業継続との比較検討や新事業へのシフトなど、方向性の見極めを行う際にも役立ちます。
多様な分野に精通した専門家が無料で相談に乗ってくれるため、廃業後の再起を視野に入れたアドバイスを得たい場合にも適しています。
商工会議所
商工会議所は、地域の中小企業や個人事業主を支援する団体として、廃業に関する相談やアドバイスも行っています。廃業手続きや資金繰り、負債整理など幅広いトピックを扱っており、地域に密着した情報を得られることが利点です。
必要に応じて、提携している士業や金融機関などの紹介を受けることも可能で、廃業全体のプランニングもサポートしてくれます。特に長年地域で事業を行ってきた場合は、商工会議所のネットワークを活かすと、廃業後のトラブル回避にも役立ちます。
M&A仲介会社
M&A仲介会社は、事業の売却や譲渡をサポートし、買い手と売り手をマッチングする役割を担います。廃業の手段としてM&Aを検討する場合は、経営者が直接交渉するよりもスムーズに条件調整を進めやすいのがメリットです。
また、企業価値の算定や契約書類の作成など、専門的なプロセスを仲介会社が支援してくれます。仲介手数料は発生しますが、譲渡による対価を得られる可能性もあるため、検討する価値は十分にあるでしょう。
士業
弁護士や税理士、司法書士などの士業は、廃業時の法的手続きや納税、負債整理など専門知識を必要とする場面で頼りになる存在です。特に法人に関しては解散登記や清算手続き、債権者対応などが複雑になる場合が多く、専門家抜きでは進行が滞るケースもあります。個人事業主であっても、税務上の処理や従業員の労務手続きなどで専門家のサポートがあると安心です。
依頼料はかかりますが、手続きの漏れやミスを減らせるメリットを考えれば、積極的に依頼を検討する価値があります。
金融機関
金融機関は、借入金の返済や負債整理に関する協議を行う際の重要な相談先です。事業規模や返済状況に応じて返済方法の再検討が必要になる場合もあり、早めに金融機関へ相談することで適切な解決策を見つけやすくなります。
特に長期の借り入れがある場合は、返済計画の見直しや制度融資を利用するなど、選択肢を増やせるかもしれません。大きな金融トラブルを避けるためにも、廃業時には一度相談してみると良いでしょう。
まとめ|早めの情報収集と専門家の活用で、廃業を成功へ
廃業を成功させるカギは、早めの情報収集と的確な支援の活用にあります。将来を見据えて、適切な方法を選択しましょう。
廃業はきちんと計画的に進めることで余計な負担やトラブルを軽減できます。法人と個人事業主では手続きが異なるため、それぞれの流れを把握し、必要に応じて専門家や公的機関に相談することが大切です。
また、廃業に関しては支援制度の利用によって、経営者の負担を軽減しながら新しい挑戦への一歩を踏み出しやすくなります。今後の方向性を検討する際には、本記事で紹介した内容を参考に、適切な廃業支援を取り入れて計画的に進めましょう。
ただし、廃業はあくまで最終手段として考え、M&A等による事業譲渡の可能性をまず検討することをおすすめします。事業継続に課題を抱えており、廃業を視野に入れている経営者や個人事業主の方がいれば、まずはM&A仲介会社等の専門家に相談し、廃業以外の選択肢がないかアドバイスを受けると良いでしょう。