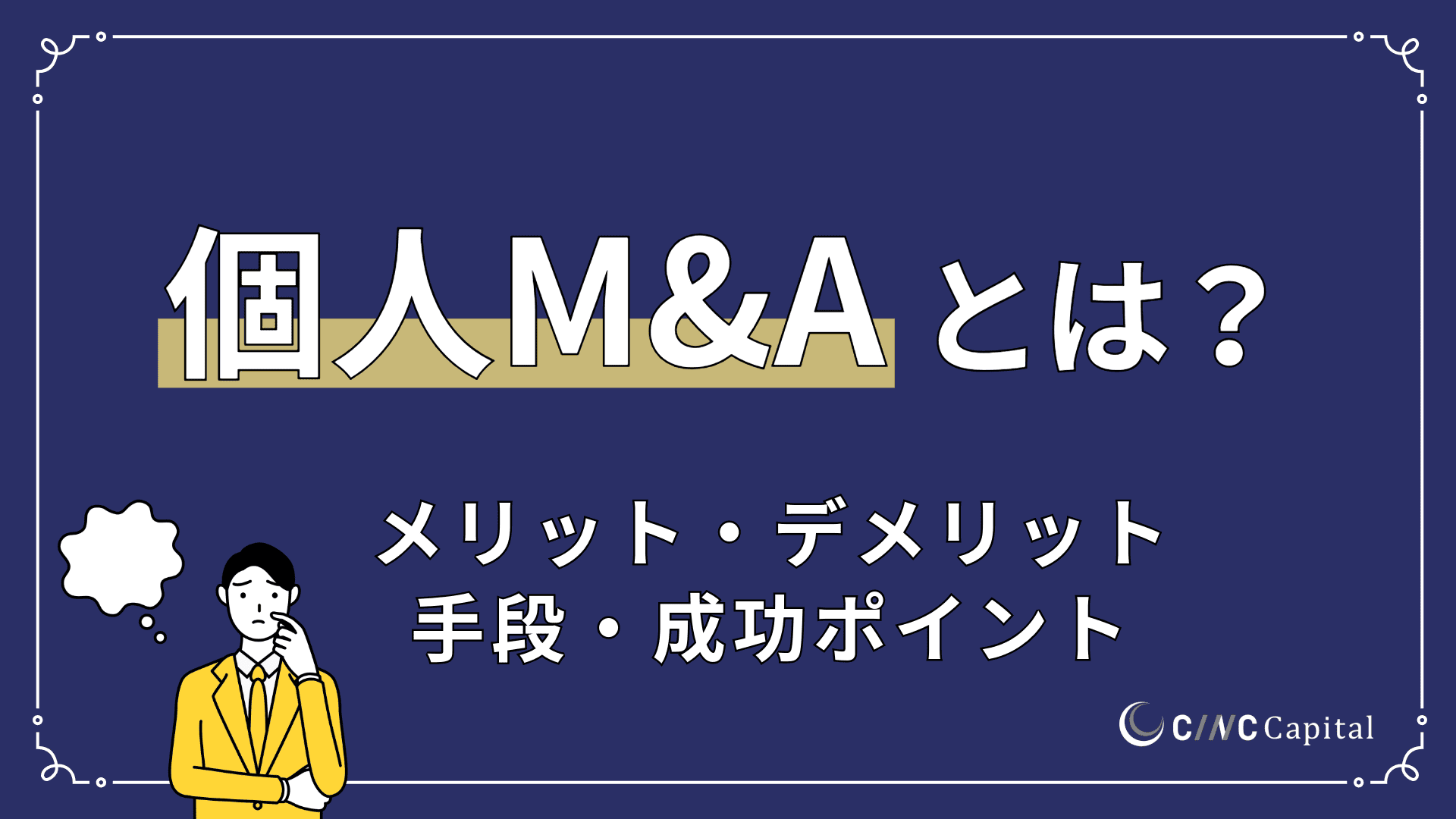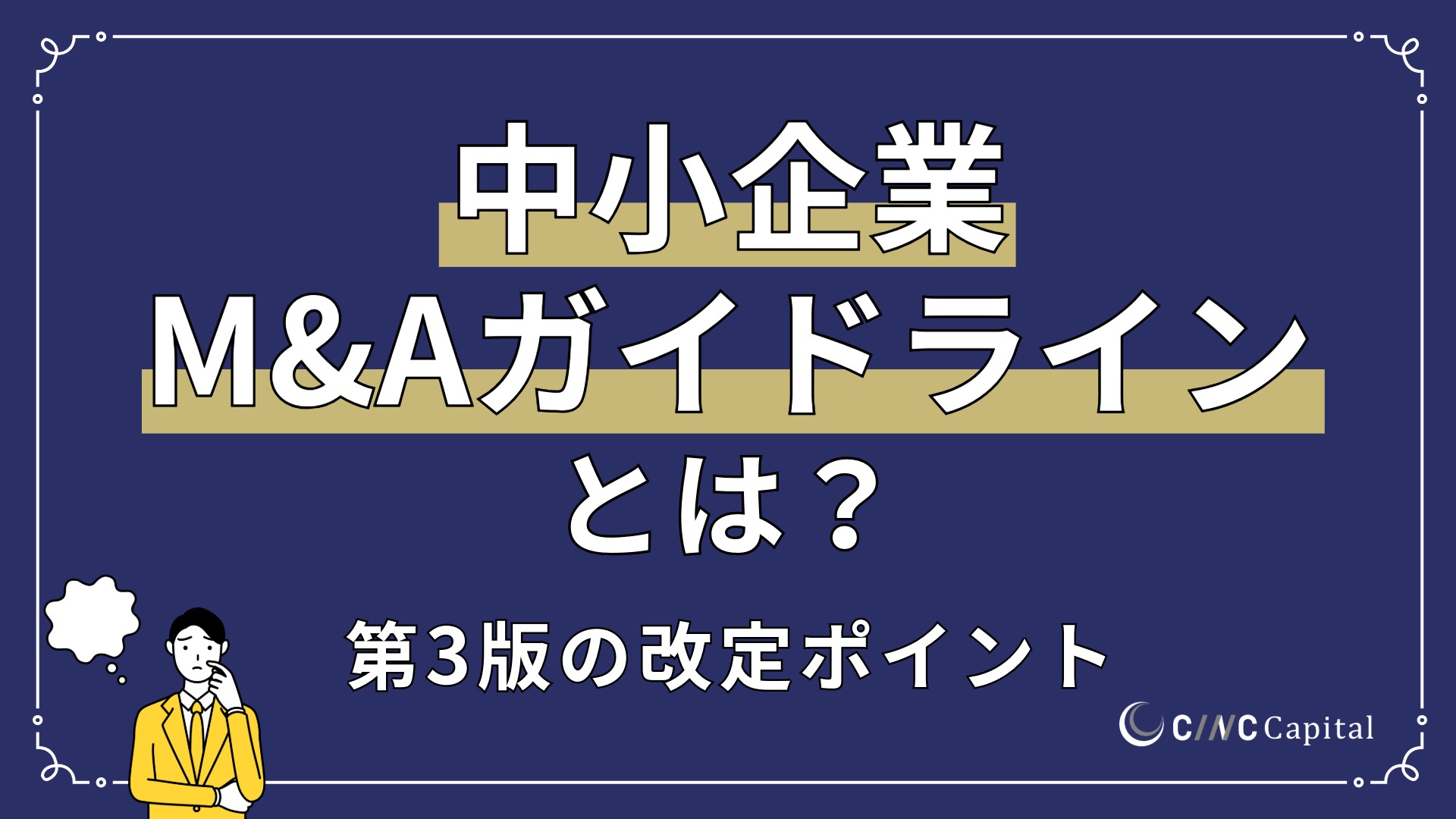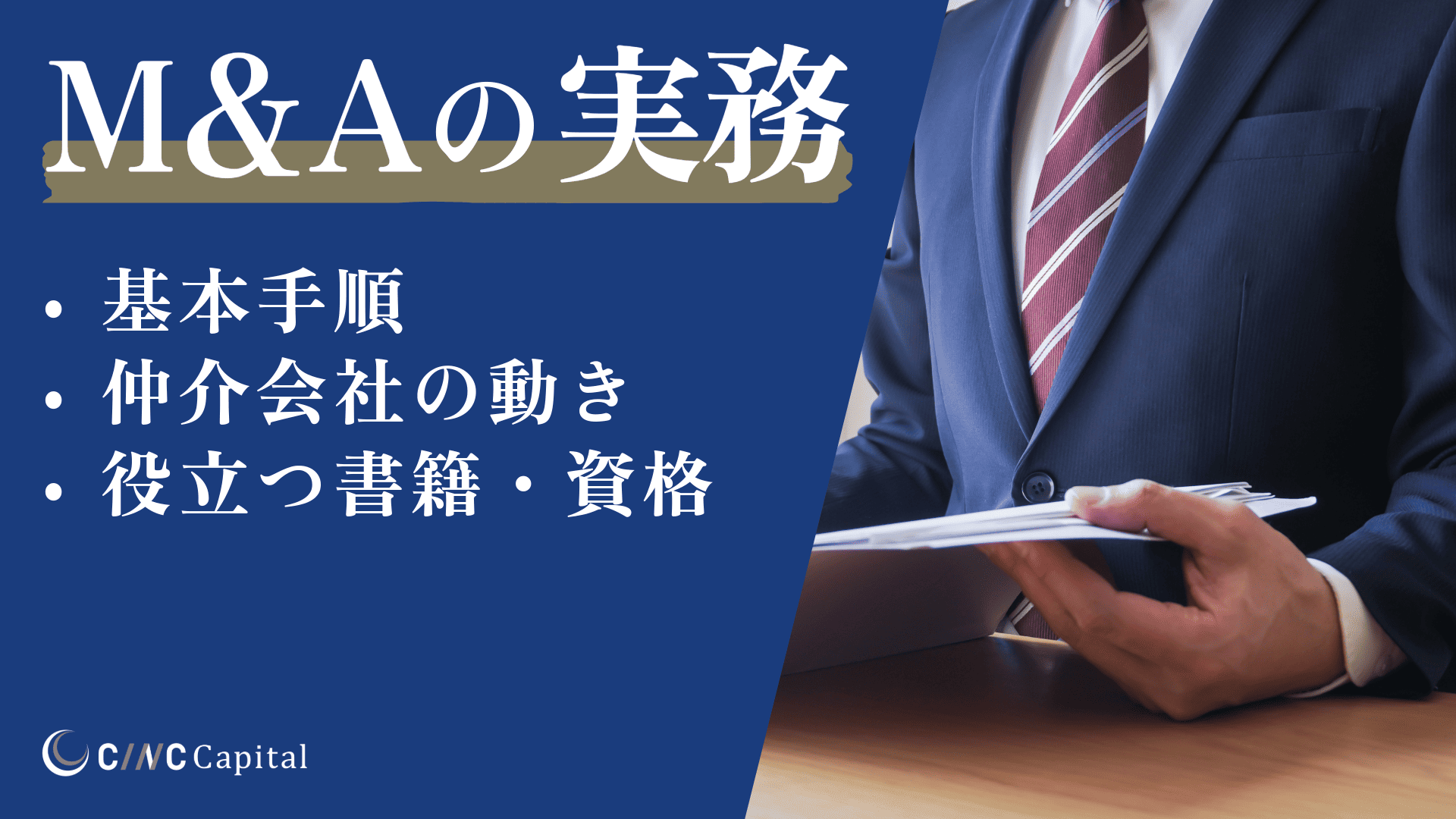CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
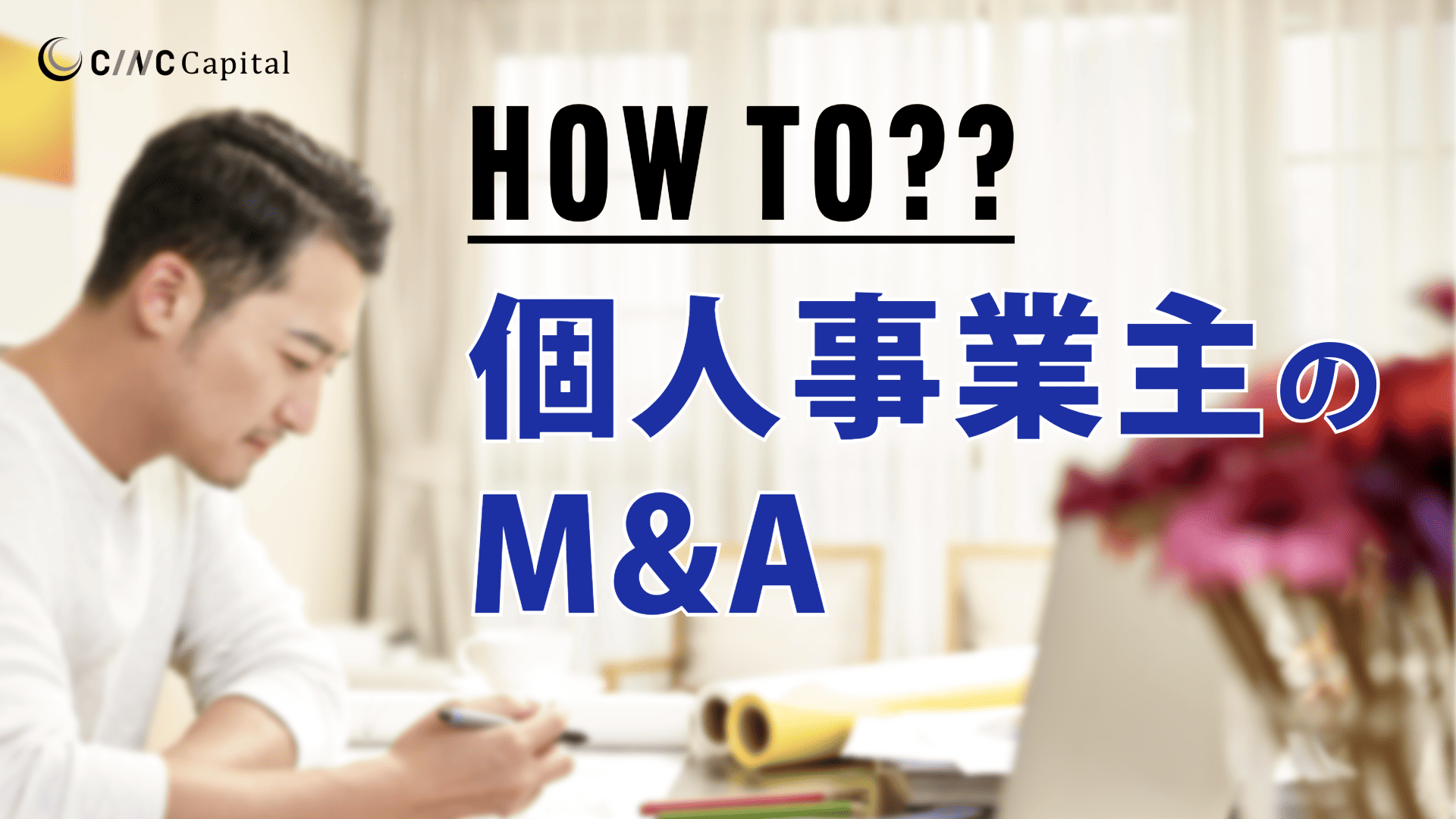
M&A / 基礎知識
- 最終更新日2025.06.26
個人事業主がM&Aするメリットは?動向や事業承継の流れを解説
事業を続けるうえで、「後継者がいない」「事業の将来が不安」「引退を考えているが、どうすればよいかわからない」と悩んでいませんか?個人事業主にとって、事業の引き継ぎは大きな問題です。
本記事では、個人事業のM&Aの仕組みや現状、売り手・買い手のメリット、成功のポイントについて詳しく解説します。さらに、M&Aをスムーズに進めるための具体的なステップも紹介します。
目次
個人事業のM&Aの現状
個人事業のM&Aは、近年増加傾向にあります。特に後継者不足に悩む個人事業主が多く、廃業ではなく事業譲渡という選択肢が広がっています。ここでは、個人事業のM&Aの基本と市場の動向について詳しく解説します。
個人事業のM&Aとは
個人事業のM&Aとは、個人事業主が自身の事業を第三者に譲渡することを指します。通常の企業間M&Aとは異なり、法人格がないため「事業譲渡」の形で取引が行われることが一般的です。
M&Aの手法には、事業譲渡、資産譲渡などがあり、取引の形態によって契約条件が異なります。適切な手法を選ぶことで、事業主はより良い条件で事業を譲渡することが可能です。
近年はM&A仲介会社やマッチングサイトの普及が進み、以前よりも個人事業の売買がしやすくなっています。規模の小さな事業であってもM&Aが活用される場面が増えており、事業の引き継ぎに悩む個人事業主にとっても選択肢の一つになっています。
個人事業のM&Aの現状や動向
個人事業のM&A市場は拡大しており、特に小規模事業の取引が活発になっています。中小企業庁のデータによると、2025年までに70歳を超える中小企業経営者は約245万人に達し、そのうち約半数が後継者未定の状況にあるとされています。この問題を解決するために、M&Aが積極的に活用されています。
実際、国内のM&A件数は年々増加しており、2022年には過去最高の4,380件を記録しました。特に小規模事業や個人事業のM&Aが増加しており、事業承継の手段として定着しつつあります。先述した通り、M&A仲介会社やマッチングサイトの活用が広がり、個人事業主でも売却先を見つけやすくなっていることが市場拡大の要因と考えられます。
【出典】独立行政法人 中小企業基盤整備機構「令和5年度 事業承継・引継ぎ支援事業の実績について」
【譲渡側】個人事業主がM&Aを実施するメリット
個人事業主がM&Aを活用すると、さまざまなメリットを得られます。特に、後継者問題の解決、個人保証の解消、譲渡益の確保といった点が大きな利点です。それぞれのメリットについて詳しく解説します。
後継者問題が解消する
後継者が不在の状態では、高齢化に伴い事業継続が難しくなり、廃業を余儀なくされる可能性があります。しかし、M&Aを活用すると、親族や従業員以外の第三者にも事業を譲ることが可能になります。これにより、長年築いてきた事業の存続が可能となり、取引先との取引や従業員の雇用も維持できます。特に、地域密着型の事業では、廃業による影響が大きいため、M&Aによって円滑な事業承継を実現することが重要になります。
個人保証の解消につながる
個人事業主が事業運営のために銀行から融資を受ける際、多くの場合、個人保証を求められます。個人保証があると、事業が赤字になった際に、事業主個人の資産で借金を返済しなければなりません。これにより、大きなリスクを抱えることになります。
M&Aを活用して事業を譲渡すると、個人保証の負担を軽減できる可能性があります。ただし、売却先が負債を引き継ぐかどうかによって保証の解除ができない場合もあるため、事前に金融機関との交渉が必要です。売却条件を決める際には、個人保証の解除を契約書に明記しておくことが重要です。
譲渡益を得ることができる
M&Aを通じて事業を譲渡すると、売却益を得られる可能性があります。売却によって得た資金は、引退後の生活資金や新たなビジネスの資金として活用することが可能です。特に、収益性の高い事業や安定した顧客基盤を持つ事業は、高値で売却できるケースもあります。
また、売却時に適切な税務対策を講じれば、手元に残る資金を最大化できます。M&A仲介会社や税理士と相談しながら、適切なスキームを選択することが重要です。譲渡益を計画的に活用すれば、事業売却後の生活も安定しやすくなります。
【譲受側】M&Aによって個人事業を譲り受けるメリット
M&Aは売り手にとってだけでなく、買い手にとっても大きなメリットをもたらします。特に、既存事業とのシナジー効果、低リスクでの事業スタート、許認可の引き継ぎといった点が魅力です。ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
既存事業とのシナジー効果が期待できる
M&Aを通じて事業を引き継ぐと、既存事業とのシナジー効果が期待できます。例えば、同業種の事業を買収すれば、顧客基盤の拡大や仕入れコストの削減が可能になります。異業種であっても、技術やノウハウを活用することで、新たな事業展開につなげられるでしょう。
具体例として、飲食店を経営している事業主が、別の店舗をM&Aで取得するケースがあります。この場合、食材の仕入れを一括で行うことでコストを削減できる可能性があります。
こうした相乗効果を生み出すことで、事業の成長スピードを加速させることが可能です。ゼロから事業を立ち上げるよりも、既存の資産や顧客基盤を活用することで、効率的な経営が実現できます。
低労力・低リスクで事業をスタートできる
新規事業をゼロから立ち上げるには、多くの時間と労力が必要になります。顧客の獲得や認知度の向上には、営業活動が欠かせません。しかし、M&Aを活用すると、すでに運営されている事業を引き継げるため、短期間で事業をスタートできます。
営業実績のある事業を買収すれば、確立されたビジネスモデルや取引先をそのまま活用できるため、売上の安定につながります。また、従業員を引き継ぐことで、人材採用や育成の手間も省けます。
許認可を引き継げる
M&Aを活用することで、事業に必要な許認可を引き継げる場合があります。ただし、業種によっては譲渡後に新たな取得手続きが必要なケースもあるため、事前に行政機関や専門家に確認することが重要です。特に、建設業や医療・福祉関連の事業では、M&A成立後に新規許可申請が求められることがあります。
例えば、飲食業や建設業、介護事業などは、営業許可の取得に時間と手間がかかります。新規で許認可を取得する場合、審査期間が長引いたり、厳しい要件を満たす必要があったりするため、スムーズな事業開始が難しいケースがあります。しかし、M&Aを活用して既存の事業を買収すれば、許認可や取引先をそのまま引き継ぐことができ、速やかに事業を運営できます。
特に、規制が厳しい業種では、許認可の取得が難しいケースも多いです。M&Aを活用すると、これらのハードルをクリアし、スムーズに市場へ参入できます。事前に許認可の更新時期や条件を確認し、確実に引き継げるよう準備を進めることが大切です。

個人事業主がM&Aを成功させるうえでの注意点
M&Aを成功させるためには、適切な準備と進め方が求められます。特に、仲介会社の活用、税務の理解、マッチング支援サイトの利用といった点を意識することで、スムーズな取引が可能になります。それぞれのポイントについて詳しく説明します。
M&A仲介会社の支援を受ける
M&Aの経験がない個人事業主にとって、仲介会社の支援を受けることは重要なポイントになります。M&Aには、事業の価値評価、契約交渉、法的手続きなど、多くの専門知識が必要になります。これらを独力で進めるのは難しく、適正な価格での売却ができなかったり、契約後のトラブルにつながったりする恐れがあります。
M&A仲介会社を利用すると、事業価値の算定や適切な買い手の選定、契約交渉の仲介など、M&Aの全プロセスにおいて専門的な支援を受けることが可能です。特に、買い手の信用調査や条件交渉を行うことで、リスクを最小限に抑えながらスムーズな取引を進められます。
特に、スモールM&Aに特化した仲介会社であれば、小規模な事業譲渡の実績が豊富なため、円滑な進行が期待できます。費用はかかりますが、専門家のサポートを受けることで、適切な条件でのM&Aが実現しやすくなります。
仲介会社を選ぶ際には、手数料体系や実績を確認することが大切です。成功報酬型の仲介会社であれば、売却が成立した場合にのみ費用が発生するため、売り手にとってリスクを抑えやすくなります。信頼できる仲介会社を選ぶことが、M&Aを成功させるための重要なポイントになります。
税金について理解したうえで実施する
M&Aで得た譲渡益には税金がかかるため、事前に対策を講じることが必要です。個人事業主が事業を売却した場合、基本的には「譲渡所得」として課税されます。これを適切に処理しないと、想定以上の税負担が発生する可能性があります。
事業譲渡による所得は、譲渡所得税の対象になり、売却価格から取得費や譲渡にかかった経費を差し引いた金額に対して課税されます。譲渡益が大きい場合、税負担を軽減するための方法を検討する必要があります。例えば、分割譲渡を行うことで、特定の年度に大きな税負担が発生するのを防ぐことが可能です。
税務の取り扱いについては、M&Aに詳しい税理士に相談するのが有効です。適切なスキームを選択することで、譲渡益を最大限手元に残しながらM&Aを進めることができます。税金に関する知識を深めることで、より有利な条件でM&Aを実施できる可能性が高まります。
M&Aマッチングサイトを活用する
近年、M&Aのマッチングサイトが増えており、個人事業主でも簡単に売却先を見つけられるようになっています。このような支援サイトを活用することで、広範な買い手候補にアプローチできるため、より良い条件でのM&Aが期待できます。
マッチングサイトでは、事業の概要や希望条件を掲載し、関心を持った買い手との交渉を進めることが可能です。ただし、マッチングサイトを利用する際には、慎重な対応が必要になります。事業の価値を適正に評価し、適切な価格設定を行わなければ、買い手が見つかりにくくなります。また、交渉の際には秘密保持契約(NDA)を締結し、事業の重要情報が不用意に漏れないようにすることも大切です。
M&Aマッチングサイトは、広範な買い手候補にアプローチできる手軽な手段です。しかし、買い手の信用リスクや、条件交渉の難航といった課題も伴います。特に、価格設定や譲渡条件を適切に設定しないと、不利な条件で売却してしまう可能性があるため、サイトの利用と並行して専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。
個人事業主がM&Aをする流れ
個人事業のM&Aを進めるには、適切な手順を踏むことが大切です。流れを理解し、計画的に進めることで、スムーズな取引が実現しやすくなります。ここでは、一般的なM&Aのステップについて説明します。
M&A仲介会社に相談する
M&Aを成功させるためには、まず仲介会社に相談することが重要です。M&Aには、事業の価値評価、買い手探し、契約交渉など、多くの工程が含まれます。専門知識が求められるため、仲介会社の支援を受けると安心して進められるでしょう。
仲介会社を利用すると、適切な買い手を探しやすくなります。市場動向や売却価格の目安についても情報が得られるため、より良い条件で交渉を進めることが可能です。信頼できる仲介会社を選ぶことが、M&Aの成功につながります。
買い手事業主・企業を探す
次に、事業を引き継ぐ買い手を探します。M&Aの相手選びは、売却後の事業継続に影響を与えるため、慎重に進める必要があります。
買い手を見つける方法として、M&A仲介会社のネットワークを活用する方法や、M&Aマッチングサイトを利用する方法があります。適切な買い手が見つかったら、秘密保持契約を締結します。事業内容を開示し、双方の条件を調整しながら交渉を進めることが大切です。
基本合意書を締結する
買い手が決まったら、基本合意書を締結します。この合意書には、M&Aの基本条件や交渉の進め方が記載されます。法的拘束力を持たないケースが一般的ですが、独占交渉権や秘密保持の内容が含まれることが多いため、慎重に作成する必要があります。
基本合意書には、譲渡価格の大枠や譲渡の範囲、スケジュールなどが盛り込まれます。売り手と買い手の双方が合意した後、本格的な調査や契約手続きへと進みます。
デューデリジェンスを実施する
基本合意書を締結した後、買い手によるデューデリジェンスが実施されます。デューデリジェンスとは、M&Aの対象となる事業の詳細を調査し、リスクを評価する作業です。
主に、財務・法務・労務・税務の観点から事業の状況を精査します。例えば、財務デューデリジェンスでは、過去の決算書やキャッシュフローの状況を精査し、隠れた負債の有無を確認するのです。
具体的には、過去3〜5年分の財務諸表を分析し、売上の安定性や負債比率を評価します。また、売掛金・買掛金の回収状況や固定資産の適正評価を行い、実際の財務状況を正確に把握します。
デューデリジェンスの結果によっては、買い手が契約内容の修正を求めることもあります。売り手は、事前に資料を整理し、スムーズな調査が進むよう準備しておくことが求められます。
最終契約書を締結する
デューデリジェンスが完了し、買い手が最終的な条件に合意したら、最終契約書を締結します。この契約書には、譲渡価格、支払い条件、事業譲渡の範囲、引き継ぎ後の対応などが具体的に明記されます。
契約締結時には、M&A仲介会社や弁護士のサポートを受けながら、内容を慎重に確認することが重要です。最終契約を締結した後、M&Aの実行に向けた準備が進められます。契約内容に基づいて、譲渡手続きを適切に進めることが求められます。
クロージングを実施する
最終契約書の締結後、クロージング(Closing)を実施します。クロージングとは、契約に基づいた実際の譲渡手続きを完了させる段階を指します。
クロージングでは、譲渡対価の支払い、事業の引き渡し、従業員の継承、許認可の変更手続きなどが行われます。契約内容に沿って、必要な手続きを進めることが求められます。
売り手は、事業の引き渡しをスムーズに行い、買い手側が運営を開始できるようサポートすることが望まれます。業務の引き継ぎ期間を設けることで、新しい経営者が問題なく事業を運営できるようになるでしょう。
まとめ|個人事業のM&Aもメリットが豊富。まずはM&A仲介会社に相談しよう
個人事業のM&Aには、売り手と買い手の双方に多くのメリットがあります。売り手は、後継者問題の解決や個人保証の解消に加え、譲渡益を得ることが可能です。一方、買い手は既存の事業基盤を活用できるため、低リスクで事業をスタートできます。
M&Aをスムーズに進めるためには、仲介会社のサポートを受けることが重要です。適切な相手探しや契約交渉を進めるうえで、専門家の支援を活用することで、成功率が高まります。税務対策や契約の細部についても、事前に準備を整えておくことが求められます。
個人事業のM&Aは、今後さらに一般的になると予想されます。売却を検討している場合は、早めに準備を進め、専門家の意見を参考にしながら計画的に進めることが成功の鍵です。まずはM&A仲介会社に相談し、自分に合った進め方を検討しましょう。