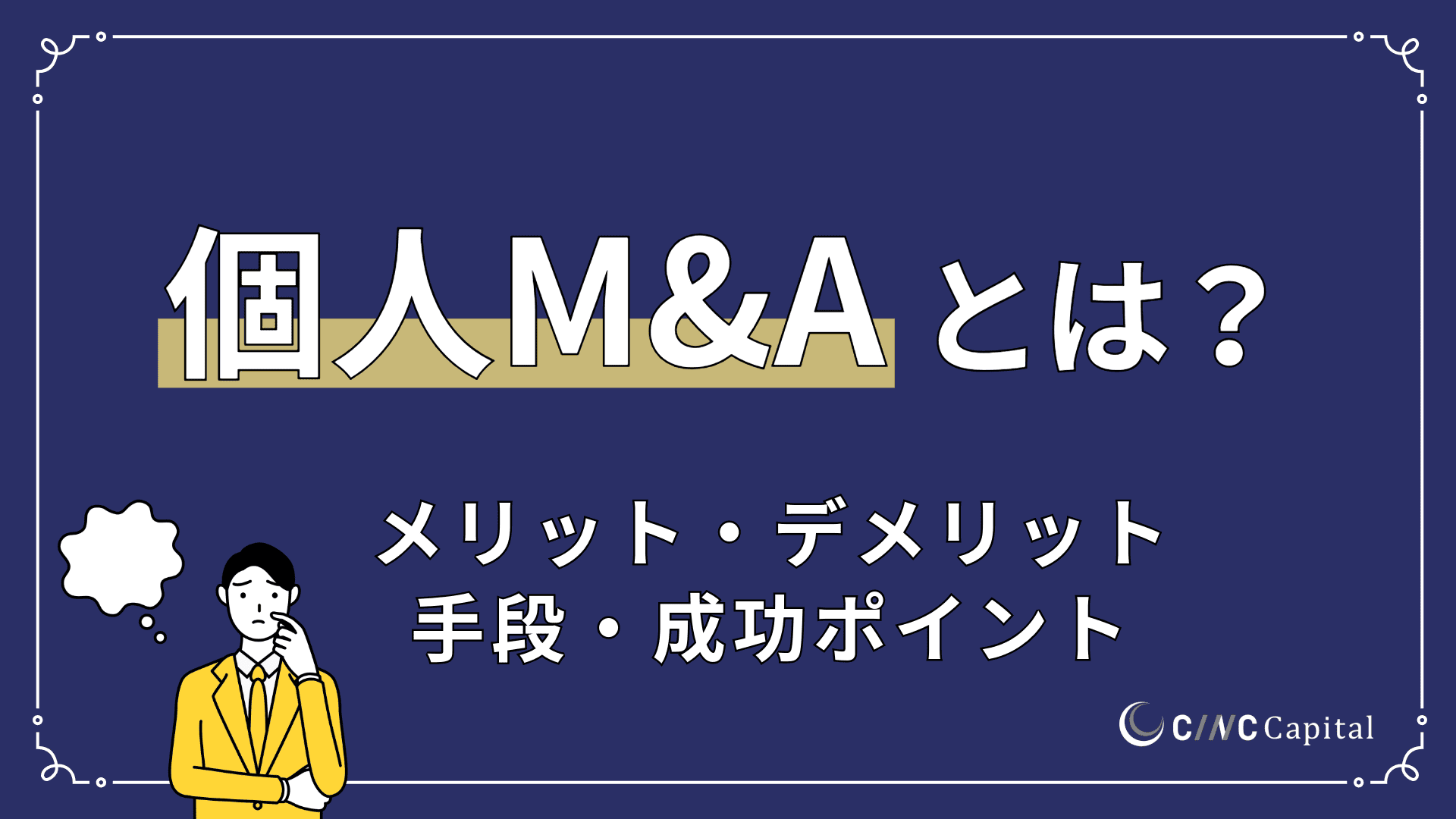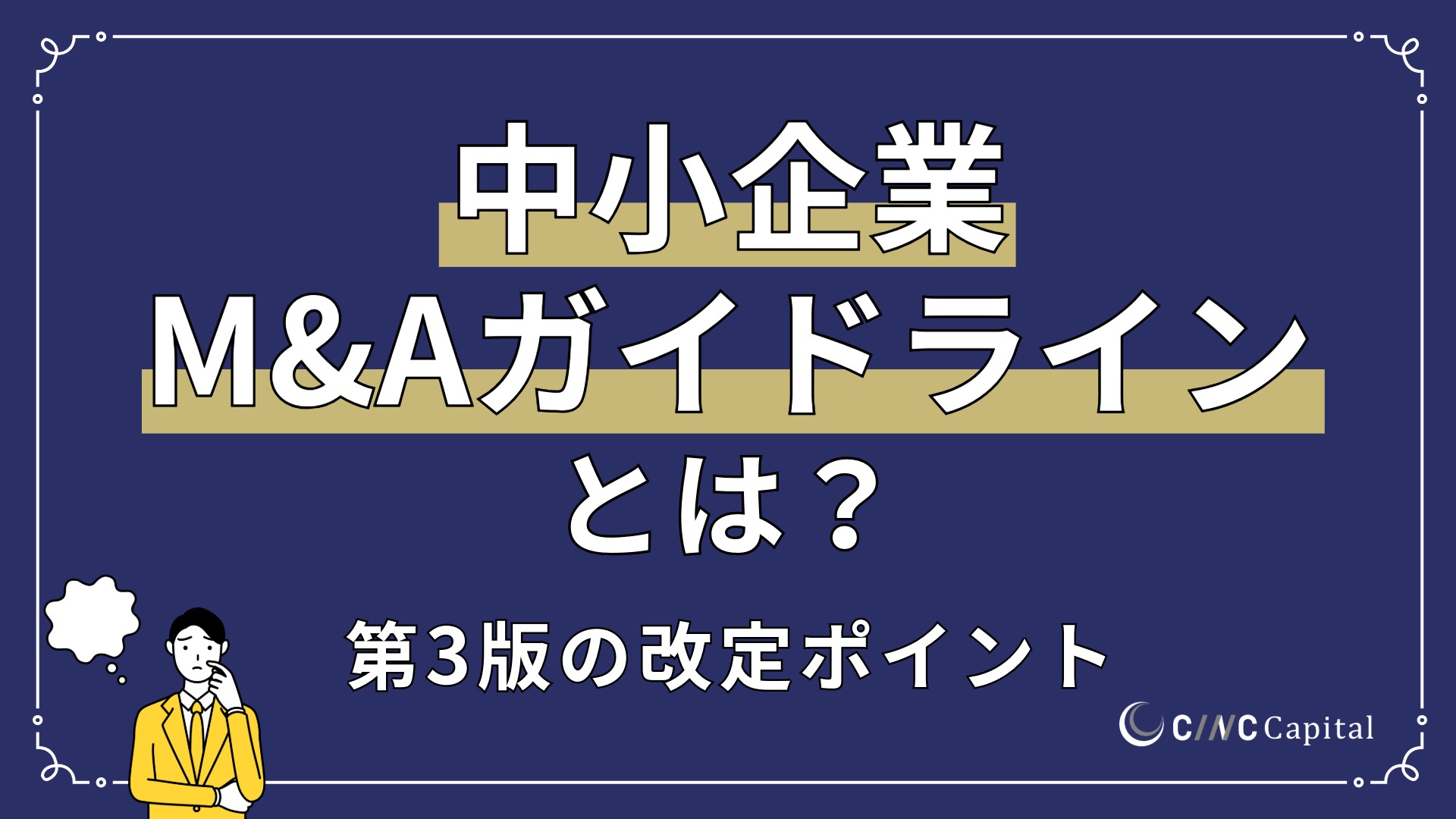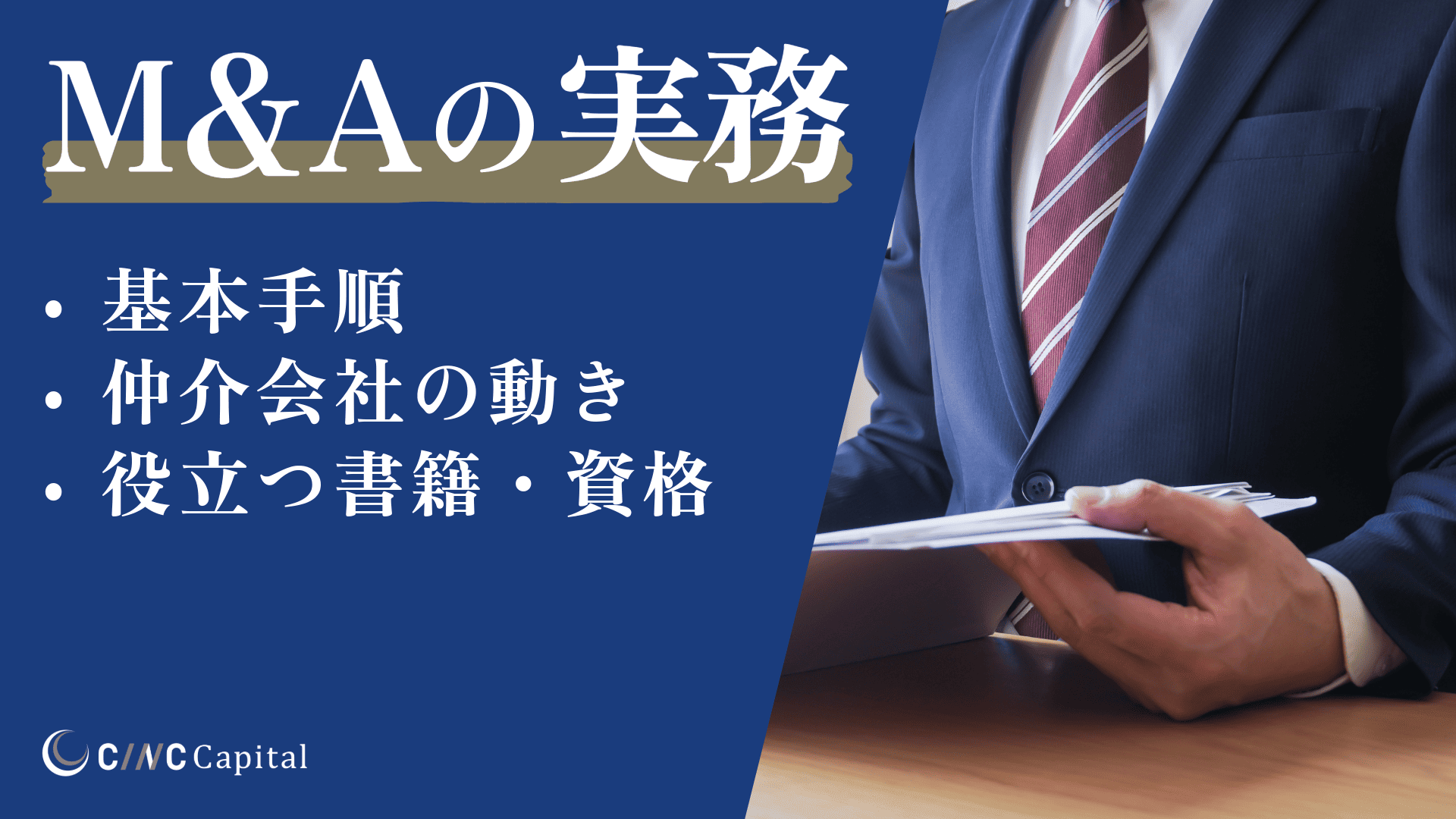CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
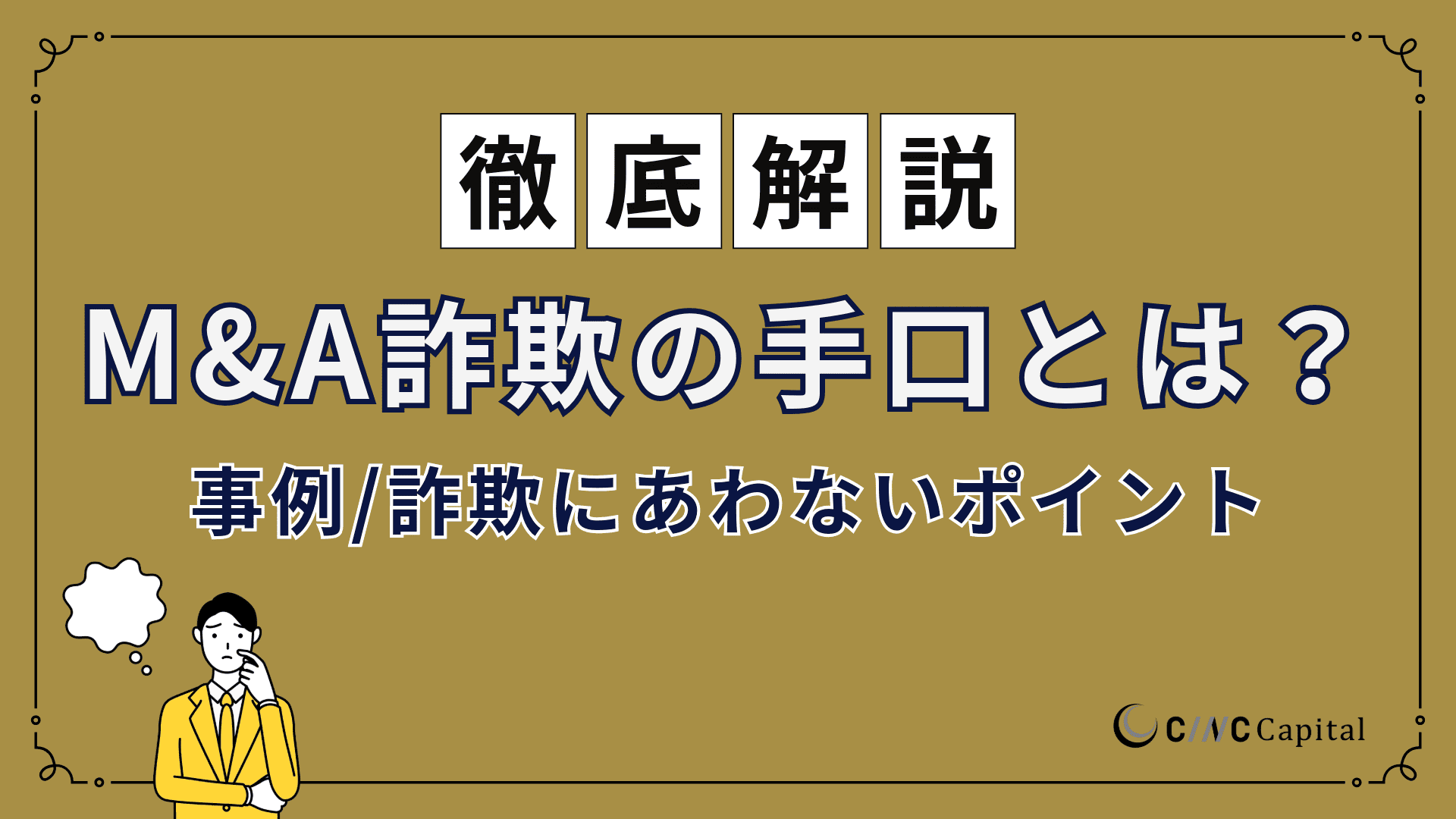
M&A / 基礎知識
- 最終更新日2025.07.22
M&A詐欺の手口とは?事例や詐欺に合わないためのポイントを解説
M&Aを検討しているものの、「信頼できる相手かどうか不安」「悪質な買い手に騙されたらどうしよう」と感じていませんか?中小企業のM&Aでは、情報の非対称性や後継者不足につけ込んだ詐欺被害が増加しています。特に準備不足のまま交渉に進むと、深刻な経済的損失につながるリスクがあるので注意が必要です。
本記事では、実際に発生した詐欺事例をもとに、代表的な手口と中小企業が狙われやすい背景を解説します。
目次
【事例】M&A詐欺の代表的な手口とは?
M&Aを悪用した詐欺は、買収という形をとりながら実質的には資産を奪う目的で行われる悪質な行為です。特に中小企業では、契約や相手先の審査が不十分なまま進むことが多く、被害が後を絶ちません。
本章では、近年実際に発生した詐欺事例をもとに、代表的な手口を3つ紹介します。
買収後の資金流用と経営破綻の誘発
M&A詐欺の典型的な手口は、買収直後に企業の資金を親会社に送金させ、経営を破綻に追い込む方法です。
近年、報道された事例では、ある投資会社が「再生支援」を掲げて中小企業に買収を持ちかけ、経営権を取得した後に企業の預金口座を掌握し、グループ会社口座へ資金を一括送金させたケースがありました。買収先企業は必要な運転資金を失い、従業員への給与支払いも困難となり、最終的に倒産に追い込まれました。
都内の老舗店舗なども被害に遭い、買収からわずか1年で閉店に至ったケースも報告されています。資金の使途を問うと、買い手企業の代表者は雲隠れし、連絡が取れなくなったと報じられています。
このように、買収を装いながら資金を吸い上げて企業を破綻させる、悪質なM&A詐欺の実態を象徴する事例もあるのです。
買収後の個人保証解除の未履行と資産差し押さえ
経営者保証の解除は金融機関の同意が必要であり、単に契約書に記載するだけでは効力が生じません。実際の事例では、買収後に新経営者が金融機関との交渉を怠り、旧経営者の保証が残ったまま会社が倒産したケースがあります。
ある地方の中小企業では、買収後に会社が経営不振に陥り、前経営者個人に数億円の債務が残されたと報告されています。こうしたケースでは、契約書に保証解除の期限や履行条件、未履行の場合の違約金などを明確に規定していなかったことが原因となっています。
買収後の経営者による不正行為と企業倒産
M&A詐欺のなかには、買収後に新経営者が会社を私物化し、不正行為を重ねて企業を破綻させる手口もあります。
実際の事例では、新経営者が会社資産を売却したり、高額な役員報酬を自身に支払わせたりするケースが報告されています。また、親会社へのコンサルティング費用や管理費の名目で資金を抜き取る手法もあります。
これらは一見すると合法的に見えるものの、実態は資金の不正流用です。企業の財務は短期間で悪化し、取引先への支払いも困難になります。最終的には倒産や破産に至り、従業員や取引先にも甚大な損害が及びます。このような詐欺的行為を防ぐためには、買収後も一定期間は経営監視体制を維持することが必要です。
M&A詐欺で中小企業が狙われやすい理由
中小企業がM&A詐欺の標的になりやすいのは、後継者不在や資金繰りの悪化といった切迫した事情を抱えていることが多いためです。
経営者は少しでも好条件の相手に出会いたいと願い、相手の背景や資金力を十分に確認しないまま契約を進めてしまう傾向があります。さらに、M&Aに関する専門知識が乏しく、仲介業者や買い手の言葉を鵜呑みにしてしまうケースも少なくありません。
実際に被害が報告された事例では、「雇用を守る」「再建支援する」といった甘言を信じて企業を譲渡した結果、資金を抜き取られ倒産に追い込まれたケースが多数あります。こうした背景から、中小企業は詐欺グループにとって格好のターゲットとなっているのです。
M&A詐欺を未然に避けるためのポイント
M&A詐欺の被害を防ぐためには、交渉前から契約締結、買収後までのすべてのプロセスでリスクに目を配る必要があります。特に中小企業では、情報の非対称性や判断の甘さが被害の温床になりやすいため、具体的な対策を実践することが重要です。
本章では、被害を避けるために押さえておきたい5つのポイントを紹介します。
信頼できる専門家のサポートを受ける
M&A詐欺を防ぐうえで、専門家による第三者のチェックは極めて有効です。経営者が契約内容や相手企業の信用性を一人で判断するのは難しく、知識不足がトラブルの原因になることもあります。
たとえば、被害に遭った中小企業では、事前に弁護士や会計士の助言を得ていれば防げた可能性が高いと報じられています。事業承継・引継ぎ支援センターや商工会議所など、信頼できる公的機関の相談窓口を活用すれば、費用負担を抑えて専門家の支援を得られます。
リスクを回避するためには、早い段階から外部の知見を取り入れることが欠かせません。
M&A仲介業者やアドバイザーの実績と評判を確認する
詐欺的なM&Aは、仲介業者のずさんな審査や誘導によって引き起こされることがあります。中小企業の経営者が仲介業者に全幅の信頼を置いてしまうと、買い手の問題点を見落とす可能性が高まります。実際に、ルシアン事件では仲介会社が買い手を「信頼できる」と説明し、経営者がそれを信じて譲渡を進めた結果、倒産に至りました。
このような事態を避けるには、仲介業者の過去の実績、顧客の評判、報酬体系などを事前に確認する必要があります。評判の確認を怠らず、透明性の高い業者を選ぶことで、詐欺に巻き込まれるリスクを軽減できるでしょう。
契約内容や支払い条件を詳細にチェックする
契約書に不備や曖昧な点がある場合、買収後に深刻なトラブルが発生するリスクが高くなります。特に、譲渡代金の分割払いや、経営者保証の解除条項には注意が必要です。過去の事例では、「後日支払う」と記された退職慰労金や残額が実際には支払われず、被害者が泣き寝入りしたケースもあります。
こうした事態を避けるには、支払い条件や保証解除の履行期限、違約時の対応などを明文化し、契約書に明記しておくことが必要です。契約内容は専門家に確認してもらい、納得できるまで交渉を重ねることが、詐欺防止に直結します。
デューデリジェンスで詐欺の兆候を見極める
M&Aにおいては通常、売り手企業に対して「デューデリジェンス(DD)」が行われますが、中小企業の事業承継では、買い手に対する調査(逆デューデリジェンス)も重要です。
売り手は買い手の財務状況や事業実態、過去の買収実績などを十分に確認すべきです。しかし、中小企業では買い手調査が省略されたり、表面的な情報のみで判断したりするケースが後を絶ちません。
報道された詐欺事例では、買収元の親会社の財務状況が不明確なまま複数の企業が買収され、後に資金流出などの被害につながったことがありました。
DDでは、決算書や登記情報に加え、買い手の過去の訴訟歴や業界での評判も確認する必要があります。事前に買い手のリスクを洗い出すことで、詐欺の兆候に早く気付くことができます。
急かされる取引や不審な条件には応じない
詐欺の多くは、冷静な判断を妨げるために契約を急がせるという特徴があります。「今すぐ契約しなければ別の買い手に渡す」といった言葉で、相手に判断の余地を与えない手法が使われます。
こうした強引な進行に対し、不安を感じながらも契約を進めてしまう被害者が少なくありません。M&Aは企業の将来を左右する重要な判断であり、十分な時間をかけて検討すべきです。もし相手が回答を急かす場合や条件を明らかにしない場合は、即座に契約を見送ることが安全です。
まとめ|少しでも不安があれば立ち止まって相談を
中小企業がM&Aを通じて詐欺に巻き込まれるリスクは決して低くありません。後継者不在や情報不足に付け込む手口は巧妙化しており、慎重な対応が求められます。被害を防ぐには、信頼できる専門家の関与、契約内容の精査、買い手の実態把握が不可欠です。
中小企業庁の調査によれば、事業承継関連のトラブルの相談件数は年々増加傾向にあり、その中には悪質なM&A関連の相談も含まれています。
また、法務省の統計では企業買収に関連した詐欺的行為の摘発事例も報告されています。ただし、多くの被害が表面化していない可能性もあり、実態はさらに深刻と考えられます。冷静に判断し、少しでも不審な点があれば立ち止まることが大切です。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。