CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
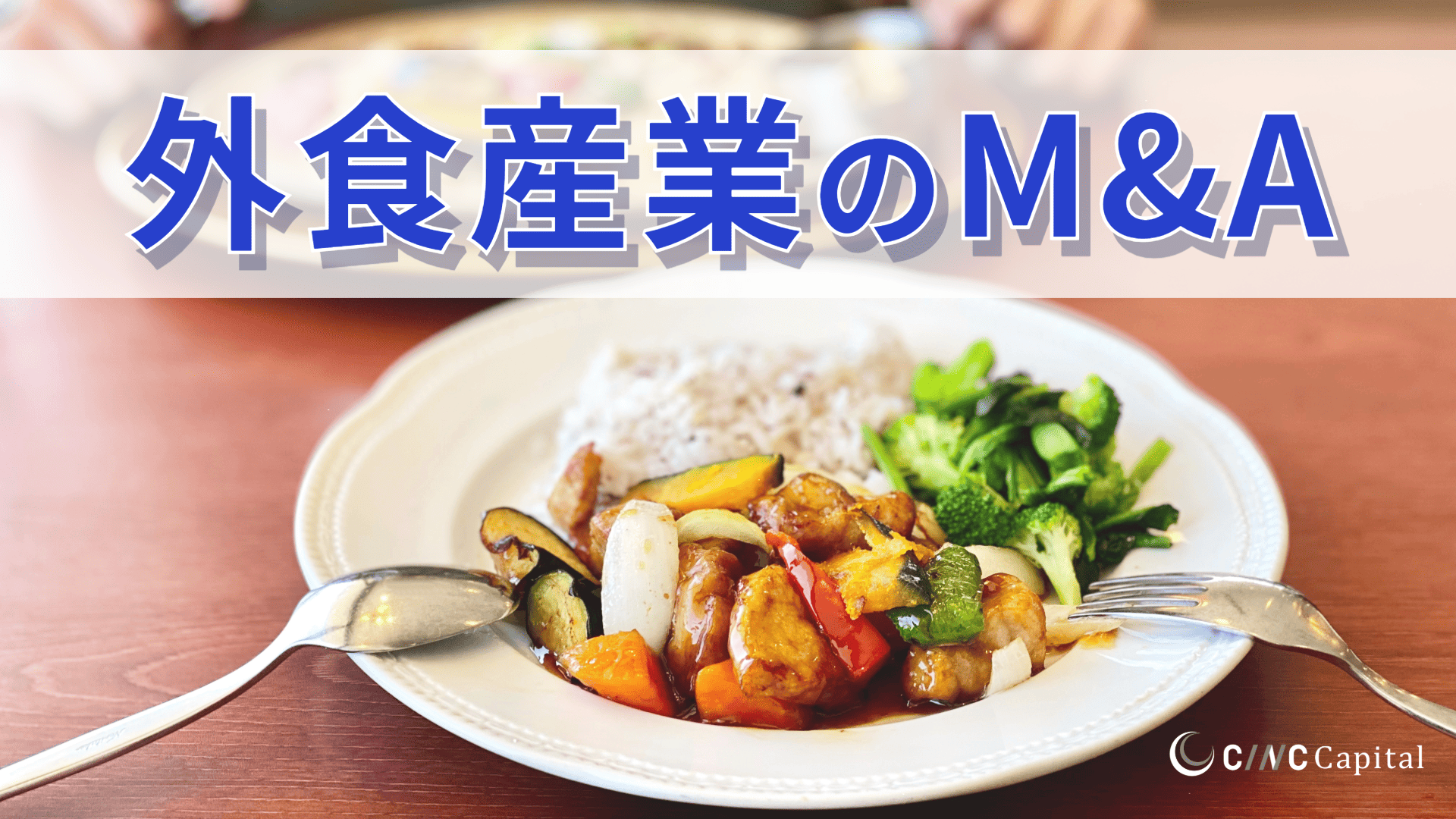
業種
- 最終更新日2025.06.26
外食産業業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
近年、外食産業は消費者ニーズの変化や人手不足、原材料費の高騰など、多くの課題に直面しています。そのなかで、M&A(企業の合併・買収)が業界の成長戦略として注目されています。
この記事では、外食産業で規模拡大やブランド力強化、新規事業展開の手段として活用されるM&Aの最新動向や成功のポイントを解説します。
目次
外食産業業界の市場動向
株式会社富士経済の推計によると、2024年における外食産業の国内市場は34兆3,916億円と見込まれています。コロナ前の2019年以前の水準にはまだ届かないものの、回復傾向が続いている状況です。
また、日本フードサービス協会の調べによると、2024年の外食産業はコロナ禍の行動規制撤廃を受けて回復傾向が続き、売上は2023年と比較して108.4%まで成長しました。近年の訪日客の増加も、ディナーレストランなどの売上を押し上げる要因となっています。
その一方で、外食産業では原材料費の高騰により値上げが進み、客単価の上昇が続いています。こうした影響から客数が伸び悩む企業や、消費者の節約志向に応じて価格据え置きや割引キャンペーンを行う企業も少なくありません。
【出典】株式会社富士経済「2024年見込 イートインやインバウンド需要を取り込む外食産業市場を調査」
【出典】日本フードサービス協会「令和6年(2024年)外食産業市場動向調査」
外食産業業界が抱える課題
外食産業はコロナ禍からの回復が進む一方で、多くの経営者が依然として厳しい状況に直面しています。ここでは、外食産業が抱える主な課題について解説します。
人手不足の深刻化
外食産業では、慢性的な人手不足が続いており、多くの飲食店が必要な労働力を確保できずに苦戦しています。なかでも少子高齢化による労働人口の減少や、過酷な労働環境に対する敬遠傾向が人手不足の大きな要因です。従業員不足が続くと、業務の負担が増して離職率が高まり、さらに新規採用が難しくなる悪循環に陥るリスクがあります。
仕入れ価格・物流コストの上昇
世界的な物価高騰の影響で、外食産業では食材の仕入れ価格が高騰し、光熱費や物流コストの増加が経営を圧迫しています。価格転嫁が難しい業界であるため、利益率が低下しやすく、経営の安定化が課題となっています。コスト削減のための工夫が求められていますが、品質を維持しながら原価を抑えることは容易ではありません。
異業種との競争激化
外食産業では、コンビニやスーパーの惣菜のほか、デリバリーサービスの充実化など、異業種との競争も激化しています。このほかにも、コンビニのイートインスペースの拡充や、デパ地下の高品質な惣菜が人気を集めることで、外食の需要が減少する傾向にあります。
外食産業業界のM&A最新動向(2025年)
近年、外食産業では人手不足やコスト高騰といった課題を背景に、M&Aに取り組む企業が見られるようになっています。ここでは、外食産業における最新のM&A動向について解説します。
業界再編を目的としたM&Aの動き
外食産業では、大手チェーンが中小規模の飲食店を買収し、業界再編を進める動きも散見されます。人手不足の深刻化や原材料費の高騰が経営を圧迫するなか、経営基盤の強化やスケールメリットを活かすためのM&Aが検討されるケースがあります。
他業種からの参入と飲食事業の多角化
M&Aによって異業種企業が飲食事業に参入するケースも見受けられます。例えば、小売業やIT業の企業が外食チェーンを買収し、デジタル技術を活用した効率的な運営を実現するケースもあります。データ分析を活用したメニュー開発や効率的な在庫管理により、収益性を向上させる戦略が見られます。
海外資本による日本市場への関心
アジア圏の投資ファンドや外食企業が日本の人気飲食チェーンを買収し、海外展開を視野に入れた経営戦略を進める動きもあります。近年、日本の高品質な飲食ブランドは海外市場でも高い評価を受けており、M&Aを通じて国際展開を模索する事例も見られます。。
外食産業がM&Aで売却するメリット
外食業界では、競争の激化や人手不足、原材料費の高騰などの課題が深刻化しています。ここでは、外食産業ならではのM&Aのメリットについて解説します。
ブランド力の活用
売り手企業は、これまでに外食産業で培ってきたブランド力を活用して事業を売却できます。なかでも地域密着型の飲食店や特色ある店舗は、新たな顧客層の獲得につながることから買い手側から高く評価される可能性があります。
統合によるシナジー効果
買い手企業との統合により、さまざまなシナジー効果が期待できます。外食産業では、食材の調達コストや物流の効率化が利益率に大きく影響します。M&Aを通じて複数の店舗で共通の仕入れルートを確保したり、物流拠点を統合したりすることで、売却後も自社の事業が価値を発揮できる可能性があるでしょう。
既存スタッフの雇用維持
外食業界では慢性的な人手不足が課題となっています。そんな中、M&Aによって自社の既存の従業員を引き継げる点は、買い手企業にとって大きな魅力となり、評価につながるでしょう。交渉次第で既存スタッフの雇用を維持できる可能性があります。一方、買い手側は新たな採用コストを抑えつつ、即戦力となる人材の確保が可能です。
外食産業がM&Aで売却するデメリット
M&Aには多くのメリットがありますが、外食産業特有のリスクやデメリットも存在します。ここでは、外食産業におけるM&Aのデメリットについて解説します。
店舗ブランドやコンセプトの崩壊リスク
外食産業では、ブランドイメージや店舗のコンセプトが集客の大きな要因となります。しかし、M&Aによって経営方針が変わることで、これまでのブランド価値が損なわれる可能性も否めません。既存のブランドイメージを考慮しながら慎重に買い手を選定することが大切です。
従業員の離職や士気低下
M&Aによって経営者が変わることにより、従業員が不安を感じて離職につながるケースがあります。特に、待遇の変化や業務内容の大きな変更が発生した場合、スタッフのモチベーションが下がりやすく、サービス品質の低下を招くおそれがあります。売却後は従業員との十分なコミュニケーションを取り、安心して働ける環境を整えることが重要です。
外食産業がM&Aで売却を成功させるためのポイント
外食産業のM&Aを成功させるには、業界特有のポイントを押さえて進めることが重要です。ここでは、外食産業ならではのM&A成功のためのポイントについて解説します。
立地と店舗ネットワークの活用
飲食店の成功において、立地の影響は非常に大きいため、M&Aでは立地や店舗ネットワークが評価対象となる可能性があります。競合店の有無やターゲット層とのマッチングなど、商圏の強みを効果的にアピールすると良いでしょう。
フードオペレーションの統合
外食産業におけるM&Aでは、フードオペレーションの統合がスムーズに進むかどうかが成功の鍵を握ります。「食材の仕入れルート」「調理プロセス」「品質管理の基準」などに着目しながら、買い手との交渉で統合プランをしっかりと策定することが重要です。
人材と企業文化の融合
飲食業界では、スタッフのスキルやサービス品質が店舗の売上に影響を与えるため、M&A後の人材と企業文化の融合も重要な課題となります。事業の売却後に従業員とのコミュニケーションを積極的に図り、買い手側との企業文化の違いによる摩擦を防ぐことが大切です。
外食産業業界のM&A事例
最後に、外食産業業界のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
すかいらーくホールディングスによるCCS社のM&A
すかいらーくホールディングスは、2025年1月、マレーシアでムスリム向けしゃぶしゃぶ店「すき屋(Suki-Ya)」を展開するCreateries Consultancy Sdn. Bhd.(CCS社)の全株式を取得し、子会社化しました。
すき屋は、豚肉とアルコールを使用しないヘルシーな鍋料理が特徴で、クアラルンプールを中心に13店舗を展開しています。
本件により、すかいらーくは中華系向け「しゃぶ葉」との二本柱で東南アジアでの出店加速を目指しており、調達や教育面でもシナジー効果が期待されています。
【出典】すかいらーくホールディングス「マレーシアCCS社の株式を取得」
ワタミ株式会社による日本サブウェイ合同会社のM&A
ワタミ株式会社は、2024年10月、日本国内で「Subway」ブランドを展開する日本サブウェイ合同会社の全持分を取得し、同社を子会社化しました。これに合わせて、Subway International B.V.とのマスターフランチャイズ契約も締結しています。
ワタミは、有機農業や再生可能エネルギーを活用した持続可能な事業モデルを推進しており、今回のM&Aにより、有機野菜を活かした商品開発や、フランチャイズ展開のノウハウ強化、海外市場進出の加速を図る方針です。
今後、日本市場でのSubway事業のさらなる拡大が期待されています。
【出典】ワタミ株式会社「マスターフランチャイズ契約の締結並びに日本サブウェイ合同会社の持分取得(子会社化)に関するお知らせ」
株式会社サンマルクホールディングスによるジーホールディングス株式会社のM&A
株式会社サンマルクホールディングスは、2024年10月、ジーホールディングス株式会社(GHD)の全株式を取得し、子会社化することを決定しました。
GHDは、牛カツ専門店「京都勝牛」やカフェ「NICK STOCK」などを展開し、インバウンド観光客の取り込みと海外進出に強みを持っています。
今回のM&Aにより、サンマルクは自社の物件情報やDX支援を活かしGHDの成長を加速させるとともに、中期経営計画に掲げる第三の成長ブランド確立を目指します。
【出典】株式会社サンマルクホールディングス「株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」
まとめ|外食産業業界のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
外食産業におけるM&Aは、市場環境や消費者ニーズの変化に対応しながら、事業成長や競争力強化を実現する重要な手段となっています。
買収後のシナジーを創出するために、適切な買い手を選定し、業界特有の要素を考慮した戦略を立てることが成功の鍵となります。信頼できるM&A仲介会社に相談して、自社にとって最適な買い手とのマッチングを目指しましょう。
M&A仲介会社を選ぶ際は、成約実績だけではなく、担当者の専門性や外食産業への理解度、提案の質などを総合的に評価することが大切です。CINC Capitalでは、外食産業の特性を深く理解した専門チームが、オーナー様の想いに寄り添ったM&Aを支援しています。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















