CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
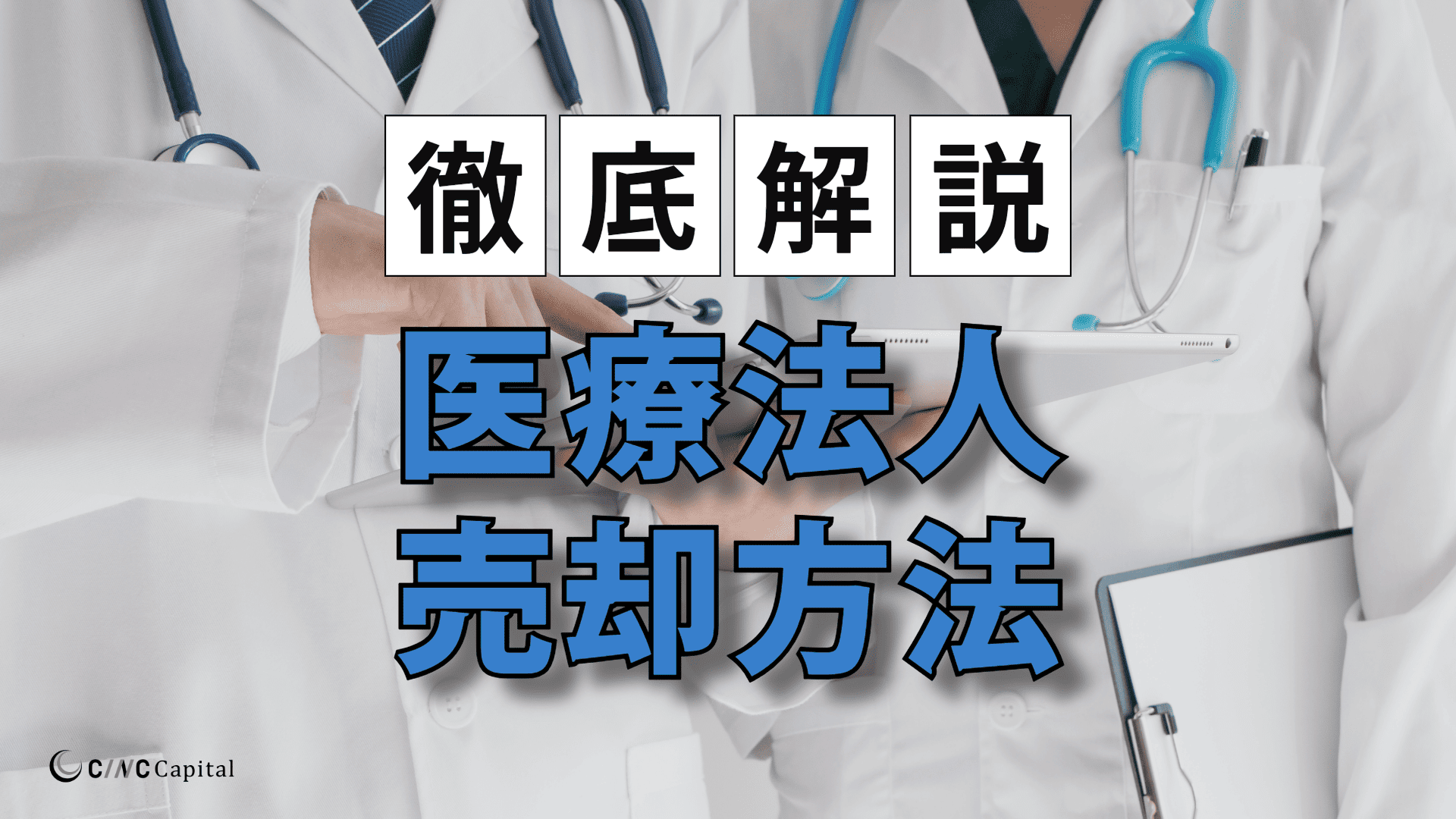
業種
- 最終更新日2025.06.26
医療法人は売却できる?メリットや注意点、手続きの流れを解説
医療法人の運営を続ける中で、後継者不足や経営の負担増加などの理由から売却を検討する経営者の方もいるでしょう。
しかし、医療法人の売却は一般的な企業とは異なり、法律や手続きが複雑で、慎重な対応が求められます。売却を成功させるためには、適切なM&Aスキームを選択するとともに、メリットや注意点を理解することが大切です。
本記事では、医療法人の売却に関する基本知識や具体的な流れについて解説します。
目次
医療法人の売却とは?
まずは、医療法人の売却に関する基本的な知識を解説します。
事業譲渡と事業売却の違い
「事業譲渡」とは、医療法人が運営する医療機関(診療所や病院など)の資産や負債を含めて第三者に譲渡するM&Aの1つのスキームです。これにより、買い手側は医療機関の設備やスタッフを引き継ぎながら、新たな法人名義で運営ができます。
一方、「事業売却」とは、売却する側の視点で使われることが多い言葉で、M&Aスキームによる売却を総称して事業売却と表現するケースがあります。なお、同様に買収する側の視点で「事業買収」と表現するケースもあります。
出資持分がある医療法人とない医療法人の違い
医療法人には「出資持分あり」と「出資持分なし」の2種類があります。
出資持分ありの医療法人
出資持分ありの医療法人は、出資者が出資割合に応じて持分を持っており、解散時には持分に応じた財産の分配を受ける権利があります。しかし、2007年の医療法改正により新たに出資持分ありの医療法人を設立できなくなりました。現在、出資持分ありの医療法人は「経過措置型医療法人」として存続しています。
出資持分なしの医療法人
出資持分なしの医療法人は、出資者による持分の払い戻しや残余財産の分配を受ける権利がなく、医療活動を行う法人として運営されます。2007年以降に設立された医療法人は、すべてこの出資持分なしの形態となっています。また、一部の医療法人では基金制度が採用されており、拠出した資金を一定の条件のもとで返還できる「基金拠出型医療法人」として運営されている場合もあります。
M&Aにおいて「出資持分あり」と「出資持分なし」のどちらが有利になるかは、状況によって異なります。例えば売り手側の医療法人の場合、純資産価値が高く、創業者が経済的利益を得たい場合は「持分あり」が有利です。一方、事業の継続性や公益性を重視する場合は「持分なし」が有利となります。
ただし、国の政策として出資持分なしの医療法人への移行が推進されている点を考慮すると、長期的には出資持分なしの医療法人の方が制度変更リスクが少ない可能性があります。個別のケースに応じて適切にM&Aを進めるためにも、M&Aの専門家へ相談すると良いでしょう。
医療法人の売却の手法
医療法人を売却する際には、主に「事業譲渡」「持分の譲渡」「合併」「法人格の売買」といった手法が用いられます。目的や状況に応じて適切なM&Aスキームを選択しましょう。
事業譲渡
事業譲渡とは、医療機関の資産・負債・従業員・契約などを他の法人に譲渡する方法です。売却する側の法人格はそのまま残るため、譲渡後も別の医療機関を運営することが可能です。また、事業譲渡の対象範囲を選択できるため、一部の診療所のみを譲渡することもできます。ただし、契約の引き継ぎには手続きが必要となるため、関係者との調整が求められます。
持分の譲渡
持分の譲渡とは、出資持分がある医療法人において、出資者が自身の持分を第三者に譲渡する方法です。出資持分は、設立時に出資した金額に応じて保有され、法人の解散時には割合に応じた財産分配を受ける権利があります。買い手側は持分の譲渡により法人の運営権を取得できるため、法人そのものを承継したい場合に適した方法です。
合併
合併は、2つ以上の医療法人を統合する手法で、「新設合併」と「吸収合併」の2種類があります。新設合併は、新たに法人を設立し、既存の法人を解散させて統合する方法です。一方、吸収合併は、既存の法人が他の法人を吸収し、存続法人として継続する方法となります。医療法人のM&Aでは、一般的に吸収合併が用いられます。
法人格の売買
医療法人の売却は、「事業譲渡」「持分の譲渡」「合併」といった手法で行われます。“法人格の売買”と表現されることもありますが、実際にはこれらの手法を用いて、医療法人が保有する権利義務や資産などを他の法人に移転することを指します。なお、出資持分のない医療法人の場合は、持分の譲渡ができないため、「事業譲渡」や「合併」といった方法で売却を進めることになります。
医療法人を事業売却するメリット
ここでは医療法人を事業売却するメリットを、売り手側の視点で解説します。
経営の安定化や設備投資が可能になる
事業基盤の安定した医療法人グループの一員となることで、資金調達の選択肢が広がり、経営の安定化が図れます。採用力の向上にともない人材確保が容易になれば、医療サービスの質の向上にもつながるでしょう。また、最新の医療設備の導入やDX(デジタル・トランスフォーメーション)による業務効率化で、より高度な医療を提供できる可能性もあります。
事業承継ができる
医療法人の事業承継は、後継者がいない場合に有効な選択肢です。経営者が高齢化し、後継者が不在の状況下では、医療機関の運営が困難になるケースがあります。事業売却を通じて別の法人や経営者に引き継ぐことで、これまで築いてきた医療機関の経営を継続できる可能性があります。
地域の医療サービスを維持できる
医療機関が閉鎖されると、地域住民の医療アクセスが悪化するおそれがありますが、医療法人が事業を売却することで、地域の医療サービスを継続して提供できます。経営状況が厳しくなっている医療機関でも、売却によって安定した運営体制を確保すれば、患者への影響を最小限に抑えることが可能です。
医療法人のブランド価値を承継できる
医療機関での長年にわたる診療実績、患者との信頼関係、地域との結びつきは、新規開院では得られない大きな資産となります。また、既存の医療スタッフを維持することで、患者の信頼関係を継続し、スムーズな運営が可能になります。売却によって、こうしたブランド価値が高く評価される可能性があるでしょう。
医療法人を事業売却する際の注意点
医療法人の事業売却は、一般企業のM&Aとは異なり、法的手続きや運営における注意点が存在します。ここでは、医療法人の売却を進める際に注意すべきポイントを解説します。
手続きが複雑になるケースがある
医療法人の事業売却は、一般企業のM&Aと比べて手続きが煩雑になります。例えば、医療機関が保有する不動産や設備、医療機器のリース契約、従業員の雇用契約などを個別に引き継ぐ必要があります。また、病床を有する医療機関では、病床数の再調整が必要となる場合があるので、行政との折衝も欠かせません。
のれんの適正な評価が求められる
医療法人の事業売却では、「のれん(営業権)」の評価を適切に行わなければなりません。その際は「医療機関のブランド力」「患者数」「地域での評判」などが評価に影響を与えます。このほかに、診療報酬や医療従事者の継続雇用状況によっても、のれんの価値は変動します。
建物の築年数や土地を適切に取り扱う必要がある
医療法人が保有する建物や土地の扱いも、事業売却の際に注意すべきポイントです。なかでも築年数が古い建物は、現行の建築基準法に適合しない場合があり、売却後に改築などの対応が必要となる可能性があります。また、賃貸物件の場合は、契約内容を事前に確認し、契約の引き継ぎが可能かどうかを明確にしておくことが重要です。
事業売却に伴い税金が発生する
医療法人の事業売却を行う際には、譲渡所得税や法人税など、さまざまな税金が発生します。のれん代や不動産の売却益がある場合は、課税負担が大きくなる可能性があります。M&Aスキームによって税負担が異なるため、専門家と相談しながら、最も有利な形で売却を進めることが重要です。
管理医師が不在になるリスクがある
医療法人の事業売却では、管理医師の不在リスクも考慮する必要があります。管理医師がいなければ診療を継続できず、一時的な休業を余儀なくされるケースもあります。売却のタイミングによっては、医師の退職や転籍により運営が困難になる可能性があるため、後継の医師を確保しなければなりません。
医療法人の売却の流れ
ここでは、医療法人の売却の流れを解説し、スムーズに売却を進めるためのポイントをご紹介します。
事前検討
医療法人の売却を進めるにあたり、まずは売却の目的を明確にすることが重要です。具体的には「後継者問題の解決」「経営の負担軽減」「医療機関の存続」などが挙げられるでしょう。売却の目的を整理することで、適切な買い手を見つけやすくなります。
M&A専門機関と契約
医療法人の売却では専門的な知識が求められます。そのため、信頼できるM&A仲介会社と契約し、サポートを受けることをおすすめします。医療法人の売却に詳しい業者をパートナーに選ぶことでM&Aの成功率を高められます。
買い手候補とのマッチング
売却する医療法人に適した買い手を見つけるため、M&A仲介会社を通じて候補者を探しましょう。希望条件を整理し、複数の候補と交渉することで、最適な相手を選ぶことが可能です。
初期交渉とトップ面談
買い手候補が決まったら、秘密保持契約を締結した上で財務状況や経営戦略などの詳細情報を開示し、初期交渉で基本的な条件をすり合わせます。また、双方の経営者が直接会うトップ面談を行い、経営理念の一致や相性を確認することも大切です。
基本合意
この段階で買い手と合意に達した場合、「基本合意書」を締結します。基本合意書には、売却価格・M&Aスキーム・今後のスケジュールなどが記載されます。基本合意を結ぶことで買い手側に独占交渉権が与えられることが一般的ですが、他の買い手と交渉ができなくなるため、慎重に判断する必要があります。
デューデリジェンス
デューデリジェンス(買収監査)は、買い手側が対象の医療法人の実態を詳細に調査するM&Aプロセスです。特に医療法人の場合、許認可の確認や診療報酬の適正性、債務状況などの点を重点的に調査することが求められます。デューデリジェンスの結果によっては、買収条件の修正が必要になることもあります。
最終交渉
最終契約の締結に向けて交渉を行います。「最終契約書」には、基本合意の内容に加えて、デューデリジェンスの結果を反映した条件が盛り込まれます。事業譲渡の場合は「事業譲渡契約書」、株式譲渡の場合は「株式譲渡契約書」などの名称で作成されます。最終契約書は法的拘束力を持つため、契約内容を慎重に確認することが重要です。
クロージング
最終契約を締結した後、譲渡手続きを行います。具体的には、不動産や医療機器などの資産移転、従業員の引き継ぎ、行政手続きなどです。医療法人の場合、厚生局や保健所などへの届出が必須となるため、売却後の手続きも重要となります。クロージングが完了したら、新しい経営体制のもとで事業が運営されます。
まとめ|医療法人の売却は医療承継のプロに相談しましょう
医療法人の売却では、一般企業のM&Aとは異なる専門的な手続きが必要で、慎重な対応が求められます。M&Aで発生するリスクを回避し、最適な条件で売却を進めるためにも、医療M&Aの専門家に相談すると安心です。医療法人の売却を検討している経営者の方は、医療分野の専門的な知識を持つM&A仲介会社へご相談ください。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















