CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
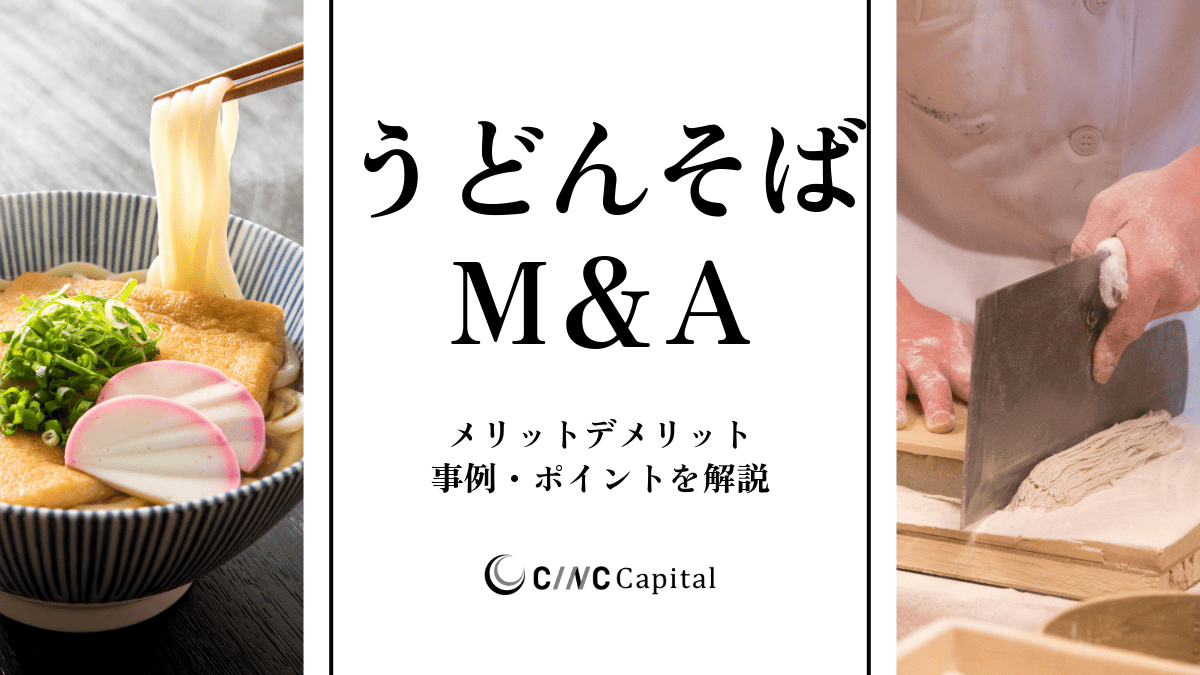
業種
- 最終更新日2025.06.26
うどん・そば屋業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
うどん・そば屋業界では近年、人手不足や原材料価格の高騰、後継者不足などの課題が深刻化しています。これらの問題が長期化することで、業界全体の活気が落ち込むリスクも指摘されるようになりました。
そうした背景からM&Aへの注目が集まり、2025年に向けてうどん・そば屋業界の動向が大きく変わる可能性があります。本記事では、市場動向や課題、そしてM&Aを行うメリット・デメリットや成功のポイントなどを解説します。
目次
うどん・そば屋業界の市場動向
うどん・そば屋業界は外食産業の中で根強い人気を持ちつつも、大手チェーンとの競合や消費者ニーズの変化など、市場環境に多様な要因が影響しています。
日本の食文化を代表する麺料理として、うどん・そばは幅広い世代に親しまれています。安定的な需要がある一方で、近年はコンビニやファストフードなど他業態との競争も激化し、差別化戦略が求められるようになっています。
大手チェーンによる多店舗展開や新興企業の参入が進むことで、麺類専門店の市場規模は拡大の兆しを見せています。特にロードサイド店舗や駅ビル内のテナントに注力したチェーンが増加し、地域密着型の店舗にも影響が及んでいます。
さらに、中食や宅配ニーズの増加を背景に、テイクアウトやデリバリーへの対応力も重要になっています。これらの市場動向と消費者の嗜好変化を踏まえ、うどん・そば屋が事業を継続・発展させるには柔軟な運営戦略が欠かせません。
うどん・そば屋業界が抱える課題
うどん・そば屋業界には、人手不足や原材料高騰など、いくつかの深刻な課題があります。ここでは、主な課題を3つ見てみましょう。
人手不足により安定した店舗運営が難しくなっている
高齢化に伴い、若年層の飲食業離れが顕著になっています。うどん・そば屋のような専門店は調理工程や接客品質が重視されるため、一定レベルのスキルを持つ人材を確保する必要があります。
慢性的な人手不足は、営業時間の短縮やメニュー数の縮小につながり、顧客満足度に影響しやすいのが現状です。アルバイトやパートに依存する経営状態を続けるのか、または正社員を採用して育成するのかといった判断が難しくなっています。
これらの状況を放置すると店舗運営に支障が出るため、人員の安定確保や研修制度の整備など、経営基盤を強固にする取り組みが急務といえます。
原材料価格の高騰によって利益率が圧迫されている
近年、小麦やそば粉の仕入れ価格が世界的な需給バランスの変動により上昇しています。為替レートの影響も受けやすく、安価な供給源を探すのが一筋縄ではいかない状況です。
高級食材を使用している店舗ほど値上げの判断が難しく、逆に低価格帯の店でも価格転嫁が難しい場面に直面します。結果的に、薄利多売で利益を確保せざるを得ない事態に陥ることもあります。
コスト管理の徹底や、新たな仕入れ先の開拓が課題解決の鍵となります。しかし、安定した原材料の確保はどの店にとっても喫緊の課題であり、経営戦略の大きな柱として考慮しなければなりません。
大手チェーンとの価格競争に苦しめられている
うどん・そばの大手チェーンが打ち出す低価格メニューは、消費者にとって非常に魅力的です。その結果、中小規模の店舗は同じ価格帯では太刀打ちできず、付加価値の提供やブランド力の確立が重要になります。
価格だけでなく、スマートフォンでの注文やキャッシュレス決済など、サービス面でもチェーン店は積極的に投資を行ってきています。個人店や小規模チェーンがデジタル投資を進めるには多大なコストとノウハウが必要で、対応の遅れは一層の差を生む恐れがあります。
大手の安定した仕入れルートや広告宣伝力に対抗するには、地域密着型の強みを生かすなど、独自性を打ち出す戦略が求められるでしょう。
うどん・そば屋業界のM&A最新動向(2025年)
2025年を見据え、うどん・そば屋業界では後継者不足や海外展開のニーズなどからM&Aの動きが活発化しています。
ここでは、主要な動向を3つ見てみましょう。
後継者不足を背景に中小店舗の売却が増加
老舗や家族経営のうどん・そば屋では、親族内で後継者を見つけることが難しいケースが増えています。こうした背景から、従来は店舗を畳むことしか選択肢がなかったオーナーが、M&Aを通じて事業譲渡を検討する例が増えているのです。
店舗を引き継ぐ買い手も、既存のスタッフやレシピ、ロイヤル顧客をそのまま引き継ぐことができるため、ゼロから事業を始めるよりリスクが低く抑えられます。
特に地方エリアで顕著な動きとして、地域の名店が売却に踏み切るケースが増加し、買い手からも注目を集めています。
多店舗展開を狙う外食チェーンによる買収
大手外食チェーンは新規出店だけでなく、M&Aを活用した多店舗展開に力を入れています。これは、ブランド力や立地の良い店舗を短期間で獲得できるメリットがあるからです。
チェーン側にとっては、既存の運営ノウハウを導入することで効率的に売上と利益を伸ばす狙いがあります。同時に、現場スタッフの労務管理や商品開発などの統一化が進めやすい点も魅力です。
大手の資本力を活かした設備投資やメニュー開発のスピード感は、高齢オーナーが持つ小規模店では真似できない規模に及ぶため、新たなシナジーが期待されています。
新興外食企業のM&Aによる海外進出
国内外食市場が成熟するなか、新興企業が海外マーケットへ進出するケースが増えています。その一環として、うどん・そば屋店舗を買収し、麺料理を海外で広める動きが活発化しているのです。
海外ではヘルシー志向や日本食ブームが継続しており、うどん・そばの認知度も高まりつつあります。買収後に店舗コンセプトを再構築し、現地法人として運営することでさらなる市場拡大を目指す企業も少なくありません。
ただし、海外での食の好みや文化的な習慣には注意が必要です。現地向けに味付けやサービス形態を工夫する必要があり、しっかりとしたマーケット調査が欠かせません。
うどん・そば屋がM&Aをするメリット
株式譲渡や事業譲渡などにより、自社の持つ課題を解決できる可能性があります。ここでは、うどん・そば屋がM&Aをする売り手目線のメリットをご紹介します。
後継者問題を解消し店舗の存続を実現できる
うどん・そば屋の経営者にとって、多くの場合一番の懸案となるのが後継者不在です。M&Aを通じて新オーナーに事業を託すことで、長年培ってきた味や店舗の伝統を存続させることができます。
キャンセルすることなく事業を続けられるため、オーナーにとっても従業員や顧客にとっても安心感が大きい点が魅力です。経営に意欲的な買い手であれば、今後の展開にも期待がかかります。
店舗経営からの引退後も従業員の雇用を守ることができる
長年勤めている従業員がいる場合、M&Aで買い手に引き継ぐことによって雇用が継続される可能性が高まります。オーナーが高齢であっても、自分の代わりにスタッフの面倒を見てくれる企業を見つけやすくなります。
特に技術力や接客スキルを持つ従業員は、買い手にとっても貴重な経営資源です。既存の人材をそのまま確保できる点は、新規参入よりも大きなメリットとなる場合があります。
設備や店舗の価値を現金化できることで老後資金に余裕が生まれる
うどん・そば屋を長年経営してきたオーナーにとって、店舗や設備には多くの資産価値が詰まっています。これをM&Aで売却することで、老後資金や新たなチャレンジへの資金として利用できるのです。
特に立地条件が良い店舗や、一定の顧客数を維持している店であれば、思わぬ高値がつく可能性もあります。オーナーの意向にあわせた売却条件を設定できるのも、M&Aの大きな利点といえるでしょう。
うどん・そば屋がM&Aをするデメリット
M&Aには、いくつかのデメリットが存在します。今後M&Aを検討する中で、売り手側が知っておくべき注意点は以下の通りです。
買収先によっては店舗の方針や味が変わってしまう可能性がある
新オーナーが経営方針を大きく変えた場合、メニューやサービスのコンセプトが従来とまったく異なる方向へ進むこともあります。これは長年の常連客にとっては衝撃的であり、離反を招くリスクになるでしょう。
また、味覚や接客スタイルは企業によっても大きく異なるため、店舗全体のイメージが変化する可能性があります。オーナーの意向が尊重されないケースもあるため、事前の条件交渉が欠かせません。
地域の常連客からの信頼を失う恐れがある
うどん・そば屋は地域密着型のビジネスであり、常連客の存在が売上を支えている場合が多いです。しかし、買収後の経営方針や味が変化すると、常連客が離れてしまう可能性があります。
こうしたリスクを回避するには、M&A後もしばらくは従来の味やサービスを維持するなど、常連客への配慮が重要です。新オーナーと既存スタッフが協力して、段階的な変化を進めることもひとつの方法でしょう。
希望の価格で売却できないケースがある
店舗売却の価格は、立地や売上高、ブランド力等を総合的に評価して決定されます。しかし、オーナーが理想とする価格と買い手側の見解にはズレが生じることが多く、交渉が難航する場合があります。
そのため、事前に企業価値評価を行い、妥当な相場を把握しておく必要があります。特に市場に出回る類似案件の動向を調査し、客観的なデータをもとにした交渉姿勢が求められます。
【買い手】うどん・そば屋をM&Aをするメリットデメリット
買い手側からみたうどん・そば屋のM&Aにはどのようなメリット・デメリットがあるのか、ポイントを整理します。
買い手企業にとって、うどん・そば屋をM&Aする最大のメリットは、すでに確立されたブランドや固定客、そして熟練した調理スタッフを一括で手に入れられる点にあります。新規事業立ち上げに比べてリスクが低く、一気に事業規模を拡大できるのです。
一方で、買収後の店舗運営にはオーナー交代に伴う混乱も生じやすく、味やサービスの統一化、スタッフのモチベーション維持など課題が少なくありません。これらをクリアしないと買収メリットが十分に発揮できない恐れがあります。
また、買い手企業の事業内容やビジョンと、うどん・そば屋の経営スタイルが噛み合わない場合には、軌道修正に時間や追加投資が必要となるでしょう。買い手にとっても事前の綿密な調査と計画がカギとなります。
うどん・そば屋業界のM&A相場は?
M&Aに際してもっとも気になる部分といえるのが価格相場ではないでしょうか。以下では、うどん・そば屋業界のM&A相場に関する情報を解説します。
価格は一概には決められない
M&Aの価格は多様な要因によって変動するため、一概に相場を提示するのは難しいものの、類似の取引事例などを参考に算定される場合があります。価格に影響を与える要因として、「会社の規模」「収益性」「将来性」「負債」「ブランド力」などが挙げられます。
M&Aにおけるうどん・そば屋業界の企業価値の算出方法
日本の中小企業のM&Aでは、企業価値算定方法として「時価純資産+営業権法」と「マルチプル法」が採用される場合が多いです。自社の価値について気になる場合は、ぜひ以下の企業価値算定シミュレーションをお試しください。
うどん・そば屋がM&Aを成功させるためのポイント
うどん・そば屋業界のM&Aを成功に導くためには、綿密な事前準備と適切な実行プロセスの管理が重要となります。以下に、特に重要なポイントを4つ解説します。
事前に店舗の収支状況や資産を正確に把握しておく
買い手は数字を非常に重視するため、収支報告や在庫管理、設備状況のチェックは入念に行う必要があります。日々の売上データや経費の内訳を明確化しておくだけでも、相手からの信頼度は大きく向上します。
特に古い店舗設備をそのままにしている場合、修繕費やリニューアル費用を買い手が負担する可能性があります。適切にメンテナンスされている店舗であるほど、高い評価が得られる傾向にあります。
自店舗の強みを明確にし、他店舗と差別化する
うどん・そば屋の場合は、オリジナルの出汁や麺の製法など、差別化要素を打ち出しやすいメリットがあります。これら独自のポイントをしっかり明文化しておくことが、M&A時に強みとして評価されやすくなります。
立地条件や顧客層の分析も重要です。例えばオフィス街で昼食需要を確保している店舗や、観光地でインバウンド需要を取り込んでいる店舗など、買い手に具体的なアピールが可能となります。
M&Aの専門家を活用する
飲食業のM&Aに特化した仲介業者や、専門のコンサルタントを利用することで、譲渡プロセスが円滑に進むケースが多いです。業界特有の課題やノウハウを熟知した専門家が間に入ることで、双方にとって納得感のある条件形成が行いやすくなります。
書類作成や面談調整などの実務を専門家に任せることで、オーナーは店舗運営や経営の最終調整に専念できます。結果として、より高い売却価格やスピーディーな成約が期待できるでしょう。
うどん・そば屋業界のM&A事例
最後に、うどん・そば屋業界のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
株式会社こむぎのによる株式会社うちだ屋のM&A
2025年3月、株式会社こむぎの(東京都千代田区)は、福岡県の老舗うどんチェーン、株式会社うちだ屋(福岡市東区)の全株式を取得しました。
うちだ屋は1977年創業、九州全域で42店舗を展開する博多うどんの名門で、地元に根ざした和食メニューが特徴です。
こむぎのは、ベーカリーブランド「小麦の奴隷」など地方発の食文化を全国展開してきた実績があり、本件買収により、柔らかさが特徴の博多うどん文化を全国に広げる戦略です。
うどん業態が再注目される中、讃岐うどん主流の市場に新たな選択肢を提供し、多様な麺文化の普及を目指す動きは、飲食業界における差別化戦略の一例といえます。
【出典】株式会社こむぎの「ホリエモンが四大博多うどん『うちだ屋』を買収、全国展開へ」
株式会社すかいらーくホールディングス
株式会社すかいらーくホールディングス(東京都武蔵野市)は、2024年9月、北九州市発のうどんチェーン「資さんうどん」を展開する株式会社資さんの全株式を取得し、子会社化することを決定しました。
資さんは、うどんや和食をリーズナブルな価格で提供するブランド力を持ち、近年は関西・関東へも出店拡大を進めていました。すかいらーくはこの買収を通じて、地方ロードサイド店舗の業態転換や新ブランドの強化を図ります。
集客力の高い資さんのブランド価値を生かしながら、グループ全体のシナジー効果を追求する動きは、外食大手による成長戦略の一環といえます。
【出典】株式会社すかいらーくホールディングス「株式会社資さんの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」
株式会社フジオフードシステムによる有限会社暮布土屋のM&A
株式会社フジオフードシステム(大阪市北区)は、2019年11月、関西を中心に石臼挽き手打ち蕎麦専門店「土山人」を展開する有限会社暮布土屋の株式90%を取得し、子会社化しました。
「土山人」は直営7店舗を運営し、ミシュランガイドにも選出された実績を持つ人気蕎麦ブランドです。フジオフードシステムはこれまで「まいどおおきに食堂」など多彩な業態を展開してきましたが、本件により新たに蕎麦業態への進出を果たしました。
今後、既存ブランドとの相乗効果を生かし、さらなる成長を目指す動きが注目されます。
【出典】株式会社フジオフードシステム「石臼挽き手打蕎麦専門店「土山人」を運営する
まとめ|うどん・そば屋業界のM&A動向を抑えてM&Aを成功させましょう
うどん・そば屋業界におけるM&Aは、課題解決やビジネス拡大のための有力な選択肢です。本記事を参考に、M&Aを成功させるための準備を進めていただければ幸いです。
うどん・そば屋業界では、人手不足や原材料価格の高騰、大手チェーンとの競合といった複合的な課題に直面しています。こうした状況の中でも、地域に根付いたブランド力や伝統の味を守りつつ成長を図る手段としてM&Aが注目されています。
実際に事業譲渡を検討する際は、自店舗の強みや経営状況を正しく認識し、適正な価格設定や条件交渉を行うことが重要です。買い手とのマッチングを成功させるためには、専門家のサポートや詳細な情報開示が大きな助けになるでしょう。
うどん・そば屋ならではの魅力を次世代へ継承し、さらなる発展を目指す選択肢として、M&Aは今後ますます需要が高まると考えられます。今のうちに動向を把握しておくことで、あなたの店舗や事業に最適な道を選びやすくなるでしょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















