CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
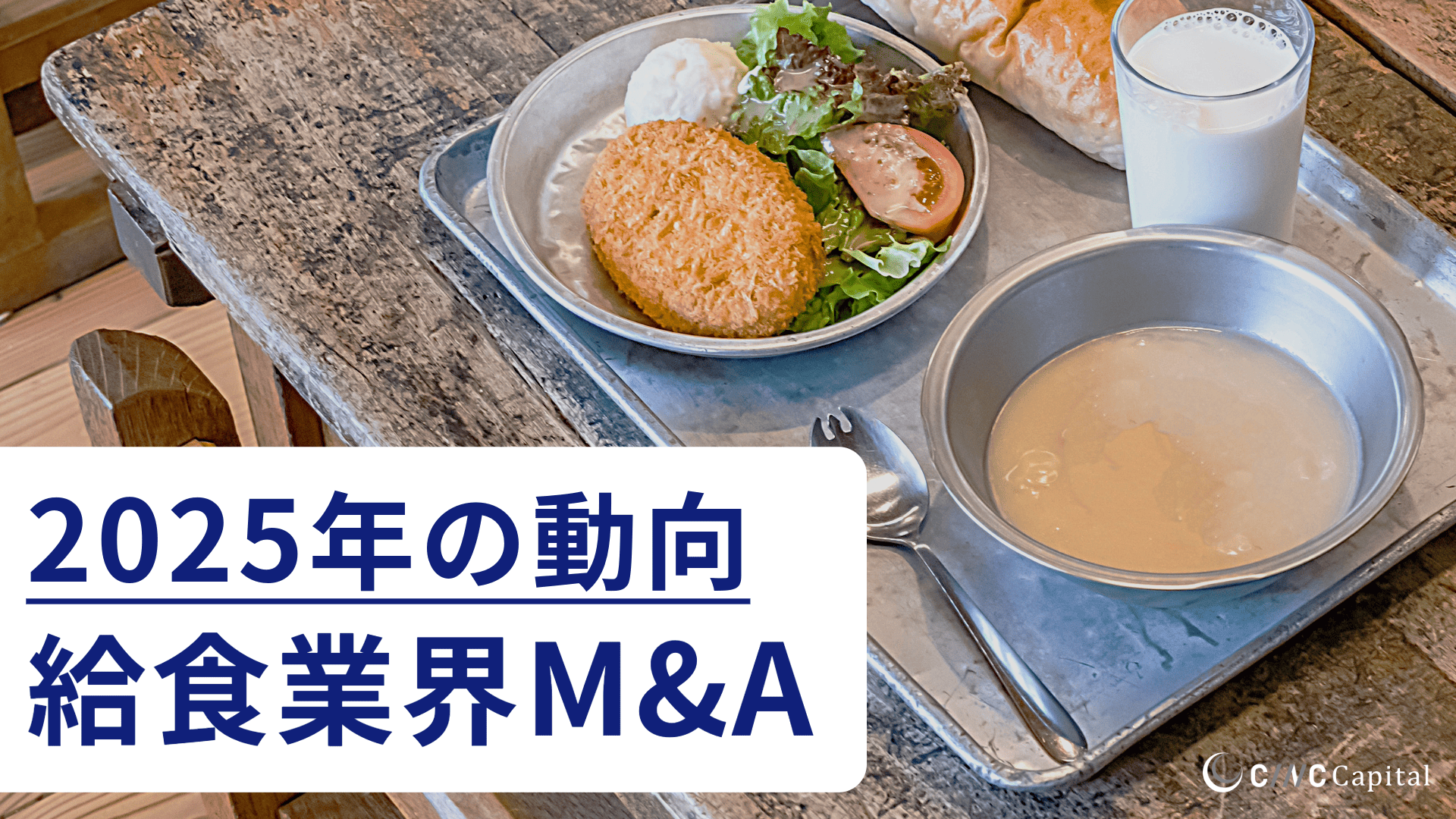
業種
- 最終更新日2025.06.26
給食業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
外食産業の中でも給食は、人材不足・価格競争・少子高齢化といった多くの課題に直面している業界です。近年はこうした課題の解決へ向けてM&Aが注目されています。M&Aは、経営基盤の強化、事業の継続、人材確保などの解決策として有効です。
本記事では、給食業界のM&A動向やメリット・デメリット、成功事例などをご紹介します。
目次
給食業界の現状
「一般社団法人 日本フードサービス協会」の調査によると、2020年の外食産業市場規模は18兆2,005億円と推計されます。このうち給食主体部門における集団給食の市場規模は2兆8,273億円で、全体の約15.5%を占めています。
集団給食には、「学校給食」、社員食堂や弁当給食などの「事業所向け給食」、「医療機関・介護施設向け給食」、「保育所給食」といった分野があります。このうち学校給食や保育所給食は、少子高齢化による影響を受けやすい分野だといえるでしょう。
【出典】一般社団法人日本フードサービス協会「令和2年(令和2年1月~令和2年12月)外食産業市場規模推計について」
給食業界が抱える課題
ここからは、日本の給食業界で問題視されている課題や傾向についてご説明します。
価格面での競争
給食業界は深刻な価格競争に直面しています。食材費や光熱費の高騰、人件費の上昇により経営環境が厳しさを増しているにもかかわらず、価格転嫁が容易ではない状況です。給食の特性上、一般的な外食と比べて低価格での提供が求められます。
超高齢化社会への対応
高齢者向け給食サービスの需要が急速に拡大する一方で、従来の提供体制では対応が困難となっています。特に医療機関や介護施設向けの給食では、1日3食365日の継続的な食事提供が求められ、栄養管理や衛生管理の基準も厳格化されています。
人手不足
給食業界における人手不足は深刻化しています。早朝勤務や休日出勤を含む厳しい労働条件に加え、業界全体の収益性の低さから給与水準を上げることが難しくなっています。特に若年層の採用・定着が課題とされています。
在宅配食の拡大
単身高齢者世帯の増加や、食の外部化ニーズの高まりにともない、在宅配食サービスの需要が増えています。その一方で、配送効率の向上や品質管理の徹底など、新たな課題も浮上しています。
給食業界のM&A最新動向(2025年)
昨今の給食業界では、新規参入や大手事業者による事業の切り離しなどの動きが見られます。ここでは、給食業界のM&A最新動向をご説明します。
関連業界からの新規参入が増える可能性がある
近年の給食業界では、食品卸売業や教育関連事業といった異業種からの市場参入が目立ちます。食品製造や物流分野で実績のある企業が、給食事業者との事業統合を通じてサービス領域の拡充を目指す動きもあります。
大手企業が給食事業の切り離しを行う動きがある
市場での競争激化にともない、大手企業の間で給食事業からの事業撤退を決断する動きが見られます。主な理由として、食材価格の上昇や人材コストの増大による利益率の悪化が挙げられます。
【売り手側】給食業界の会社がM&Aをするメリット
経営基盤強化や雇用維持など、M&Aには複数のメリットがあります。主なメリットを見ていきましょう。
経営基盤の強化
売り手側は、M&Aにより経営基盤を強化できる可能性があります。たとえば、大手企業のグループに参画することで、食材調達コストの最適化や物流費用の効率化を実現できます。設備投資や業務改善への取り組みが加速し、より強固な事業運営が可能となるでしょう。
従業員の雇用維持
売り手側は自社の専門人材の雇用を維持・確保できます。従業員の雇用を守るとともに、給食に関する専門知識や技術の継承にもつながるので、業界にもたらされるメリットも大きいといえるでしょう。
事業の継続
後継者問題に直面している企業にとって、M&Aは事業存続への有効な解決策となるでしょう。長年にわたって構築してきた顧客基盤や取引先との信頼関係を維持しながら、円滑な事業承継を実現できます。
経営の安定化
M&Aを通じた事業統合は、企業経営の安定性を大幅に向上させます。事業規模の拡大により、市場における競争優位性が高まり、新規市場への参入や事業多角化が容易になるでしょう。
さらに、複数の営業拠点を運営することで、経営効率の向上とリスク分散を同時に図れます。
【売り手側】給食業界の会社がM&Aをするデメリット
売り手側の企業は、給食業界のM&Aを成功へ導くうえで、以下のデメリットに注意する必要があります。
従業員の待遇の変化
売り手側の従業員にとって、自社の合併・買収には不安がつきものです。とりわけ新体制への移行期においては、社員のモチベーションの低下や退職者の増加といったリスクが高まります。待遇面を含めた従業員のケアが必要になるでしょう。
取引先や顧客からの反発による事業への影響
M&Aをきっかけに、売り手側が長年にわたり築き上げてきた取引先との関係性に変化が生じる可能性があります。先方が経営体制の変更に対して懸念を示し、取引条件の見直しや取引自体の継続を再検討するケースも少なくありません。
【買い手側】給食業界の会社をM&Aするメリット・デメリット
買い手側の企業は、給食業界のM&Aで以下のメリット・デメリットを押さえておくことが大切です。
買い手側のメリット
買い手側の企業は、既存の給食事業者を取得することで、新規事業の立ち上げにかかる時間とコストを節約できます。M&Aを活用することで、給食事業に関する専門知識や豊富な実務経験を持つ従業員をまとめて確保できる可能性があります。
買い手側のデメリット
給食業界では、人件費や原材料費の上昇で利益が圧迫されており、これらの費用管理が経営課題となっています。加えて、社会の高齢化が進む中、介護施設向けの食事サービスや特殊な配慮を要する食事の提供など、新しいニーズへの対応も必要です。
給食業界のM&A相場は?
給食業界で相場を算出する際は、時価純資産額に「のれん代」を加算する方式が一般的です。ただし、革新的なビジネスモデルや将来性の高い新規事業を展開している企業の場合は、相場よりも高額になることがあります。
実際の取引価格はケースによって異なるため、詳しくはM&A仲介会社などに相談することをおすすめします。
給食業界の企業がM&Aを成功させるためのポイント
ここでは、給食業界の企業がM&Aを成功させるためのポイントを解説します。
人手不足を解消する
売り手側の企業が豊富な経験を持つスタッフを確保すると、事業の安定性が向上します。特に、調理技術に長けた人材や、専門知識を有する栄養士などの確保は、提供するサービスの品質維持に大きく影響を及ぼします。
経営環境を整える
企業の経営環境は、M&Aにおいて重視されます。売り手側の企業は、市場における競争優位性を高めることで、交渉を有利に進めやすくなるでしょう。
給食業界においては、独自の食材の開発や調理の効率化など、利益を出す仕組みを作ることが大切です。
給食業界に詳しい専門家にアドバイスをもらう
M&Aを成功させるためには、給食業界特有の課題や市場動向を熟知した専門家のサポートが不可欠です。中でもデューデリジェンス(買収監査)の段階では、財務・税務・労務など多岐にわたる分野での詳細な調査が必要となります。
さらに、M&A後の経営統合プロセス(PMI)においても、専門家の知見を活用することで、期待したシナジー効果を最大限に引き出せるでしょう。M&A仲介会社の力を借りれば、さまざまなリスクを最小限に抑えつつ、円滑な事業統合を実現できます。
給食業界のM&A事例
株式会社トーカンによる三給株式会社のM&A
セントラルフォレストグループは、子会社のトーカンを通じて三給株式会社の全株式を取得し、子会社化する契約を締結しました。三給は東海エリアの給食向け食品卸売業を展開し、その子会社であるヒカリはスーパー惣菜向け食品卸売業を手掛けています。
本件により、セントラルフォレストグループは給食市場へ参入し、中食・惣菜分野での売上拡大を図ることで、企業価値の向上を目指します。なお、三給の代表取締役社長は林元造氏から神谷亨氏に交代する予定です。
【出典】セントラルフォレストグループ株式会社「三給株式会社の株式取得に関する株式譲渡契約書締結についてのお知らせ」
NGFホールディングス株式会社によるケータリング・ホールディングス株式会社のM&A
NGFホールディングス株式会社(本社:名古屋市中区)は、2024年8月1日付で、東京ケータリング・ホールディングス株式会社(TCHD)の全株式を取得しました。譲渡元は、大和PIパートナーズ株式会社が運営するDPIP企業支援1号です。
TCHDは関東地方を中心に、学校・企業・病院での給食提供や寮・保養所・レストラン運営を手掛け、連結売上高は100億円超に達します。NGFHDは、TCHDの営業基盤を活用し、関東以北の市場開拓を進め、さらなる事業拡大を図る方針です。
本件により、NGFHDの連結売上高は500億円超、事業所数約1,440カ所、従業員数約1万2,000名となる見込みです。両社のノウハウ・リソースを活かし、シナジー効果を最大化していくとしています。
【出典】大和PIパートナーズ株式会社「東京ケータリング・ホールディングスの発展的承継について」
オイシックス・ラ・大地株式会社によるシダックス株式会社のM&A
オイシックス・ラ・大地株式会社は、2023年11月10日、持分法適用関連会社であるシダックス株式会社の株式を公開買付け(TOB)に応募し、さらに第三者割当増資を引き受けることで、シダックスを連結子会社化することを発表しました。
今回のM&Aは、シダックスの経営陣が主導するマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として実施されました。オイシックスは2022年10月にシダックスを持分法適用関連会社としていましたが、上場企業同士の提携では経営資源の共有や意思決定に制約があることが課題とされていました。そのため、シダックスを子会社化することで、迅速な意思決定を可能にし、事業の成長を加速させる狙いがあります。
オイシックスは、シダックスが持つ給食事業や車両運行サービス事業とのシナジーを強化し、食の領域における新たなビジネスモデルの構築を目指しています。特に、給食業務にオイシックスのミールキットを活用することで、業務の効率化や食の品質向上が期待されます。
今回のM&Aは、食品業界におけるサプライチェーンの統合とサービスの多様化を進める好例といえます。今後、オイシックスの成長戦略の一環として、どのようにシダックスとの協業が進むのか注目されます。
まとめ|給食業界のM&A動向を抑えてM&Aを成功させましょう
M&Aは、課題解決と競争力向上を図れる経営戦略の一つです。給食業界において人材・技術の確保、経営基盤の強化を狙いつつ、事業の持続可能性を高められます。一方で、従業員の待遇変化や取引先との関係維持といったリスクには注意が必要です。仲介会社をはじめ、専門家のサポートを受けながらM&Aを成功に導きましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















