CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
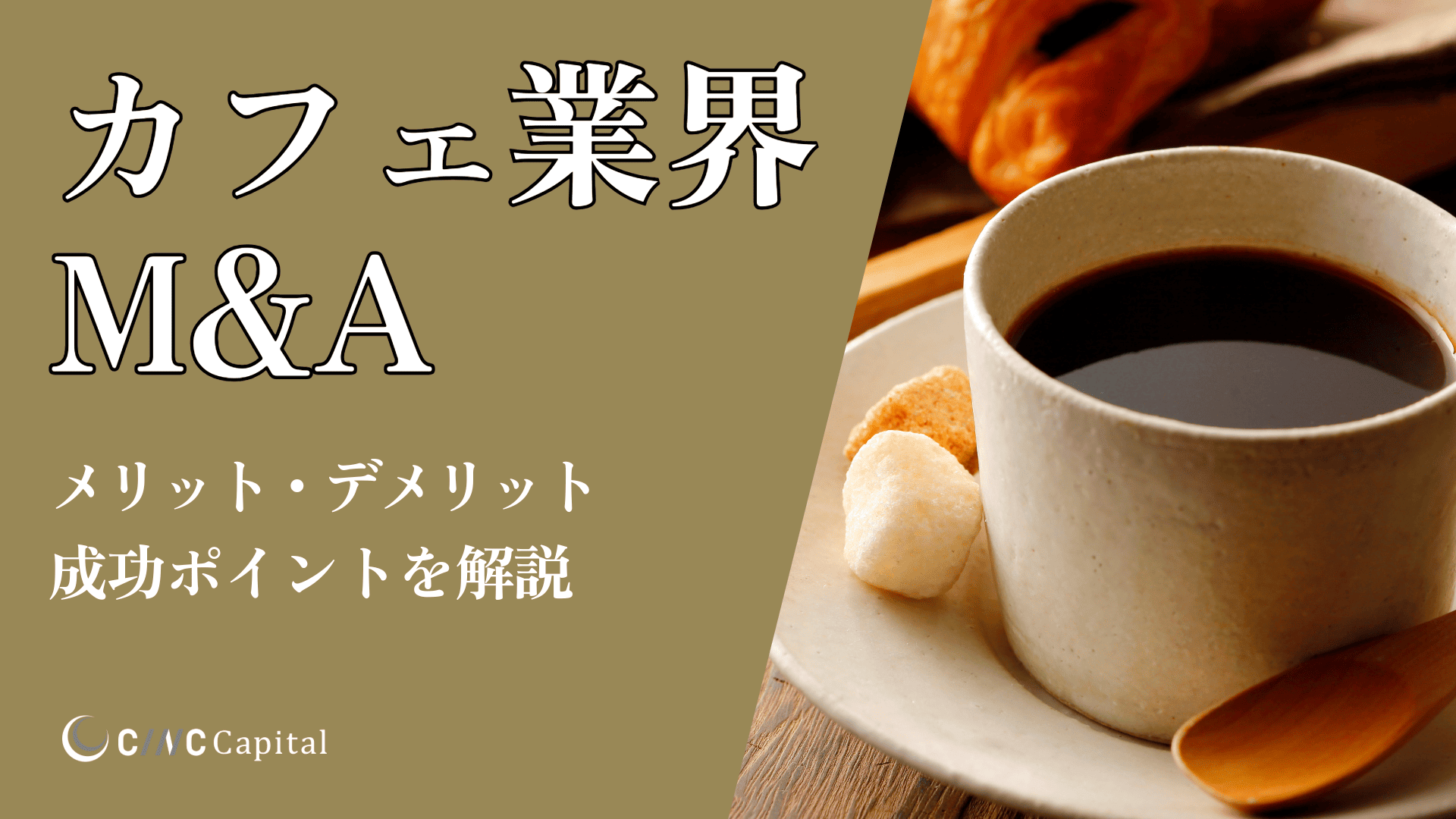
業種
- 最終更新日2025.06.26
カフェ業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
カフェ業界は、原材料費の高騰や人手不足、大手チェーン店との競争激化など、厳しい課題に直面しています。「経営を続けられるか不安」「後継者が見つからない」といった悩みを抱える方も多いです。
こうした中、M&Aを通じた事業売却や拡大を検討する経営者が増えています。成功には業界動向の把握や専門家のサポートが欠かせません。
この記事では、2025年に向けたカフェ業界のM&A動向、メリットデメリット、成功事例を解説し、経営者の選択肢を広げる情報をお届けします。
目次
カフェ業界の市場動向
喫茶店業界の市場規模は1兆円を超えており、ここ20年間は約1.02〜1.28兆円でほぼ横ばいで推移しています。テイクアウトやデリバリーサービスの需要拡大により、新たな収益機会が生まれてきました。
顧客ニーズの変化に伴い、カフェの役割は従来のコーヒーを提供する場所から、多機能な空間へと進化を遂げています。テレワークスペースとしての利用や、コワーキングスペースの併設など、新しい価値提供が求められる時代に変化しています。
一方で、業界内での競争は一段と激化しており、大手チェーン店の出店攻勢や新規参入企業の増加により、独立系カフェの経営環境は厳しさを増しています。こうした状況を背景に、事業の継続や成長戦略としてM&Aを選択する企業が増えてきました。
【出典】厚生労働省「今日から実践!収益力の向上に向けた取組みのヒント」
カフェ業界が抱える課題
カフェ業界では原材料費の高騰、深刻な人手不足、大手チェーンの寡占化という3つの重要な課題を抱えています。ここでは、それらの課題について詳しく見ていきましょう。
原材料費の高騰による利益率の低下
コーヒー豆や乳製品、小麦粉などの主要原材料の価格上昇により、多くのカフェで利益率が低下する傾向にあります。
世界的な気候変動や供給網の混乱により、コーヒー豆の国際相場は過去10年で最高値圏で推移しています。また、乳製品や砂糖などの価格も前年比で15〜20%上昇しており、カフェの収益を圧迫する要因です。
特に個人経営の小規模カフェでは仕入れ量が少なく、価格交渉力も限られているため、より深刻な影響を受けています。
人手不足の深刻化
厚生労働省の調査によると、2024年の飲食店を含むサービス業の有効求人倍率は2.8倍を超えており、慢性的な人材不足が経営課題です。
この背景には、シフト制による不規則な勤務時間や、接客業特有のストレス、業界全体の賃金水準の低さなどが要因として挙げられます。特に、コロナ禍以降は従業員の働き方に対する価値観が変化し、より柔軟な勤務形態や待遇改善を求める声が強まっています。
この状況に対して、多くのカフェ事業者がデジタル技術の活用や業務プロセスの効率化を進めていますが、接客を重視するカフェ業態では、完全な機械化や省人化には限界があるのが現状です。
大手チェーンの寡占状態
カフェ業界において大手チェーンの店舗数は年々増加傾向にあり、市場の寡占化が進んでいます。これにより、独立系カフェの経営環境は一段と厳しさを増している状況です。
大手チェーンは豊富な資金力と効率的な経営システムを活かし、積極的な出店戦略を展開しています。特に、駅前や商業施設など、集客が見込める好立地への出店を強化しており、独立系カフェにとって望ましい出店場所の確保が困難になっています。
カフェ業界のM&A最新動向(2025年)
カフェ業界のM&A市場は活性化が進んでおり、ブランド統合、地域密着型カフェのM&A、DX推進の3つの動向が注目されています。
ブランド統合では、大手チェーンが複数のカフェブランドを統合し、原材料の共同購入や人材配置の効率化を図るケースが増加すると予想されます。統合により経営資源の最適化と市場シェア拡大が進んでいます。
地域密着型カフェは、地域住民との強い関係性を武器にM&Aの対象として注目されています。地域密着型カフェは地域のコミュニティの中核として機能し、固定客との強い信頼関係を築いているという特徴が、M&Aにおける重要な評価ポイントです。
DX推進を目的としたM&Aでは、モバイルオーダーやキャッシュレス決済を導入し、業務効率化と顧客体験向上を図る企業が増加しています。大手がIT企業を買収し、データ分析や店舗運営の最適化を進める動きが加速しています。
今後は、デジタル技術を活用しつつ、カフェ本来の価値を維持する戦略がM&A成功の鍵となるでしょう。
【売り手】カフェ業界がM&Aをするメリット
株式譲渡や事業譲渡などにより、自社の持つ課題を解決できる可能性があります。ここでは、カフェがM&Aをする売り手目線のメリットをご紹介します。
買い手企業のリソースを活用して成長を続けられる
カフェ業界でM&Aによる事業売却を考える経営者にとって、買い手企業の持つ豊富なリソースは大きな魅力となります。特に経営ノウハウや資金力、人材、システム基盤などを活用することで、店舗の成長を加速させることが可能です。
調達力の強化やシステム面での業務効率化、人材採用や教育研修のノウハウ活用による人手不足の解消から設備投資まで、可能性が広がり安定した経営基盤を築くことができます。
従業員や顧客に安定した環境を提供できる
M&Aを通じて買い手企業の経営資源を活用できることで、従業員にとっては安定した雇用環境が、顧客にとっては質の高いサービスが継続的に提供できるようになります。
特に人材面では、買い手企業の充実した研修制度や福利厚生を活用できるため、従業員のスキルアップやモチベーション向上につながります。また、経営基盤が安定することで、長期的なキャリアプランを描きやすい環境が整うでしょう。M&Aを成功させた多くのカフェでは、従業員の離職率が低下し、顧客満足度も向上しているケースも見られます。
事業承継の問題をスムーズに解決できる
事業承継は多くのカフェ経営者にとって大きな課題となっています。M&Aを活用することで、後継者不在の問題を効果的に解決できる可能性が高まります。
特に個人経営の小規模カフェでは、家族内での事業承継が難しく、培ってきた経営資源や従業員の雇用を守れるか不安を抱えている経営者が多いのが現状です。事業承継の成功に向けて、早い段階から事業承継の選択肢としてM&Aを検討し、準備を進めることが重要となります。
【売り手】カフェ業界がM&Aをするデメリット
M&Aには、いくつかのデメリットが存在します。今後M&Aを検討する中で、売り手側が知っておくべき注意点は以下の通りです。
事業譲渡後に経営方針が大きく変わる可能性がある
買い手企業の経営理念や運営方針によって、これまで大切にしてきた店舗の個性や価値観が大きく変わってしまう可能性があります。
特に懸念されるのは、長年かけて築き上げてきた店舗の雰囲気や接客スタイル、メニュー構成などが、買い手企業の標準化された運営方針に統一されてしまうことです。例えば、地域に密着したアットホームな雰囲気のカフェが、チェーン店的な画一的なサービスを求められる可能性があります。
このような変更は、既存の常連客の離反や従業員のモチベーション低下につながる可能性があります。こうしたリスクを最小限に抑えるため、買い手企業と事前に十分な協議を行うようにしましょう。
なお、近年では買い手企業側も、既存店舗の個性や地域性を活かすことの重要性を認識しており、必ずしも全面的な方針変更を行わないケースも増えています。M&A後も店舗の魅力を維持しながら、相乗効果を目指しましょう。
顧客からの信頼維持が難しくなる場合がある
M&A後の経営方針の変更や組織文化の違いにより、長年築き上げてきた顧客との信頼関係が揺らぐリスクがあります。特に地域密着型のカフェでは、常連客との関係性が重要な経営資源となります。
具体的には、メニューの急激な変更や価格改定により、これまで親しんできた味や雰囲気が大きく変わってしまうケースが挙げられます。また、長年勤務していたスタッフの異動や退職により、顧客とスタッフの関係性が途切れてしまうことも考えられます。
これらの問題を防ぐため、M&A後も既存の顧客価値を維持できるよう、顧客とのコミュニケーションを丁寧に行い、信頼関係を維持するよう努めましょう。
譲渡価格が期待より低くなる可能性がある
原材料費の高騰による利益率の低下や、人手不足による人件費の上昇、さらには競合店との競争激化による売上の伸び悩みなどの要因により、将来的なキャッシュフローの見通しが保守的に評価される場合があります。
また、地域密着型の独自性やブランド価値、固定客の存在といった定性的な要素は、数値化が難しく評価額に十分反映されにくい面があります。経営者が長年かけて築き上げた無形の資産が、適切に評価されないケースも見られます。
このような事態を避けるためには、事前に専門家のアドバイスを受けながら、財務内容の改善や経営効率の向上に取り組むことが重要となります。M&A実施の2〜3年前から計画的に準備を進め、企業価値の向上に努めることで、より適正な譲渡価格での売却が可能となるでしょう。
【買い手】カフェ業界をM&Aするメリットデメリット
ここでは、買い手側のメリット・デメリットを整理します。
メリット
カフェ業界のM&Aは、既存ブランドや顧客基盤を即座に活用できる点がメリットです。新規出店ではブランド認知や集客に時間がかかりますが、M&Aならすでに確立された評価や信頼をそのまま引き継ぐことができます。特に地域密着型カフェでは、常連客や地域コミュニティとの強い絆が貴重な資産となります。
さらに、SNSフォロワーや会員データ、商圏分析データなどのデジタル資産も活用可能で、マーケティングや経営戦略に役立ちます。また、既存のスタッフや取引先も基本的には継続可能なため、人材確保や業務フローの構築もスムーズに進みます。
加えて、市場参入のスピードを大幅に短縮できる点も大きなメリットです。物件確保や許認可取得などの準備期間を省略できるほか、すでに営業実績があるため、即座に収益化が可能です。
ただし、成功の鍵は既存の雰囲気や提供価値を維持しながら、慎重に統合を進めることです。ブランドの強みを活かしつつ、段階的な戦略を取ることで、M&Aの効果を最大限に引き出せます。
デメリット
カフェ業界のM&Aにおける買い手側のデメリットとして、期待収益が得られないリスクが挙げられます。買収後に常連客の離反や従業員の退職、競合店の影響、原材料費の上昇などが発生し、売上が低下する可能性があります。また、経営方針の急激な変更によって、店舗の魅力が失われるリスクもあります。
さらに、従業員や顧客への配慮不足は、長年築かれた信頼関係を損ね、事業価値を毀損する原因となります。例えば、待遇の変更や画一的なサービスの導入が、従業員や顧客の不満を招くことがあります。これを防ぐためには、買収前の綿密な調査と慎重な統合計画の実施が不可欠です。
カフェ業界のM&A相場について
M&Aに際してもっとも気になる部分といえるのが価格相場ではないでしょうか。以下では、カフェ業界のM&A相場に関する情報を解説します。
価格は一概には決められない
M&Aの価格は多様な要因によって変動するため、一概に相場を提示するのは難しいものの、類似の取引事例などを参考に算定される場合があります。価格に影響を与える要因として、「財務状況」「収益性」「成長性」「立地条件」「ブランド力」「人材」などが挙げられます。
M&Aにおけるカフェ業界の企業価値の算出方法
M&Aの譲渡価格は、「DCF法」「類似会社比較法」「時価純資産法」など複数の算定方法を状況に応じて使い分け、あるいは組み合わせて算出します。自社の価値について気になる場合は、ぜひ以下の企業価値算定シミュレーションをお試しください。
カフェ業界がM&Aを成功させるためのポイント
カフェ業界のM&Aを成功に導くためには、綿密な事前準備と適切な実行プロセスの管理が重要となります。以下に、特に重要なポイントを4つ解説します。
文化や価値観の統合を円滑に進めるための計画を立てること
カフェ業界のM&Aにおいて、文化や価値観の統合は成功の鍵を握る重要な要素です。特に、長年培ってきた店舗の雰囲気やサービス品質を維持しながら、新しい経営体制へと移行することが求められます。
企業文化の統合を成功させるためには、まず現状の分析から始める必要があります。両社の経営理念、サービス提供方針、従業員の働き方などを詳細に把握し、共通点や相違点を明確にしていきましょう。
さらに、統合後の新しい企業文化をどのように創造していくかという視点も欠かせません。両社の良い部分を活かしながら、より強い組織を作り上げていくという前向きな姿勢で取り組むことで、M&A後の相乗効果を最大限に引き出すことができるでしょう。
従業員や顧客への配慮を徹底し信頼関係を維持すること
カフェ業界のM&A成功には、従業員と顧客への丁寧な配慮が不可欠です。従業員には早期からコミュニケーションを図り、雇用条件の明確化や段階的な制度移行を進め、モチベーション低下を防ぐことが重要です。
顧客対応では、サービス品質や店舗の雰囲気を維持しながら慎重に変革を進める必要があります。特に常連客には、新サービスの導入を丁寧に説明し、信頼関係を継続することが大切です。従業員と顧客の満足度を高めることで、M&A後の持続的な成長を実現できます。
明確な経営目標を設定してM&Aの方向性を定めること
カフェ業界のM&A成功には、明確な経営目標の設定が不可欠です。財務目標(売上・利益率)、店舗運営方針(サービス・価格戦略)、組織体制(人材育成・意思決定)を明確にし、M&A後のビジョンを具体化する必要があります。
特に、買収後の統合プロセスを慎重に設計し、既存の強みを活かしながらデジタル化やブランド戦略を推進することが重要です。また、従業員のモチベーション維持や顧客満足度向上の施策も設定し、定量・定性両面での目標達成を目指すことが成功の鍵となります。
適切なタイミングでM&Aを検討する
理想的なタイミングを逃さないために、「経営状態が安定している時期」や「業界環境の変化」を見極め、2〜3年前から準備を開始することが重要です。
「経営状態が安定している時期」に関して、財務状況が良好で、売上や利益が安定または成長している時期に売却を検討すると、より高い評価を得られる可能性が高まります。
また「業界環境の変化」に関して、原材料費の高騰や人手不足など、今後の経営環境がさらに厳しくなると予想される場合は、早めにM&Aを検討することも選択肢の一つです。特に、競合の出店攻勢が激しい地域では、経営環境の変化を先取りした判断が求められます。
適切なアドバイザーや専門家を活用する
M&Aを成功させるには、プロの力を借りることも大切です。専門知識がない状態で交渉を続けると、不当な条件で売却してしまう可能性も考えられます。プロのサポートを受け、希望の条件での成約を目指しましょう。
カフェ業界のM&A事例
最後に、カフェ業界のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
株式会社サンマルクホールディングスによる株式会社倉式珈琲のM&A
2024年1月19日、サンマルクホールディングス(HD)は、完全子会社である倉式珈琲を吸収合併することを決定しました。本合併は簡易合併・略式合併の形式で行われ、2024年4月1日に効力を発生させる予定です。
サンマルクHDは、「サンマルクカフェ」などを展開し、事業ごとに子会社を設立して運営してきました。しかし、倉式珈琲のフルサービス喫茶業態の収益化が難航しており、経営の効率化を図るため、同社を吸収合併し「倉式珈琲事業部」として再編することを決定しました。これにより、ブランドを維持しつつ、コスト削減や経営資源の最適化を目指す方針です。
倉式珈琲は2015年に設立されましたが、2023年3月期には営業損失3.1億円、純損失4億円を計上し、厳しい経営状況が続いていました。今後、サンマルクHDの直接管理のもとで業態の見直しや事業再構築が進められると考えられます。
外食業界では、コロナ禍後の消費回復が進む一方で、人件費や原材料費の高騰が課題となっています。そのため、M&Aや事業統合による経営の効率化を図る動きが加速している状況です。
【出典】株式会社サンマルクホールディングス「完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ」
株式会社コメダホールディングスによるPOON RESOURCES PTE. LTD.のM&A
2024年9月6日、コメダホールディングス(HD)は、シンガポールの連結子会社KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD.(KIH)を通じて、現地でカフェやタイ料理レストランを展開するPOON RESOURCES PTE. LTD.(POON)の株式70%を取得し、孫会社化する基本合意書を締結しました。
コメダHDは、東南アジア市場での事業拡大を視野に入れ、海外展開を進めています。今回の買収により、POONが展開する「Kaffe & Toast」「Saap Saap Thai」「Ma Mum」などのブランドと連携し、シンガポール国内や東南アジア各国でのコメダ珈琲店の展開を強化する狙いがあります。
POONは、病院や公共施設、ショッピングモールなどに店舗を展開し、ハラル対応のメニューを提供するなど、地域に密着したビジネスモデルを確立しています。これにより、コメダHDは東南アジア市場での成長機会を拡大し、現地の食文化に適応したブランド展開が期待されます。
近年、日本の外食企業は、国内市場の成熟や人件費の高騰を背景に、海外市場への進出を加速させています。今回のM&Aは、コメダHDにとってシンガポール市場への本格参入を意味し、今後の成長戦略の重要な一歩となるでしょう。
【出典】株式会社コメダホールディングス「特定子会社の異動及び当該特定子会社による株式取得(孫会社化)に関する基本合意書締結に関するお知らせ」
ロート製薬株式会社とカフェ・カンパニー株式会社の資本業務提携
カフェ・カンパニー株式会社は、ロート製薬株式会社と資本業務提携を締結しました。本提携により、ロート製薬がカフェ・カンパニーの第三者割当増資を引き受け、同社はロート製薬の持分法適用会社となりました。
カフェ・カンパニーは、「WIRED CAFE」をはじめとする飲食店舗を国内外で展開し、「食を通じたコミュニティの創造」を理念としています。一方、ロート製薬は、医薬品や機能性食品を手がけるほか、農畜産物の生産やレストラン運営にも取り組み、「食」を健康事業の一環として位置づけています。
今回の提携により、ロート製薬の機能性素材や生産技術と、カフェ・カンパニーの飲食店舗運営・商品開発ノウハウを融合させることで、健康的な食生活の提案を強化する狙いがあります。具体的な事業内容は今後協議されますが、カフェ・カンパニー代表の楠本修二郎氏がロート製薬の食分野アドバイザーに就任するなど、連携を深める方針です。
近年、外食業界では「食と健康」をテーマとした事業展開が拡大しています。今回の提携は、飲食業とヘルスケア産業の融合を加速させる事例として注目されます。
【出典】カフェ・カンパニー株式会社「カフェ・カンパニーは、ロート製薬と資本業務提携を締結。」
まとめ|カフェ業界のM&A動向を抑えてM&Aを成功させましょう
カフェ業界のM&A成功には、事前準備と適切なパートナー選びが不可欠です。市場環境や競合分析を行い、自社の強みと課題を明確にすることが重要です。
特に、財務の透明性確保、従業員と顧客との関係維持、適切な企業価値評価が成功の鍵となります。カフェ業界特有のブランド力や顧客ロイヤリティを正しく評価し、統合後のシナジーを最大化しましょう。
2025年に向けてM&Aの活発化が予測される中、DX推進や経営スタイルの変革を視野に入れ、持続的成長を実現する戦略的なM&Aを検討してみてはいかがでしょうか。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















