CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
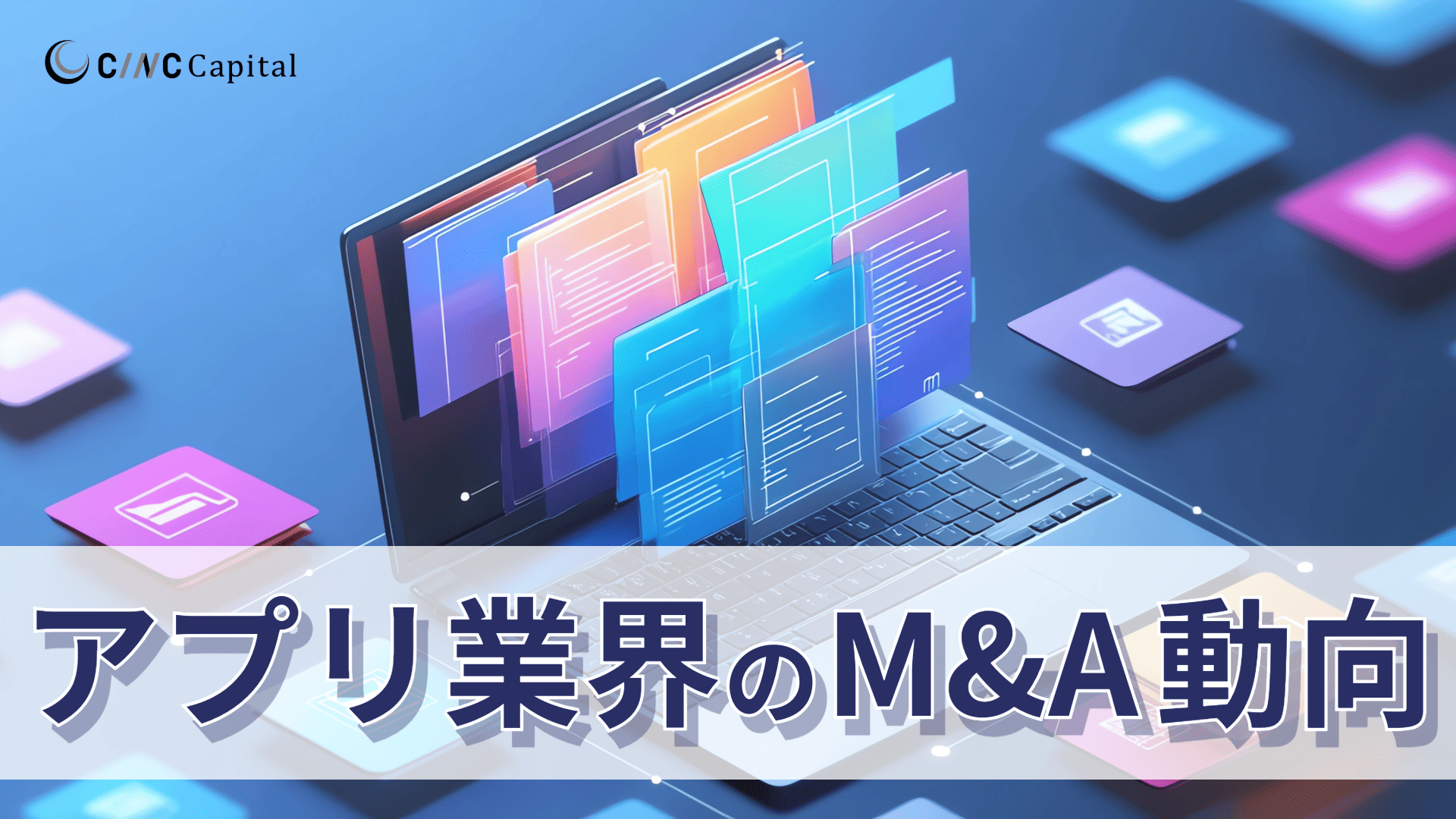
業種
- 最終更新日2025.06.26
アプリ業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
アプリ市場は近年著しい成長を遂げており、今後も事業の統合や買収といったM&Aへの関心が高まり続けると予想されています。特にモバイルデバイスの普及やサブスクリプション型モデルの台頭が、アプリ業界に強い追い風をもたらしています。
ここではアプリ業界の最新動向やメリット・デメリット、成功事例などを踏まえながら、2025年まで視野に入れたM&Aのポイントを解説します。
目次
アプリ業界の市場動向
アプリ市場は年々拡大し、多様化するユーザーのニーズに合わせた新サービスや技術が生まれています。ここではアプリ業界全体の市場の盛り上がりと、今後の推移について概観します。
スマートフォンやタブレット端末の普及に伴い、さまざまな領域でアプリの需要が急上昇しています。ゲームやSNSといった従来の人気ジャンルだけでなく、教育や医療などの専門分野でもアプリ化が進み、ユーザー層が一段と広がっています。こうした拡大トレンドは、国内市場に限らずグローバルにも扉が開かれており、競争はより激化しているのが現状です。
アプリの収益モデルが多様化しており、広告モデルや課金モデルだけでなく、近年ではサブスクリプション型の定額制が幅広く受け入れられています。これはユーザーとの長期的な関係を構築しやすいメリットがあり、安定収益が見込めることから買収ニーズも高まりやすい領域です。こうした背景は、M&Aを通じて迅速に収益化やブランド強化を狙う企業を後押ししています。
大手企業だけでなくスタートアップが次々に参入し、新たな技術やプロダクトを武器に市場を切り拓こうとしています。投資家やVCもアプリ企業に対し積極的に資金を投じており、M&Aによるエグジット(投資回収)を前提とした動きも活発です。今後の市場拡大は確実とみられ、将来的には新しいサービスモデルがさらなる成長を牽引するでしょう。
アプリ業界が抱える課題
急拡大しているアプリ市場ですが、その一方でさまざまな課題も存在します。以下では主に3つの課題を取り上げ、それぞれの背景と課題解決の重要性について解説します。
開発コストの高騰
アプリ開発の競争力を維持するためには、高度なシステム構築やユーザーインターフェースの設計、そしてテスト運用など幅広い工程が必要です。最新技術に対応するための人材確保や研修コストも膨らみやすく、スタートアップにとっては資金面で大きな障壁となります。また、クラウド技術やAIなどの導入も進んでいるため、新規導入や保守費用は年々かさんでいくでしょう。
その結果、多くの企業が手が回らずに開発スピードを落としたり、品質面での不備を残したまま公開してしまうケースが散見されます。こうした事態を防ぐため、開発パートナーや外部資本との連携を検討する必要があります。資本提携やM&Aが開発コストの分散化と質的向上の手段として有力視されるのは、このような背景があるからです。
特に国内だけに固執せず、コスト削減と高度な開発力を求めて海外開発拠点を活用する企業も増えています。クロスボーダーでのM&Aや提携が開発リソースを効率化する上で重要となり、企業規模に関係なく柔軟な選択肢として考慮されるようになっています。
ユーザー獲得の難易度上昇
市場に溢れるアプリの数が増大するにつれ、ユーザーの目が肥え、ニッチなカテゴリーに至るまで高品質を求めるようになっています。広告出稿やキャンペーン、インフルエンサーとのコラボレーションなど、マーケティングにかかる費用は年々高騰中です。
ユーザーを獲得した後も、アクティブ率の維持や購買・課金につなげるための施策が求められます。この継続的な取り組みには、データ分析やUI/UXの改善が欠かせません。こうした対応が後手に回ると、アプリストアのレーティングや口コミに大きく影響が及び、短期間でユーザー離れが進行するリスクも高まります。
そのため、知名度の高い企業や既存顧客基盤を持つ企業とのM&Aにより、早期に安定したユーザー数を確保するケースが増えています。特に大手のプラットフォームや知名度のあるブランドに買収されることで、大規模プロモーションや相乗効果が得られ、市場での存在感を一気に高めることが可能です。
技術革新への対応
アプリ業界ではAIやAR、VRなどの新技術が短いスパンで登場し、ユーザー体験の革新を求められます。そのため、定期的なアップデート対応や技術習得が欠かせず、最新動向を見極める情報収集能力も求められます。
こうした技術革新を活かしたサービス開発を行うには、高度なエンジニアやデザイナーが必須となり、それを支える組織体制も重要です。しかし、多様な分野にわたる専門人材を自社で抱えるのは難しく、タイミングを逃すと競合他社に先を越されるリスクが大きくなるでしょう。
結果として、技術力を持つ企業を自社グループに取り込むM&Aや、専門サービスとの提携が急増する傾向にあります。特に成長が見込める分野に先行投資することで、市場シェアを迅速に拡大する動きが顕著になっています。
アプリのM&A最新動向(2025年)
2025年までにアプリ業界のM&Aはさらに活性化すると見込まれており、新しいビジネスモデルやグローバル展開を見据えた動きが目立ちます。
ここでは、主な動向を3つ見てみましょう。
サブスクリプションモデル企業への注目
サブスクリプション型アプリは安定収益が見込めるため、投資価値が高いと見なされることが多いです。ユーザーから定期的に支払われる料金により、企業側は収益計画を立てやすく、M&A後も収益を維持・拡大しやすい特徴があります。
特に動画配信や音楽ストリーミング、クラウド学習ツールなどは、毎月の定額課金を通じて継続的に利益を生み出せる分野として脚光を浴びています。優れたUI/UXとコンテンツの質を両立できる企業は、高額な評価を受けるケースも珍しくありません。
この分野では、買収後にサービスをグローバル展開させる動きも活発です。既存のサブスクリプションモデルを他国の顧客に横展開することで、急速に売上を拡大できる戦略が注目されています。
海外市場の拡大を目指したクロスボーダーM&A
世界規模で競合他社と争うアプリ業界では、海外市場への進出が大きな成長エンジンとなります。クロスボーダーM&Aによって海外の企業やサービスを統合し、迅速に現地市場に参入する成功例が増えてきました。
現地の法規制や文化的背景への対応が必要になりますが、既に海外展開している現地企業を買収することで、そのノウハウをスムーズに取り込むことができます。これは単なる海外展開のスピードアップだけでなく、現地でのブランド確立やユーザー基盤の獲得にも効果的です。
デジタル領域は国境を超えてサービスを展開しやすい特徴があるため、クロスボーダーM&Aの成否が企業の将来性を大きく左右します。実際に、海外のプラットフォームや開発企業との提携を通じて、新技術や顧客市場を取り込む事例も増加しているのです。
中小規模アプリの吸収統合
特定の分野で人気を集めている中小規模アプリや、一定のユーザーベースを持つニッチアプリは、大手企業にとって魅力的な買収対象となります。すでにある程度のユーザー支持を得ているため、大幅なプロモーションコストをかけずに事業を拡大できるからです。
例えば、限定的な地域向けの特化型サービスや、特定の機能に強みを持つアプリなどが注目されやすいと言えます。こうした買収活動が活発になることで、業界全体の発展速度も加速する傾向があります。
一方で、買収される側の中小企業にとっても、リソース不足を解消したり新技術を導入したりするチャンスとなります。大手の開発力やブランド力を活用して、もともと持っていたサービスをさらに高い次元に引き上げることが可能です。
【売り手】アプリがM&Aをするメリット
株式譲渡や事業譲渡などにより、自社の持つ課題を解決できる可能性があります。ここでは、アプリ業界でM&Aする売り手目線のメリットをご紹介します。
資金の確保
M&Aを活用すると、事業の売却益によって一時的にまとまった資金が手に入ります。これを新規事業開発や既存サービスの拡充、借入金の返済などに充当することで、経営リスクを軽減しながら成長戦略を描きやすくなります。
特に個人やベンチャーキャピタルが株主の場合、M&Aによるエグジットが投資回収の大きな手段となります。経営者や投資家が得た資金を新たな事業へ再投資することで、イノベーションのサイクルが加速する効果も期待できます。
投資家から見ても明確な出口戦略がある企業は評価が高まりやすく、早期からM&Aを想定して事業を進める企業も少なくありません。これがアプリ市場全体の流動性を高め、活性化の要因になっています。
大手企業参加に入ることによるブランド力の向上
売り手のアプリがベンチャーである場合、大手企業の資本や営業チャネルを活用し、一気に認知度を高めることができます。知名度アップだけでなく、既存ユーザーにも安心感を与えやすく、信頼度の向上が期待できます。
大手企業の傘下になることで、共同プロモーションや提携サービスとの連結など、単独では実現しにくい施策に取り組むことができる点も利点です。これにより、従来のサービスに不足していた部分を大手のリソースで補完し、競合との差別化を強化する可能性が広がります。
さらに、販売チャネルが国内にとどまらず、グローバル規模の販路にアクセスできる場合も大いにあります。元々のアプリがもつ強みをさらに生かすことで、より広い市場でブランド力を高めることができます。
リソース不足の解消
開発リソースや人材教育、マーケティングコストなど、中小規模のアプリ企業が抱える課題は多岐にわたります。M&Aを通じて大手や資金力のある企業のグループに入ることで、これらの課題を一挙に解消できる可能性があります。
具体的には、開発費や広告費、専門人材の確保などを支援してもらえるため、新規機能のリリースや国際展開にも取り組みやすくなります。特に高額なライセンス費用やITインフラの整備など、自社単独では負担が大きい部分を補えるのは非常に大きなメリットです。
リソース不足の解決は、アプリそのものの品質向上だけでなく、ユーザー体験の大幅な向上にもつながります。結果として、ユーザー満足度が高まり、さらなる成長の循環を生み出す原動力となるでしょう。
【売り手】アプリがM&Aをするデメリット
M&Aには、いくつかのデメリットが存在します。今後M&Aを検討する中で、売り手側が知っておくべき注意点は以下の通りです。
ブランド独自性の損失
アプリが持つ独自の世界観やデザイン、ユーザーコミュニティは、買収後の組織変更や新方針に合わせて修正される可能性があります。大手のガイドラインや方針に統合されることで、個性的だったイメージが薄れてしまうリスクがあるのです。
特にユーザーコミュニティが強固なアプリの場合、アプリ自体の魅力はコミュニティの存在感と表裏一体となっています。買収先の施策やマーケティングがコミュニティの声に合わないと、急激に活気を失う恐れもあります。
結果として、元々のブランドが築いてきたファンベースを活かし切れず、ユーザー離れを招くケースも考えられます。ブランド独自性を維持するためには、買収前の段階から双方でビジョンをすり合わせることが重要です。
買収条件への制約
M&Aには契約条件や株式譲渡の割合、役員構成など、細かな部分まで合意が必要となります。条件を巡る交渉が難航すると、短期的に経営方針が不安定になりやすい傾向があります。
また、買収後に買い手による経営者の交代や部門の再編成が行われることも少なくありません。こうした変化は売り手が想定していた戦略や組織体制を大きく変える可能性があり、不透明感が拭えない点がデメリットとなります。
さらに、M&A契約においては、原則として売却時の一括払いを目指すべきです。やむを得ず分割払いとなる場合は、確実な支払いを担保する条件(エスクロー口座の活用、親会社保証など)を設定することが重要です。
近年海外ではアーンアウト方式も見られますが、日本国内の一般的なM&Aでは推奨されず、売り手側のリスクが大きいため避けるべき手法と言えます。事前にシナジーや収益計画の実現性を十分に精査しておくことが不可欠です。
ユーザーの不満や離脱リスク
M&Aに伴い運営体制や開発方針が変わると、既存ユーザーにさまざまな影響が及ぶ可能性があります。例えば、機能の変更や料金体系の見直しなどが行われる場合、ユーザーの不満が一気に高まるかもしれません。
また、新たなブランドイメージが既存のユーザー層と合わず、ユーザーに『別物になってしまった』という印象を与えるリスクもあります。こうした状況が生じると、ネガティブな口コミや低評価レビューが増え、離脱者の拡大を招く可能性があるでしょう。
ユーザー離脱を防ぐためには、M&A後の運営方針やサービス改善点をしっかりと周知し、ユーザーコミュニケーションを丁寧に行うことが大切です。買収元の知名度やリソースを活かしつつ、従来の魅力を損なわないバランスが求められます。
【買い手】アプリをM&Aするメリットデメリット
買い手側は、アプリの既存ユーザーベースを活用して事業拡大を図れる一方で、買収・統合に伴うリスクも考慮しなければなりません。
買い手にとってのメリットは、すでに一定のユーザー数と認知度を獲得しているアプリを手に入れられるという点です。開発初期のリスクを回避しつつ、時間とコストを大幅に節約できるため、新規参入よりも効率よく市場での地位を築けます。
一方で、買収先の組織融合や方針調整が円滑に進まなかった場合、統合コストの増大や事業運営の混乱が発生するリスクがあります。特に開発体制やカルチャーの違いは、予想以上に現場レベルで摩擦を引き起こすことがあります。
また、アプリのユーザーコミュニティの感度が高い場合、買収後の変更に対して強い抵抗感を示すことも考えられます。こうした点を踏まえ、買い手側は対象アプリのブランドやカルチャーを尊重しながら、適切なタイミングで統合を進める必要があります。
アプリ業界でM&Aを成功させるためのポイント
アプリ業界のM&Aを成功に導くためには、綿密な事前準備と適切な実行プロセスの管理が重要となります。以下に、特に重要なポイントを3つ解説します。
適切な評価を得る
アプリ企業のM&A評価では、一般的に『EBITDA×マルチプル』方式や『時価純資産+営業権』方式が用いられます。特にアプリ業界では収益安定性によってマルチプルが3~8倍程度まで変動する点が特徴です。サブスクリプションモデルのように継続収益が見込める場合は高いマルチプルが適用される傾向があります。
M&Aプラットフォームや専門家が提供する評価ツールを活用すると、市場相場との比較分析も行いやすくなります。企業価値の正確な算出は、売り手と買い手が互いに納得感を得る上で不可欠です。
適切な評価を受けるためには、日頃から経営指標や開発状況を整理し、財務諸表だけでなくアプリの利用状況など定量データを確認できる体制を整備することが重要です。
明確な戦略目標を設定する
買収後の統合方針やシナジーの目標を明確にしておくと、M&Aプロセス全般で一貫した意思決定が可能になります。特にアプリの場合、開発の方向性や機能追加の優先順位など、具体的なロードマップが必要です。
また、売り手アプリの強みや弱点を分析し、買い手企業がそれをどのように補完するのかを事前に検討することが大切です。両社の強みを活かして戦略を組み立てることで、利用者への価値提供を最大化することができます。
戦略目標を設定する段階では、技術者やマーケティング担当者など実務レベルの声を反映することも忘れてはなりません。現場の声を取り入れることで、実行可能で効果的な方策を立案できます。
適切なアドバイザーや専門家を活用する
法務や財務関連の知識はもちろん、アプリ市場の動向や技術面にも精通した専門家のサポートが不可欠です。M&Aでは契約書やデューデリジェンスなど多くの法的・実務的手続きがあり、本業に集中できなくなるリスクを避けるためにもアドバイザーの活用が望まれます。
近年では、バトンズやTRANBIなどのマッチングプラットフォームが充実してきており、売り手と買い手の双方を専門家が手厚くサポートするケースが増えています。成約事例やアドバイザーによる実務サポートを活用することで、スムーズな取引とリスク低減が期待できます。
適切なアドバイザーの選定が進むことで、企業価値や交渉条件もより公平かつ透明な形になりやすく、双方が納得するスピーディなM&Aが実現しやすくなるでしょう。
アプリ業界のM&A成功事例
最後に、アプリ業界のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
アクセルマーク株式会社によるスパイラルセンス株式会社のM&A
アクセルマーク株式会社は、2024年12月にスパイラルセンス株式会社の全株式取得に向けた基本合意を締結しました。スパイラルセンス社は、ゲーム・アプリ開発やXR開発、Web制作を手がける企業で、エンタメ分野に強みを持ちます。
本件は、アクセルマーク社が注力するトレーディングカード(トレカ)事業の拡大戦略の一環であり、EC開発や人材サービス領域の強化、グループ全体の開発体制・収益性向上を目的としています。広告事業とのシナジーも期待されており、成長領域での多角化を目指すM&A事例といえます。
【出典】アクセルマーク株式会社「子会社等の異動を伴う株式譲渡契約に関する基本合意書締結のお知らせ」
GMOメイクショップ株式会社によるanect株式会社のM&A
GMOメイクショップ株式会社は、2024年10月1日付で、モバイルアプリ開発プラットフォーム「Appabrik」を展開するanect株式会社の全株式を取得し、連結子会社化しました。EC市場が拡大を続ける中、顧客とのエンゲージメント強化においてモバイルアプリの重要性が増しています。
今回のM&Aにより、GMOメイクショップはアプリを通じた購買体験の高度化を図り、OMO対応やリピート率向上を狙います。anectの開発力と同社のEC構築SaaSとのシナジーで、事業者へのソリューション提供力を一層強化する動きといえます。
【出典】GMOメイクショップ株式会社「GMO メイクショップによるanect 株式会社の株式取得のお知らせ」
株式会社fonfunによる株式会社ゼロワンのM&A
株式会社fonfunは、2024年3月に株式会社ゼロワンが運営するノーコード業務アプリ開発SaaS事業を41百万円で譲り受けることを決定しました。本事業は、CRM領域での実績もあるクラウド型ソリューションで、顧客のDX推進に貢献するものです。
fonfunではSMS事業とのシナジーや、DX支援事業の拡大を図る中期経営計画の一環として、本件を実施。損益は改善傾向にあり、運営統合により利益確保と3~4年での投資回収が見込まれています。業務課題解決を支援する体制強化として注目されるM&Aです。
【出典】株式会社fonfun「ノーコード業務アプリ開発SaaS事業の譲受に関するお知らせ」
まとめ|アプリのM&Aを円滑に進めるために
アプリ業界のM&Aは、業界の進化に合わせてますます重要性を増していきます。慎重な計画と的確な判断が、双方にとっての理想的なM&Aを実現する鍵となるでしょう。
アプリ市場は技術革新やユーザー嗜好の変化がめまぐるしく、市場機会もリスクも同時に拡大している状況です。M&Aを検討する上では、短期的な利益だけでなく、中長期的な事業ビジョンやユーザー体験を重視する姿勢が不可欠といえます。
成功への近道としては、早い段階から適切な評価と綿密な戦略目標を設定し、専門家の力を借りながら交渉・統合プロセスを進めることが大切です。これに加えて、買収後のユーザーコミュニケーションを手厚く行うことで、ブランド独自性を損なうリスクを抑えつつ、拡大路線を走ることができます。
今後もアプリ業界のM&Aは一層活発化する見通しがあるため、準備を怠らず適切なタイミングを見極めることが重要です。企業の価値最大化とユーザーの満足度向上、双方を意識した施策こそが円滑なM&A成功のカギとなります。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















