CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
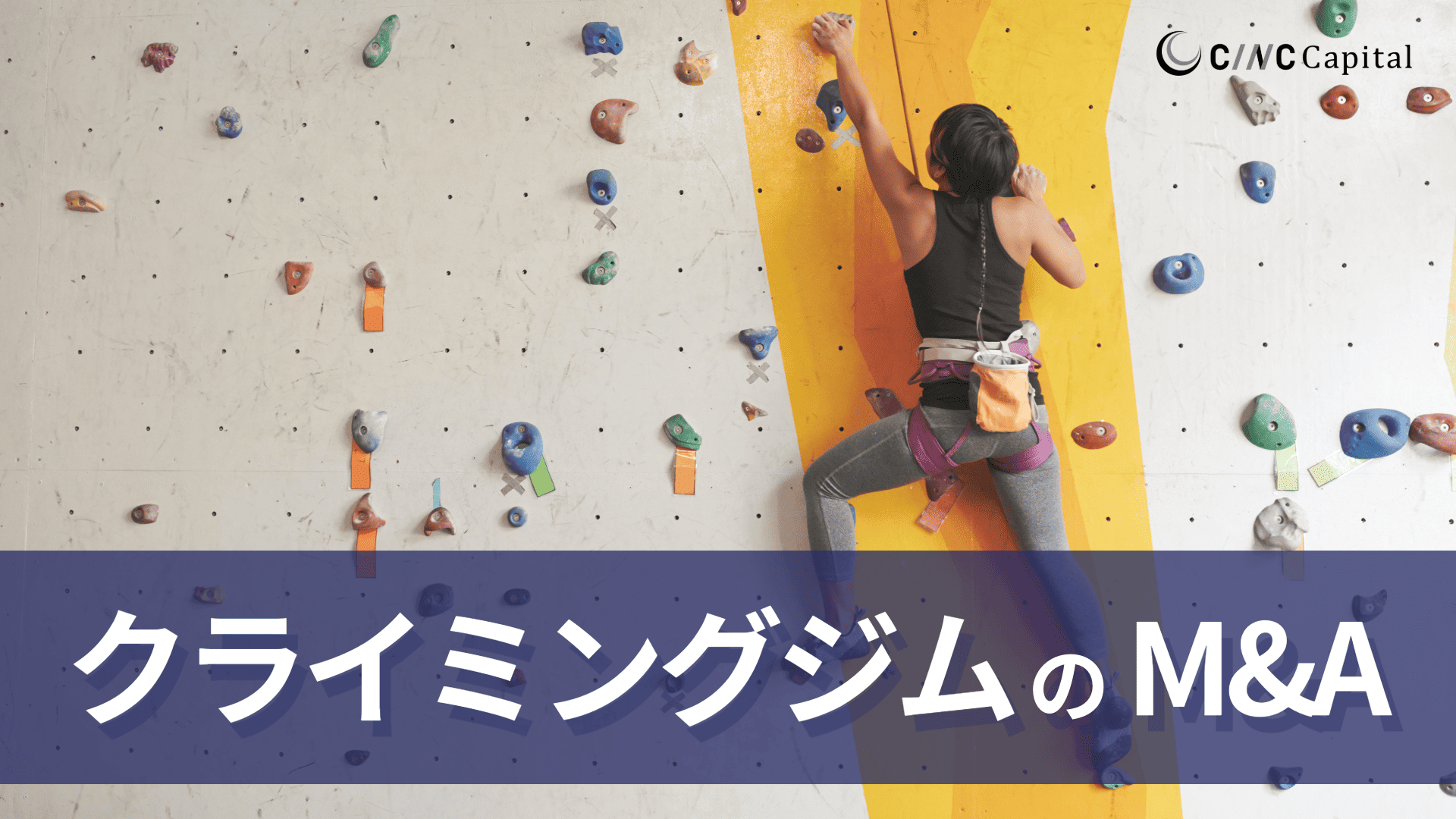
業種
- 最終更新日2025.06.26
クライミングジム業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
東京オリンピックで競技として採用されたことを機に、日本でもクライミング人口が増加しています。成長途上の日本市場、そして国内のクライミングジムでは、専門人材の確保難や設備投資の負担、会員獲得競争の激化といった経営課題が見られます。
こうした問題の解決策として選択肢に入るのがM&Aです。この記事では、2025年のクライミングジム業界におけるM&A最新動向やメリット・デメリット、成功のポイントをお伝えします。
目次
クライミングジムの市場動向
「Grand View Research」のレポートによると、世界のクライミングジム市場は2024年に約33億ドル規模に達し、2030年までの年平均成長率(CAGR:Compound Annual Growth Rate)は約9.3%になると予想されています。
特筆すべきは、ボルダリング専門施設の急増です。この「ボルダリングブーム」が業界全体の成長を牽引しています。実際、ボルダリング市場における2023年の市場規模は、約15億米ドルから2032年には約40億米ドルへと拡大する見通しです。本市場もまた、年平均成長率が約8%と拡大傾向にあります。
また、「公益社団法人 日本山岳・スポーツクライミング協会」が発表した2021年の資料によると、日本国内におけるクライミングジムはおよそ800店舗にのぼります。なかでもボルダリングは初心者も取り組みやすいため、商業施設などで幅広く展開されています。
【出典】Grand View Research「Climbing Gym Market Size & Trends」
【出典】Business Research Insight「ボルダリングジム市場の概要」
【出典】公益社団法人 日本山岳・スポーツクライミング協会「中・長期経営計画(中期編)2021年〜2025年」
クライミングジム業界が抱える課題
日本のクライミングジム業界は、さまざまな経営課題に直面しています。専門人材の確保難、継続的な設備投資の負担、そして会員獲得競争の激化が、市場拡大の障壁となっているのです。詳しく見ていきましょう。
施設運営に必要な専門技術者の確保
クライミングジム運営における最大の課題は、専門人材の確保です。特に「ルートセッター」と呼ばれる壁面課題の設計者の不足が、多くのジム経営者を悩ませています。
ルートセッターは単なる壁面装飾係ではありません。利用者の技術レベルや好みを熟知した上で、安全性と挑戦性を兼ね備えた壁面課題を考える専門家です。「楽しく挑戦できる課題」と「確実に技術が向上する課題」のバランスを取る高度な技術が求められます。
東京オリンピックでスポーツクライミングが正式種目となって以降、全国的にジム数が急増しましたが、専門人材の育成はそのペースに追いついていません。優秀なルートセッターの育成には数年の経験と継続的な研修が必要であり、短期間での人材供給が難しいのが実情です。
施設維持・更新のための設備投資負担
クライミングジム経営では、壁面やホールド(クライミング用の突起物)など設備の定期的な更新・メンテナンスが必須です。これには多額の資金が必要となり、中小規模ジムを中心に大きな経営負担となっています。
会員獲得の競争激化
施設数の増加にともない、新規会員獲得をめぐる競争は年々厳しさを増しています。都市部では限られた顧客層を奪い合う状況となっており、各ジムは独自の差別化戦略を模索している状況です。
例えば、最新設備の導入や魅力的なホールドを使った「映える課題」の設定など、視覚的アピールを重視するジムがあります。一方、特定のクライミングスタイルへの特化や地域コミュニティの形成に力を入れるなど、独自の魅力を打ち出す方針で運営を行うジムも見られます。
クライミングジム業界のM&A最新動向(2025年)
ここでは、2025年におけるクライミングジム業界のM&A最新動向を解説します。着実にクライミングジムの人気が高まっている日本において、どのような動きが起きているのでしょうか。
大手フィットネスチェーンによる個人経営施設の買収
大手フィットネスクラブを運営する企業が、クライミング・ボルダリング施設を買収する動きが見られるようになっています。従来型のフィットネスサービスとの差別化を図るための戦略であり、短期間で事業エリアを拡大しつつ、多様化する顧客ニーズに応えるのが狙いです。
地域密着型ジム同士の経営統合
経営基盤を強化するため、地域密着型クライミングジムの経営統合の動きも出てきています。施設の老朽化対策や設備更新のための投資負担を軽減し、激化する競争環境で生き残るための戦略として注目されています。
異業種からの参入と多角的経営の展開
クライミングジム業界では、関連する異業種からの参入によるM&Aも見られるようになりました。クライミングが単なるスポーツではなく、コミュニティ形成やライフスタイル提案としての価値を持つことが広く認識された結果です。例えば、レジャー産業やアウトドア関連企業、健康産業などからの参入により、施設の多機能化が実現するケースがあります。
クライミングジム経営者がM&Aで売却するメリット
事業承継・事業売却は、経営課題を効果的に解決し、事業発展を実現する手段の一つです。ここでは、クライミングジムを売却するメリットについて、売り手側の目線で解説します。
専門インストラクターの確保・育成体制強化
個人経営のジムでは体系的な人材育成プログラムの構築が難しく、優秀なスタッフの確保・定着が経営課題となっています。M&Aにより、買い手企業が持つ研修システムを活用することで、インストラクターの技術向上と定着率改善が期待できるでしょう。
また、グループ企業内での人材交流も重要なメリットです、さまざまな施設での経験を持つインストラクターの受け入れや、スタッフの技術交流が可能になり、指導レベルの底上げにつながります。
会員プラットフォームの共有と顧客基盤拡大
複数施設間での会員相互利用が可能になることで、「どの店舗でも利用できる」という顧客メリットが生まれます。会員満足度の向上と定着率改善が期待できるでしょう。
また、買い手企業のマーケティングノウハウや広告宣伝力も大きな武器となります。単独では実行困難だった大規模プロモーションや効果的な集客活動により、新規顧客を獲得しやすくなります。
競技者育成環境の整備
個人経営のジムでは、オリンピック基準に適合した施設整備や指導体制構築のための資金・知見が不足しがちです。買い手企業の資金力と専門性を活用すれば、世界水準の競技環境整備も可能です。
また、オリンピック正式種目としての認知度向上は、クライミングジムへの注目度を高め、新たな顧客層の開拓が期待できます。買い手企業のブランド力と組み合わせることで、市場拡大の波に乗る絶好の機会が得られるでしょう。
クライミングジム経営者がM&Aで売却するデメリット
M&A(合併・買収)には、経営効率化や市場拡大が期待できる一方、見落とされがちなデメリットもあります。ここでは、クライミングジムをM&Aをするデメリットをご紹介します。
コアユーザーが離れるリスク
商業化されたボルダリングジムは、クライミング文化全体の一部分にすぎません。M&A後に経営陣がクライミング文化への深い理解を欠いたまま意思決定を行うと、施設の本質的魅力が低下し、コアユーザーが離れていくリスクがあります。
また、多くのクライマーにとって、ジムは「第二の居場所」としての意味を持ちます。買収後に施設の内装が企業カラーに統一されたり、地域に根ざした独自イベントが中止されたりすると、長年の常連客が離れていくケースが少なくありません。
高スキル人材の流出リスク
異なる企業文化の衝突により、従業員のモチベーションや生産性低下を招く恐れがあります。クライミングジムのような専門技術を要する業界では、こうした人材面での問題がサービスの質に直結するものです。例えば、新経営陣の方針とスタッフの価値観が一致しないと、サービス品質が低下したり、離職したりする可能性が高まります。
クライミングジム経営者がM&Aで売却を成功させるためのポイント
業界特有の課題を理解し、適切な準備を行うことで、事業承継・事業売却の成功確率を高めることができます。以下、3つのポイントに分けて解説します。
インストラクター・スタッフの技術体系化
クライミングジム事業の価値を高めるには、インストラクターやスタッフの技術・ノウハウを体系化することが重要です。特定の人材に依存したビジネスモデルではなく、システム化された運営体制の構築がポイントとなります。
具体的には、インストラクターの指導メソッドや顧客対応のノウハウをマニュアル化し、誰でも一定水準のサービスを提供できる体制を整えましょう。初心者向け指導プログラムや上級者向けトレーニング方法など、ジム独自の指導法を文書化することで、事業の付加価値が高まります。
設備資産の適正評価と耐用年数の明確化
クライミングジム事業では、壁面設備やホールドなどの専門設備が重要資産となります。そのため、設備の状態、購入時期、定期的なメンテナンス履歴を詳細に記録し、資産価値を適切に評価・提示しましょう。
競合との差別化ポイントの整理
自社独自の強みや特長を可視化し、買い手企業に対して明確な価値提案をしましょう。立地条件、設備特性、提供サービスの独自性など、競合ジムとの差別化ポイントを明確にし、自社の優位性を示すことが重要です。
クライミングジム業界のM&A事例
最後に、クライミングジム業界のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
株式会社ルネサンスによる株式会社 BEACH TOWNのM&A
スポーツクラブ運営の株式会社ルネサンスは、2021年4月にアウトドアフィットネス事業を展開する株式会社BEACH TOWNの株式51.7%を取得し、子会社化することで基本合意しました。
BEACH TOWNは、公園や自然を活用したヨガやランニングなどのプログラムを全国24か所で運営し、パークPFI事業でも実績を持つ企業です。
ルネサンスはこれまでにもアウトドアフィットネスを取り入れた取り組みを行ってきており、今回の提携により当該事業の拡大と地域活性化支援に拍車をかける狙いです。
コロナ禍におけるニーズの高まりや、官民連携事業(PPP)での展開強化を見据えた戦略的なM&Aといえます。
【出典】株式会社ルネサンス「アウトドアフィットネスを展開する株式会社 BEACH TOWN の株式取得について基本合意書を締結したことに関するお知らせ」
北陸電気工事による桜ヶ池クライミングセンターのM&A
2020年、北陸電気工事(北陸電工)は富山県南砺市が所有する「桜ケ池クライミングセンター」を、1100万円で取得しました。施設は老朽化が進んでいたことから、同社が改修しつつ、これまで通り運営を継続する方針です。
高所作業を伴う送変電工事や配電線工事を主力とする北陸電工にとって、クライミングと事業の親和性は高く、人材確保や選手のセカンドキャリア支援も視野に入れた戦略的な取得といえます。
また、SDGsの推進や大会の誘致による地域活性化も期待されています。地方創生と企業活動を融合させた特色ある事例です。
【出典】日本経済新聞「北陸電工、クライミング施設取得 南砺市から1100万円で」
株式会社テーオーホールディングスによる株式会社テーオー総合サービススポーツクラブ事業のM&A
テーオーホールディングスは、連結子会社であるテーオー総合サービスのスポーツクラブ事業を、2022年1月1日付で株式会社オカモトに譲渡しました。
対象事業は1980年から運営され、道南地域唯一の「健康増進施設」として長年地域に貢献してきましたが、少子高齢化やコロナ禍の影響により厳しい経営環境が続いていました。
事業の継続と発展を図るため、全国600店舗以上を展開し「JOYFIT」などを運営するオカモトグループへの譲渡を決定。同グループとの事業シナジーが期待されるとともに、利用者へのサービス継続が可能となる意義ある事例です。
【出典】株式会社テーオーホールディングス「連結子会社の一部事業の譲渡に関するお知らせ」
まとめ|クライミングジム業界のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
クライミングジム業界特融の経営課題を解決するには、インストラクターの技術体系化や設備資産の適正評価など、専門的な準備が不可欠です。業界特性を熟知したM&Aの専門家に相談することで、これらを解決するヒントが得られるでしょう。今後、事業承継・事業売却を検討している経営者は、M&A仲介会社などのアドバイザーに相談してみてください。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















