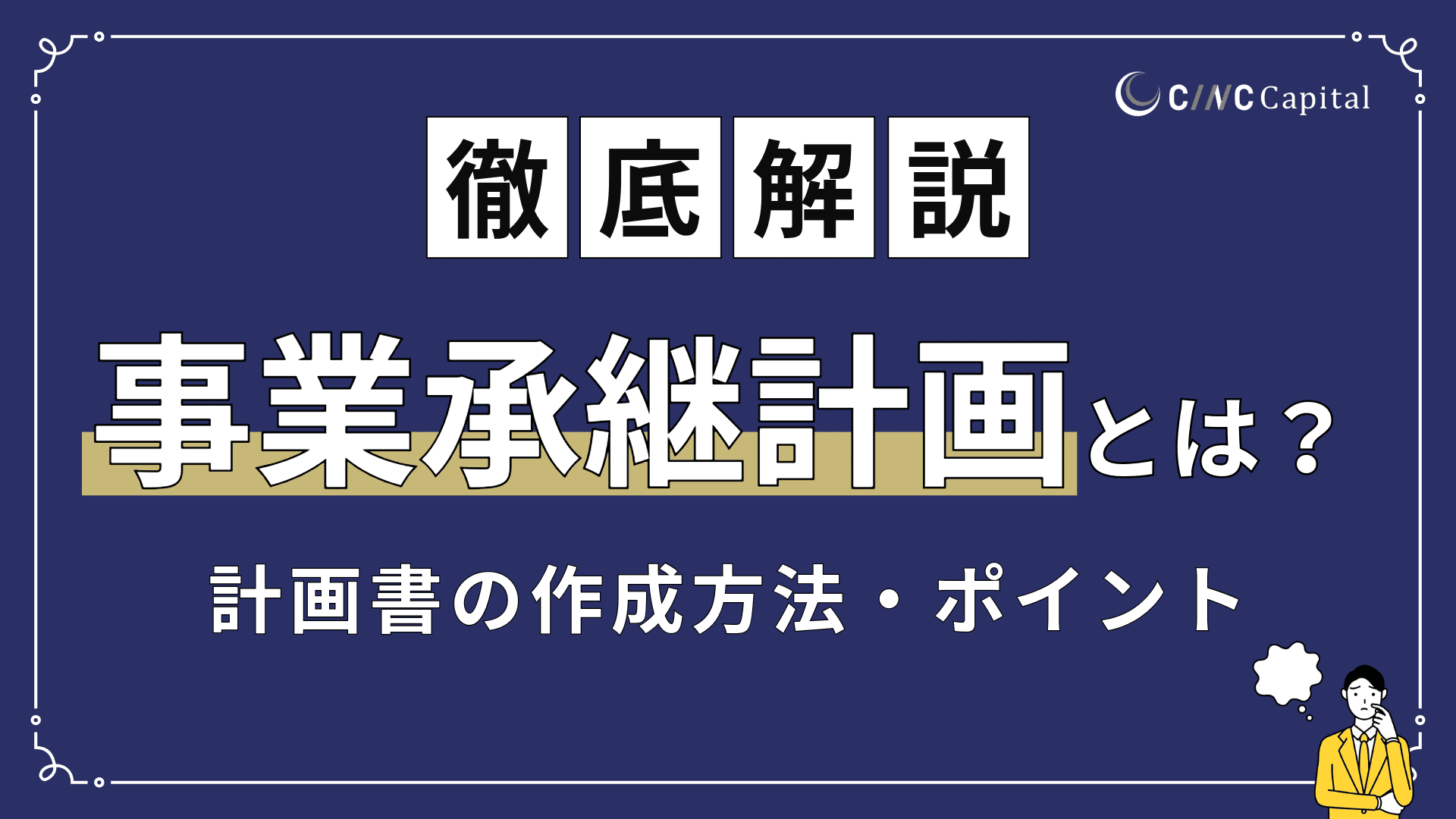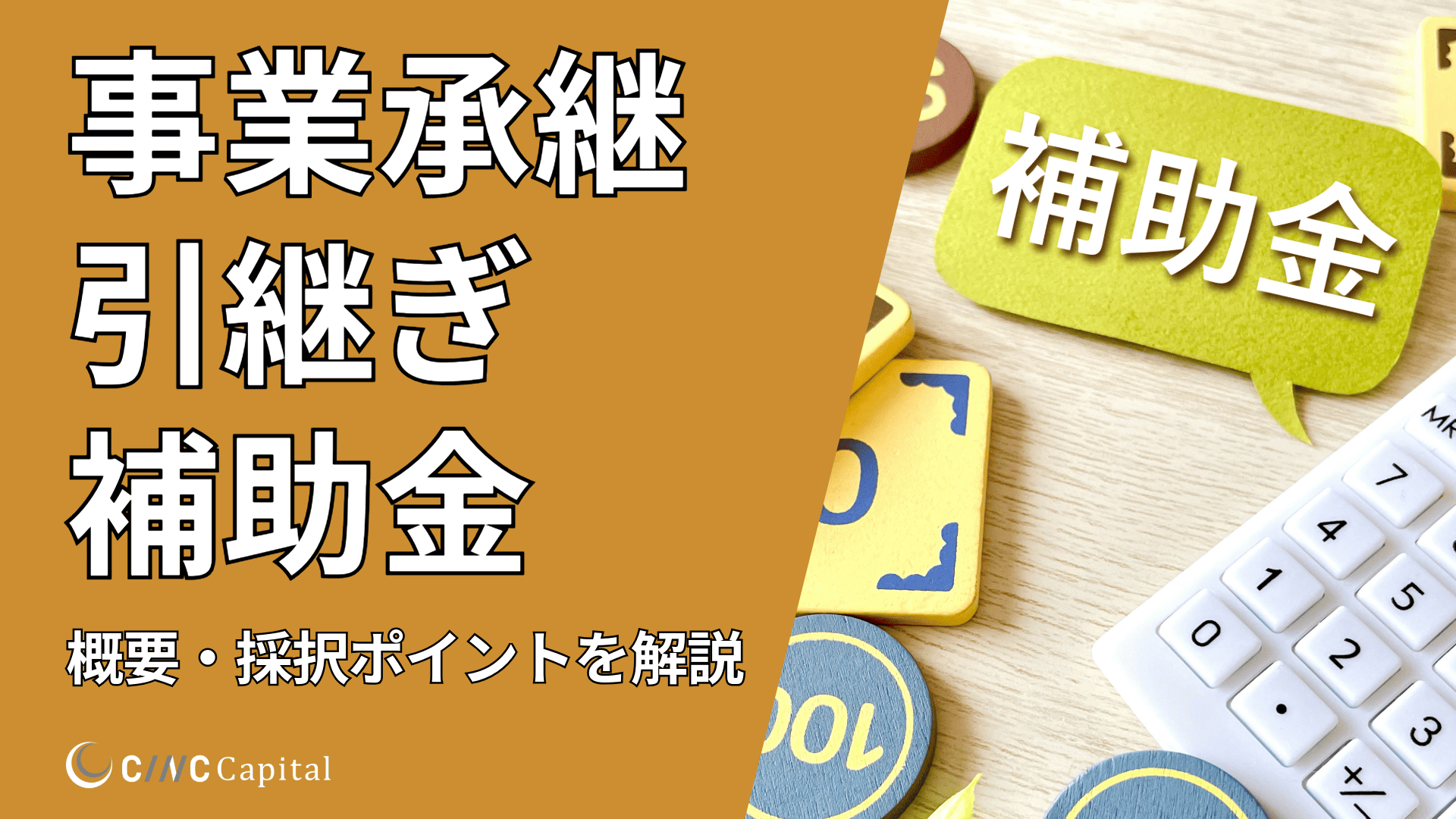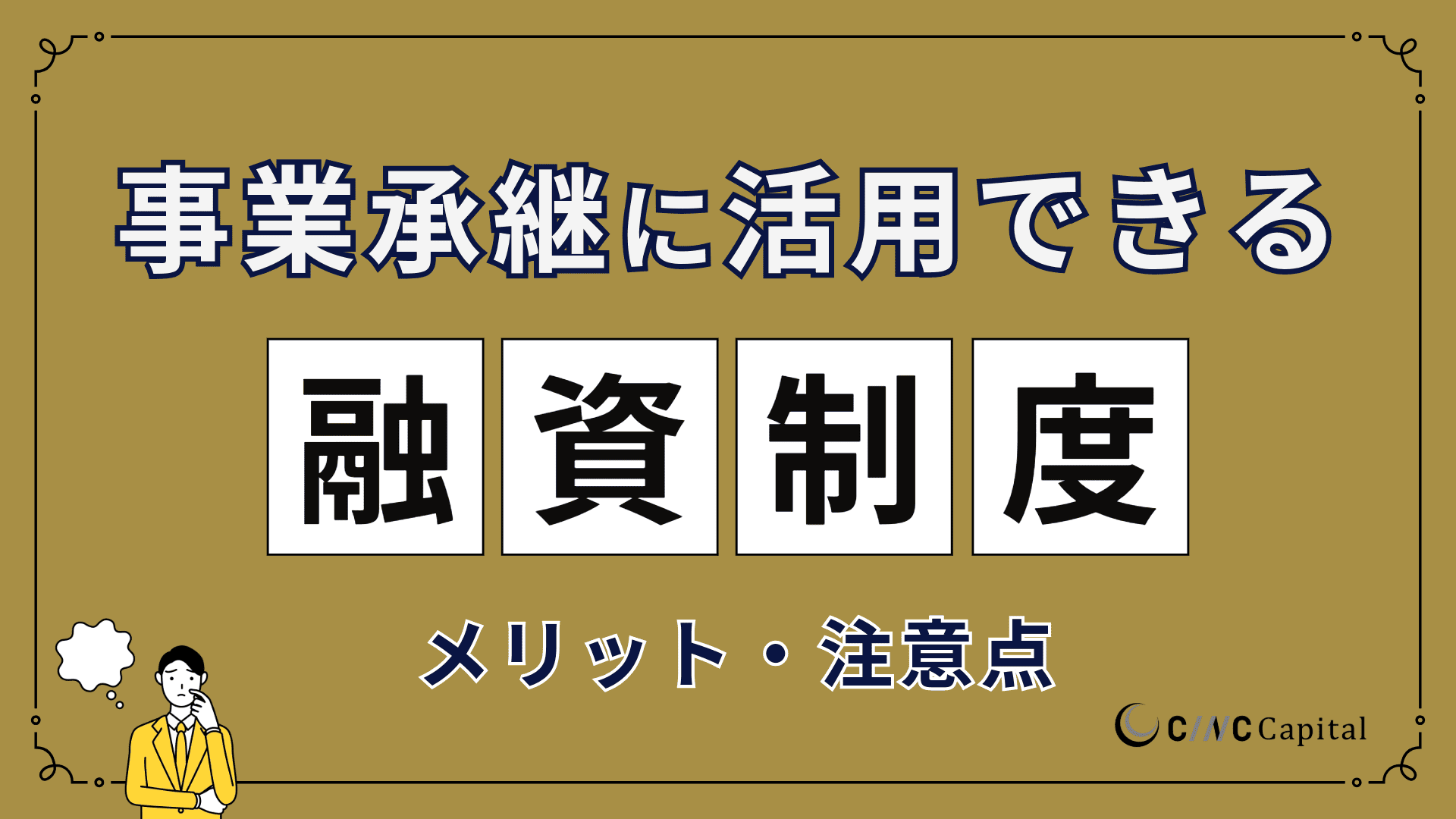CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

事業承継
- 最終更新日2025.07.08
事業承継型M&Aとは?メリットやデメリット、成功させるためのポイントを解説
近年、日本では中小企業の後継者不足が深刻な問題となっており、事業承継に悩む経営者が増えています。親族内での承継が難しい場合や、経営を引き継ぐ適任者が見つからない場合、M&Aを活用した「事業承継型M&A」が有効な選択肢となります。
しかし、「M&Aは大企業が行うもの」「従業員の雇用はどうなるのか」といった疑問や不安を抱く経営者も少なくありません。
本記事では、事業承継型M&Aの仕組みやメリット・デメリット、成功させるためのポイントについて解説します。
目次
事業承継型M&Aとは?
事業承継型M&Aとは、M&A(企業の合併・買収)を活用して事業承継を行う手法を指します。自社内に後継者がいない場合でも、第三者に事業を譲渡することで、存続を可能にする方法です。
かつては後継者がいなければ、経営者の引退とともに廃業することが一般的でした。しかし、廃業すると従業員の雇用が失われ、取引先のビジネスにも影響を及ぼす可能性があります。また、長年築いてきた商品やサービスを利用できなくなる顧客も出てくるでしょう。
このような課題を解決する手段として、事業承継型M&Aが注目されています。譲受企業との相乗効果(シナジー)が期待できる場合、事業のさらなる発展も見込める点が大きなメリットです。
M&Aと事業承継は、厳密にいえば同じ意味ではありません。事業承継は、現在の経営者が後継者に経営を引き継ぐことを指します。一方、M&Aは企業や事業の売買・合併を指し、事業承継の手法の一つとして活用されます。
事業承継型M&Aの現状
政府が後押ししている
日本では、中小企業の後継者不足が深刻化しており、政府もM&Aによる事業承継を積極的に支援しています。後継者が見つからずに企業が廃業すると、雇用が失われ、地域経済に悪影響を与える可能性があるためです。
中小企業庁では、事業承継・M&Aによる中小企業の成長を実現するために、支援体制の強化へ積極的に取り組んでいます。具体的には、中小企業を対象としたM&Aガイドラインの整備や、支援機関登録制度の充実化などが進められています。
近年、事業承継型M&Aは単なる後継者対策にとどまらず、企業の成長戦略や業界再編の手段としても活用されるケースが増加傾向です。特に、中小企業が競争力を維持・強化するために、大手企業やほかの同業者と統合する動きが加速しています。
例えば、地方の老舗企業が全国展開を目指す際に、大手企業の傘下に入ることでブランド力や営業力を強化する事例もあります。また、業界内での再編が進めば、資源の最適化や経営の効率化が実現しやすくなるでしょう。
【出典】中小企業庁「事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について」
事業承継型M&Aのメリット
事業承継型M&Aには、後継者不在や従業員の雇用維持など、多くの問題を解決できるのがメリットです。ここでは、それぞれのメリットについて具体的に解説します。
後継者不在の問題を解決できる
経営者の高齢化が進む中、親族や社内に適切な後継者が見つからず、事業の存続が難しくなるケースが増加中です。事業承継型M&Aを活用すれば、第三者に経営を引き継ぐことが可能になり、後継者不在の問題を解決できます。特に、事業譲渡を選択することで、幅広い買い手候補の中から最適な承継先を見つけられる可能性が高まります。
連帯保証の解除や税負担の最適化
多くの中小企業経営者は、会社の借入に対して個人保証を行っており、引退後の負担が懸念されます。M&Aによる事業承継を行うと、金融機関との交渉次第で個人保証を解除できる可能性が高まります。また、M&Aによる承継では株式譲渡益への課税のみとなるため、事業承継税制と比較して相続税や贈与税の複雑な対応が不要です。
従業員の雇用を安定させることができる
企業を廃業した場合、従業員は職を失い、雇用が不安定になります。しかし、事業承継型M&Aを活用すれば、従業員の雇用を維持しながら経営を引き継ぐことが可能です。特に、譲受企業が人材やノウハウを評価し、積極的に活用する場合には、従業員にとっても安定した職場環境が確保されるでしょう。
事業の存続と発展を実現しやすくなる
M&Aによる事業承継では、単に会社を存続させるだけでなく、譲受企業の経営資源やノウハウを活用することで、さらなる成長を実現しやすくなります。例えば、譲受企業の技術や販売網を活用することで、新たな市場の開拓や事業の拡大が期待できます。単独では困難だった成長戦略を加速できる点が大きなメリットです。
創業者利益を得る機会を確保できる
M&Aを通じて事業を譲渡することで、経営者は自社株を売却し、創業者利益を得られます。引退後の生活資金を確保したり、新たなビジネスに挑戦したりするための資金を手に入れることが可能です。また、親族内承継とは異なり、M&Aでは契約によって引継ぎ時期や条件が明確に決まるため、経営者が計画的に引退準備を進められます。事業の成長に貢献してきた経営者にとって、さまざまなメリットが期待できます。
取引先や地域社会との関係を維持しやすくなる
企業の廃業は、取引先や地域経済にも大きな影響を与えます。しかし、事業承継型M&Aを活用することで、取引先との関係を維持し、地域経済への貢献を続けることが可能です。また、譲受企業が地元企業との連携を重視する場合には、地域社会とのつながりをさらに強化できるでしょう。
事業承継型M&Aのデメリット
事業承継型M&Aには多くのメリットがある一方で、譲渡企業にとって無視できないデメリットも存在します。リスクを事前に把握し、適切な対策を講じることで、スムーズなM&Aを進められるでしょう。
経営方針や企業文化の変化に適応する必要がある
事業承継型M&Aでは、経営権が新たなオーナーに引き継がれるため、これまでの経営方針や企業文化に変化が生じる可能性があります。特に、譲渡企業が長年培ってきた価値観や社風が新たな経営者の方針と合わない場合、従業員の戸惑いや業務の混乱を招くことも考えられます。
経営の一貫性を保つためには、M&Aの交渉段階で譲受企業のビジョンや方針をしっかり確認し、自社の価値観と大きく乖離しないか慎重に判断することが重要です。
従業員や取引先が不安を感じるおそれがある
M&Aによって経営者が交代すると、従業員や取引先は将来の雇用や取引関係に対する不安を抱く可能性があります。特に、待遇や雇用条件の変更、新しい経営陣の意向による組織再編が行われる場合、従業員のモチベーション低下や離職につながるリスクもあります。
また、取引先にとっても、経営方針の変化による契約内容の見直しや取引条件の変更が懸念されるため、不信感を抱かれるケースもあります。こうした問題を回避するためには、M&Aの計画段階から従業員や取引先に対して丁寧な説明を行い、できる限りの不安を解消することが大切です。
売却条件や価格が希望に添わない場合がある
事業承継型M&Aでは、必ずしも希望通りの条件で売却できるとは限りません。譲渡企業側が想定する企業価値と、市場における評価が一致しないケースも多く、売却価格が期待を下回る可能性があります。また、買い手候補との交渉が難航し、当初の希望条件を調整せざるを得なくなることもあります。
希望する条件での売却を成功させるためには、早い段階からM&Aの準備を進め、複数の買い手候補を比較検討することが重要です。
事業承継型M&Aを行う際のポイント
事業承継型M&Aで成功を収めるためには、タイミングや支援制度の活用、専門家への相談など、複数の要素が重要です。ここでは、事業承継型M&Aを円滑に進めるためのポイントを紹介します。
補助金や税制を活用する
事業承継を進めるためには、公的な支援制度を最大限に活用することが重要です。特に、事業承継税制や、事業承継・引継ぎ補助金などの制度は事業承継型M&Aにおいて大きな助けとなります。
事業承継税制は、後継者が前経営者から株式や資産を受け継ぐ際に、一定の条件を満たすことで贈与税や相続税の猶予を受けられる制度です。税負担を軽減し、事業承継の負担を減らすことが可能です。
また、事業承継に伴う新たな事業再編や経営資源の引き継ぎを支援するために、事業承継・引継ぎ補助金制度があります。事業承継にかかる費用を一部補助してもらうことが可能で、経営者の負担を軽減できます。
公的な支援を活用する
事業承継を支援する公的な制度を活用することは、スムーズな承継を実現するために非常に有効です。支援を受けるにあたっては、中小M&Aガイドラインや事業承継ガイドラインなどを参考にするとよいでしょう。
中小M&Aガイドラインは、中小企業庁が提供しています。事業承継に必要な手順や留意点がまとめられており、事業承継を円滑に進めるための有益な情報が提供されています。
同じく中小企業庁による事業承継ガイドラインでは、後継者不在の中小企業に対する支援策や、事業承継のために必要な取り組みが具体的に示されています。これに基づき、事業承継のための支援制度(税制優遇措置や補助金など)を活用することで、事業承継の過程で生じる課題に早期に対応することが可能となります。
M&Aの時期を定める
事業承継型M&Aのタイミングを見極めることは非常に重要です。承継を開始する時期が遅すぎると、後継者の育成が間に合わなかったり、企業価値が低下したりするリスクがあります。そのため、後継者を早い段階で確定し、事業承継を計画的に進めることが求められます。
M&Aを進める際には、経営者の年齢や企業の成長段階に応じて、適切なタイミングを設定することが必要です。引退直前の急な承継では、M&Aが難航する可能性もあるため、できるだけ早い段階から準備を始めることが理想的です。
事業承継に詳しい専門家へ相談する
事業承継型M&Aを成功させるためには、専門家の助けが不可欠です。特に、M&Aアドバイザーや税理士、弁護士などの専門家に相談することで、交渉や手続きが円滑に進む可能性が高まります。
専門家のアドバイスを受けることで、M&Aに関する法律や税務の面でのリスクを事前に回避することが可能です。さらに売却条件の交渉や契約書の作成などの重要な場面でも、より適切な対応ができます。事業承継型M&Aを検討する際は、ぜひ信頼できる専門家に相談し、戦略的に進めることをおすすめします。
まとめ|事業承継の課題解決としてM&Aの活用を検討しましょう
事業承継型M&Aは、企業の経営者が引退や後継者不在の課題を解決するための有効な手段です。事業承継に際しては、適切なタイミングでの準備や、株主の理解を得ることが重要です。また、補助金や税制、そして公的支援を活用することで、事業承継を円滑に進められます。さらに、M&Aのプロセスをスムーズに進めるために、専門家への相談も欠かせません。
事業承継型M&Aは、単なる経営者の引退対策にとどまらず、企業の価値を最大化し、次世代への成長を促進する手段としても非常に有益です。事業承継を成功させるために、早期の準備と適切な支援を活用し、M&Aを活用して事業の発展と持続可能な成長を実現しましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。