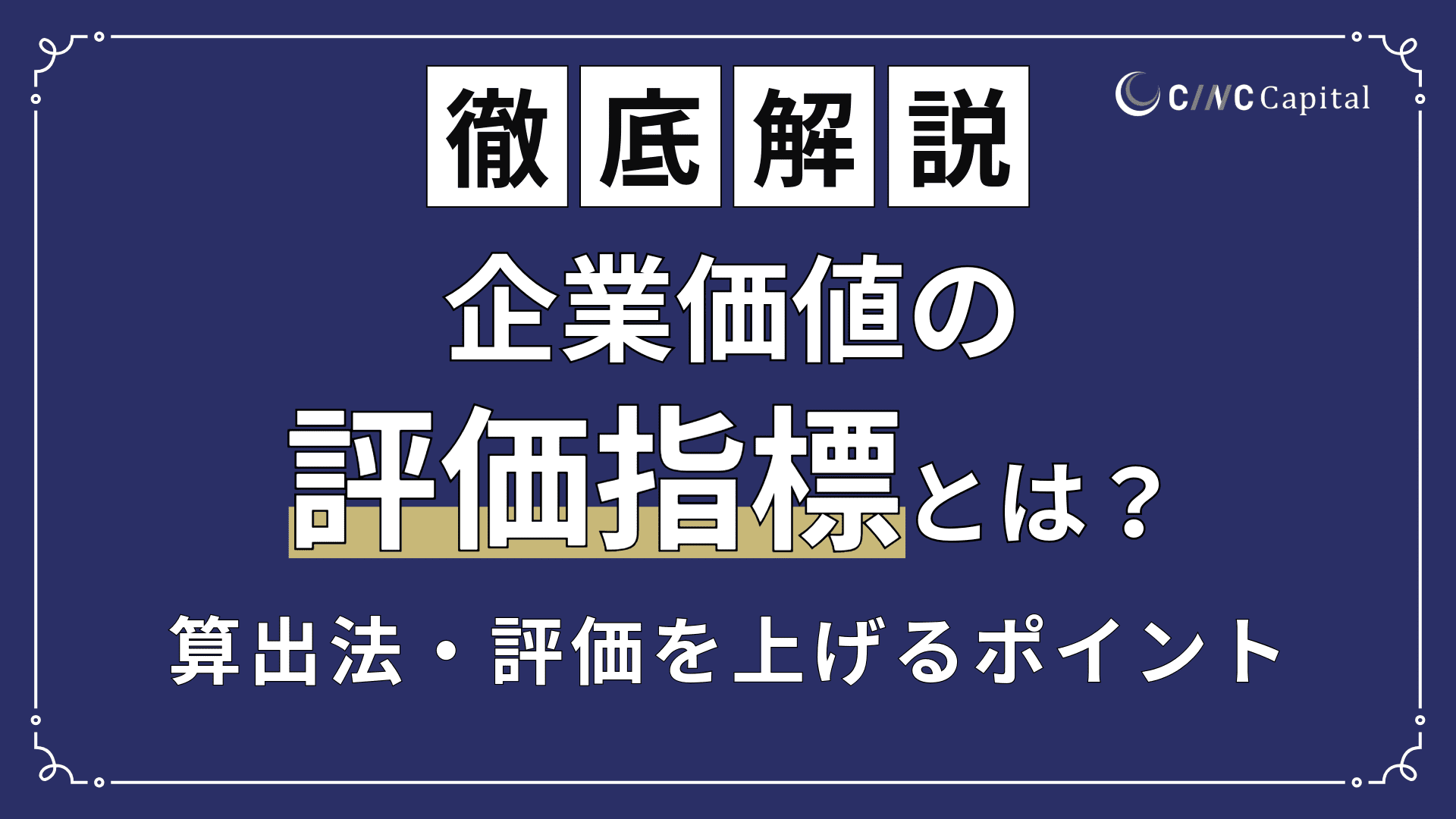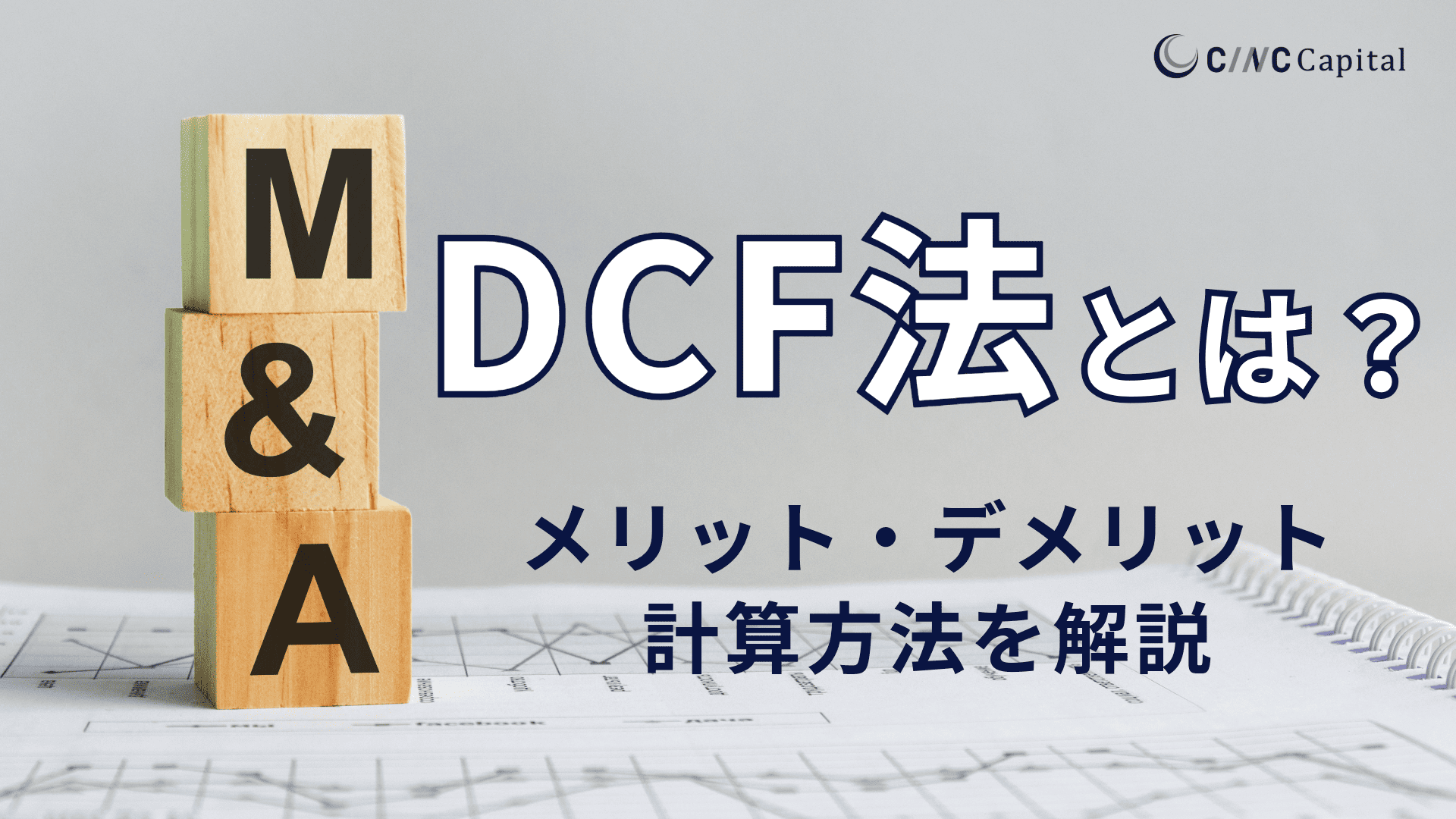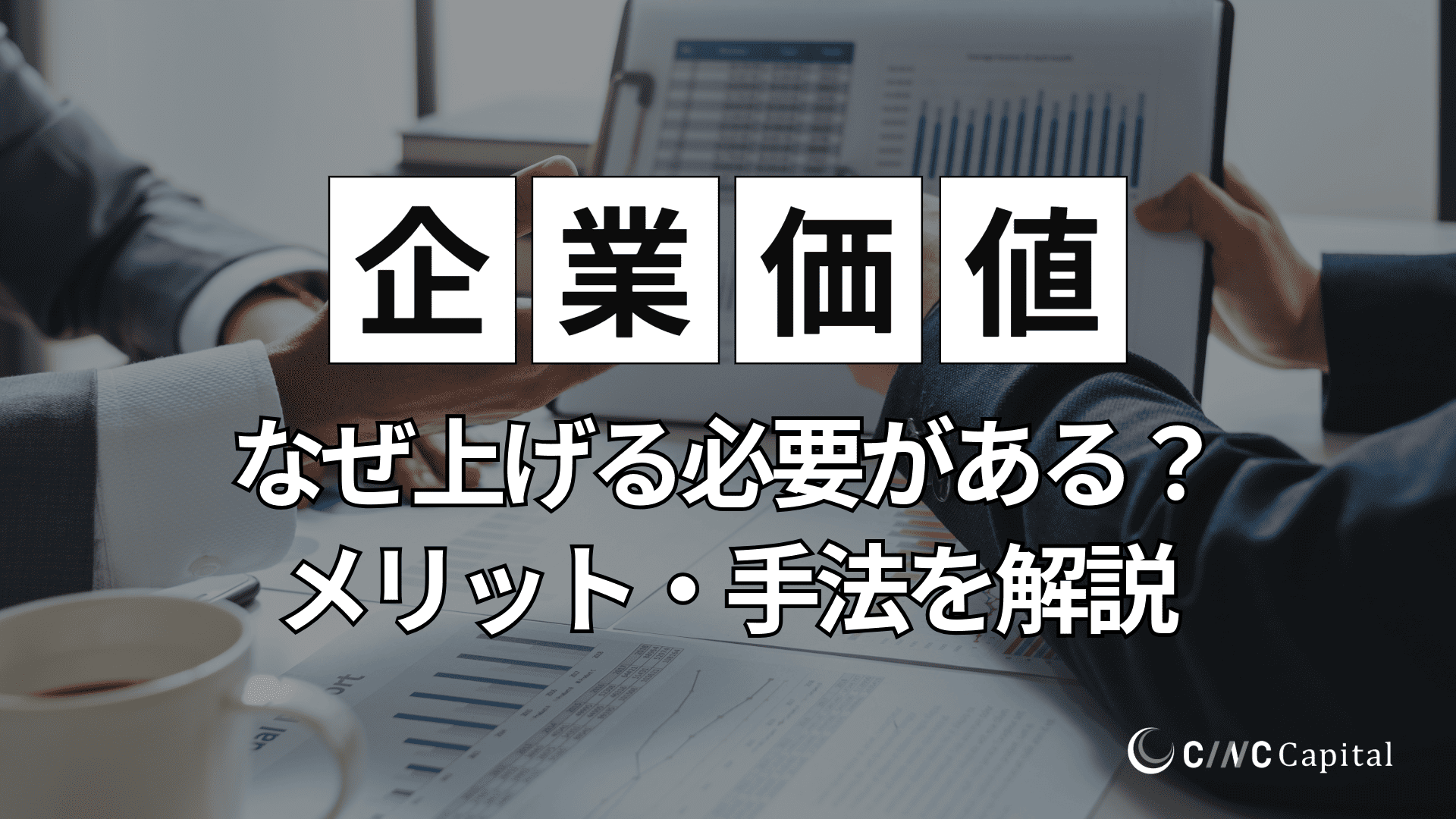CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
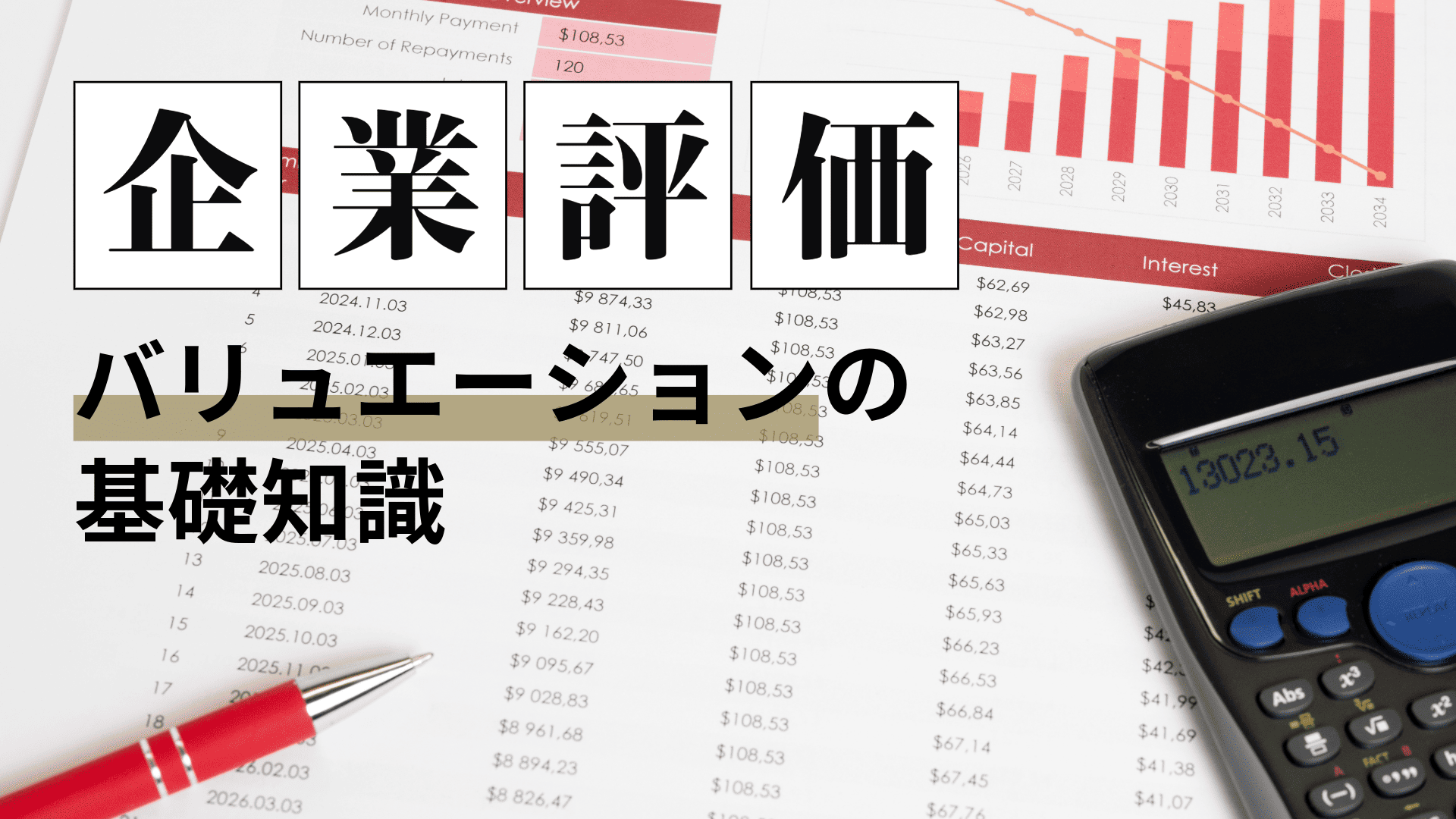
評価 / 企業価値評価(バリュエーション)
- 最終更新日2025.06.26
M&Aのバリュエーションとは?行うタイミングや種類、主な手法
M&Aの取引を成立させるためには、売り手・買い手が納得できる価格を見極める必要があります。その際に必要となるプロセスが「バリュエーション」です。
バリュエーションによって取引の参考となる価格を知ることが、スムーズな交渉につながります。
この記事では、M&Aのバリュエーションに関する基礎知識を解説します。バリュエーションの役割や実施するタイミング、主な手法について確認してみましょう。
目次
M&Aにおけるバリュエーションの基礎知識
M&Aにおける「バリュエーション」とは、どのような意味の用語なのでしょうか。初めに、バリュエーションについて基本から解説します。
そもそもバリュエーションとは?
企業価値評価のことを指す
そもそも「バリュエーション(valuation)」には、「企業価値評価」という意味があります。企業の価値を評価する際は、複数のアプローチ方法があり、それぞれ特徴が異なります。そのため、M&Aの目的や状況に応じて適切な手法を選ぶことが大切です。
具体的には、収益性や資産・負債の金額といった要素によって評価が行われます。バリュエーションの種類や手法について、詳しくは後述します。
M&Aにおけるバリュエーション(企業価値評価)とは?
譲渡価額を決定する基準となる
M&Aにおけるバリュエーションには、企業の収益や資産などを算定し、譲渡価額を決める基準とする重要な役割があります。企業価値の評価につながる要素は一つではありません。投資のような重要な判断を行う際は、適切な手法を選んで企業のあらゆる価値を客観的に評価し、数値化して判断の参考にする必要があります。
企業全体の価値を評価する
バリュエーションによって算定される企業価値(Enterprise Value:EV)とは、企業全体の価値のことを指します。M&Aではさまざまな要素によって評価が行われます。例えば、企業価値は以下のように定義されます。
-
事業価値+非事業用資産-有利子負債
-
株主価値+有利子負債
-
時価総額+有利子負債(上場企業の場合)
バリュエーションで企業の価値を算出する目的
M&Aで行われるバリュエーションには、取引の目安となる金額を示すことで、売り手・買い手の交渉をスムーズにする役割があります。交渉によって双方が納得できる価格を導き出すためには、取引の指標となる金額の目安が必要です。
特に売り手側の企業にとっては、バリュエーションを通じて自社の評価額を把握しておくことが、相手先との交渉を円滑に進める上で役立つでしょう。
M&Aのバリュエーションを行うタイミング
M&Aのバリュエーションは、主に「基本合意契約の締結を行う前」または「デューデリジェンス後の最終契約の交渉を行う前」のタイミングで行われます。M&Aを検討する際は、どの時点でバリュエーションを実施するか確認しておきましょう。
基本合意契約の締結を行う前
「基本合意契約」とは、M&Aの交渉をスムーズに進めるために、譲渡価格や基本的な条件に関して合意した際に締結する契約のことです。デューデリジェンスの実施前に締結し、売り手側・買い手側がこの先も交渉を継続するにあたり、合意した内容を書面に残して確認する意味合いがあります。
一般的に、この段階でバリュエーションが行われるケースが珍しくないものの、限定的な情報から算定することになります。以降のデューデリジェンスで、新たに問題が発見される可能性がある点に注意が必要です。
デューデリジェンス後の最終契約の交渉を行う前
「デューデリジェンス」は、買い手側の企業が取引に関する判断の参考とするために、売り手側の企業に対して実施する詳細な調査のことです。
デューデリジェンスの結果を反映させて企業価値を算定できることから、このタイミングでバリュエーションを実施するケースがよくあります。
その後はバリュエーションの結果を踏まえて、売り手側の企業との交渉を進めていくことになります。
意思決定を行う前
まれに、M&Aの意思決定を行う前にバリュエーションが実施されることがあります。この場合は、取締役会の説明で用いる資料を用意するためにバリュエーションが必要となるケースなどが考えられます。
M&Aのバリュエーションの種類
M&Aのバリュエーションには、以下のようなアプローチ方法があります。ここでは、算定方法の種類や、それぞれの特徴を解説します。
インカムアプローチ
「インカムアプローチ」とは、将来的に期待できる収益の予測を踏まえて企業価値を算定する方法です。
現状だけでなく、将来性までを含めた評価を行えるというメリットがあります。将来的に成長の可能性がある企業を適切に評価することが可能です。
マーケットアプローチ
「マーケットアプローチ」とは、株式市場における市場価格から企業価値を算定する方法です。上場企業の場合は市場株価による評価が行われます。
一方、非上場企業の場合は規模や事業内容が類似する上場企業を参考にする方法や、類似するM&A取引を参考にする方法で評価が行われます。
コストアプローチ
「コストアプローチ」は、純資産価値に基づいて企業価値を算定する方法です。
純資産価値とは、企業の資産から負債を差し引いたものです。清算価値の算定や、資産保有会社の評価、他の評価方法のクロスチェックなどで用いられることがあります。
M&Aのバリュエーションを行う主な手法
M&Aのバリュエーションは、以下の手法で行われます。前述した「インカムアプローチ」「マーケットアプローチ」「コストアプローチ」の種類別に、計算方法や特徴などをご紹介します。
インカムアプローチ
DCF法
「DCF(Discounted Cash Flow)法」は、キャッシュフローに基づいて企業価値を算定する手法です。フリーキャッシュフロー(=企業が自由に使えるキャッシュのこと)を現在価値に割り引くことによって計算するのが特徴となっています。
EVA法
「EVA(Economic Value Added)法」は、企業が生み出した付加価値に基づいて企業価値を算定する手法です。EVAは「経済的付加価値」を意味します。利益から資本コストを差し引くことで算出します。
マーケットアプローチ
PER法
「PER(Price Earnings Ratio)法」は、株価利益率から企業価値を算定する手法となります。PERとは、株価が1株あたりの純利益の何倍になっているかを示すものです。上場する類似会社のPERとの比較によって評価が行われます。
PBR法
「PBR(Price Book-value Ratio)法」は、株価純資産倍率から企業価値を算定する手法です。PBRは株価が1株あたりの純資産の何倍で買われるかを示しています。複数の投資対象が割安であるか、割高であるかを判断する場合に適しています。
類似企業比較法
類似企業比較法は、非上場企業の企業価値を算定するために、類似企業の企業価値や財務指標などを参考にする手法です。規模や事業内容が近い企業を選定するのが一般的です。
企業価値評価では、株価比較の尺度である「EV/EBITDA倍率」が用いられます。その際、非上場企業の企業価値は、評価額から「非流動性ディスカウント」が割り引かれる場合があります。
※EV/EBITDA倍率:M&Aで企業を買収する場合、その企業が獲得するおよそ何年間の本業利益で、投資額を回収できるかを測定する指標のこと。
コストアプローチ
時価純資産法
「時価純資産法」は、企業の資産と負債の時価総額から企業価値を算定する手法です。資産の時価総額から負債の時価総額を差し引いて計算します。資産と負債を時価に換算することによって、公正な評価がしやすくなります。
再調達原価法
「再調達原価法(取替原価法)」は、対象企業が保有する資産を現時点で再取得する場合の費用を基準に企業価値を算定する手法です。
物理的な減価や機能的な陳腐化を考慮して評価が行われます。再現が難しい無形資産の評価の際に用いられることがあります。有形固定資産をはじめ、様々な資産の評価に用いることができます。
まとめ|M&Aにおけるバリュエーション方法を理解して、M&Aを進めていこう
ここまで、M&Aにおけるバリュエーションの基礎知識を解説しました。M&Aでは売り手と買い手が納得して取引を進めるために、目安となる価格が必要となります。
M&Aの目的や状況に応じて適切なバリュエーションの手法を選択しましょう。相場と照らし合わせながら、高すぎず低すぎず適切な価格を提示することで、取引を成立させやすくなります。
簡易的に自社の企業価値を知りたい方は、ぜひ「企業価値算定シミュレーション」をお試しください。
また、CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、バリュエーションのご相談を承っております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。バリュエーションやM&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。