CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
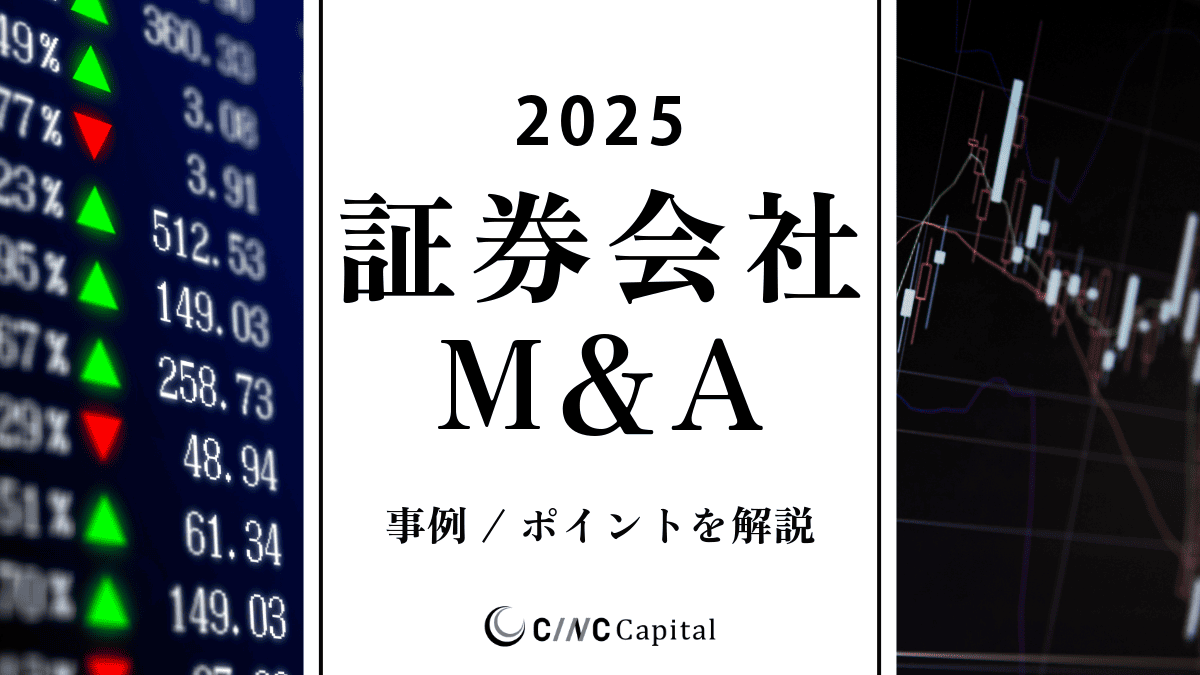
業種
- 最終更新日2025.06.26
証券会社のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
証券会社業界では、急速なデジタル化や新規顧客層の拡大を背景に、M&Aを活用した経営戦略の再編が加速しています。大手証券会社による事業の多角化や、地方証券会社の統廃合、フィンテック企業との提携・買収など、多様な動きが活発化しているのが現状です。
本記事では、国内の証券会社におけるM&A動向、メリット・デメリット、成功のポイントを徹底解説します。
目次
証券会社業界の市場動向
日本の証券会社業界は、急速なデジタル化や新たな顧客層の獲得を背景に、経営戦略の再編とM&Aによる統合が進んでいます。各社はこうした変化に対応し、柔軟な成長戦略を模索している状況です。
「日本証券業協会」の「FACT BOOK 2024」によると、日本の証券会社業界の市場規模は5兆4,263億円に達しました。これは2023年度決算の営業収益であり、前期比で29.4%増加していたことがわかりました。
市場規模の拡大の理由は多岐にわたりますが、手数料収入の構造変化やデジタル化への対応、M&A活動の活発化が相乗的に影響を与えているとされます。
証券会社業界が抱える課題
証券業界は、競争の激化やデジタル化の波、少子高齢化による顧客基盤の変化など、複合的な課題に直面しています。詳しく見ていきましょう。
競争激化によるビジネスモデルの転換
対面型取引を中心としたビジネスモデルは、ネット証券の台頭により手数料収入が圧迫され、収益性が低下しつつあります。従来の株式取引を主要な収益源としていた企業は、収益確保のために預かり資産を活用したモデルへと移行しているといわれています。
少子高齢化による顧客基盤の変化
日本市場における顧客層の高齢化は、取引頻度や資産運用ニーズに影響し、証券会社の成長戦略における重要課題となっています。とりわけ昨今は、若年層の人口減少が顕著です。各社は高齢者向けサービスの充実と同時に、若年層に向けた投資教育やサービス改善策の導入を進め、顧客維持と新たな顧客層の開拓を急いでいます。
デジタルトランスフォーメーション(DX)への対応
「デジタルトランスフォーメーション(DX)」化推進を受けて、業界全体で取引効率化とコスト削減が進んでいます。老舗証券会社も例に漏れず、デジタルチャネルの強化を迫られているのが現状です。従来の対面販売に依存していた企業も、デジタル対応の強化やシステム統合を急務とする状況にあります。
証券会社業界のM&A最新動向(2025年)
証券会社のM&A活動は、事業の多角化やデジタルトランスフォーメーションの推進を目的として、重要な転換期を迎えています。ここでは、証券会社業界のM&A最新動向をご紹介します。
大手証券会社によるM&Aの活発化
国内の主要証券グループは、M&Aを通じた事業の多角化と収益基盤の強化に積極的です。各社とも豊富な金融ノウハウと確立されたネットワークを活かし、大型案件や上場企業の買収、MBO(マネジメント・バイアウト)などの戦略的取引を推進しています。その結果、M&A関連収益は各社の成長エンジンとしての位置付けを強めている状況です。
地域証券会社の統合・再編の加速
地方および中小の証券会社は、競争激化や経営環境の変化に対応するため、統廃合を含む再編を加速させています。地域証券会社同士の合併、大手証券会社による買収などが多く、各社が事業の持続可能性と経営基盤強化に注力しています。
フィンテック企業との提携・買収
フィンテック企業との提携・買収を進め、業務のデジタル化と効率化を図りつつ、新たな金融サービスの開発や市場拡大を目指す動きが活発化しています。従来の金融ノウハウと最先端技術の融合は、業界全体の競争力を高めている一つの要因です。
証券会社がM&Aをするメリット
M&Aは従来の事業承継にともなう課題を解決し、証券会社の持続的な成長を支える経営戦略です。ここでは、証券会社がM&Aをするメリットをご紹介します。
資本力の向上
M&Aによって各社の保有する金融資源やノウハウが統合され、単独では実現が難しい資本力(資金調達力)を獲得できます。特に証券会社においては、資本力が市場内での信用力・流動性に影響するため、M&Aを機に業界内での優位性をさらに高められるでしょう。
従業員の雇用継続・待遇向上
M&Aでは一般的に、既存従業員の雇用維持が重視されます。たとえ買収されたとしても、自社の従業員は引き続き安定した就業環境で働ける可能性があります。また、労働条件や待遇の見直しが進むことで、従業員のモチベーション向上や組織全体の生産性向上にもつながるでしょう。
株式譲渡益による経済的リターン
M&Aを通じた株式譲渡は、経営者に大きな経済的リターンをもたらします。譲渡益を得ることで、自己資本を効率的に回収できると同時に、引退後の生活資金の確保や新たな事業への再投資に活用できます。
証券会社がM&Aをするデメリット
証券会社のM&Aにおいては、ブランド統合の不備による顧客離れ、組織再編による従業員の離職・モチベーション低下、さらには金融規制の強化による手続きの煩雑化など、さまざまなリスクが存在します。デメリットや注意点を見ていきましょう。
既存顧客が離脱する懸念
ブランド統合が適切に行われない場合、これまで築き上げたブランドイメージや顧客の信頼が損なわれ、既存顧客が他社へ流出する可能性が高まります。統合プロセスにおいて情報共有が不十分であったり、顧客サポート体制が整備されていなかったりすると、顧客離れを招くのは必然です。
組織変更にともなう従業員の離職・モチベーション低下
売却後の統合プロセスでは、業務体制や評価制度の変更が避けられず、従業員が自身のキャリアや将来に対して不安を抱くことがあります。特に、給与体系や役職などに影響がおよぶ場合、従業員のモチベーションが低下し、結果として離職率の上昇につながる可能性があります。
金融規制・コンプライアンス強化による手続きの煩雑化
証券会社の売却には、金融業界特有の厳格な規制やコンプライアンス要件が適用されるため、一般的なM&Aと比較して手続きが複雑になります。追加的な監査や法的確認が必要となることで、取引の進行が遅延し、売却条件の見直しやコスト増加につながるリスクがあります。
証券会社がM&Aを成功させるためのポイント
証券会社の売却プロセスでは、業界特有の評価基準や厳格な規制対応、システム統合など、多岐にわたる要素を考慮することが大切です。ここでは、M&Aを成功に導くポイントをご紹介します。
企業価値の適切な算定
自社の企業価値を評価する際、売上高だけでなく、総取引量や顧客基盤の質、独自の収益構造といった指標を考慮するのが一般的です。たとえば、「EV/EBITDA倍率」などの評価手法を活用し、類似企業との比較を行うことで、適切な企業価値を算定できます。これにより、自社に最適な売却条件がわかります。
自社の価値について気になる場合は、ぜひ以下の企業価値算定シミュレーションをお試しください。
企業価値算定はこちら
規制当局とのスムーズな調整
証券会社は金融商品取引法などの厳格な規制のもとで業務を行っており、M&Aを実施する際には規制当局との連携が不可欠です。適切な許認可の取得、コンプライアンス体制の整備をはじめ、情報の透明性を確保しながら規制当局と調整を進めることで、買収後のトラブルを未然に防ぐことができます。
買い手企業の戦略と合致したスキーム選択
買い手側の長期的な成長戦略や事業展開の方向性と合致するM&Aスキームを選択することが、双方にとっての利益を最大化する鍵です。株式譲渡や事業譲渡などの手法の特徴を十分に理解し、財務面と戦略面のバランスを考慮して、どのスキームが適切か判断しましょう。
証券会社のM&A事例
SMBC日興証券とSMBCフレンド証券のM&A
2016年9月30日、SMBC日興証券とSMBCフレンド証券は合併契約を締結し、2018年1月1日付でSMBC日興証券を存続会社とする吸収合併を実施しました。本合併は、両社の強みを活かしながら統合シナジーを創出し、競争力を強化することを目的としています。
SMBCフレンド証券は主に個人投資家向けのサービスを提供していましたが、証券業界全体の競争激化や収益環境の変化を受け、経営の効率化が求められていました。一方、総合証券会社であるSMBC日興証券は、リテールおよびホールセール両面での事業拡大を進めており、合併によって商品・リサーチの多様化やコンサルティング型営業の強化を図る狙いがありました。
また、両社のシステムや販売チャネルの統廃合を進めることで、コスト削減と経営の効率化を実現し、持続的な成長を目指しています。証券業界では、低金利やデジタル化の進展により、さらなる統合や再編の動きが続いており、今回の合併もその流れの一つといえます。
【出典】株式会社三井住友フィナンシャルグループ「SMBC日興証券・SMBCフレンド証券券の合併契約の締結について」
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社による高木証券株式会社のM&A
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社は、完全子会社である東海東京証券と髙木証券の合併に向けた協議を2018年12月に開始し、2019年度上期中に東海東京証券を存続会社とする吸収合併を実施しました。
本合併の目的は、両社の経営資源を統合し、経営の効率化やセグメント別戦略の共同展開を進めることにあります。東海東京証券は名古屋を拠点とする大手証券会社で、髙木証券は関西圏に強い地盤を持つ老舗証券会社でした。2017年に東海東京フィナンシャル・ホールディングスが髙木証券を完全子会社化し、経営統合を進めていましたが、証券業界の競争激化や市場環境の変化を受け、さらなる企業価値向上のために合併を決定しました。
本合併により、東海東京証券は関西圏での営業基盤を強化し、顧客サービスの向上を目指しました。また、経営インフラの統合によるコスト削減や業務効率化も期待されます。証券業界では、異業種からの参入やデジタル化の進展により、今後もM&Aによる業界再編が進む可能性が高いと考えられます。
【出典】東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社「当社連結子会社間(東海東京証券と髙木証券)の合併に向けた協議開始に関するお知らせ」
マネックスグループ株式会社によるコインチェック株式会社のM&A
2018年4月6日、マネックスグループ株式会社は、仮想通貨取引所を運営するコインチェック株式会社の全株式を取得し、完全子会社化することを発表しました。買収額は約36億円で、4月16日に株式取得を完了しました。
コインチェックは、国内有数の仮想通貨取引所として急成長を遂げていましたが、2018年1月に発生したNEM(ネム)の不正流出事件を受け、経営管理や内部統制の強化が急務となっていました。この状況を受け、マネックスグループは、自社の金融業界におけるリスク管理ノウハウや顧客資産保護の仕組みを活用し、コインチェックの再建を支援することを決定しました。
本買収により、マネックスグループは仮想通貨事業への本格参入を果たし、「第二の創業」と位置付ける新たな成長戦略を加速させました。また、コインチェックはマネックスの支援を受け、経営管理体制を強化し、顧客にとってより安全な取引環境の整備を進めました。仮想通貨業界では規制強化が進む中、大手金融グループによる買収や統合が今後も増えていく可能性があります。
【出典】マネックスグループ株式会社「株式取得によるコインチェック株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」
まとめ|証券会社のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
証券会社におけるM&Aは、近年ますます重要度が高まっています。一方で、M&Aには顧客の離脱リスク、組織再編による従業員のモチベーション低下、金融規制による手続きの煩雑化といった課題も存在します。これらを乗り越えるためには、M&Aの専門家のアドバイスが欠かせません。まずはM&A仲介会社に相談し、直近の業界動向の把握から始めましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















