CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
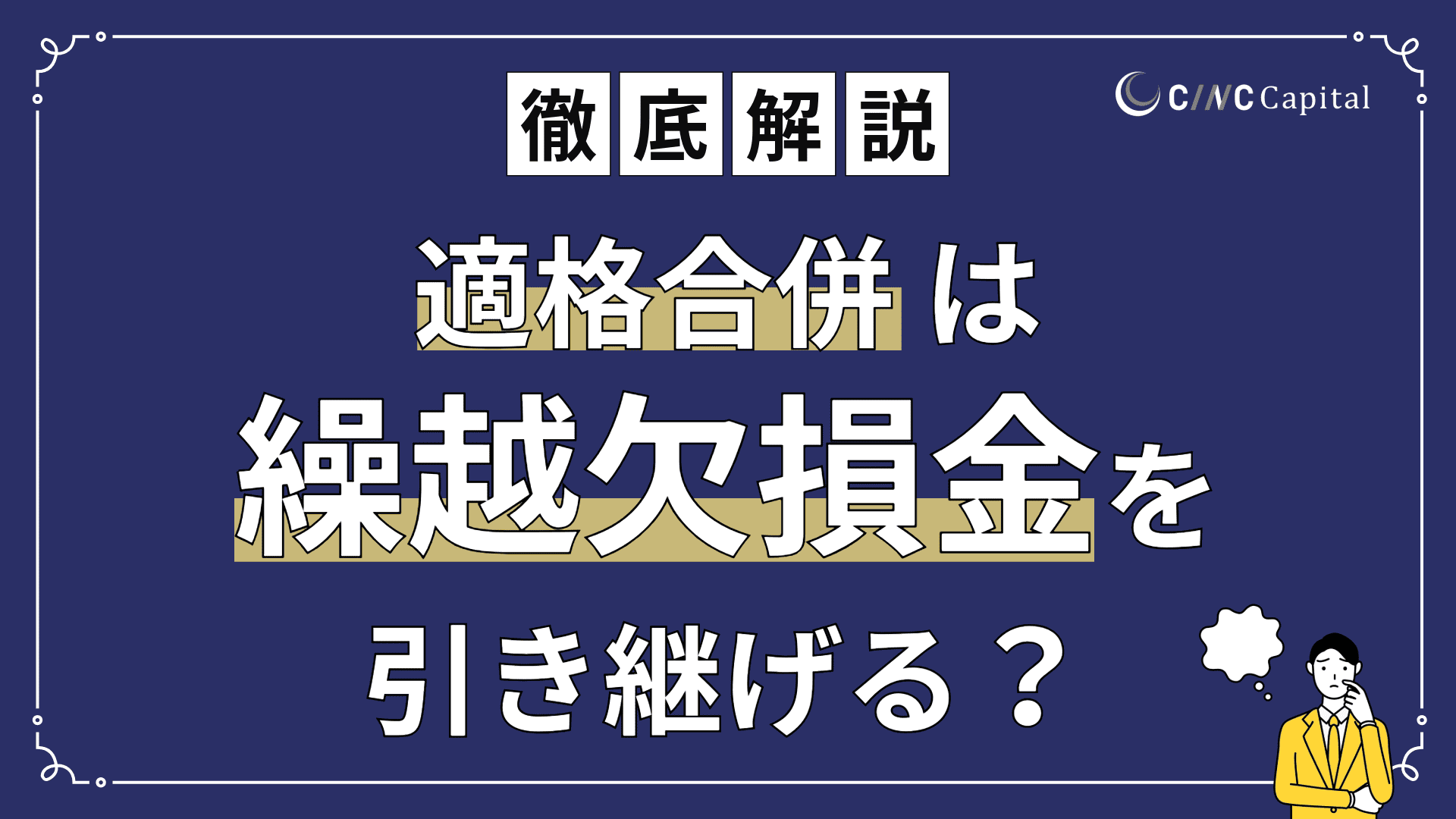
M&A / スキーム
- 公開日2025.09.29
適格合併は繰越欠損金を引き継げる?要件や引き継ぎ制限の条件について解説
適格合併で繰越欠損金を引き継げるかどうか、よく分からずに悩んでいませんか?
合併後に赤字を活かせるかどうかは、税制上の条件や制限を正しく理解しているかどうかで大きく結果が変わります。
本記事では、適格合併の定義や繰越欠損金の節税効果、引継ぎの可否を分ける要件や制限の内容について、わかりやすく解説します。
目次
適格合併とは?
適格合併とは、税務上の一定の条件を満たすことで、合併に伴う課税を回避できる制度です。
被合併会社の資産・負債を時価ではなく簿価で引き継げるため、譲渡益が発生せず、税負担を抑えて事業再編を進められます。
さらに、一定の要件を満たせば、被合併会社の繰越欠損金も存続会社で引き継ぐことが可能です。
赤字企業を吸収しても、欠損金を活かして将来の法人税を軽減できる点は大きなメリットです。
適格合併の仕組みを正しく理解し活用することが、M&A成功において重要になります。
繰越欠損金とは?
繰越欠損金とは、法人が過去の事業年度で生じた赤字(欠損)を、翌年度以降の利益と相殺できる制度を指します。
法人税の計算において、課税所得を抑えられるため、企業にとっては非常に重要な節税手段の一つです。
本章では、繰越欠損金の持つ節税効果と、制度の利用における上限(限度)について、具体的に解説します。
繰越欠損金の節税効果
繰越欠損金は、将来の利益と相殺することで法人税を減らす効果があります。
なぜなら、黒字となった年度の課税所得から過去の赤字を差し引くことができるからです。
前期に1,000万円の赤字を出し、今期に800万円の利益があった場合、課税所得はゼロとなるため、法人税の支払いは不要になります。
このように、繰越欠損金を活用すれば、赤字を無駄にせず税負担を抑えられるため、資金繰りの安定化にもつながります。
繰越欠損金の限度
繰越欠損金には、使用できる期間や控除額に制限があります。
青色申告法人が繰越できる期間は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金については原則10年間ですが、それ以前の欠損金には異なる期間が適用されます。
具体的には、資本金が1億円を超える法人(いわゆる大法人)では、繰越欠損金による控除限度額が当期所得の50%までに制限されます。
また、資本金が1億円以下であっても、大法人に100%支配されている法人なども同様の制限が適用されます。
この制度は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
したがって、制度の恩恵を最大限に活かすためには、自社が控除制限の対象に該当するかを事前に確認し、活用可能な範囲で適切に損益通算することが大切です。
会社が合併すると繰越欠損金はどうなる?
企業が合併を行う際、被合併会社の繰越欠損金を引き継げるかどうかは重要な検討ポイントです。
原則として、合併により被合併会社の欠損金は消滅します。
これは、法人税法上、消滅法人の欠損金は引き継げないとされているためです。
ただし、適格合併に該当し、かつ所定の要件を満たす場合には、例外的に欠損金の引継ぎが認められます。
欠損金の活用を前提としたM&Aを行うには、制度の理解と事前準備が不可欠です。
適格合併で繰越欠損金を引き継ぐための要件
適格合併によって繰越欠損金を引き継ぐには、合併の形態に応じて一定の要件を満たす必要があります。
本章では、大きく分けて7つの要件について順に解説します。
金銭等不交付要件
繰越欠損金を引き継ぐには、合併対価を株式のみとする必要があります。
税務上の適格合併は「対価が株式のみ」であることを前提としているからです。
例えば、合併の際に現金や不動産などの資産を対価として交付してしまうと、合併は適格と見なされず、繰越欠損金の引継ぎも認められません。
完全支配関係(支配関係)継続要件
完全親子関係の合併では、支配関係が継続していることが必須です。
その理由は、税法が「合併まで完全支配が継続していた」ことを前提に適格合併の簡略要件を認めているからです。
合併時点で完全支配が失われていた場合、税務上の要件を満たせなくなり、欠損金の引継ぎが制限されます。
このため、合併前から存続会社またはその親会社が被合併会社の株式を100%保有している状態を維持し続けることが求められます。
従業者引継要件
適格合併と認められるには、被合併会社の従業員の多くを継続雇用することが必要です。
その背景には、「事業の実体が引き継がれている」ことを税務上で確認する意図があります。
被合併会社の従業員がほとんど退職し、実質的な組織が解体された場合、事業継続とは見なされず、適格性を失うおそれがあります。
目安としては、従業員の80%以上を存続法人が引き継ぐことが望まれ、雇用の維持が制度活用の前提になるのです。
事業継続要件
繰越欠損金の引継ぎには、被合併会社の主要事業が合併後も継続される必要があります。
これは、制度が「実体ある事業の承継」を重視しているからです。
例えば、合併後に旧会社の主要事業がすぐに廃止された場合、形式的な統合に過ぎないと判断される可能性があります。
事業関連性要件
合併に関わる両社の事業に関連性があることも、引継ぎの要件となります。
関連性がなければ、租税回避目的の合併と見なされるリスクがあるからです。
まったく別業種の企業を合併して欠損金だけを引き継ぐようなケースでは、税務上問題視されるおそれがあります。
事業規模要件または、経営参画要件
合併当事者の事業規模に大きな差がある場合は、経営者の引継ぎによって共同性を補う必要があります。
これは、「支配関係がない場合でも対等な経営統合が行われている」ことを証明するためです。
例えば、一方の会社がもう一方の10倍以上の規模であり、かつ役員も引き継がれないと、欠損金引継ぎの意義が問われます。
このため、両社の売上や従業員数が概ね5倍以内に収まるか、それが難しい場合は、両社の特定役員が統合後も経営に参画する体制を整えることが条件となります。
株式継続保有要件
被合併会社の支配株主が、合併によって取得した株式を一定期間保有し続けることも求められます。
この要件は、「合併が短期的な利益目的でない」ことを示すために設けられています。
合併直後に支配株主が株式をすべて売却した場合、実質的にM&Aを使った節税目的の取引と疑われるリスクがあります。
繰越欠損金の引継ぎ制限がかからないケース
適格合併であっても、被合併会社の繰越欠損金には通常、税法上の引継ぎ制限が設けられています。
しかし、例外的にこの制限が適用されず、欠損金をそのまま引き継げる場合があります。
本章では、制限がかからない代表的なケースについて詳しく説明します。
共同事業を行うための合併
共同事業を目的とした合併では、引継ぎ制限が適用されません。
その理由は、形式的な赤字買収ではなく、実質的な事業統合が目的とされているからです。
例えば、類似業種や補完関係にある企業が事業効率化やサービス拡充を目指して合併するケースでは、租税回避とはみなされません。
このような場合は、被合併法人の繰越欠損金をそのまま合併法人で使用できるため、節税と事業強化を同時に実現できます。
合併法人と被合併法人の間に5年を超える支配関係がある
5年以上継続して支配関係がある場合、繰越欠損金に引継ぎ制限はかかりません。
これは、長期間の一体経営が行われていれば、租税回避の意図がないと判断されるためです。
合併法人が5年以上前から被合併法人の株式を50%超(過半数)保有し続けていた場合、引継ぎ制限の対象外になります。
「みなし共同事業要件」を満たす
資本関係はあるが5年未満の支配にとどまる場合でも、一定の条件を満たせば共同事業とみなされ、引継ぎ制限が解除されます。
この制度が設けられているのは、支配期間が短くても実質的に共同経営が行われている場合、租税回避とは認められないからです。
以下のいずれかの要件を満たせば、「みなし共同事業」と判断されます。
「事業関連性要件」+「事業規模要件」+「事業規模継続要件」
事業内容に関連性があり、合併当事会社の規模に大きな差がなく、支配開始から合併までの間に急成長していないことが条件です。
これらの要件が揃うことで、合併が実質的な事業連携に基づくものと認定されます。
例えば、関連業種で売上や従業員数が5倍以内で推移し、合併までの間に事業が急拡大していなければ、欠損金の引継ぎ制限はかかりません。
「事業関連性要件」+「特定役員引継要件」
事業に関連性があり、かつ両社の特定役員が合併後も引き続き経営に参画する体制であれば、みなし共同事業と認定されます。
その理由は、経営者レベルでの連携があることで、実質的な事業統合と見なされるからです。
両社から最低1名ずつの代表や取締役が合併後の法人でも特定役員として就任する体制が整っていれば、引継ぎ制限は適用されません。
被合併法人の「時価純資産超過額」が繰越欠損金額以上
被合併法人の時価純資産が欠損金を上回る場合も、引継ぎ制限はかかりません。
この理由は、保有資産に十分な価値があり、欠損金を用いて節税を図る合理性があると認められるためです。
帳簿上は赤字でも、時価評価で見れば資産価値が高く、債務超過にない企業であれば、欠損金の引継ぎが可能です。
繰越欠損金の引継ぎ制限がかかるケース
繰越欠損金は、適格合併であっても、すべてを引き継げるとは限りません。
特に租税回避の防止を目的として、一定の条件に該当する欠損金については、引継ぎに制限がかかります。
本章では、引継ぎ制限が課される代表的な2つのケースについて解説します。
支配関係が事業年度開始日前の繰越欠損金
合併法人が支配関係を有する前の事業年度で発生した欠損金は、引き継ぐことができません。
なぜなら、支配関係が生じる前に蓄積された欠損金は、節税目的の合併によって悪用されるリスクが高いため、税法上で制限されているからです。
黒字企業が赤字企業を買収し、その赤字を相殺して法人税を圧縮しようとする場合、買収前の欠損金を利用することは認められません。
支配関係事業年度開始日以後の繰越欠損金のうち特定資産の譲渡等損失額
支配関係が生じた後に発生した欠損金であっても、その一部は引継ぎが制限される場合があります。
理由は、含み損を持つ資産を意図的に譲渡し、帳簿上の損失を作り出す行為が、税負担を不当に軽減させる手段として使われることがあるためです。
合併前に高額の設備や不動産を売却して損失を出した場合、それが「特定資産の譲渡等損失額」に該当すれば、その分の欠損金は引き継げません。
まとめ|会社状況を理解し、M&Aを実施しよう
繰越欠損金は、適格合併の仕組みやルールを正しく理解すれば、大きな節税効果が期待できます。
制度をうまく活用することで、合併後の法人税の負担を軽くすることが可能です。
ただし、欠損金を引き継げるかどうかは、合併の種類や会社同士の関係、事業の継続性など、いくつかの条件によって決まります。
そのため、自社の状況をよく把握したうえで、最も合った合併の方法を選ぶことが、M&Aを成功させるための大切なポイントです。

















