CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
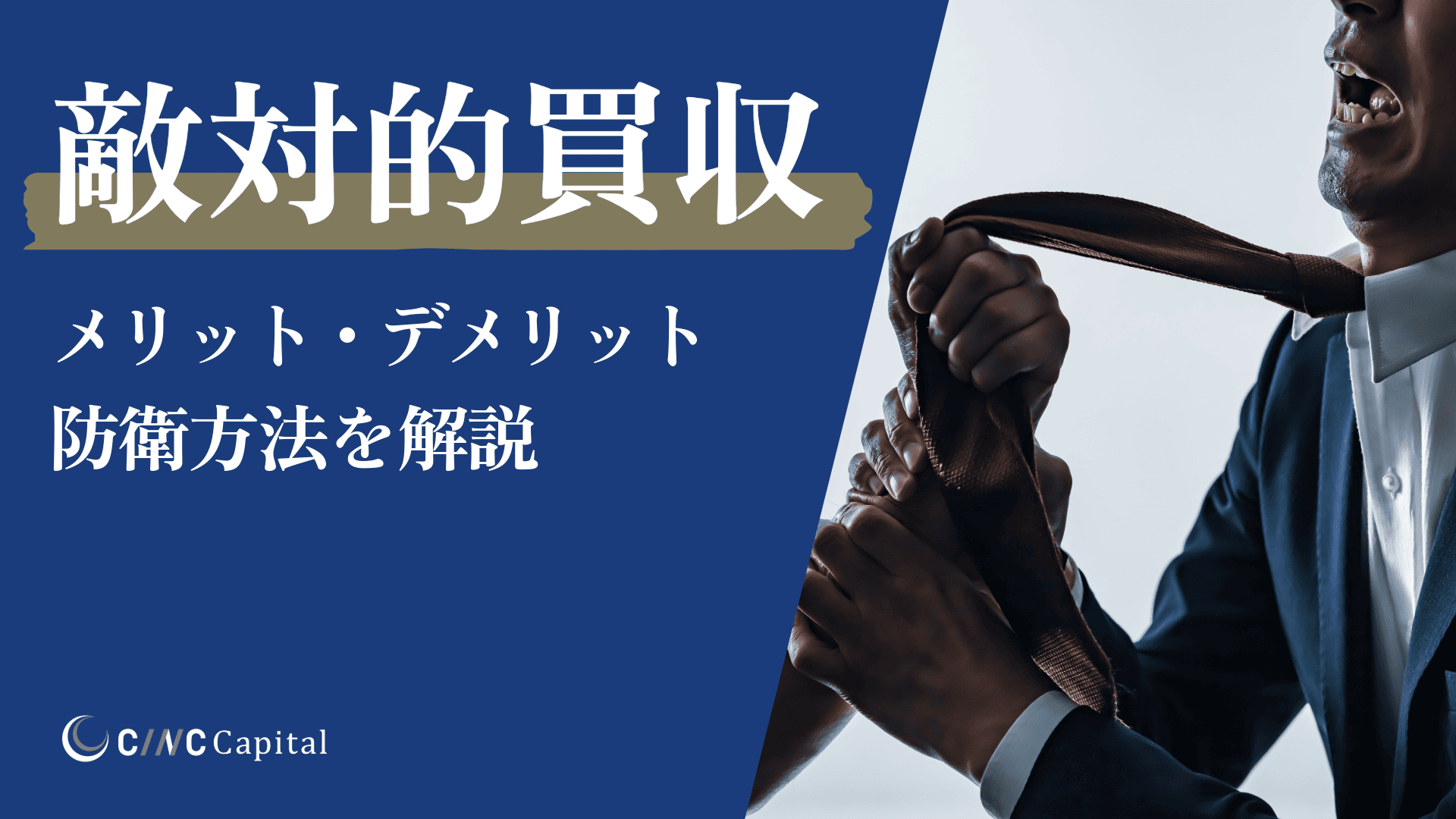
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.06.26
敵対的買収とは?メリットやデメリット、防衛策について解説
企業が経営権を奪われるリスクを避けるためには、敵対的買収の仕組みや対策を理解することが重要です。しかし、敵対的買収と友好的買収の違いや、なぜ買収が行われるのか、具体的な手法について詳しく知る機会は少ないかもしれません。
本記事では、敵対的買収の概要やメリット・デメリット、防衛策、買収を仕掛けられやすい企業の特徴について解説します。
目次
敵対的買収とは?
敵対的買収とは、M&Aの一形態であり、企業の経営陣や主要株主の同意なしに、外部の企業や投資家が株式を取得し、経営権を掌握する手法です。経営者の意思に反して行われるため、防衛策が講じられ、買収の成否はその攻防によって決まります。
買収は双方にとって成長の機会をもたらす一方で、経営の混乱や企業価値の毀損といったリスクも否定できません。ここでは、敵対的買収の特徴、友好的買収との違い、実施される理由、主な手法について解説します。
友好的買収との違い
敵対的買収は、企業の経営陣が同意しないまま進められるため、友好的買収とは異なる特徴を持ちます。友好的買収では、買収する側とされる側が協議を重ね、統合後のシナジーを考慮しながら進められます。
一方、敵対的買収では、買収される企業の経営陣が反発し、防衛策を講じるため、交渉が難航する傾向があります。さらに、従業員の士気低下や取引先の離反が起こり、経営の不安定化を招く可能性もあるのです。
このように、敵対的買収は交渉の柔軟性に欠ける一方、経営改革を強行する手段として活用される場合もあります。企業の買収戦略を理解するうえで、友好的買収との違いを把握することが重要です。
なぜ敵対的買収が行われる?
敵対的買収は、企業の経営改善や市場シェアの拡大を目的に実施されることが多いです。特に、経営が停滞している企業や、市場評価が低い企業は標的になりやすくなります。
買収者にとって、敵対的買収は短期間で支配権を獲得し、経営改革を強行できる手段です。例えば、不採算事業を抱える企業では、買収後に組織再編を行い、コスト削減や事業の最適化が可能です。
また、競合企業を取り込むことで市場シェアを拡大し、競争力を強化できます。加えて、敵対的買収は投資戦略としても用いられます。企業価値の低さを狙い、買収後に経営を立て直し、高値で売却するケースもあります。
このように、敵対的買収は経営改革や市場シェアの拡大、投資収益の確保を目的として行われますが、対象企業側の抵抗によって成功の難易度が高くなる特徴があります。
敵対的買収の手法
敵対的買収には、主に以下の3つの手法があります。
公開買付(TOB)
対象企業の株式を市場で大量に買い集め、支配権を獲得する手法です。TOBは、一定の価格で株主から直接株式を買い取る形で実施されます。市場価格よりも高い価格を提示することで、多くの株主が売却に応じやすくなります。
プロキシーファイト(委任状争奪戦)
株主総会での議決権を獲得し、取締役の交代を目指す方法です。買収者は株主から議決権の委任状を集め、取締役会を支配することで、企業の経営権を奪います。この手法は、買収側が実際に多くの株式を保有していなくても、経営権を掌握できる点が特徴です。
グリーンメーラー(高値買戻し要求)
買収者が対象企業の株式を取得した後、経営陣に対して高値での買い戻しを要求する手法です。企業側は買収を防ぐために、高額な資金を支払って株式を買い戻さざるを得なくなります。グリーンメーラーの目的は企業の支配権の獲得ではなく利益を得ることにあるため、投資ファンドなどが利用するケースが多いです。
敵対的買収のメリット
敵対的買収は、適切に活用すれば双方の企業にとって大きな利益をもたらす可能性があります。ここでは、敵対的買収がもたらす主なメリットとして、「企業価値の向上」「経営の効率化」「市場シェアの拡大」の3つについて解説します。
企業価値を向上できる
敵対的買収は、企業価値の向上を目的として活用されることがあります。特に、意思決定の遅れや成長の停滞が課題の企業では、新たな経営方針を導入することで、価値を引き上げることが可能です。
長年課題を放置している企業では、外部資本や経営ノウハウの導入により、事業戦略の転換や資本効率の改善が進みます。例えば、不採算部門を整理し、成長性の高い事業に集中することで、収益向上が期待できます。
このように、敵対的買収は企業の潜在価値を引き出し、経営再構築が成功すれば、大幅な企業価値の向上につながるのです。
経営の効率化につながる
敵対的買収は、企業の経営効率を改善する手段として活用されることがあります。特に、組織の硬直化や意思決定の遅れが業績低迷の原因となっている企業では、新たな経営体制の導入により、効率化を進めることが可能です。
買収後は、非効率な部門の整理やコスト削減を進め、事業の最適化を図ります。例えば、買収対象企業の重複する業務を統合し、組織のスリム化を進めることで、業務効率の向上を目指します。さらに、経営陣を交代させることで、新たな戦略を迅速に実行し、意思決定のスピードを高めることも可能です。
ただし、企業文化の違いが統合の障害となることもあるため、買収後のマネジメントを適切に行うことが重要です。
市場シェアを拡大できる
敵対的買収は、市場シェアを拡大するための有効な戦略です。特に、同業他社を買収することで競争優位性を確立し、業界内での地位を強化できます。
新市場への参入や顧客基盤の拡大には通常、時間とコストがかかります。しかし、敵対的買収によって競争相手を取り込めば、短期間で事業拡大が可能です。さらに、既存の販路やブランド力を活用することで、効率的な成長が期待できます。
ただし、市場独占とみなされる場合は、規制当局の審査が厳しくなるため、慎重な対応が必要です。
敵対的買収のデメリット
敵対的買収には大きなメリットがある一方で、リスクが伴います。経営統合の過程で対立や混乱が生じることに加え、企業の信用低下につながる可能性もあり、慎重な対応が必要です。ここでは、敵対的買収の主なデメリットとして「企業文化の対立」「経営の安定性低下」「イメージダウン」の3点について解説します。
企業文化の対立を引き起こすリスクがある
敵対的買収により、企業文化の対立を引き起こす可能性があります。買収側と買収対象企業の経営方針や価値観が大きく異なる場合、社員の抵抗が生じ、業務統合が難航することがあります。
企業文化は長い時間をかけて形成されたものであり、買収後に経営方針や文化が急激に変更されると、従業員の士気が低下し、離職につながることがあるのです。特に、買収側が自社の文化を無理に押し付けると、統合が失敗するリスクが高まります。成功には、従業員との信頼関係を築き、段階的に統合を進めることが重要です。
経営の安定性を損なうおそれがある
敵対的買収は、企業の経営の安定性を損なうリスクがあります。買収をめぐる攻防が長引くと、経営資源が割かれ、業績悪化につながる可能性があります。
買収対象企業は防衛策の実施や株主との交渉に多くの労力を費やすことになり、本業への注力が疎かになれば競争力の低下を招きます。一方、買収側も予想以上のコスト負担や経営改革の遅れにより、投資回収が困難になることがあります。
このように、敵対的買収は成長戦略として活用される一方で、統合が失敗すれば経営の混乱を招くおそれがあるため、慎重な計画とリスク管理が求められます。
イメージダウンのリスクがある
敵対的買収は、買収者の企業イメージを損なうリスクがあります。特に、強引な手法が用いられると、消費者や取引先の信頼を失う可能性があります。
敵対的買収は買収対象企業の経営陣や従業員の反発を招き、メディアでも批判的に報じられることがあります。結果として「強引な経営」と見なされると、買収者のブランド価値が低下するおそれがあります。また、顧客が競合へ流出し、売上減少につながることも考えられるでしょう。
敵対的買収を防ぐには?5つの防衛策
買収対象企業が敵対的買収を回避するためには、事前に適切な防衛策を講じることが重要です。ここでは、主要な防衛策として「ポイズン・ピル」「ホワイトナイト」「クラウン・ジュエル防衛」「ゴールデン・パラシュート」「株式持ち合い」の5つについて解説します。
ポイズン・ピル
ポイズン・ピルは、敵対的買収者が一定割合(通常15〜20%)の株式を取得した際に発動する買収防衛策です。具体的には、買収前に既存株主に対して新株予約権を付与し、発動時にその予約権を使って市場価格よりも安く新株を取得できるようにします。
このとき、買収者には予約権の行使を認めず、もしくは不利な条件を課すため、買収者の持株比率は大幅に希薄化します。これにより、敵対的買収のコストや難易度が高まり、買収自体を断念させる効果が期待できます。
なお、日本ではアメリカ型の常設的なポイズン・ピルの導入が難しいため、「事前警告型」と呼ばれる、買収提案がなされた段階で発動する方式が主流です。導入には慎重な判断と株主への説明が必要とされます。
ホワイトナイト
ホワイトナイトは、敵対的買収を仕掛けられた企業が、友好的な第三者に支援を求め、買収を阻止する手法です。外部企業や投資家が株式を取得し、買収者の影響力を抑えて経営権を守ります。
この方法のメリットは、買収を防ぐだけでなく、資本提携によるシナジー効果が期待できる点です。例えば、ホワイトナイトによる支援で企業の成長が促されることがあります。
ただし、新たな支配権の問題が生じるリスクもあるため、慎重な交渉が必要です。
クラウン・ジュエル防衛
クラウン・ジュエル防衛は、敵対的買収者が狙う主要事業や資産を他社やグループ会社に売却し、買収の魅力を低下させる防衛策です。対象事業が失われれば、買収の目的がなくなり、買収者を撤退させることが可能になります。
この手法は買収阻止に有効ですが、主要資産の売却によって自社の事業基盤が弱まるリスクも伴います。実施する際は、長期的な経営戦略を検討することが重要です。
ゴールデン・パラシュート
ゴールデン・パラシュートは、敵対的買収により経営陣が解任された際、多額の退職金や特別報酬を受け取る契約を事前に設定する防衛策です。これにより、買収コストが増大し、買収を断念させる効果が期待できます。
この手法は経営陣の立場を守る目的で導入されますが、株主から「自己保身」と見なされることもあります。そのため、透明性を確保し、株主の理解を得ることが重要です。米国の大企業では広く採用されていますが、日本では導入例が少ない防衛策です。
株式持ち合い
株式持ち合いは、取引先やグループ会社同士で株式を保有し合い、敵対的買収を困難にする防衛策です。安定株主を確保することで、市場での株式取得を難しくし、買収者が支配権を握るのを防ぎます。
この方法のメリットは、経営の独立性を維持し、長期的な安定を確保できる点です。特に、日本では大手銀行や商社が取引先と株式を相互保有し、この仕組みを活用してきました。
しかし、近年はコーポレートガバナンスの強化により持ち合い解消が進んでおり、防衛策としての効果が低下しています。そのため、他の防衛策と併用することが重要です。
敵対的買収を仕掛けられやすい企業の特徴
特定の条件を満たす企業は、買収者にとって魅力的なターゲットとなり、敵対的買収の対象として狙われやすい傾向があります。ここでは、敵対的買収を受けやすい企業の主な特徴を3つ解説します。
株価が割安もしくは低い持株比率である場合
株価が割安で市場評価が低い企業は、敵対的買収のターゲットになりやすい傾向があります。特に、資産価値や収益力に対して株価が低い企業は、買収後の企業価値向上が期待されるため、投資家に狙われやすくなります。
また、持株比率が低く、安定株主が少ない企業も、株式を買い集めやすいため、買収のリスクが高まります。敵対的買収を防ぐには、株主構成を安定化させ、適正な株価を維持することが重要です。
独自の技術や特許を所持している場合
他社にはない独自の技術や特許を持つ企業は、敵対的買収のターゲットになりやすいです。特許技術や独自のノウハウは競争優位性の源泉であり、他社が模倣できないビジネスモデルを持つ企業は、買収者にとって魅力的な存在となります。例えば、製薬業界や半導体業界では、新薬や先端材料の特許を持つ企業が頻繁に買収の対象となっています。
特に、特許の有効期限が長く、競合が参入しにくい領域ほど、収益性の高さから狙われやすくなります。買収を防ぐには、特許戦略を強化し、パートナー企業との連携で経営基盤を固めることが重要です。
買収防衛策を導入していない場合
買収防衛策を導入していない企業は、敵対的買収のターゲットとなる可能性があります。防衛策がなければ、経営陣が迅速に対抗できず、買収者にとって成功しやすい企業と見なされます。
例えば、ポイズン・ピルやホワイトナイトを導入している企業は、買収の難易度が上がり、敵対的買収を避けやすくなります。一方、防衛策を持たない企業は、外部投資家に株式を取得されやすく、経営権を奪われるリスクが高まります。
このように、防衛策を取っていない企業は買収の脅威にさらされやすいため、独立性を維持するには、事前に対策を整え、経営の安定性を高めることが欠かせません。
まとめ|敵対的買収は慎重な対応が必要な買収手法
敵対的買収は、企業価値の向上や市場シェア拡大の可能性があるものの、企業文化の対立や経営の不安定化などのリスクが伴います。敵対的買収を仕掛ける側には緻密な戦略が求められ、また長期的な成長を考えると、友好的買収のほうが企業にとって望ましいケースもあります。
一方、買収対象となる企業の視点で見ると、自社の独立性を保つためには事前の防衛策の導入が重要です。敵対的買収のメリットやデメリット、手法をしっかり理解し、適切に実行、対処を進めていきましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















