CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
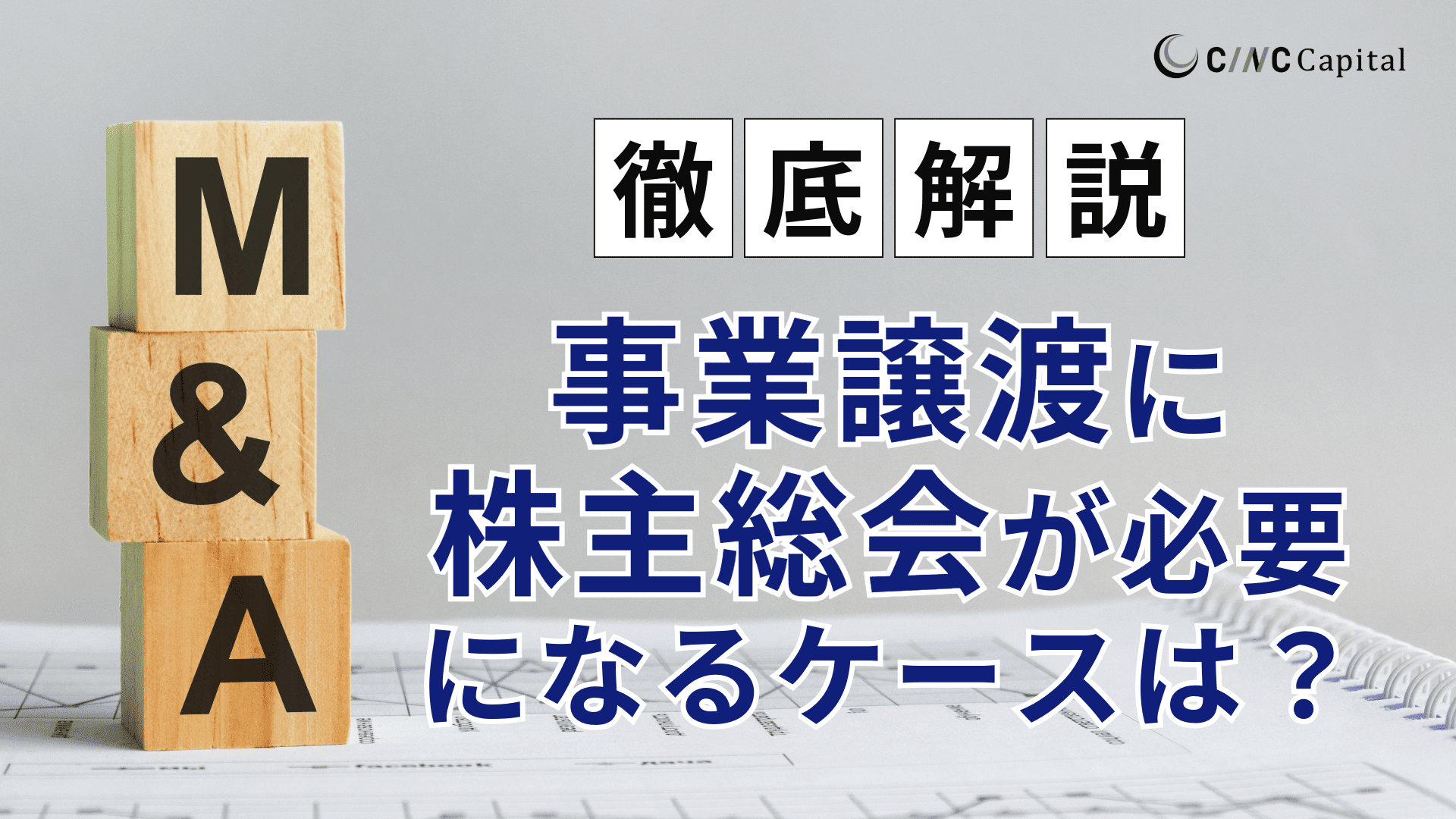
M&A / スキーム
- 公開日2025.09.30
事業譲渡に株主総会が必要となるケースは?特別決議の条件や流れ、よくある質問を解説
事業譲渡は会社の将来を左右する大きな決断であり、その実行には法律上の厳密な規定が存在します。
特に株主総会における特別決議を要するケースでは、綿密な計画と情報の共有が重要です。
そこで本記事では、事業譲渡において株主総会の特別決議が必要となる条件や具体的な手続きの流れを解説します。
目次
事業譲渡で株主総会の特別決議が必要になる条件
事業譲渡は企業活動において重要な戦略の一部ですが、実施にあたっては法的手続きが不可欠です。
特に、会社法第309条第2項の規定では株主総会の特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の中での議決権の3分の2以上の賛成)が必要な場合が明記されています。
事業譲渡において特別決議を求める条件には、売り手側と買い手側それぞれに異なる要件があります。
これらの要件を詳しく見ていきましょう。
【売り手側】株主総会の決議が必要となる条件
会社が事業の全部または重要な一部を譲渡する際には、売り手側において特別決議が求められます。
事業の主要な部分を譲渡すると、会社の経営方針や事業活動に重大な影響を与えるためです。
例えば、製造業を営む会社が、主力製品の製造部門を他社に譲渡する場合、会社全体の事業活動に直接影響します。
多くの株主にとっても関心の高い重大な判断となるため、特別決議が必要です。
また、子会社の株式を譲渡し、議決権の過半数を失う場合場合も、特別決議が必要です。
実質的に子会社の事業を手放すことと同様の影響があるためです。
会社の経営方針や事業活動に関する主要な意志決定に際しては、株主総会を通じて、すべての株主が意思決定の過程に関与する機会を持つことが重要です。
会社の方向性に対する合意を形成し、透明性の高い意思決定を実現します。
したがって、こうした事業譲渡には、特別決議が必要です。
【買い手側】株主総会の決議が必要となる条件
- 「事業の全部」を譲り受ける場合
買い手側が「事業の全部」を譲り受ける場合は、株主総会の特別決議が必要です。
事業内容が大幅に変化し、株主への影響が大きいためです。
- 「事業の一部」を譲り受ける場合
事業の一部のみを譲り受ける場合は、原則として特別決議は不要です。
ただし、以下の場合は例外的に特別決議が必要になります。
- 譲受対価が純資産の1/5を超える場合
- 総議決権の6分の1超を有する株主が反対した場合
例えば、ある小売業の会社が他社の大手小売チェーンの多くの店舗群を一括で譲り受ける場合、実質的に事業の規模や内容が大きく変わるケースでは、特別決議が必要です。
ただし、単に多くの店舗を取得するだけでは「事業の全部」に該当しない場合もあるため、実際の取引内容や規模によって判断されます。
事業譲渡で株主総会の特別決議が不要な条件
企業が事業譲渡を行う際には、特別決議が必要となるケースがあります。
しかし、特定の条件を満たす際には、特別決議を省略できます。
ここでは、売り手側と買い手側それぞれで特別決議が不要となる条件について見ていきましょう。
【売り手側】株主総会の決議が不要となる条件
- 軽微な事業譲渡の場合
売り手側で特別決議が不要になるケースがあります。
軽微な事業譲渡(企業の全体的な規模に対して譲渡の影響がごく小さい)に該当する場合です。
軽微である判断基準としては、譲渡する事業の資産価値が以下の条件を満たす場合です。(会社法第467条第1項第2号)
・譲渡企業の総資産額の20分の1以下(5%以下)
・または定款で定めた割合以下
例えば、企業全体の事業規模に比べて非常に小さい事業部門や、売上高や資産価額がごく一部にすぎない事業を譲渡する場合などが該当します。
ただし、法律上は「売上高の5%未満」といった明確な基準はなく、主に資産価額で判断されます。 -
特別支配会社への譲渡の場合
親会社が総議決権の90%以上を持つ場合(特別支配会社)、その親会社への譲渡の場合も、特別決議は不要です。
したがって、事業譲渡を検討する際には、まず該当する事業が軽微なものかどうかを判断することが重要です。
この判定を行うことで、不要な手続きを省略し、迅速な譲渡が可能です。
【買い手側】株主総会の決議が不要となる条件
買い手側の会社が事業を譲り受ける際、「事業の全部」を譲り受ける場合には特別決議が必要ですが、「事業の一部」を譲り受けることは原則として特別決議は不要です。
ただし、「事業の全部」を譲り受ける場合でも、対価として交付する財産の帳簿価額の合計が、譲受会社の純資産の1/5未満であるケースは、株主総会の決議が不要となります(会社法第468条2項)。
また、一定数の株主(総議決権の6分の1超)が反対した際には、株主総会が必要となる場合もあります。
例えば、企業全体の総資産の5%にも満たない規模の事業を「全部」譲り受ける際には、決議が不要となることがあります。
ただし、「事業の一部」を譲り受けるときは、資産価値や売上規模が企業全体に比べて小さい場合でも、特別決議が不要となるのが原則です。
事業譲渡の計画を進める際には、法的な条件を慎重に確認し、適切な手続きを選択することが重要です。
事業譲渡での株主総会の流れ
事業譲渡を円滑に進めるためには、株主総会の正確な手続きを理解することが重要です。
株主総会の流れを把握しておくことで、法的に求められる要件を満たし、トラブルを避けることができます。
ここでは、事業譲渡における株主総会の基本的な流れとして、株主総会の招集と周知、事前準備、そして実際の総会実施のステップを詳しく見ていきます。
株主総会の招集と周知
株主総会の招集と周知は、すべての株主が参加できるようにするためのステップです。
会社法第299条による、招集通知は総会の2週間前までに送付する必要があり、非公開会社の場合は1週間前までに通知します(定款でさらに短縮可能な場合もあります)。
また、取締役会を設置している会社の場合は総会の1週間前までに通知(定款で定める場合は短縮可能)、取締役会非設置会社の場合も、定款で1週間より短い期間を定めていれば、期限は定款に従います。
事業譲渡がテーマの場合も、会社の種類に応じて期間内に全株主へ通知を行い、総会で議論される議案や関連資料を同封することが望ましいです。
そして、招集通知と同時に総会に関連する資料を事前に提供することで、株主が総会において適切な意思決定をできるように準備を促すことができます。
資料の内容としては、具体的な議案の詳細、事業譲渡の背景情報、およびその影響を記載したものが必要です。
これにより、株主は自らの判断を裏付ける情報を事前にしっかりと把握し、総会に臨むことができます。
事前準備
総会を円滑に運営するためには、準備期間中に多岐にわたる事前準備が必要です。
まず、取締役会で招集事項(開催日・会場・議題など)を決定し、議案や関連資料を整理して、株主にわかりやすく説明できる資料を作成します。
準備段階で法的な手続きについても確認しておくことが、後々のトラブルを防ぐために不可欠です。
事前準備として、以下の作業が必要です。
- 議案説明資料
- 計算書類
- 事業報告書
- 予想される質問に対する想定問答集の作成
- リハーサルやシナリオの作成など
また、会場の手配もポイントであり、会場が手配されていないと総会当日に混乱が生じる可能性があります。
オンライン総会を実施する場合は、技術的な支援を前もって手配することも欠かせません。
株主総会の実施
株主総会の実施は、計画されたすべての議案を株主の前で正式に議論し、決議を行う場です。
総会は、議長(通常は取締役から選任)の挨拶から始まり、各議案が順に提案されます。
それぞれの議案について説明が行われ、株主からの質問や意見が受け付けられたあと、投票手続きが行われ、結果が発表されます。
投票は、一般的に書面または電子投票が採用され、公正かつ透明な方法で集計されるまでが一連の流れです。
議事録の作成
株主総会における議事録の作成は、全ての議事内容を正式に記録するための重要なステップです。
議事録は法律的な証拠となるだけでなく、後日確認や紛争解決の際にも大変役立つため、その内容は正確かつ詳細に作成される必要があります。
例えば、株主総会の開催日時や議長の発言、各議案に対する採決結果、出席した取締役等の氏名など、会社法で定められた情報を漏れなく記載します。
これによって、議事内容に関する認識の相違を防ぎ、透明性を確保します。
会社法第318条第2項により、議事録は、本店で10年間の保管が義務付けられています。
また同条第3項により電子ファイルでの作成・保存も認められています。
また、旧商法時代は議長や出席取締役の署名・押印が義務でしたが、現行会社法では署名・押印は不要です。
ただし、定款や会社の方針によって署名・押印を行う場合もあります。
正確な議事録の作成は、株主総会の信頼性を高め、会社経営の透明性を確保するための要となります。
株主総会後の手続き
株主総会が終了したあとには、決議された内容を具体的に実行するための手続きが必要です。
これは、事業譲渡のような重要な事項について、総会で決定された方針に基づき、迅速かつ正確に履行されることが求められます。
法的な報告なども含まれ、これを怠ると法的な問題を引き起こす可能性があります。
例えば、株主総会で事業譲渡が承認された場合、次に行うべきは事業譲渡契約の締結です。
契約が締結されたあとは、関係する登記の変更や、必要に応じた対外的な発表を行います。
上記の手続きを速やかに進めることで、法的リスクを回避しつつ、ビジネスの連続性を確保することができます。
株主総会の議事録に記載する項目
株主総会の議事録には、開催日時や開催場所、議題など、多岐にわたる要素を正確に記録することが求められます。
ここでは、株主総会の議事録に必ず記載すべき主な項目について解説していきます。
開催日時
株主総会の議事録を作成する際には、開催日時を必ず記載することが重要です。
開催日時がしっかりと記録されていることで、その総会が合法かつ正式に行われたことを証明できます。
開催日時を明確に記載することで、後日になってから総会開催の正当性を確認する際にも役立ちます。
これは会社法施行規則第72条第3項に定められた法定記載事項です。
開催場所
開催場所は株主総会の議事録において重要な項目です。
総会がどこで開催されたかを明確に記載することで、参加株主が実際にその場に出席したことを証明するために重要です。
記録の正確性を保つためには、具体的な住所を記載することが求められます。
「東京都千代田区丸の内1-1-1◯◯ビル会議室」のように住所だけでなく建物名や部屋名も記載することで、どこで会議が行われたかを明確に示し、公式な記録としての価値が高まります。
また、「本店において開催」と記載する際は、登記上の本店所在地であることが前提となります。
「本社」や「事務所」などと記載する場合は、具体的な住所を併記することが実務上の安全策です。
さらに、オンライン開催や遠隔出席の場合は、その出席方法(例:テレビ会議システム)も記載する義務があります。
議長および議事録作成者の氏名
株主総会議事録には、会議を進行する議長の氏名と、議事録作成に係る職務を行った取締役の氏名を記載することが会社法施行規則で義務付けられています。
議事録作成者の記録により、総会が適切な責任者のもとで運営され、議事録の作成にも責任者が存在したことを示すことができます。
例えば、「議長:山田太郎(取締役)、議事録作成に係る職務を行った取締役:佐藤花子」と記載することで、どの人物が会議を指導し、どの人物が議事録の作成に責任を持ったかが明確になります。
これにより、議事録の信頼性と透明性が確保されるのです。
出席株主の氏名および出席株数
株主総会の議事録において、出席した株主の氏名および各株主の保有株数を詳細に記載することは、会社法施行規則で定められた必須記載事項ではありません。
ただし、議事録の冒頭や別紙として「出席株主数」「出席議決権数」を明記することは、実務上よく行われています。
出席株主などの記録を残すことで、総会での議決権行使が正当な株主によって行われたことを示すことができ、透明性の向上にも寄与します。
ただし、法的には議事録本体ではなく、必要に応じて「株主リスト」等として別途作成・保管されることが一般的です。
議案の内容と採決の結果
株主総会の議事録には、会議で議論された議案の詳細と採決の結果を正確に記載することが重要です。
会社法施行規則第72条第3項により、「議事の経過の要領及びその結果」を明記することが義務付けられています
具体的には、どのような議案が提案され、それに対してどのような投票結果が出たのかを明確に記載します。
例えば「第1議案:経営方針の見直し・賛成300株、反対200株」のように、議案名や内容と賛成・反対の具体的な数を記載することも実務上よくありますが、法的には「満場一致で承認可決した」「賛成多数をもって可決した」などの記載で十分です。
特別決議が必要な場合は「3分の2以上の賛成をもって可決した」と決議要件を明記します。
上記のように記載することで、決議の内容や結果に関する情報を公式な形で保存でき、必要に応じて後日確認や検証が容易になります。
また、株主や関係者は決定がどのように達成されたかを容易に把握でき、透明性のある運営が可能です。
総会で述べられた内容の要約
株主総会の議事録には、会議中に述べられた重要な発言や意見を要約して記載することが必要です。
会社法施行規則第72条第3項により「議事の経過の要領及びその結果」を記載することが義務付けられており、議事録には議論の要点や主な発言の概要も含めることが求められています。
「山田社長より、現年度の業績に関する説明が行われた」「田中株主より、今後の経営方針について質問があった」といったように、主要な発言や質疑応答の内容を簡潔にまとめて記載します。
すべての発言を詳細に記録する必要はありませんが、議事の流れや重要なポイントを明確にまとめることで、後日内容を確認したり、参考にしたりすることができます。
事業譲渡の株主総会によくある疑問
事業譲渡においては、株主総会の開催や決議が必要になることがあります。
ここでは、事業譲渡の株主総会に関するよくある疑問とその回答について解説します。
株主が一人の場合は株主総会を開催する?
株主が一人の場合でも、形式的には株主総会を開催する必要があります。
これは会社法の規定によるものであり、決算報告や重要な事項の決定には、一人であっても株主総会の手続きが求められます。
ただし、会社法第300条では、株主全員の同意があれば招集手続きを省略できる制度もあります。
さらに会社法第319条の「みなし決議・報告」という制度を利用すれば、実際の開催を省略して書面上の決議や報告とすることも可能です。
実務上は、オーナーが唯一の株主である中小企業の場合、一人ですべての議決を行うことになりますが、決議内容を文書で記録することが求められます。
これは後々の確認や法的な整合性を保つためにも重要です。
したがって、たとえ株主が一人であっても、株主総会の形式を整え、決議内容を適切に記録することが必要です。
形式的なものであっても、法律に基づく手続きは企業の信頼性や運営に関わる重要な要素ですので、しっかりと記録を残しましょう。
株主総会が必要なのに開催しない場合はどうなる?
株主総会が必要なのに開催しなかった場合、会社法違反となり、会社および役員に対して罰則が科される可能性があります。
会社法第296条により、毎事業年度に1回以上の定時株主総会開催が義務付けられており、違反した場合は会社法第976条第18号により、100万円以下の過料が科されることがあります。
また、過料は会社だけでなく、代表取締役などの役員個人にも課される場合があります。
例えば、事業譲渡が行われたにも関わらず、株主総会を開催しなかった際、その取引自体が無効とされるリスクがあります。
さらに、取締役の報酬や選任なども株主総会決議がないと法的根拠がなくなり、報酬返還請求や損害賠償請求を受ける可能性があるため注意が欠かせません。
株主間でトラブルが発生した場合、過去の決議の有効性が争われることもあり、虚偽の議事録作成も罰則の対象です。
このように、株主総会の開催や手続きの不備は後に大きな問題を引き起こす可能性があるため、慎重に対処することが求められます。
委任状での議決権行使は可能?
委任状を用いて議決権を行使することは可能です。
会社法第310条第1項により、株主が代理人を立てて議決権を行使できることが明記されています。
具体的には、株主が株主総会に直接出席できない場合でも、ほかの者(代理人)に議決権を委任し、その代理人が株主総会で議決権を行使できます。
議決権を行使した際、代理人が株主総会に出席し、委任状(代理権を証明する書面)を会社に提出する義務があります。
委任状を有効に活用することで、議決権を行使できない状況でも株主の意思がきちんと総会に反映されることが大切です。
これは、株主の利益を守り、重要な事業譲渡の際に適切な決議が行われるための基本的な手法の一つといえます。
したがって、株主としては信頼できる代理人を選定し、明確な指示を委任状に記載することが求められます。
利益相反取引に該当する場合の特別な手続きは?
利益相反取引に該当する場合、会社法により特別な手続きが求められます。
利益相反取引とは、会社の利益と取締役や監査役など役員の利益が相反する可能性がある取引を指し、会社の利益を守るために通常の取引よりも厳格な手続きが求められます。
- 取締役会設置会社の場合
取締役会設置会社においては、利益相反取引を行うにあたり、事前に取締役会の承認を得ることが必要です(会社法第356条・365条)。
この際、当該取引に関する重要な事実を取締役会に開示しなければなりません。
さらに、当該取引に特別な利害関係を持つ取締役は、会社法第369条第1項に基づき、承認決議に参加できず、議決権も行使できません。
この規定は、当該取締役による不当な影響を排除し、会社の子旺盛な意思決定を担保する趣旨です。
- 取締役会非設置会社の場合
一方、取締役会を設置していない会社では、利益相反取引については株主総会での承認が必要です(会社法第356条)。
また、承認を得ずに利益相反取引を実施した場合、会社は当該都市引きの無効を主張できる可能性があります。
さらに、役員は会社に損害を与えたと認められるときは、損害賠償責任を問われる可能性もあります。
もっとも、承認が事前に行われていなかった場合でも、事後的に取締役会または株主総会で追認を得ることで、取引の有効性が補完されることもあります。
利益相反取引の際には、会社法の要件に則り、透明性と公正性を確保した手続きを実施することが極めて重要です。
会社は、ガバナンス体制の整備や適切な情報開示を通じて、健全な経営体制を維持することが求められます。
これらの手続きを怠ると、取引の有効性が争われたり、役員に対して法的責任が追及されたりするリスクがあるため、十分な注意が必要です。
事業譲渡におけるガバナンス体制とは、譲渡企業と譲受企業の間で透明性を確保し、責任を明確にするための監視・管理の仕組みを指します。
まとめ:株主総会が必要な事業譲渡かを見極めて手続きを進めましょう
事業譲渡においては、株主総会での適切な決議を経ることが重要です。
特に、株主総会での特別決議が求められる場合、その要件や流れを正確に理解し、適切な準備が企業の透明性と信頼性を確保する鍵となります。
また、場合によっては専門的な知識を必要とする場面も多いため、M&A仲介会社などの専門家への相談が賢明です。
自社に最適な手続きを選択し、法的リスクを回避するためにも、専門的なサポートを活用することをおすすめします。
CINC Capitalは、中小企業庁「M&A支援機関登録制度」に登録された正規支援機関であり、M&A仲介協会の会員でもあります。
業界歴10年以上の実績あるプロのアドバイザーが、事業譲渡に関わる株主総会の準備から実行、契約後のフォローまで、一貫してサポートいたします。
事業譲渡をご検討中の企業様は、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
貴社にとって最適なM&Aのかたちをご提案いたします。

















