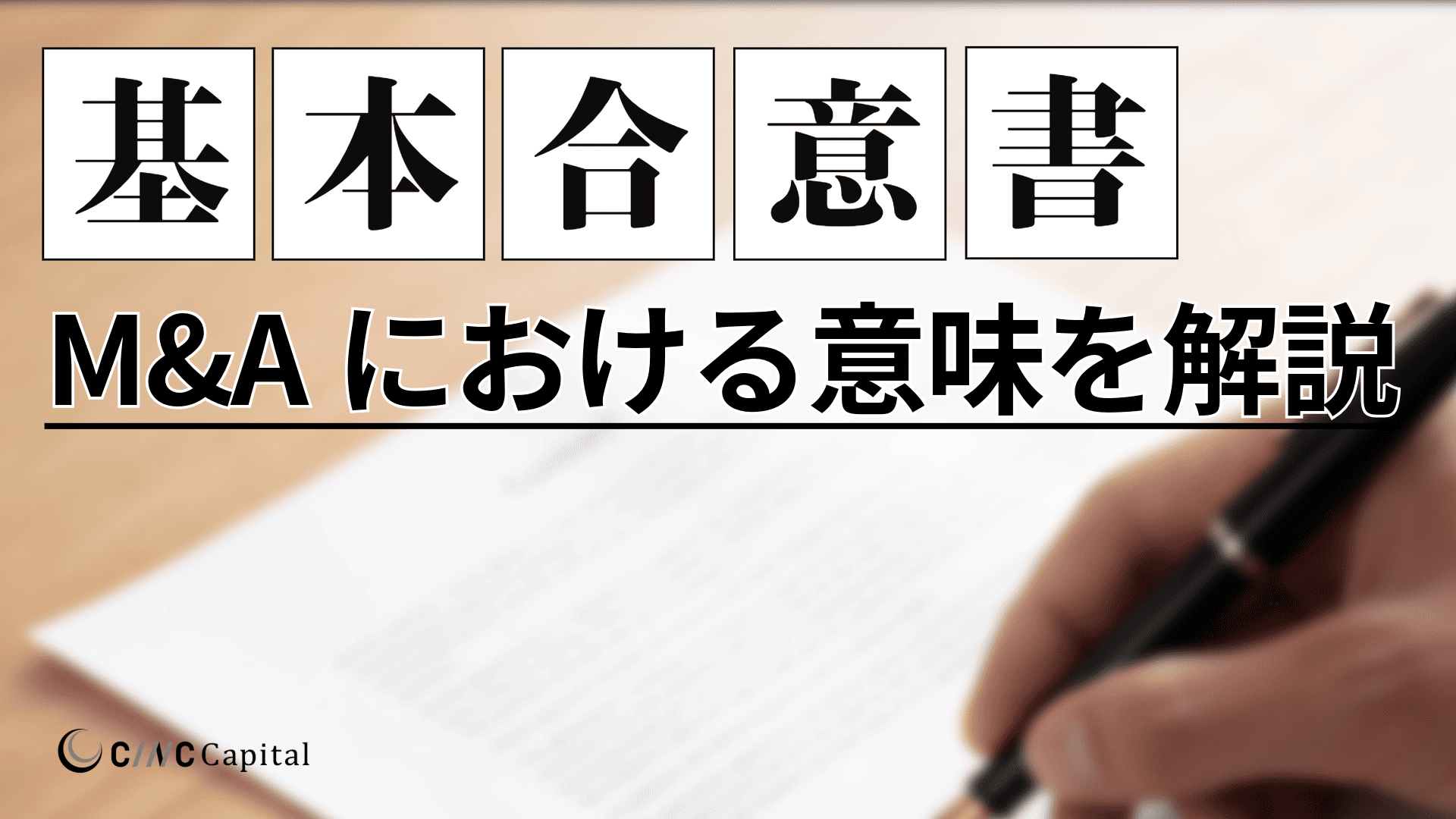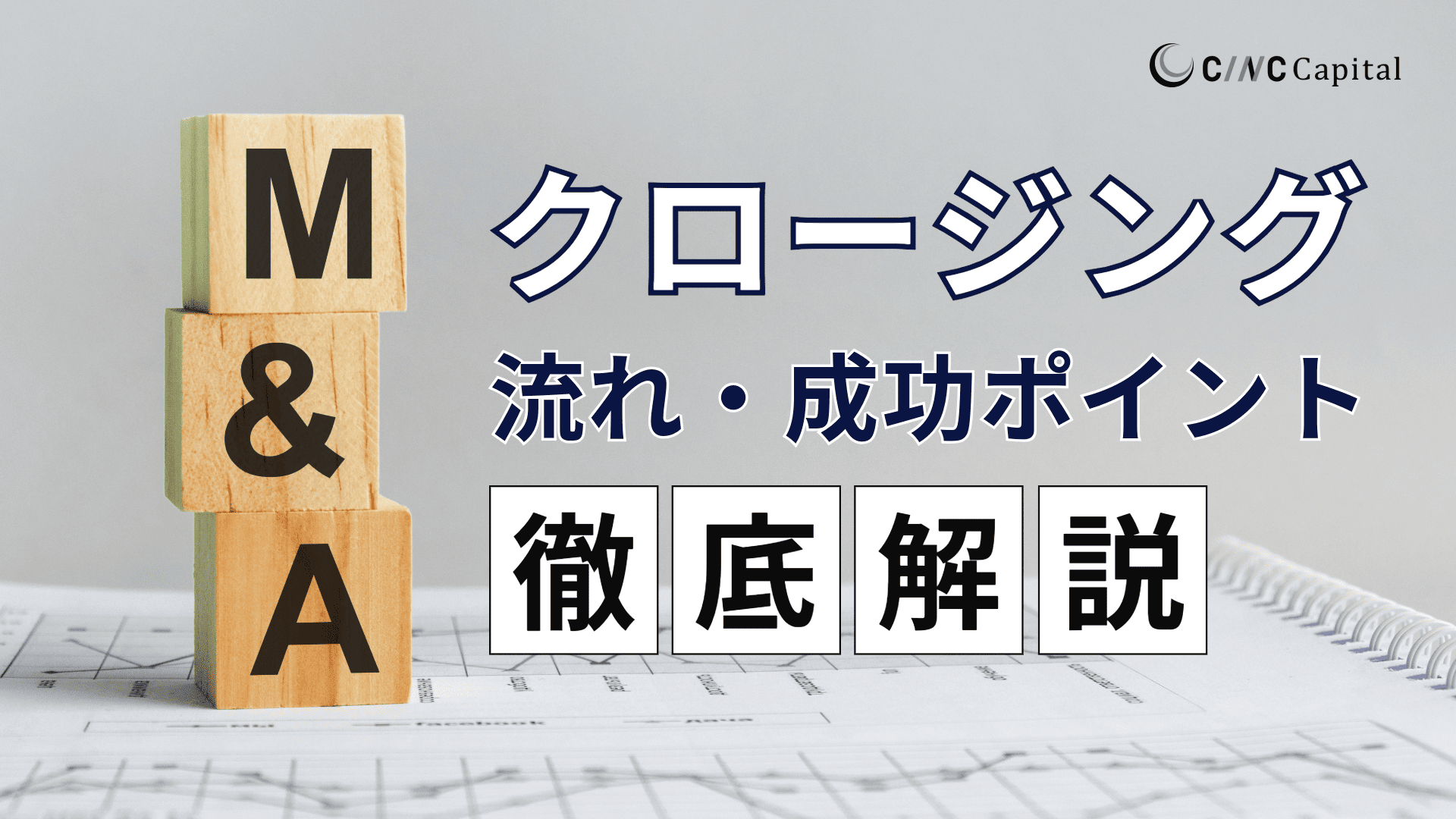CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

M&A / スキーム
- 最終更新日2025.10.16
事業譲渡における会社法のポイントを解説|特別決議や競業避止義務の注意点
事業譲渡は会社の経営に大きな影響を与える重要な取引ですが、法律の理解が不十分なまま進めると、契約の無効やトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、事業譲渡の定義から、株主総会の特別決議、競業避止義務、反対株主の株式買取請求権など、会社法に基づく重要なポイントを詳しく解説します。
目次
事業譲渡の定義
事業譲渡とは、会社が営む事業の全部または一部を他の会社に譲渡する取引です。
M&Aの一手法として位置づけられ、単なる資産売却とは異なり、顧客や契約関係、負債などが引き継がれることもあります。事業譲渡は、企業の経営戦略の一環として利用され、資金調達や不採算事業の整理に活用されることが一般的です。
事業譲渡を行う際は、会社法に沿った手続きが求められます。特に、一定の条件を満たす場合には、株主総会の特別決議が必要です。売り手と買い手双方にとってメリットのある取引ですが、契約内容の精査が不可欠になります。
事業譲渡のメリットとデメリット
事業譲渡には、売り手と買い手にとって大きなメリットがある一方で、慎重な対応が必要なデメリットも存在します。
売り手は、事業を切り離して経営資源を集中できるため、他の事業の強化や新規投資につなげることが可能です。買い手は、特定の事業だけを取得できるため、不要な負債を引き継がずに済みます。
一方で、売り手にとっては契約や許認可の移転手続きが必要になり、時間と労力がかかります。買い手にとっても、従業員の雇用継続や新たな事業運営の負担が発生し、スムーズな移行が求められます。
事業譲渡で重要な会社法第467条と第468条とは?
事業譲渡を行う際には、会社法の規定を正しく理解することが必要です。特に、第467条と第468条は、株主総会の承認要否を定めており、慎重な対応が求められます。
事業譲渡が会社の経営に与える影響が大きい場合は、株主総会の特別決議が必要です。一方で、一定の条件を満たせば、株主総会を開かずに取締役会の決議のみで進められるケースもあります。
適切な手続きを踏めば、事業譲渡を円滑に進められます。ここでは、それぞれの条文について詳しく解説します。
会社法第467条の概要
会社法第467条では、株主総会の特別決議が必要となる事業譲渡を定めています。特別決議とは、議決権を持つ株主の3分の2以上の賛成を要する決議で、通常の決議よりも厳格な基準が求められます。
以下のケースでは、株主総会の特別決議が必要になります。
- 会社の事業の全部を譲渡する場合
- 会社の重要な事業の一部を譲渡する場合(資産の5分の1以上が対象)
- 他社の事業の全部を譲り受ける場合
- 事業の全部を賃貸する場合(または事業経営を委任する場合)
これらのケースでは、株主の利益に大きな影響を与える可能性があるため、慎重に承認を得る必要があります。適切な手続きを怠ると、契約の無効やトラブルにつながるリスクも高まります。
会社法第468条の概要
会社法第468条では、特定の条件を満たす場合に株主総会の特別決議を省略できると定めています。すべての事業譲渡で株主総会の承認が必要になるわけではなく、次のようなケースでは例外が認められます。
- 簡易事業譲渡:譲受会社が譲渡対価として支払う額が、譲受会社の純資産額の20%以下の場合、株主総会の承認を省略できます。取引の規模が小さく、株主の権利への影響が限定的であるためです。
- 略式事業譲渡:譲受会社が譲渡会社の株式を90%以上保有している場合、譲渡会社側での株主総会決議が不要になります。親会社が子会社の事業を取得する際に、形式的な手続きを省略するための規定です。
これらの条件に該当する場合、株主総会の特別決議は不要になります。そのため、取締役会の決議だけで事業譲渡を進めることができます。
ただし、簡易事業譲渡であっても、少数株主が一定割合以上の反対を表明した場合には、特別決議が必要になるケースがあります。そのため、事前に株主への説明を行い、適切に対応することが求められます。
会社法第21条「競業避止義務」に注意する
事業譲渡を行う際、譲渡企業には「競業避止義務」が課されます。競業避止義務とは、事業を譲渡した企業が、譲渡後に譲受企業と競争しないよう制限を設ける規定です。会社法第21条で定められており、譲受企業の利益を保護し、事業の継続性を確保する目的があります。
この義務により、事業を譲渡した会社は、特約がない限り、同一の市町村および隣接する市町村の区域内で、同じ事業を営むことが禁止されます。ただし、この制限は当事者間での合意によって変更できます。
また、競業避止義務の期間について、会社法では「譲渡の日から20年を超えることはできない」と規定されています。これは、「自動的に20年間禁止される」という意味ではなく、「特約によって定める場合でも最長20年までしか設定できない」という意味です。そのため、実際の適用期間は契約内容に依存します。
競業避止義務に違反すると、譲受企業から損害賠償請求を受ける可能性があります。そのため、事業譲渡を行う際は、契約内容を十分に確認し、競業避止義務の範囲や期間を明確にしておくことが重要です。特に、契約によって制限を短縮または緩和できるため、事前に専門家へ相談し、適切な条件を設定することが望まれます。
事業譲渡における反対株主の株式買取請求権とは?
事業譲渡を行う際、反対する株主には株式買取請求権が認められています。これは、会社法第469条で定められている権利であり、特別決議を要する事業譲渡が実施される場合に、反対する株主が会社に対して自己の株式を買い取るよう請求できる制度です。株主が不本意な取引によって損失を被ることを防ぐために設けられています。
この権利を行使するには、事業譲渡に関する株主総会の前に反対の意思を表明し、総会後に買取請求を行う必要があります。株式の買取価格は、株主と会社の協議で決定しますが、合意に至らない場合は裁判所が最終的な価格を決めることになります。
反対株主の権利を考慮せずに事業譲渡を進めると、後の紛争につながる可能性があります。そのため、企業側は事前に十分な説明を行い、適切な手続きを踏むことが重要です。買取請求を行う株主も、権利行使の期限や条件を正しく理解し、適正な手続きを進める必要があります。
事業譲渡の主な手続きの流れ
事業譲渡は、多くの法的手続きや関係者との調整が必要になるため、適切な手順で進めることが求められます。手続きを誤ると、取引の遅延や契約の無効につながる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
手続きの流れは、以下の順で進みます。
- 事前準備
- 基本合意書の締結
- 詳細条件の交渉
- 法的手続きの実施
- 従業員・取引先対応
- クロージング
それぞれの段階で必要な作業や注意点について、見ていきましょう。
事前準備
事業譲渡を進める前に、譲渡対象の事業を整理し、譲渡の目的や条件を明確にする必要があります。この段階では、財務状況の確認や対象事業の評価を行い、譲渡価格の目安を決めることが一般的です。
また、譲渡に伴うリスクを分析し、課題を洗い出すことも重要になります。必要に応じて、M&Aの専門家や弁護士、税理士と相談し、適切な手続きを進められるよう準備を整えます。
基本合意書の締結
基本合意書は、事業譲渡の条件を大枠で合意し、正式契約に向けた交渉の基礎を固めるための文書です。この段階では、譲渡価格や対象事業の範囲、契約締結までのスケジュール、独占交渉権などを取り決めます。
基本合意書には、法的拘束力を持つ条項と持たない条項があります。 具体的には、秘密保持義務、独占交渉権、誠実交渉義務などの条項には法的拘束力が生じることが一般的です。一方で、譲渡価格や具体的な取引条件は拘束力を持たないのが標準的な構成となっています。
また、秘密保持契約(NDA)は、基本合意書を締結する前に別途締結するケースと、基本合意書の中に含めるケースの両方があります。どの形式を取るかは、当事者間の合意や交渉の進め方により異なります。
基本合意書には、通常、有効期限や特定の条件が満たされない場合の無効化条件も含まれます。これにより、交渉が一定期間進展しない場合や、契約締結に至らなかった場合に、当事者双方の権利関係を明確にすることが可能です。
取引の透明性を確保し、円滑な交渉を進めるためにも、契約内容の確認を十分に行うことが重要です。
詳細条件の交渉
基本合意後、譲渡対象の事業について詳しく調査し、最終的な契約条件を交渉します。この段階では、財務・法務デューデリジェンスを実施し、リスクの有無を確認することが重要です。
譲渡価格の最終決定や負債の引き継ぎ範囲、従業員の処遇、事業譲渡後の競業避止義務の内容などを詰め、契約書に反映させます。交渉内容によっては、譲渡の条件が変更されることもあるため、慎重な対応が求められます。
法的手続きの実施
交渉がまとまったら、事業譲渡契約書を締結し、法的手続きを進めます。契約締結には、譲渡企業の取締役会決議が必要であり、一定の規模を超える場合は株主総会の特別決議も求められます。
また、譲渡対象に許認可や特許・商標権が含まれる場合は、行政手続きを経て名義変更を行う必要があります。取引完了後も、契約が適法に履行されるよう、弁護士などの専門家と協力しながら進めることが大切です。
従業員・取引先対応
事業譲渡では、従業員や取引先との関係維持が重要なポイントになります。事業譲渡では労働契約が自動的に承継されないため、従業員の雇用継続には個別の同意が必要です。そのため、従業員への説明や条件交渉を丁寧に行い、安心して勤務を継続できるよう配慮することが求められます。
取引先に対しても、事業譲渡の内容を適切に伝え、契約の引き継ぎや条件変更を交渉する必要があります。特に、取引契約が譲渡によって影響を受ける場合は、円滑な引き継ぎができるよう調整することが重要です。
クロージング
クロージングは、事業譲渡契約に基づき、実際に譲渡を完了させる最終手続きです。この段階では、譲渡対象の資産や契約の名義変更、従業員の転籍手続き、対価の支払いなどを実行します。
譲渡完了後は、譲渡企業と譲受企業が引き継ぎ業務を行い、取引先や顧客に対して事業の継続性を示すことが求められます。クロージングを円滑に進めることで、事業の安定した運営が実現できます。契約内容が適切に履行されているかを確認し、問題があれば迅速に対応することも重要です。
まとめ|会社法と特別決議の内容を理解し、事業譲渡を備えよう
事業譲渡を成功させるには、会社法の規定を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが重要です。特別決議の要否を判断し、必要な承認を得ることで、法的リスクを回避できます。
競業避止義務や反対株主の株式買取請求権にも注意し、契約内容を慎重に確認することが求められます。弁護士や税理士と連携し、計画的に進めることで、スムーズな事業移行が実現できるでしょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。