CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
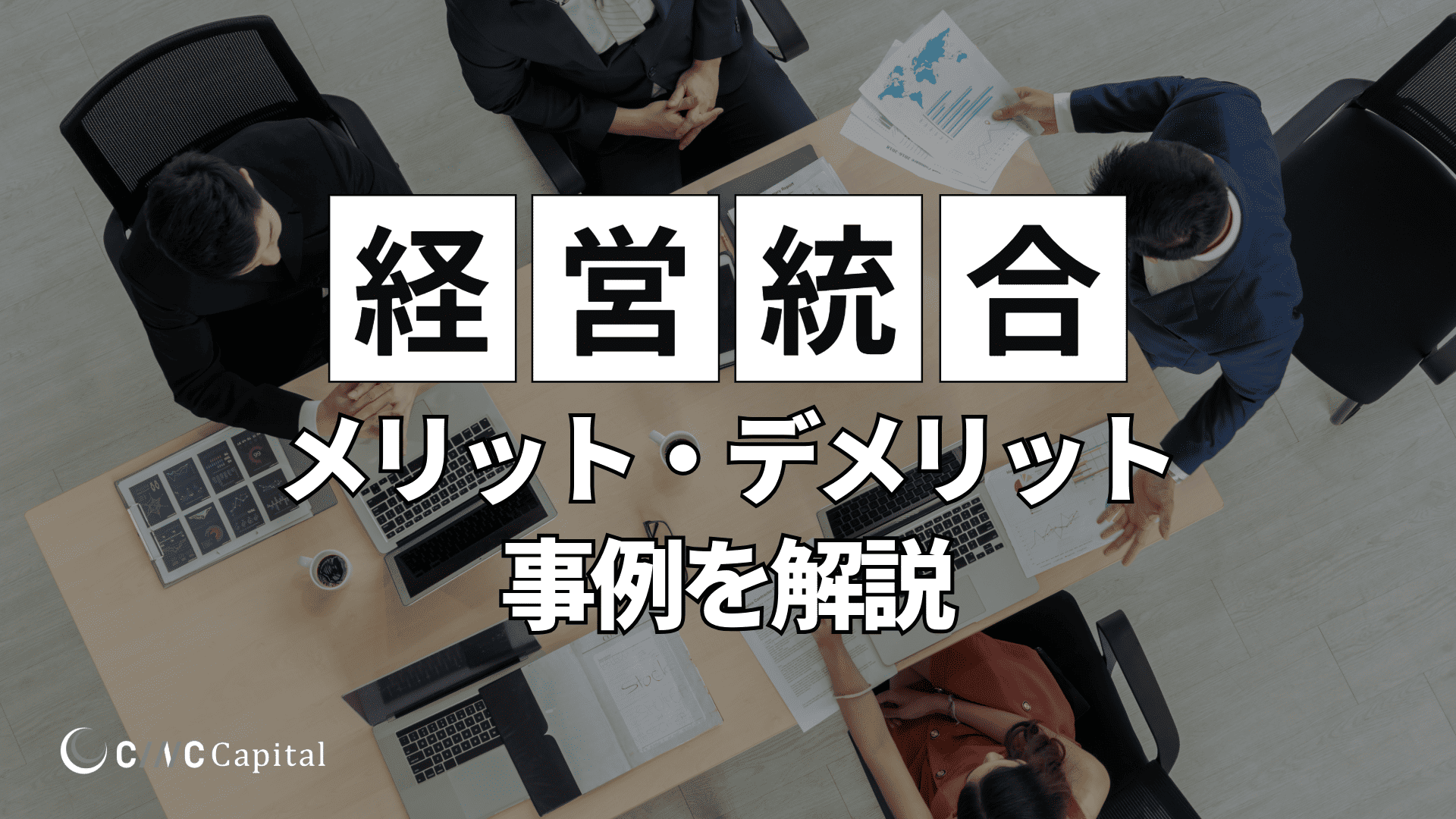
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.06.26
経営統合とは?合併や買収との違い、メリットデメリット、事例をわかりやすく解説
市場競争の激化や事業拡大を見据え、企業同士の統合を検討するケースが増えています。しかし、経営統合の仕組みやメリット・デメリット、他の手法との違いがわからず、判断に迷うこともあるでしょう。
本記事では、経営統合の概要や目的、合併・買収との違い、実際の進め方、統合事例を詳しく解説します。経営統合を適切に活用することで、企業の競争力強化や成長戦略を実現できる可能性があります。
目次
経営統合とは?
経営統合とは、複数の企業が経営を一体化し、競争力を高める手法の一つです。
合併やM&Aと並ぶ企業再編の選択肢として活用されることも多く、対等な関係での統合が特徴です。
まずは、経営統合の目的や合併・買収との違い、子会社との違い、資本提携・業務提携との違いについて詳しく解説します。
経営統合の目的
経営統合の主な目的は、企業同士の強みを活かし、シナジー効果を生み出すことです。特に、事業規模の拡大、コスト削減、技術力の向上、マーケットシェアの拡大が主要な目的となります。例えば、製造業では研究開発の効率化、小売業では物流網の統合などが考えられます。
また、経営環境の変化に対応するために統合を行うケースもあります。市場競争の激化や、グローバル化の進展により単独企業では対応が難しい場合、統合によって持続可能な成長を目指すことがあります。このように、経営統合は単なる企業の結合ではなく、より強固な企業グループを形成し、持続的な競争優位性を確立するための戦略といえます。
合併との違い
経営統合と合併は混同されがちですが、両者には大きな違いがあります。合併では、企業の法人格が一つに統合され、消滅する企業も出ます。一方、経営統合では、企業の法人格を維持する場合が多く、持株会社方式などでグループ化する点が特徴です。
例えば、企業Aと企業Bが合併すると、どちらか一方が存続会社となり、もう一方は消滅します。これに対し、経営統合では新たに持株会社Cを設立し、AとBはその傘下に入る形となります。この仕組みにより、各企業のブランドや事業運営の独立性を保ちながら、グループ全体の経営効率を向上させることができます。
合併では統合後の経営方針が一本化されやすい半面、企業文化の違いや組織再編の負担が大きくなります。一方、経営統合では、シナジー効果を生み出しつつ、各社の強みを活かせるメリットがあります。
買収との違い
買収とは、一方の企業がもう一方の企業の株式を取得し、一定の経営権を獲得することを指します。買収には、経営権を完全に掌握するケースと、出資比率を抑えて経営に関与するケースの両方が含まれます。これに対し、経営統合では企業同士が対等な立場で経営を一体化するため、主導権の所在が異なります。
買収は、企業が成長戦略の一環として競争力を高める手段の一つですが、買収される企業側の意向が反映されにくい点がデメリットです。例えば、A社がB社を買収した場合、B社の経営方針はA社によって決定されることが一般的です。
一方、経営統合では、企業同士が対等な立場で協力し、持株会社方式などを活用しながら経営を統合することが一般的です。この違いにより、買収は経営権の移転が主体となるのに対し、経営統合は協調的な成長戦略として位置づけられます。
子会社との違い
子会社とは、親会社がその会社の議決権の過半数(50%超)を保有し、経営を支配している企業のことです。経営統合と異なり、子会社化では親会社が支配的な立場に立ち、経営方針を決定することが一般的です。
例えば、A社がB社の議決権付き株式を51%保有すれば、B社はA社の子会社と見なされます。このような場合、B社の経営判断はA社の意向に大きく影響されるため、独立性は低くなります。一方、経営統合では通常、持株会社を設立し、各企業の法人格を維持したまま経営を統括する形となるため、各社の自主性が一定程度保たれます。
そのため、経営統合はグループ全体のシナジーを活かしながら、参加企業のブランドや事業戦略を継続できる柔軟な仕組みとして機能します。対照的に、子会社化では支配関係が明確になる分、親会社の経営方針に従う必要があるため、戦略の自由度が制限されることがあります。
資本提携や業務提携との違い
資本提携と業務提携は、経営統合と異なり、企業の独立性を維持したまま特定の領域で協力関係を築く形態です。経営統合では企業全体が一体となるのに対し、これらの提携では限定的な協力にとどまります。
資本提携
資本提携とは、企業が他社の株式を一定割合取得することで、資本関係を築きつつ協力体制を強化する手法です。株式の取得は一方向でも成立し、必ずしも相互保有である必要はありません。また、取得比率も様々であり、数%の少数持分から、子会社化に至らない範囲での資本参加まで幅広く存在します。
資本提携のメリットは、経営権を移譲せずに、戦略的なパートナーシップを形成できる点にあります。例えば、大企業がスタートアップ企業の株式を取得して資本提携をすることで、共同開発や販路拡大を目的とした協力関係を築けます。
業務提携
業務提携は、特定の事業分野において協力関係を築くことを指します。例えば、A社とB社が販売網を共有する業務提携を結ぶ場合、両社の流通ネットワークを活用して相互の売上向上を図ることができます。
業務提携のメリットは、経営統合や資本提携よりも柔軟に事業戦略を変更できる点です。一方で、提携関係が解消されるリスクもあるため、長期的な視点での関係構築が重要になります。
経営統合の種類
経営統合には、企業同士がどのように統合するかによって複数の方式が存在します。その中でも主要な方法が「株式交換方式」と「株式移転方式」です。これらの手法は、企業が持株会社を設立するか、あるいは既存の企業を親会社とするかによって異なります。以下では、それぞれの特徴とメリット・デメリットについて解説します。
株式交換方式
株式交換方式とは、一方の企業が親会社となり、もう一方を完全子会社とする経営統合の手法です。具体的には、親会社となる企業が子会社となる企業の全株式を取得し、その対価として自社の株式を交付します。この方式を採用すると、現金を用いずに統合できるため、資金負担が少ない点が特徴です。
株式交換方式の利点は、迅速に統合を実現できることです。企業間で交渉がまとまれば、法的手続きを経て短期間で統合が完了します。また、既存の親会社を活用するため、新たな持株会社を設立する必要がなく、スムーズな経営統合が可能です。
一方で、デメリットとしては、親会社と子会社の関係が明確になるため、子会社側の経営の自由度が制限される点が挙げられます。また、親会社の株式を対価とするため、既存株主の持株比率が希薄化する可能性があることにも注意が必要です。
株式移転方式
株式移転方式とは、新たに持株会社を設立し、その持株会社が統合する企業の全株式を取得する方式です。これにより、統合企業は新設の持株会社の完全子会社となります。この方式は、両社が対等な立場で経営統合を進めたい場合に適しています。
株式移転方式のメリットは、統合する企業が対等な関係を維持できる点にあります。新たに持株会社を設立するため、企業間の力関係が明確になりにくく、公平な統合が実現しやすくなります。また、持株会社が経営戦略を統括し、各子会社の事業運営を最適化できることも利点の一つです。
ただし、デメリットもあります。持株会社の設立に伴い、法的手続きや準備に時間とコストがかかるため、統合までに長期間を要する可能性があります。また、新たな経営管理機構を構築する必要があるため、運営の複雑さが増す点も課題となります。
経営統合を行うメリット
経営統合は、単なる企業の合併や買収とは異なり、各社の法人格を維持しながらシナジー効果を発揮する点が特徴です。適切に経営統合を進めることで、企業の競争力強化や経営効率の向上が期待されます。ここでは、主なメリットとして「シナジー効果の創出」「独立性・自主性の維持」「従業員の混乱抑制」の3つについて解説します。
シナジー効果が期待できる
経営統合の大きなメリットは、シナジー効果を生み出せることです。シナジー効果とは、複数の企業が統合することで単独では得られない成果を上げることを指します。例えば、製造業では共同調達によるコスト削減、小売業では物流の効率化が実現できます。
シナジー効果を得ることで、企業全体の収益力が向上し、市場競争力が強化されます。また、技術やノウハウの共有により、新製品開発のスピードが向上し、成長の加速も期待できます。その一方で、統合後の経営戦略が不明確な場合、シナジー効果が十分に発揮されないリスクもあるため、事前の綿密な計画が重要です。
独立性・自主性の維持につながる
経営統合は、各企業が独立性や自主性を保ちながらグループ経営を行えます。合併では一つの法人に統一されるため、企業文化や経営スタイルの違いが問題になりやすいですが、経営統合では各社が法人格を維持できるため、柔軟な経営が可能です。
例えば、持株会社方式の経営統合では、統合後も各企業が独自のブランドや事業戦略を継続できます。これにより、統合前の企業文化や強みを活かしつつ、グループ全体での競争力を高めることができます。特に異なる業種の企業が統合する場合、それぞれの独立性を維持しながらシナジーを生かす経営が求められます。
ただし、統合後も各社が完全に独立していると、グループ全体の意思決定が遅れる可能性があるため、統一された経営方針の策定が重要です。適切なガバナンスを整備し、柔軟性と統制のバランスを取ることが、統合成功の鍵となります。
従業員の混乱を抑制できる
経営統合は、合併とは異なり、組織の大規模な再編を伴わないため、従業員の混乱を最小限に抑えることができます。合併では、社名変更や組織の統廃合が発生し、従業員の不安が増大することがあります。しかし、経営統合では企業の独立性が保たれるため、既存の社内制度や企業文化を維持しながら統合を進められます。
例えば、経営統合によってグループ内の企業が協力体制を強化し、業務プロセスを標準化することで、従業員にとっても明確なキャリアパスが確保されやすくなります。また、統合に伴うリストラのリスクも低いため、従業員のモチベーションが維持されやすい点もメリットです。
ただし、統合後の経営方針や役割分担が不明確な場合、従業員の不安が生じる可能性があります。そのため、経営陣は統合の目的やメリットを適切に説明し、社内コミュニケーションを強化することが求められます。
経営統合を行うデメリット
経営統合には多くのメリットがある一方で、組織運営や統合プロセスにおいてデメリットも存在します。特に、「組織の煩雑化」「統合作業の負担」「株価の変動リスク」は、統合を進める上で慎重に対応するべき課題です。ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
組織の煩雑化のおそれがある
経営統合を行うと、グループ全体の規模が拡大するため、組織運営が煩雑になる可能性があります。特に、異なる企業文化や業務プロセスを持つ企業同士が統合する場合、意思決定のスピードが低下し、組織の一体感を損なうリスクが生じます。
統合によって管理部門の役割が増加し、重複する業務が発生することもあります。例えば、人事や経理などのバックオフィス部門が各企業ごとに存在すると、業務の効率化が難しくなります。また、企業ごとに異なるシステムを使用している場合、それらを統合するための調整作業が必要となり、コストや時間の負担が増大します。
こうした問題を回避するためには、統合前の段階で組織の最適な管理体制を設計し、必要に応じて業務プロセスを標準化することが求められます。経営陣が適切なガバナンスを確立し、グループ全体の効率性を維持できる体制を整えることが、成功の鍵となります。
統合の作業には負担がかかる
経営統合を実現するためには、財務・法務・システムなどの多岐にわたる統合作業が必要です。このプロセスには膨大な時間とコストがかかるため、統合が完了するまで企業の経営資源が分散し、本業の業務に影響を及ぼす可能性があります。
統合の初期段階では、基本合意書の締結やデューデリジェンス(Due Diligence: DD)を実施し、企業の財務状況や法的リスクを精査する必要があります。その後、統合条件の交渉や契約締結、各種法的手続き、従業員や取引先への説明など、慎重な対応が求められます。さらに、システムの統合やブランド戦略の調整など、実務レベルでの調整も欠かせません。
これらの作業に適切に対応しないと、統合後の事業運営に混乱を招く可能性があります。そのため、事前に統合準備委員会を設置し、明確なロードマップを作成することが重要です。スムーズな統合を実現するためには、専任の統合チームを組織し、関係者との調整を綿密に行う必要があります。
株価の変動に注意が必要となる
経営統合が発表されると、市場の期待や不安によって株価が変動することがあります。特に、統合の目的やシナジー効果が市場に十分に理解されない場合、投資家の不安感が高まり、株価が下落するリスクがあります。
株式交換方式や株式移転方式を用いる場合、統合比率(交換比率)が適正かどうかも株価に影響を与えます。例えば、買収する側の企業の株価が過大評価されていると、市場からの信頼を失い、統合後の株価下落を招く可能性があります。また、統合によって業績の先行きが不透明になると、一時的な売りが発生し、株価が変動しやすくなります。
株価の安定を図るためには、統合の意図やメリットを投資家に十分に説明し、市場とのコミュニケーションを強化することが不可欠です。適切なIR戦略を展開し、透明性のある情報開示を行うことで、株主の信頼を維持し、株価の過度な変動を抑えることが求められます。

経営統合の流れ
経営統合は、企業同士の合意形成から法的手続き、実務統合まで、複数の段階を経て完了します。統合をスムーズに進めるためには、各プロセスを適切に管理し、ステークホルダーとの調整を行うことが不可欠です。ここでは、経営統合の一般的な流れとして「基本合意書の締結」「デューデリジェンスの実施」「統合条件の交渉と確定」「正式契約の締結」「法的手続きの実行」「ステークホルダーへの対応」「統合準備委員会の設置と実務作業」「クロージング」について解説します。
基本合意書の締結
経営統合の第一歩として、企業間で基本合意書(MOU: Memorandum of Understanding)を締結します。これは、統合の基本方針や目的、交渉の進め方を明確にし、今後の詳細な協議の土台を作るための重要な文書です。
基本合意書を締結することで、両社の経営陣や株主に対し、統合の方向性を示すことができます。これにより、企業価値の向上や競争力強化といった統合の目的を明確にし、経営統合に向けた具体的なプロセスを進めることが可能となります。
ただし、この段階では法的拘束力を持たないことが一般的であり、統合が確定するわけではありません。そのため、基本合意書の内容を慎重に設計し、両社の戦略的な合意を得ることが重要です。
デューデリジェンス(DD)の実施
基本合意書を締結した後、デューデリジェンスを実施し、統合対象の企業の財務・法務・事業の詳細を精査します。これは、統合後のリスクを正確に把握し、適切な意思決定を行うために不可欠なプロセスです。
デューデリジェンスでは、財務状況の確認、法的リスクの洗い出し、業務プロセスの評価などが行われます。例えば、財務デューデリジェンスでは負債やキャッシュフローの健全性を調査し、法務デューデリジェンスでは契約や知的財産権の問題を確認します。
この段階で問題が発見された場合、統合条件の修正や契約の再交渉が必要になることもあります。そのため、デューデリジェンスの結果を慎重に分析し、リスクに適切に対処することが求められます。
統合条件の交渉と確定
デューデリジェンスの結果を踏まえ、統合の具体的な条件を交渉し、最終的な合意を形成します。このプロセスでは、株式交換比率、経営体制、統合後のブランド戦略など、重要な事項が議論されます。
統合条件の交渉では、両社の利害が対立することもあるため、公平な基準で条件を設定することが重要です。例えば、経営権の分配や取締役会の構成について、統合の目的に沿ったバランスを取る必要があります。
交渉がまとまった後は、正式な合意書を作成し、関係者と共有します。この段階で慎重な調整を行うことで、統合後のトラブルを防ぎ、スムーズな統合作業が可能になります。
正式契約の締結
統合条件が確定した後、経営統合契約を正式に締結します。この契約では、統合の実施方法、各社の役割、統合後の経営体制などが詳細に定められます。
正式契約を締結することで、統合に関する両社の義務と責任が明確になり、経営統合が法的に確定します。この段階では、株主総会の承認を得る必要がある場合もあり、関係者への説明を十分に行うことが求められます。
契約締結後は、法的手続きや統合作業を進める段階へと移行します。
法的手続きの実行
正式契約を締結した後、経営統合に必要な法的手続きを実施します。株式交換や株式移転の登記、独占禁止法(競争法)上の審査、監督当局への届出などが含まれます。
特に、独占禁止法の規制に該当する場合は、公正取引委員会などの審査を受ける必要があります。この審査では、市場競争への影響が評価され、承認が得られなければ統合を進めることはできません。
法的手続きは、統合のスケジュールに大きく影響するため、早期に準備を進めることが重要です。
ステークホルダーへの対応
経営統合の成功には、株主、従業員、取引先などのステークホルダーの理解と協力が不可欠です。統合によって事業環境が変化するため、適切な情報開示と説明が求められます。
例えば、従業員には統合後の雇用や待遇に関する説明を行い、不安を払拭する必要があります。株主に対しては、統合のメリットやシナジー効果を具体的に説明し、統合の意義を理解してもらうことが重要です。
ステークホルダーの信頼を得ることで、統合後のスムーズな運営が可能になります。
統合準備委員会の設置と実務作業
正式契約を締結した後、統合準備委員会を設置し、実務レベルでの統合作業を進めます。財務、人事、ITシステムの統合など、具体的なタスクを管理することが目的です。
この委員会が円滑に機能することで、統合後の業務の混乱を防ぎ、迅速に一体化を実現できます。関係部署と連携しながら、統合プロセスをスムーズに進めることが求められます。
クロージング
最終段階として、統合の実施日(クロージング)を迎えます。この日をもって、統合契約の内容が正式に発効し、新たな経営体制がスタートします。
クロージング後は、統合後のシナジーを最大限に活かすための施策を実施し、経営統合の成果を具体的に示すことが重要です。
経営統合の事例
経営統合は、日本国内外で様々な業界において進められています。企業の競争力向上や市場の変化への対応として、多くの企業が統合を選択しています。ここでは、3つの経営統合の事例について解説します。
本田技研工業と日産自動車の経営統合
本田技研工業株式会社と日産自動車株式会社は、2024年末に経営統合の協議を開始しました。統合の目的は、電動化・自動運転技術の進化に対応し、競争力を高めることでした。両社は共同持株会社の設立を検討し、統合によるシナジー効果を最大化する計画を立てていました。
経営統合が実現すれば、開発費の削減や技術の共有により、EV市場での競争優位性を強化できると期待されていました。しかし、統合に向けた詳細な交渉の過程で、経営方針や組織体制の違いが浮き彫りになりました。特に、本田技研側が「株式交換による統合」を提案したのに対し、日産側が「対等な立場での経営統合」を希望したことが調整の難航につながりました。
最終的に、2025年2月に両社は統合協議を解消すると発表しました。発表では「独立性を維持しながら電動化と技術開発を進める方針に変更する」と説明されており、統合には至らなかったものの、両社は戦略的提携を継続する意向を示しました。
【出典】本田技研工業株式会社「日産自動車とHonda、経営統合に向けた検討に関する基本合意書を締結」
マツモトキヨシホールディングスとココカラファインの経営統合
株式会社マツモトキヨシホールディングスと株式会社ココカラファインは、2021年に経営統合を完了し、日本国内最大級のドラッグストアグループを形成しました。この統合の目的は、店舗網の拡大と調剤薬局事業の強化、そしてプライベートブランド(PB)商品の共同開発でした。
両社は株式交換方式を採用し、マツモトキヨシがココカラファインを完全子会社化する形で統合しました。これにより、約3,000店舗を超える大規模なドラッグストアチェーンが誕生しました。統合後の新会社「マツキヨココカラ&カンパニー」は、既存のブランドを維持しつつ、経営基盤の強化を進めています。
統合のメリットとして、共同仕入れによるコスト削減、デジタル化の推進、顧客データの活用が挙げられます。特に、ECサイトと実店舗の連携強化により、利便性を高める施策が展開されました。一方で、システム統合や社内文化の融合に時間を要するなど、統合初期の課題も見られました。
2025年現在、グループ全体での業務最適化が進められており、業界内での競争力が一層強化されています。統合によって国内市場における地位を確立しつつ、今後は海外展開も視野に入れた戦略を進める計画です。
【出典】株式会社マツキヨココカラ&カンパニー「株式会社マツモトキヨシホールディングスと株式会社ココカラファインとの経営統合に際しての吸収分割契約の締結等のお知らせ」
日本アンテナとエレコムグループの経営統合
無線通信機器メーカーである日本アンテナ株式会社は、2024年にエレコムグループとの経営統合を発表しました。統合の目的は、通信機器事業の強化と新技術開発の加速です。エレコムは、グループ内のDXアンテナと日本アンテナを統合し、無線通信分野での競争力を高める狙いがありました。
統合は、株式交換方式によりエレコムが日本アンテナを完全子会社化する形で進められました。この統合により、エレコムグループは、放送用・通信用アンテナ市場でのシェア拡大を実現し、5G通信関連事業の強化にもつなげています。
日本アンテナにとって、この統合は経営基盤の強化と研究開発リソースの拡充につながるものでした。特に、エレコムの資本力とマーケティング力を活用することで、国内外の市場開拓を進めやすくなりました。
統合後の課題として、ブランド戦略や販売チャネルの調整が挙げられます。エレコムの既存事業とのシナジーを最大化するため、各部門の連携を強化する必要があります。今後は、無線技術の開発強化と海外市場の拡大を重点課題として取り組む計画です。
【出典】エレコム株式会社「日本アンテナ株式会社の株式交換による完全子会社化及びエレコムグループとの経営統合に関する基本合意書の締結に関するお知らせ」
まとめ|独立性の維持・シナジー効果を期待している企業には経営統合がおすすめ
経営統合は、独立性を保ちながらシナジー効果を生み出せる有効な戦略です。市場競争の激化や技術革新に対応し、成長を加速させる企業に適しています。一方で、組織の複雑化や統合作業の負担、株価の変動リスクが伴うため、慎重な準備が不可欠です。
成功の鍵は、統合の目的を明確にし、適切なプロセスを設計することにあります。シナジー効果を最大化し、競争力を強化するためには、経営戦略の統一とステークホルダーへの対応が重要です。経営統合を検討する企業は、事前の計画を綿密に行い、持続的な成長を実現する体制を整えることが求められます。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















