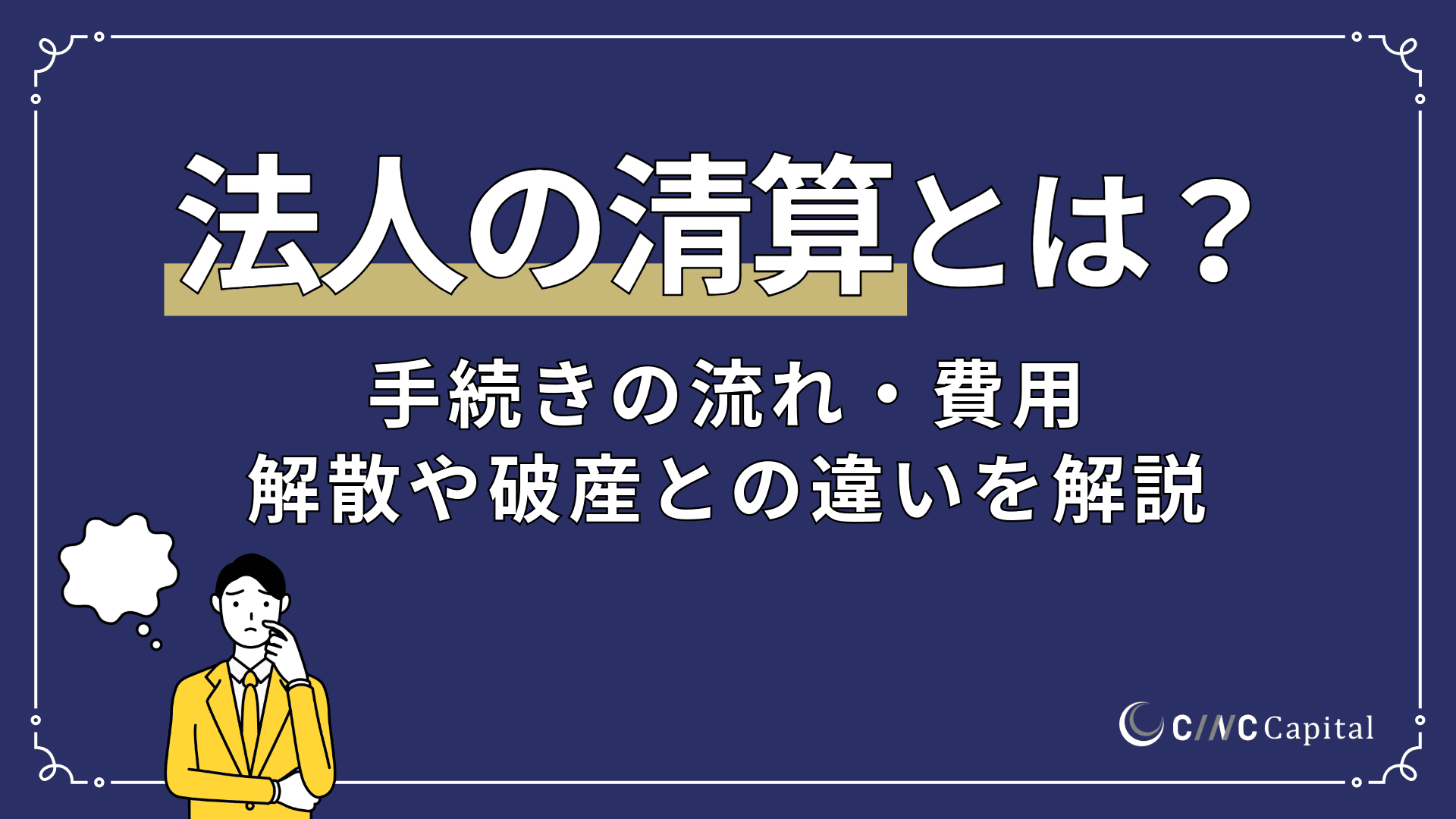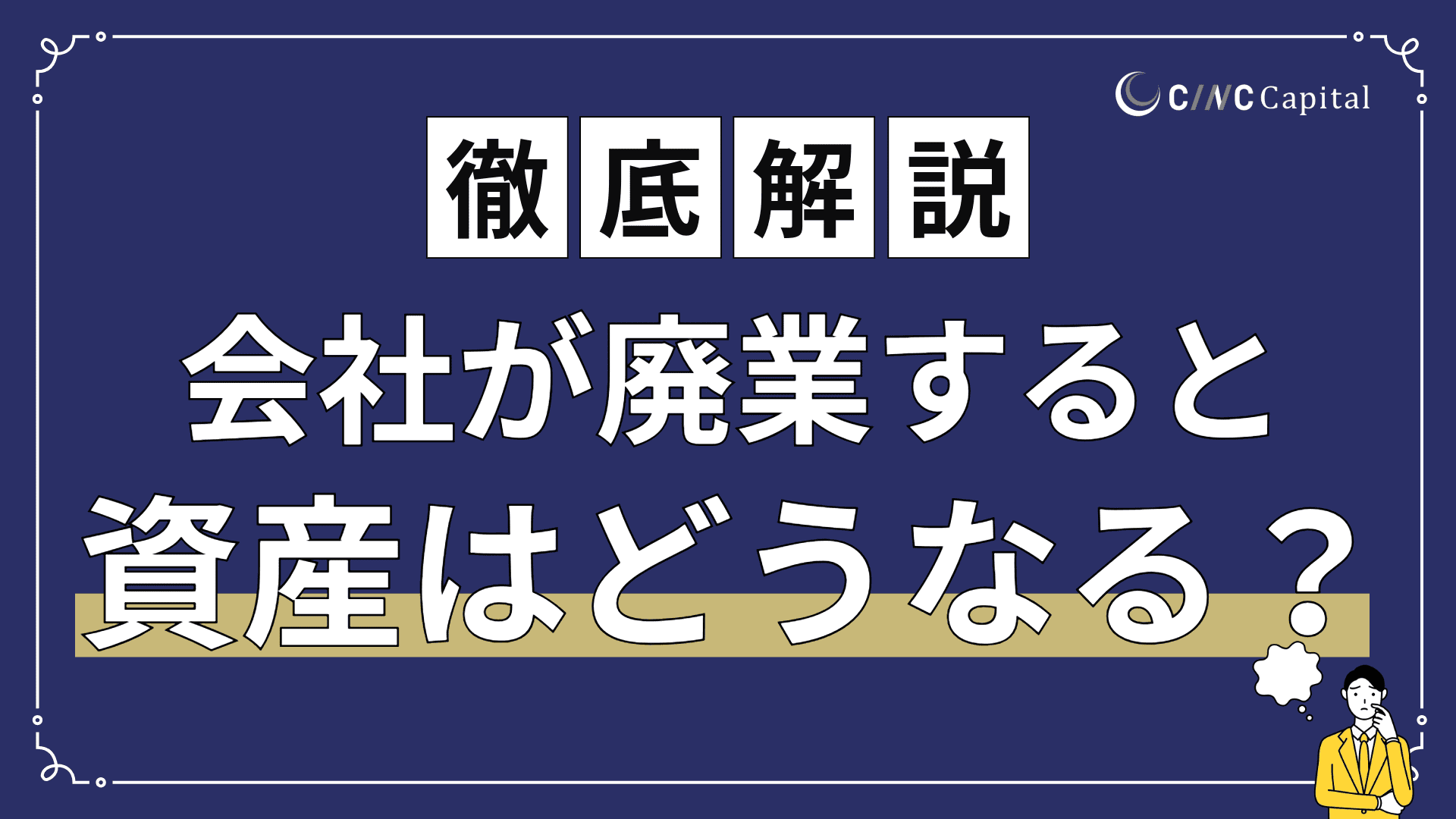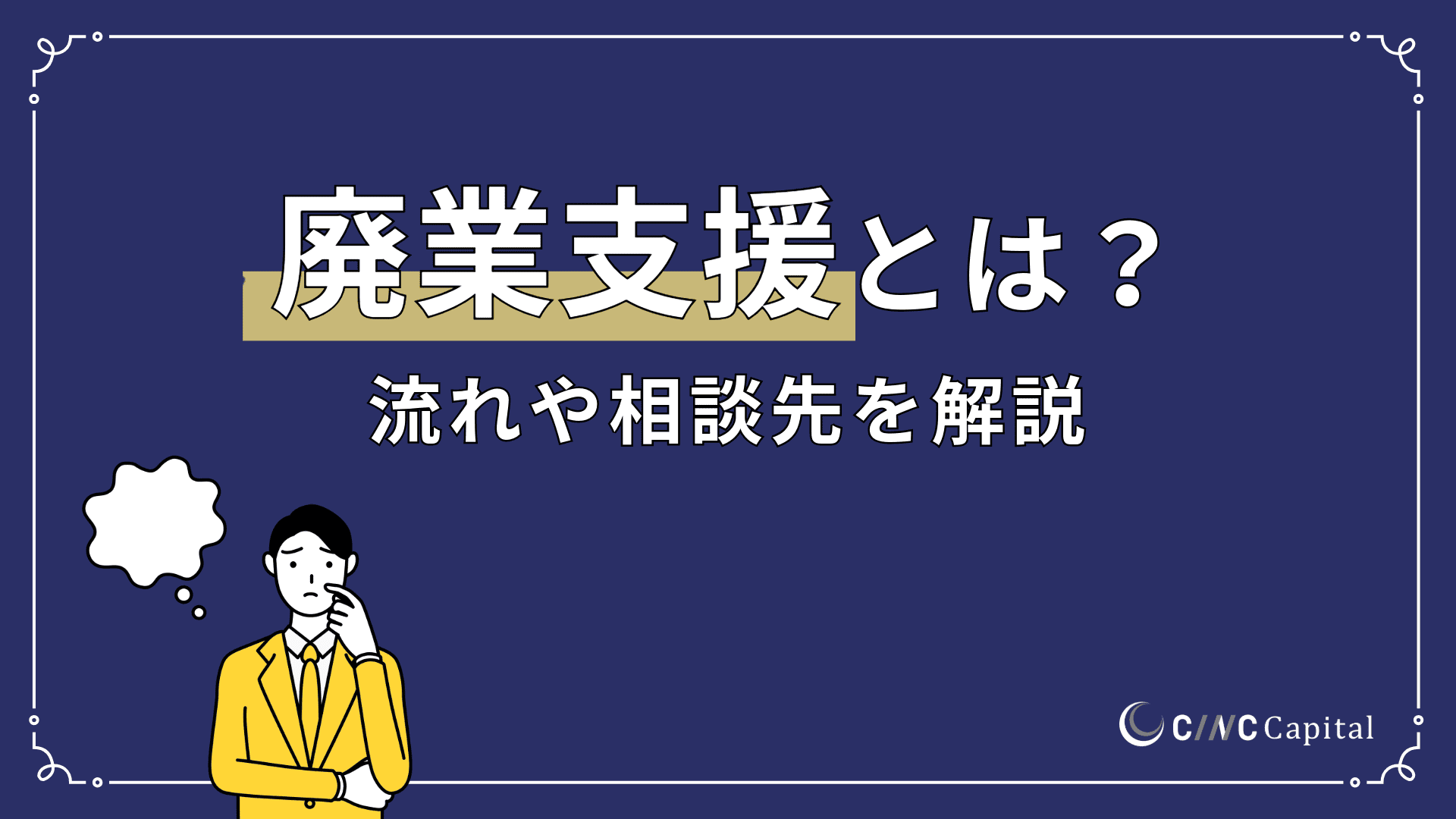CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
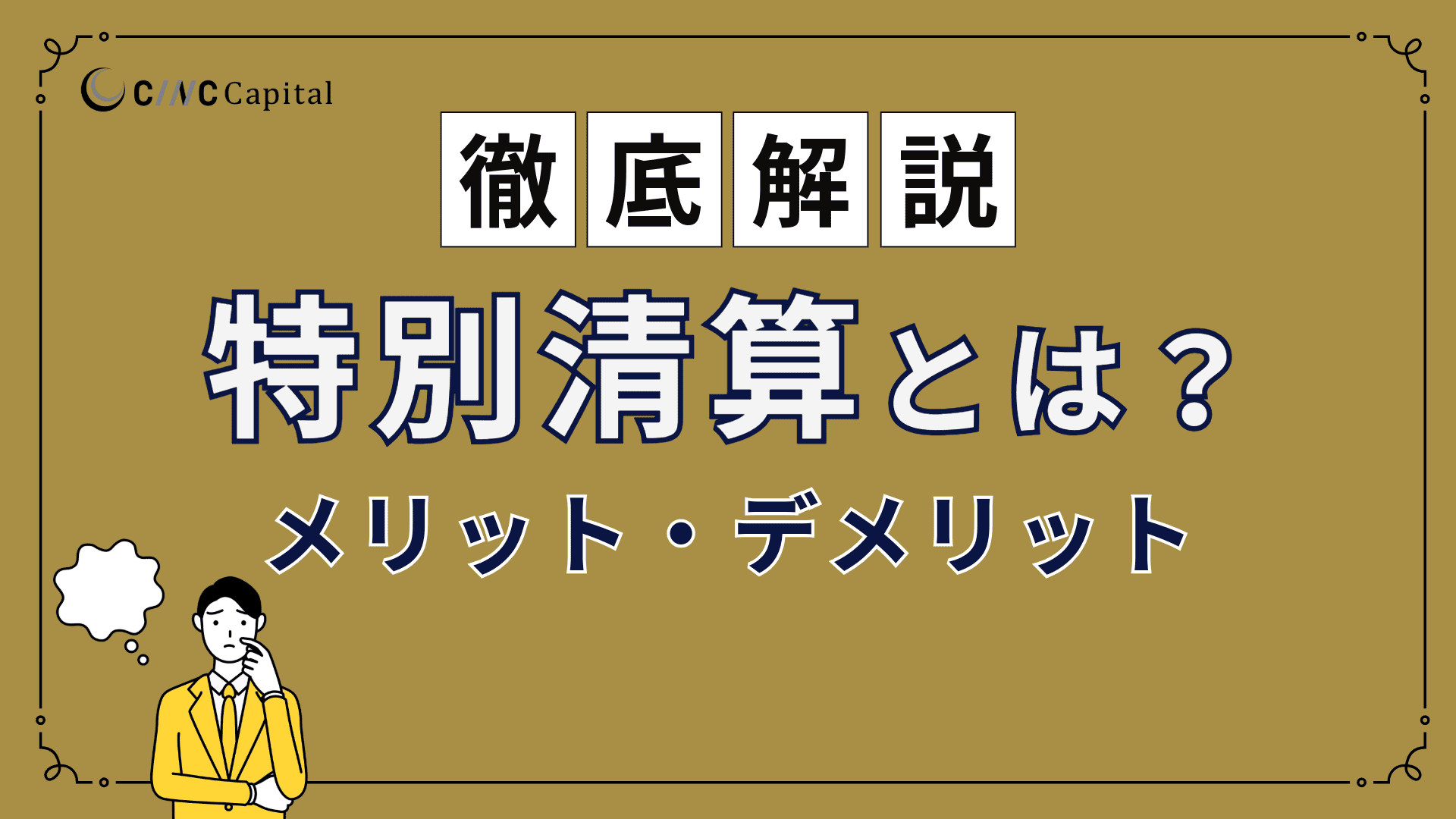
清算・廃業・解散 / 清算
- 最終更新日2025.06.26
特別清算とは?流れやメリット、デメリットをわかりやすく解説
会社を整理したいものの、通常の清算手続きでは対応できないケースもあります。そんなときに選択肢となるのが「特別清算」です。特別清算は、会社の経営を円満に終わらせるための法的手続きの一つで、主に債権者との関係整理を目的としています。
しかし、どのような流れで進むのか、メリット・デメリットには何があるのかを知らないと、かえってトラブルを招く可能性もあるでしょう。
この記事では、特別清算の基本から手続きの流れを解説します。会社整理を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
特別清算とは?
特別清算とは、株式会社において通常の清算手続きでは対応しきれない場合に適用される、会社法に定められた法的な清算手続きです。
具体的には、清算中の株式会社が債務超過の状態にある場合や、債権者との間で債務整理が必要な場合に、裁判所の監督のもとで債権者との協議を行い、会社を整理する手続きを指します。
まずは、通常の生産や破産との違いと、手続きの方法をご紹介します。
清算と特別清算の違い
通常清算は、会社の財産ですべての債務を返済できる「資産超過」の状態で行う清算方法で、裁判所が関与することなく、社内の手続きのみで完了できます。手続きは比較的シンプルで、すべての債務返済後に余剰財産があれば株主に分配されます。
一方、特別清算は、会社が債務超過であるか、その状態にあると認められた場合、または債権者との間で債務の整理が必要な場合に利用できる手続きであり、裁判所の監督下で進められる点が大きな違いです。債権者との協議や合意が必要となり、通常清算に比べて手続きが複雑になります。
|
区分 |
特別清算 |
通常清算 |
|
財務状況 |
債務超過 |
資産超過 |
|
裁判所の関与 |
あり |
なし |
|
債権者との合意 |
必要 |
不要 |
|
株主への分配 |
可能性あり |
残余財産を分配 |
特別清算と破産との違い
特別清算と破産はどちらも債務整理の手段ですが、性質や手続きの厳格さ、関係者の同意要否などに違いがあります。
特別清算では債権者との合意により一部債務免除を受けつつも事業価値の最大化を図れるのに対し、破産では事業や資産を強制的に処分して債権者に配当する形となるため、回収率が低くなる傾向があります。
特別清算では、株主総会で選任された清算人が中心となって手続きを進め、柔軟な交渉が可能です。対して破産は、裁判所が選任する破産管財人が主導し、すべての債権者を平等に扱う厳格な手続きが求められます。
また、特別清算には債権者・株主の同意が必要ですが、破産では同意は不要です。
|
区分 |
特別清算 |
破産 |
|
手続きを進める人 |
清算人(株主総会等で選任) |
破産管財人(裁判所が選任) |
|
手続きの性質 |
簡易・柔軟 |
厳格・平等処理が原則 |
|
利用できる会社 |
清算中の株式会社のみ |
ほぼすべての法人 |
|
同意の要否 |
株主・債権者の同意が必要 |
同意不要 |
|
裁判所の関与 |
あり(監督) |
あり(破産手続きの全面管理) |
|
費用 |
比較的少額(条件により5万円程度で済む場合がある) |
高額(予納金20万円以上が一般的) |
特別清算の手続きの方法
特別清算の進め方には、大きく分けて「協定型」と「個別和解型」の2種類があります。
協定型
協定型とは、債権者全体に共通する内容を盛り込んだ「協定案」を作成し、債権者集会にて同意を得て進める方法です。協定案には弁済率・弁済期限・債務免除の条件などが定められ、一定の要件を満たす同意が得られれば有効となります。
具体的には、債権者集会に出席した債権者の過半数の人数、かつ総債権額の3分の2以上の同意を得る必要があります。全員の合意は不要で、法定多数の同意を得れば協定は成立し、効力が発生します。協定型は債権者の数が多い場合でも対応可能で、柔軟な清算を目指す際に有効な手法といえます。
個別和解型
個別和解型では、債権者ごとに個別に和解を行い、それぞれに異なる条件で合意を得る方法です。裁判所の許可を得ることで効力が発生しますが、すべての債権者からの同意が必要となります。そのため債権者数が少なく、協力的な関係が築かれている場合に選ばれる傾向です。例えば、グループ企業内での子会社の整理など、関係者が限定的で調整しやすいケースでは、個別和解型がスムーズに進むことがあります。
特別清算における債権者との関係
特別清算を行う上では、債権者との関係性が非常に重要となります。特に、メインバンクや大口の取引先など、主要な債権者からの理解や同意を得られなければ、手続きをスムーズに進められないでしょう。信頼関係の構築に努めるとともに、事前調整を実施することが求められます。
特別清算を行うメリット
特別清算は、会社の整理を図る際に破産よりも柔軟性やスピード、社会的影響の面で優れた選択肢となる場合があります。ここでは、特別清算を行うことによって得られる主なメリットについて解説します。
破産よりも手続きが簡易で迅速に進められる
特別清算は、破産手続きと比べて裁判所を介した手続きが簡素で、短期間で終結することが多いのが特徴です。破産の場合には厳格な債権調査や配当の手続きが求められ、すべての債権者に対して平等な弁済が基本とされるため、時間も手間もかかります。
一方、特別清算では、一定数の債権者の同意と裁判所の認可が得られれば簡略化された方法で進められ、迅速な清算が可能です。特に小規模な債権者が多いケースや早期に資産処分を進めたい場合には大きな利点となります。
債権者との合意を前提とするため柔軟に対応できる
特別清算では、債権者との協議や合意をもとに清算手続きを進めるため、個別の事情に応じた柔軟な対応が可能です。例えば、債権者ごとに異なる条件で和解したり、特定の債権者に優先的に弁済したりといった調整も、裁判所の認可を得ることで実現できます。
この柔軟性は、破産手続きのように画一的な弁済方法しか選べない手続きとは大きく異なる点です。一部債権者との関係性を重視したいケースや、業務上の取引先との関係を一定程度維持したい場合などに有利な手段となり得ます。
会社の信用を維持しやすく破産よりも社会的影響が少ない
破産は「倒産」というイメージが強く、企業の信用を大きく損なうことにつながります。その影響は子会社単体にとどまらず、親会社や関連会社にまで及ぶこともあります。特に上場企業グループの子会社が破産手続きを選んだ場合には、グループ全体の信用が揺らぎかねません。
これに対し、特別清算はあくまで「会社の整理・清算」の一種であり、破産に比べて社会的な印象も穏やかです。事業譲渡後に不要となった部門を整理する場合などにおいても、信用面でのダメージを抑えながら手続きを進められます。そのため、企業全体のレピュテーションリスクを軽減する手段として有効です。
特別清算のデメリット
特別清算は破産と比べて柔軟で迅速な処理が可能な反面、いくつかの制約やデメリットもあります。ここでは、特別清算を選択する際に留意すべき主なデメリットについて解説します。
債権者の同意が必要であり調整が困難な場合がある
協定型の特別清算を成立させるためには、債権者の過半数かつ総債権額の3分の2以上の同意が必要です。個別和解型であれば債権者全員の同意が求められます。債権者の数が多い場合や利害関係が複雑な場合には、合意形成が難航するケースもあるでしょう。
例えば、少数の大口債権者が反対するだけで手続きが進まなくなる可能性もあります。結果的に破産へ移行せざるを得なくなることもあるため、事前の調整には相当な労力がかかるでしょう。
裁判所の関与が必要なため一定の手続き負担が発生する
特別清算は法的整理手続きであり、手続きの各段階で裁判所の認可や判断を受ける必要があります。そのため、私的整理と比べて形式的な書類作成や報告義務などの負担が増え、会社や弁護士の手間がかかります。
なかでも協定案の認可については、裁判所とのやり取りが不可欠です。清算人の選任も状況によっては裁判所の関与が求められるため、想定以上に時間やコストがかかることもある点に注意が必要です。
破産と比べて対応できるケースが限定される
特別清算は、あくまで株式会社が清算中に選択できる手続きであり、適用範囲が限られています。例えば、合同会社やNPO法人などはこの手続きを利用できず、破産など他の法的整理を検討する必要があります。
また、会社の資産に全く余力がない場合や、債権者との間で債権額の争いがあるケースでは、特別清算の利用が困難となるため、破産の選択肢が検討されます。このように、破産と比べて利用可能な状況が限られている点も、デメリットとして把握しておくべきといえるでしょう。
特別清算の流れ
特別清算は、会社を法的に清算するための手続きの一つであり、通常の清算と比べて複雑なプロセスが必要です。ここでは、実際に特別清算を進める際の主な流れを10のステップに分けてわかりやすく解説します。
Step1.専門家に相談・依頼
特別清算は裁判所を通じた手続きが必要であり、法的な判断や書類作成も多く含まれます。そのため、まずは弁護士などの専門家に相談し、会社の状況を説明したうえで、最適な清算方法を検討しましょう。手続き全般を弁護士に依頼することで、適切かつスムーズな進行が可能となります。
Step2.株主総会で会社の解散と清算人の選任を決議
特別清算を行うには、前提として会社を解散する必要があります。そのため、株主総会で解散決議を行い、同時に清算人を選任します。原則として取締役が清算人となりますが、実務上は弁護士などの第三者を清算人として選任することも可能です。
Step3.解散と清算人就任の登記
株主総会の決議を受けたら、2週間以内に「解散」および「清算人の就任」の登記申請を法務局に行います。登記が完了すると会社は営業活動を停止し、清算に専念する状態になります。
Step4.債権者への公告と催告
清算人は、官報に「一定期間内に債権を申し出るように」という公告を行い、債権者に対して申し出を促します。併せて、把握している債権者には個別に通知(催告)を行う義務があります。これを経て、会社が抱える債務の全体像を明確にすることが可能です。
Step5.財産・債務の調査と財産目録の作成・承認
清算人は、会社が保有する資産および債務の状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。これらは株主総会で承認を得る必要があり、承認後は裁判所への提出資料としても活用されます。
Step6.裁判所へ特別清算開始の申し立て
債務超過の疑いがある場合や、通常の清算では対応が難しい事情がある場合には、裁判所に対して特別清算の開始を申し立てます。申し立てには、登記事項証明書や財産目録、債権者一覧表など、多くの書類が必要となります。
Step7.裁判所による開始命令と公告、監督委員の選任
裁判所は申立内容を審査し、要件を満たしていると判断したら特別清算の開始を命じます。命令が出されると、その旨が官報で公告されます。
また、併せて裁判所から監督委員(主に弁護士)が選任され、手続きの監視・助言が行われます。
Step8.協定案(和解案)の作成と債権者集会の開催・決議
清算人は、債務弁済の計画を立てて協定案を作成します。協定案には返済金額や期限、免除額などの記載が必要です。協定案を債権者に送付したうえで、裁判所の許可を得て債権者集会を開催し、過半数出席かつ議決権総額の3分の2以上の同意をもって可決されます。
※債権者との個別和解によってすべての債務整理が完了する場合には、債権者集会の開催や協定案の認可が不要なこともあります。ただし、和解が成立しない場合は破産手続きに移行する可能性もあります。
Step9.裁判所へ協定認可の申し立てと認可後の履行
債権者集会で協定案が可決された場合、清算人は裁判所に対して協定の認可申し立てを行います。認可が下りると、協定内容に従って債権者への支払いが開始されるため、清算人は計画に基づいて速やかに債務の弁済を進めます。
Step10.清算終了後、特別清算終結の申し立てと登記
すべての弁済が完了すると、清算人は裁判所に「特別清算終結」の申し立てを行い、裁判所の許可を得て登記手続きを行います。この登記をもって会社の法人格は完全に消滅し、特別清算の手続きはすべて終了します。
まとめ|特別清算は複雑な手続き。専門家に相談を
特別清算は、通常の清算では対応が難しい場合に、裁判所の関与のもとで会社の債務整理を行う制度です。申し立てには一定の要件があり、債権者の利益保護や手続きの公正性が重視される点が特徴です。手続きには、会社の解散決議から始まり、多くのステップがあります。
複雑な手続きであるため、弁護士などの専門家に相談・依頼することが非常に重要です。適切な支援を受けながら進めることで、関係者間のトラブルを防ぎ、スムーズな清算を実現しやすくなります。
ただし、特別清算はあくまで会社が終わることを前提とした選択肢です。事業の一部に継続の可能性がある場合や、資産や顧客基盤に価値がある場合などは、清算ではなくM&Aによる事業承継も検討できます。M&Aによる事業承継のメリットとしては、以下が挙げられます。
- 債権者に対してより高い返済率を実現できる可能性がある
- 従業員の雇用を維持できる
- 取引先との関係を継続できる
- 事業価値を最大化できる
- 経営者にとっても経済的なメリットが大きい場合がある
特に、債務超過でも事業そのものに価値がある場合は、M&Aを優先的に検討することをおすすめします。弊社CINC Capitalでは、特別清算を検討される企業に対しても、M&Aの可能性を事前に見極めた上で、最適な選択ができるようにサポートを行っています。