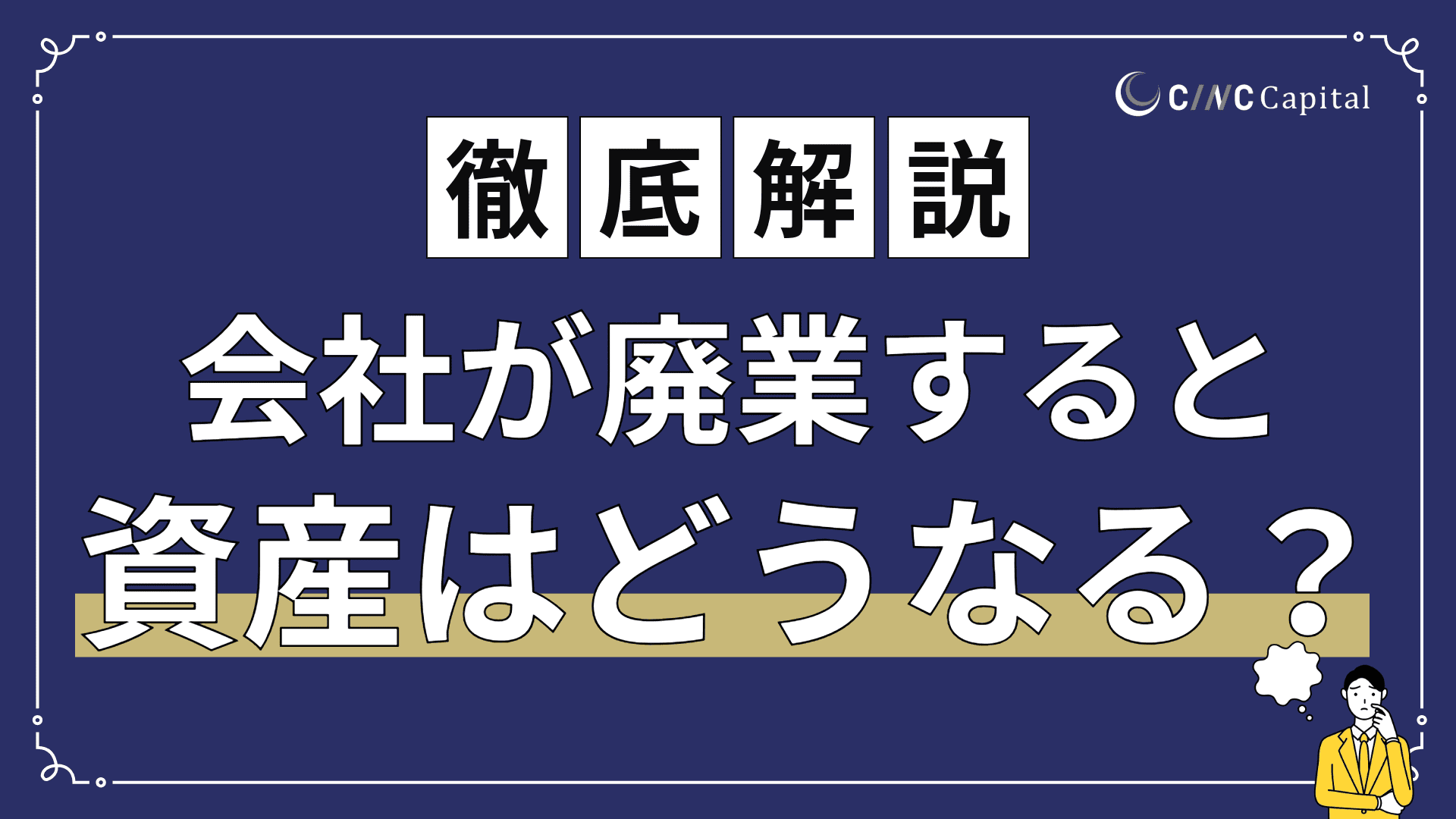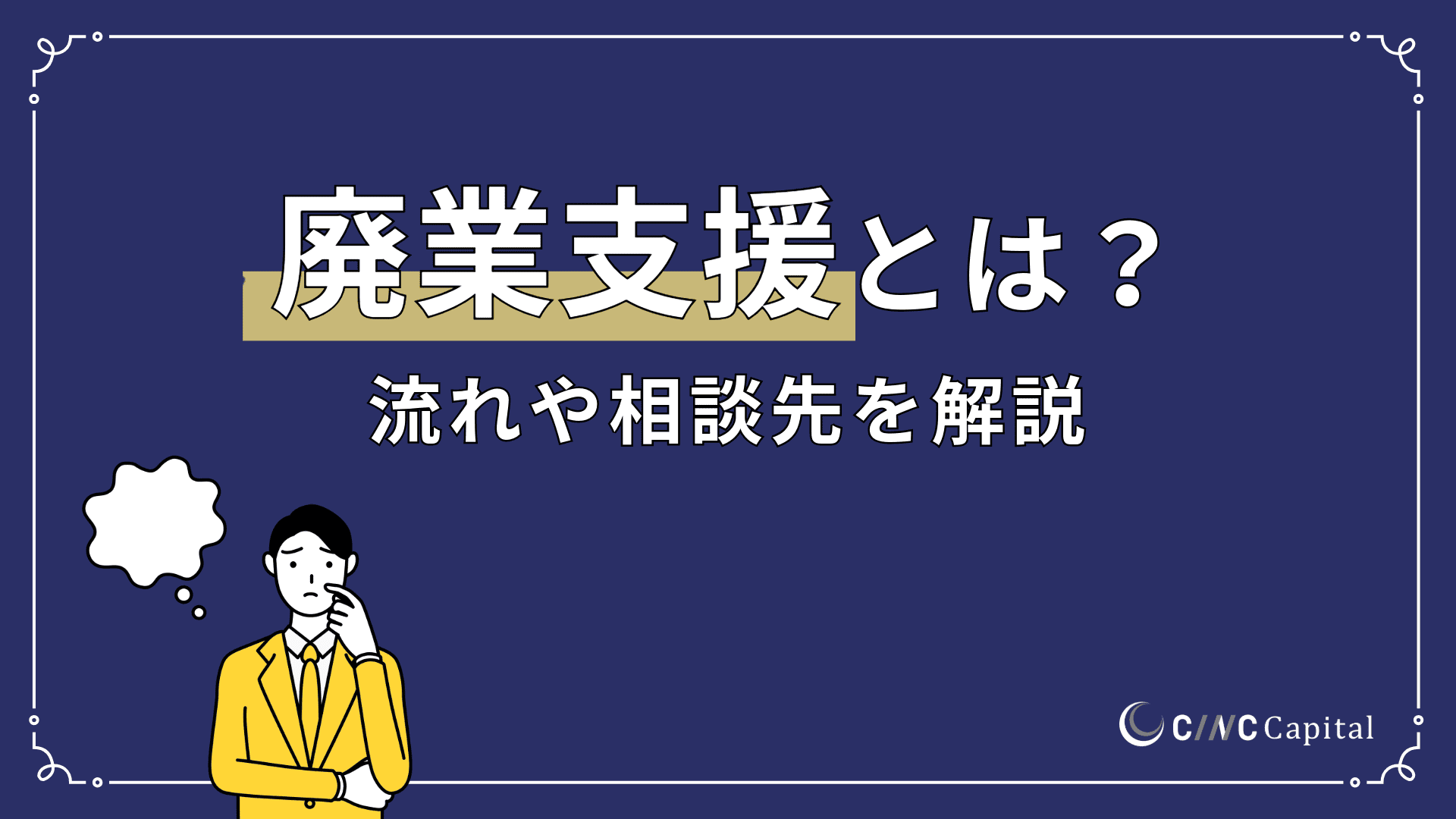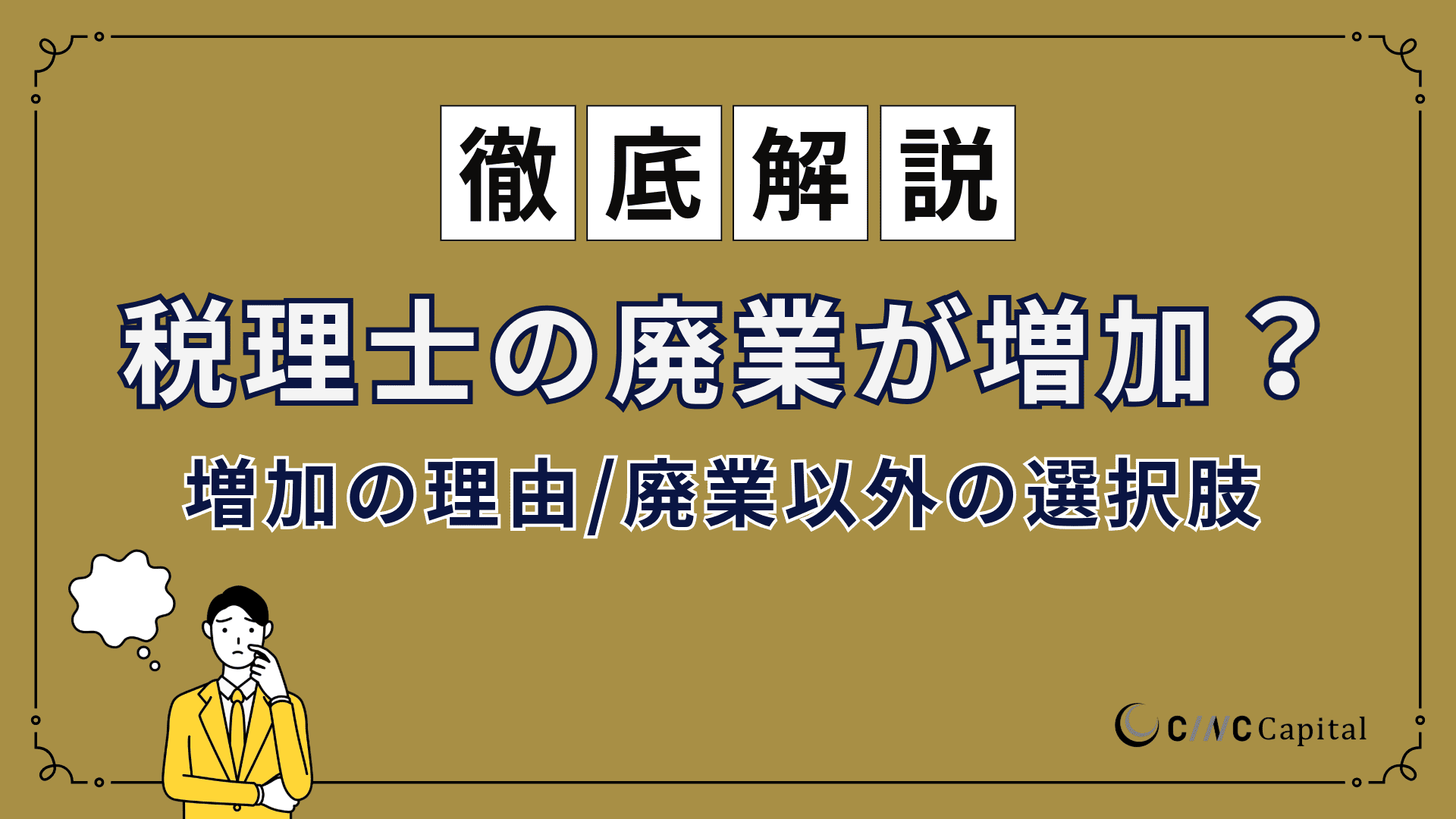CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
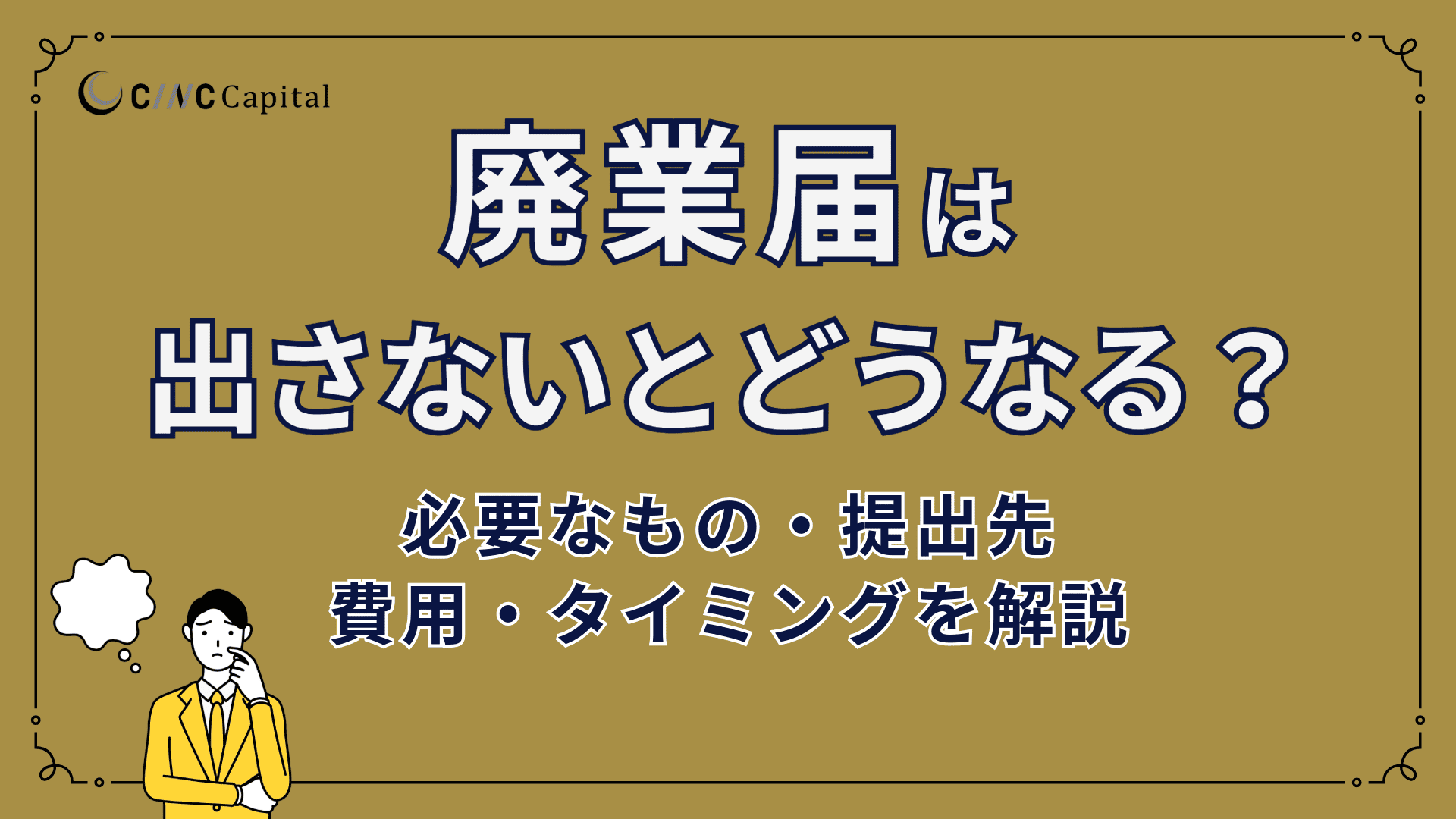
清算・廃業・解散 / 廃業
- 最終更新日2025.06.26
法人の廃業届は出さないとどうなる?必要なものや提出先、費用、タイミングを解説
法人が事業を終了させる場合は、さまざまな手続きを行う必要があります。その中でも特に意識しておきたいのが法人の廃業届です。申請時にミスや漏れがあると後々トラブルになる可能性もあります。
本記事では、法人の廃業届の基本的な内容や提出しなかった場合のリスク、提出に必要な書類や手続きのタイミングについて解説します。
目次
法人の廃業届とは?
まずは法人の廃業届がどのようなものか概要を押さえておきましょう。
法人が実質的に事業活動を止める際、税務署などに対して事業廃止の事実を伝えるために提出するのが一般的に“廃業届”と呼ばれる書類です。ただし、各種制度上は“解散”や“清算”といった法的手続きを進めることが必要であり、個人事業の廃業届とは手順や書類名が異なる場合もあります。また、法人の場合は履歴事項全部証明書の取得や解散公告など、会社法に基づいたステップがあるため、届出だけでは完結しない点も把握しておきましょう。
実務上は、税務署に提出する事業廃止届出書などを指して“法人の廃業届”と呼ぶケースが多いです。解散・清算を行い法人格を消滅させるまでの一連の流れにおいて、税務署や自治体に適切な届出を行うことが、法的に事業を終了したとみなされるための重要なポイントとなります。書類内容を誤ってしまうと、不要な延滞税や書類の再提出が発生するおそれがあるため、正確な理解と作成が求められます。
なお、法人の廃業届は“提出すれば終わり”というものではなく、あくまで行政サイドに対して法人が事業継続の意思を持たないことを明示するための書類です。にもかかわらず、この届出を怠ると不要な税務調査の対象になったり、法人住民税などの納付書が送られ続けるなどのリスクが生じます。こうしたトラブルを回避するためにも、必要な手続きをしっかり把握しておきましょう。
法人の廃業届は出さないとどうなる?
法人が廃業届を提出しなかった場合、どのようなトラブルが発生するのか、そのリスクを確認しておきましょう。
法人の廃業届を提出しないままにしておくと、税務署や自治体などからは法人が活動を継続しているとみなされる可能性があります。結果として、法人税や法人都道府県民税、法人市町村民税などの書類や納付書が引き続き送付されてしまうことがあります。支払い義務のない税金に対しても書類上の確認や連絡が必要となり、手続きの負担や時間のロスが発生するかもしれません。
さらに、廃業届を未提出のまま放置していると、税務当局からの税務調査やヒアリングを受けることもあります。たとえば、異常な確定申告状況や無申告が続いていると認識された場合に、活動実態の確認を求められるケースが考えられます。こうした調査を受ければ、廃業したにもかかわらず無申告とみなされたり、不必要な税負担の問題に巻き込まれるリスクも高まるでしょう。
また、法人住民税については事業を行っていない間でも最低限の均等割が課せられる場合があり、廃業の意思表示をしていないことで費用がかさむ可能性があります。そうしたコストを抑えるためにも、確実な届出を行っておくことが大切です。
廃業の流れと廃業届を提出するタイミング
法人を廃業する際には、法律上・税務上のさまざまな手続きが必要です。特に「廃業届をいつ提出すべきか」は迷いやすいポイントです。ここでは、法人廃業の一般的な流れと、廃業届の提出タイミングについて整理して解説します。
1. 解散の検討と準備
法人の解散理由、解散予定日、清算人候補などを検討します。株主(または社員)に解散の意向を伝え、必要な資料や今後の手続きの概要を共有します。また、解散決議に必要な定款の規定の確認も行います。
2. 株主総会(または社員総会)での解散決議
法人の解散について、株主総会(または社員総会)で特別決議を行います。議事録には、解散日や清算人に選任された者の氏名などを明記します。
3. 清算人の選任
同じ総会において清算人を選任します。一般的には代表取締役がそのまま代表清算人に就任しますが、必要に応じて別の人物を選ぶことも可能です。
4. 解散および清算人選任の登記
解散決議後、原則として2週間以内に法務局で「解散登記」と「清算人選任登記」を行います。この登記により、会社の代表者が清算人に変更されます。
5. 税務署・自治体への異動届出書の提出
解散登記後は速やかに、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ「解散届出書」や「事業廃止届出書」などの異動届を提出します。届出書には解散日を明記し、税務処理との整合性を保ちます。
6. 解散公告および債権者への催告
解散登記後、官報にて「解散公告」を掲載し、債権者に対して債権申出の催告を行います(通常、2か月以上の期間を設けます)。把握している債権者には個別に書面で通知する必要があります。
7. 財産目録および貸借対照表の作成・承認
清算人は会社の財産・負債の状況を調査し、「財産目録」と「貸借対照表」を作成します。これらの書類は株主総会(または社員総会)で提出し、承認を受けます。
8. 清算業務の実施
会社の資産を売却するなどして現金化を行い、債務を支払うための清算業務を進めます。未回収債権の回収や、契約の整理などもここに含まれます。
9. 残余財産の分配
すべての債務の弁済が完了した後、残った財産がある場合は、株主の出資比率に応じて分配を行います。分配方法については株主総会で定めることもあります。
10. 清算事務報告書の作成・承認
清算人は、これまでの清算事務の内容と結果を「清算事務報告書」としてまとめ、株主総会(または社員総会)に提出し、承認を得ます。
11. 清算結了の登記
清算事務報告書が承認された後、原則として2週間以内に法務局にて「清算結了登記」を行います。これにより法人格が完全に消滅し、登記簿が閉鎖されます。
12. 清算確定申告
清算結了登記の後、清算期間中の法人所得について、管轄の税務署へ「清算確定申告」を行います。これが法人として最後の税務手続きとなります。
なお、個々の法人の状況によって手続きが異なる場合があるため、必要に応じて専門家への相談を行いましょう。
法人の廃業届に関するよくある質問
法人の廃業届に関しては、書類関連や提出先、費用面など、さまざまな疑問が生じます。代表的な質問を挙げ、その答えをまとめました。
法人の廃業届で必要なもの・書類一覧
一般的には、税務署に提出する『事業廃止届出書』や『異動届出書』などが必要です。解散登記の後は、解散日や決算状況を示すために解散確定申告書を添付する場合もあります。清算結了の際にも清算確定申告書を提出し、最終的な税金を計算する流れです。
法務局では『解散登記申請書』や『清算人選任登記申請書』、清算終了時には『清算結了登記申請書』が必要となるのが通常です。また、自治体によっては法人県民税や法人市民税の廃業届に相当する書式があるため、都道府県・市町村ごとに確認することも大切です。
それぞれの書類は、法人名・所在地・解散日・清算人などの情報を正確に記入する必要があります。書類不備や誤記があると、後日修正手続きを要するだけでなく、場合によっては税金計算に影響が生じるかもしれません。
廃業届の提出先は?
税務署と法務局、そして都道府県や市区町村の担当部署に書類を提出するケースが一般的です。特に解散登記や清算結了登記は法務局が管轄しており、税務署への申告や届出は解散の初期から手続きを進めることが多いでしょう。
税務署では法人税や消費税に関する廃業届や、源泉所得税関連の届出を行う必要があります。自治体に対しては、法人住民税の納税義務を終了させるための手続きを行うことになるでしょう。
提出先が複数にわたるため、手続きを分割して行うと提出漏れが起こりがちです。どのタイミングで、どの役所・機関に書類を提出するものなのかを一覧化しておくと、スムーズに進められます。
廃業にかかる費用は?
費用としては、まず解散登記と清算結了登記の登録免許税が発生します。解散登記には3万円、清算結了登記には2千円、清算人の選任登記については9千円といった程度の費用がかかるのが一般的ですが、詳細は法人の種類や状況によって変わる場合があります。
税理士などの専門家に依頼する場合には、報酬という形で追加のコストが発生します。書類作成や手続きに関する業務を代行してもらうことで、ミスを削減できる利点がある一方、ある程度の予算を確保しておく必要があります。
なお、提出時期を誤ったり、提出忘れがあると、延滞税や不必要な税金を支払うリスクが生じます。正確な手続きと計画的なスケジュールを心がければ、費用を最小限に抑えることができるでしょう。
法人の廃業手続きは自分でできる?
法人自体が小規模であり、財務状況もシンプルであれば、一定の書類作成スキルを持っている人ならば自力で対応できることもあります。しかし、解散決議や清算結了の登記手続きは専門用語が多く、記入漏れ・記入ミスを起こしやすいのも事実です。後から修正が必要になると、時間や手間がかかるだけでなく、予定外の費用が発生する可能性もあるでしょう。
専門家(税理士・弁護士・司法書士など)に依頼するメリットとしては、手続き漏れや書類不備を最大限防げる点が挙げられます。特に、税務署に提出する確定申告関連の処理は正確性が求められ、専門家を通じて進めるほうが安心というケースが多いです。
反面、専門家への依頼は当然コストがかかります。依頼する際は、どこまで業務範囲に含めてもらえるのか、総戸締まりまで面倒を見てもらえるのかなど、事前にしっかり確認して契約を結ぶと安心です。
法人の廃業届を提出する際の注意点
法人の廃業届を提出する際に気を付けたいポイントを具体的に挙げていきます。
正しい提出タイミングと手順を理解し、確実に書類を届け出るだけでなく、提出後のフォローアップも重要です。提出後になってから書類不備が発覚し、再提出を求められるケースもあるため、注意点をしっかり押さえておくことが大切です。
誤記や記入漏れがないようにチェックを行う
廃業届や関連書類の中には、法人名・所在地・代表者名・解散日など多くの項目を記載する必要があります。抜け漏れや誤字があると受理されない、もしくは追加提出を求められるおそれがあります。余裕を持って書類を作成し、全て整合性が取れているかを複数回確認しましょう。
特に日付の記載ミスはトラブルになりやすい部分です。解散日や株主総会の決議日を正しく反映できているかどうか、いつの時点で税務署が申告書を受け付けるかなど、整合をしっかりとる必要があります。
税務署以外にも必要な提出先を確認する
法人住民税や事業税など、都道府県・市町村ごとの手続きが必要な場合があります。提出の遅れや誤った提出があると、住民税の納付書が届き続けたり、廃業後も税金が課税されると誤解されるケースがあります。
さらに、法人が社会保険の適用対象となっていた場合には、年金事務所や健康保険組合などへの脱退届や資格喪失手続きも必要です。各機関に順次連絡を入れるなど、チェックリストを作成した上で進めるとスムーズに対応できます。
提出後の控えや関連書類は必ず保管しておく
廃業届の控えや決議書、登記情報などは後から確認が必要になるケースがあります。たとえば、清算結了後に税務調査が入ったり、過去の税務申告との整合を求められる場合もあります。
提出前にコピーを取り、発行日や受領印などを確認しておくことで、手続きの証跡をしっかり残すことができます。必要に応じてファイリングしておくと、後日参照や追加手続きが発生した際にもスムーズに対応できるでしょう。
まとめ|適切なタイミングで廃業手続きを行いましょう
法人の廃業に際しては、適切なタイミングで手続きを行い、後々のトラブルを回避しましょう。
法人の廃業は解散決議から清算結了まで、手続きが複雑になりやすい特徴があります。税務署や法務局といった複数の機関で必要な書類が異なるため、事前に必要書類を把握して準備を進めることが大切です。
廃業届を出さないまま放置することで、余計な税金や書類のやり取りが続き、トラブルやコスト増につながるおそれがあります。適切なタイミングで確実に届出をし、提出後の控えも保管しておくことで、後から疑問点や問題が生じてもスムーズに対処できるでしょう。
自身で手続きする場合は、書類の書き方や提出期限を間違えないよう注意が必要です。専門家へ依頼することでスムーズに進められるケースも多いため、状況に応じた判断を行い、法人の廃業を円滑に完了させるようにしましょう。