CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
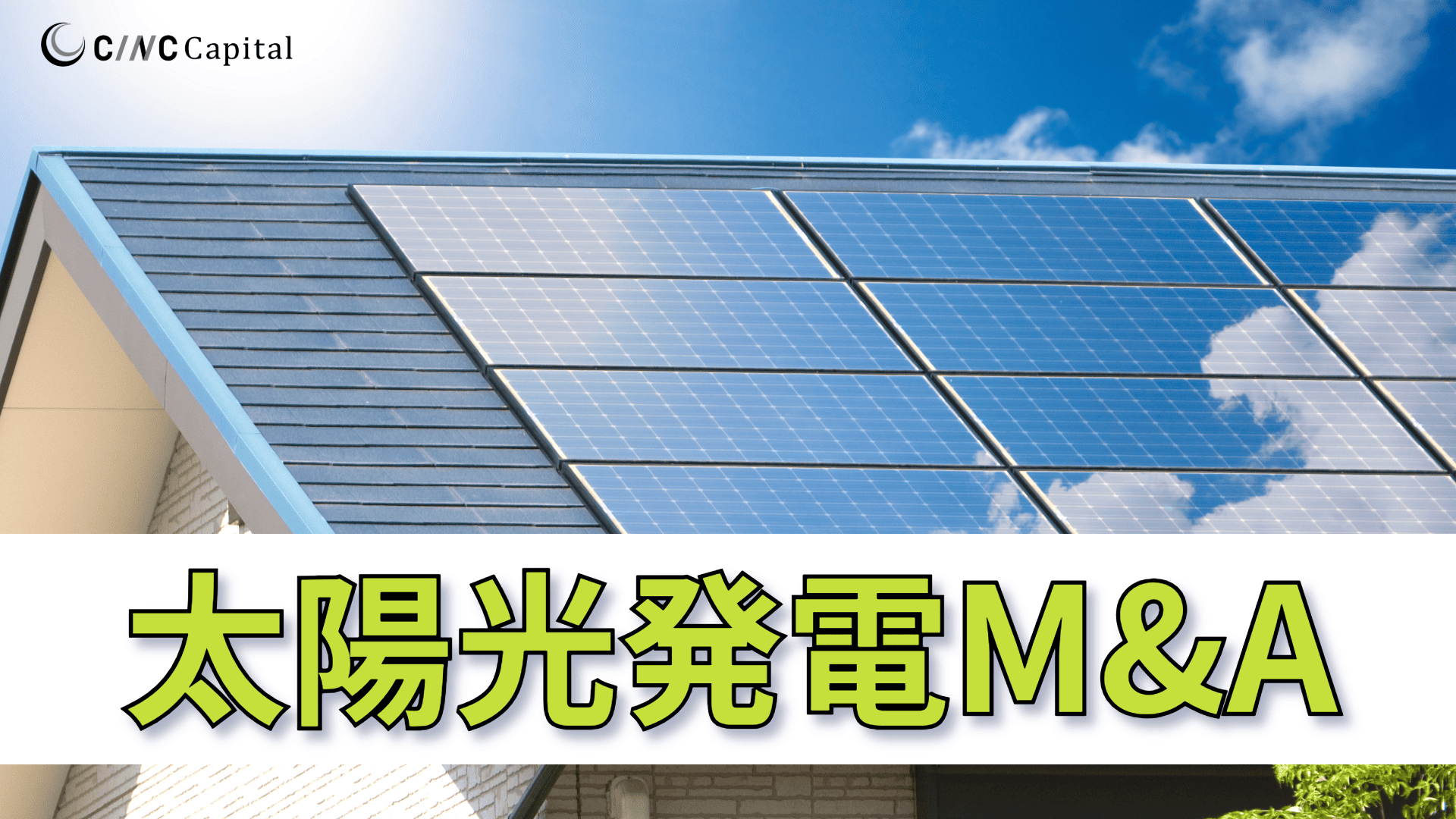
業種
- 最終更新日2025.06.26
太陽光発電のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
世界的に再生可能エネルギーへの注目が高まる中、太陽光発電市場は拡大を続けています。一方で、競争の激化や規制強化、老朽化設備の問題など、事業者は多くの課題に直面しています。
このような状況下で新たな成長戦略として活用されているのがM&Aです。
この記事では、太陽光発電業界のM&Aの最新動向や成功事例を取り上げ、メリットや具体的な成功のポイントについて解説します。
目次
太陽光発電業界の市場動向
数ある再生可能エネルギーの中でも、太陽光発電市場は着実に拡大を続けてきたものの、近年は成長のペースが鈍化しています。その背景の一つとして挙げられるのが、「FIT(固定価格買取制度)」価格の低下です。
FITは発電した電力を一定の価格で買い取る仕組みですが、年々価格が引き下げられており、新規参入を抑制する一因となっています。また、事業用太陽光のFIT認定量も減少傾向にあり、大規模プロジェクトにおいて採算性の確保が一層厳しくなっている状況です。
一方で、今後の太陽光発電市場では「PPA(電力購入契約)」の新規導入が進むと予想されています。PPAは発電事業者と電力事業者が締結する契約で、一定期間にわたり一定の価格条件で電力を売買するのが特徴です。
キャッシュフローを中長期的に固定できるため、発電事業者にとっては事業の安定化につながります。企業の再生可能エネルギーへのニーズの高まりにともない、導入が進むと期待されています。
太陽光発電業界が抱える課題
太陽光発電は再生可能エネルギーの中でも大きな注目を集める分野ですが、近年はさまざまな課題に直面しています。ここでは、太陽光発電業界が抱える課題について解説します。
住宅用の太陽光発電の導入が減少している
住宅用太陽光発電の導入件数は、かつてのピーク時と比較して大幅に減少しています。資源エネルギー庁が公表する資料「国内外の再生可能エネルギーの現状と今年度の調達価格等算定委員会の論点案」によると、2014年度における住宅用太陽光発電の導入量は207.4万kW(476,577件)でした。
一方、2021年度の導入量は85.9万kW(153,101件)に減少しています。その背景にあるのは、新設住宅着工数の減少です。新設住宅着工数は年々減少傾向にあり、太陽光発電の設置が多い新築住宅の減少が導入量の減少につながっています。
【出典】資源エネルギー庁「国内外の再生可能エネルギーの現状と今年度の調達価格等算定委員会の論点案」
システム導入費用のコスト低減
太陽光発電業界では、システム導入費用のコスト低減が進んでいます。なかでも住宅用太陽光発電の分野では、工事技術の向上や大量生産によるスケールメリットによって、導入コストが抑えられるようになりました。低コスト化によって、太陽光発電が一般市民にとってより身近な存在となったといえるでしょう。
一般社団法人太陽光発電協会では、太陽光発電がFITから自立した電源となるために、2025年までに業界トップランナー企業で7円/kWh(調達価格8.5円程度)、2030年までに業界平均で7円/kWh(調達価格8.5円程度)を目標としています。
【出典】一般社団法人太陽光発電協会「太陽光発電の現状と自立化・主力化に向けた課題」
太陽光発電業界のM&A最新動向(2025年)
太陽光発電業界では、再生可能エネルギーの需要拡大や経営環境の変化に伴い、M&Aの動きが加速しています。ここでは、太陽光発電業界のM&A動向をご紹介します。
再生可能エネルギー分野への新規参入のためM&Aが活発化している
再生可能エネルギー市場では、異業種企業が太陽光発電業界への新規参入を図る動きが活発化しています。特に、不動産開発業者やエネルギー関連事業者が太陽光発電関連企業を買収することで、事業を拡大する傾向が見られます。
また、再生可能エネルギーを活用した電力供給事業の展開や、太陽光発電技術を応用した新サービスの事業化を目的として、異業種企業と資本業務提携を結ぶケースも少なくありません。
倒産件数が過去最高になっている
太陽光発電業界では、経営難により倒産する企業の件数が高まっています。「株式会社東京商工リサーチ」が公表するデータによると、2020年度における太陽光関連事業者の負債は過去最大の461億3,500万円に達しました。また、同年度の太陽光関連事業者の倒産件数は54件となっています。
近年はFIT(固定価格買取制度)の売電価格低下や、資材コストの高騰などが経営を圧迫しており、事業継続が困難となる企業が多くなりました。主要事業への経営資源の集中を余儀なくされ、太陽光発電事業を売却する動きも見られます。
【出典】株式会社東京商工リサーチ「2020年度「太陽光関連事業者」の倒産状況」
太陽光発電業界がM&Aをするメリット
ここでは、太陽光発電業界でM&Aをするメリットを売り手企業の目線で解説します。
設備事故リスクの軽減
太陽光発電設備は、長期間にわたり安定して運用することが求められますが、老朽化や自然災害などによる設備事故のリスクを避けられません。M&Aを通じて設備を売却することで、これらのリスクを回避し、事業から撤退する際の負担を軽減できます。
また、管理コストが高騰している設備を手放し、経営資源をほかの事業に集中させることも可能です。
専門的知識が豊富な人材の雇用維持
売り手企業は、M&Aを通じて事業の移譲先を見つけることで、従業員の雇用継続や適切な技術承継を実現できる可能性があります。買い手候補の中には、太陽光発電事業に関する専門知識や経験を持つ事業者も多く、売却後も事業の適切な運営が期待されます。
安全管理体制の強化
太陽光発電設備の安全運用には、高度な管理体制が求められます。すでに安全管理のノウハウを保有している買い手企業との取引によって、売り手企業は設備の安全性を向上し、負担を軽減できる可能性があります。
国への定期報告の体系化
太陽光発電事業では、国や自治体への定期的な報告義務が課されますが、報告を行う体制構築が中小規模の事業者の負担となることがあります。売り手企業がM&Aを通じて事業を譲渡することで、報告業務を効率的に行う体制を持つ企業に一任できます。
売買のプラットフォームが充実している
近年、太陽光発電事業の売買を支援するプラットフォームが充実化しており、売り手企業にとって事業譲渡の相手先の選定が以前よりも容易になっています。適切な買い手企業を見つけやすくなり、迅速かつスムーズな取引が期待できます。
太陽光発電業界がM&Aをするデメリット
一方で、M&Aで十分な準備や慎重な検討が行われない場合、期待した成果を得られない可能性もあります。以下のデメリットに留意しておきましょう。
想定価格より低い金額で売却したことで利益が残らない
事業を売却する際、想定していた価格よりも低い金額で取引が成立してしまうケースがあります。設備の老朽化や市場環境の変化が影響し、売却価格が下落することも考えられます。こうした場合、譲渡後に十分な利益が残らないリスクを事前に考慮しておくことが大切です。
買い手側の戦略によって経済条件が変わりやすい
M&A後、買い手企業の経営戦略や方針の変更により、売却時に合意した経済条件が変動する可能性があります。例えば、買い手が設備の運用を見直すことで、雇用条件や地域貢献の約束が守られないリスクも存在します。
このような事態を避けるため、契約時に詳細な取り決めを行うことが重要です。
太陽光発電業界がM&Aを成功させるためのポイント
太陽光発電業界がM&Aを成功させるためのポイントを説明します。売り手企業は、太陽光発電設備や運用状況を見直し、買い手に安心感を与える準備を行いましょう。
設備や保守点検を健全な状態にしておく
買い手企業が最も重視するのは、発電設備が適切に稼働しているかどうかです。設備の老朽化や故障がある場合、M&A後に多額の修理費用がかかるリスクが懸念されるため、売却前に必要な修繕や保守点検を実施しておくことが大切です。
また、定期点検記録や保守履歴を整備し、設備の健全性を証明できるようにしておくと、買い手からの信頼を得やすくなります。
事業計画通りに発電を行う
売却対象の太陽光発電事業が事業計画通りに発電を行っているかは、重要な評価ポイントの一つです。特に、過去数年間の発電量が計画値に近い場合、買い手企業にとってリスクが低い事業として魅力的に映ります。一方で、計画値との差が大きい場合、原因を明確にして改善策を講じることが求められるでしょう。
売電実績がある
安定した売電実績は、買い手企業が安心して投資するために欠かせない指標の一つです。売電契約が固定価格買取制度(FIT)に基づいている場合、長期的に安定した収益が期待できるため、事業の価値が高まります。売電契約書や実績データを整備し、買い手に正確な情報を提供すると、交渉を有利に進めることが可能です。
気候による影響が事業計画と乖離していない
太陽光発電は天候に大きく左右される事業です。そのため、気候条件が事業計画に与える影響を適切に分析し、計画通りの発電が可能であることを示すと良いでしょう。例えば、年間の日射量データや天候による発電量の変動を具体的に提示し、事業計画との乖離が少ないことを説明できれば、買い手企業の安心感を高められる可能性があります。
太陽光発電業界のM&A事例
WWB株式会社による日本ライフサポート株式会社のM&A
2021年11月、A balance株式会社の連結子会社であるWWB株式会社は、日本ライフサポート株式会社から産業用太陽光発電事業を譲り受ける契約を締結しました。本取引により、WWBは日本ライフサポートが保有する連系済低圧発電所や仕掛品、人員リソースを承継します。
WWBは、太陽光発電システムの企画・製造・販売・施工をワンストップで提供する企業であり、A balanceグループの中核として再生可能エネルギー事業を推進しています。一方、日本ライフサポートは個人住宅向けの太陽光発電システム販売・施工を主力事業としており、今後はこの分野に注力する方針です。本譲受により、WWBは産業用太陽光発電事業の強化を図るとともに、バリューチェーンを拡充し、より高品質な再生可能エネルギーのソリューション提供を目指します。
譲受価額は1億6,900万円で、初年度売上は約17億円を見込んでいます。このM&Aは、再生可能エネルギー市場の成長に伴い、企業間の事業再編が進んでいることを示す好例です。産業用太陽光発電事業の拡大により、WWBの市場競争力が一層強化されることが期待されます。
【出典】 Abalance株式会社「当社連結子会社における事業譲受に関するお知らせ」
中部電力株式会社による株式会社ジェネックスはじめ3社のM&A
2023年11月、中部電力株式会社は、太陽光発電事業の強化を目的として、株式会社ジェネックス、株式会社ジェネックスパートナーズ、株式会社日本エネルギーネクスト(以下「ジェネックスグループ」)の全株式を取得し、完全子会社化することを決定しました。
ジェネックスグループは、中部地方を中心に約200カ所、合計発電出力約6.0万kWの太陽光発電所を保有し、開発・運営・保守管理を手掛けています。さらに、今後約8.2万kW規模の新規開発を予定しており、高いプロジェクト開発力を有する企業です。
今回の買収により、中部電力は再生可能エネルギー事業の拡大を加速し、太陽光発電の開発を強化する方針です。また、ジェネックスグループの発電所を小売電気事業者が提供するオフサイトPPA(電力購入契約)に活用し、企業の脱炭素ニーズにも対応する考えです。
電力大手が地域の発電事業者を取り込み、再生可能エネルギーの開発を加速する動きは、業界全体の脱炭素化と安定供給を支える重要な戦略の一環といえます。今後、中部電力がどのように再生可能エネルギー事業を拡大していくかが注目されます。
【出典】中部電力株式会社「株式会社ジェネックスはじめ3社の株式取得(完全子会社化)について」
株式会社フィットによる株式会社 Plus one percentのM&A
2022年3月、株式会社フィットの100%子会社である株式会社Plus one percentは、日本ファシリティ・ソリューション株式会社(東京電力エナジーパートナーの子会社)が提供するエネルギーサービス事業に対応した非FIT太陽光発電所の建設工事を受注しました。本プロジェクトは、株式会社エネテクが日本ファシリティ・ソリューションとEPC契約を締結し、Plus one percentが用地選定や建設工事を担当する形となります。
本発電所は、固定価格買取制度(FIT)を適用しない非FIT太陽光発電所であり、同社グループとして初の試みとなります。非FIT発電所は、政府の買取制度に依存せずに発電・販売を行う仕組みであり、今後の再生可能エネルギー事業における新たなモデルとして注目されています。今回の受注を通じて、Plus one percentは非FIT市場への参入を果たし、持続可能なクリーンエネルギーの供給に貢献することが期待されます。
再生可能エネルギー市場では、FIT依存から脱却した事業モデルの構築が求められており、今回の案件はその一例といえます。今後、非FIT型の発電事業が拡大することで、より柔軟な電力供給の仕組みが整備されることが期待されます。
【出典】株式会社フィット「株式会社 Plus one percent の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
まとめ|太陽光発電業界のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
太陽光発電業界では、再生可能エネルギー分野への関心の高まりや市場環境の変化を背景に、M&Aが活発化しています。売り手企業は現状の設備や運用状況を整理し、買い手にとって魅力的な条件を揃えることがM&A成功の鍵となります。取引を成功へ導くためには、事前の準備と市場動向の把握が欠かせません。M&A専門家の協力を得ながら、慎重に取り組みましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















