CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
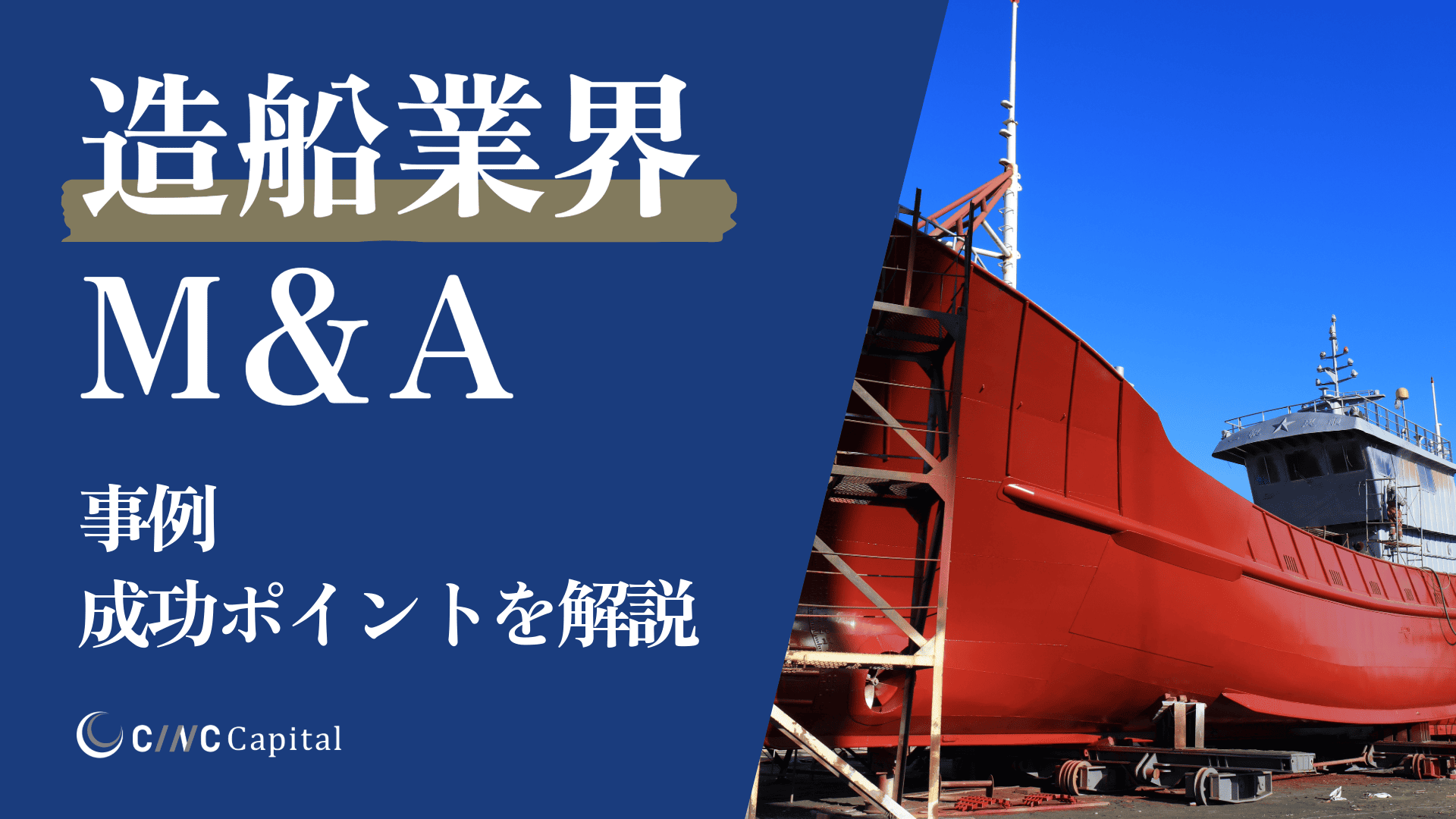
業種
- 最終更新日2025.07.02
造船のM&A動向は?事例や成功のポイントを解説【2025年】
造船業界の将来に不安を感じていませんか?
環境規制や人材不足、国際競争の激化により、事業継続に不安を感じる経営者も少なくありません。
本記事では、2025年時点の最新M&A動向や、実際のM&A事例などを詳しく紹介します。
目次
造船業界の市場動向
2024年の世界の造船市場は、過去17年間で最大の受注量を記録しました。新規受注契約は、補正総トン数(CGT)で6600万CGT、契約金額ベースでは2040億ドルに達しました。
これは、2007年の9400万CGT以来の高水準であり、市場の力強い回復を示しています。2024年における世界の新規受注船は2,412隻、合計6581万CGTに上り、CGTベースで前年比33.77%の大幅な増加となりました。
この活況を反映し、世界の造船所の総生産量も2024年には前年比で13%増加したのです。
造船業界が抱えている課題
日本の造船業界は、長年にわたり世界的な地位を築いてきましたが、近年ではさまざまな課題に直面しています。
以下では、特に深刻な4つの課題について解説します。
人材不足と技能継承の停滞
造船業界では、熟練技能者の高齢化と若年層の業界離れが進行し、技術の継承が危ぶまれています。
このような状況に対処するため、2019年に導入された特定技能制度を活用し、外国人労働者の受け入れが進められています。外国人労働者の受け入れが進むと、労働力不足の緩和や技術の継承、生産性の向上が期待されるでしょう。
国際競争力の低下
日本の造船業は、かつては高い技術力で世界をリードしていました。しかし、近年では中国や韓国の国家的支援を受けた造船業界に押され、価格競争力や納期面で劣後する場面が増えています。
これにより、国際競争力の低下が顕著となり、受注の減少や市場シェアの縮小が進んでいます。
環境規制と次世代船への対応遅れ
国際海事機関(IMO)の環境規制強化により、LNGやアンモニア燃料船などの次世代環境対応船の開発が急務となっています。
しかし、日本の造船業界では、研究開発費の制約や技術的な課題から、これらの新技術への対応が遅れている状況です。今後も新技術の対応が遅れると、国際的な競争力のさらなる低下が懸念されています。
鋼材高騰などによるコスト圧迫
2021年以降、鋼材価格の高騰が造船業界の採算を直撃しています。これに加え、資機材や加工外注費の上昇も続いており、造船所の経営を圧迫しています。これらのコスト増加は、船価の上昇を招き、受注競争力の低下につながってると言えるでしょう。
造船業界のM&A最新動向(2025年)
日本の造船業界では、国際競争力の強化や技術革新への対応を目的としたM&Aの事例が見られるようになっています。
本章では、主要な動向として3つの観点から解説していきます。
大手企業連合による競争力強化
日本の造船業界では、国際競争力の強化を目的として、大手企業間の連携が進んでいます。その代表例が、今治造船とジャパンマリンユナイテッド(JMU)による資本業務提携です。
両社は2021年1月に共同出資会社「日本シップヤード株式会社(NSY)」を設立し、LNG船を除く一般商船・海洋浮体構造物の設計・販売を手がけています。この提携により、国内シェア約5割、世界シェア約12%の巨大グループが誕生し、韓国や中国の造船大手に対抗する体制が整備されました。
NSYの設立は、設計・営業部門の統合によるスケールメリットの追求と、国際競争力の強化を目的としています。
中堅企業の統合で設計力とコスト力を両立
中堅造船企業においても、技術力とコスト競争力の両立を目指した統合が進行しています。
常石造船は、三井E&S造船の商船事業の一部を取得し、2021年10月に資本提携を実施しました。さらに、2022年10月には三井E&S造船の追加株式を取得し、持株比率を66%まで引き上げ、同社を連結子会社化しました。
この統合により、常石造船は三井E&Sの技術を取り入れ、自社のコスト力を活かして受注競争で優位に立っています。
防衛造船やエンジン分野でも提携進む
防衛造船や舶用エンジン分野においても、再編や提携が進展しています。
三井E&S造船は、艦艇・官公庁船事業を三菱重工業に譲渡し、2021年10月に移管が完了しました。この結果、三菱重工業は防衛造船の体制を強化し、日本の防衛産業を安定させる役割を担っています。
また、日立造船は舶用エンジン事業を分社化し、今治造船が35%出資する新会社を設立しました。この新会社は、舶用原動機の製造およびアフターサービス事業を手がけ、次世代燃料対応のエンジン開発や供給体制の強化を図っています。
造船業界でM&Aを成功させるためのポイント
日本の造船業界は、技術革新や国際競争の激化、環境規制の強化など、さまざまな課題に直面しています。これらの課題に対応し、持続的な成長を実現するためには、M&Aを活用した戦略的な取り組みが不可欠です。
本章では、M&Aを成功させるための主要なポイントについて詳しく説明します。
環境船や次世代技術への共同投資
脱炭素社会の実現に向けて、造船業界では環境対応船や次世代技術の開発が急務となっています。しかし、これらの開発には莫大な投資と高度な技術力が求められるため、単独企業での対応は困難です。そのため、M&Aを通じて資源を統合し、共同で研究開発を進めることが効果的です。
例えば、アンモニア燃料船の開発プロジェクトでは、複数の企業が連携し、エンジンの開発から船舶の建造、商業化までを一貫して進めています。このような共同投資により、技術革新のスピードを加速し、国際競争力を高めることが可能となります。
生産拠点や業務プロセスの統合を早期に進める
M&A後の統合プロセスにおいて、生産拠点や業務プロセスの統合を早期に進めることが、収益性の向上に直結します。具体的には、ドックや造船所の再配置、生産工程の標準化、資材調達の一元化などが挙げられます。
また、統合によって得られるスケールメリットを活かし、受注競争力を強化することも可能です。
人材流出を防ぐ組織統合マネジメント
造船業界では、熟練技能者の高齢化と若手人材の確保が大きな課題となっています。M&Aによる組織統合の際には、文化の違いや待遇格差が原因で人材の流出が起こる可能性があります。
そのためには、組織文化の統一や待遇の見直し、キャリアの見通しを示すことが重要です。さらに技能伝承の仕組みを構築し、若手人材の育成に注力することで、持続的な人材確保が可能となります。
営業・設計・生産のシナジーを具体化する
M&Aを成功させるには、営業・設計・生産の各部門でシナジーを具体化することが大切です。営業では顧客拡大、設計では技術共有による開発力向上、生産では工程や設備の効率化が期待されます。
これらを実現するには、初期段階から部門連携を強め、明確な目標と施策を定める必要があります。
再編の目的と将来ビジョンを明確化する
再編の目的と将来ビジョンを明確にし、関係者全体で共有することが不可欠です。目的が曖昧なままでは、統合プロセスが迷走し、期待される効果が得られない可能性があります。
市場シェアの拡大、技術力の強化、コスト競争力の向上など、具体的な目標を設定し、それに向けた戦略を策定することが重要になるでしょう。
造船業界のM&A事例
三井E&S造船による三井造船昭島研究所のM&A
常石造船株式会社のグループ会社である三井E&S造船株式会社は、船舶・海洋分野の流体力学研究を手がける株式会社三井造船昭島研究所の全株式を取得しました。
本件により、常石グループは昭島研究所の先進的な水槽・風洞施設を活用し、自動・自律運航技術やエコシップ、新燃料船の研究開発を強化。流体設計力の向上と競争力の強化が期待されています。
また、同研究所の潮流水槽などを活かし、洋上風力・波力発電や海洋構造物の解析技術にも応用を拡大し、造船以外の新事業分野への展開も視野に入れた戦略的なM&Aといえます。流体試験インフラの内製化は、開発スピードの向上と外部委託コストの削減にもつながると見られます。
【出典】常石造船株式会社「常石造船、グループである三井E&S造船株式会社による株式会社三井造船昭島研究所全株式取得のお知らせ」
日立造船による日立造船プラント技術サービスのM&A
日立造船株式会社は、グループ会社である日立造船プラント技術サービス株式会社を吸収合併し、2024年4月1日付で同社の権利義務をすべて継承しました。
本合併は、日立造船を存続会社、日立造船プラント技術サービスを消滅会社とする100%子会社吸収合併方式で、株式発行や資本金の増加は行われていません。
プラント事業における設計・施工・メンテナンスなどの業務一体化による経営資源の集約と効率化が狙いとみられ、事業運営のスピード向上やコスト削減に寄与する施策と位置付けられます。事業領域の明確化とグループ内機能の統合を通じて、今後の競争力強化が期待されます。
【出典】日立造船株式会社「合併公告」
セイカダイヤエンジンによる田中造船のM&A
西華産業株式会社の連結子会社であるセイカダイヤエンジン株式会社は、FRP船舶の製造・修理などを手がける株式会社田中造船の全株式を取得し、同社を孫会社化する株式譲渡契約を締結しました。2024年4月1日に株式取得が実行される予定です。
セイカダイヤエンジンは舶用エンジンの販売や保守サービスを主力としていますが、今回のM&Aにより、造船事業まで事業領域を拡大。これにより顧客の多様なニーズに応える建造計画の実現が可能となり、川上から川下まで一貫したサービス提供が可能になると見込まれます。
部品供給や保守対応の一体化によるシナジー効果が期待され、顧客満足度と事業競争力の向上に繋がる戦略的なM&Aといえます。
【出典】西華産業株式会社「当社連結子会社による株式会社田中造船の株式取得(孫会社化)に関するお知らせ」
まとめ|造船業界のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
日本の造船業界は、国際競争力の低下や人材不足、環境規制への対応など多くの課題を抱えています。
こうした背景のもと、企業同士の連携や再編が加速しており、M&Aは業界全体の構造を変える重要な手段となっています。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















