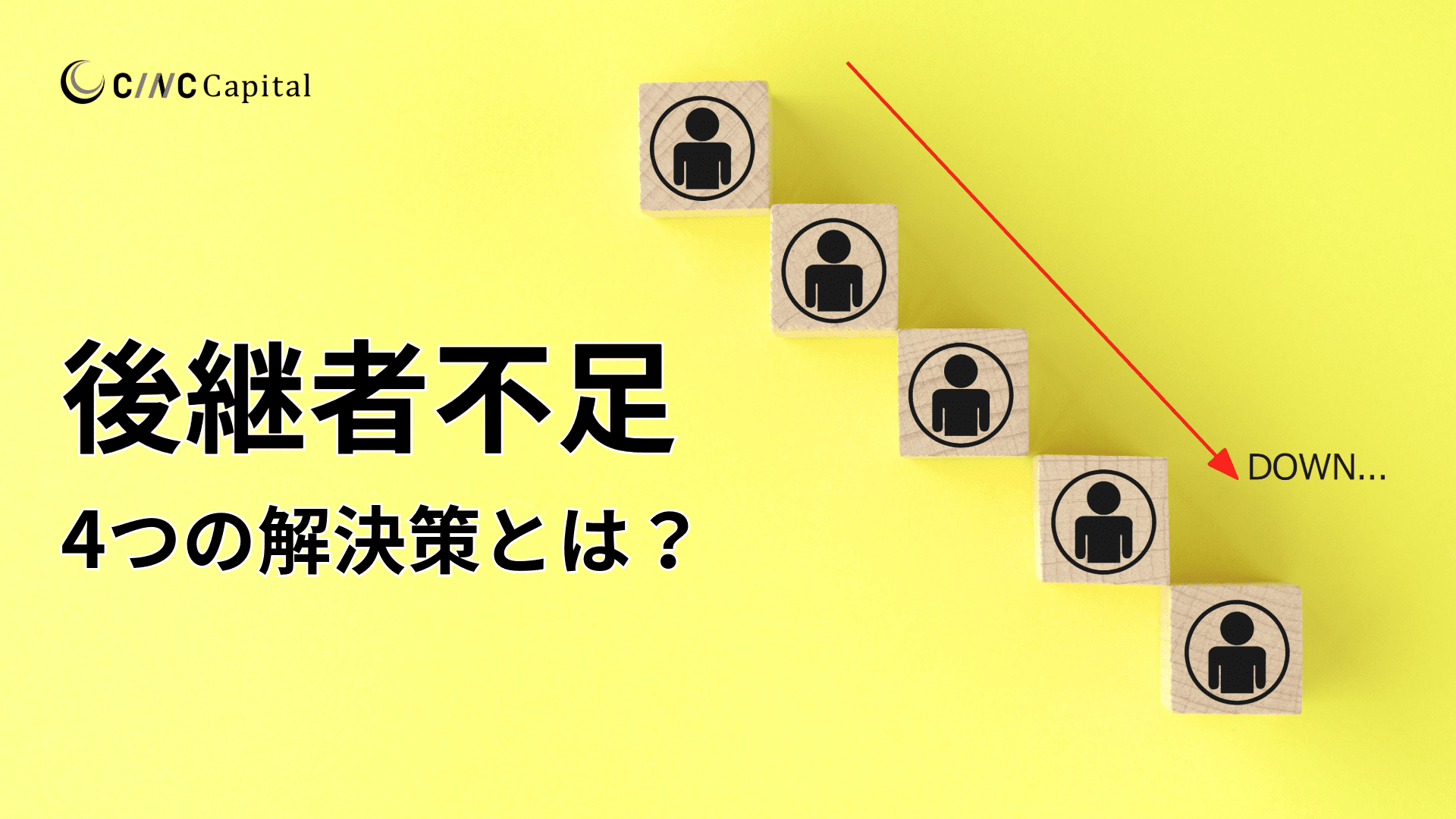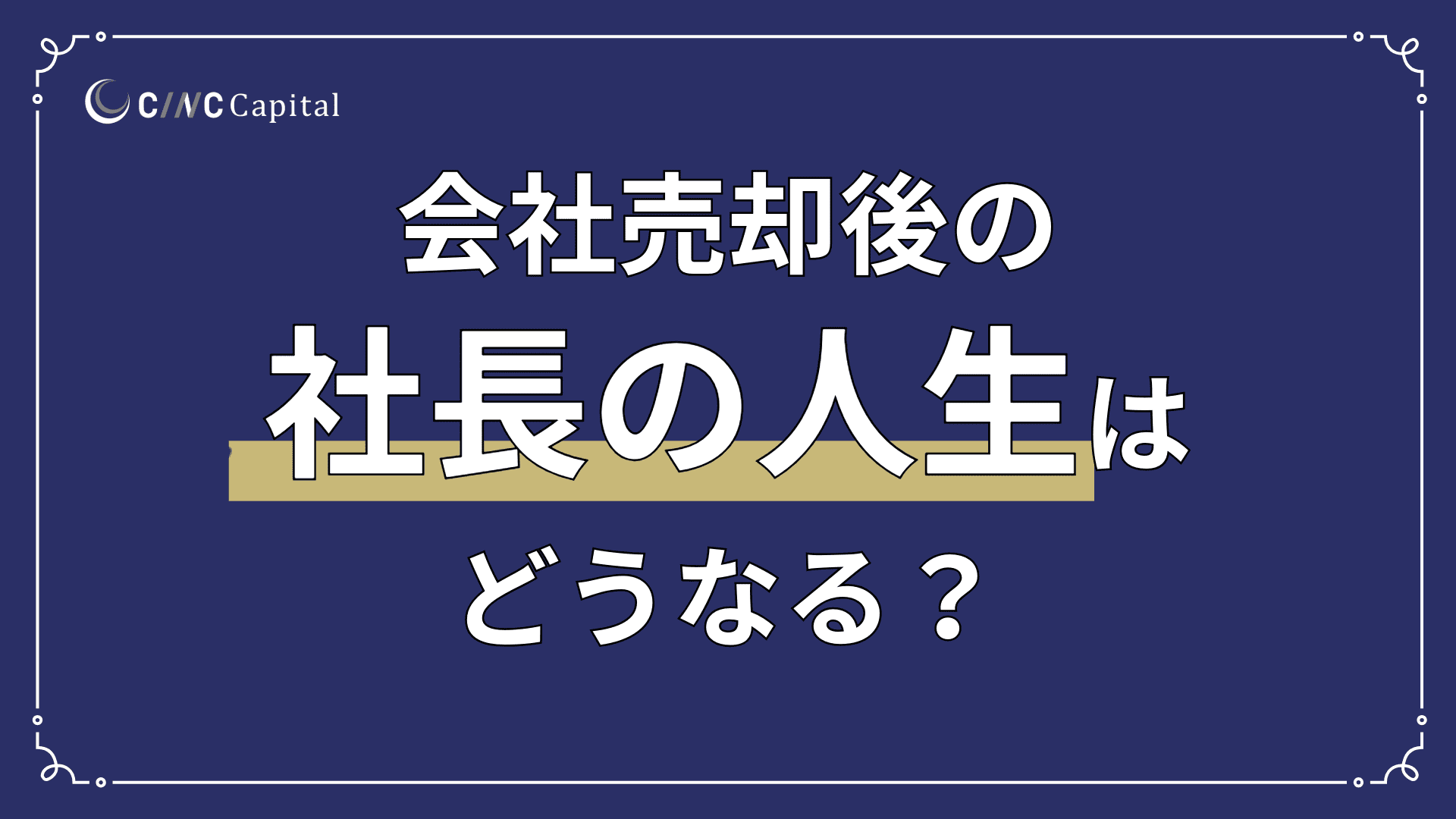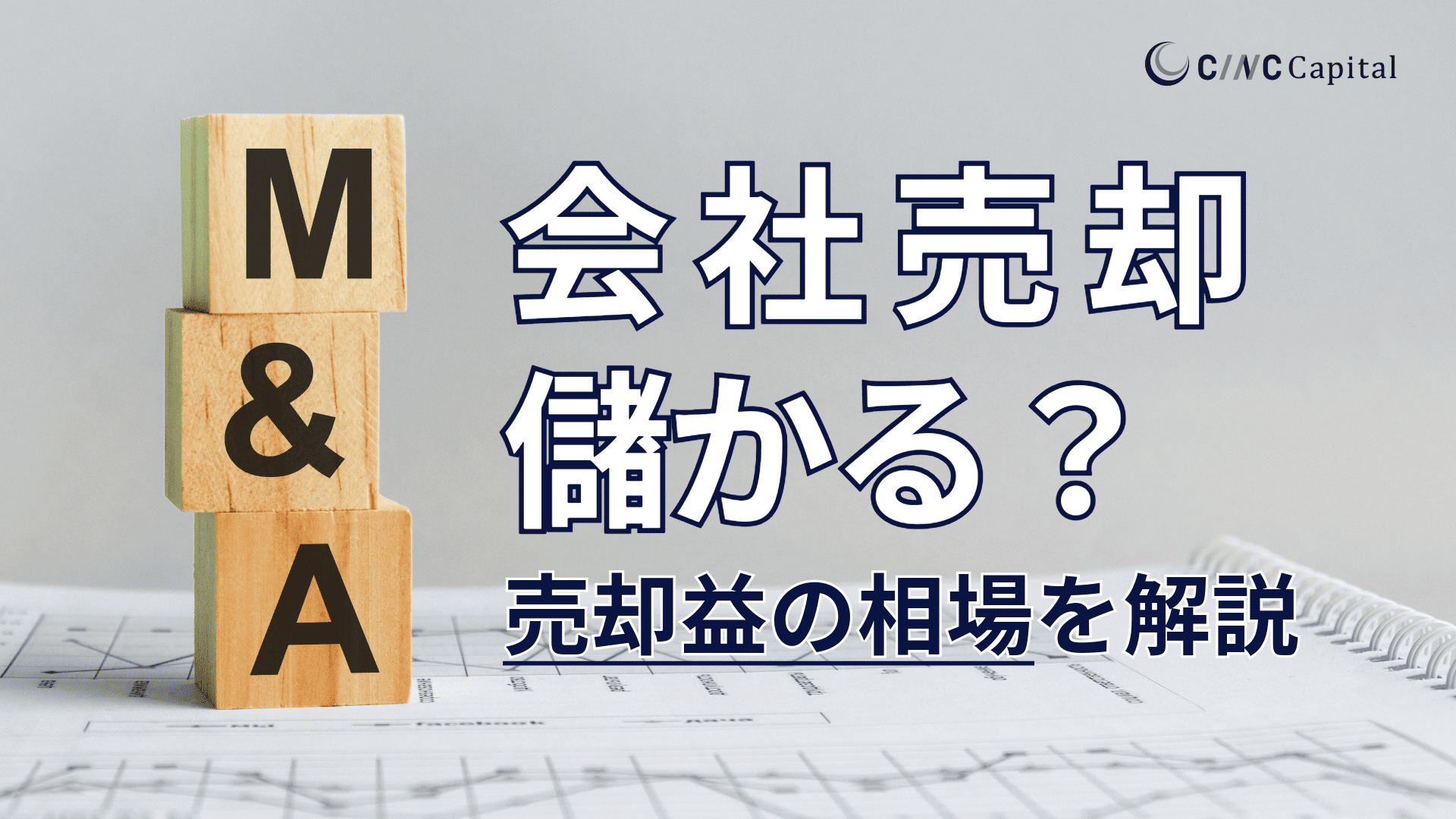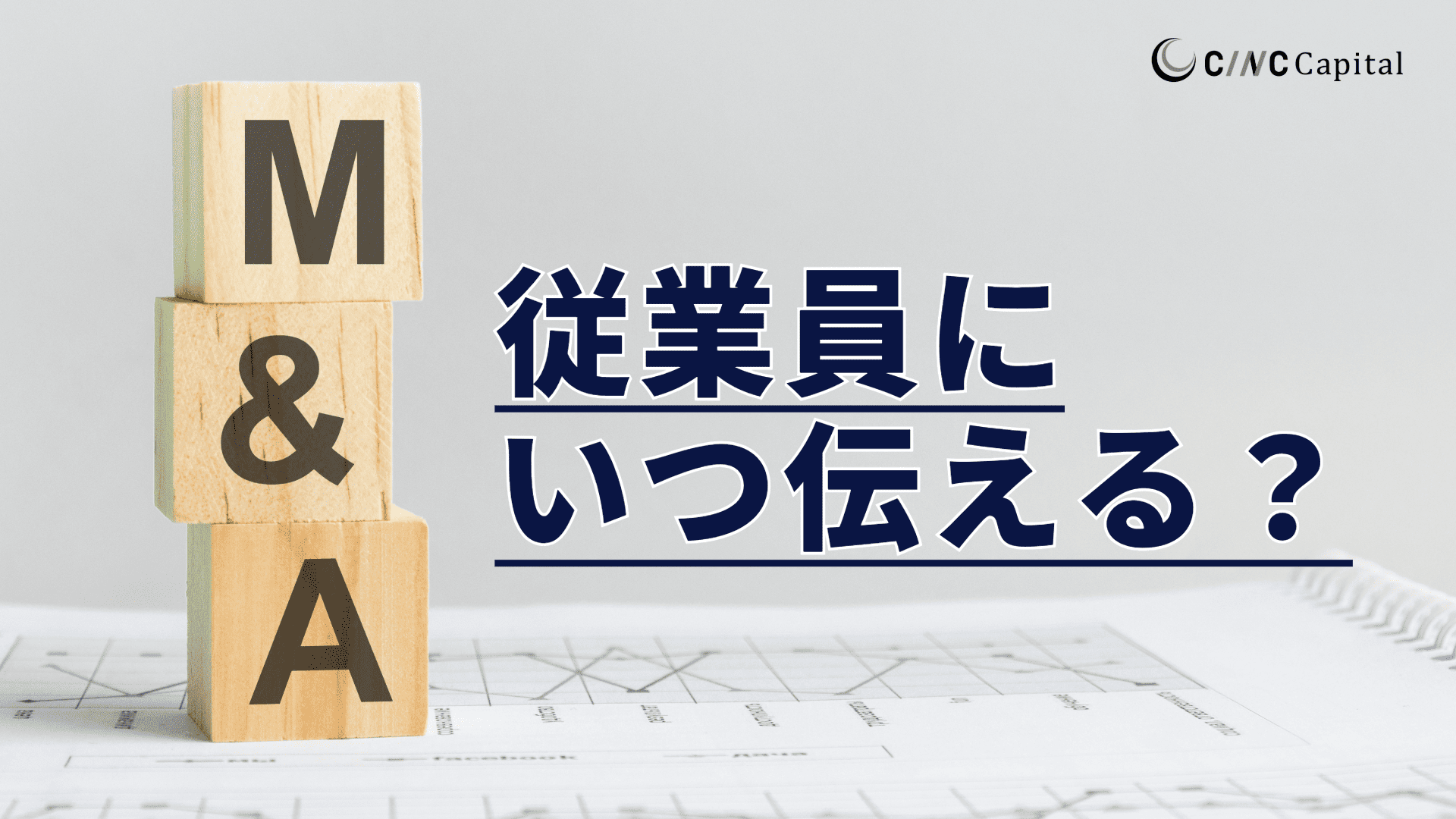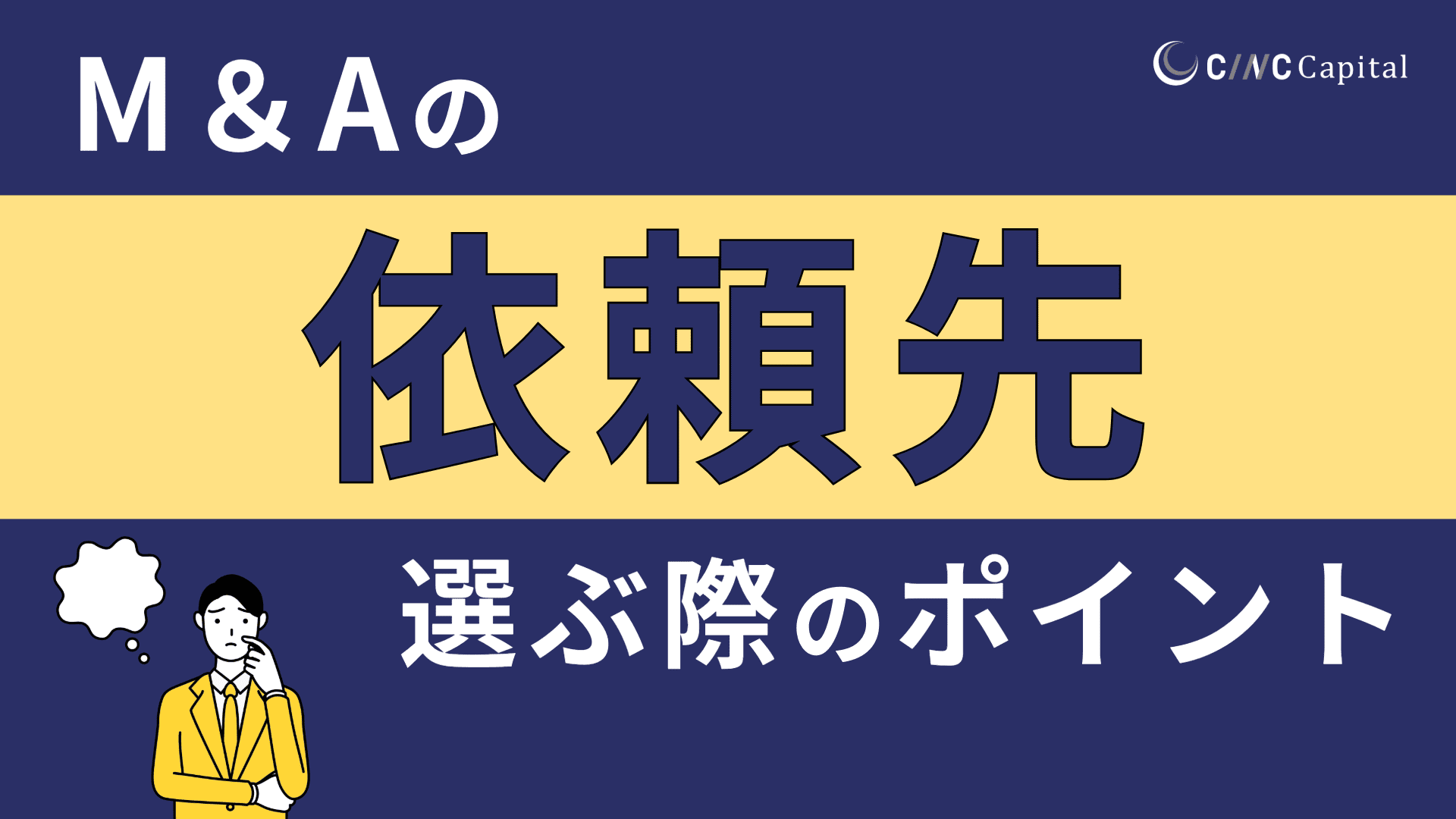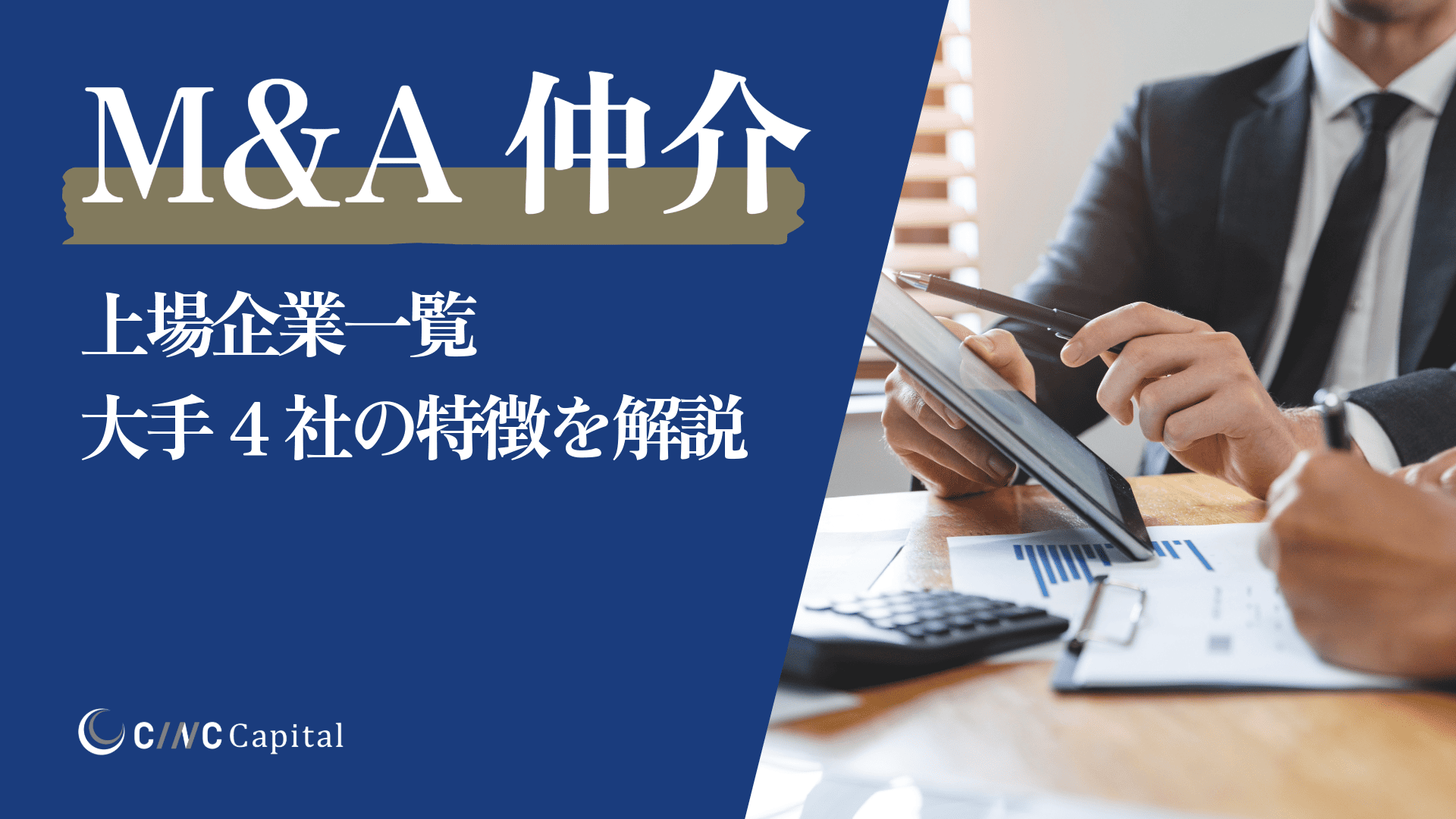CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。

業種
- 最終更新日2025.10.16
酒蔵業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
酒蔵業界では、日本酒の需要の変化や少子高齢化にともなう事業承継の課題が深刻化しています。そんな中で、M&Aは酒造りの伝統やブランドを守りつつ、事業の成長を図るための有効な手法だといえるでしょう。
本記事では、酒蔵業界の現状や具体的なM&Aの事例、成功のポイントを解説します。M&Aを成功に導くために、ぜひ参考にしてみてください。
目次
酒蔵業界の現状
国税庁が公表する資料「酒のしおり(令和6年6月)」によると、酒類等製造免許場は年々減少傾向にあることが分かります。
なかでも清酒の製造を行う製造免許場のデータを見ると、昭和45年の時点で3,533場が存在したのに対して、平成元年は2,438場、さらに令和4年は1,536場まで減少を続けています。
その一方で、近年は海外において日本酒が「SAKE」として人気が高まり、アジアや欧米で需要が拡大しています。
酒蔵業界は中小企業が大半を占めており、近年の国内市場の縮小を受けて、経営難による老舗酒蔵の廃業などの厳しい状況に直面しています。
資金不足や人材不足から競争環境へ対応できない酒蔵や、後継者不足や売上減少により事業承継が困難な酒蔵も少なくありません。
こうした現状を受けて、M&Aを活用して伝統的な酒造りを次世代へ引き継ぐ動きが注目されています。
酒蔵業界が抱える課題
酒蔵業界では、消費者ニーズの変化や経営環境の厳しさから、多くの酒蔵が事業の継続に困難を抱えています。ここでは、酒蔵業界特有の課題について解説します。
後継者が不足している
酒蔵業界では酒造りを支える次世代の人材が減少しており、特に家族経営の酒蔵では深刻な後継者問題が発生しています。適切な後継者が見つからないために事業承継が困難となり、廃業を選ばざるを得ない酒蔵も少なくありません。
設備が老朽化している
多くの酒蔵は長い歴史を持っているために、設備の老朽化が進んでいます。設備の更新には高額な投資が必要ですが、中小酒蔵では資金力の問題で対応が難しく、効率的な生産体制を構築できないことがあります。
ブランディングが難しい
酒蔵が伝統を守りながらブランド価値を高めることは、決して容易ではありません。問屋主体の販売体制の中で、消費者へ直接アプローチする機会には限りがあり、魅力ある商品を持ちながらブランディングに苦戦している酒蔵が多く存在します。
製造時期が限られている
日本酒の製造作業は冬の寒い時期に集中するため、年間を通じた安定的な生産が難しい状況です。製造時期が限られる商材であるために、キャッシュフローの問題や雇用の変動が発生し、経営に負担を与えています。
酒蔵業界のM&A最新動向(2025年)
近年の酒蔵業界では、事業承継問題や経営環境の変化を背景にM&Aが注目を集めています。ここでは、酒蔵業界における最新のM&A動向について解説します。
大企業や異業種企業によるM&Aは増えている
大手酒造メーカーや異業種の食品・飲料企業による酒蔵の買収が増加傾向にあります。その背景にあるのが、日本酒の海外市場への進出です。海外市場では、日本酒の品質や文化的価値が高く評価されています。こうした需要に注目した大手企業が、地域の酒蔵を買収し、ブランドの再構築や流通ネットワークの強化を図っているのです。
また、異業種企業による酒蔵の買収では、日本酒を活用した新規事業開発や観光産業との連携など、付加価値を生み出すことが主な目的です。例えば、観光業や飲食業の企業が酒蔵を買収し、酒蔵の見学ツアーや日本酒イベントを展開するなど、酒造りの伝統を観光資源として活用する動きが見られます。
中小企業によるM&Aも積極的に行われている
酒蔵業界では中小企業間のM&Aも活発化しています。こちらは、地域の中小規模の酒蔵が互いにノウハウや設備を共有し、経営基盤を強化することが主な狙いです。同じ地域内での統合や協業によって、生産効率の向上や固定費の削減が期待できます。
また、中小企業のM&Aは後継者不足や設備の老朽化といった課題の解決手段としても注目を集めています。後継者不在の酒蔵の事業をM&Aで引き継ぐことで、地域の伝統産業を守りつつ、相手先の酒蔵との相乗効果を生み出せるでしょう。地域全体の酒造業が活性化し、安定した供給が可能になることで、消費者にもメリットがもたらされます。
酒蔵がM&Aをするメリット
酒蔵業界において、M&Aは経営課題を解決するのに有効な手段です。ここでは、酒蔵がM&Aを行うことで得られるメリットを、売り手側の目線で解説します。
伝統や技術を継承できる
M&Aを通じて酒蔵の事業を引き継ぐことは、長年培われた伝統や独自の酒造り技術を次世代へ受け継ぐ大きなチャンスとなります。後継者不足で廃業の危機にある酒蔵でも、買い手側に事業を譲渡することで、酒造免許を引継ぎ、自社が持つ伝統や技術を継承できます。
従業員の雇用を継続できる
酒蔵が廃業すれば従業員が失業することになりますが、M&Aによって新たな経営体制の下で事業を継続すれば、雇用を守れる可能性があります。杜氏や職人たちが培った技術と経験を残せるのも、売り手側の酒蔵にとって大きなメリットです。
設備や技術が充実する可能性がある
M&Aで買い手側の事業と統合し、相手先の資金力や技術を活用することで、設備の刷新や新たな技術の導入が期待できます。場合によっては、より高品質な酒造りが可能となり、競争力の向上が図れるでしょう。
販売網や販路の拡大が期待できる
M&Aにより、買い手企業が持つ販売チャネルや取引先ネットワークを活用できるため、新たな市場や販路の開拓が期待できます。特に、事業規模の小さい酒蔵にとっては、顧客基盤の拡大や酒米確保ルートの維持が大きなメリットとなります。
ブランド価値の向上を目指せる
買い手企業とのシナジー効果により、ブランド力の向上が期待できます。例えば、知名度の高い企業による買収の場合、相手先の信用力やブランドイメージが自社の酒蔵に良い影響をもたらし、新たな顧客層を獲得できる可能性があります。
酒蔵がM&Aをするデメリット
酒蔵がM&Aを行うと、事業継続の可能性や経営の安定といったメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。ここでは、酒蔵がM&Aをするデメリットを売り手側の目線で解説します。
蔵を手放さなければいけなくなる
酒蔵のM&Aにおいて、売り手側にとって大きな覚悟が必要となるのは、愛着のある蔵を第三者の手に渡さなければならないことです。取引の成立後は、酒蔵の物的・文化的な資産が他者に引き継がれ、以前の経営者の意思や方針が反映されなくなる可能性もあります。家族で代々引き継がれてきた酒蔵の場合、蔵を手放すことへの心理的な負担は大きくなるでしょう。
ブランドイメージが変わる可能性がある
多くの酒蔵のブランドは、土地の歴史や蔵独自の製法などから築き上げられたものです。しかし、M&Aにより経営者が変わると、以降のブランド戦略が大きく変更される可能性があります。事業規模の拡大や商品展開の多様化を目指す過程で、従来のブランドイメージが損なわれ、顧客の信頼を失うリスクや銘柄・商標の変更リスクも考えられます。
伝統や文化が失われるリスクがある
日本各地の酒蔵には、地域の伝統や文化が息づいています。M&Aでは、こうした伝統的な価値観が新たな経営方針や業務効率化の影響で失われるリスクがあります。特に、買い手側が酒造業の特性を十分に理解していない場合は、ベテランの杜氏や職人が退職したり、地域社会とのつながりが希薄になったりする可能性もあるでしょう。
酒蔵がM&Aを成功させるためのポイント
ここでは、酒蔵業界で伝統やブランドの価値を守りながらM&Aを成功させるためのポイントを解説します。慎重な計画と適切な準備に取り組みましょう。
売却先の選定を慎重に行う
売り手側の酒蔵の伝統やブランドは、長い年月をかけて築かれた貴重なものです。M&Aでは、こうした価値を尊重してもらえる買い手を選ぶことが成功の鍵となります。日本酒の市場や文化を深く理解し、酒蔵が培ってきたストーリーを継承できる相手先を見極めることが重要です。買収後もブランドイメージが守られるよう、売却先の選定は慎重に行いましょう。
現状必要な許認可が有効かどうかを確認する
酒造業には「酒類製造免許」や「酒類販売免許」など、法的に必要な許認可が存在します。M&Aでは、現状の許認可が有効であるか、名義変更や継続手続きが必要であるか、酒造組合との調整など、条件に応じた対応が求められます。許認可の更新漏れや規制違反があると、事業の継続に大きな影響を及ぼすため、専門家のサポートを受けながら入念にチェックすることが大切です。
醸造技術の継承を確実に行えるように準備をする
日本酒の品質は、醸造技術や杜氏の知識などに大きく依存しています。M&Aによってこれらの技術が失われないよう、従業員や職人との信頼関係を構築し、技術継承の仕組みを整えることが必要です。従業員への研修、技術のドキュメンテーション化などに取り組み、醸造技術のスムーズな引き継ぎへ向けて準備しましょう。
専門家にアドバイスをもらう
ここまでご紹介した通り、酒蔵のM&Aは一般的な事業のM&Aに加えて、許認可や技術などの複雑な要素が関係します。酒蔵業界のデューデリジェンスでは、「酒造免許の承継」「杜氏・蔵人の雇用継続性」「酒米の仕入れ契約の承継」「製造設備・貯蔵在庫の評価」などが重要となります。
法務や財務のほか、酒蔵業界特有の専門知識が求められるため、信頼できるM&Aアドバイザーに相談すると良いでしょう。経験豊富な専門家のアドバイスを受けることで、酒蔵M&Aのリスクを最小限に抑えて、成功へと導くことができます。
酒蔵業界のM&A事例
株式会社久原本家グループによる株式会社伊豆本店のM&A
2024年4月26日、久原本家グループ(福岡県久山町)は、創業300年以上の歴史を持つ老舗酒蔵・株式会社伊豆本店(福岡県宗像市)の株式を取得し、子会社化したと発表しました。
伊豆本店は1717年に創業し、福岡・宗像の地で酒造りを続けてきた蔵元です。代表銘柄「亀の尾」は、一度は絶滅した幻の酒米「亀の尾」を11代目が復活させたことでも知られ、現在は約20種類の日本酒を展開しています。
本件の背景には、久原本家グループの社主・河邉哲司氏と伊豆本店が親戚関係にあり、以前から経営相談を受けていた経緯があります。両社はこれまでにも、久原本家のブランド「博多 椒房庵」での日本酒製造委託など、業務上のつながりを築いてきました。今回の買収により、伊豆本店の伝統ある酒造技術の継承と、両社の強みを活かした事業拡大が期待されています。
久原本家は、醤油や味噌などの発酵食品を手がけており、日本酒事業との親和性が高いと考えられます。今後は、レシピ開発を活かした日本酒と和食のペアリング提案や、宗像地域の魅力を活かした新たなブランド展開を進める計画です。老舗酒蔵の伝統を守りつつ、新たな価値を創造する取り組みとして注目されます。
【出典】株式会社久原本家グループ「株式会社 伊豆本店、子会社化のお知らせ」
宝ホールディングス株式会社によるカナダの清酒蔵Ontario LimitedのM&A
2023年5月8日、宝酒造インターナショナル株式会社は、カナダ・オンタリオ州で清酒製造・販売を手がける**Ontario Spring Water Sake Company(オンタリオ社)**の発行済株式の80%を取得し、連結子会社化したと発表しました。
オンタリオ社は2010年に設立され、カナダ東部で唯一の酒蔵として、日本食市場向けの純米酒「泉(Izumi)」や、清酒をベースにしたカクテル「Sakeカクテル」を製造・販売しています。今回の買収により、宝酒造グループはカナダ市場での和酒製造・販売拠点を確立し、北米市場でのプレゼンスを強化する狙いがあります。
近年、世界的に日本食の人気が高まる中、日本酒市場も成長を続けています。特に海外では、従来の清酒の枠を超えた「イノベーティブなSAKE」の開発が進んでおり、宝酒造グループも現地ニーズに対応した新商品の開発を強化する方針です。
本件の買収は、宝酒造グループが掲げる「グローバル和酒・日本食材No.1企業」を目指す戦略の一環であり、今後の北米市場での展開に注目が集まります。
【出典】宝ホールディングス株式会社「カナダの清酒蔵の株式取得に関するお知らせ」
株式会社ベルーナによる谷櫻酒造有限会社のM&A
2023年6月30日、株式会社ベルーナ(埼玉県上尾市)は、創業170年以上の歴史を持つ谷櫻酒造有限会社(山梨県北杜市)の全株式を取得し、子会社化したと発表しました。
谷櫻酒造は、1848年の創業以来、八ヶ岳南麓の清らかな湧水を活かした酒造りを続けてきた老舗酒蔵です。伝統的な生酛造りによる豊かな風味が特徴で、ロンドンの国際アルコール品評会「IWSC」で数々の受賞歴を誇る銘柄を展開しています。
ベルーナは、日本酒事業の成長を見据え、自社ブランドでの日本酒開発やグルメ事業とのシナジー強化を目的に本件の買収を決定しました。酒蔵業界では、歴史ある酒蔵の事業承継が課題となる中、ベルーナの経営資源を活用することで、谷櫻酒造のブランド価値向上と事業拡大が期待されます。
本件は、異業種企業による老舗酒蔵のM&A事例として注目され、日本酒市場のさらなる活性化につながる可能性があります。
【出典】株式会社ベルーナ「「谷櫻酒造有限会社」の子会社化に関するお知らせ」
まとめ|酒蔵業界のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
酒蔵業界のM&Aは、蔵の伝統やブランドを次世代へ受け継ぎながら、新たな価値を創出する大きなチャンスです。
M&Aを成功させるためには、業界特有の課題を理解し、慎重に計画を進める必要があります。事業への理解がある適切な買い手を選定するほか、許認可の手続きを確認し、醸造技術を継承する準備が必須です。
M&Aを通じて酒蔵の魅力を次世代へつなげるために、専門家へ相談した上で、着実に準備を進めていきましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。