CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
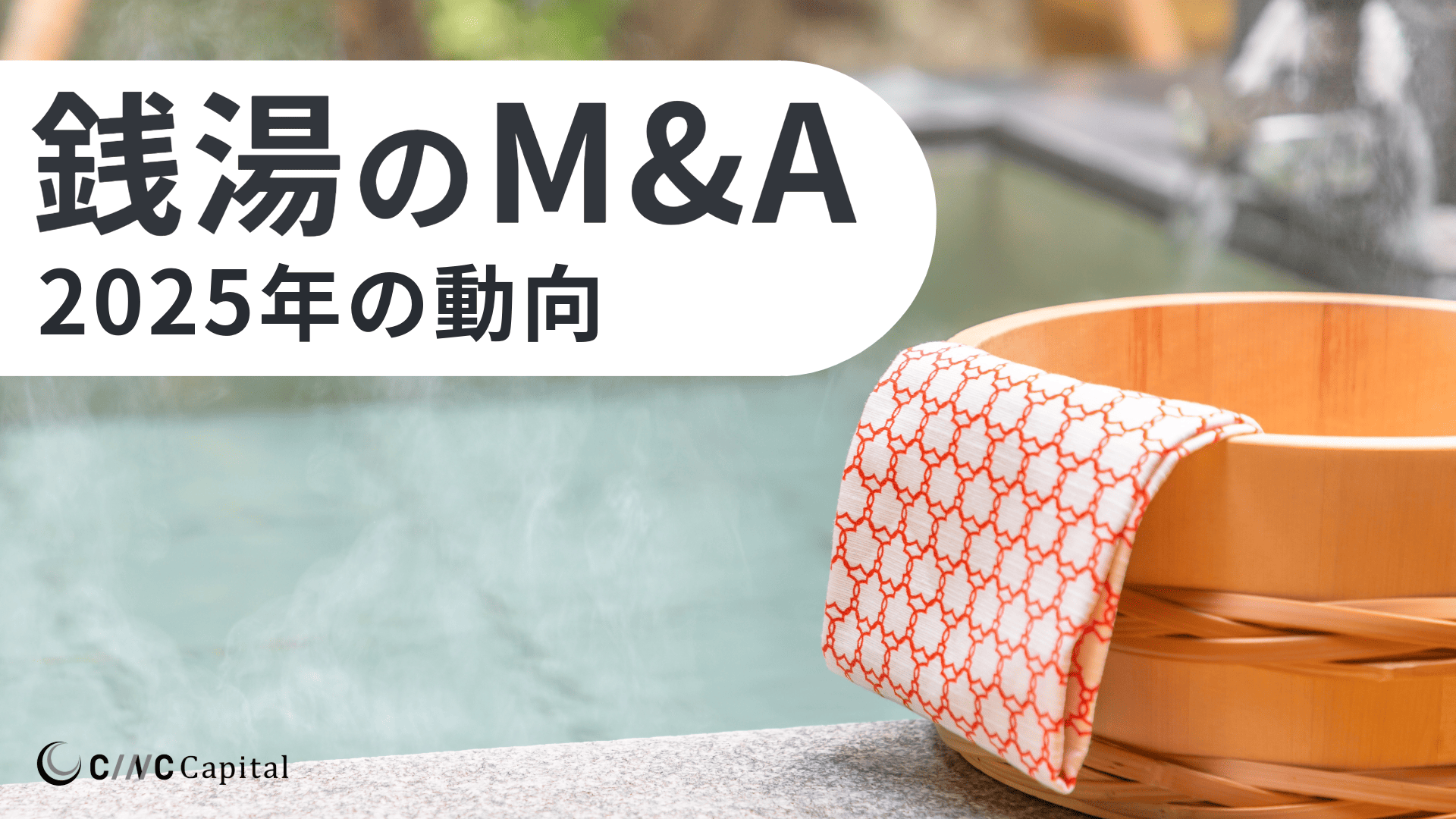
業種
- 最終更新日2025.06.26
銭湯業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
銭湯業界は、高度経済成長期をピークに大きな転換期を迎えており、事業承継や経営改革が喫緊の課題となっています。
施設の老朽化や後継者不足などの構造的な問題に直面する一方で、サウナブームによる若年層の需要増加という、新たな可能性も見え始めています。
本記事では、銭湯業界のM&A最新動向や、メリット・デメリット、成功事例、さらには成功に導くためのポイントを徹底解説します。
目次
銭湯業界の市場動向
「東京商工リサーチ」によると、日本の銭湯施設数は、1968年のピーク時には1万7,999軒を数えたとのことです。しかし、2022年には1,865軒まで減少し、約90%もの激減となりました。
急激な減少の背景には、1960年代から1970年代にかけての高度経済成長期における生活水準の向上があります。各家庭への内風呂の普及により、銭湯は日常生活における「必須の場所」から「選択肢の一つ」へと位置づけが変化しました。
また、近年はロシアによるウクライナ侵攻の影響が大きく、燃料費の高騰が深刻な課題となっています。これに加えて、設備の老朽化に伴う修繕費用の増大や、清掃などの維持管理費用の上昇も、経営者の大きな負担となっています。
【出典】株式会社東京商工リサーチ「街の銭湯、ピークから1万6000軒減少」
銭湯業界が抱える課題
銭湯業界は、温泉施設の老朽化や運営コストの上昇、集客の課題など、複合的な問題に直面しています。それぞれ具体的に見ていきましょう。
施設が老朽化してきている
銭湯施設の多くは高度経済成長期に建設され、大規模な設備更新が必要な時期を迎えています。修繕費用の捻出が困難な状況により、一部施設は業態転換を検討せざるを得ない状況に追い込まれています。設備の老朽化は安全性の観点からも看過できない問題のため、早急な対応が求められるでしょう。
水道光熱費の高騰によってコストが圧迫されている
エネルギーコストの上昇により、銭湯の経営が圧迫されているといわれています。特に燃料費と水道光熱費の高騰は、収益を大きく圧迫する大きな要因です。一方、一般公衆浴場の料金が自治体によって規制されているため、コスト増加分を料金に転嫁できない現状があります。
新規集客が難しく常連客依存になりやすい
銭湯業界では、新規顧客の獲得が困難な状況が続いています。中でも地方部では、高齢化する常連客への依存度が高く、若年層の利用が少ないことが課題です。
サウナ特化型施設が増えたことで客数が減少している
2021年以降のサウナブームを背景に、サウナに特化した新規施設の出店が多く見られます。この影響により、従来型の銭湯施設では客数の減少が顕著で、業界全体が厳しい競争環境に変化しつつあります。
銭湯業のM&A最新動向(2025年)
近年は業界再編の動きが活発化しており、中小施設の事業存続に向けた選択肢として、M&Aが検討されています。特に2024年以降、大手企業による銭湯・温浴施設の買収が見られました。業界の再編が徐々に加速しています。
2025年に向けては、デジタル化への対応やサービスの多様化が求められる中、M&Aを通じた経営基盤の強化が重要になると予測されています。具体的には、ITシステムの導入による業務効率化や顧客体験の向上が、今後の成長戦略の鍵となるでしょう。
銭湯業がM&Aをするメリット
ここからは、銭湯業がM&Aをするメリットについて、売り手目線で解説します。M&Aを有効活用できれば、事業存続の一助となるはずです。
資金を調達することができる
事業売却により、適切な企業価値評価にもとづいた売却益が得られます。老朽化した設備の更新や新たなサービス展開に向けた投資資金として活用することで、事業の持続的な成長につながります。
銭湯を続けていくことができる
M&Aを通じて事業承継することで、長年地域に根付いた銭湯文化を存続させられます。買い手側の経営ノウハウや資金力を活用し、より多くの利用者に愛される施設に発展させられるでしょう。
従業員の雇用を確保できる
事業承継は、長年働いてきた従業員の雇用を守る有効な手段です。新たな経営者のもとで従業員の雇用を維持しながら、これまで培ってきた顧客との関係性を継続できるのは大きいでしょう。
後継者不在の問題を解消できる
銭湯業界における後継者不足は深刻化していますが、M&Aによりこの問題を効果的に解決できます。加えて、買い手側企業から経営陣が派遣されることで、新たな視点や経営ノウハウが導入されるケースもあります。
経営の効率化や事業拡大が期待できる
買い手側の経営資源を活用し、経営効率化や事業拡大、サービスの多様化に対応できます。地域密着型のビジネスである銭湯業において、地域のニーズや文化を理解した上での事業展開が可能となり、新たな企業価値の創造につながるでしょう。
銭湯業がM&Aをするデメリット
リラクゼーション需要の高まりや健康志向の拡大により、新たな成長機会が生まれている一方で、さまざまな課題も顕在化しています。ここでは、銭湯業がM&Aをするデメリットをご紹介します。
文化や理念に変化が起きることがある
長年培ってきた独自の経営理念や企業文化が、M&A後に変化する可能性があります。とりわけ地域密着型のサービスを提供してきた施設の場合、新しい経営陣との価値観の違いが顕著になるかもしれません。
従業員や取引先・顧客から反発されるリスクがある
急な経営方針の変更や新サービスの導入は、従来のサービスに慣れ親しんだ顧客からの反発を招くことがあります。また、従業員によっては、新しい経営体制への不安から離職を選択する可能性も考えられるでしょう。
企業価値の算定や交渉が難しい
銭湯業界では、施設の老朽化や収益性の変動が大きいため、適正な企業価値の算定が困難です。選択するスキームの種類、設備投資の必要性、将来の収益予測の不確実性も、価格交渉を複雑にしている要因とされます。
銭湯業がM&Aを成功させるためのポイント
ここでは、銭湯業がM&Aを成功させるためのポイントを解説します。業界特有の課題を理解し、適切な準備をおこなうことが重要です。
損益や負債の状況を明確にする
企業価値を適切に評価するために、財務状況の透明性を確保しましょう。特に銭湯業界では、水道光熱費の変動が経営に大きな影響を与えるため、過去数年間の収支状況を詳細に分析する必要があります。
設備の状態の確認と必要に応じた更新
配管やボイラー設備などの水回り設備については、専門家による詳細な調査が不可欠です。また、将来的な設備投資計画や修繕予定についても、事前に明確にしておきましょう。各設備の状態を確認し、適切な対応を取ることが大切です。
温泉権などの許認可関係を確認しておく
銭湯業界特有の要素として、温泉権や各種営業許可があります。これらの権利・許可の継承可能性について、事前に法的な確認を行ってください。とりわけ温泉権については、譲渡に関する制限や条件を詳細に把握しておきましょう。
銭湯業界のM&A事例
株式会社極楽湯ホールディングスによるり株式会社エオネックス及び株式会社利水社のM&A
極楽湯ホールディングスは、2020年4月1日付で株式会社エオネックスおよび株式会社利水社の全株式を取得し、子会社化しました。エオネックスグループは、北陸地域を中心に温泉掘削・温泉設備工事、地質調査、測量業務を行う企業で、温浴施設の運営も手掛けています。
極楽湯は、日本および中国で「極楽湯」「RAKU SPA」ブランドの温浴施設を展開しており、今回のM&Aにより、温浴設備のメンテナンス体制を強化し、運営コストの削減を図る狙いがあります。特に、自社施設の安定稼働と将来的な温浴施設の出店拡大に向けて、温泉掘削技術や設備管理のノウハウを内部化することが期待されます。
今後、極楽湯はエオネックスグループと連携し、温浴施設の開発・運営の効率化を進め、さらなる事業成長を目指します。
【出典】株式会社極楽湯ホールディングス「株式会社エオネックス及び株式会社利水社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
サンフロンティア不動産株式会社による株式会社ホテル大佐渡のM&A
サンフロンティア不動産は、2021年4月26日付で**「ホテル大佐渡」**の株式譲受を完了しました。同ホテルは、昭和39年開業の老舗宿泊施設で、佐渡島西海岸の絶景ロケーションを活かした客室や温泉、地元食材を用いた料理が特徴です。
今回の買収により、同社グループが佐渡島内で運営する宿泊施設は計4施設・248室に拡大。「たびのホテル佐渡」「佐渡リゾート ホテル吾妻」「ドンデン高原ロッジ」との相乗効果を高め、観光客の誘致と地域活性化を推進します。
さらに、連結子会社サンフロンティア佐渡が展開するタクシー・観光バス・レンタカー事業や、古民家活用のレストラン事業とも連携し、地域の魅力を発信する戦略を強化。宿泊・交通・食の一体的な提供により、佐渡観光の利便性向上と観光産業の活性化を目指します。
【出典】サンフロンティア不動産株式会社「「ホテル大佐渡」株式譲受完了のお知らせ」
まとめ|銭湯業界のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
銭湯業界のM&Aには、資金調達や銭湯文化の存続、従業員の雇用確保といった複数のメリットがあります。一方で、従業員や顧客の反発リスク、企業価値の算定が困難な点など、無視できないデメリットも存在します。
株式譲渡や事業譲渡などを検討している方は、M&A仲介会社などの専門家に相談し、成功の糸口を探ってみてはいかがでしょうか。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















