CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
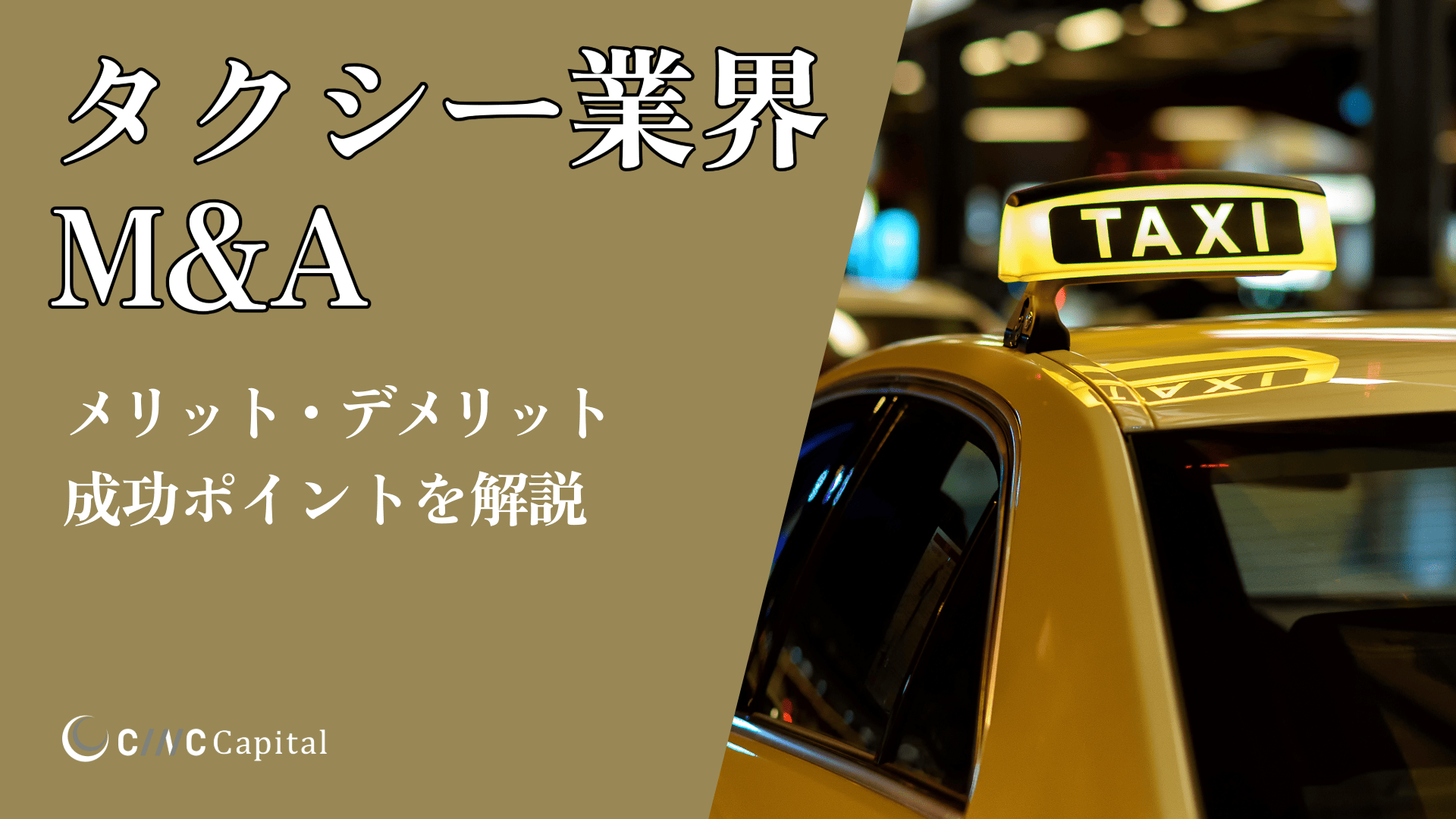
業種
- 最終更新日2025.06.26
タクシー業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
近年、タクシー業界では高齢化によるドライバー不足や、配車アプリ・ライドシェアの普及による競争の激化など、市場環境が大きく変化しています。タクシー需要そのものも地域差が大きく、都市部と地方部での稼働率の違いや配車アプリ活用状況による収益格差も広がりつつあります。
こうした背景のもと、事業を維持・発展させる手段としてM&Aが一層注目を集めています。企業買収や事業譲渡などの形態を通じて、老舗タクシー会社の後継者問題を解消したり、新しい技術を導入して顧客満足度を高めたりする動きが増加傾向にあります。
本記事では、タクシー業界の最新動向を踏まえた上で、M&Aのメリット・デメリットや成功事例、そして成功のポイントについて詳しく解説します。
目次
タクシー業界の市場動向
タクシー業界は近年の市場規模縮小や業界再編の動きに大きく影響を受けています。ここでは、タクシー需要の変化や規制動向の背景を概観します。
近年はドライバーの高齢化や新規参入の難しさなどが重なり、市場全体の輸送回数が伸び悩んでいます。その一方で都市部では、配車アプリの導入による利便性向上から利用者数が安定している事例も見られます。こうした地域差を踏まえて、タクシー事業をうまく維持・伸ばしていくためには、M&Aを活用した譲渡・継承が重要な選択肢となっています。
タクシー業界は規制緩和と規制強化を繰り返してきた歴史があり、免許制度や賃率設定などのルールが複雑です。特に駅構内で営業するための「乗り場使用権」を得るには、行政や鉄道事業者の許可が必要であり、事業拡大には様々なハードルがあります。こうした制約を乗り越えるために、すでに優良な営業権を保有する企業を買収するM&Aニーズが生まれています。
さらに、2025年に向けては地域公共交通の再編に関わる政策も進められており、タクシーを含む二次交通への支援や新技術の導入が注目されています。業界の将来を見据えたとき、スケールメリットを狙った再編や新技術を導入することで生き残りをはかろうとする動きが、今後ますます加速していくと考えられます。
タクシー業界が抱える課題
市場規模の変化とともに、タクシー事業者はさまざまな課題に直面しています。代表的な課題を整理して見てみましょう。
高齢化が進むドライバー不足の深刻化
タクシードライバーの平均年齢は上昇傾向にあり、人材確保の難しさが業界の大きな問題となっています。若い人材が長時間労働や不規則な勤務体系を敬遠することもあり、事務職や他の接客業種に流出しがちです。結果として、事業継続のためには新人教育コストの増加や、既存ドライバーへの勤務負荷などの課題が一層深刻化しています。
配車アプリやライドシェアの普及による競争激化
スマートフォンの普及に伴い、配車アプリが急速に一般化し、ライドシェア事業者も市場に参入するようになりました。これにより、従来のタクシー会社だけでなく、異業種やスタートアップとの競争が激化しています。新しいサービス形態に柔軟に対応できない事業者は市場シェアを失いかねず、さらなる経営努力が求められています。
燃料費や車両維持コストの増加
燃料価格が上昇すると直接的に収益を圧迫しやすく、車両のメンテナンスや保険なども合わせると経営コストは無視できない水準です。さらに近年では、環境対応車両への切り替えなど投資負担も増加し、経営体力のない中小企業にとっては大きなプレッシャーとなります。コスト削減とサービス品質維持の両立が、一段と難しくなっているのが現状です。
タクシー業界におけるM&Aの最新動向
タクシー業界では人材確保や技術導入を目的としたM&Aが増加傾向にあります。ここでは代表的な動向を見ていきます。
人材や設備獲得を目的とするM&A
タクシードライバーや車両設備を一括して獲得できる点は、買い手企業にとって大きな魅力です。既存の営業権や運行ノウハウを得ることで、短期間で収益を安定させられる可能性があります。特に地方の老舗タクシー会社を買収することで、新規事業参入のハードルを下げつつ地域貢献にもつなげる取り組みが見られます。
DX推進によるサービス向上を目的とするM&A
配車アプリや顧客管理システムなど、IT技術を活用したデジタル化がタクシー業界でも加速しています。買い手企業が持つ先進的なノウハウを売り手企業に導入することで、効率的な運行管理や予約対応が可能になり、顧客満足度の向上につながります。デジタル技術に精通した企業同士のM&Aは、全体的なサービスレベルを押し上げる効果が期待されています。
後継者不足解決と雇用維持のためのM&A
経営者や役員の高齢化と後継者不在が深刻化している中小タクシー事業者にとって、M&Aは事業存続のための重要な選択肢です。買収によって新たな経営層を迎えることで従業員の雇用も維持され、長年築いてきた地域とのつながりを断ち切らずに済むケースが多く見られます。業界再編の流れの中で、こうしたケースは今後も増えていくと予想されます。
【売り手】タクシー業界がM&Aをするメリット
タクシー事業者がM&Aを利用することで得られる利点として、後継者問題の解消だけでなく、事業強化などが期待できます。
後継者不足の問題を解決し事業を存続できる
高齢化した経営者が自社の後継者を見つけられない場合でも、M&Aを活用すれば経営ノウハウや権利を円滑に引き継ぐことができます。これにより地域の公共交通を担う役割を守り続けられるため、地元との関係性も維持されやすくなります。長期的視点で見ると、事業が存続することで地元の雇用やサービス水準への貢献が期待できる点は大きいと言えます。
従業員の雇用を守ることができる
M&Aで新しい資本や経営方針が導入されると、事業の継続性が確保され、従業員の雇用も安定しやすくなります。特に家族経営や地元密着型のタクシー会社では、従業員とその家族が地域のコミュニティの一部を形成しているケースが多いため、雇用維持は極めて重要です。買い手企業も地元のノウハウを活用しながら人材を確保できるため、Win-Winの関係が構築されることが期待されます。
業界内の競争力を高めることができる
資本力のある企業による買収や合併を行えば、サービスの拡張や車両の更新、DX化への投資などがしやすくなります。特にタクシー業界では、新しい配車システムやキャッシュレス決済などの導入が競合との差別化につながるため、買い手企業の技術力や資金力を活用するメリットは大きいでしょう。これらの取り組みによって利用者の満足度が高まり、売り手企業のブランド力向上にも寄与する可能性があります。
【売り手】タクシー業界がM&Aをするデメリット
一方で、M&Aには組織の文化変化や顧客関係の維持などデメリットも伴います。考慮すべきリスクを確認しましょう。
企業文化の変化が従業員の離職につながる可能性がある
買収先企業の経営スタイルや組織統治が従来の企業文化と合わない場合、従業員のモチベーションが大きく下がる恐れがあります。これまで築いてきた働きやすい環境や社内コミュニティが損なわれることで、熟練ドライバーの離職が急増する事例もあり得ます。M&A実施時には従業員への十分な説明や意見集約が欠かせません。
顧客や取引先との関係性が損なわれる可能性がある
長年にわたって地元の利用者や取引先から支持されてきた企業の場合、社名変更やサービス体制の変更を機に信頼感が揺らぐことがあります。地域密着をモットーとしてきたタクシー会社ほど、この点は大きなリスクとなり得ます。新体制への移行過程で顧客や取引先とのコミュニケーションを密にし、混乱や不信を最小限に抑える工夫が必要です。
買い手企業の方針変更によりサービス内容が変化する可能性がある
買い手企業の経営戦略や投資計画によっては、従来のタクシーサービスが大きく変容する場合があります。送迎の対象範囲や料金体系の見直し、場合によっては事業の統合・縮小もあり得ます。事前の協議でサービスの継続性を明確にしておくことが、売り手企業にとっても従業員にとっても重要なポイントです。
【買い手】タクシー業界をM&Aをするメリットデメリット
買い手側にも既存の経営資源獲得や事業規模拡大など、多くのメリットがありますが、業界特有の規制や人員管理などリスクも存在します。
まずメリットとしては、営業拠点や車両・ドライバーなどの経営資源を迅速に手に入れられる点が大きいでしょう。市場参入やシェア拡大のスピードを高めるうえで、既存のノウハウを引き継げることは大きなアドバンテージとなります。また、許認可や乗り場使用権など、時間のかかる手続きプロセスをショートカットできるのも大きな利点です。
一方、タクシー業界特有の課題であるドライバーの高齢化や労務管理には、綿密な対策が求められます。さらに、地方と都市部では需要や競合環境が異なるため、買収後の統合計画によっては想定通りのシナジーが得られないリスクも存在します。買い手企業は事前デューデリジェンスにおいて、財務状況だけでなく地域特性や顧客動向の調査を入念に行うことが不可欠です。
また、配車システムの導入状況や厚生年金基金など、業界特有の確認項目も多くあります。買い手はこれらを総合的に把握して、買収後の経営プランを明確化する必要があります。成功裡にM&Aを進めるためには、バリュエーションや労務管理に適切なアドバイザーの力を借りることが望ましいです。
タクシー業界のM&A相場について
M&Aに際してもっとも気になる部分といえるのが価格相場ではないでしょうか。以下では、タクシー業界のM&A相場に関する情報を解説します。
価格は一概には決められない
M&Aの価格は多様な要因によって変動するため、一概に相場を提示するのは難しいものの、類似の取引事例などを参考に算定される場合があります。価格に影響を与える要因として、「会社の規模」「収益性」「将来性」「負債」「ブランド力」などが挙げられます。
また、タクシー業界では特に営業権(乗り場使用権など)や車両台数、許認可などの固有資産の評価が重要な指標となります。
M&Aにおけるタクシー業界の企業価値の算出方法
日本の中小企業のM&Aでは、企業価値算定方法として「時価純資産+営業権法」と「マルチプル法」が採用される場合が多いです。自社の価値について気になる場合は、ぜひ以下の企業価値算定シミュレーションをお試しください。
タクシー業界がM&Aを成功させるためのポイント
M&Aを円滑に進めるためには、従業員・顧客とのコミュニケーションや地域特性の考慮が重要となります。その具体的なポイントを見てみましょう。
従業員や顧客との信頼関係を維持するよう務める
M&Aに伴う組織再編では、従業員や顧客が不安を感じやすいものです。早期の段階から情報共有を徹底し、不透明感を取り除くことで、社員のモチベーション低下や顧客離れを防ぐことができます。特にドライバーとの連携を強化し、現場の声を施策に反映する姿勢が信頼獲得のカギとなります。
地域特性を重視した統合計画を立てる
タクシー業界では地域密着が大きな強みとなる場合が多く、都市部と地方でのニーズは大きく異なります。そのため、包括的な事業計画を立てる際には地域性を見極めることが重要です。配車エリアの拡大やサービス形態の見直しを行う場合でも、地域住民の移動ニーズや観光客の利用状況などを踏まえた施策が求められます。
適切なアドバイザーや専門家を活用する
タクシー会社のM&Aでは、許認可や運行管理に関する法的手続き、財務・税務問題など専門的な知識が必要です。専門家の意見を取り入れないまま交渉を進めると、後になって大きなトラブルが発生するリスクがあります。経験豊富なアドバイザーや仲介会社を活用することで、M&Aプロセスをスムーズに進行させることが可能になります。
タクシー業界のM&A事例
最後に、タクシー業界のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
第一交通産業株式会社による苫小牧観光ハイヤー株式会社のM&A
第一交通産業株式会社の連結子会社である第一交通サービス株式会社は、2022年7月、北海道苫小牧市を拠点とする苫小牧観光ハイヤー株式会社の全株式を取得し、同社を完全子会社化しました。
買収後は「苫小牧第一観光ハイヤー株式会社」へ商号を変更し、第一交通グループの一員として再出発しています。これにより、北海道内のグループ保有タクシー台数は529台に拡大し、全国では8,127台体制となりました。
本件は、地域に根ざした中小タクシー会社を取り込むことで、エリア拡大と効率的な車両・人員配置を図る戦略の一環です。地方都市でのサービス網拡充を通じて、安定した収益基盤の構築を進めています。
【出典】第一交通産業株式会社「苫小牧観光ハイヤー株式会社(北海道)の株式取得に関するお知らせ」
newmo株式会社による株式会社未来都のM&A
タクシー・ライドシェア事業を展開するnewmo株式会社は、2024年7月、大阪の老舗タクシー会社・未来都の全株式を取得し、経営権を取得しました。未来都は創業60年以上の歴史を持ち、大阪府内に10拠点・606台のタクシーを保有する地場大手です。
これにより、newmoグループの車両数は計646台となり、大阪で第5位の規模に成長しました。newmoは急速な事業拡大を目指しており、今回のM&Aは経営基盤の強化と、将来のライドシェア参入に向けた布石といえます。地域交通の課題解決とデジタル活用を軸に、今後の動向が注目されます。
【出典】newmo株式会社「newmo、大阪の老舗タクシー会社「未来都」の経営権を取得」
日本交通株式会社によるイースタンエアポートモータース株式会社のM&A
日本交通株式会社は2021年3月、イースタンエアポートモータースの全株式を取得し、同社の運営を引き継ぎました。また、ハロー・トーキョーの営業権譲受についても申請し、認可後に運営を開始する方針です。
これにより、日本交通グループの保有台数は全国で8,257台に拡大しました。イースタンエアポートは空港送迎、ハロー・トーキョーは高品質サービスでそれぞれ信頼を築いており、両社の統合で移動サービスの質的向上を図ります。
コロナ禍を背景に、タクシーの社会的役割が見直される中、事業規模の拡大と多様なニーズへの対応が狙いです。
【出典】日本交通株式会社「都内ハイヤー・タクシー最大手「日本交通」 イースタンエアポート、ハロー・トーキョーを譲受」
まとめ|タクシー業界の特徴を理解し、M&Aを成功へ
タクシー業界独特の課題や規制を踏まえた上で、M&Aを活用することで次世代への事業承継やグローバル化にも対応できる可能性があります。総括として、これまでのポイントを振り返りましょう。
タクシー業界はドライバー不足や競争の激化など困難な状況にありますが、M&Aを通じて後継者問題の解消やサービス品質の向上を図る動きが加速しています。売り手企業にとっては事業存続や雇用維持が大きな利点となり、一方の買い手企業にも効率的な資源獲得や市場シェア拡大のチャンスがあります。
ただし、成功のためには従業員・顧客との信頼関係を保ち、地域の特性を十分に考慮した統合計画を策定することが重要です。加えて、法務や財務、運行管理といった専門分野に精通したアドバイザーのサポートを受けることでリスクを最小限に抑えられます。
今後、タクシー業界はさらなる技術革新や利用ニーズの多様化が見込まれており、経営者は柔軟な発想と迅速な対応が求められるでしょう。M&Aタクシーの取り組みを通じて、新たなビジネスチャンスを創出しながら業界全体が持続的に成長していくことが期待されます。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















