CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
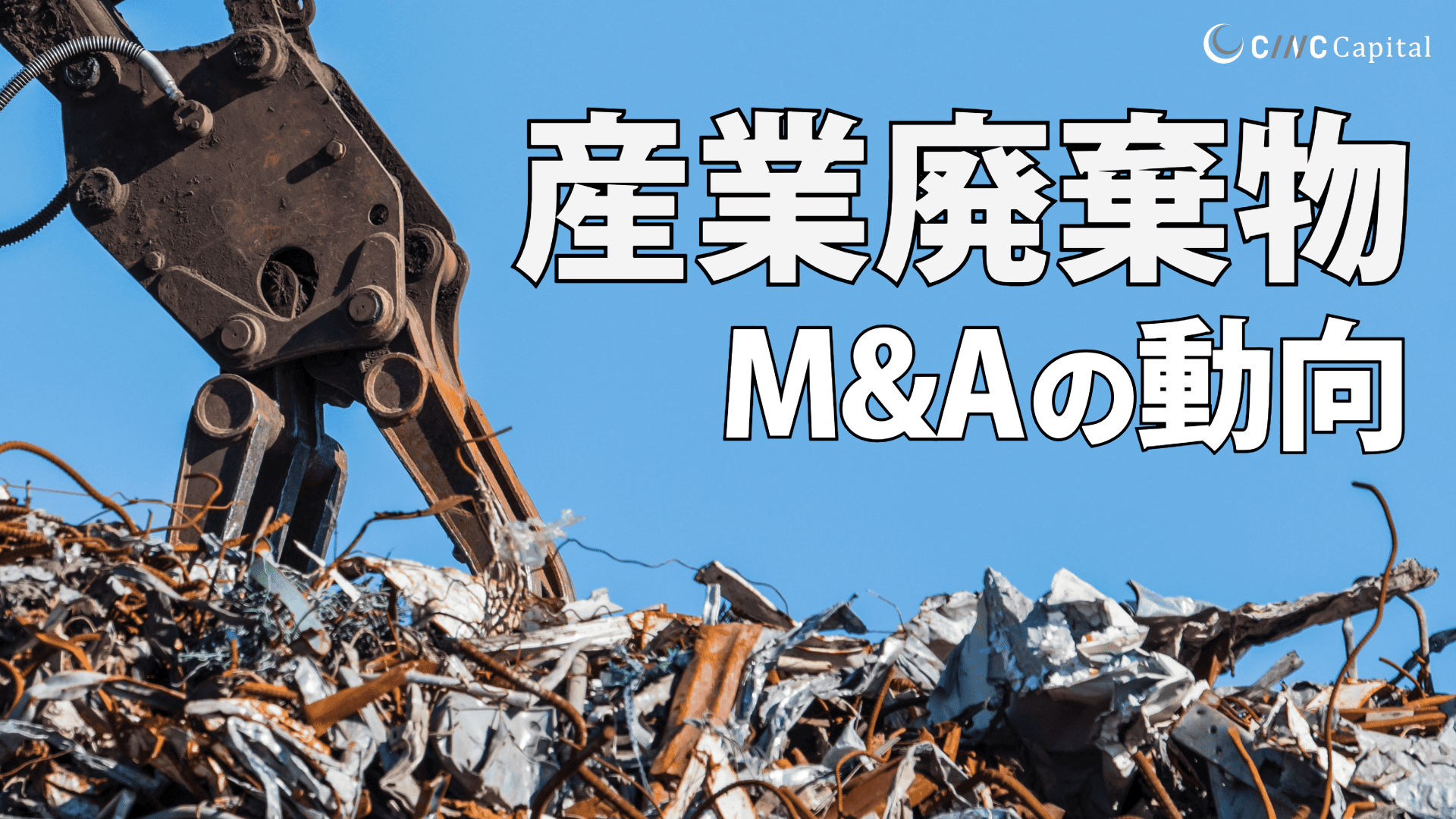
業種
- 最終更新日2025.06.26
産業廃棄物処理業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
環境規制の強化や持続可能な社会への移行が進む中、産業廃棄物処理業界では戦略的なM&A(合併・買収)が盛んに行われています。特に大手企業による中小企業の買収、隣接事業との統合など、業界再編の動きが加速の一途を辿っているようです。
今回は、産業廃棄物処理業界の市場動向やM&A最新動向、メリット・デメリット、成功のためのポイントを詳しくご紹介します。ぜひ今後の経営戦略の参考にしてください。
目次
産業廃棄物処理業界の市場動向
世界の廃棄物処理市場は、2020年時点で1兆5,120億米ドルという巨大な規模に達しており、2021年から2027年の間、年平均2.2%の成長率で拡大すると見られています。その背景には、新興国での工業化の進展や、環境規制の強化にともなう処理需要の増加があります。
過去に環境省が実施した調査によると、国内の産業廃棄物処理業界の市場規模は約5.3兆円で推移しています。業種別でいうと、「電気・ガス・熱供給・水道業」「農業・林業」「建設業」の3業種で全体の約7割を占めており、各産業の動向が市場規模に直接的な影響を与えています。
今後は、環境規制の強化や持続可能性への要求が高まり、再資源化技術の革新や処理効率の向上が求められると予測されています。特に、デジタル技術を活用したトレーサビリティの確保や、環境負荷低減に向けた取り組みが重要となるでしょう。
【出典】Report Ocean「世界の廃棄物管理市場は、2021年から2027年の予測期間中、2.2%以上の複合年間成長率で成長すると予測される」
【出典】環境省「平成 23 年度産業廃棄物処理業実態調査業務 報告書」
産業廃棄物処理業界が抱える課題
産業廃棄物処理業界は、環境保護と事業継続の両立という大きな課題に直面しています。規制の強化や人材確保の困難さ、競争の激化など、複数の問題が複雑に絡み合い、業界全体に影響を及ぼしているのです。具体的に見ていきましょう。
競争の激化
市場の成熟化にともない、事業者間の競争が激しさを増しています。特に収集運搬業では、同業者が多数存在するため、取引先の獲得競争が熾烈です。こうした状況の中、業界全体でコスト競争が激しくなっており、利益率の低下が懸念されています。
環境規制の強化への対応
環境保護意識の高まりを背景に、産業廃棄物処理に関する規制は年々厳格化しました。処理業者は水質汚濁防止法や大気汚染防止法など、複数の法規制を遵守する必要があり、これらへの対応コストが経営を圧迫しています。
人手不足と技術者の育成
産業廃棄物処理業界における人材確保の問題は深刻さを増しています。「全国産業資源循環連合会」の調査によると、業界の約半数の事業者が「従業員不足」を経営上の重要課題と認識しているようです。業界特有の労働環境や給与水準の低さが、人材確保を困難にしている要因と考えられます。
【出典】全国産業資源循環連合会「産業廃棄物処理業景況動向調査結果について 〔2024 年 7-9 月期(概要版)〕」
産業廃棄物処理業界のM&A最新動向(2025年)
日本の産業廃棄物処理業界では、環境規制の強化や技術革新の必要性を背景に、M&Aの動きが活発化しています。ここでは、産業廃棄物処理業界におけるM&Aの最新動向をご紹介します。
技術革新を促進するM&Aの増加
昨今はプラスチック廃棄物の土壌再生技術など、独自の処理技術を持つ企業の価値が高まっているといわれています。そのため、環境負荷の低減や処理効率の向上を目指し、先進的な技術を持つ企業の買収が増加傾向にあるのです。
中小企業の買収や合併が増加
環境規制によるコスト負担の増加や、設備投資の必要性が高まる中、大手企業による中小企業の買収が増えています。経営改善による企業価値の向上が期待されており、中小企業のM&Aは今後さらに加速することでしょう。
隣接事業者によるM&Aの増加
資源循環事業など、隣接する業種との統合によるシナジー効果を狙ったM&Aも増えています。特筆すべきは、収集運搬事業者と中間処理事業者の統合による、廃棄物処理の一貫体制構築を目指す動きです。廃棄処理の全プロセスを一社で完結させることで、サービスの多様化と付加価値の向上を狙っています。
産業廃棄物処理企業がM&Aをするメリット
ここでは、産業廃棄物処理企業がM&Aを実施するメリットを売り手側の視点でご紹介します。
経営基盤の安定
M&Aを通じて大手企業の傘下に入ることで、豊富な資金を活用した技術開発が可能となり、経営基盤の強化につながります。中小規模の企業にとって、単独での設備投資や技術革新は大きな負担となりますが、M&Aを活用することでこれらの課題を解決しやすくなります。
後継者問題の解決
産業廃棄物処理企業の中でも、後継者不在による事業継続の危機が増えているといわれています。M&Aは、こうした後継者問題を解決し、企業の存続と雇用の維持を両立させる手段として有効です。
売却益や譲渡益の獲得
事業評価が適正に行われれば、自社の許認可や処分場が価値として評価され、長年培ってきたノウハウや施設資産を現金化できます。特に廃棄物処理許可や地域独占性を持つ事業者は高評価を受けやすく、多額の譲渡益を得られる可能性があります。
廃業費用の負担回避
産業廃棄物処理業を清算する場合、施設の解体や環境対策など、多額の費用が発生します。M&Aを選択することで費用負担を回避しつつ、事業承継を円滑に進められるでしょう。また、個人保証や債務などの経営者個人の負担も、適切なM&Aスキームにより解消できる可能性があります。
専門人材の雇用維持
事業承継により、これまで培ってきた技術やノウハウを持つ従業員の雇用を維持できます。とりわけ昨今は、熟練技術者の確保が難しくなっています。既存の人材を活用できることは、事業の安定運営につながる大きなメリットです。
産業廃棄物処理企業がM&Aをするデメリット
M&Aの実施後、企業文化の衝突や人材の流出、取引先との関係変化など、事業継続に影響を与える可能性があります。売り手側の視点で詳しく見ていきましょう。
専門性が活かせなくなる可能性
産業廃棄物処理業界では、各企業が長年にわたって培ってきた独自の技術やノウハウが事業基盤となっています。M&Aによって経営体制が変わることで、これまでの専門的な処理技術や効率的な業務プロセスが失われるリスクがあります。業務効率が低下し、競争力が弱まる恐れもあるでしょう。
従業員が新体制に適応できず離職するリスク
現場の実務経験や専門知識を持つ人材が環境変化に適応できず、離職するケースが少なくありません。新しい企業文化や業務プロセスの導入によって、従業員のモチベーションが低下し、結果として貴重な人材の流出を招くリスクが高まります。
顧客との関係変化への懸念
M&Aによる経営体制の変更は、既存の取引関係にも影響を及ぼします。特に、地域密着型のビジネスモデルを展開している企業では、経営方針の変更が取引停止につながる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。許認可承継の複雑さにも注意が必要です。
産業廃棄物処理企業がM&Aを成功させるためのポイント
産業廃棄物処理企業がM&Aを成功させるには、以下5つのポイントを押さえておくことが大切です。売り手企業側の視点でご説明しましょう。
アピールポイントの明確化
産業廃棄物処理業界のM&Aでは、企業独自の廃棄物処理技術や運営システム、ノウハウの質が重要視されます。例えば、プラスチック廃棄物の土壌再生技術など、特殊な処理技術を有する企業ほどM&A市場で高い評価を受ける傾向にあります。
加えて環境関連事業との連携、産業廃棄物処理の一貫体制の構築など、事業の多角化・効率化をしている企業は、交渉売却時に有利といえるでしょう。
綿密な事前準備
自社の強みと弱みを明確に分析し、M&Aによって達成したい目的を明確にしましょう。後の事業展開についても具体的な計画を策定し、買い手と売り手、双方の利益を最大化できるように準備を進めてください。
デューデリジェンスへの対応
M&Aでは通常、事前に「デューデリジェンス(買収監査)」を実施します。産業廃棄物処理企業の場合、環境規制への適合状況や廃棄物処理プロセスの適正性について、詳細な調査を行う必要があるためです。
具体的なチェックポイントとしては、「許認可の承継可否確認」「過去の環境規制違反履歴」「産廃処分場の残余容量」「施設の法令適合性」「土壌汚染調査」「周辺住民との関係」などが挙げられます。
万が一、過去に環境規制違反などがあった場合、買収後に多額の是正コストが発生するリスクがあります。デューデリジェンスには相応の時間とコストがかかるので、できるだけ余裕を持って対応しましょう。
専門家の活用
産業廃棄物処理業界のM&Aでは、業界特有の知識に加え、法務・会計・税務など幅広い専門知識が求められます。また、廃棄物処理法の許可承継手続きのほか、自治体への各種届出、施設の変更許可申請などの複数の手続きが必要です。M&A仲介会社のサポートを受けることで、これらの複雑な実務手続きをスムーズに進められるでしょう。
産業廃棄物処理業界のM&A事例
成友興業株式会社による株式会社栄興産業のM&A
成友興業株式会社は、2024年7月16日付で株式会社栄興産業の全株式を取得し、子会社化する契約を締結しました。本件は、成友興業の環境事業の強化および首都圏での事業拡大を目的としています。
成友興業は、東京都内で建設汚泥やがれき類の中間処理事業を展開し、都市再開発や環境エンジニアリング事業に取り組んできました。一方、栄興産業は、埼玉県川口市に拠点を持ち、解体コンクリート塊の中間処理事業を展開しており、首都圏の産業廃棄物処理市場で実績を積んでいます。今回のM&Aにより、成友興業は埼玉県への事業拡大を実現し、グループ全体での相互支援体制を強化することで、より効率的な廃棄物処理ネットワークを構築する狙いです。
本件は、成友興業のM&A戦略の一環として、東京都以外の首都圏地域での市場拡大を目指す動きの一例となります。今後は、同社の経営リソースを活用し、栄興産業の事業基盤を強化することで、グループ全体の収益力向上と企業価値の向上を図る方針です。
【出典】成友興業株式会社「株式会社栄興産業の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
大栄環境株式会社による株式会社海成のM&A
大栄環境株式会社は、2024年12月6日付で、建物総合解体業を手掛ける株式会社海成の全株式を取得し、2025年1月6日付で連結子会社化する契約を締結しました。本件は、関東エリアにおける解体工事と廃棄物処理の事業基盤を強化し、グループ全体のシナジーを高めることを目的としています。
海成は1974年に創業し、官公庁や大手ゼネコンを顧客に持つ解体工事の実績豊富な企業です。今回のM&Aにより、大栄環境グループの関東エリアの関連企業である栄和リサイクルや共同土木と連携し、解体工事の受注拡大や、解体工事から発生する廃棄物をグループ内で効率的に処理する体制を構築します。これにより、廃棄物の受入量の増加や、資源循環の強化が期待されます。
また、海成は国家資格取得支援や女性活躍の推進にも力を入れており、大栄環境が進める人材育成や多様性推進の方針とも一致しています。本件M&Aは、持続可能な循環型社会の形成に向けた同社の戦略の一環であり、グループ全体の成長と企業価値向上につながるものと考えられます。
【出典】大栄環境株式会社「株式会社海成の株式取得(連結子会社化)に関するお知らせ」
北日本紡績株式会社による金井産業株式会社のM&A
北日本紡績株式会社は、2021年10月4日付で金井産業株式会社の全株式を取得し、同社を子会社化する契約を締結しました。本件は、北日本紡績が新規事業として掲げるリサイクル事業の本格的な展開を目的としています。
北日本紡績は、廃プラスチックのリサイクルを軸に、プラスチックペレットの製造およびアジア市場への輸出を計画しています。これに伴い、同社は既に東樺化成からプラスチックペレット加工施設と技術ノウハウを取得していましたが、さらなる事業基盤の強化を図るため、産業廃棄物の収集運搬業許可や中間処理設備を有する金井産業をグループに迎えることを決定しました。
金井産業は、山口県を拠点とし、合成樹脂の製造・販売や産業廃棄物のリサイクル事業を展開しています。本件M&Aにより、北日本紡績は安定的な廃プラスチックの供給源を確保するとともに、リサイクル事業の全国展開に向けた基盤を強化することが可能になります。今後は、廃プラスチックの大規模調達を進め、国内外でのリサイクル事業の拡大を目指す方針です。
【出典】北日本紡績株式会社「金井産業株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
まとめ|産業廃棄物処理業界のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
M&Aは技術力の強化や経営基盤の安定、事業承継問題の解決など、多くのメリットをもたらします。一方で、組織統合の課題や人材流出リスクもあり、慎重な計画が必要です。M&A仲介会社のサポートを受けて、戦略的に会社譲渡や株式譲渡を実行しましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















