CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
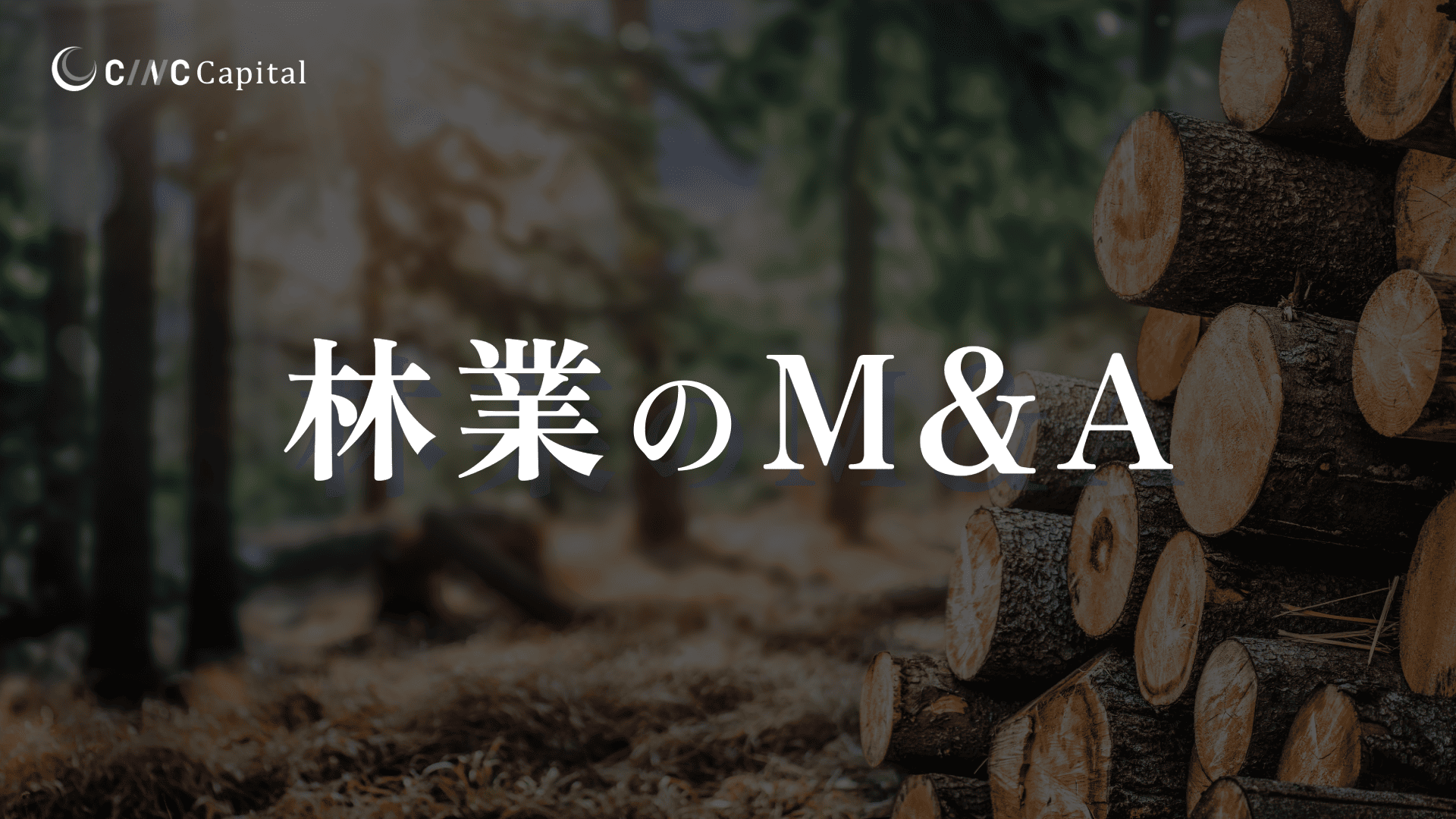
業種
- 最終更新日2025.06.26
林業のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
林業関連企業の経営者の皆様、事業承継や規模拡大でお悩みではないでしょうか。「後継者が見つからない」「木材価格の下落で経営が厳しい」といった声が多く聞かれます。このような課題を解決する選択肢として、M&Aが注目されています。
林業業界のM&Aを成功させるには、業界動向の把握や専門家への相談が欠かせません。この記事では、2025年に向けた林業業界のM&A動向、具体的な事例、メリットデメリット、成功のポイントを解説します。
目次
林業業界の市場動向
林業業界は近年、大きな転換期を迎えています。国内の木材自給率は2021年に約40%まで回復し、木材価格も持ち直しの傾向にありますが、依然として厳しい経営環境が続いているのが現状です。
特に2025年に向けては、カーボンニュートラルの実現に向けた木材利用の促進や、建築分野での国産材活用の増加が見込まれる一方で、担い手不足や設備投資の遅れが深刻な課題となっています。そのため、事業継承や経営基盤の強化を目的としたM&Aへの関心が高まってきています。
林業業界の現状
国内の林業業界は大きな変革期を迎えており、特にデジタル化の進展、環境保全意識の高まり、木材需要の変化が重要なポイントです。
ドローンやGPSを活用したスマート林業が進み、持続可能な経営のためにFSC(Forest Stewardship Council)認証取得が増加し、建築分野では国産材活用が進み、都市の木造化が注目されています。
一方、人材不足や経営基盤の脆弱さが課題となっており、M&Aを活用した経営効率化や技術導入が業界の新たな選択肢として注目されています。
※FSC認証:森林の環境や地域社会に配慮して作られた製品であることを示すマーク
林業業界が抱える課題
林業業界は現在、大きな転換期を迎えており、複数の重要な課題に直面しています。ここでは、特に経営の継続性を脅かす課題について3つ見ていきます。
後継者不足
林業業界の後継者不足は事業継続の最大のリスクです。林業経営者の約7割が60歳以上で、若者の林業離れや都市部就職の増加、技術継承の難しさが問題となっています。
1980年に約10万人いた就業者は2020年に約4万4000人に減少し、新規就業者の離職率はデータの出所により異なりますが、3年で30%以上、5年で40%以上離職しているというデータもあります。これにより森林管理の不備が進み、災害リスクが高まっています。
【出典】林野庁「林業労働力の動向」
木材需要と木材価格の減少による収益性の低下
日本の林業業界は国産材の価格下落により収益性が低下し、多くの経営者が厳しい状況に直面しています。
スギ原木価格は1985年(昭和60年)をピークに低下傾向で推移し、2023年には10,000円/㎥〜18,640円/㎥で推移しています。価格の下落は、安価な輸入材との競争や木材需要の減少が要因です。コストは上昇する一方で売上が減少し、森林管理の遅れも深刻化しています。
この状況を打開するため、規模の経済を活かしたM&Aが注目され、バイオマス発電など新分野への展開が今後の成長戦略として期待されています。
【出典】eTREE「木材価格の最新動向|ウッドショック後の価格は?」
環境規制の強化
林業業界では環境規制の強化が進み、経営への負担が増大しています。カーボンニュートラル推進に伴い、森林管理計画の厳格化やモニタリング義務が強化され、管理コストが上昇しました。
さらに、生態系保護のため伐採規制や作業時期の制約も拡大し、FSC・SGEC認証取得の重要性も高まっています。特に小規模事業者にとって負担が大きく、M&Aによる規模拡大や専門人材確保が求められています。経営基盤の強化が、規制対応の鍵となるでしょう。
【売り手】林業業界がM&Aをするメリット
株式譲渡や事業譲渡などにより、自社の持つ課題を解決できる可能性があります。ここでは、林業業界がM&Aをする売り手目線のメリットをご紹介します。
後継者不在問題を解消できる
M&Aは後継者不足に悩む林業事業者にとって、有力な事業承継の手段です。林業は技術や地域との関係性が重要であり、単なる売却ではなく価値の継承が求められます。
実際、老舗林業会社が木材加工企業とM&Aを実施し、雇用維持と安定供給の両立を実現した例もあります。M&Aにより、従業員の雇用継続、森林管理の維持、取引先との関係継続が可能になり、地域の林業発展にも貢献します。適切な相手とWin-Winの関係を築くことが成功の鍵です。
競争の激化する市場環境の中で事業を安定させることができる
林業市場の競争が激化する中、M&Aは事業の安定性を高める有効な手段となります。M&Aにより規模の経済を活かした効率化が可能になり、機械設備の共同利用や人材配置の最適化で生産性を向上させられます。
具体的には、森林資源の集約化、高性能林業機械の導入、管理部門の統合、柔軟な人員配置などの効果が期待できます。また、木材価格変動リスクへの対応力や取引先との関係強化、ICT導入の促進にも寄与し、持続可能な経営を実現する手段となります。
販路の拡大が期待できる
M&Aを活用することで、林業事業者は販路拡大と経営の安定化を実現できます。特に中小事業者にとって、大手企業のネットワークを活用できることは大きな利点であり、住宅メーカーや建材メーカーとの取引機会が広がります。
また、M&Aにより販路が全国規模に拡大し、物流コストの削減も可能になります。さらに、バイオマス発電用木材供給など新市場へ参入しやすくなり、営業ノウハウやデジタルマーケティングの活用も促進されます。
【売り手】林業業界がM&Aをするデメリット
M&Aには、いくつかのデメリットが存在します。今後M&Aを検討する中で、売り手側が知っておくべき注意点は以下の通りです。
従業員の不安や反発が発生する可能性がある
M&A後の従業員の不安や反発は、事業統合の大きな課題です。特に林業では、地域密着型の企業文化や技術の継承が重視されるため、不安が強まりやすいです。
懸念点として、雇用条件の変更、勤務地の変化、作業方法の変更が挙げられ、モチベーション低下や熟練従業員の流出につながる可能性があります。
円滑な統合には、説明会や個別面談を通じた丁寧なコミュニケーションが不可欠で、従業員の声を反映しながら不安を解消することが重要です。
売却後の利益配分や権利関係が複雑になる可能性がある
林業業界のM&Aでは、森林の所有権や収益配分の複雑化が重要な課題です。特に、伐採権や補助金の受給資格、森林経営計画の継承など、権利関係の整理が不可欠となります。複数の地権者との契約が絡む場合、調整に時間がかかることもあります。
また、地域住民との慣習的な約束の引き継ぎも考慮すべきポイントです。トラブル回避には、事前に権利関係を整理し、収益配分や管理方針を具体的に契約で定めることが重要となります。
【買い手】林業業界をM&Aするメリットデメリット
M&Aは林業企業にとって、事業の成長と安定をもたらす有力な手段です。特に、既存の人材やノウハウを引き継ぐことで、技術の継承や人材育成コストの削減が可能になります。林業は地域との信頼関係が重要な業界であり、従業員の経験や地域のつながりを活かすことで、円滑な事業継続が期待できます。
また、森林資源の確保による安定供給や、大手企業のネットワークを活用した販路拡大も大きなメリットとなり、新たな市場への参入が容易になります。
しかし、M&Aにはリスクも伴います。地域の文化や慣習への適応が求められ、住民との信頼関係が損なわれると事業運営に支障をきたす可能性があります。また、燃料費や人件費の高騰により、伐採・運搬コストが増大するリスクもあります。
さらに、森林の所有権や収益配分の整理が必要となり、契約の調整には時間とコストがかかる場合があります。これらの課題を克服するためには、M&A後の統合プロセスを慎重に進め、地域との調和を図りながら経営基盤を強化していくことが不可欠です。
林業業界のM&A相場について
M&Aに際してもっとも気になる部分といえるのが価格相場ではないでしょうか。以下では、林業業界のM&A相場に関する情報を解説します。
価格は一概には決められない
M&Aの価格は多様な要因によって変動するため、一概に相場を提示するのは難しいものの、類似の取引事例などを参考に算定される場合があります。価格に影響を与える要因として、「会社の規模」「収益性」「将来性」「負債」「ブランド力」などが挙げられます。
M&Aにおける林業業界の企業価値の算出方法
M&Aの譲渡価格は、「DCF法」「類似会社比較法」「時価純資産法」など複数の算定方法を状況に応じて使い分け、あるいは組み合わせて算出します。自社の価値について気になる場合は、ぜひ以下の企業価値算定シミュレーションをお試しください。
林業業界がM&Aを成功させるためのポイント
林業業界のM&Aを成功に導くためには、綿密な事前準備と適切な実行プロセスの管理が重要となります。以下に、特に重要なポイントを4つ解説します。
森林資源や経営資源を正確に評価し、適切な価格交渉を行う
林業企業のM&Aでは、適切な価格交渉を行うために森林資源と経営資源の正確な評価が不可欠です。森林資源の評価では、単なる面積だけでなく、樹種や林齢、地形やアクセス性を考慮する必要があります。
例えば、成熟した杉や檜の人工林は価値が高いですが、急斜面では作業効率が低く、評価額が下がることもあります。また、保有設備や従業員の技術力、販路の強みなども経営資源の評価において重要な要素です。価格交渉には専門家と連携し、慎重に進めることが成功の鍵となります。
環境保護の観点を重視し、持続可能な事業運営を目指す
林業業界のM&Aでは、環境保護を取り入れた持続可能な事業運営が、企業価値向上と長期的成長の鍵となります。ESG投資の観点からも、環境配慮企業への評価が高まり、森林認証の取得や再造林の推進が求められています。
例えば、FSC認証やSGEC認証を取得すれば、持続可能な経営を行う企業としての信頼を強化できます。また、カーボンニュートラルへの貢献を通じて温暖化対策にも寄与し、補助金や優遇措置の活用機会も拡大します。環境保護と効率的経営の両立が、M&A成功の鍵となります。
地域社会や行政との連携を強化し、円滑に統合を進める
林業業界のM&A成功には、地域社会や行政との関係構築が不可欠です。林業は地域経済や環境に影響を与えるため、住民や自治体の理解と協力が事業の安定性を左右します。早期から意見交換会を開催し、森林保全活動に参加することで信頼を築くことが重要です。
また、行政と連携し、補助金活用や森林経営計画の策定を進めることで、円滑な事業統合が可能になります。
M&Aの専門家を活用する
M&Aを成功させるには、プロの力を借りることも大切です。専門知識がない状態で交渉を続けると、不当な条件で売却してしまう可能性も考えられます。プロのサポートを受け、希望の条件での成約を目指しましょう。
林業業界のM&A事例
最後に、林業業界のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
株式会社タケエイによる株式会社泉山林業のM&A
2024年1月、株式会社タケエイは、岩手県八幡平市の泉山林業の全株式を取得し、子会社化することを決定しました。本件は、タケエイの親会社であるTREホールディングスグループが推進する木質バイオマス発電事業の一環として実施されました。
泉山林業は、立木の伐採から素材(丸太)への加工、チップの製造・販売を手掛ける企業で、1993年の設立以来、林業分野での高い専門性を有しています。特に、自社で高性能なチップ加工機を保有し、オーダーに応じた製品を提供できる技術力を持つ点が特徴です。また、林野庁の研修を修了したフォレストマネージャーやフォレストリーダーが複数名在籍しており、人材面でも強みを持っています。
タケエイは、岩手県花巻市での森林経営計画を進めており、植林から木質バイオマス燃料の調達・発電・売電までの一貫体制を構築しています。泉山林業の子会社化により、燃料材調達ルートと熟練した人材の確保が可能となり、バイオマス発電事業の安定性が向上することが期待されます。また、グループ内のタケエイ林業と連携することで、伐採から燃料材の生産・販売までの業務を内製化し、再生可能エネルギー事業のさらなる拡充を目指します。
本件の買収額は非公開ですが、第三者(会計士・弁護士等)によるデューデリジェンスを実施の上で決定されています。本件の短期的な業績への影響は軽微とされていますが、中長期的にはグループシナジーによる収益拡大が見込まれるM&Aといえます。
【出典】株式会社タケエイ「株式会社泉山林業の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
綿半ホールディングス株式会社による有限会社須江林産のM&A
2024年9月、綿半ホールディングス株式会社は、子会社である綿半建材株式会社を通じて、有限会社須江林産(長野県佐久市)の全株式を取得し、子会社化しました。
須江林産は1990年に創業し、民有林・国有林の管理、立木の伐採、素材丸太・チップ用原木の販売を手掛ける企業です。特に、森林所有者や行政との強いネットワークを活かし、民有林の管理に強みを持っています。また、20〜30代の技術職員・技能職員が多く在籍し、次世代の森林整備人材の育成にも注力しています。
本買収により、綿半グループは素材丸太の生産から加工・施工・販売までを一貫して担う体制を確立。従来の建材・住宅事業と林業を結びつけることで、「伐る・植える・育てる・使う」の循環型林業を推進し、長野県の林業発展と企業価値の向上を目指します。
近年、木材の安定供給や持続可能な森林経営の重要性が高まっており、林業と建材産業の連携強化は業界のトレンドとなっています。本件は、林業資源の確保と自社サプライチェーンの強化を狙った戦略的M&Aの一例といえるでしょう。
【出典】綿半ホールディングス株式会社「須江林産が綿半グループ入り」
まとめ|林業業界のM&A動向を抑えてM&Aを成功させましょう
林業業界のM&Aは、適切に準備を整えることで、企業の継続的な発展と林業の持続可能性を両立させることができます。2025年に向けて、業界のM&A動向を理解し、しっかりと準備することが成功への近道となるでしょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















