CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
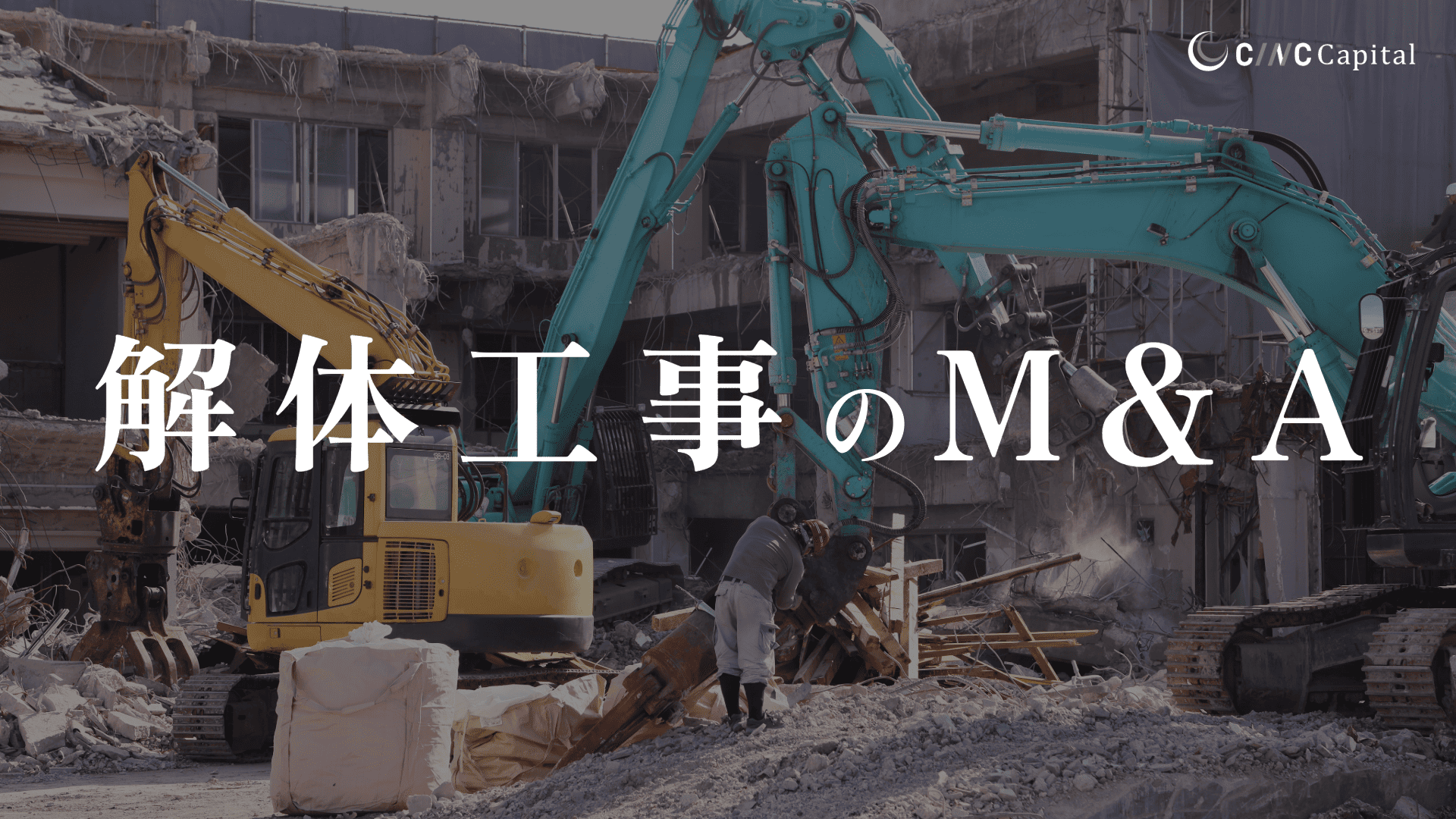
業種
- 最終更新日2025.06.26
解体工事業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説
建築物の解体を担う解体工事業界では、M&Aが活発に行われているといわれています。
M&Aは企業の持つ課題の解決策となり得る手法です。どのようなメリットがあるのかを確かめてみましょう。
この記事では、解体工事業界の市場動向や主な課題、最新のM&A動向、メリット・デメリットなどをご紹介します。
目次
解体工事業界の市場動向
解体工事業界の市場規模は、年ごとに増減は見られるものの、全体を通して上昇傾向にあるといわれています。要因とされるのが、解体需要の増加です。老朽化した建物や空き家などが増え、解体が必要とされるケースが見られます。また、地震や豪雨などの自然災害が多く、被害を受けた建物の解体需要も拡大傾向にあるようです。
【出典】国土交通省「建設工事受注動態統計調査 建設工事施工統計調査」
解体工事業界が抱える課題
解体工事業界では、以下のような問題が生じているといわれています。具体的な課題を確認しましょう。
産業処理場の不足と処理コストの高騰
解体工事の際には産業廃棄物が出てきます。以前までは海外への輸出も可能でしたが、制限が行われた結果、産業廃棄物の処理に影響が生じています。解体工事で生じる産業廃棄物の処理場が不足し、処理費用が高騰しているのは大きな課題の一つです。
人材不足と高齢化
解体工事業は中小企業や個人事業主も少なくありません。幅広い業界において、中小企業などの人材不足や高齢化は問題になっています。特に技術を持つ職人が不足しやすい点は、経営者の悩みの種となるでしょう。
アスベスト対応
法改正により、解体工事前にはアスベストの有無を調査することが義務化されました。有資格者が法律に基づく方法で事前調査を実施し、結果を報告しなければなりません。こういった対応のハードルの高さも解体工事業の課題となります。
解体工事業のM&A最新動向(2025年)
M&Aを成功させるためには、業界の動向をつかむことも重要です。以下では、解体工事業のM&A動向について解説します。
需要の増加に伴いM&Aの件数は増加傾向にある
ご紹介した通り、解体工事自体の需要は高まる傾向にあります。業界の成長性が期待できる一方で、人材不足に悩まされているのが現状です。上記のような課題解決手段の一つとしてM&Aが選ばれており、件数が増加傾向にあるといわれています。
建設業界内の関連事業者からのM&Aが活発に行われている
解体工事以外の事業を手掛ける企業とのM&Aも注目を集めています。例えば、産業物処理業とのM&Aにより、産業廃棄物処理に関連する問題を解消できるケースがあります。
元請け会社によるM&Aも見られる
解体工事業は、ゼネコンなどの大手からの下請けとして案件を受注するケースが多く見られます。元請け企業が解体工事業を買収するM&Aも珍しくありません。
解体工事業がM&Aをするメリット
解体工事業がM&Aを行うことで、以下のような効果を得られると期待できます。具体的なメリットをチェックしてみましょう。
後継者問題の解決につながる
経営者が高齢になり、後継者を探すものの見つからず、廃業に至るケースは少なくありません。M&Aによって事業を譲渡することで、後継者不在による廃業を回避できます。
雇用を維持できる
廃業した場合は従業員が職を失うことになりますが、M&Aによる事業の売却・譲渡なら雇用を継続できるのがメリットです。従業員の雇用を守る上でも、有効な手段となります。
経営基盤を強化できる
M&Aにより、中小企業や零細企業が大手企業の傘下に入ることもできます。経営基盤の強化により、安定した売上の維持も可能となるでしょう。
担保や個人保証を解消できる
中小企業の場合、経営者個人が担保や個人保証を背負っていることが珍しくないでしょう。交渉次第では、M&Aで担保や個人保証を引き継いでもらうことも可能です。金銭面でも精神面でも負担を解消できるでしょう。
解体工事業がM&Aをするデメリット
M&Aはメリットばかりではなく、気をつけておきたいデメリットも存在します。事前に注意点を把握した上で検討を進めましょう。
組織や文化の統合が容易ではない
異なる文化を持つ組織を統合し、事業を続けていくのは容易ではありません。うまくいかない場合、かえって業務効率や作業品質の低下を招くこともあるでしょう。計画的に統合を進めていくことが求められます。
従業員が不安を感じ離職率の上昇が懸念される
業務の方針や人間関係の変化に付いていけず、従業員が離職を選択するケースもあります。モチベーションを維持できるよう、丁寧なフォローを行うことが重要です。
企業が持つ資産や価値を適切に評価されないおそれがある
M&Aに際して、企業の資産や価値を正しく評価されなければ、売却価格が低くなってしまうことがあります。重機や設備といった有形資産だけではなく、長年培ってきたノウハウや顧客との信頼関係などの無形資産も評価対象として判断してもらいましょう。
企業の価値を適切に見極めるには、M&Aの専門知識を持つプロへ依頼することが大切です。簡易的に自社の企業価値を知りたい方は、以下よりシミュレーションをしてみることをおすすめします。
解体工事業がM&Aを成功させるためのポイント
M&Aを成功に導くために、どのようなポイントに気をつけたら良いのでしょうか。以下では、具体的なコツや注意点を解説します。
解体工事業として必要な条件が揃っているか確認する
現在、解体工事業を行うためには各種許認可が必要です。かつては「とび・土木工事」の許認可さえあれば事業を開始できましたが、制度が変化している点に注意が必要です。
M&Aのプロセスにおいては解体工事業登録・産業廃棄物処理業許可・特定建設業許可の承継をはじめとした確認が必要です。また、各種資格者の確保状況も把握しておきましょう。
M&A後、スムーズに事業を始めるには、現在必要な許認可や免許、設備などが揃っていることが求められます。必須の条件が揃った状態であれば、評価も高まりやすいでしょう。
他社にはないアピールポイントを整理する
競合と差別化できる部分があると、買い手へのアピールにつながります。例えば、特殊な技術を持っている、豊富な解体工事実績があるといった場合は積極的に伝えましょう。事前に自社のアピールポイントを整理しておくことがおすすめです。
解体工事業界に詳しい専門家にアドバイスをもらう
M&Aでは法律や会計などの専門知識はもちろん、業界の知識も求められます。特に解体工事業界のデューデリジェンスでは、「重機・機材の評価方法と残存価値」「産業廃棄物処理の契約関係」「作業員の資格保有状況」「事故履歴とリスク管理体制」などの詳細なチェックが実施されます。
解体工事業界に知見の深いM&Aの専門家に依頼して、アドバイスをもらいましょう。M&A仲介会社であれば、相手企業の選定や自社に合うM&Aスキーム、各種手続きなど、さまざまな内容を相談可能です。
解体工事業界のM&A事例
最後に、解体工事業界のM&A事例をご紹介します。検討時の参考にしてみましょう。
株式会社鈴木商会による株式会社木村工務店のM&A
株式会社鈴木商会は、北海道釧路市の解体業者である株式会社木村工務店の全株式を取得し、完全子会社化しました。本件は、解体業への進出と資源循環ビジネスの強化を目的としたM&Aです。
鈴木商会は、北海道を拠点に資源リサイクル事業を展開し、産業廃棄物の収集・加工を手掛けています。一方、木村工務店は地域密着型の解体業者として長年にわたり釧路で事業を展開し、同エリアで有数の規模を誇ります。
本件M&Aにより、鈴木商会は解体業への参入を果たし、解体から廃棄物処理・リサイクルまでを一貫して行う体制を構築。これにより、道東エリアにおけるサービスの利便性向上と、持続可能な資源循環の実現を目指します。
廃棄物処理・リサイクル業界では、解体業との統合による一貫体制の強化が重要視されており、本件は業務領域の拡大とシナジー創出を目的とした戦略的M&Aの事例といえます。
【出典】株式会社鈴木商会「【プレスリリース】株式会社木村工務店の全株式取得による完全子会社化のお知らせ」
株式会社カシワバラ・コーポレーションによる株式会社小椋組のM&A
株式会社カシワバラ・コーポレーションは、東京都八王子市の解体業者「株式会社小椋組」の全株式を取得し、2024年6月28日付で完全子会社化しました。本件は、再開発案件やインフラ設備解体の強化を目的としたM&Aです。
小椋組は1980年の創業以来、東京都を中心にビル・マンション・工場・学校などの大規模解体工事を手掛けてきました。近年では、石油化学・電力などインフラ関連プラントの老朽化に伴う設備解体や、再生可能エネルギーへの転換に対応した事業も展開しています。
本M&Aにより、カシワバラ・コーポレーションは、関東エリアでの解体事業を強化し、将来的な全国展開を視野に入れます。高度経済成長期に建設された設備の老朽化が進む中、解体需要の拡大に対応するための戦略的買収といえます。
解体業界では、都市再開発やインフラの再構築に伴い、大規模解体のニーズが高まっており、本件は市場の変化に対応した成長戦略の一環といえます。
【出典】株式会社カシワバラ・コーポレーション「大型物件の解体事業を展開する『株式会社小椋組』全株式取得による完全子会社化に関するお知らせ」
株式会社コンセックによる株式会社丸金建設のM&A
株式会社コンセックは、岡山県倉敷市の建設会社「株式会社丸金建設」の全株式を取得し、2023年10月2日付で完全子会社化します。本件は、工事部門の強化と地域密着型事業の拡大を目的としたM&Aです。
コンセックは、建設・土木工事向けの製品開発や施工を手掛ける企業で、「メーカー部門」「工事部門」「商社部門」の三位一体体制を構築。一方、丸金建設は、公共工事を中心に土木工事・舗装工事・解体工事を展開し、地域に根ざした信頼性の高い事業を展開しています。
本M&Aにより、コンセックは工事部門を強化し、グループ内での技術交流や相互支援体制を強化。また、地域密着型の丸金建設を傘下に加えることで、より安定した事業基盤を確立します。
建設業界では、インフラの老朽化対策や再開発の進行に伴い、M&Aを活用した事業規模拡大が進んでおり、本件はその一環といえます。
【出典】株式会社コンセック「株式会社丸金建設の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」
特種東海製紙株式会社による株式会社駿河サービス工業のM&A
特種東海製紙株式会社は、静岡県の廃棄物処理・解体業者「株式会社駿河サービス工業」の全株式を取得し、2020年1月17日付で完全子会社化しました。本件は、環境関連事業の強化と資源循環型ビジネスの拡大を目的としたM&Aです。
特種東海製紙は、中期経営計画において**「環境関連事業」の収益化を戦略の一環と位置づけており、既存の「特殊素材」「産業素材」「生活商品」に次ぐ第4の基幹事業として環境事業を推進**。本件により、廃棄物処理のノウハウを持つ駿河サービス工業と協業し、資源再活用ビジネスの強化を図ります。
駿河サービス工業は、静岡県東部・神奈川県西部を中心に木質系廃棄物の処理を手掛け、安定した業績を確立。本M&Aにより、リソースの相互活用やグループ内廃棄物の再資源化を進め、持続可能な循環型社会の実現を目指します。
廃棄物処理業界では、環境規制の強化や再資源化のニーズ拡大に伴い、M&Aを通じた事業強化が進んでおり、本件はその一例といえます。
【出典】特種東海製紙株式会社「株式会社駿河サービス工業の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
まとめ|解体工事業界のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
解体工事業界では人材不足や産業処理場不足など、さまざまな課題が噴出しています。M&Aは企業の持つ問題を解消し、経営基盤安定や成長につなげる一歩となるでしょう。
また、M&Aを成功させるためには業界内の動向を把握することも欠かせません。M&A仲介会社へ相談し、適切なアドバイスをもらいましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















