CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
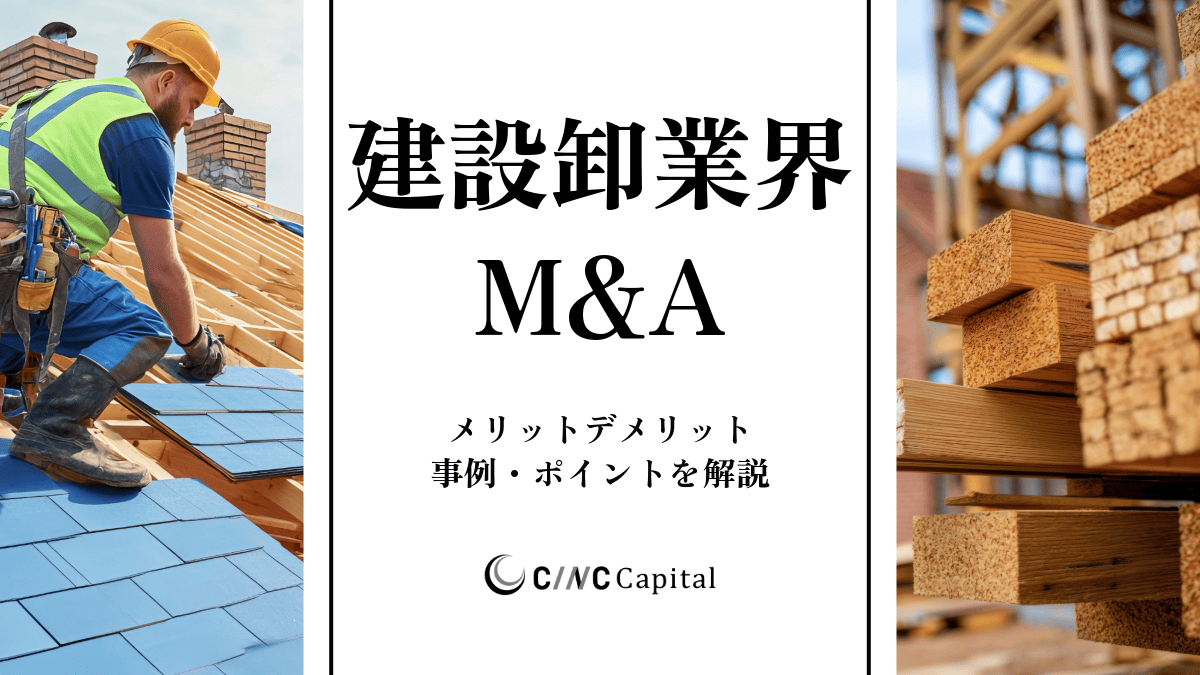
業種
- 最終更新日2025.06.26
建材卸業界のM&A動向(2025年)メリット/事例/成功のポイントを解説
建材卸売業界では、原材料価格の高騰や物流コストの上昇、人手不足などの課題が深刻化しています。そんななか、経営の安定や成長戦略の一環としてM&A(企業の合併・買収)を選択肢とする企業が見られます。地域密着型の建材卸企業が大手資本の傘下に入ることで、仕入れコストの削減や物流網の強化を実現し、競争力を高めるケースもあるようです。
また、後継者不在による会社譲渡や、異業種との提携による新市場開拓といった案件事例もあります。本記事では、2025年の最新M&A動向や建材卸業界特有のメリット、成功のポイントを解説します。
目次
建材卸業界の市場動向
建材卸業界は、新築住宅の着工数減少や人口減少の影響を受けながらも、リフォーム需要や環境配慮型建材の普及によって変化を遂げています。2024年度の住宅設備・建材市場は約4兆429億円に達すると予測されており、省エネ性能を重視した高価格商品の成長が市場を支えているといえるでしょう。しかし、2040年度には人口減少や新築住宅着工数の減少を背景に、市場規模は3兆9804億円に縮小すると見込まれています。
一方で、鉄鋼や軽量コンクリートなどの建材在庫が増加している状況です。この背景には、人手不足や建築費の高騰による工事の遅延があり、建材卸業界にとっては取引先の工事スケジュールが不透明になるリスクが生じています。
建材市場の動向をみると、住宅建材市場は縮小傾向です。建材卸業界は、納入先である建設会社やハウスメーカー、工務店の需要に大きく依存しており、新築住宅の着工数減少が売上に影響を与えています。一方、非住宅向けの建材市場では、商業施設や公共インフラ向けの需要が一定数を維持。しかし、オフィスビルの新規着工はテレワークの定着によって伸び悩んでいます。
このような状況のなか、住宅リフォーム市場は堅調に推移しているのが特徴です。矢野経済研究所によると、2023年の住宅リフォーム市場規模は推計で7.4兆円に達すると見られています。2024年は一時的に落ち着く見込みですが、長期的な予想では増加していくと考えられています。
新築住宅市場の縮小に伴い、リフォーム需要が今後も市場を支える要因となるでしょう。また、環境規制の強化やESG・SDGsの推進により、省エネや環境配慮型建材の市場が拡大しています。
【出典】株式会社富士経済「住宅設備・建材市場トレンドデータ便覧2024」
【出典】株式会社矢野経済研究所「住宅リフォーム市場に関する調査を実施(2024年)」
建材卸業界が抱える課題
建材卸業界は、リフォーム需要の増加や環境配慮型建材の普及など成長の可能性がある一方で、複数の課題を抱えています。市場環境の変化に適応し、持続的な成長を目指すため、適切な対応策を講じる必要があります。
住宅新設需要の減少
少子高齢化による人口減少の影響もあり、新築住宅の着工数は長期的に減少傾向にあります。こういった状況が建材卸事業者の売上にも影響を与えています。一方でリフォーム需要は伸びているため、企業によっては事業の方向性を見直す必要があるでしょう。
建材価格の高騰によるコスト増大
世界的な資材不足や円安の影響で、建材価格の高騰が続いています。ウッドショックの影響で木材価格が大幅に上昇し、コスト負担が増大しました。価格転嫁が難しい中小の建材卸事業者にとっては、経営の圧迫要因となっています。
人材不足と事業承継問題
建築業界全体が継続的に人手不足の状況にあり、建材卸業界にも影響が広がっています。高齢化による経営者の引退が進む中、後継者不足により事業継続が困難になるケースも増加傾向です。こうした課題に対応するため、M&Aを活用して事業基盤を強化する動きが加速すると考えられます。
建材卸業界のM&A最新動向(2025年)
建材卸業界では、市場環境の変化や企業戦略の多様化に伴い、M&Aを選択する企業も見られます。ここでは、2025年における建材卸業界のM&Aの最新動向について、主要なポイントを3つ解説します。
事業規模拡大を目的としたM&A
近年、外装材や内装材など、特定の分野に強みを持つ建材卸業者が補完関係にある企業を買収することで、取り扱い商品の幅を広げる動きが見られます。企業は多様なニーズに応えやすくなり、受注増加や競争力向上につながる点がメリットです。また、全国展開を目指す企業が地方の有力な建材卸業者を買収し、事業エリアを拡大するケースも見られます。
サプライチェーン統合によるM&A
建材卸業者が、建材メーカーや工事業者とM&Aを行い、サプライチェーンを統合する動きもあります。建材の仕入れから販売までのプロセスを一元化し、コスト削減や品質管理の強化を図ることが可能になるためです。特に木材や金属材の調達に関わる企業が、安定した供給を確保するためにM&Aを進めるケースがあります。こうした動きは、長期的な経営の安定化にも寄与しています。
後継者不足や経営課題の解決を目的としたM&A
中小規模の建材卸業者では、後継者不足や経営の不安定さを理由にM&Aを活用するケースがあります。資金力のある大手企業や同業者へ事業を譲渡することで、事業の継続が可能となり、従業員の雇用も維持しやすくなる点が魅力です。地方の建材卸業者が大手グループの傘下に入ることで、経営基盤の安定化を図るケースも確認されています。
建材卸業界でM&Aを活用して売却するメリット
建材卸業界におけるM&Aの売却メリットは、一般的なM&Aの利点だけでなく、業界特有の事情を考慮することが重要です。以下では、建材卸業界ならではの売却メリットについて解説します。
事業の安定化と成長機会の拡大
建材卸業は、市況の変動によって経営が不安定になりやすい業界です。大手企業への売却により、資本力や仕入れルートの拡充が可能になり、安定した事業運営が実現できます。また、販路の拡大によって新規顧客の獲得や売上向上も期待できます。
従業員の雇用継続と働きやすい環境の提供
中小規模の建材卸会社では、経営難によるリストラや廃業のリスクがつきまといます。M&Aによる売却により、従業員の雇用を維持できるだけでなく、福利厚生の向上やキャリアアップの機会も提供できるでしょう。買い手企業のもとでより安定した環境が整えば、従業員のモチベーション向上にもつながります。
サプライチェーンの強化とコスト削減
建材卸業では、メーカーや施工業者との関係が重要です。M&Aによって買い手企業のサプライチェーンに組み込まれることで、仕入れコストの削減や物流の効率化が可能になります。メーカーと一体化することで、より安定した仕入れと価格競争力の向上が図れます。
後継者不在の問題解決
建材卸業は家族経営の企業が多く、後継者不在の問題に直面するケースが増えています。M&Aを活用すれば、後継者がいなくても事業を存続させることが可能です。同業他社や関連企業に売却することで事業の継続性が確保され、顧客や取引先との関係も維持しやすくなります。
建材卸業がM&Aで売却を成功させるためのポイント
建材卸業のM&Aを成功させるためには、業界特有の事情を踏まえた準備や戦略が必要です。ここでは、M&Aを円滑に進め、より良い条件で売却を実現するためのポイントを解説します。
早期準備と戦略的な売却計画
M&Aは短期間で完了するものではなく、交渉や手続きに時間がかかるため、計画的に準備を進めることが重要です。とくに建材卸業は在庫管理や取引先との関係が複雑であり、適切な売却時期を見極める必要があります。経営が安定しているうちに売却準備を進めることで、より良い条件でのM&Aが実現しやすくなります。
事業の強みと成長性の明確化
建材卸業のM&Aでは、事業の強みや成長性を明確にし、買い手に魅力を伝えることが重要です。取り扱い商品の特徴や市場の成長性、独自の仕入れルート、安定した顧客基盤などを整理し、売却価値を高める工夫が求められます。環境対応型の建材を扱っていたり、特定の地域で強いネットワークを持っていたりする場合は、それがアピール材料となり、買い手の関心を引きやすくなるでしょう。
財務状況と在庫管理の整理
建材卸業は在庫管理が経営に大きな影響を与えます。M&Aに向けて財務状況を整理し、在庫の適正化を進めることが重要です。買い手が財務デューデリジェンスを行う際に、不良在庫や未回収債権が多いと評価が低くなってしまう可能性があるため、事前に改善しておくと良いでしょう。
適切な買い手の選定
建材卸業のM&Aでは、買い手の選定が成功の鍵を握ります。建材の種類や販売先によって得意とする分野が異なるため、自社の事業と相性の良い買い手を選ぶことが重要です。例えば、異なる建材を扱う企業と統合することで取り扱い商材を増やし、事業の成長を加速させることができます。また、既存の取引先や従業員の雇用が継続されるかも重要な判断基準となります。
正しい企業価値評価手法の理解
建材卸業のM&Aを成功に導くためには、自社の価値がどのように算出されるかを正確に把握しておく必要があります。特に中小規模の企業においては、「時価純資産+営業権法(基礎価額法)」や「マルチプル法(類似業種比準法)」が代表的な評価手法として用いられています。
「時価純資産+営業権法」では、倉庫や配送設備などの資産に加え、営業権(のれん)も含めて企業価値が算出されます。建材卸業では在庫の比重が大きいため、在庫の実質的な価値をどれだけ正確に評価できるかが、査定結果に大きく影響します。
一方の「マルチプル法」は、「EBITDA(利払前・税引前・償却前利益)」に業界平均の倍率をかけて価値を見積もる方法です。建材卸業の場合、業界の特性や規模によって適用される倍率は変動します。どの手法が用いられるかを事前に理解し、査定に備えた資料の整備を進めることが、納得感のあるM&Aにつながるでしょう。
専門家の活用とスムーズな交渉
M&Aを成功させるためには、M&A仲介会社などの専門家を活用することが有効です。建材卸業は業界特有の商習慣があるため、専門家の知見を活かすことで、交渉をスムーズに進められます。また、契約内容やリスクの確認も専門家とともに行うことで、売却後のトラブルを防ぐことができます。
建材卸業界のM&A事例
最後に、建材卸業界のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
丸紅建材リース株式会社による竹本基礎工事株式会社のM&A
2025年2月、丸紅建材リース株式会社は、基礎工事を手がける竹本基礎工事株式会社(兵庫県尼崎市)の全株式を取得し、子会社化することを決定しました。
丸紅建材リースは、仮設鋼材のリース・販売・工事を主力とする企業で、社会インフラの整備に貢献しています。竹本基礎工事は、場所打ち杭工法「スーパートップ工法」などを用いた基礎工事に強みを持ち、高速道路や橋梁整備などで多数の実績があります。
本件M&Aは、双方の技術や工事機械、ノウハウの相互活用を通じて、収益力とサービス提供価値の向上を図る戦略的提携です。建設業界では、施工力や機材・技術力の補完を目的としたM&Aが活発化しており、本件も中長期的な企業価値の向上と持続可能な社会づくりを見据えた取り組みといえます。
【出典】丸紅建材リース株式会社「竹本基礎工事株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
ナイス株式会社によるセレックスホールディングス株式会社のM&A
2024年10月、ナイス株式会社は、住宅用サッシやエクステリアを中心に事業展開するセレックスホールディングス株式会社の株式を取得し、議決権ベースで85.5%を保有する子会社化を行いました。
セレックスは中京圏を中心に、高性能サッシの施工力を武器に業容を拡大してきた企業で、住宅性能の向上が求められる今後の市場ニーズに適応する強みを持ちます。
本件M&Aは、ナイスが展開する木材・建材・住宅設備機器に加え、サッシ・エクステリア分野まで商材を拡充することで、1棟あたりの納材シェアを高め、地域における存在感を強化する狙いがあります。
2025年の省エネ基準適合義務化を背景に、省エネルギー性能の高い住宅関連商材を一体的に提供する体制を整える戦略的な動きであり、脱炭素社会への貢献も期待されています。住宅建材業界における製販一体化の流れを象徴するM&A事例です。
【出典】ナイス株式会社「セレックスホールディングス株式会社の株式の取得に関するお知らせ」
JKホールディングス株式会社による太平洋建材株式会社のM&A
2024年5月、建材卸売大手のJKホールディングス株式会社は、大阪を拠点に内装材・外装材の販売を手がける太平洋建材株式会社の全株式を取得し、子会社化することを発表しました。
太平洋建材は、関西圏において堅実な営業基盤を持ち、直近では売上高4,370百万円、当期純利益116百万円と安定した成長を見せています。
本件M&Aにより、JKホールディングスは関西地区での販路拡大とともに、内装建材分野への事業領域の拡充を図る方針です。これによりグループ全体としての商材提供力と地域対応力の強化が期待されます。
建材業界では、エリア戦略と製品ポートフォリオの最適化を目指したM&Aが活発化しており、本件もその一環として注目される事例です。
【出典】JKホールディングス株式会社「太平洋建材株式会社の取得(子会社化)に関するお知らせ」
まとめ|建材卸業界のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
建材卸業界のM&Aを成功させるためには、成約に至るまでの準備が重要です。自社の強みを明確にし、適切な買い手を見極めることに加え、在庫管理や財務状況の整理も行っておきましょう。
また、M&Aには専門的な知識が必要なため、早い段階で専門家へ相談し、適切な支援を受けましょう。建材卸業界のM&Aは、事業の成長や承継の手段として有効な選択肢の一つです。業界の動向を把握しながら戦略を立て、M&Aを成功に導きましょう。
CINC Capitalでは、建材卸業界に詳しい専門チームが、オーナー様の想いを尊重しながらM&Aをお手伝いしています。業界特有の商習慣や在庫管理に関する豊富な知識を活かし、最適な買い手とのマッチングを提案いたします。

















