CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
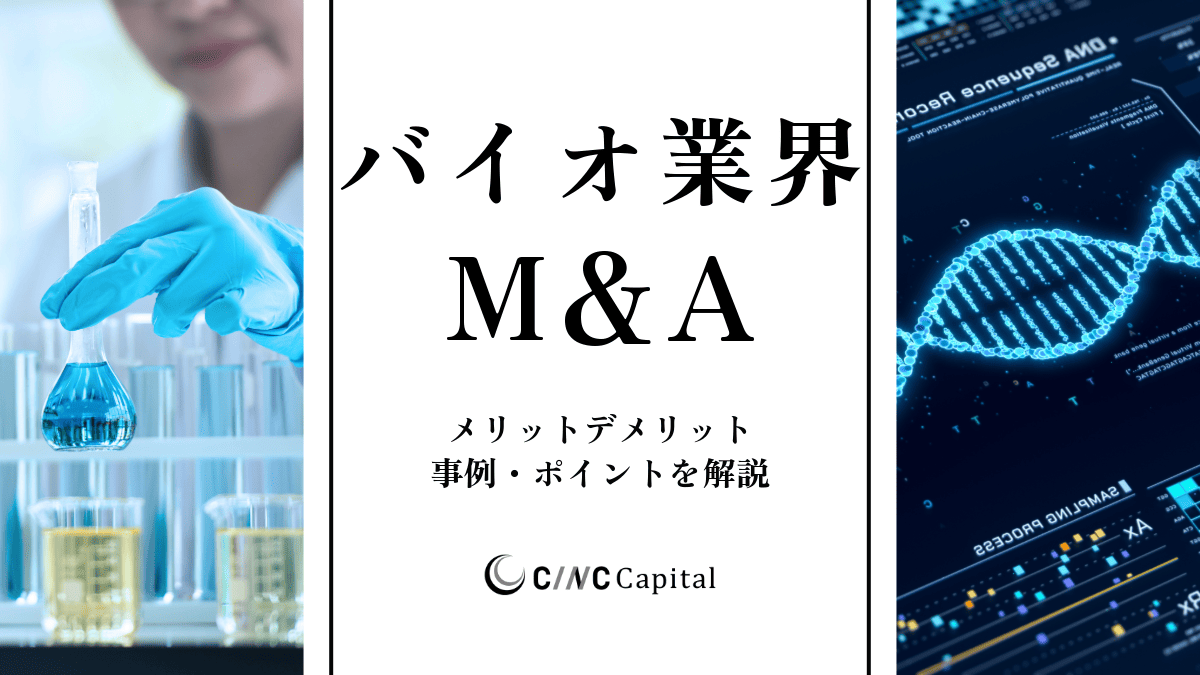
業種
- 最終更新日2025.06.26
バイオ業界のM&A動向(2025年)メリット/事例/成功のポイントを解説
近年、バイオ業界では技術革新が進み、医薬品やバイオテクノロジーの分野で新たな市場が次々と生まれています。しかし、研究開発には多くの資金と時間が必要であり、業界内で競争が激化している状況です。
こうした環境のなかで、M&A(企業の合併・買収)が重要な戦略として注目されています。
本記事では、バイオ業界におけるM&Aの最新動向や成功のポイント、具体的な事例を解説します。
目次
バイオ業界の市場動向
バイオ業界は、医薬品・農業・食品・環境技術など幅広い分野で発展を続けており、世界的に市場規模の拡大が予測されています。
経済産業省が2023年5月に発表した「バイオ政策の進展と今後の課題について」の資料では、バイオ・医薬品製造業界が国内外で大きく成長している現状が伺えます。なかでも注目が高まるバイオエコノミーの分野では、2030年から2040年にかけて世界市場が200兆円から400兆円に達すると試算されています。
海外では、米国や中国を中心に巨額の投資が行われており、各国が産業政策を通じてバイオ関連企業を国内に誘致する動きが活発化している状況です。日本国内でも、バイオ技術を活用した脱炭素社会の実現(GX)が重要視されており、官民を挙げての投資が進められています。
また、医薬品開発を主軸とする創薬ベンチャーは、資金調達や事業規模の拡大を目的としたM&Aが推進されている分野の一つです。政府のスタートアップ支援施策による後押しもあり、バイオ業界全体でM&Aが活発に行われています。
【出典】経済産業省「令和5年 バイオ政策の進展と今後の課題について」
バイオ業界が抱える課題
バイオ業界は市場規模の拡大が予測される一方で、解決すべき課題も多く存在しています。ここでは、バイオ業界が直面する主な課題について解説します。
特許切れリスクと競争の激化
バイオ医薬品は特許の有効期間が限られており、特許が切れると後発のバイオシミラー(バイオ後続品)が市場に参入し、価格競争が激しくなります。先行企業の収益が大きく減少するリスクがあるため、M&Aを活用して新しい技術や特許を獲得し、市場での優位性を維持しようと努める企業も見受けられます。
規制の厳格化と承認プロセスの長期化
バイオ医薬品やバイオ技術を活用した製品は、安全性や有効性の審査が厳しく、各国の規制をクリアするためには長い開発期間と多額の費用が必要です。特に日本では、海外に比べて承認プロセスが長く、国内市場への新規参入が遅れるケースもあります。
高額な研究開発費と資金調達の課題
バイオ業界では、新薬や新技術の開発に莫大な資金が必要です。特にスタートアップ企業や創薬ベンチャーは、研究開発費の負担が重く、資金調達が大きな課題となっています。こうした状況のなかで、大手企業がM&Aを通じて資金を提供し、技術革新を支援するケースが見られます。
バイオ業界のM&A最新動向(2025年)
バイオ業界はM&Aが一定の注目を集めている分野であり、2025年以降も大きな動きが起こる可能性があります。ここでは、バイオ業界における最新のM&A動向を解説します。
先端技術の獲得と競争への対応
最先端の技術分野である「バイオ医薬品」「ゲノム編集」「細胞・遺伝子治療」などでは、企業間の競争が見られます。これらの技術を持つ企業の買収が、競争力を高めるために重要な戦略となっている状況です。近年では、遺伝子治療やがん免疫治療といった分野において、次世代の治療法を早期に導入するために、スタートアップ企業の買収が行われるケースも確認されています。
日本企業によるバイオベンチャーの買収
日本企業がバイオベンチャーを買収し、M&Aを通じた連携を図る動きが見られます。なかでも製薬業界の大手企業が創薬に関連する技術を持つバイオベンチャーに注目しており、関係を築こうとするケースがあるようです。有望な技術や市場のニーズを先取りするために、M&Aを検討する企業も存在しています。
規制の変化に対応するための戦略的提携
各国で医薬品やバイオ製品に関する規制が変化するなか、規制にスムーズに対応できる企業との提携や買収が重要になっています。規制が厳しい市場においては、既に規制対応が整った企業を買収することが、事業展開の迅速化やリスクの低減に効果的です。このような規制環境を意識したM&Aが今後ますます活発になることが予想されます。
バイオ業界がM&Aで売却するメリット
バイオ業界におけるM&Aは、売却企業にとってもさまざまなメリットをもたらします。ここでは、売却企業側のメリットについて解説します。
先端技術とイノベーションの提供
バイオ業界では、ゲノム編集・細胞治療・遺伝子治療といった先端技術が急速に発展しています。売り手企業はM&Aを通じて、これらの革新的な技術や研究成果を提供し、買い手企業に新たなイノベーションの可能性を加えられます。技術の移転と相乗効果により、事業の売却後も自社のブランド価値を高められるでしょう。
ポートフォリオの多様化と安定化
売り手企業は自社と異なる技術を持つ企業との統合によってポートフォリオの多様化を図れます。特定の治療法や市場に依存しない安定した収益基盤を確立することが可能です。また、買い手企業の子会社として事業が継続される場合、売却した事業の価値が維持され、次の成長ステージへと繋がる可能性も高まります。
事業承継と円滑な移行
中小規模のバイオ企業にとって、事業承継は大きな課題です。M&Aを行うことで事業の経営権をスムーズに移行し、企業の継続性を保てます。特に、バイオ業界の事業では専門知識と技術が必須なため、信頼できる買い手企業へ譲渡は、事業承継の重要な手段の一つとなるでしょう。
バイオ業界がM&Aで売却を成功させるためのポイント
バイオ業界でM&Aを成功へ導くには、業界の規制や高度な技術の承継といった背景があるため、特別な注意を要します。ここでは、バイオ業界におけるM&A成功のための重要なポイントを解説します。
規制対応力を明確に示す
自社の規制対応力を明確に示すためにも、買い手側からの調査へ向けて抜かりなく準備をしておきましょう。バイオ業界では医療や製薬に関する厳しい規制があり、万が一規制対応に不備があると事業に大きな影響を与えるリスクがあります。そのため、M&Aでは買い手側から承認状況や過去の規制実績を詳細に調査される可能性があります。
技術・研究者チームの統合
売り手・買い手の双方が、異なる技術や知識を持つ研究者同士の連携を促進し、新しい治療法や技術の開発を進められる体制を整備することが重要です。バイオ業界では、研究開発部門が企業の競争力に直結します。M&A後の研究開発チームや技術者の統合が成否を左右します。買い手側との企業文化の違いや作業方針の調整を上手く進めるためにも、専門家による支援が欠かせません。
臨床データの質と量
M&Aの交渉を進めるにあたり、買い手企業から求められる臨床データの質と量を十分に確保することが不可欠となります。買い手企業へ治療薬や医療技術の有効性を証明するためには、質の高い臨床データが必要です。データが十分でない場合や信頼性に欠ける場合は、買い手企業から評価を得られず、M&Aの成功が難しくなるでしょう。
M&A戦略の明確化
バイオ業界特有の事情を踏まえながら、早期にM&A戦略を策定し、事業の方向性やブランド戦略を明確にしておくことが重要です。M&A戦略が曖昧な場合は、自社の価値が適切に評価されずに希望価格での売却を実現できなかったり、適切な買い手が見つからなかったりするおそれがあります。その際は、バイオ業界の実績を有する信頼できる専門家に相談して、買い手とのマッチングから交渉をスムーズに進めましょう。
バイオ業界のM&A事例
最後に、バイオ業界のM&A事例をご紹介します。自社のM&A検討時の参考にしてみましょう。
株式会社サイトリ細胞研究所によるホテル金沢株式会社のM&A
株式会社サイトリ細胞研究所は、2024年3月、連結子会社である株式会社ホテル金沢の全株式をサムティホテルマネジメント株式会社へ譲渡し、同社を連結子会社から除外しました。
サイトリグループはリアルアセット事業からメディカル事業への事業転換を進めており、本件もその一環となります。譲渡先のサムティホテルマネジメントはホテル運営事業に強みを持ち、今後の運営力強化が期待されます。
ホテル金沢は引き続き地域の宿泊ニーズに応える体制を維持していく見込みです。
【出典】株式会社サイトリ細胞研究所「連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ」
株式会社免疫生物研究所による株式会社AIBioのM&A
株式会社免疫生物研究所は、2023年3月、連結持分法適用会社であった株式会社AIBioを子会社化しました。
AIBioは、韓国のAbcontek社との合弁企業として設立され、ダニ媒介性感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」向け治療用抗体医薬品候補の開発を進めていましたが、Abcontek社が資金負担困難となったことを受け、免疫生物研究所が実質的支配権を取得しました。
子会社化により意思決定の迅速化を図り、早期導出に向けた体制強化が期待されています。
【出典】株式会社免疫生物研究所「連結持分法適用会社株式会社AIBioの子会社化に関するお知らせ」
JNC株式会社による株式会社ニッポンジーンのM&A
JNC株式会社は、2020年10月、動物用診断薬事業を株式会社ニッポンジーンに譲渡しました。対象となったのは「豚コレラエライザキットⅡ」や「牛白血病エライザキット」など4種類の動物用体外診断用医薬品で、2001年から展開されてきた実績ある製品群です。
譲渡後、在庫がなくなり次第ニッポンジーン製品への切り替えが進められています。事業の選択と集中を進めるJNCと、診断薬事業を強化するニッポンジーン双方にとって戦略的な動きとなりました。
【出典】JNC株式会社「動物用診断薬事業の譲渡についてのお知らせ」
まとめ|バイオ業界のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
バイオ業界では、革新的な技術の進展や市場競争の激化により、M&Aが重要な成長戦略の一つとなっています。バイオ業界で事業を売却するなら、業界の特性を理解し、適切な戦略をもってM&Aを実施することが大切です。
最新の業界動向や成功のためのポイントを押さえて、計画的にM&Aを進めましょう。その際は、バイオ業界に強みを持つM&A仲介会社などの専門家から支援を受けるようおすすめします。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















