CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
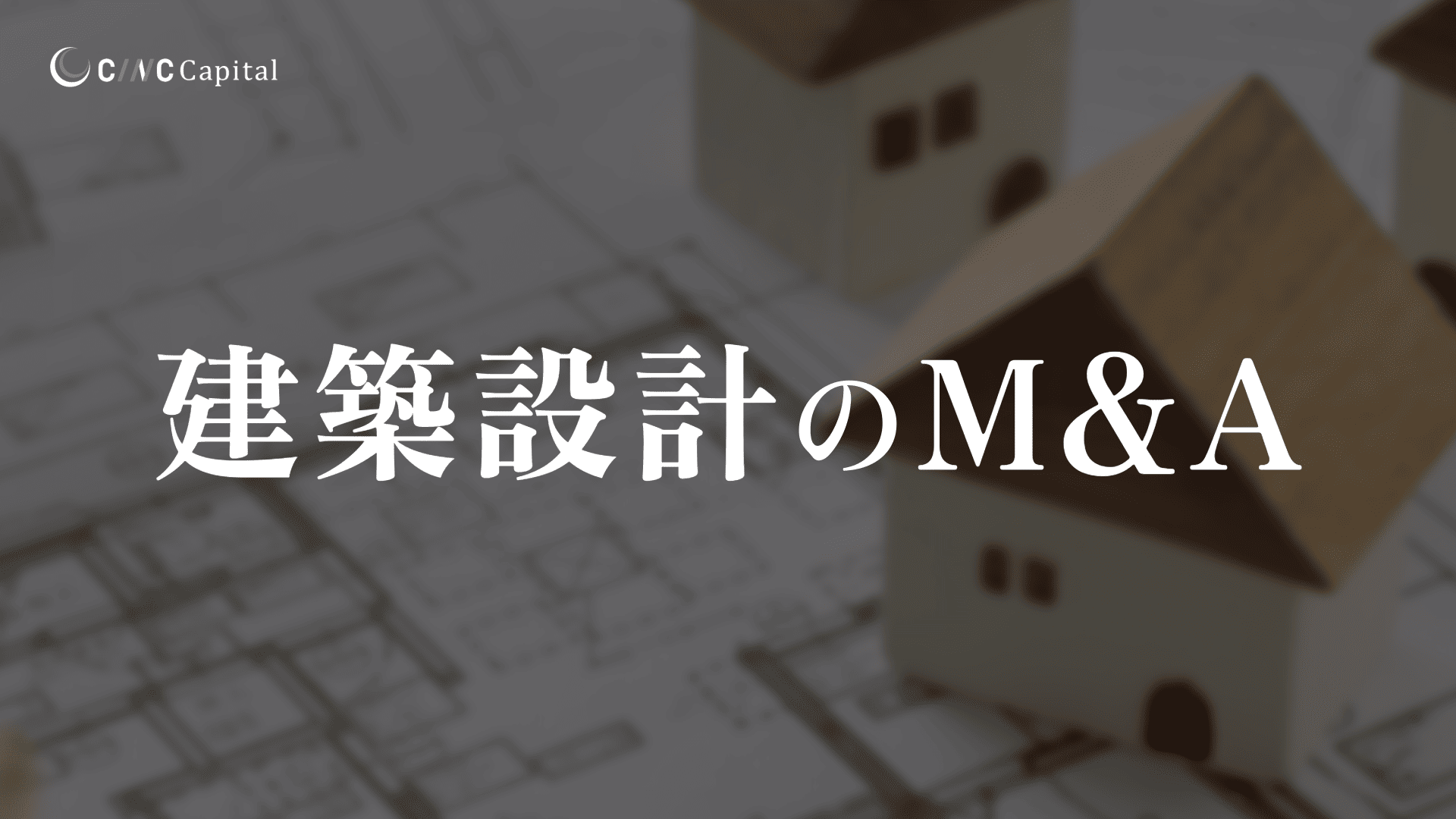
業種
- 最終更新日2025.06.26
建築設計業界のM&A動向(2025年)メリット/事例/成功のポイントを解説
建築設計業界では、近年M&Aの動きが活発化しています。業務の専門性が非常に高い一方で、慢性的な人材不足で建築士をはじめとした資格者の確保が難しいという課題に直面している状況です。小規模な設計事務所を中心として、M&Aを活用した事業承継が注目されています。
本記事では、経営者がM&Aを検討する際のメリットやデメリット、成功事例を解説します。仲介会社や専門家に相談を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
建築設計業界の市場動向
建築設計業界は、国内建設市場全体の一部を構成する重要な業界であり、住宅・オフィス・工場・物流倉庫・内装リフォームなど幅広い分野に関わっています。「矢野経済研究所」が公表する調査結果によると、2023年度における国内建設市場全体の規模は、工事費予定額ベースで24兆2,989億円(前年比4.8%増)と拡大傾向にあります。なかでも、物流倉庫や工場の需要が市場を牽引している状況です。
ただし、現状は建築資材価格や人件費の上昇が進行しており、建設費の高騰が業界全体に影響を与えています。「ウッドショック(=木材の価格高騰)」や「アイアンショック(=鉄の価格高騰)」といった資材価格の高騰はその一例です。
このような状況下で、床面積の縮小や建設計画の見直し、効率的な設計や資材の活用などが求められています。また、近年はSDGsやカーボンニュートラルの推進により、環境負荷の低減を目的とした設計への需要が高まっているのもポイントです。
建築設計業界では、これらの市場動向を踏まえた上で、効率的な設計プロセスや事業の最適化を図ることが、成長力や競争力につながると考えられています。経営者にとっては、M&Aを活用した経営戦略が重要となるでしょう。
【出典】株式会社矢野経済研究所「国内建設8大市場に関する調査を実施(2025年)」
建築設計業界が抱える課題
建築設計業界は市場が成長を続けながらも、その一方でさまざまな課題に直面しています。以下では、業界が抱える主な課題について解説します。
日本経済の停滞と市場への影響
建築設計業界における市場の動向は、日本経済の状況に大きく影響されます。特にオフィスビルや商業施設などの開発を中心としたビジネス向け市場では、経済成長の停滞が業界全体の需要に影響を及ぼすといえるでしょう。近年は長期的な経済停滞や企業の投資抑制の傾向により、新規プロジェクトが減少傾向にあります。
人口減少による住宅需要の減少
少子高齢化にともなう人口減少は、住宅市場において深刻な影響を与えています。新築住宅の需要が減少する中で、建築設計業界は戸建て住宅や集合住宅の設計依頼が減少傾向にあります。家庭向け市場の縮小が、業界全体の成長にも少なからず影響を与えている状況です。
慢性的な人材不足
設計業務では高度な専門性とクリエイティビティを求められるため、経験豊富な設計者の確保が困難な傾向にあります。なかでも中小規模の設計事務所では後継者不足が顕著となっており、人材不足で企業の存続が危ぶまれるケースも多くなっています。
資材価格の高騰と経営への影響
建築資材の価格が急騰していることも重要な課題の一つです。例えば、木材の価格高騰は「ウッドショック」として知られています。
ウッドショックは新型コロナウイルス感染拡大の影響や、国際的な供給網の混乱、ロシア・ウクライナ情勢などの要因によって発生しました。資材高騰は建築設計のコスト増加につながり、多くの設計事務所の経営を圧迫しています。
建築設計業界のM&A最新動向(2025年)
建築設計業界は、都市開発や再開発の需要が高まる中で、M&Aが注目されています。ここでは、建築設計業界における主要なM&Aの動向を見てみましょう。
大手企業による中小設計事務所の買収が増加
建築設計業界では、大手企業が中小規模の設計事務所を買収する動きが見られます。その背景には、都市部での再開発需要の増加があり、設計スキルを有する専門家を確保する必要性が高まっていることが挙げられます。
事業継承を目的としたM&Aが目立つ
建築設計業界には少人数で経営する設計事務所が多く、業界全体で後継者不足が課題となっています。特に技術者不足が深刻な中小事務所においては、事業を継続するためにM&Aでの売却を選択するケースが目立っている状況です。
建築設計会社がM&Aをするメリット
ここでは、建築設計会社がM&Aをするメリットを売り手側の視点からご紹介します。
優秀な人材の雇用を継続できる
建設業界では慢性的な人材不足が続いており、有資格者や専門的なスキルを持つ人材の需要が高い傾向にあります。大規模プロジェクトや特殊な設計案件にも対応できる即戦力を有する企業は、買い手から高く評価される傾向にあります。
M&Aで事業を売却することで、設計実績が価値化され、自社が確保した優秀な人材の雇用を継続できる可能性が高まるのがメリットです。
シナジー効果が期待できる
M&Aでは、売り手側・買い手の強みを融合させることで、双方の事業でシナジー効果を発揮できる可能性があります。売却した事業は、元の経営者の手を離れた後で技術やノウハウを活かすことができ、市場での競争力向上に貢献できるかもしれません。
こうしたシナジー効果が期待される場合、事業の評価が高まることがあります。
経営基盤の安定化
多くの中小規模の建築設計会社では、経営の不安定さが課題となります。M&Aによって大手建築設計会社の傘下に入ることで、資金調達や設備投資による経営基盤の安定化が期待できるでしょう。
プロジェクト継続性を確保し、既存の顧客との信頼関係を引き継ぎながら、売却後の事業が長期的に成長できる可能性があります。
建築設計会社がM&Aを成功させるためのポイント
建築設計会社のM&Aを成功させるには、業界の課題を踏まえた戦略が重要となります。ここでは、建築設計会社がM&Aを成功させるためのポイントを売り手側の視点で解説します。
事前準備を徹底する
建築設計会社がM&Aを進めるには、入念な準備を行うことが重要です。例えば、自社の財務状況や取引先との関係性などを整理する必要があります。
ほかにも、建築士など資格者の人数や、重要なプロジェクトの件数を確認し、業界特有の資産評価を行うことも重要なポイントだといえます。準備が不十分だと交渉が滞りやすくなるため、計画的に取り組むと良いでしょう。
有資格者の確保と引き継ぎ計画
建築設計会社の評価において、建築士など有資格者の在籍状況が大きなポイントとなります。買い手企業にとっては買収によって有資格者を確保できることが大きな魅力となるため、売り手側では資格者の退職を防ぐ対策に取り組み、計画的に引き継ぎを行いましょう。引き継ぎ後の安定した事業運営に協力することが大切です。
専門家のサポートを活用する
建築設計業界の特性を十分に理解し、かつM&Aに精通した専門家のサポートを受けることで、取引をスムーズに進められます。
例えばデューデリジェンスの段階では、「建築士の資格保有状況」「進行中プロジェクトの承継性」「設計図面の著作権」「過去の設計責任」「建築確認申請の履歴」などを詳細にチェックする必要があります。
そんなとき業界特化型のM&A仲介会社なら、建築設計業界における売却に精通しているのが魅力です。適切な相手先の選定、デューデリジェンス、買い手企業との交渉までM&Aプロセスにおける手厚いサポートが期待できるでしょう。建築設計業界で事業の売却を検討されるなら、M&A仲介会社へご相談ください。
建築設計業界のM&A事例
株式会社オープンハウスグループによる株式会社三栄建築設計のM&A
2023年8月16日、オープンハウスグループは三栄建築設計の完全子会社化を目的とした**公開買付け(TOB)**を発表しました。三栄建築設計は、過去の経営陣の問題により信用が低下し、金融機関の融資制限など経営環境が悪化していました。これを受け、大株主である創業者が株式売却を決断し、オープンハウスグループが取得する形となりました。
オープンハウスグループは、三栄建築設計のデザイン性の高い戸建住宅や販売力を活用し、商品ラインナップの拡充やシナジー効果を期待しています。また、資材調達コストの削減や関西エリアでの事業強化も見込まれます。今後、三栄建築設計は非公開化され、グループの信用力を活かし経営の安定化を図る方針です。
【出典】株式会社オープンハウスグループ「株式会社三栄建築設計株式(証券コード:3228)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
ERIホールディングス株式会社による国土工営コンサルタンツ株式会社のM&A
2024年5月21日、ERIホールディングスは、大阪の建設コンサルタント会社である国土工営コンサルタンツ(KEC)の全株式を取得し、子会社化する基本合意書を締結しました。
KECは1967年の創業以来、橋梁などの設計・点検調査や補修・補強設計を手がけ、近年はBIM/CIMモデリング事業にも注力しています。今回のM&Aにより、ERIホールディングスは関西地域での土木インフラ関連事業を強化し、グループ内でのBIM/CIM活用を促進する狙いです。
これにより、ERIホールディングスは3社目の建設コンサルタント会社を取得し、地域の公共事業にさらに貢献する体制を整えることになります。株式譲渡は2024年6月中を予定しており、今期の業績への影響は軽微とされています。
【出典】ERIホールディングス株式会社「株式取得(子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ」
株式会社守谷商会による未来ネットワーク株式会社のM&A
2024年11月8日、守谷商会は未来ネットワーク株式会社の全株式を取得し、完全子会社化することを決定しました。
守谷商会は長野県を主要拠点に総合建設業を展開しており、今回のM&Aにより、新たな商品ラインアップを追加し、顧客ニーズの多様化に対応する狙いです。未来ネットワークはユニットハウスの製造・設計・コンサルティングを手掛け、特に仮設建築やモジュール建築の分野で強みを持ちます。
これにより、守谷商会はプレハブ・ユニットハウス事業を強化し、建築市場の変化に対応する競争力を高めることが期待されます。株式取得は即日完了し、今期の業績への影響は軽微とされています。
【出典】株式会社守谷商会「未来ネットワーク株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」
まとめ|建築設計業界のM&A動向を押さえてM&Aを成功させましょう
建築設計業界では、事務所の後継者不足などを理由に、M&Aで事業を売却する戦略が注目を集めています。事業を売却するには、自社の財務状況を整理したり、既存の資格者の雇用を維持したり、相手先と契約条件を調整したりする必要があります。
入念な準備と適切な戦略が欠かせません。こうした場面では、建築設計業界に詳しい専門家のサポートを活用することで、スムーズな交渉とリスク管理が可能となります。
これから建築設計業界でのM&Aを検討している経営者の方は、業界の最新動向を押さえた上で、自社に合った戦略を立てることが重要です。専門家に相談しながら計画を進めて、課題解決につながるM&Aを実現させましょう。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、M&Aのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















