CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
CINC CapitalはCINC(証券コード:4378)のグループ会社です。
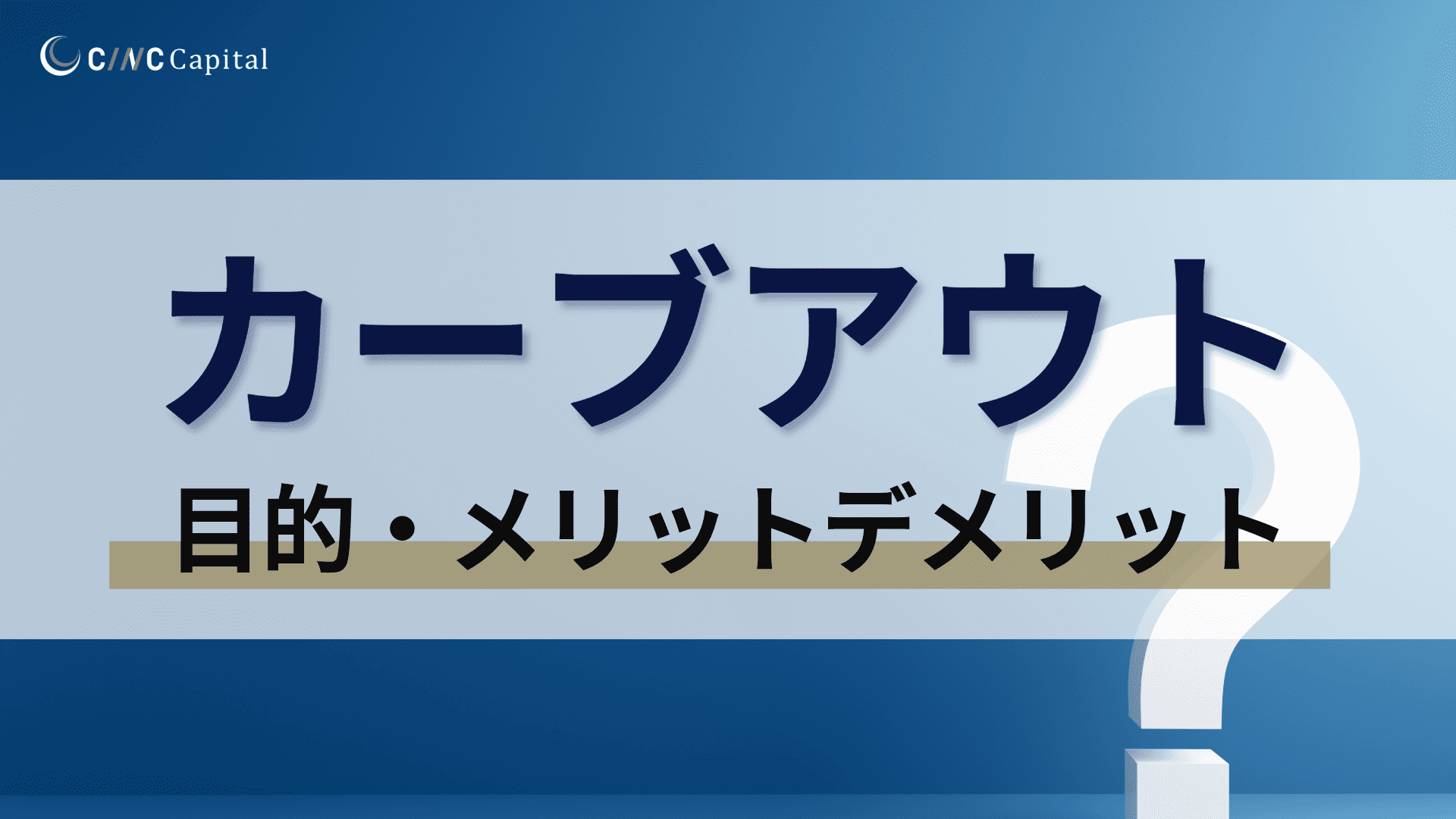
M&A / スキーム
- 最終更新日2025.06.26
カーブアウトとは?目的やメリット・デメリット、スピンオフやスピンアウトとの違いも解説
カーブアウトとは、企業が事業の一部を切り出して新会社として独立させる手法を指します。新たに設立された会社に対して外部資本を入れることで成長を促し、親会社も自社の経営資源を効率的に再分配できる点が特徴です。
本記事では、カーブアウトの基本的な意味や定義に加え、その目的、メリット・デメリット、類似するスピンアウトやスピンオフとの違い、さらには成功事例に至るまでを解説します。
事業ポートフォリオの最適化や新規事業の創出を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
カーブアウトの基本的な意味と定義
まずはカーブアウトという言葉の定義や、ビジネスの現場でどのように捉えられているかを確認しましょう。
カーブアウトは、1990年代から欧米企業を中心に採用されてきた企業再編の手法で、会社分割の一形態として扱われることがあります。親会社が事業の一部を切り離し、新会社を設立することで、双方が独立した形で経営戦略を展開できる点が特徴です。
近年、日本でも大企業による非中核事業の分社化や、新たな成長機会を求めてカーブアウトを活用するケースが増加傾向にあります。これは経済環境の変化が激しくなり、より柔軟に事業を再配置できる仕組みが求められている背景があるためです。
カーブアウトによって誕生した新会社は、親会社のバックアップを受けつつ、外部資本からの出資を受けやすい構造が作りやすいとされています。そのため、新会社が独自の成長機会をつかみやすくなると同時に、親会社もリスクやリソースを適切にコントロールしながら事業ポートフォリオを再構築できます。
ビジネスにおけるカーブアウトの概要
ビジネスの観点では、カーブアウトは企業が保有する事業群の中から特定の部門やサービス領域を切り出し、別法人として独立稼働させる手段です。これによって、本体の経営資源をコア領域に集中させつつも、新会社に外部投資を誘致しやすくする効果が期待できます。
外部からの出資を得ることで、新会社は研究開発や市場拡大に必要な資金を確保しやすくなります。また、親会社のブランドやノウハウを活用できる場合が多く、一定の競争力を保ちながら早期に顧客を獲得できる点もメリットの一つです。
一方で、切り離された事業が十分に独立できるかどうか、事前の検討と経営チームの力量が求められます。新会社が自立せず経営に混乱が生じると、親会社にとっても望ましくない影響が出る可能性があります。
スピンアウトやスピンオフとの違い
カーブアウトとスピンアウト・スピンオフの違いの前に、まずはスピンアウトとスピンオフの定義をおさらいしましょう。
スピンアウトとは
スピンアウトとは、親会社から事業部門や子会社を分離し、親会社が株式の一部または全部を保有し続ける手法のことを指します。スピンアウトでは、親会社が新会社の株式を一定割合保有し続けるため、経営の独立性は高まるものの、資金調達や事業方針の決定には親会社の意向が影響しやすい傾向があります。
スピンオフとは
スピンオフとは、親会社から事業部門を分離・独立させ、その株式を親会社株主に比例配分する手法です。スピンオフでは、親会社が新会社の株式を100%手放し、経営・資本ともに完全独立します。この手法は、上場企業で活用される手法です。
カーブアウトとスピンアウト・スピンオフとの違い
カーブアウトは、外部投資家を積極的に受け入れる形態をとることが多く、新会社の資金調達力や経営母体の多様性を強化しやすい点に強みがあります。これに対してスピンアウトやスピンオフは、親会社からの独立に加え、既存の株主へ新会社の株式を分配する形で利益還元が行われることが一般的です。
いずれの手法も親会社と新会社の経営資源の切り分け方や事業計画の立て方が非常に重要になります。特にカーブアウトにおいては資本関係の再編が絡むため、法務面や財務面の準備を綿密に行う必要があります。
カーブアウトの目的と役割
カーブアウトが行われる背景には、経営戦略や成長戦略に関連する明確な目的があります。
ここでは、主な目的と役割について3つ見ていきましょう。
選択と集中による事業ポートフォリオの最適化
企業が抱える複数の事業の中には、成長余地が大きいものや将来的な収益が見込めるものがある一方で、収益性が低く足かせとなっているものも存在します。選択と集中の観点から、親会社がコア事業にいっそう注力し、不採算または非コア事業を切り離すことで効率的な経営構造を築く効果が期待できます。
このプロセスは単純に不採算事業を切り離すだけでなく、将来性のある事業をより伸ばすためにも活用できます。事業ポートフォリオの見直しは定期的に行われるべきであり、カーブアウトはその再編手段の一つとして位置づけられています。
重要なのは、カーブアウト後に親会社と新会社の間でどのようなシナジーを保てるかです。親会社の知見や技術、ブランド力を活かしつつ、新会社が独自の戦略を展開できる関係構築が成功に直結します。
経営資源の効率的な活用
カーブアウトは、経営資源をコア事業に集中させるだけでなく、新会社側が外部からリソースを得やすい体制を整えられる強みもあります。特に、新会社にとっては独立した経営判断がしやすくなるうえ、出資者を引き入れて研究開発やマーケティングに注力しやすくなるメリットがあります。
一方で、親会社が新会社の経営にどの程度関わるかは事前の取り決め次第です。過度な干渉は新会社の意思決定速度を阻むリスクがありますが、まったく関与しないとシナジーを失う恐れもあります。
最適なバランスを取るためには、事業分割の目的と新会社の成長ビジョンを明確に定義することが重要です。経営資源を適材適所に再配置することで、組織全体としての成果が最大化されます。
新規事業創出や資金調達の促進
カーブアウトの大きな役割として、新たな事業領域の創出や市場拡大を目指す動きが挙げられます。親会社の下では扱いにくかった独自技術や新商品開発を切り離し、新会社として迅速に事業を展開できる利点があります。
また、新会社は親会社だけではなく外部からの出資を受け入れやすくなり、経営者が思い描くビジョンを実現するための多様な資金調達手段を確保できます。スタートアップ投資に積極的なベンチャーキャピタルや事業会社などと連携しやすい点も注目されます。
こうした外部資金の流入によって、新会社は短期間での研究開発強化や人材獲得を実現しやすくなります。結果として、企業グループ全体の成長加速にも寄与すると期待されています。
カーブアウトを行うことで得られるメリット
カーブアウトの実施には、親会社・新会社双方にメリットが存在します。ここでは、主な3つのメリットを見ていきましょう。
親会社のコア事業への集中と成長
親会社は、不採算や戦略的優先度の低い事業を切り離すことで、経営管理の負担を減らしながら主力事業に集中的に投資できるようになります。これにより、企業全体の業績向上やブランド力強化につながる可能性が高まります。
また、カーブアウト後の連携方法によっては、親会社が新会社の成果を活かしながら自社のコア領域に反映させることも可能です。両社の強みを補完し合うことで、市場における競争優位性をさらに高められます。
このようにカーブアウトを通じて得られる経営効率化や成長の加速は、グローバル化が進む現代ビジネスにおいて非常に有効な手段といえます。
外部資金調達による成長機会の拡大
新会社が親会社と資本関係を持ちながらも独立しやすい形態は、投資家にとって魅力的な投資先になります。親会社が保有する知的財産やブランド資産を活用しつつ、自律的な経営方針を打ち出せる点が評価されるためです。
特に欧米では、こうしたカーブアウト企業に対するベンチャーキャピタルやプライベートエクイティファンドの出資事例が数多く見られます。これによって、新会社の成長投資がより積極的に行われることが期待できます。
結果的に、新会社はスピード感を持って拡大しやすく、親会社にもリターンが還元されやすい仕組みが生まれます。投資家・親会社・新会社が三方良しとなる可能性がある点が、外部資金調達の大きなメリットです。
企業価値向上と不採算事業の整理
不採算事業の影響が企業全体の財務指標を圧迫している場合、カーブアウトによる切り離しは企業価値の向上に直結します。投資家目線では、収益性の低い部門が整理されることで企業の魅力が増すと評価されることが少なくありません。
一方で、必ずしも不採算事業だけを切り離すとは限らず、将来的な独立成長を見据えた期待値のある事業を分社化することもあります。こうした場合、長期的なリターンを得るために外部出資者や市場の評価を高めることが重要です。
親会社と新会社がそれぞれの強みに集中できる構造を作ることで、グループ全体の企業価値を底上げし、財務の安定化や事業の持続的成長を実現しやすくなります。
カーブアウトにおけるデメリットや課題
カーブアウトには企業にとって魅力的なメリットがある一方で、リスクや課題も存在します。カーブアウトにおけるデメリットや、その対策について解説します。
外部出資者による干渉のリスク
新会社に外部出資者を迎える際、経営方針や優先順位に影響を与えるリスクが高まります。特に、投資家が短期的な利益にフォーカスする場合、企業の長期的な成長戦略と相反する意見が出ることがあります。
こうした干渉を回避するためには、契約書上で経営方針に関する権限を明確にしておくことや、社外取締役や監査体制を整備しておくことが重要です。透明性の高いコミュニケーションも欠かせません。
また、親会社側も一定の影響力を保つ一方で、新会社の自立性を尊重する仕組みが必要となります。両社の強みを合わせることが、カーブアウトの最大の効果を引き出す鍵と言えます。
従業員モチベーションへの影響
カーブアウトの際には、親会社から新会社へ移籍する従業員が出るため、組織変更による不安が高まることがあります。特に、待遇の変化やキャリア路線の不透明さが離職率上昇につながるリスクも否めません。
これを防ぐためには、新会社が実現するビジョンと成長戦略をしっかりと共有し、従業員の役割やキャリアパスに関する具体的な展望を示すことが重要です。
さらに、親会社との人事連携をどの程度続けるかを明確にしておくことで、従業員に安心感を与えることができます。適切なインセンティブ設計も、モチベーションを維持するための戦略の一つです。
許認可引継ぎや契約承継の困難性
事業を切り離すにあたり、製造業や医療関連など特定の許認可が必要な分野では、新会社として再申請や承継手続きが必要になる場合があります。許認可の取得には時間と費用がかかるため、十分な計画が求められます。
さらに、既存の取引先との契約についても二重管理や再交渉を行わなければならないケースが多く、法務・経理部門にかかる負担は大きくなります。
これらの手続きが滞ると、事業開始時期の遅延や信用リスクの拡大につながる可能性があるため、専門家と協力してスムーズに進める体制を整えることが欠かせません。
カーブアウトの準備とステップ
カーブアウトの成功には、対象事業の選定や適切なスキームの構築など、入念な準備が必要です。以下をもとに、必要な準備を把握しておきましょう。
対象事業の特定と事業価値の計算
カーブアウトを検討する際には、まず対象事業の成長余地や競合優位性を事前調査し、切り離しによる効果を定量的に把握することが重要です。市場規模や技術レベル、将来的な収益見込みなどの要素を総合的に評価します。
これらの分析結果をもとに、事業価値の算出を行い投資家や銀行からの理解を得やすくする資料を整えます。客観的データを示すことで、出資の妥当性や投資リスクを明確にすることができます。
準備段階で正確な事業価値を算出できれば、新会社設立の際の株式発行条件や資本構成について、交渉をスムーズに進めることができるでしょう。
適切なスキームの選択(会社分割や事業譲渡)
一般的にカーブアウトは、会社分割(新設分割・吸収分割)や事業譲渡などの手法によって実行されます。それぞれのスキームは、親会社と新会社の資本関係や従業員の異動などに大きく影響を与えるため、慎重な検討が必要です。
会社分割であれば、新会社を設立して事業を移管する形式となるため、スピンオフ・スピンアウトと近い形を取りやすい特徴があります。一方、事業譲渡は必要な資産や契約だけを切り離す方法であり、交渉範囲が限定的になる場合があります。
どのスキームを選択するかは企業の目的や法務・税務上のメリット・デメリットを比較しながら判断されます。事業規模や株主構成など、固有の条件によって最適解が異なる点を理解しておきましょう。
法務・会計における重要事項の整理
カーブアウトは、法務や会計の観点で多くの手続きが発生します。例えば、登記変更や契約の再締結、財務諸表の分割など、専門的な作業が数多く必要となります。
加えて、移転価格税制や消費税・法人税の観点など、税務面の最適化を図るには会計士や税理士などの専門家との連携が不可欠です。これらの手続きが整わないと、事後的に問題が発覚するリスクがあります。
事前にタスクを洗い出し、優先順位をつけて実施することで、カーブアウト当日のスケジュールを円滑に進められます。特に許認可関連の期限などに注意を払いながら準備を進めることが成功の鍵となります。
国内外の成功事例
国内外で複数の大企業がカーブアウトを行い、大きく事業を成長させています。
特に日本企業の場合、事業の一部を新会社へ切り離して外部資本を取り入れ、高度な技術開発や新市場開拓を行う例が目立ちます。
また、海外でも同様に、非中核事業をカーブアウトすることで基幹事業に経営資源を集中させる動きが多く見られます。
以下の具体事例では、どのように企業がスキームを構築し、どのような成果を得たのかを把握することができます。自社でのカーブアウト計画の参考として捉えてみてください。
オリンパスの映像事業
オリンパスは長年にわたりカメラ事業を手掛けてきましたが、映像事業の採算性が課題となっていました。そこで映像事業を分社化・譲渡することで、医療機器などコア領域への経営資源集中を図りました。
結果的に、親会社は医療機器部門に投資を集中でき、競争力を高めることに成功しています。一方で映像事業を譲り受けた新会社側も、独立した経営戦略で製品開発を続ける余地が生まれました。
この事例は、不採算事業を手放すだけでなく、新会社が新たな方式で成長を続けられる可能性を示した点で注目されています。
【出典】オリンパス株式会社「映像事業の譲渡に関する意向確認書の締結について」
日立製作所の物流部門
日立製作所が手掛けていた物流部門は、分社化して外部企業との共同出資による新会社を設立しました。この動きにより、物流部門は親会社以外の顧客開拓を迅速化し、新たなマーケットでの成長を期待できる仕組みが作られました。
同時に、日立製作所はエネルギーやITなどのコア領域に資源を集中し、グローバル事業の拡大を加速させています。親会社と新会社双方が自社の強みに注力する形を構築した好例です。
結果として、物流部門は外部の専門知識や資金を活用し、効果的な物流ソリューションを展開しています。親会社も新会社も互いに成長を促進できる点が大きなメリットとなりました。
【出典】株式会社日立物流「HTSK 株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」
ファイメクス(武田薬品工業からカーブアウト)
武田薬品工業は、新薬開発の一部を切り離し、ファイメクスとして独立させました。これは新薬の研究開発を加速させるために外部投資を積極的に受け入れる狙いがありました。
ファイメクスは独立した企業として柔軟な開発体制を築き、必要に応じてグローバル規模のパートナー企業とも協力しやすくなったと言われています。武田薬品工業はコアとなる領域にさらなる経営資源を投下できるようになりました。
この事例は、研究開発型企業が持つ高度な技術を切り離すことで、新たな資金調達の道を開き、スピード感あるイノベーションを可能にする好例といえます。
【出典】東大IPC「武田薬品工業株式会社のカーブアウトベンチャー、 ファイメクス株式会社への出資を決定」
まとめ|カーブアウトを理解した上で検討を
カーブアウトは経営戦略として強力な手段ですが、適切な準備やリスク管理が欠かせません。メリット・デメリットを十分に理解した上で検討を進めることが重要です。
カーブアウトは企業の事業ポートフォリオ最適化や新規成長市場への迅速な参入を可能にする魅力的な手法です。一方で、外部資本の受け入れや従業員のモチベーション管理、複雑な法務・会計手続きなど、慎重に対処すべき課題も多く存在します。
成功への鍵は、どの事業を切り離すのか、どのスキームを選択するのか、そして親会社と新会社の間でどのようにシナジーを生み出すかを明確化する点にあります。実際の成功事例を参考にしつつ、専門家と連携しながら計画を進めていくことが求められます。
最終的には、親会社と新会社の双方が成長機会を広げ、企業全体の価値を高める仕組みづくりが重要です。リスクを十分に認識しながらも、有望な事業を分化・発展させる選択肢としてカーブアウトを活用してみてはいかがでしょうか。
CINC Capitalは、M&A仲介協会会員および中小企業庁のM&A登録支援機関として、カーブアウトのご相談を受け付けております。業界歴10年以上のプロアドバイザーが、お客様の真の利益を追求します。M&Aの相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

















